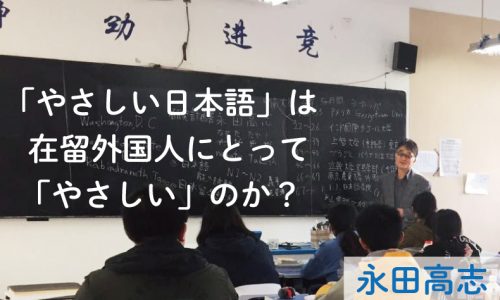『君の名は。』の衝撃
さて、『君の名は。』です。皆さんもご存知のように、2016年に公開されたこのアニメーション映画は、実に250億円以上もの興行収入を誇り、映画史に残る記録的な大ヒットを達成しました。普段はアニメーション映画をほとんど観ないという方も、この映画作品だけは公開時、あるいはテレビ放映で観たという方も多いのではないでしょうか。
その筋立ては、立花瀧という男子高校生と、宮水三葉という女子高校生の意識が、ある日突然に入れ替わるという出来事から幕を開けます。監督・総指揮を務めた新海誠のインタビューによると、この設定は、古く平安時代の古典『とりかへばや物語』や、大林宣彦監督による映画『転校生』〔松竹、1982〕など、先行するさまざまな物語作品から着想を得たもののようです。(詳細は、http://filmers.jp/articles/2016/08/19/post_78/などを参照のこと。)一方は東京の都心に近いと思われる華やかな住宅街、他方は糸守町という山里の小さな集落に住む2人は、各々の生活に干渉しつつも少しずつ打ち解けていくのですが、あるタイミングでなぜか突然入れ替わりは途絶えてしまいます。三葉の行方を探す瀧は、記憶を頼りにそれらしい場所を探し歩くのですが、その過程で実は2人の入れ替わりには3年の隔たりがあり、現在時点の三葉は、彗星が隕石となって墜落したことによって、糸守町ごと消滅してしまっていたということを知らされるのです。
三葉を救うため、神聖な力が宿るとされた宮水神社の口噛み酒を飲み、再び入れ替わりを果たした瀧は、糸守町の住民たちを集団避難させるために三葉のクラスメイトたちと作戦を立てるのですが、どうしても町長である三葉の父親を説得することができません。万策尽きたかに思われましたが、「カタワレ時」と呼ばれる黄昏のわずかな時間、入れ替わりがもとに戻り、瀧と直接会話することができた三葉は、瀧から糸守町の集団避難計画を受け継ぎ、何とか父親の説得に成功することで、糸守町は彗星の被害から逃れることができました。そして8年の月日が流れ、「ずっと誰かを探している」感覚を抱きつづけていた瀧と三葉は、たまたま東京で互いの姿を見かけ、名前を尋ね合うところで物語は大団円を迎えることになります。
『君の名は。』については、広く知れ渡ったアニメーション映画ということもあり、これまでにも多くの論説で取り上げられましたが、管見の限りでは、いわゆる「セカイ系」的な文化思潮の典型として位置づけようとするものが目立ちました。(✳)もともと『ほしのこえ』(MANGAZOO.COM、2002)や『雲のむこう、約束の場所』(コミックス・ウェーブ・フィルム、2004)など、新海作品は「私」とあなたのささやかな人間関係を、壮大な宇宙規模で描こうとする物語様式が多かったこともあり、監督の新海自身もまた「セカイ系」の旗手のようにみなされていたのです。
他方で『君の名は。』は、彗星の落下により引き起こされてしまった災厄を食い止めるという、ある種の歴史改変SFであったことから、とりわけ震災後の日本社会との関連を指摘するものも多くありました。たとえば、笠井潔は『君の名は。』について、「3・11後のわれわれの時代意識を、瀧と三葉の入れ替わりという設定は虚構的に典型化している」と指摘し、「もしも自分があなただったら……」といった反実仮想を扱うことの同時代的な意義を論じています(『例外状態の
こうした先行する論点に対して、本連載では改めて『君の名は。』で並行世界が扱われたという基本的な事実に立ち返り、その批評的射程を再検討してみたいと思います。
(✳)たとえば、藤本一勇「二つの「世界/セカイ」の狭間で──『君の名は。』と『この世界の片隅に』──」(『表象・メディア研究』第9号、2019.3)では、同年に公開された片渕須直監督のアニメーション映画『この世界の片隅に』(東京テアトル、2016)との比較を通じて、『君の名は。』の「セカイ系」的な側面が精緻に検討されています。
一人称的世界から離れて
僕が『君の名は。』を観たとき最初に思ったのは、「初めに瀧くんが恋をしていたあの三葉ちゃんは、果たして本当に救われたのか?」ということでした。つまり、物語の半ばで、瀧が3年前の糸守町に帰還した後の世界は、もともとの時間軸のあり方から決定的にズレており、したがって結末で再会を果たした三葉もまた、物語が開始した時点での三葉とはどこかで異なっているのではないかと感じられたのです。
もちろん、これは三葉の具体的な中身(そのひとの属性に関わるあれこれ)が変化したということを言っているのではありません。実際、三葉本人の来歴や人格を探ってみても、そこにはあの三葉とこの三葉のあいだに寸分の違いも見いだせないでしょう。そうではなくて、一切の来歴や人格とは無関係に、タイムトラベルによって歴史のあり方を変えてしまった以上、言わば時空の構造そのものが分裂しているのだから、各々の三葉もまた、端的に別の存在であると考えるのが自然ではないのかということです。
すぐにお分かりと思いますが、これは要するに、本連載で何度も取り上げてきた柄谷行人の言葉を用いるならば、「特殊性」ではなく「単独性」の次元に含まれる問題であるということです。いかなる確定記述にも還元しえない何らかの剰余──それはもちろん、具体的な中身を説明しようとした瞬間、単なる錯覚に過ぎないものとして取り逃がされてしまうわけですが──こそが、ほかならぬそのひと・そのものの特別さを示す条件になるというパラドキシカルな感覚があるからこそ、2人の奇跡的な再会というエンディングに、僕は感銘を受けながらも、何かしっくりとこない思いを抱いたのだと思います。
本連載の8回目でも示した、円城塔『Self-Reference ENGINE』に登場した問いを思い返してみましょう。それは、無数に分裂を繰り返す「この平面宇宙に、お前と限りなく似た女の子が存在するかどうか」というものでした。『Self-Reference ENGINE』は、こうした問いのモチーフとなる舞台設定(多元宇宙の存立構造)を丁寧に描くことで、「単独性」をめぐる思考のあり方を、ひとつの文学的なテーマとして提示することに成功していたわけですが、『君の名は。』ではそういった感性の現れが、それでもなお 2人は再会を果たしたという(やや安直な)メロドラマとして昇華され、少なくとも表層的には幸福な結末を迎えることになりました。しかし、そこに前述のようなわだかまりを感じたのは、僕だけではないはずです。
もっとも、あの三葉とこの三葉の差異が取り立てて重要な問題となるのは、瀧の一人称的な視点から『君の名は。』の物語世界を把捉しているからだと考えることもできます。もし、誰の視点とも異なった三人称的なポジションから、分岐する時空のあり方を同時に俯瞰することができるならば、そもそもそのようなあるひと・あるものの同一性をめぐる問いは、最初から成立しないからです。前回の連載で、こうであったこともできたという自由意志の可能性は、決断の時点から遡行的に見いだされたものであるという中島義道の見解を紹介しました。しかし、それはあくまで視点人物(=一人称的な認識主体)の水準に関わる事柄であり、たとえば本連載の2回目で取り扱った、東浩紀『ゲーム的リアリズムの誕生』における美少女ゲームのプレイヤー視点のような、あらゆる可能性の行方を並列的に把捉できるメタ・ポジションを想定してみれば、そのような決断に伴う可能性の事後的な成立は、もとより問題とならないはずなのです。(もちろん、実際のところは僕たちが一人称的な認識主体である以上、ひとつきりの生のあり方しか引き受けられないのですが……。)
この議論を聞いて、ロバート・ゼメキス監督による往年の名作映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(ユニバーサルスタジオ、1985~1990)で、エメット・ブラウン博士(ドク)が黒板を用いて説明してくれたタイムトラベルの仕組みを想起した方も多いのではないでしょうか。ドクによれば、タイムトラベルとは、単に時間の矢印が単線的に巻き戻るのではなく、そもそも矢印のあり方自体が分岐し、各々が異なる歴史を進んでいくことを意味しています。こうした複数的な歴史の分岐を許容してしまえば、そこに居る人びとの生のあり方もまた多元的であり、それぞれの人物の造形が〝同じ〟であるか否かという論点が、初めから意味を持たないことは言うまでもないでしょう。
これは、いわゆるタイムパラドックスの解決策としてもきわめて有力なものです。たとえばD・ドイッチュは、量子論的な多世界解釈を肯定するための思考実験として、タイムトラベルの考察において「仮想実在生成装置」の存在を認めるべきであると主張しています。その要諦となる部分を引用しておきましょう。
もし仮想実在生成装置がこのタイムトラベル系列の期間中に起きたことの総体を記録するのであれば、装置は実験室時計によって定義されるそれぞれの瞬間に対していくつかのスナップショットを蓄えなければならないが、今度はそれがすべて異なっているだろう。言い換えると、五分間のタイムトラベル期間の実験室についていくつかの異なった平行な歴史があるだろう。私はそうした歴史をそれぞれ、順々に経験したので、どれかが他のものよりも実在的でないと語る理由はない。だから、ここで提示されているのは小さな多宇宙である。もしこれが物理的なタイムトラベルであったとすれば、個々の瞬間の多宇宙スナップショットは平行宇宙になる。
(『世界の究極理論は存在するか──多宇宙理論から見た生命、進化、時間』林一訳、朝日新聞社、1999.11)
これは要するに、歴史改変によって起こりうる因果関係の辻褄の合わなさを、単にどちらの世界も 存在するというかたちで認めてしまえばいいというものですが、多世界解釈の可否という科学的な議論は措くとしても、タイムトラベルの理屈はそのような仕方で説明されるのが、最も合理的かつ自然なように僕には思えます。(✳✳)
ともかく、タイムトラベルという出来事の成立を多世界解釈的に肯定してみるならば、世界がこのただひとつしかなく、あらゆる可能性は非‐現実的なものとしてそこに従属するという発想自体が、きわめて一人称的な認識主体の視点に依拠したものであり、従って前述した三葉に対する「単独性」の感覚というのも、単なる無根拠なロマンティシズムに陥ることなく、時空の存立構造そのものの分裂という仕方で、実に簡単に認めることができるはずなのです。では、こうした世界の見方は、実際にはひとつきりの 現実世界に生きる僕たちに対して、どのような示唆を与えてくれるでしょうか。
(✳✳)ただし、タイムトラベルにはこのパラドックスの解決案(多世界解釈)を認めたとしても、なおいくつかの重要な哲学的課題が残存しています。そのことも、本来であれば今回取り上げる『君の名は。』解釈の根幹に関わってくるものであり、丁寧に検討すべき事柄なのですが、紙幅の関係でここでは取り上げません。詳細は、青山拓央『タイムトラベルの哲学』(ちくま文庫、2011.1)がきわめて魅力的な議論を展開しているので、ぜひご参照ください。
記憶の固執
『君の名は。』に話を戻すならば、以上のような論点をめぐって、杉田俊介は「歴史の改変によって、改変された後の三葉たちの命は助かるが、改変される前の人々の存在が歴史的・物語的にそもそも無かったことにされてしまう」という事態を、端的に「歴史修正的な記憶喪失」であると指摘し、そこに「震災後の私たちの社会的な集団記憶喪失(震災のことなんかすっかり忘れている日本社会)」を重ね合わせています(『戦争と虚構』作品社、2017.11)。杉田は、単に『君の名は。』が災厄を忘却する現代の日本社会のあり方を素朴に反映していたと述べているわけではなく、そこになお「ぎりぎりのロマン派的な批評」を読み込んでもいるのですが、ここで改めて注目すべきなのは、「改変される前の人々の存在が歴史的・物語的にそもそも無かったことにされてしまう」ことが、作中の認識主体による記憶の問題として提示されていることです。
もちろん『君の名は。』が、瀧あるいは三葉を視点人物とした一人称的な作劇構成となっている以上、歴史改変を試みる認識主体のパースペクティヴから物語世界を把捉したとき、当の視点人物が並行移動してしまった後の歴史のあり方は、現実世界ではないもの(少なくとも、視点人物の今後の生活には直截に関わらないもの)として、ただちに僕たちの意識からも消去されてしまうでしょう。(以下、わかるひとだけ。かつて、エリック・ブレス監督の『バタフライ・エフェクト』(アートポート、2005)という、より良い結果を得るために幾度もタイムトラベルを繰り返すSF映画がありましたが、そこでも主人公が並行移動した後の歴史がどうなったのかということに拘泥する鑑賞者は、あまり居なかったのではないかと思われます。)それは、ある特定の視点人物に感情移入し、その背景としての物語世界そのものには親近感を抱きにくいという、人間の認知構造の宿命のようなものかもしれません。(✳✳✳)
ただ、そういった過ぎ去りゆく並行世界に対する鑑賞者レベルでの忘却とは別に、そもそも『君の名は。』では、結末で登場人物たち(瀧と三葉)自身の記憶が消去されていました。なぜ、わざわざそのような設定を施す必要があったのでしょうか。この点について、長山靖生は『君の名は。』の「終盤近く、事成した後、ふたりは「夢の出来事」の記憶を失うが、それは支払わなければならない当然の代償」であると指摘しています(「SFのある文学誌──[第49回]『君の名は。』の時場 新海ファンタジイの文脈」『SFマガジン』2016.12)。長山によれば、ある種の物語パターンとして「救済の引き換えに、人は「自分の一番大切なもの」を失わなければならない」のであり、とりわけ「『君の名は。』のふたりが支払う代償は「惹かれ合っていた相手の記憶」なのだ」と言うのです。確かに、記憶の喪失というモチーフは作中でも独特の切なさを喚起するため、単に感動を呼び起こすための表現上の演出として理解することもできるわけですが、僕としてはそれ以上の方法論的な面白みを、そこに見いだすことができるように思えます。
瀧と三葉は、歴史改変によってふたつの並行世界を移動してきたわけですが、結局のところ結末で現実世界のあり方はひとつに決定づけられ、もうひとつの起こりうる可能性があったという出来事そのものが、彼らの記憶から消去されてしまいました。そのようなあるひとつの時空の唯一性・特権性を前提としてみれば、各々の「単独性」をめぐるロマンティックな感覚とは、言わば一人称的な世界把握に伴うバグのようなものであり、単なる認識論的な錯誤として処理されてしまうでしょう。
しかし、そのような世界の見方は貧相であるばかりか、僕たちが必ずしもひとつきりの現実世界だけに唯一性・特権性を感じているわけではないという、きわめて当たり前の事実を取りこぼしているように思えます。もちろん、先述したように僕たちは一人称的な世界の見方に依拠している以上、論理的にはひとつきりの生しか引き受けることができないわけですが、しかし実際はこうでなかったにもかかわらず、それでもなおこうであったはずではないかという(無根拠な)信念が、時として僕たちの意識を貫くわけであり、現実世界と可能世界の階梯秩序は、錯誤の余地を与えない論理的位相とは別に、そのような経験的位相からも検討されてよいはずなのです。(✳✳✳✳)そして、ゼロ年代の並行世界をめぐる一連の物語文化は、そのような〝間違った〟思考や感性のあり方を肯定するものだったというのが、この連載を通して僕がずっと言ってきたことでした。
僕たち一人ひとりの生の経験の奥底には、ありえたかもしれない無数の出来事の可能性が潜在しており、そこには実際の現実世界とは異なりながらも、なお固有の質感を与えることができる。少なくとも『君の名は。』のエピローグで、「ずっと誰かを探していた」瀧と三葉に共感を寄せることができるなら、端的な現実世界のこうでしかなさ以上に、こうではなかったかもしれないという可能性の氾濫にこそ、切実なリアリティを感じ取ることができるように思えるのです。『君の名は。』は、そのような喪われた記憶を呼び覚ます想像力の光源となっていた点で、きわめて魅力的な映画作品たりえていたと言えるでしょう。(✳✳✳✳✳)
その後の新海誠は、ご存知のように『天気の子』(東宝、2019)というアニメーション映画を手がけ、これもまた大きな話題となりました。同作の結末では、ヒロインの命運と日本全体の異常気象を主人公が天秤にかけることになりますが、まさにそれはミクロな人間関係とマクロな世界情勢が直結するという「セカイ系」の話型そのものであり、『天気の子』の達成により、ゼロ年代的な物語文化の継承者としての新海の地位はますます不動のものになったと言えます。しかし、僕にはやはり『君の名は。』に描かれた並行世界のドラマツルギーこそが、新海作品の真骨頂だったように思えてなりません。それは、私たちの思考や感性が、必ずしも現実世界のこうでしかなさだけに準じて組み立てられているわけではないという事実を、端麗なアニメーション映像によって思い出させてくれるからです。
次回は、伴名練『なめらかな世界と、その敵』(早川書房、2019.8)を扱います。
(✳✳✳)マリー=ロール・ライアンは、次のように虚構世界への没頭の機制を説明しています。
虚構を読む読者にたいして登場人物が擬似現実性を持っていることは、その登場人物たちに感情移入しようとする自然な傾向にも見て取れよう。登場人物というものを──構造主義でやっていたように──テクスト上に特性の集合体にすぎないと見なしてしまったら、お気に入りの登場人物に都合のよい結末を望んだり、悪役の奸計が成功して主人公が窮地に陥るのではなどと気を揉んだり、少なくとも一部の人たちがホラーものに恐怖したりロマンスに紅涙を絞ったりなどしていられるものだろうか。文学の登場人物には存在論上の両義性があり、《登場人物について知っていること》と《登場人物とのかかわりかた》とのあいだには食違いがある。
(『可能世界・人工知能・物語理論』岩松正洋訳、水声社、2006.1)
この見解に僕は完全に同意しますが、同時に気になるのは、そのような「感情移入」の仕方が、登場人物たちの生きる虚構世界そのものには適用されないのか(適用されないとすればそれはなぜなのか)ということです。たとえば、ある虚構世界の造型自体に愛着を感じるというのは、それこそ壮大なサーガとなっている一部の物語作品(「機動戦士ガンダム」シリーズの宇宙世紀など)には起こりうるでしょうが、それでも「キャラ萌え」などの情念のあり方と比べて、依然としてあまり市民権を獲得していないのではないかと思われます。僕たちと虚構世界の登場人物が人間同士だからと言ってしまえばそれまでなのですが、この点については、ちょっと僕のなかでもまだ整理ができていないので、いずれ腰を据えて考えるべき問題であろうと思っています。
(✳✳✳✳)なお、昨年夏に刊行された入不二基義『現実性の問題』(筑摩書房、2020.8)は、こうした現実世界の圧倒的な「本物らしさ」を再考するための端緒となるアイディアが多く詰め込まれています。その検討は、別の回(全体のまとめとなる回)で丁寧に行ないたいので、いまは本連載の問題意識と密接な関連があるということだけ申し添えておきます。
(✳✳✳✳✳)ところで、やや話はズレてしまうかもしれませんが、近年、現代ドイツの哲学者であるマルクス・ガブリエルの邦訳『なぜ世界は存在しないのか』(講談社選書メチエ、2018.1)が、一部の知識人のあいだで大きな注目を集めました。ここで具体的な中身を検討することはできませんが、その流行の要因について、篠原雅武は「災害や大量殺戮とともに不安が高まり、それを的確に伝えているかどうかが不明な大量の情報がテレビやインターネットで流されるなか、現実感のよりどころをどこに求めたらよいのかがわからなくなっている状況のなかでの哲学」であったことを挙げています(『「人間以後」の哲学──人新世を生きる』講談社選書メチエ、2020.8)。これは牽強付会な繋げ方かもしれませんが、渡邊大輔は『君の名は。』のアニメーション映像に「あらゆる対象を可塑性の海に溶かしこむ、人類=観客なき「ノンヒューマン的転回」のあとの風景」を見いだしていました(「彗星の流れる「風景」──『君の名は。』試論」『ユリイカ』第48巻13号、2016.9)。破局の経験をくぐり抜け、既存の「現実感」のスケールが劇的に変容していくなかで、時代状況に対峙するための想像力の供給装置として、ガブリエルの哲学と『君の名は。』の流行現象には、ある種の共振性を読み取れるように思えます。