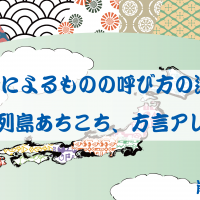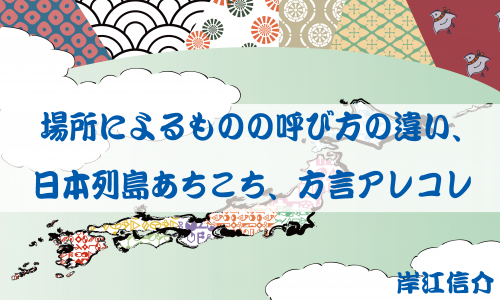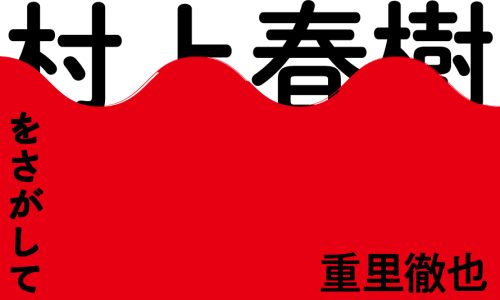性愛で自由を問う
助川幸逸郎 重里さんは『驟雨』を高く評価されています。この作品の魅力は重里さんから見たら、どういう点にあるのでしょうか。
重里徹也 主人公が性愛に自分の心と身体を開いて、自分を実験台にして性愛とは何か、人間とは何かを探っている。そういう小説だと思います。
助川 具体的に例えばどういうところですか。恋愛心理みたいなものがどういうふうに移ろっていくかを、自分を実験台にしてやっているっていう感じですかね。
重里 恋愛といっても、ロマンチックなものではなくて、人間の「骨」というか、「はらわた」というか、「生き物としての根っこ」というか、本質をえぐり出すような恋愛ですね。そして、人間関係というのは一体、どういうものなのかを探っているように思います。とても面白いと思ったのは、自由の問題です。人間は本当に自由を求めているのだろうか、という問題です。それが問われている。
助川 あんまりこの作品を論じる際に「自由」は問題にならないと思うのですが……。少し説明してください。
重里 主人公は自身をとても自由な人間だと思っている。ところが、娼婦の家に通う内に、自由でなくなってくる。道子という特定の娼婦にとらわれていく。
人間という存在が自由を求めるものなのか、不自由を求めるものなのか、それがギリギリのところで探られている、そんな風に思ったのです。そこが私はとても面白いと思いました。私たちにとっても、きわめて切実なテーマだと思います。
助川 私は大学生の時に、年上の女性を好きになったことがあります。『驟雨』を読んで、そのときの心理をありありと思い出しました。
ものすごく魅力的な人だったのですが、タイプではなかったんだけど、それまで自分がこういうタイプが好きだって思っていたのとは全然ちがうひとだったんですね。普通に恋愛してるんだったら、たとえ片思いでも「ああ、自分はものすごい恋をしてるんだ」という感じで、自分の状況を受けいれることができます。でも、これまでの恋愛とはパターンがちがうのに、そのひとに夢中になってしまっている場合、自分で自分をどう扱っていいんだかわからない。そのときの何ともいえず苦しい感情が、この小説を読みながら鮮明によみがえってきました。
重里 辛いのだけれど、一方で「辛い」とはいえない感覚もあるのではないでしょうか。
恋愛にまとわりつく物語というか、ロマンティシズムみたいなものを剥ぎとって、なお残るものがあるのだろうか。あるとしたら、それは何か。そこを問いかけている小説に読めました。
助川 サルトルが「人間は自由の刑に処されている」というふうに言っています。実は人間が自分を自由だって感じるのは、うまく枠にはまってるときなのかもしれません。
私は恋愛をしている。私は会社のために一生懸命働いている。そういう「わかりやすく名づけられる状況」を選んで、そこに身を投じている時に、人間は「なんて自分らしいんだ」と感じて「自由」を自覚するのだと思います。
反対に、今まで体験のしたことのない状況に置かれ、自分のみの判断でどこかに行かねばらならない場合、人間は、自分の感情を名づけられなくなり、苦しむのではないでしょうか。
この小説を読みながら、そんなことを考えさせられました。人間性の深淵に光をあてた作品であることはまちがいありません。
重里 日本の戦後文学、現代文学では、通奏低音のように自由の問題が問われ続けているように思います。自由とは何なのか。自由とはどれぐらいの価値があるものなのか。自分は、日本人は、人間というものは、ほんとうに自由を求めているのだろうか。そういう問いが一貫して流れているように感じます。その結晶のような小説の一つが『驟雨』ですね。
刻印された戦争体験
重里 もう一つ、見逃せないと思ったのは、この作品は一九五四年、敗戦から九年後の作品なのです。なぜ主人公がこういう心持ちを持っているのか、そこのところも、この「敗戦から九年後」という時代が背景になっているのだろうと感じました。
助川 それは間違いなく正鵠を射た見方だろうと感じます。
吉行淳之介は大正十三年生まれで、私の父と同い年なんですよ。
重里 吉本隆明も大正十三年ですね。三島由紀夫は一つ下ですから、同世代です。
助川 この世代は、戦争で仲間をたくさん亡くしています。敗戦を期に、それまで疑うことすら許されなかった価値観が転倒するのも体験した。それゆえ壮絶なニヒリズムを抱えこまざるを得なかった。
私の父も、戦後の混乱期に、闇市でヤクザと無謀な喧嘩をしたりしていたようです。そのときの心の根底に、もう仲間もみんな死んじゃったし、日本もひっくり返っちゃったんだから、喧嘩して死んだとしてもそれまでだ、みたいな気分があったと言っていました。戦後しばらくのあいだは、そうした虚無的な思いを払拭しきれなかったみたいです。
重里 戦争を体験したことに由来するニヒリズムは、まちがいなく吉行にもあるし、吉本にもあったと思います。
助川 『驟雨』の主人公は、名づけえない感情に敢えてのめり込んでいく。その背後にも、戦争を経験したゆえの「自己破壊的な構え」みたいなものある気がします。
それから、この小説が書かれた一九五四年は、高度経済成長を支えた五五年体制成立前夜です。よく知られている通り、ファースト・ゴジラ(映画「ゴジラ」。よく「ゴジラ1954」と呼ばれる)もこの年に公開されています。ファースト・ゴジラは、ゴジラと芹沢博士という「戦争の亡霊」が心中することで、戦争の呪縛から日本人が解放されるという作品です。世の中全体が、戦後の混乱から脱却して繁栄に向かおうとしているときに、吉行はその流れに同化できない思いをこの小説に託したのでしょう。
重里 一九五四年の「ゴジラ」は何度も観ました。ある種の三角関係を描いている。戦争のために片目を失った芹沢が自分の開発した薬物を使って、ゴジラと心中する。残された若い男女が、これから「平和で明るい戦後社会」を謳歌するのを予感させる。
吉行には、そういうものに合流するのが、恥ずかしいというか、後ろめたいというか、バカらしいというか、空虚だというか、そういう心情があったのでしょうね。
ところで興味深いのは、三島はこの年に『潮騒』を発表しているのですね。
助川 時代の荒廃を大前提として、そういう混乱状況を遮断した人工楽園を構築してみせた。そのことによって、逆説的に現状の混迷を読者に知らしめようとした。それが『潮騒』のたくらみだったというのが私の解釈です。しばしば指摘されるように、三島の文体や人物設定には「つくりものくささ」が拭いがたく漂います。その「つくりものくささ」は、『潮騒』みたいな「敢えて時代をネグレクトした作品」を書くときにはプラスにはたらいたのではないでしょうか。
これに対し吉行は、『驟雨』の中で赤線地帯を「滅びゆく習俗」として描いています。この「滅びゆくもの」に固執するところに、吉行の精神のありようを私は感じます。戦後の荒廃は癒やされつつある。でも、俺はそう簡単に癒やされたくない。そうした意地を、『驟雨』の吉行には感じるのです。
重里 ただ、内面はどうあれ、本人の意志に反してか、吉行も戦後を生きていくわけですね。そして時代は高度経済成長を加速していく。石原慎太郎の『太陽の季節』が登場するのは翌一九五五年です。明暗といえば明暗が、くっきりと前面に出てくる。
助川 戦争の傷が封印された社会を生きのびていくのだけれど、ぬくぬくとは生きのびたくない。そんな覚悟というか葛藤がこの作品から伝わってきます。
重里 『驟雨』の主人公は会社勤めをしています。「汽船会社」に勤務している。そこにはとても俗っぽい世界が広がっている。まさに高度経済成長を突き進み始めた日本ですね。同僚の結婚といったエピソードもはさまれる。
主人公は、そういう俗なるものに背を向けて孤独を求めていくのだけれど、そこにも安住できない。人間は、どうしようもなく自由と孤独を求める生き物である反面、自由と孤独に身を浸している状況にも満足できない。非自由(何者かへの従属)、非孤独(何者かとのつながり)を求めてしまう。そのへんのところが鮮やかに描かれています。
助川 この小説は、モチーフとしては長編になりうる作品だと私は思います。主人公は、同僚の結婚式につながっていく俗っぽい世界を軽蔑しきっている。しかしだからこそ、うまく世の中を渡っているタイプだと思うんです。
スノビズムというのは、本気でのめりこんでいる人間ではなく、「こんなのくだらないよね」といっている人間によって支えられているわけですから。
重里 なるほど。くだらないと思っているからこそ、そこに合わせる演技もやりやすいし、器用に立ちまわることもできるわけです。
助川 かつて、スラヴォイ・ジジェク(スロベニアの哲学者)が「社会主義体制というのは、本気で社会主義を信じている人間に支えられていたわけではない。社会主義を微塵も信じていないがゆえに、体制に服するそぶりを完璧に演じられる人間たちが維持していた」といっていました。
迷い戸惑う「永沢さん」
助川 それでこの主人公、ある意味『ノルウェイの森』の永沢さんではないでしょうか。
重里 何ものも本気で信じられないゆえに、語学も外交官試験も恋愛も、冷徹に仕組みを見きわめて成果を出していく。けれどもそれらの成果によっては心の底にある空虚は埋められない。それが永沢という人物です。
助川 村上が吉行を高く評価するのは、永沢的なキャラクターをリアルに描けるから、という面もあるのではないでしょうか。
重里 『驟雨』は、永沢を主人公とした小説とも読めるわけですね。
自由と孤独を永沢は享受していた。ところが、ある日を境にそうではなくなった。自由や孤独よりも優先する価値があるような気がしてきた。まだ、迷っている。そういうドラマとして読めるということでしょうか。
助川 ただし、永沢は最後まで全力で逃げるタイプです。もしこの作品の主人公みたいに、「名づけ得ぬ感情をもたらす対象」と出会ってしまったとしたら、永沢はそこから逃げ出すでしょう。「この出会いは、自分がこれまで構築した世界を壊す」と感じて。
永沢が抱えていたのはあくまで「虚無」だと思いますが、『驟雨』の主人公はより自己破壊的です。永沢(もしくは村上)は直接戦争を体験していない。その違いはやっぱりあるように感じます。
重里 三島はどうなのでしょうか。
助川 おそらく三島も逃げるでしょう。逃げて、代わりに「天皇」を持ってくるんですね。三島の「天皇」は「虚無」に直面しないための装置でしょう。
重里 永沢って、すごく三島に近い印象を持ちました。永沢や三島は逃げる。ところが、逃げるか逃げないか迷っていて、立ち止まって、喫茶店であれこれ考えている人間を吉行は描いた。そういうことになるでしょうか。
助川 永沢と『驟雨』の主人公の違いは、そのように考えるのが創造的かもしれません。三島や永沢が心にしまい込んでいた葛藤を吉行は浮かび上がらせたということですね。
重里 ところで、日本の戦後文学、現代文学は、自由の問題を問い続けたし、今も問い続けている。その背景に戦争体験があることは見てきた通りです。ただ、もう一つ、触れなければいけない問題があるように思うのですね。
助川 それは何でしょうか。
重里 左翼体験であり、政治闘争体験であり、リベラリズム的なイデオロギーですね。
政治運動をした当事者はもちろん、そうではない人たちも考えざるをえなかった。自由とは何か。自分はほんとうに自由を求めているのか。ひょっとしたら、日本人は自由なんて欲していないということはないのか。自由とは、そんなに価値のあるものなのか。自由に優先する価値はないのか。これは見逃せないポイントのように思います。それは、ポリティカル・コレクトネス(PC、政治的正しさ)の問題ともかかわってきます。
吉行淳之介とPC
助川 実は吉行について、どういうエクスキューズをつければいまの若者たちに読んでもらうことができるのかということを考えていました。
吉行が描くのは性愛の世界で、しかもこの『驟雨』のように赤線地帯が舞台になったりしている。何か補助線を引かないと、PCの観点に照らして「授業でとりあげるのは不適当」みたいに言われかねません。
何せ、いまの学生さんは、『ノルウェイの森』を授業でやると、「主人公たちが鬼畜すぎる!」といって怒るわけですから。
重里 それは、だけど、どうなのだろう。
助川 たとえば、敢えて鬼畜な人間を描いて、そういう人間が「例外的な異常者ではないかもしれない」と読者に考えさせようとする作品もあるわけですよね。
ところが、このごろの学生さんの感想文を読むと「こんな鬼畜な人間を描くなんて、作者も大概だ」みたいな意見が実に多い。太田豊太郎(『舞姫』の主人公)がダメ人間だとなると、森鷗外まで「道徳にもとる作家」にされてしまうのです……。
重里 ほんとうに鬼畜な人間は、鬼畜な人間を小説に書きません。鬼畜な人間との間に距離があるからこそ、そういう人間を描いて問題提起ができるのです。文鳥を死なせてしまって悪いと思っていない人間は、文鳥のことなど、題材にしません。華奢な文鳥に比べて、自分の手が大きいことを意識しているからこそ、夏目漱石は『文鳥』を書いたのでしょう。
それより、もう少し複雑なPCの話をしましょう。『驟雨』のディティールで気になることがあったのです。
主人公が娼婦の道子に髪を洗ってもらう場面がありますよね。又吉直樹がよくこれを書くのですよ。
助川 ふつうに考えると、女性に髪を洗ってもらうって、幼児のころにお母さんにやってもらうわけですよね。だとすると、吉行も又吉も、女性に母性をもとめているキャラクターを描こうとしているのかもしれません。
重里 何げないけれど、『驟雨』のなかで、印象に残る場面でした。
助川 あの主人公は自分でもほとんど無意識のうちに女と遊んでるつもりで女に母性を感じてしまった。それがつまずきの石になった。そういうことを吉行は書きたかったのかもしれません。
重里 あるいは、吉行がはっきり自覚しないで、そういう男を描いてしまったという見方もできますね。これは、PCの問題とからめても面白いと思います。男性にとっての母性をどう考えるか。
助川 一般的には、男性が女性に母性をもとめる姿勢は批判の対象となります。たしかに、幼児が母親にもとめるような「無条件の承認」を、自分にとって「他者」でしかない相手からお願いされても女性は迷惑でしょう。しかし、いっさい母性と関係のない性愛や恋愛というのは、すくなくとも男性にとってありうるのだろうか。
私は、母親とあまり相性が良くなかったので(笑)、自分の母親に似たタイプの女性を好きになったことはないです。でも、女性に優しくされたときに妙な安心感を覚えて、「世間の人は、母親からこういう感情をあたえられていたのか」としみじみ思うことはあります。こんな風に感じること自体が「害悪」なのでしょうか――もちろん、女性に「癒し」だけを求めるのが「女性蔑視」に他ならないのはわかるのですが。
重里 これは文学を考えるうえでの基本ですが、主人公の行為を「正しさ」で裁いても、文学作品を読んだことにはならないですね。この問題は、もうケリがついたと思っていました。