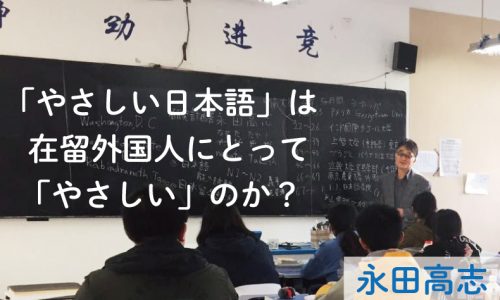夢と現実の等価値
筒井康隆という名前は、特に現代日本文学に関心のない読者でもいちどは耳にしたことがあるのではないかと思います。言うまでもなく筒井は、日本SFの黎明期からつねに第一線で活躍してきた書き手であり、その膨大な作品群は、狭義のSFのみならず純文学やミステリ、さらにはライトノベルにいたるまであらゆるジャンルにまたがって展開されています。ただ、ほぼすべての発表作品に伏在する一貫したテーマとして、〝虚構が虚構であるとはどういうことなのか〟という問いがあることは、筒井ファンなら誰しもが納得してくれるところでしょう。以下では、そのような問題意識が存分に発揮された王道の筒井SFとして、1987年に発表された『夢の木坂分岐点』を検討していくことにします。
『夢の木坂分岐点』は、ごく普通のサラリーマンとおぼしき小畑重則という人物が、ふとまどろんだり映画を観たり小説を書いたりするなかで、少しずつ姓名を変えていき、その度に少しずつ異なった人生を歩んでいくといった、非常に奇妙な筋立てを持つSF作品です。全体の基調が、夢のなかに特有の荒唐無稽な描写に満ちており、どこからどこまでが現実の出来事であるのかが分からないような趣向が施されています。また、少しずつ名前を変えていく登場人物(たち)も、もともとの現実世界に帰還することを目指しているというわけでもなく、むしろ変転する人生を積極的に肯定する存在として描かれています。物語の展開をたどってみても、冒頭で登場した小畑重則という主人公(?)は二度と出現せず、この小説作品が、単に現実世界に生きるただひとりの特殊な「私」を取り戻すことを是として作られたわけではないことが了解できます。
こうした筋立ての意義について、作中で登場人物の言葉を借りてとても明確に説明している場面があるので、まずはそこを引用しておきましょう。姓名や設定が少しずつ変わっていくなかで作家となった大村常昭は、ある講義に赴き、聴衆に「ひとつの個性が多くの世界で同時に生活することも可能ではないのか」と問うたうえで、次のように持論を展開します(以下、ブロック部分はすべて作品本文からの引用を示します)。
これらの世界をすべて、現在現存する現実の世界ではないと否定してしまうのではなく、その中で現実の世界に生きると同様の懸命の努力で生活してみたらどうであろうか。今わたしは実際にそう心懸けているのですが、これがどういうことになるかというと、現実と虚構と夢、この三つの世界を等価値と看做して生きることになります。さらに申しますと現実の世界を、これは虚構世界だとか夢の世界だとか思ってもいっこうに差し支えはないことにもなる。皆さんの中には現実と虚構と夢を三つの世界に分割してしまうのはおかしいのではないか、虚構も夢も現実の一部にしか過ぎないのではないかと思われるかたもおられましょう。しかしもし仮にそうであったとしても虚構や夢は明らかに現実世界内部の治外法権地帯である。これに反対なさるかたはおられないでしょうし、現実から一歩も出ようとせずにこうした地帯へ踏み込もうとは絶対になさらない方もおられる以上、わたしとしてはこれらを現実とは等価値の別世界と考えずにはいられないのです。
『夢の木坂分岐点』には、とりわけ夢の世界を往還するための科学的な装置が作中に登場するわけではなく、作中に散りばめられた超常現象の数々は、すべて主人公(たち)の夢というかたちで解釈可能なようになっています。その意味で、この小説作品を狭義のSFというジャンルに括るのは不適当なことなのかもしれません。ただ、夢と現実を本当の意味で「等価値」のものとみなす感性が、登場人物の口からこれほど明け透けに語られる小説作品というのも、当時としてはかなり珍しかったのではないかと思います(もちろん、その系譜はいくらでも遡ることができるでしょうが)。『夢の木坂分岐点』は、1987年に谷崎潤一郎賞を受賞しますが、その2年前の受賞作は、本連載でも後に触れることになるであろう村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(新潮社、1985.6)でした。両作は、ともに広義の複数世界を取り扱った小説作品であり、その偶然の共鳴が企図されたわけではないでしょうが、こうした現実世界の揺らぎを扱う物語作品の台頭が、ある意味で同時代の社会状況を映し出す鏡となっていたことは疑いありません。その文化史的な意義を探ることも非常に興味深いところですが、ここでは『夢の木坂分岐点』に固有の思想的射程について、もう少し見ておくことにしましょう。
寓喩としてのサイコドラマ
作中では、サイコドラマというやや特殊な慣習が社会で流行していることが描かれています。これは、あらかじめセッションの時間を区切ったうえで、自分と対話相手がもともと持っていた地位や立場を入れ換え、各々に課せられた役割を新たに演じなおしていく一種の心理療法であり、この演技によってサイコドラマの参加者たちは、自分がどのような存在であるのかを対象化して見つめ返すことができるとされています。象徴的な場面を引用しておきましょう。
責められて重昭は今確固とした自我のぐらつきを感じはじめている。浜中が自分自身のように、死んだ父親のように、えたいの知れぬ尋問者のように見えはじめていた。と同時に自分が自分でもあり浜中でもあり、また自分でも浜中でもないただのスパイのようにも感じられ、まるでただそのスパイ行為を責められているだけのつまらぬフィクション的人物のようにおびえはじめてもいた。浜中は現実のこの局面で今のおれほどおびえたであろうか、そんなことを思う一方で責め続ける大畑重昭への腹立ちさえ生まれはじめていた。
ここで示される「自我のぐらつき」と「腹立ち」は、明らかに夢世界に対する主人公(たち)の応対の仕方を戯画的に示すものであり、小説全体への自己言及の効果を持っていると思われます。事実、このサイコドラマを経て、この時点での語り手である重昭は、以下のように述懐するのです。
夢のすべては現実や虚構に知恵だの情感だのといったさまざまな膨らみをあたえてくれるのだからたとえ夢の中と悟っていてもけんめいに生きねばならぬ筈だと重昭は確信している。そうとも。なにもひとつの生き方だけに縛られている必要はない。夢であろうが現実であろうが虚構であろうが、幸不幸や貧富や時代の違いはあってもひとりの人間が多くの生をくり返し生きることは可能である筈だ。
「ひとりの人間が多くの生をくり返し生きることは可能である」という信念は、それを逆の立場から捉え返してみれば、どのような時空間であろうとも、いま・ここが「私」の生きるこの現実世界であるという開きなおりをもたらすことになるでしょう。あたかもサイコドラマによって異なる人格を演じなおすかのように、異なる並行世界の異なる「私」のあり方を、これ以降の主人公(たち)は積極的に引き受けていくことになるのです。別の箇所からも引用しておきましょう。
夢かも知れず虚構かも知れずもしかしたら現実そのものかもしれないこのいくつもの生の中のひとつの生を生きている彼が今までもそうであったようにすでに大村常賢ではなくなっているかもしれないのだし、だからといって松村常賢に戻っているという状況でもなさそうだった。名前などどうであってもよい筈だと彼は思い、そして考える。芸名であってもペンネームであってもおれはただおれであればいいのだ。流転する姓名はひとりの人間に与えられたいくつもの生を象徴しているだけのものであろう。いや。しかしこれはおれの強がりかもしれないな。わはははははははは。
こうした決意表明からは、どれほど姓名が流転しようとも、そのたびごとに現れる「おれ」をただ「おれ」であると認めればよいのだという確信が、終わらない夢を見つづける主人公(たち)に救済をもたらしていることが了解できます。つまり、どのような境遇であろうと、その都度の認識主体こそが「私」であるという端的な事実を受け入れることで、ほかならぬ「私」の「この」性(復習となりますが、ある性質に還元されうる「私」ではなく、ただこうであるという「私」のこと)を認めていこうとするのです。そこに、敢えて──つまらないことですが──文学的な主題を汲み取ってみるなら、たとえば今日の高度情報消費社会において、絶えず分裂・拡散しつづける「私」という存在の空虚さに対して、ある種の処方箋を与えてくれるものであったと言えるかもしれません。
しかし、そのような解釈の枠組みは、この小説作品が持つ独特の不気味さを、きわめてありきたりな教訓に変えてしまうものでしかありません。『夢の木坂分岐点』を読むうえで注意しておきたいのは、主人公(たち)の姓名が変転するにつれて、その基底をなす社会秩序や生活環境のあり方もまた少しずつ揺れ動いており、かつそのような状況のダイナミックな変化の機制を、主人公(たち)はごく平然と受け入れているということです。夢の世界というのは得てしてそういうものかもしれませんが、自己のあり方と現実世界の姿かたちがともに変転している以上、ここでその連続性を繋ぎ留めているのは、ただ認識主体としての「私」の意識や記憶のみであり、それはどちらかと言うと「転生」という表現が近いようにも思われます。こうした設定の妙は、単に「私」という存在のかけがえのなさを考究しようとする〝自我中心主義〟的な発想からは、決して生まれえないのではないでしょうか。つまり、ここでは「私」らしさをめぐる探索の旅路が、それを包み込む容器としての現実世界そのものの生成変化と不可分に結びついていることが示唆されているのです。
夢世界であることの意味
通常、僕たちが生きていて素朴に「私って何だろう?」という問いに直面するとき、その容器としての現実世界の秩序構造には、あまり注意が向くことはありません。存在が不確かなのはあくまでも「私」の側であり、現実世界はある程度まともであるという前提がなければ、その確からしさを問うための基準自体が失われてしまいかねないからです。しかし、『夢の木坂分岐点』においては、すべては夢のなかであるという理屈を借りることで、容器としての物語世界そのものがきわめて歪んだ形状をしており、特に物語の後半ではほとんど前後の脈絡がないまま変幻自在に流動していくことになります。それは必然的に、そもそも狂っているのは世界なのか「私」なのかという究極の選択を、そこに応対する主人公(たち)に突きつけることになるでしょう。
教えてください。夢の木坂へはどう行けばいいのでしょう。そこには夢の木が立っているのでしょうか。あそこへ行ったのはいつのことだっただろう。それとも夢の中で行っただけだったのか。そもそも今は夢ではないのか。夢の中で虚構を想い、その虚構の中で夢を見た。明日覚醒するその世界は夢か虚構か。
作中では「夢の木坂」という複数の路線が乗り入れる「分岐駅」が、それぞれの夢を留め合わせる蝶番のような役割を果たしていますが、その実在の確かさは最後まで宙づりのままに置かれています。つまり、ここで「私」という存在の不確かさと、夢世界の実在性を担保する外的根拠の不確かさが、奇妙なかたちで共振していくことになるのです。
夢世界というのは不思議なもので、ひとが夢を見る仕組みが、詰まるところ脳内の情報処理に伴う記憶の再構成である以上、その構成の仕方は、たとえランダムであるにせよ、夢を見る主体がいままで過去に経験してきた潜在意識の集積と、ある程度の整合性を持っていなければならないはずです。しかし、実際の物語作品においては、夢を見る主体がまったく経験したことのないような出来事が頻出し、またそのような造型が好まれる傾向にあります。たとえば、クリストファー・ノーラン監督、レオナルド・ディカプリオ主演の映画『インセプション』(ワーナー・ブラザース、2010)は、夢世界の探索を扱った名作SFですが、そこではある人物の夢に侵入していく際、超常的なガジェットを用いて外部から偽の情報を植えつける(インセプション)ことで、その秩序構造を自在に変革できるような工夫が凝らされています。言わば、ここで夢とは、あるべき世界の改変可能性を探るためのイメージの試金石となっているのです(近代日本文学の領域であれば、たとえば内田百閒の小説作品などが思い起こされるでしょうか)。
『夢の木坂分岐点』もまた、夢世界が単なる容器としての機能を果たさなくなっているために、主人公(たち)の切迫した内省はどこか滑稽さを帯び、彼らの旅路は明確な着地点を持たないまま永遠に浮遊しつづけることになります。ここにおいて、伝統的に「私」の内部で試みられていた存在の不確かさをめぐる問いが「私」の外部へと投射されることで、その考察を支える基盤自体が改めて問い返されることになるのです。
加えて『夢の木坂分岐点』の筋立てを、眼の前の世界に対するリアリティの感じ方という観点から捉えなおしてみたとき、本当の意味で夢世界と現実世界の区別がなくなってしまうという端的な事実が、認識主体としての「私」自身の生成変化というかたちで描き出されていることもまた非常に重要です。夢か現実かという一人称的な知覚の不確かさが、「私」という存在そのものの造形変化と重ね合わされることで、主観と客観の混淆という作品全体を貫くモチーフが浮かび上がってきます。それは、数多の並行世界のなかで、とりわけこの現実世界にこそ唯一性・特権性を感じるというのは、そもそも認識論的な問題なのか存在論的な問題なのかという問いを誘発させることになるでしょう。
とするともし今自分が目醒めてもそこは新たな夢の中に過ぎないのかもしれない。彼はそう思い少し寒くなった。チワワのように顫えていることが自覚できる。だがすぐにそれは真実それほど脅えるべきことなのだろうかと彼は考えなおす。大乱歩に「うつし世は夢。夜の夢こそまこと」という箴言があった。目醒めとは実は新たな夢への横滑りであり、実はそれこそが人間の生かもしれぬ。ではいつもと同じことをするわけだ。恐れることはない。昨夜の妻との媾合は夢精に過ぎず明日の会社でのいやな出来ごとは新たな悪夢であるだけなのだからな。
現実世界において、そこに「私」が〝いる〟という事実を出発点として、あるがままその姿かたちを認めていこうとする思考のあり方もまた、夢の世界でまったく同じように成り立ってしまうということに注意してください。夢というのは不思議なもので、端から見ればどれほど滅茶苦茶な内容であろうとも、その当事者にとっては疑いなくこの現実世界であると容易に信じられてしまいます。(夢のなかでこれは夢だと感じられる明晰夢というものを僕は観たことがないのですが、明晰夢をよく観るひとは、もしかしたら現実世界の唯一性・特権性を疑いなく確信できるひとたちなのかもしれません。)どのような夢も、誰かによって観られたものであり、その実在の根拠を外部から暴き立てることが原理的に意味をなさない以上、前述した認識論的な問題と存在論的な問題は、もとより当事者の視点からは区別をつけることができません。先に、どのような時空間であろうとも、いま・ここが「私」の生きるこの現実世界であるという開きなおりについて言及しましたが、そもそもの話、そういうふうにいま・ここ(現実世界か夢世界かを問わず)を把握することでしかひとは生きることができず、ゆえに主人公(たち)はその悲哀自体を何とか肯定しようとしていたのかもしれません。そう考えると、『夢の木坂分岐点』のラストシーン──ネタバレになるので詳細は伏せますが──は、非常に感動的なものとして僕たち読者に迫ってくるように思えます。
その後の筒井作品において、現実世界と夢世界の往還という主題は、たとえば『パプリカ』(中央公論社、1993.9)に、並行世界に生きる「私」という主題は、たとえば『ダンシング・ヴァニティ』(新潮社、2008.1)へと展開していきます。それらはいずれも重要な問題提起を行なっており、きわめて意義深いものなのですが、1987年という時代に書かれた『夢の木坂分岐点』という小説作品は、上記の二作品に繰り込まれたイマジネーションの直接的な淵源となっているとともに、そこにはリアリズムとしての近代小説に描かれていた「私」の葛藤をすり抜けてしまうような、きわめて独特の世界認識が書き込まれていたように思えます。そのような現実世界の唯一性・特権性をめぐる揺らぎは、ゼロ年代の物語文化における〝並行世界ブーム〟の諸相に脈々と受け継がれているのではないでしょうか。
もちろん、そうした思想的課題を取り扱うためのギミックは、何も夢世界に限ったものではありません。現実世界の唯一性・特権性をめぐる揺らぎということで考えるならば、今日最もアクチュアルなものは、やはりヴァーチャル・リアリティ(仮想現実)ではないでしょうか。ということで、次回はヴァーチャル・リアリティを扱った現代日本SFの先駆けとして名高い岡嶋二人『クラインの壺』(新潮社1989.10)を検討していくことにしましょう。