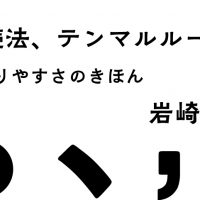1.はじめに/具象化されない不安の価値
対話の場を作りながらその場の持つ意味や妥当性に不安を抱かずにすんだ者は幸いである。だが、表に出しこそはしないまでも、人々の無知[1]であることへの対処は知ってしまうことが最良の解答なのだろうかと、自問自答せずにいなかった者がいるだろうか。
連載第2回でこのぼんやりとした不安を、むやみやたらに混沌に目鼻をつけない方が良いのに[2]と昔語りをしたが、十数年の時を経て、その不安が言語化され始めているという感触を持っている。無知は正されていくべきで専門家はその手助けができるとする主張に対し、消費者団体の人たちは身をひき、私は全方位から光を当てられて謎が何も無くなってしまったら寂しいものだと黙るだけだったが、2022年5月の第69回科学史学会年会「作られた無知の諸相」[3]に接し、目を開かされた。
シンポジウムは、無知が生産される様々なメカニズムを解明する科学史研究の興隆があり、「社会学やジェンダー論の領域でも、知識の不確実性やバイアスが特定のタイプの無知を生み出すことが指摘されてきた」と述べることから始まった[3, 243]。私は、無知(英:ignorance、独:Ignoranz)か非知(英:non-knowledge、独:Nichtwissen)かの区別[4, 247]を脇に置くが、シンポジウムでは無知(非知)の分類[4, 258]および「科学的非知文化—科学内部において知識の生産だけだけでなく、unknownsの発見、解釈、処理の過程に置いても異なる認識傾向が存在する」と紹介された[5, 259]。「無知は悪い側面ばかりではない。抑圧・搾取を内包する研究の禁止やプライバシーの保護など、むしろあえて無知であることが有徳である場合もある」[4, 248]という解釈に私は鼓舞された。
推し進めたい技術を有している側が対話や熟議を通して無知の人々の語りやその構造を理解することは、推進にとっての躓きの石となる物を取り除くことになり、無邪気さを装いながら人々を教化する意図を隠蔽している。連載第2回の4節最後から三段落目の最後で触れたたように、観察を通してだが、消費者団体に所属する市民は知ることと受け入れることを一体としていず、むしろ技術の推進側には組みしていないという態度をとる。蒙を啓いてあげようとする側にとっては空振りとなってしまう。この状況は推進側にとっては好ましくないが、ぐずぐずしている人々にとっては意味がある。科学技術に由来する諸事を時のフィルターにかけることになるからだ[6]。
ぐずぐずしている状況というのは、熟慮したり熟議をしたりする時をもたらす。そして上記シンポジウムで語られたことだが、「既知の未知への対処のみを目指す伝統的な制御指向の非知文化(遺伝子組換え作物の安全性をめぐる論争で言えば、分子生物学や遺伝工学)」に対する「未知の未知に対する高度な敏感さを備えた複雑性指向の非知文化(エコロジー、疫学など)」の対抗と挑戦が強まり、政策の方向転換が生じた[5, 259]ということだ。そのぐずぐずの間に、私たちが問題を認識する枠組みが変容することがあり、政策の方向転換につながることもあると思えた[6]。
今回依拠した事例は、培養肉を題材にした対面で行った農業者ダイアローグと学生アンケートの単純な集計結果等である。培養肉とは、出版物[7][8]や研究者のホームページ[9]などから言葉を借りれば、動物の細胞を培養して増やし、増やした細胞を用いて作られるものである。
北海道東部の大樹町で行われたダイアローグでは4名の酪農家と畜産農家が集まった。札幌近郊の千歳市では酪農・畜産農家に加え農家以外の方も参加した。これら農業者の反応と北大農学院修士課程の学生に聞いた(発話ではなく書かれた文字として)培養肉の第一印象を見比べながら、新興科学技術あるいはフードテック界隈では熟議は求められているのかと問題提起し、熟議を求めていないようにさえ見える今こそ、熟議は必要だと語りたい。
| 時期 | 対話の名称/地域/参加者数/所要時間 | 主催・その他 |
| 2019-20年 11月21日 11月22日 2月24日 2月25日 | 事例23)培養肉農業者ダイアローグ 第1回-1:道東の大樹町/4名/3時間 第1回-2:札幌近郊の千歳市/5名/3時間 第2回-1:大樹町/4名/3時間 第2回-2:千歳市/7名/3時間 | 主催:分野横断リスク問題研究会(北大農学研究院内/世話役:吉田) 協力:JST/RISTEX(資料・情報の提供) |
| 2020年 5月12-26日 | 事例24)培養肉 アンケート:講義終了後に培養肉の第一印象や思うところを述べる/修士課程の171名 | 農学院開講科目「科学研究・科学技術と倫理」第1回を担当 |
なお、事例23)はJST/RISTEXと音源を共有しているがRISTEXの請負で行ったものではない。下記URLに事例23)と24)の簡易とりまとめを置いている。
2.イメージし得ないものをどう語るかという難問/培養肉農業者ダイアローグ
2019年春、NHKラジオの早朝番組で培養肉が紹介されたのを聞いたとき、ある宿題が思い出された。連載第1回の事例2)—「振り向けば、未来」第5回の「翻弄されたと畜場(2010年7月12日)」—で話題提供者が参加者に投げかけた問いで、私は浅慮にもBSE問題にこだわり過ぎ、適切に受け止められず、対話の枠組みの外だと見做し、宿題としただけで報告書には直接的な表現では盛り込まなかった。「みなさん、肉を食べるとはどういうことなのか、肉を食べる文化とは何だろうと考えたことはありますか」[10]と問われたのだ。これは、命をいただくという行為を含め、肉を食べる文化というものを正面から考えてほしいという、狭い枠組みに縛り付けられた私たちへの、と畜業者からの切実な語りかけだった。
2019年の夏には、11月開催予定の科学技術社会論学会年次研究大会で、「培養肉のELSIを考える」というセッションのディスカッサントを務めることになった。オーガナイザーはJST/RISTEX科学技術振興機構社会技術研究開発センターの三村恭子氏で、私が招かれた理由は、BSE問題、遺伝子組換え作物やゲノム編集作物の問題を中心に市民や農業者を交えた対話活動をしていたからである[11]。その後RISTEXとは変則的ながら小規模な培養肉農業者ダイアローグを企画することになり[12]、目的の設定や簡単にはいかない参加者の勧誘、会場の確保などプログラム作成は私が担当し、資料提供(RISTEXが所持している資料に基づいた説明をRISTEX側が行う)と会場費および現地への私の旅費等をRISTEXが担当した。音源は共有するが分析結果等は共有しない、つまり語られたことの使われ方は両者では異なるということで合意した[12, 3]。なお、参加者には謝金は支払われていない。
ダイアローグ(2019年11月〜2020年2月)参加者は農業者としての矜持を語り、培養肉への違和感を表明した。第1回の全参加者9名のうち8名は培養肉という言葉を知らなかったと述べた。1人の畜産農家だけが言葉を知っていて、漠然とiPS細胞(人工多能性幹細胞)にイメージを重ね、「iPS細胞は(再生)医療でお世話になっていて大事だとわかっている(が、…)」[12, 5]と発言している。この連想は間違ってはいず、開発者も2022年3月に「最終的に、再生医療にも応用できたら」[13]と述べているし、厚生労働省の2022年12月の某審議会資料でも、培養する細胞が固体由来か細胞株由来(人工多能性幹細胞iPS細胞も含まれる)かの2系統に分けて情報提供されている[14]。
さて、大樹町の第1回を振り返るなら、参加者は全くイメージできないものを如何に受け止めるかで苦慮し、培養肉登場の理由が後付けに思えると述べることから始めた。このとき彼らは、「通常の肉にとって代わろうとしているのかどうか不明で、畜産を否定しないのなら、情報提供の際の表現に工夫と配慮が必要」で、「牛の環境負荷は確かにあるが、これまでも散々言われ研究もされているのではないか」と述べ、農家も研究者も何もしていなかったわけではないと反論を試みている[12, 5]。その上で、自分たちはメガファームではなく小規模農家であり、地域での循環を意識した上での牛飼いの矜持を持っていると語った。正体不明のフードテック食品に対して生産者の矜持で応じたのだった。家畜の糞尿も「身の丈にあった小規模農家の場合、畑に返すという地域での農業の営みの範囲で評価される」[12, 6]と、循環する堆肥として捉えることができ、大規模化するとその循環が困難になると語っていた。
このような語りは、主催側に酪農・畜産農家を一括りにすることはできないと気づかせた。ダイアローグは、培養肉開発側のステークホルダーになるであろう農家の考え方を知る上での手頃なツールになったが、参加者には役立ったという実感をもたらしてはおらず(事後アンケートは行わなかったが、もっとしっかりした対話の場が必要だったと、しばらくしてから電話で言われた)、効用は両者で非対称だった。この非対称性を予測し得たのに、私はなぜダイアローグを企てたのか。それは、考えるためには情報が必要で、情報は持っている側からもらうしかないということに尽きるのだが、同時に情報提供側との質疑応答を超える語り合いを、参加者間の対話の始まりを期待したからだ。小さな対話をその先の議論につなげる出発点にしたかったからで、場の持つ限界については事前に参加者の了解をもらっていた。
A:突っ込んで言えば、人工的というのと自然というのとどう違うのかということ。人工的といっているけど、それは環境を人工的にして、実は自然的にどんどん増殖していっているではないか。これ人工と言えないんじゃないかという理屈が成り立つかもしれませんね。
吉田:なるほど逆か
A:そう。どこを人工的というのか、自然というのか。
吉田:培養肉も見方を変えると
A:自然じゃないか
C:自然だよな
吉田:研究開発される方達が、怖がる消費者は自然を崇めて人工的なものを拒否して困るって言い方をしますけれど、ここで提示されたのは、自然と人工が交換し合うってこと(ですか)。
C:さっき(話を聞いたけど)、血管は何で(どうして)できるのか、なんてのは分かっていない。分かっていないけどできるんだよな。それは自然の摂理、我々の分からない自然の摂理なんだよな。
A:(そういうことは)いっぱいある。
C:無限にある。分からないことだらけだ。
大樹町での2回目で、参加者の「食品というのは元々自然界にあるものという、自然なものであるというのが、哲学、鉄則…人工的に作ったものが本当に食べ物としていいのかどうか」との語りを受けて、「自然界から作られたものということの奥の方には、前回出ていた、食べるものは命をいただくことだという循環につながるということですか」と聞いてみた。そうだと答えるので、さらに「培養肉をたべるということは命をいただく(自然なこと)ということに抗っているというイメージなのか」と問いかけた。自然か人工かという点についてどのように思っているのかを知りたかったからだ。しかし、上記の囲みのように、こちらの思惑を超えた語り合いとなった[12, 12]。
3.学生たちの語り方
学生はどう語ったか。事例24)は北海道大学農学院の学生が応じた「培養肉アンケート」[12, 13-29]である。2020年5月12日に「リスクコミュニケーションを再考する」という講義の締めくくりでフードテックの話題として、ベンチャーのみならず日清や日本ハムなどの大企業も乗り出し始めた培養肉を紹介した。簡単な集計報告を皆さんに配るという約束で、第一印象を2、3個書くようお願いした(直感で深く考えず手短にと指示)。ほとんどの学生が第一印象を書いた後で、考えたこと(熟考したと思われる)をしっかり書き連ねていた。これは誤算で、集計に手間取ることになった。
下表のように、発言総数1,337個のうち311個の直感的な第一印象を除いた1,026個を4群に分類し、各群をさらに16項目に分けた。数字の前に付けた(+)と(−)の符号の意味は、(+)が培養肉に対し肯定的に述べているもので、(−)は否定的に述べているものである。言及数は関心の高さを反映すると仮定し、70個以上で線引きすると、順に「6. 肉の美味しさ・品質」>「5. 購買意欲・価格・商品内容や宣伝」>「9. 地球環境問題と家畜と培養肉」>「1.技術開発・可能性・開発目標」>「12. 動物福祉とヴィーガン」>「13. 今の酪農・畜産・農村及び関連他産業が被るさまざまな影響」となる。
なお、第Ⅱ群「食べるという行為については」の「7. 食文化・食育・食べる楽しみの視点」と「8. 倫理・フィロソフィー」の2項目を合算すると最大(132個)の関心事になるので、学生たちは食べるという行為に付随する事柄に強い関心を示したとも言える[15, 2]。
| 群 | 中項目(Ⅰ- Ⅳ群中16項目) |
| Ⅰ. 培養肉開発 =技術開発・安全性・リスクおよびレギュレーションについて = 226個 | 1.技術開発・可能性・開発目標 91(+31, 53, – 7) 2.安全性・安全性の保証・食べて大丈夫かという懸念 52(+3, 21, – 28) 3.健康影響評価・リスク・意図せざる何か・事故や責任 43(0, 27, -16) 4.レギュレーションの問題 40(0, 40, 0) |
| Ⅱ.食べるという行為について =368個 | 5.購買・価格・商品・宣伝の面から 113(+16, 81, -16) 6.肉の美味しさ・品質について 123(+9, 82, -32) 7.食文化・食育・食べる楽しみの視点から 68(+2, 48, -18) 8.倫理・フィロソフィー 64(+4, 47, -13) |
| Ⅲ.培養肉が掲げる長所について=258個 | 9.地球環境問題(温室効果ガス、水質汚染、土地問題など)と畜と培養肉 97(+29, 52, -16) 10.人口問題と食料問題 56(+34, 18, -4) 11.家畜や野生動物と感染症の問題 27(+22, 5, 0) 12.動物福祉とヴィーガン 78(+27, 46, -5) |
| Ⅳ.ステークホルダーへの配慮=畜産・酪農・関連産業への影響= 174個 | 13.今の酪農・畜産・農村及び 関連他産業等が被る様々な影響 72(0, 52, -20) 14.今後の培養肉産業・酪農畜産の今後の展開と家畜が有する特質や多角的な視点 34(+6, 21, -7) 15.人件費を含む生産コストと大量生産につなげる試みの視点から 44(+13, 21, -10) 16.設備投資とランニングコストおよび総合的判断 24(+3, 15, -6) |
| Ⅴ. 直感的な第一印象=311個 | ■. 第一印象として 174(+46, 46, – 82) ■ 主張 68(+11, 51, -6) ■ 懸念やモヤモヤしたもの 69(+6, 48, -15) |
学生は技術開発や培養肉が掲げる長所を高く評価している。同時に、直感的な第一印象では食料安定供給上の複合リスクの心配をしていて、電力依存は食料安全保障上のリスクを発生させると認識し、培養肉生産に完全シフトすることはリスクがあると述べている。培養肉生産システムが破綻した時を想定し、仮に培養肉依存の世界になっていたとして、さまざまな問題で工場が稼働できなくなった場合、その対処や伝統的食肉生産へ戻るまでの道のりの困難さを想像している。家畜はいったいどうなるのか、絶滅しないようこれまでとは異なる管理が必要になるのだろうかとも問い、培養元の家畜はどれくらい残すべきなのかと問いを投げかけている[15, 12] 。
学生は培養肉に対し、「家畜が温室効果ガスや水質汚染の要因なので状況緩和に貢献」し、「食料問題を解決し、感染症の低減に貢献し、食中毒を減らし、動物福祉に寄与する」とし、「肉を生産するために必要な牧草地・畑や畜舎など、土地を必要としないので有望だ」と考えているが、切り札であるとするのではなく「冷静な検証が必要だ」と考えている[15, 6]。
農業者は暮らし方を含め日々の営みを通して培養肉を考え、学生も自分の専門分野と食べるという行為から考えている。農業者たちは牛と共に地域を循環させるという生活信条あるいは日々の営みの哲学を語った。学生たちは前向きな科学主義に立脚する一方で、農業が抱える命を育て奪うという本質を受け止めており、農業者と同様に工場生産的・産業的な農業哲学[16, 121-2]への懸念を表明する者たちもいた。
4.フードテック技術に熟議は似合わないのか?
培養肉では人々の間にどのようなコミュニケーションが生じるであろうか。情報の伝え方やコミュニケーションに関しては、農業者と学生とでは語る際の視点が異なっていた。消費者、生産者、研究開発者が同じテーブルを囲んで話し合うにはどのような枠組みが妥当なのだろうか。今は先行きが見えない。研究開発側も「培養肉が社会に出るときのハードルとは…むしろ新しいものへの枠組みを設ける決断の困難さだともいえるのではないか」[8, 58]と語っていて、先行きを眺めている。
ダイアローグから見えてくるのは、農業者は情報の受け手側の視点を持ち、情報の伝え方一つで人々の受け止め方は影響を受ける、と考えていることである。「培養肉はSDGsにつながるという言い方は、うまく都会の消費者を絡めとるやり方だ」と言い、「災害もうまく利用して、異常気象・天候に左右されない農業ということで、自然だけでは難しいから培養肉へと誘導されていく」と語った[12, 7]。
農業者はまた、地球規模の課題に対し自分たちの課題としてどう向き合うか(知って考えることは大事だ)という視点から、「対立構造にある人たち、食べる人・作る人が一緒になって話し合う」ことを望み、そのために難しいけれど「向こう(開発側)のやり方によらない」場で、「みんなで議論しないと(ならない)」と願っている。また、あちらこちらでそれぞれみんなが(勝手に)言い合っているので、コーディネーター役が必要だとも述べていたが、その役を誰が担うのが望ましいかについては語られなかった[12, 7]。
それに対し学生は、開発・研究者の立場で知識や情報を発信し普及する側の視点で語る。説明・教育・啓蒙という意味での情報公開と情報の共有の必要性を述べ、リスクコミュニケーションを積極的に行い研究者と大衆のリスク認知の差異を縮小することを推奨する。とはいえ、学生も意思決定に際しては議論が必要だと認識していて、「複雑に絡み合っていることの一つ一つに焦点を」あわせることの大事さに言及している。そして専門家に期待する。「意思決定を主導することが専門家の責任だ。(専門家は)その素質と可能性において議論の音頭取りをして、研究を社会に還元するよう試みてほしい」とまで言っている[15, 7]。
学生はまた、市民との意見交換や議論を、市民との相互理解のための情報共有の手段として有用であると考えている。その理屈は、「十分な情報開示の必要性」からであり、また「消費者の抵抗は開発・研究者が粘り強くリスクの大きさ、メリットを説明することでなくすことが可能」とも考えている。同時に、「消費者は怖がるだけでなく知ろうとする姿勢も大事だ」と述べており、上述した農業者の知って考えることは大事だという姿勢にもつながる[15, 7]。
だが、知った上で選択したり拒否したりすればよいとする消費者(農業者)の姿勢は、研究競争に晒されている開発者に受け入れられるだろうか。この状況は、成果物として未だ姿を見せていない研究開発の最上流の場合とも、出来上がり流通に乗る段階という場合とも異なっている。前者であれば、文末脚注[17]に示したように、研究へのフィードバックがある意味可能な対話の場が考えられ、後者であれば、ゲノム編集トマトのように理解増進のためのリスクコミュニケーションが展開されるだけであろう。
培養肉開発への参入者は多様で、動きは急速である。開発側は、どのようなコミュニケーションを誰と行いたいのだろうか。一般の市民・消費者の中に支持者を増やすためのコミュニケーションであるなら、熟議はむしろ足枷になると考えるかもしれない。自陣営に囲い込むためのアクションこそが必要で、華々しいデモンストレーションこそが相応しいと考えるかもしれない。ステークホルダーとのコミュニケーションは試みられるのだろうか。
培養肉開発側のステークホルダーでもある酪農・畜産農家が望んでいたのは、情報を得た上での対話や熟議であり、学生が主にイメージしていたのは、開発者が率先して理解して支持してもらうためのコミュニケーションである。両者はどうすれば接続可能となるか。農業者が望んでいるような対話の場は果たして実現可能だろうか。
問いで終わらせるのであれば連載に挑みはしなかった。ひつじ書房松本功氏の誘いを受けて躊躇った際に自覚したのは、自分も語りたいということだった。そして、実は密かにもう一つ予感していたことがあった。熟慮を片手に熟議の扉を開ける方向に一歩進み出ることができるのではないかと。公的資金を得て2005年から始まった対話・熟議の場づくりは、2004年の、お金をかけずにできる範囲で、手弁当で始めた市民と研究者との対話の会が発端になった。ほぼ20年経った今、対話の場を諦めず・手放さず、もう一度手弁当で試みようと思う。
反感であれ好感であれ、関心を持つ人々が熟議の場を、情報取得機能とするだけではなく、教え諭される側からの異議申し立て機能を持つものとしてとして保っていくことは、フードテックの健全な展開にこそ必要なのではないかと、開発側に問いかけたい。
枠組みの問題など課題は多いが、基礎研究の始まりと製品化目前の中間点に位置する培養肉というフードテックにも、熟議は似合う。
【最後に】
連載は、対話の場ではどのように語られたのか、それはどんな語り口だったのかという文脈で、論文としてではなく語り物として書きました。お読みいただいた皆様の中には、当然ですが、異論や反論もあろうかと思います。ひつじ書房にそういったご意見をお送りいただけましたら、可能な限りお応えしたいと思っています。なお、私の周りには培養肉に対し懸念を示す人たちばかりではなく関心を持つ人たちもいます。学生たちも農業者たちも、同床異夢かなとは思うものの、共存するという視点を持っています。
ご意見、ご感想、反論などは以下のメールアドレスにお送りください。
toiawaseアットhituzi.co.jp
<了>
参考文献と注 (URLの最終閲覧日はいずれも2023年2月17日)
[1] 本堂毅・平田光司・尾内隆之・中島貴子(2017)『科学の不定性と社会』信山社。第7章「「科学の不定性」に気づき、向き合うとは」, 107−121 /プロジェクト研究を始めてしばらくの間は、やがて解決される無知とそれ以外という大雑把な区分でBSE全頭検査問題を考える対話の場を準備していた。知らないという状況は政治的なのだと感じる瞬間は何度もあったし、対話の題材にする項目の取捨選択において自らもそうしていたのではないかと、今でも思い悩むことがある。無知については連載第4回の文末脚注[17](井口暁 (2019)「第三部 リスク・ダイアローグの可能性」『ポスト3・11のリスク社会学〜原発事故と放射線リスクはどのように語られたのか』ナカニシヤ出版)が参考となる。
[2] 連載第2回の注[3]( 湯川秀樹(2017)「具象以前」『詩と科学』平凡社、p.54. )
[3] 2022年5月29日の科学史学会第69回年会シンポジウム「作られた無知の諸相」 科学史研究No.303, 243-274.
[4] 鶴田想人、岡本江里菜、村瀬泰菜(2022)「無知研究の諸相—無知学・無知の社会学・無知の認識論」『科学史研究』No.303, p.244-250.
[5] 井口暁(2022)「アグノトロジーと非知社会学」『科学史研究』No.303, pp256-265.
[6] ぐずぐずの効用とは時の効用でもある。2004年から06年にかけての「北海道食の安全安心条例」と「遺伝子組換え作物等の栽培等による交雑等の防止に関する条例(いわゆる北海道GM条例)」が出来上がり機能していくプロセスを間近で見ていて、条例の見直しに関する条項を付ける根拠に道庁農政部職員がよく話していたのが、「時のアセスメント」という公共事業での政策評価システムの考え方である。「時の」という言葉自体の発端は道の幹部職員(後の北海道副知事 磯田憲一氏)と作家の倉本聰氏との対話にあり(https://www.fsight.jp/7109)、「時のアセスメント」という言葉は当時の堀達也北海道知事が1997年の新年の挨拶で用いたと言われている。時のアセスメントの意義については山口二郎北海道大学名誉教授(現法政大学教授)(https://www.jbaudit.go.jp/koryu/study/mag/pdf/j20d05.pdf)が1999年に論じている。
[7] ポール・シャピロ(2020)鈴木素子訳『クリーンミート』日経BP
[8] 竹内昌治、日比野愛子(2022)『培養肉とは何か?』岩波ブックレットNo.1072、岩波書店
[9] 東京大学竹内昌治研究室ホームページ http://www.hybrid.t.u-tokyo.ac.jp/culturedmeat/
[10] リスコミ職能教育プロジェクトホームページ(http://lab.agr.hokudai.ac.jp/voedtonfrc/)の「旧プロジェクト等の報告書」バナーに置かれている報告書「振り向けば、未来」、p.17.
[11] 第18回科学技術社会論学会総会・年次研究大会オーガナイズドセッション「D-1-1 【OS】 培養肉の ELSI を考える」(https://jssts.jp/wp/wp-content/uploads/2022/11/sts2019_program_ver2_20191001.pdf )
[12] 農業者ダイアローグ集計と学生アンケート集計を、それぞれの言葉を残しながら、別々に整理した後で一つにまとめたもの。学生には短縮版を配布している。「報告 培養肉に対する様々な見方」(http://scri.co.jp/食と農をめぐる対話ラボラトリ/?fbclid=IwAR2WP97hSb8Kmh18qNl3zWkBgy3JVP-1OoJNTip78TFaKFfdNZsY7v_qMVg)。記事本文(p.2)でiPS細胞に重ねた参加者の語りは、インテグリカルチャー社の川島一公氏の2022年3月11日付発言「私も再生医療をやっていまして、最終的に、再生医療にも応用できたらと考えています」[13]に接続する。
[13] 川島一公(2022)「細胞培養技術が切り開く未来」『日本農業の動き216』農政ジャーナリストの会、78-104(104)/インテグリカルチャー社の川島一公氏の2022年3月11日付発言「私も再生医療をやっていまして、最終的に、再生医療にも応用できたらと考えています」
[14] https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001021172.pdf 2022年12月12日開催の厚生労働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会において、議題3のその他として北嶋聡委員が「細胞培養食品について—食品衛生上のハザードやリスクを考慮」と題した講義資料である(pp.8-10)。
[15] 前出[12]の報告を下敷きに、農業者と学生の言葉を重ねたものである。「素案+萌芽的研究では初期段階で市民との対話は行わない方が良いのか」(http://scri.co.jp/食と農をめぐる対話ラボラトリ/?fbclid=IwAR2WP97hSb8Kmh18qNl3zWkBgy3JVP-1OoJNTip78TFaKFfdNZsY7v_qMVg)
[16] 秋津元輝、佐藤洋一郎、竹内裕文(2018)「序 農と食の新しい倫理を求めて」『農と食の新しい倫理』昭和堂、p.8。「食料を他の物資と同様に扱い、農業を他産業と同様と見なす産業的農業哲学」と「農業は、その固有な倫理的性格ゆえに、他の産業形態から区別される」とする農業哲学がある。
[17] 分子ロボット倫理委員会(2022)『分子ロボットをめぐる対話要点集』CBI学会出版 https://cbi-society.org/home/documents/eBook/ebook4_MolRobo2020.pdf 基礎研究の段階で、一般の人には全くイメージできない分子ロボット(https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202202192307.html)なるものを題材に、農業者や消費者がどのように反応するかを確かめ、研究にフィードバックさせることを目的として行った対話であり、主催したのは分子ロボット倫理研究会である。