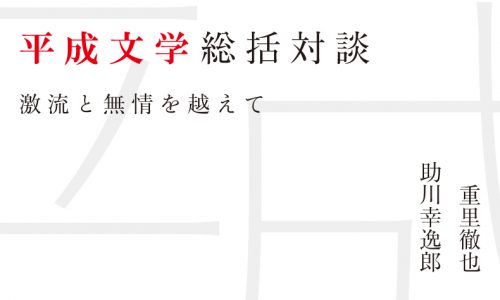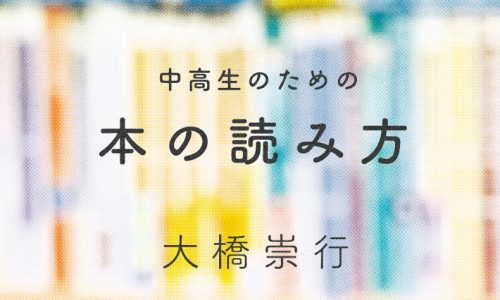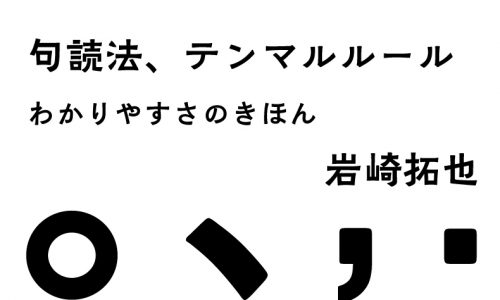- ホーム
- その他
その他
-

書評『人間とは何だろうか―脳が生み出す心と言葉』(酒井邦嘉著 河出書房新社 2025年12月)
文部科学省 教科書調査官(体育) 渡辺哲司1. 言語学徒こそ読者言葉こそが人間の本性――と郷田は言う(第5章)。郷田とは、言語学者/彫刻作家に…
-
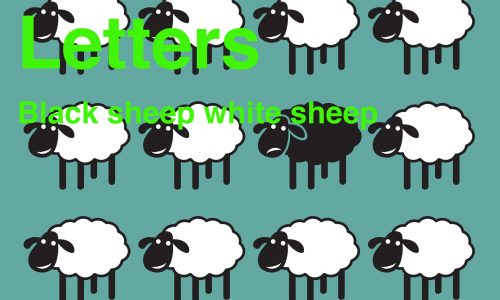
『デュルケーム世俗道徳論の中のユダヤ教』伊達聖伸氏書評への著者からの回答(平田文子)
伊達聖伸氏の書評(『週刊読書人』2022年4月22日号)を拝読し、伊達氏には、本書に関心を持っていただいたこと、複数の指摘や意見をいただいたことに心より感謝…
-
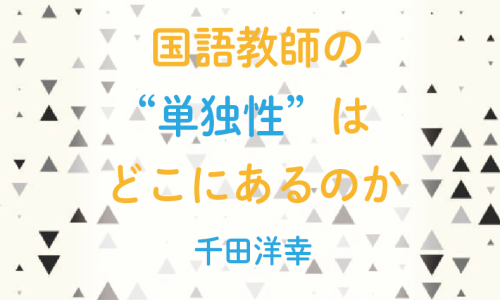
国語教師の“単独性”はどこにあるのか|第11回 教師「である」ことと教師「する」こと|千田洋幸
予備校や塾の講師、高校での非常勤講師などもふくめると、教師という立場に自分をおいてからすでに40年以上が経過しているが、いまだに「先生」と呼ばれることにかす…
-

地域に息づく方言オノマトペの世界|第1回 地域に息づく方言のオノマトペ|川﨑めぐみ
方言オノマトペはどのようなもの?方言には独特のオノマトペ(擬音語や擬態語)の表現があることをご存知ですか。お住まいの地域に特徴的な方言のオノマトペがあっ…
-
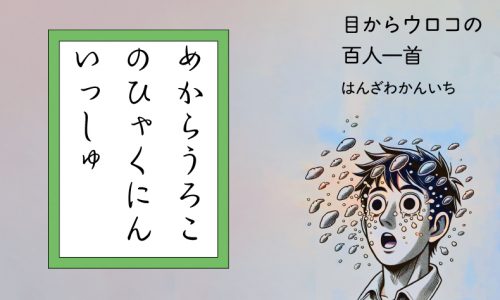
目からウロコの百人一首|第17回 42 契りきなかたみに袖を絞りつつ末の松山浪越さじとは|はんざわか…
2011年に起きた東日本大震災の時の津波によって、浪がついに「末の松山」を越えたということが、当時、一部で話題になりました。まさに「想定外」のことが起き…
-
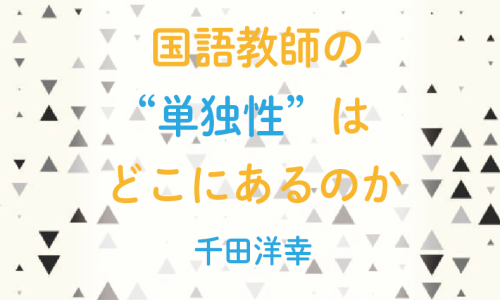
国語教師の“単独性”はどこにあるのか|第10回 “醜悪な言葉たち”は学習対象たりうるか|千田洋幸
私は授業で、物語の両義的な機能について説明するために、ふたつの古典的な論文を紹介することがある。ひとつは内田伸子「絵本の読み手から語り手へ」、もうひとつは本…
-
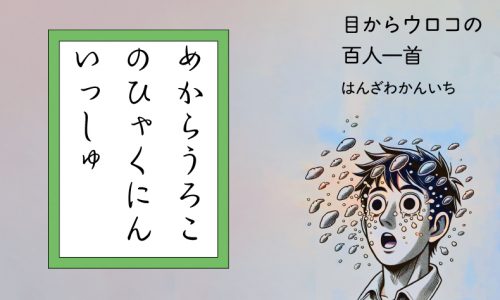
目からウロコの百人一首|第15回 39 浅茅生の小野の篠原しのぶれどあまりてなどか人の恋しき|はんざ…
浅茅生の小野の篠原しのぶれどあまりてなどか人の恋しき この歌は、後撰集(巻9・恋一・577番)から採られたものですが、古今集(巻11・恋歌一・505番…
-
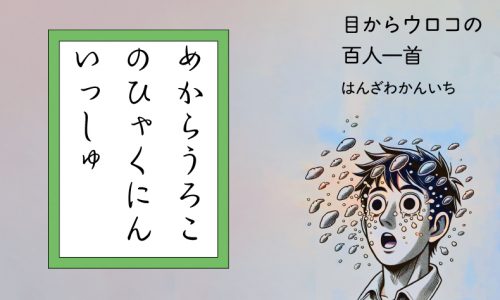
目からウロコの百人一首|第13回 35 人はいさ心も知らずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける|はんざわ…
人はいさ心も知らずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける 古今集(巻1・春歌上・42番)には、「初瀬に詣づるごとに宿りける人の家に久しく宿らで、ほど経て後に至れり…
-
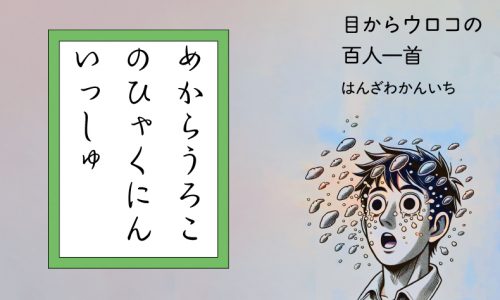
目からウロコの百人一首|第9回 13 筑波ねの峰より落つるみなの川恋ぞつもりて淵となりぬる|はんざわ…
筑波ねの峰より落つるみなの川恋ぞつもりて淵となりぬる ご当地ソングというのがありますが、この歌も「筑波ね」や「みなの川」という、今の茨城県でも代表的な…
-
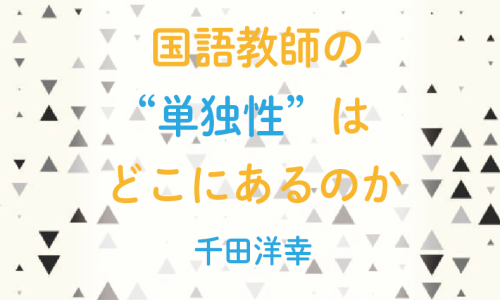
国語教師の“単独性”はどこにあるのか|第8回 教室のタブー/教材のポテンシャル|千田洋幸
みずからの教材論を授業実践とどう有機的にむすびつけるか、というテーマは教師にとって永遠の課題だろうが、教材論に文学研究や批評における成果…