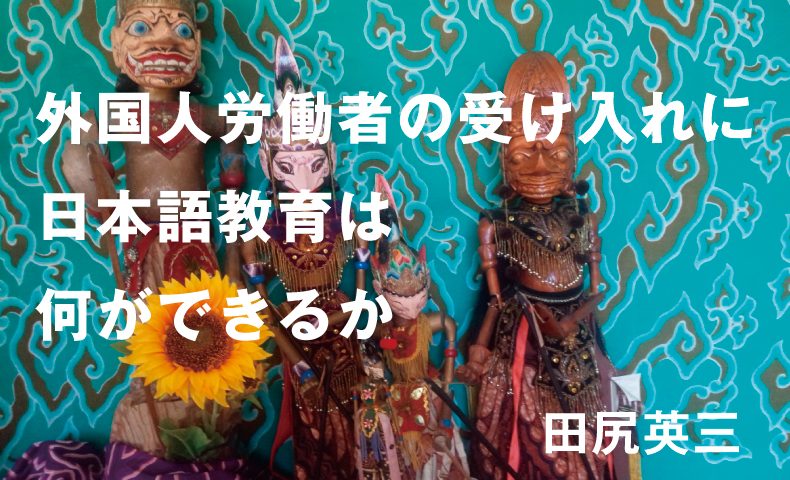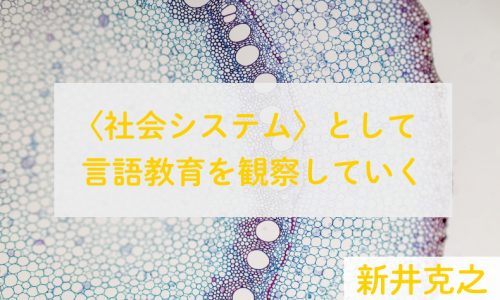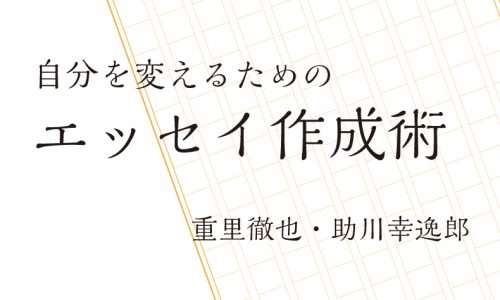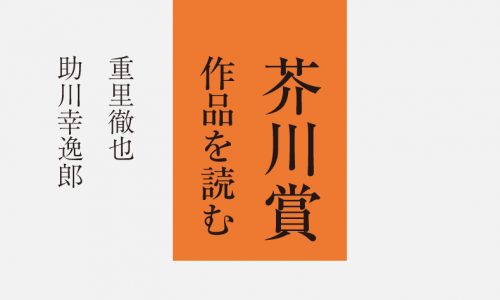★この記事は、2025年9月30日までの情報を基に書いています。
なお、過去の政府の外国人施策については、第62回で扱っています。必ず参照してください。
東京都議会選挙時から始まった外国人政策の政治問題化は、自由民主党総裁選挙では重要な争点となって表れてきています。
今回は、現時点までの外国人政策の政治問題化の流れを見ていきます。そこでは、日本語教育についての目配りはあまり感じられません。日本語教育関係者は、その点について問題意識を持たないのでしょうか。
1. これまでの流れ
2025年6月22日開票の東京都議会銀選挙で当選者を伸ばして注目されたのは、国民民主党と並んで参政党(0人→3人)でした。
そして、2025年7月20日投票が行われた参議院選挙では、参政党の当選者は0人から7人になりました。参政党は「日本人ファースト」をキャッチフレーズとして、外国人の増加を選挙では問題にしました。そこでは、インバウンド外国人旅行者、外国人の土地所有、在留外国人などの増加を一緒にして扱っています。そして、そこで訴えられた問題の多くはエビデンスの無い事例であったことは、橋本直子さんやマスコミにより明らかにされました。
それでも、既成政党は参政党の「日本人ファースト」という外国人排斥への訴えが有権者の投票行動に関係していると考えて、それに呼応する動きを始めました。
田尻は、第63回に書いたように、この流れが起こった原因の一つは、これまでの政府による外国人受け入れ施策の説明不足と考えています。移民を受け入れているのに公式的には存在しないとする「ステルス移民政策」と呼ばれたこともありました。
これも第63回に書いたことですが、すでに実施されている外国人管理行政の厳格化は、以下のように、今も進んでいます。
- 在留資格「管理・経営」での資本金要件が500万円以上から3000万円以上に大幅に増額され、常勤の職員も二人以上必要であり、「中小企業診断士による事業計画確認」も必要となりました。また、9月11日の朝日新聞によると、申請者か常勤職員のいずれか一人に「相当程度の日本語能力」を求める可能性もあると報じられています。あたかもアメリカのトランプ政権による専門技術を持つ外国人向けのH-1B申請の手数料を10万ドルにしたことと呼応しているようも見えます。在留資格「管理・経営」の件は、9月25日締め切りのパブリックコメントの欄で意見募集が行われました。施行日は、2025年10月中旬となっています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000115&Mode=0
現在「管理・経営」の在留資格を持つ人も、今後は更新時に影響が出るかもしれません。
行政書士法人ACROSEEDの「ビザ申請サービス」のサイトによれば、資本金3000万円以上の企業は約4%にとどまっていることを考えれば、この措置はかなり厳しいものになります。
以下に、身近にいる外国人への不満・不安が原因となり問題化された事例を列挙します。
- 9月25日、JICA アフリカ開発会議に合わせた会合で出された「アフリカホームタウン構想」撤回
JICAが発表した構想では、山形県長井市をタンザニアの、千葉県木更津市をナイジェリアの、新潟県三条市をガーナの、愛媛県今治市をモザンビークの「ホームタウン」と認定して交流を行うことにしましたが、日本の各都市に「移民反対」という大量の意見が寄せられ、9月25日JICA理事長が記者会見をして撤回を表明しました。
この構想自体JICAの当該地域への事前説明が十分ではないこともあり、移民受け入れという点だけが強調されて炎上してしまい、構想の撤回ということになりました。今後の日本のアフリカ政策に影響を与えることが懸念されています。 - 9月18日、宮城県村井嘉浩知事は県議会で、イスラム教徒向けの「土葬墓地」設置を白紙撤回しました。10月26日投開票の宮城県知事選挙で、新人候補が「移民に繋がりかねない」として県主導での「土葬墓地」の取りやめを公約に挙げたことが背景にあると言われています。
- 9月22日、北九州市教育委員会が「ムスリム対応の給食実施を決めた」という情報がSNSで広がり、1000件を超える抗議などが寄せられたため、教育委員会はそのような事実はないという記者会見を行いました。毎日新聞によると、事実としては、「にこにこ給食」としてアレルギーなどに関わる28品目を除いた給食を実施することになり、その中に豚肉も含まれていたということを捉えてこのような噂が広まったそうです。田尻としては、この北九州市の取り組みを評価します。
2. 日本維新の会の「外国人政策及び『移民問題』に関する政策提言」について
9月19日に日本維新の会藤田代表が鈴木法務大臣に政策提言を申し入れました。藤田代表は、党内では「外国人政策と人口戦略調査会」の会長です。
https://o-ishin.jp/news/2025/09/19/17456.html
提言のURLは、次のとおりです。
https://o-ishin.jp/news/2025/images/d7bcd9a9198ec55cc96b66fb056da2dbe4295b4a.pdf
参議院選挙後で外国人政策に特化した提言を出したのは、現時点では日本維新の会だけです。この提言をこの時期に出した意図は田尻には分かりませんが、この時期にこのような提言を出した意味は大きいと考えて、大事なポイントを扱うことにしました。
今後、他の政党が同様の外国人政策を出した場合には、必ずこの「未草」の記事で扱うことにします。
記者会見では、日本維新の会は「これまでの国家戦略なき移民政策とも言える対応に真正面から向き合う抜本的改革案として提出した」と述べています。
前文の「政策思想と基本認識」には「日本語教育の充実」とありますが、日本語教育に触れたのはこの箇所だけです。人口については、「2040年代に外国人人口の比率が10%を超えると想定」しています。
第1部「国家戦略の確立」では、以下の項目が挙げられています。
- 外国人比率を含む人口戦略の立案(田尻注:外国人比率は高めに想定しています)
- 外国人受入れを含む「人口政策」を統括する司令塔機能の強化(田尻注:具体的な部署名は挙げていません)
- 外国人政策担当大臣の新設
第2部:国家戦略に基づく外国人政策の整備
第1章:違法行為への対応と制度基盤強化
〇出入国在留管理庁の人的体制強化と専門性向上
〇不法滞在者の確実な出国確保と強制送還体制の構築
〇偽装滞在・不法滞在・「移民ビジネス」への厳格な取締り強化(田尻注:「特に、日本語学校や専門学校、技能実習制度を悪用した『移民ビジネス』が横行」という表現が見られます)
〇外国人犯罪対策と治安・法秩序の維持
〇難民等認定制度の厳格化と真の人道支援の強化
〇国籍取得審査の厳格化と帰化取消制度の創設(田尻注:すでに永住権の取消事項は決められました)
〇査証発行審査の厳格化と日本版ESTA(電子渡航認証システム)早期導入
第2章:制度の誤用・濫用・悪用への対応
〇社会保険料未納・医療費未払いの実態調査ならびに厳格対応(田尻注:「専門家の試算によれば、外国人の財政への貢献は平均129万円である一方、財政からの受益は171万円となり、差し引き42万円の財政赤字となっているとの指摘もある」とありますが、根拠は示されていません)
〇帰国後も含めた不正給付防止のための追跡体制整備
〇医療費窓口負担未払い、生活保護制度適用及び高額医療費適用の厳格対応
〇給付金などの支給対象の厳格化
〇留学生への奨学金制度の適正化(田尻注:「学部・修士課程における留学生への給付型奨学金は、卒業後の日本での就労を条件とする『契約型奨学金』に転換する。」、「博士課程については分野別の戦略的配分を行い、安全保障上懸念のある分野は特定国からの留学生を除外する」、「奨学金受給留学生の卒業後5年間の進路追跡調査を厳格化する」、「真に日本の国益に資する留学生支援制度を構築する」などの表現が見られます。留学生の国籍差別になる可能性を懸念します)
〇外国人児童の教育機会確保と公教育制度の適正化(田尻注:「近年では、日本の学校に在籍しながら日本語がほとんどできない状態で進級・卒業する『学びの空洞化』や、外国人学校に通いながらも日本社会との接点を持たない『言語的孤立』の問題も生じている。さらに、ウィークリーマンションに住民票を置いて学区内の公立学校へ通う外国人児童が都市部で増加するなど、公教育制度の趣旨に反する事例も報告されている」などの制度に関わる事例は確たるデータを示してほしいと思います。「外国人児童」は「外国人児童生徒等」とすべきです。理由の説明は省きます)
また、以下の点にも言及しています。
- 「学齢期の外国人子女に対する公立学校入学前の言語習得学校(プレスクール)制度を創設し、『JSL(第二言語としての日本語)カリキュラム』の導入と専門教員の配置を進めることを提言する」(田尻注:「プレスクール」はすでの文部科学省の『帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業』として実施されていますし、『JSLカリキュラム』小学校版は2003年に、中学校版は2007年にできています。『専門教員』が何を指すのかは不明です)
- 「国による支援員の大幅増員」(田尻注:この点は賛成ですが、どのような支援員を想定しているのかも不明です)
- 「教育無償化制度については、原則として日本国籍保有者を対象とすることとし、外国人については納税実績等を考慮した段階的な適用を検討すべき」(田尻注:運用にあたっては慎重であるべきです)
第3章:社会統合を重視した外国人の受入れ
〇外国人集住都市の適正化と地域コミュニティ支援
- 「特定の民族が急速に集住した地域では、ゴミ出しや騒音などの生活習慣の違いによるトラブル、自治会活動への不参加、言語の壁によるコミュニケーション不足を原因とした地域住民との分断などの問題が生じている。また、特定民族の集住地域が固定化することで母語の文化圏が形成され、日本社会との接点が少ない閉鎖的なコミュニティとなるリスクも指摘されている」(田尻注:ここだけ「民族」という語を使っていることなどから、ある特定地域のことを指しているのでしょうが、この地域を明示し、実態調査をしたうえで提言すべきと考えます)
〇外国人の日本語能力及び日本社会への理解の促進(田尻注:ここでは、「在留外国人の日本語能力の不足は、就労機会の制限、医療や行政サービスへのアクセス困難、地域社会での孤立など、様々な社会問題の原因となっている」と書かれていて、日本語能力の不足が社会問題の原因とされていますが、むしろ「社会問題の原因」は、日本語能力の不足している外国人労働者を受け入れてきた制度そのものに問題があると考えます。また、「在留資格に係る各種手続時における日本語能力の評価基準を明確化し、在留期間や就労内容に応じた段階的な日本語能力の習得を義務付けるべきである」とありますが、この問題は文部科学省・厚生労働省・法務省などでの調整が必要です。)
〇外国人労働者受入企業の責任明確化と罰則強化
〇外国人観光客に係る財源確保
日本維新の会の提言全体を通してみると、日本の人手不足の状況における外国人の貢献や訪日外国人増加に伴うプラスの面はあまり評価せずに、訪日・在留外国人に係る政治問題化された争点への対応が主になった提言だと考えられます。ここで問題となっている点については、対応を考える前提となる客観的なデータを押さえる必要があります。
また、ここに書かれている日本語教育に係る提言は、現在実施されている日本語教育施策への理解不足が見られます。その点については、日本語教育の側からの情報発信不足もあると田尻は考えています。外国人受け入れにあたっての日本語教育の重要性を関係機関・団体が、広く発信してきませんでした。そのため一般社会における日本語教育への理解不足が起こっているのです。
3. 知っておくべき外国人関係の資料について
参議院選挙の時の参政党の外国人政策の項目については、すでにICUの橋本直子さんやマスコミによる問題点が指摘されていますので、ここでは取り上げません。
ここでは、日本総合研究所が7月25日に公表したResearch Focusの「外国人労働者政策をめぐる内外の状況~欧米の経験と日本の課題~」(日本総研調査部の石川智久さんと後藤俊平さんの共著)を取り上げます。データは新しいものが示されていますし、問題点も的確に指摘されています。田尻のコメントも加えます。
https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchfocus/pdf/15991.pdf
主要国のデータは大変重要ですので、各自でプリントして持っておいてください。ここでは、日本の事例について扱います。「要旨」は、以下の2点です。
〇わが国でも、人手不足の深刻化に伴い、外国人材の活用が拡大。もっとも、増加している外国人労働者の多くは低~中スキル労働省が多く、高度外国人材の活用は他国に比べて限定的。近年では、留学生や技能実習生などの「育成」を通じた高度人材獲得の動きも。
〇外国人の定住傾向も強まるなかで、「生活者」としての外国人住民が直面する課題も顕在化。外国人のわが国社会への包摂を図るには、①方向性の不在、②司令塔の不在、③統計の不在、の「3つの不在」の解消が重要に。
「3つの不在」とは、以下のように説明しています。
〇方向性の不在・・・今後、日本社会が外国人とどのように共生していくのか。目指す将来像を国民的議論の中で明確化していく必要。移民政策を取らないという政府の立場と「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」や「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」との方向性の乖離が見られる。国の方向性が不明確ななか、地方自治体の取り組みが先行しているが、現状では地域格差がみられる状況で、居住地によって受ける行政サービスに格差。
〇司令塔の不在・・・外国人政策には担当省庁の緊密な連携が不可欠。省庁横断的に総合的かつ戦略的な政策立案を。現状、多文化共生に向けた取り組みは各省庁が行い、非常設の関係閣僚会議で連携を図る(田尻注:日本語教育は常設の「日本語教育推進会議」がある)。全体最適を目指すには省庁横断的な政策立案を担う司令塔が必要。今般、内閣官房に設置された部局の格上げ等も検討に値。内閣府の下に多文化共生庁を設置し、他省庁より一段高い位置づけで常設化。
〇統計の不在・・・現状、外国人関係の統計整備は諸外国に大きく見劣り。正確な実態把握、適切な政策検証に向けて統計整備を。統計は政策立案の基盤となる重要なインフラであり、実態把握に向けた統計の拡充が急務として、OECDレポートにおける移民・外国人関連統計の掲載状況を示している。統計整備に遅れがみられる一因として、諸外国の多くが出生地基準を採用する一方、わが国は国籍基準を採用。この結果、国際比較が困難になっているほか、国際児や帰化者など「外国に背景をもつ人口」の実態把握にも支障。
「3つの不在」はそのとおりですが、司令塔の名称と位置づけについては、田尻は別の考えを持っています。
まず、田尻は「多文化共生」という語を使いません。その理由はこれまで何度も言ってきましたが、簡単に言うと以下のようになります。
〇欧州評議会では複言語・複文化主義という語を使っていて、「多文化共生」という語を使いません。「多文化共生」の適当な訳語もありません。現在の日本では多くの日本人は日本語しか使いませんから、複言語状況になることは当面ありません。
〇最近の外国人排斥の動きをみると、日本人が日本文化や日本の生活習慣を重視しているのが分かります。このような状況では、日本に異文化や他国の生活習慣を持ち込むのを認めるとは思えません。現在の日本は、DEI(多様性・公平性・包摂性)に不寛容な社会です。
〇「多文化共生」は努力目標としては考えられますが、現実の施策としては実状に合っていません。
司令塔の名称として、これまで「外国人庁」や「移民庁」が挙がっていますが、「外国人庁」では国籍要件が目立って、親や親戚が外国籍である児童生徒等が支援の対象から外れる可能性がありますし、「移民庁」は政府が「移民」を認めていないので省庁名としては不適当です。
〇現在の状況を前提とするならば、「外国人包摂庁」はいかがでしょう。この場合でも「外国人」という語は残りますが、「包摂」で広くカバーしているのではないかと思っています。この名称も、田尻は最良とは思っていません。政府が外国人の受け入れの方針を明確にした段階で、名称も決まると考えています。
政府内での位置づけですが、かなり強い権限を持たせた省庁でなければなりませんので、内閣府の下部機関でうまく機能するかどうかが不安です。その時の総理大臣や担当大臣が外国人政策(田尻注:日本に外国人政策と呼べるものはないと考えています。あるのは、その都度出てきた問題に対処する対症療法的な外国人施策です)に理解があり、担当大臣に強い権限を与えなければ、機能しません。田尻は、司令塔が政府内のどこに位置づけられるかということよりも、その時の総理大臣がどれだけ外国人政策に問題意識を持っているかが重要だと考えています。いまのところ、この点についての私案はありません。
4. 新しく入管議連が設立
2025年6月20日に「国家の将来構想から出入国管理を考える議員連盟」(通称「入管議連」)が設立されました。
9月25日に総会が開かれました。会長は古川禎久議員、会長代行は藤田文武議員、古川元久議員、里見隆治議員、幹事長は寺田学議員、事務局長は宮崎政久議員です。寺田議員のオフィシャルサイトによると、6月の立ち上げには約50人の参加者があったそうです。9月26日の産経新聞では、25日に参加したのは15人と書いています。当日は、鈴木法務大臣の「外国人の受入れの基本的な在り方の検討のための論点整理」という講演が行われました。この講演資料は公開されていません。
当日は、法務大臣勉強会の資料を基にした出入国在留管理庁の「外国人の受入れの在り方の検討のための論点整理 ~活力ある強い日本の実現/国家の安全・安心の死守~」の説明がありました。
この議連は、出入国と在留管理の在り方を検討するものです。ここで問題にされるのは、外国人の日本語能力だけです。在留資格変更時にチェックされる日本語能力をどのように育成するかは当面検討課題になっていません。どのようにして日本語能力を伸ばすかという日本語教育は、ここでは重視されていません。
5. この時期に出された外国人施策各種
前回の「未草」の記事から9月30日までに出された外国人関係の施策や関連記事を時間軸に沿って列挙します。
〇8月29日
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課所管の「第3回 福祉人材確保専門委員会」が開かれました。この委員会では、会議福祉士養成施設を卒業後5年間は国家試験に合格しなくても介護福祉士の資格取得可能で、卒業後6年目以降介護等の業務に継続的に従事していれば引き続き資格取得が可能になるという経過措置が2026年まで設けられていますが、その経過措置を延長するかどうかを諮るものです。この経過措置は、外国人介護福祉士候補者に大きく関わっています。
介護福祉士は全国的に不足していますが、日本人のなり手が少なく、介護施設は外国人の割合が増えています。現在の介護人材の受け入れの仕組みは、EPA・在留資格「介護」・技能実習・特定技能1号の4種類の大きく分かれています。そのうち、全国の養成施設の入学者の半数は留学生です。2024年度の国家試験の養成ルートでの日本人の合格率は91.9%ですが、留学生は35.1%です。多くの留学生は、この経過措置で各地の介護施設で働いています。各地の介護施設は、この経過措置の延長を望んでいます。ただ、それでは介護福祉士の質の維持が難しいとして反対する人たちもいます。
この委員会がどのような結論を出すかを今後も注視していきます。
〇9月1日
第154回の文部科学省中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会が開かれました。この部会では、「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策に関する論点整理が行われました。この中では、「教員資格認定試験について、様々な専門性を持つ人が教師としての資質を身につけていけるような試験の在り方」を検討すべきとしています。田尻は、登録日本語教員がこの認定試験を受けて外国人児童生徒等の日本語教育に関われるようになれるか注視しています。
〇9月3日
国際交流基金が「2024年度 海外日本語教育機関調査結果概要」を公表しました。
https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/information.html
143の国・地域での日本語教育機関では、機関数・教師数・学習者数とも過去最高を記録しました。詳しい内容は、資料にあたってください。余裕がありませんので、田尻の興味のある点だけを扱います。
学習者数の多い順は、中国、インドネシア、韓国、オーストラリア、タイ、ベトナム、米国、台湾、ミャンマーなどの順になっています。
日本語教育を新規に実施した国は、コソボ、ジブチ、赤道ギニアで、再開した国は、マーシャル、バルバドス、オマーン、ウガンダ、エチオピア、ザンビアです。
確認できなかった国・地域は、キリバス、ベリーズ、サンマリノ、イエメン、コンゴ共和国、セーシェルです。
ここには挙がっていませんが、9月10日に日本政府がロシア国内で日本語教育などを行ってきた「日本センター」を閉鎖する方針を決めたことが分かりました。
「日本センター」は1994年に開設され、モスクワやサンクトペテルブルクなどに6か所あります。ロシア政府は、2024年1月にウクライナ侵攻に対する日本の対ロ制裁に反発し、日本センターに関する日ロ政府間の覚書の履行を停止しました。
龍谷大学で交換留学生として来日していたモスクワ大学の優秀な留学生たちが、今どうしているか心配しています。
〇9月4日
第106回の厚生労働省社会保障審議会年金数理部会が開かれました。
今回の部会の国立社会保障・人口問題研究所の林玲子さんの基調講演資料を紹介します。
https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001556530.pdf
この資料によると、現時点では外国人労働者が年金の受給条件を満たす前に帰国する者が多いと考えられ、年金制度を支える貢献度が大きいと考えられることや、将来外国人労働者が高齢化しても家族呼び寄せた出生行動等で日本の社会保障制度の支え手を生み出す原動力ともなる、と指摘しています。
〇9月5日
「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」が閣議決定を経て改訂されました。
大変大事な方針ですが、その内容はすでに扱っていますので、ここでは扱いません。各自確かめておいてください。
第12回の文部科学省教育課程部会 教育課程企画特別部会が開かれました。「資料1 論点整理(素案)」の45/46ページに「日本語指導が必要な児童生徒の教育課程に係る課題・方向性」が書かれています。細かなところで、国際教育課で扱っている内容と異なっている点があるのが気になります。
https://www.mext.go.jp/content/20250904-mxt-kyoiku-000043994_03.pdf
第13回の部会でも、同じ資料が出てきます。
〇9月17日
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課所管の第4回の「福祉人材確保専門委員会」が開かれました。
「資料2 介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験義務付けの経過措置について」の21ページの「介護福祉士養成施設の定員充足状況の推移」で、2025年入学者のうち、留学生が56.9%となり、初めて留学生が入学者の半数を超えたことが報告されました。
「資料3 准介護福祉士について」で、2023年以降准介護福祉士の規定を削除することがフィリピン政府との確認が行われたことが分かります。准介護福祉士が介護福祉士に比べて不当な扱いを受ける可能性があるとして、2011年以降フィリピンのEPA就学コースの送り出しを停止していることの確認です。以前、准介護福祉士という資格で受け入れをしていたことを知りました。
〇9月19日
第13回の文部科学省中等教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会教育課程企画特別部会の「資料1論点整理」の45ページに「日本語指導が必要な児童生徒の教育課程に係る課題・方向性」が、46ページに「柔軟な教育課程編成の促進(小・中学校の全体イメージ)が出ています。
https://www.mext.go.jp/content/20250919-mxt-kyoiku-000044946_03.pdf
〇9月24日
第7回の初等中等教育の「外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議が開かれました。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/196/siryo/1418919_00007.html
配布資料の中の「参考資料5 外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議における主な検討事項」は事務局がまとめた資料ですが、今後の会議の方向性を示したもので重要です。
〇9月26日
厚生労働省労働基準監督課が「外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業所に対して行った令和6年の監督指導、送検等の状況を公表しました」という資料が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63807.html
特定技能外国人の関係法令違反は、初めて公表されました。それによると、監督指導をした5,750の事業所のうち、4,395の事業所(76.4%)に法令違反があり、7件は送検されました。
特定技能制度でも、すでに多くの違反事例が報告されました。この制度自体に問題のあることが分かった数字と言えます。
〇9月29日
新聞各紙に出入国在留管理庁の有識者会議で、在留外国人の永住許可の取り消し規定の運用案が公表されたとあります。対象者は、91万8千人で影響は大です。
この有識者会議は、「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」のことだと思いますが、9月30日現在この有識者会議の情報は更新されていませんので、朝日新聞の記事を基に書きます。
税金や社会保障費を故意に払わない場合などの「悪質性」が取り消しの要件になるということですが、明確な基準のない規定は今後運用上の問題が生じる可能性があります。
6. 気になる出版物等
〇「激論!日本人ファーストを問う」(2025年10月、『文藝春秋』10月号)
参政党の安藤裕議員、関西国際大学の毛受敏弘さん、慶應義塾大学名誉教授の堀茂樹さんたちの討論で、日本語教育の重要性を強調している点はありがたいのですが、看過できない発言もあります。
堀さんの「必要なのは『多文化共生』ではなく『同化』だ」という発言です。この討論記事の冒頭にもこの箇所が引用されています。この討論の中で、この発言以降安藤さんと堀さんは「同化」を前提に論が進められていて、毛受さんのその点の修正意見も見られません。
言うまでもなく、「同化」という語はアジア・太平洋戦争で日本の植民地政策の中で「同化政策」として使われた語です。当時の日本語教師はその同化政策の一端を担ったとして非難されました。戦後の日本語教育は、その過去を反省して国際協力のための日本語教育に全力で取り組んできました。現在の日本語教育も、在留外国人の「同化」の手伝いをしてはいけないと考えています。
「日本人ファースト」が在留外国人の「同化」を進めるものならば、田尻は反対します。
〇「特集 『日本語教育の参照枠』のインパクト」(2025年9月、『日本語学』2025年秋号、明治書院)
もうすでに予定の分量をオーバーしているので、簡単にコメントします。
・松岡洋子さんの「『日本語教育の参照枠』とは何か」に、1990年に難民認定法が改定されたと書いていますが、これは間違いです。ちなみに、長山和夫さんと平山智之さんの論文には「1990年、改正入管法が施行」と正しく書かれています。同一の出版物の中に間違った記述と正しい記述があるのは編集上でも問題です。それにしても、田尻が何度もこの誤りを強調しても、日本語教育研究者の間では一向に改まる気配はありません。
また、松岡さんは「単純労働力」という語も使っていますが、これは好ましくないと考えられています。どのような労働でも「単純」なものはありません。外国人の労働問題を扱っている人は、「非熟練労働者」という語を使っています。
・一般の読者からすると、山本弘子さんの「Can-doモデル(留学分野)の構築」が、最も期待した論文だったと思います。現在、日本語教育機関は認定されるために、カリキュラムに「日本語教育の参照枠」をどのように反映させるか苦労しているからです。文法シラバスに慣れて、文型積み上げ方式で日本語能力を測る目安としていた人たちにとって、行動中心アプローチで「日本語教育の参照枠」を日本語能力評価の参考の枠組みとする現在の文部科学省の動きは、まさに「インパクト」を与えるものです。特に、「留学」分野で日本語教育機関の認定を受ける必要のある多くの日本語教育機関にとっては、Can-doモデルでシラバスをどのように構築するかは最も知りたい情報です。ただ、このような雑誌の性格上、認定される秘訣のようなものを書く訳にはいけなかったのだと思います。この論文は、参照枠の説明に留まっています。
残念ながら、『日本語学』の編集部が想定したような、日本語教育の世界での「インパクト」を扱った論文を書くことは難しかったのでしょう。
〇高谷幸「ひもとく 移民との共生」(2025年9月20日、朝日新聞)
マスコミでも、外国人政策が連日のように取り上げられている時期に、朝日新聞で「移民との共生」に係る本を紹介する記事で、移民問題の研究者である東京大学の高谷さんがどのような本を紹介するのか大いに期待したのですが、その期待は全く外れました。
移民問題を取り扱うのなら最新の資料に基づいて論じなければなりませんが、高谷さんが紹介した本は、いずれも現在の移民問題を考えるのには古いものばかりでした。『移民と日本社会』は2020年の、『日本で働く』は2021年の、『芝園団地に住んでいます』は2019年の出版物です。『移民都市』の出版は2024年ですが、原著は2015年のものです。
移民問題は、この数年で大きく状況が変化しています。ここで挙げられている著作よりも、もっと適切な著作が出版されています。朝日新聞のこの欄の担当記者は、このような点に気付かなかったのでしょうか。
※参議院選挙後、一気に外国人政策が政治問題化しました。すでに在留外国人への厳格な外国人施策が始まっています。このような動きに対して、日本語教育関係者の目立った動きがあるように田尻には見えません。
9月30日の日本経済新聞の篠崎瑠架記者の「外国人政策、総裁選の議論は規制強化に傾斜、成長への共生描け」には、「外国人への日本語教育への拡充や社会になじんでもらうためのレクチャーは地域のボランティアに頼っているのが実情だ」とあります。社会一般の意識はこのようなものだと考えられます。日本語教育関係者が興味を持っている在留資格「留学」や日本語教育学の研究は、内部の視点からしかものを見ていないのです。このような内向きの姿勢では、政府の会議に呼ばれることもなく、また実際に呼ばれても有効な施策を提言出来ていません。
今後、日本語教育を取り巻く状況は大きく変わる可能性が高いと思われます。日本語教育関係者は、いつまでその動きに背を向け続けるのでしょうか。