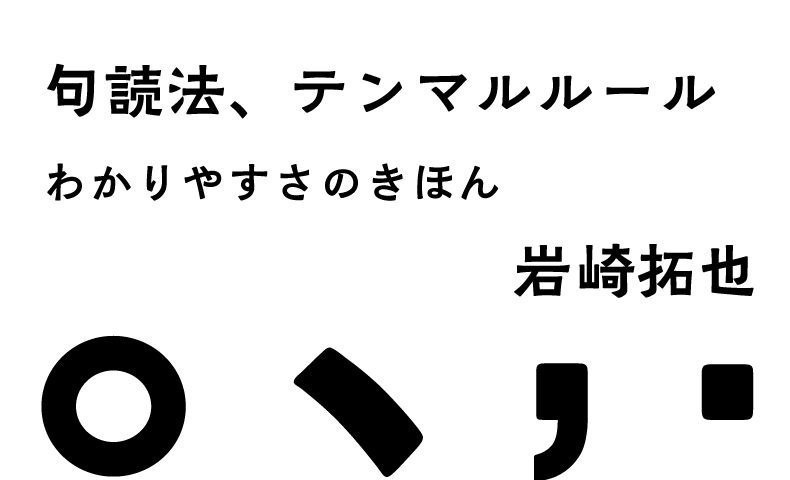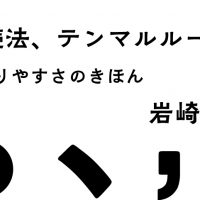この連載では、これまでに最初に現在までの句読点の規則、句読点成立の過程、読点の打ち方のコツ、そして、読点と句点を使うさいに迷うところについてまとめてきました。ここまでの連載を読まれたみなさんは句読点についてどう感じましたか。きっとこれまで以上に句読点の難しさ、複雑さを感じているのではないでしょうか。
このような句読点にたいする現状に日本語の研究者も黙っていたわけではありません。どのような傾向があるのかを見いだそうと、さまざまな角度から研究をがんばってきた歴史があるのです。今回はそんな「句読点の研究」にフォーカスをあてていきたいと思います。
とはいえ、句読点の研究を全て取りあげると、おそらくこの連載が終わってしまうほどの量になってしまいます。そこで、現在までに行われてきた句読点についての研究のなかでも私が独断と偏見で選んだ重要な論考を取りあげて、これまでの句読点の研究史を振り返ってみたいと思います。
日本初?の句読点研究
日本語における句読点についての研究書で最も古いものとされているのが、権田直助(1895)の『増補訂正 国文句読法』です(これは再版されたもので、正確には1888年に出版された『国文句読考』が最初です。ですが、句読点の研究者は『増補訂正 国文句読法』のほうをよく挙げます)。なお、連載の第二回で貝原益軒(かいばらえきけん)が1703年に『点例』、太宰春台(だざいしゅんだい)が1728年に『倭読要領』で示していると述べましたが、これらは漢文訓読に関する句読点の解説書です。
権田直助は、幕末から明治前期にかけて活躍した国学者・神道家・医者なのですが、彼は読点の難しさについて次のように書いています。
「讀ハ、(中略)文の屬きの長き所を、誦詠に便きほどに適へて、切るものなれば、一概にハ定め難し。」
(p.13)
このように、権田直助は読点の規則を定めることの難しさを指摘しつつ、句読点をもとに「句法」一つと「読法」五つを定めて、どのように打てばいいのかを竹取物語や古今和歌集仮名序などを例として取りあげ、実際に句読点をつけて解説をしています。
この『増補訂正 国文句読法』では、句法も読法もいずれもどのような語の後に打つとよいのかについて述べられていますが、それだけではなく、1文が短い場合は、これらの句読法は使用しないことが多いことも同時に指摘しています。
1950年代の句読点研究
つぎに1950年代の研究をまとめていきます。1950年代における句読点の研究は、ローマ字教育や句読点の指導について関連した研究がいくつか見られるのが特徴的なのではないかと思います。
たとえば、『象は鼻が長い』や、いわゆる「主語廃止論」で有名な三上章における句読点についての論考です。三上章(1954)「クエスチョンとコンマ」(『ことばの教育』16-7、p.31、日本ローマ字教育協議会(三上章(2011)『三上章論文集』くろしお出版に再録(pp.106-105)))では、倒置法における読点を問題としてあげています。たとえば、下の二つの例文のうち、一つ目は問題ないのですが、二つ目のように倒置で文が示された場合、従属節は形式上とイントネーション上は文末であるにもかかわらず、節末は読点で示されます(下線部分)。その一方で、主節末ではセンテンスが終わっていない形ですが、意味としては完全に終止形となっており、句点が打たれます(二重下線部分)。
・雨ガ降ッテモ,出カケヨウゼ.
(三上1954:106)
・出カケヨウゼ,雨ガ降ッテモ.
三上はこのような構文にも使用できる句読法が必要だと述べていて、試案としてセミコロン( ; )やエクスクラメーションマーク(!)とコンマ(,)を組み合わせた符号(!の下の点が ,になっている符号)を使うのはどうかと述べています。
また、別の論文(三上章(1956)「句読法私案」『IZUMI』18-27、いずみ会(三上章(2011)『三上章論文集』くろしお出版に再録(pp.175-143)))では、ローマ字化(romanization)と関連した句読法について考察を行っています。ですので、句点はマル(。)ではなく、ピリオド(.)を対象としています。そのうえで、どのようにすれば句読法が正しくわかりやすく実行されるかどうか、いくつかの私案を提示しています。具体的には、助詞「は」と「が」、接続詞「および」、引用節を示す「と」などの文法項目をもとに、句読点だけでなく、そのほかの記号の使い方についても考察を行っています。以下に、句読点の使い方をまとめたものを示します。
- テンは、文末としてのピリオドとして使う
- テンは、二単位以上からなる略字に使う
- テンは、小数点として使う
- テンは、番号を示すさいに用いてもよい
- コンマは、動詞や係助詞、接続助詞などで立ち止まる息継ぎのブレスに打つ
- コンマは、同種類の語句がただ並ぶときに使う
- コンマは、倒置によって終止の形が前方に繰り上がった直後には打たない
- コンマは、引用句の終わりが終止形であるときには打たない
- コンマは、格助詞や連体法といった直後に係り先がある語の直後には打たない
(筆者注:ここでの「テン」は「ピリオド( . )」を指しています。)
(1)は、マルと同じ用法ですが、(2) (3) (4)については、ピリオドの用法であることがわか ります。このことから、三上(1956)では、三上(1954)と同様に、倒置法における句点の打ち方のみを問題点としていることがわかると思います((7)は同じ倒置法のなかでも読点を問題としています)。また、三上は引用節を示す「と」の直前に読点を打つことはせず、引用節では引用符やイタリック体を使用して明示することを提案している点が斬新な点だと言えます。
八木橋雄次郎(1957)「作文指導と句とう法」(『ことばの教育』86、pp.9-12、日本ローマ字教育協議会)では、句読法指導の困難さは、日本には句読法が確立していないためであり、指導すべき教師自身にも句読法の体系も決まりも確立していないと指摘しています。そのうえで、句読法の指導は、文章を読みやすくし、誤読を防ぎ、表現の効果をあげ、自分の考えを間違いなくまとめるために必要ではあるものの、個性的な表現を無視してはいけないため、無理のない指導が必要だと述べています。
そのほかの句読法の指導については、内田武雄(1957)「句とう法の指導について−特に小学校1、2年においての−」(『ことばの教育』86、pp.17-19、日本ローマ字教育協議会)が小学1、2年生にたいする句読法の指導方法を、日吉透雲(1957)「句とう法の指導について−中学生のばあい−」(『ことばの教育』86、pp.20-22、日本ローマ字教育協議会)では、中学生にたいする句読法の指導の方法を提案しています。また、栃内和男(1957)「句とう法の指導はローマ字文でこそやれる」(『ことばの教育』86、pp.23-25、16、日本ローマ字教育協議会)では、句読法の指導はローマ字文によって初めて合理的に進められると指摘が存在します。
それ以外の違った角度から行われた句読点研究に近藤益雄(1957)「精薄児の作文と句とう点の指導」(『ことばの教育』86、pp.13-16、日本ローマ字教育協議会)があります。近藤(1957)では、知的障害を持つ児童における句読点指導の実例を報告しています。このような児童特有の句読点の誤用として、以下の六つをあげています。
- とにかくどこにでもでたらめに句読点をつけるもの
- あまりたくさん句読点を使いすぎるもの
- 「た」と「す」という文字の直後にはいつでも句点をつけるもの
- 句点と読点を取り違えるもの
- 読点ばかり打つもの
- 動詞の終止形と連体形との見分けがつかないために誤るもの
なお、(6)は、句読点をつける練習において現れる間違いで、自分で書く作文にはあまり現れないと報告しています。また、これらの誤用をなくすために実際の指導としては、次の12例を挙げています。
- 句読点を忠実にちゃんと呼吸を切って正しく読んできかせる
- 文章中の句読点を「テン」「マル」と発話して読みきかせる
- 一つの文を1句ずつ改行して示し、それを1文につなげさせて書き改めさせる
- 1句ずつチョークの色を変えて文を書き、それに句読点をつける
- 読み方に注意し、1句ごとに正確に区切って読み、それを書き写しながら句読点をつけさせる
- 句読点を逐一発話して、その通りに書き写させる
- 句読点なしの文を板書し、何度も音読してやって、みんなで句読点をつける
- 句読点無しの文を板書し、みんなで黙読して句読点をみんなでつける
- 筆談で指導する
- 2、3行ずつ書かせて持って来させて句読点のつけ方を教えていく
- 子供の作文の一部を板書して、グループで句読点のつけ方をしらべ、間違いがあったら、なおす
- 作文を自由に書かせ、あとで句読点の間違いをなおし、再度清書させる
知的障害を持つ児童は、文法的に文を読み取ることが困難なため、句読点の打ち方を学ぶことは難しいと近藤(1957)は述べており、このくらいの細かな指導を行わないといけないと指摘しています。
永野賢(1957)「句とう点のうち方」(『言語生活』66、pp.62-66、筑摩書房)では、上述した権田直助の『増補訂正 国文句読法』や文部大臣官房図書課(1906)『句読法案・分別書キ方案』などで示された基準に、私見を加えた形で句読法を整理しています。この永野(1957)の句読法研究は、以降の研究や教育現場においても参考にされていて、句読点研究史の観点から見ても重要なものだと言えるでしょう。永野(1957)における句読法の特徴をあげると、並列の読点は語句が二つ以上並ぶ場合で用い、短い語形の名詞などの並列には中点「・」を用いると明言している点が『句読法案』とは異なる点として挙げられます。また、接続詞の後は読点を打つと明言している点も『句読法案』と異なります。さらに、永野(1957)では、接続助詞後に読点を打つことも明言されています。具体的には「叙述に対する限定や条件などを表わす文や語句には、次のように打つ。(永野1957: 64)」とあり、これには「ので・ば・と・が・ても・て」などが含まれています。
1960年代の句読点研究
1960年代の句読点研究は、小説や雑誌、新聞の句読点についてまとめた研究が見られ始めたのが特徴的です。
土屋信一(1966)「雑誌「太陽」(明治28−昭和3)に見る表記の変遷」(『言語生活』182、pp.36-42、筑摩書房)では、雑誌「太陽」に見られる表記の変遷を分析して、その結果を以下の3点にまとめています。
- 文章の理解を増そうと努める傾向
- 表記の単純化の傾向
- 漢学的素養の衰退と欧文的表記の進出
(1)の文章の理解を増そうと努める傾向では、小見出しやサブタイトル、段落の一字下げ、句読点の付与、強調符号に頼らなくなる、カッコやかぎカッコを使うなどの傾向があることをまとめています。(2)の表記の単純化の傾向については、強調符号の単純化、外来語の表記の統一化、句読点の用法の分化などを挙げています。(3)の漢学的素養の衰退と欧文的表記の進出については、強調符号・外来語表記の整理、段落の一字下げ、句読点使用の普及、引用符号の一般化などがあることをまとめています。
なお、雑誌「太陽」における句読点の現れ方については、以下の四つにまとめています(例は土屋1966で挙げられている例です)。
- 句点と読点を用いるもの
漢字の躰たる、一言一語、各一符號をなし、其數の繁殖數萬に至る、學者の盡く之を記憶する、困難知るべし、是れ漢字の害尤を大する者なり。(三宅雪嶺・漢字の利害) - 読点のみのもの
畏こけれども、今上陛下ご誕生の地は、皇居の東北に在り、鐡欄を繞らし、御産屋存し、祐の井の碑は早や苔むしぬ、仙洞御所は日の御門より東北に在り、喬林欝蓊とし、御庭の風致妙なるは、拝觀したるものゝ皆忘れ得ざる所なり、(中川紫明楼・京都の新案内記) - 句点のみのもの
千八百十五年三月一日。ナポレオンは佛國の南部ジユアン灣頭カンヌに上陸せり。上陸せり。歸國せり。との風説さへも未だ聞き知らぬ者のあるに。はやナポレオンは佛都巴里の「チユイルリー」宮に在り。(戸川殘花・ヲートルロー合戦の記) - 読点と無表記のもの
(略)左様な人ゆゑ遣るとて金は添へるに及ばず、只取返さぬといふ一通あらば必ず貰ふて呉れるならん早く病人と談合あれと云れて長助はホロホロ涙、幾度となく禮を述る折から店の方にて御客様が下女の知らする聲に主人は急ぎ立去りたり(饗庭篁村・從軍人夫)
(4)は、(2)の変形で、一層読点を少なくしたものと考えるべきだと土屋は述べています。上記の四つのうち、(3)と(4)は、早くになくなったとありますが、(2)の読点のみの表現形式は長く続いたものの、徐々に句点も使われるようになり、(1)に移っていったと考察しています。また、(1)の句点と読点を用いる表現形式は、現在の表現形式とは若干異なっており、現在の句読法では句点で示されるべきところに読点が用いられていることが多かったこと(=「読点の守備範囲の広さ」)と報告しています。
岩淵悦太郎(1967)「新聞文章の変転の方向」(『新聞研究』195、pp.44-51、日本新聞協会)では新聞の文章の変化をまとめています。そのなかでは、戦後の新聞に起こった著しい変化として、句読点を使うになったことと、段落が立てられるようになったことをあげています。ただし、戦前においても、社説には句読点が打たれていることがあったと述べています。
武田孝(1969)「句読点は現状のままでよいか」(『文法』01-03、pp.110-115、明治書院)では、20名の作家が同じテーマで書いた作品の中の句読点数を計算して、分析しています。その結果、句読法が書き手にとっても読み手にとっても無関心であることが多く、無視されているという現状をまとめています。そして、句読法にかんする提案としては、句読点の機能の再認識と句読法の確立、望ましい協力の姿勢をあげています。「望ましい協力の姿勢」というのは、「世の人々に読まれる文章・作品の執筆者たちが、句読法について関心と理解を深め、できるだけ決められた基準を守ることによって、自己の思想や感情がまちがいなく読者に伝わるようにと、読点一つの打ち方にも最新の注意を払う努力をすること」(p.115)というように、書き手は読み手の立場になって句読点を使わなければならないという指摘です。
1970年代の句読点研究
1970年代の句読点研究は句読法の指導についてや、文学作品などで使用されている句読点の研究が多く見られます。
樺島忠夫(1970)「特集 悪文矯正の手帖 悪い文章からよい文章ヘ―効果的な句読法」(『国文学 解釈と教材の研究』15-2、pp.125-132、学灯社)では、句読点は意味的なまとまりをはっきりさせるために打つという立場に立ち、句読法は読みやすくわかりやすい文章にするための視覚的な工夫であると述べています。そのうえで、どこに句読点が打たれるのかを分析しています。樺島(1970)では、読点だけでなく、句点にたいする問題点も挙げているのが特徴的です。たとえば、以下の(1)のように、構文的に関係がある一つの文でも、その途中で句点が打たれ、見かけ上二つの文になってしまうものがあります。この問題について樺島(1970)では、「たとえば」のような誘導成分が頭にきた場合は、これを受ける成分までが構文論的には一つの文とはなっても、見かけ上は途中に句点を入れて二つ以上の文にしたほうが落ち着く場合があるとしています。ようするに、長い文は短くしたほうが読みやすいということでしょう。
- 私の推理に従えば、彼はたしかに朝大阪を出た。そしてその日の夜には東京で食事をしたということになるのだ。
さらに樺島(1970)では、機械にどのような規則を与えれば、上手く句読点を打てるようになるか分析を行っています。その結果を以下の四つの手順にまとめています。
- 3個またはそれ以上後の成分にかかるか並列するかの成分の後には読点を打つ
- 独立成分の後では読点を打つ
- 接続助詞を伴わないで次の成分と並列する成分の後では読点を打つ
- 文の終わりでは句点を打つ
なお、この基準だけでは、完璧ではなく、文末かどうかの判断させる手順を考える必要性やその他の規則も付け加える必要性があることを付記しています。
西池和己(1973)「句読法の一基準」(『作文教育』22,pp.39-44,全日本国語教育学会作文部会)では、国語教科書の編集にあたって必要な規準を作成しています。この論文において句読点は、論理的、心理的、生理的立場から規定され、表現の目的や相手意識からも制約されるものであるとし、一つの立場から句読法として体系づけることは困難であると述べています。
句読点を研究するときに避けて通れないのが、大類雅敏の一連の研究です。書籍や辞書、研究論文など数多くあるのですが、ここでは、大類雅敏(1974)「句読点の効果的な使い方」(『国文学 : 解釈と鑑賞』39-7、pp.292-325、至文堂)を取りあげます。
句読点の効果的な使い方を示すために、句読点の意義、歴史、種類、手順、方法、法則、上達と、多岐にわたり考察が行われています。そのなかで、句読点の意義・目的については、両義性の解消、理解困難の解消が主であるとし、句読法が個人の呼吸によって異なるとはいえ、同じ文型ならば、同じ位置に句読点を打つべきであると考えています。この句読点の用法の法則化につながるような考え方を位相の秩序と呼称してます。また、大類の一連の研究では、テンとマルだけではなく、そのほかの符号についても言及しているのが特徴的です。一般に用いられる句読点として「。」「、」「?」「!」「・」「−−−−」「……」およびかぎカッコと二重かぎカッコを認めています。
また、実際に書かれた文章からみた句読法を研究するさいには、精粗の比較だけでは不十分であり、文構造、語順、文の長短、文体印象、さらには呼吸との関係といった、厄介な問題が存在していることを指摘しています。
さらにこの大類(1974)の論文では、先行研究を踏まえた上で、独自の句読法を作成し、提案しています。
【句法】
- マルは一つの文の終わりに打つ
- 「 」や( )に囲まれる文の終わりに打つのを原則とする。引用文(文全体)の場合は必ず打つ
- 言い残しや余韻・余剰の「……」は、その直後にマルを打ってもよい。また、「。……」としてもよいが、改行しないと誤用と見あやまられる
- 「 」や( )で囲まれても、題名・標語・格言などの場合は用いない
- 箇条書きの場合は、文の形の場合でも、「……こと・もの・者・とき・場合」などで終わる項目の列記の場合などでもマルを打つ
- ただし、箇条書きの場合でも、次に示す時はマルを用いない
- 題目・標語など、簡単な語句を掲げる場合
- 物事の名称だけを列記する場合
- 言い切ったものを「 」を用いずに「と」で受けた場合
【読法】
- 文の中で語句の切れつづきを明らかにしないと、誤読や誤解を生ずる場合に用いる
- 対等(同格も)の関係で並ぶ同じ種類の語句の間に用いる。ただし、題目や標語や簡単な語句を並べる場合にはつけない
- 文の主題となる語(を含む文節)の直後に打つ
- 叙述にかんする限定・条件を表す文・語句の直後に打つ
1)限定・条件を表す前置きの文の後
2)挿入文になっている場合の前後
3)時・場合・場所・方法などを表す語句が文全体を限定するとき、その語句の後に打つ
4)接続詞の直後に打つ。文中の接続詞には、その前後に打つ
5)文頭の副詞の後に打ってもよい。文中の副詞には、その前後に打ってもよい接続詞と異なり、副詞は呼応を考えて打つ
6)感動詞や呼びかけの後の語に打つ
7)語句を隔てて修飾する場合、修飾する語句の後に打つが、ナカテン「・」を用いるとよい - 倒置の場合、主語(を含む文節)が文中にきたときはその前、述語が文中にきたときはその後に打つ
- 会話文などを「 」で囲んだ場合、「 」の前には打たなくてもよく、また、「 」を助詞とで受けて叙述のことばに続かない場合はその後に打ち、「 」を用いない場合には引用文や会話文に打つ
- 呼吸の切れめや間のところに打つ
- 仮名が、いくつも続く場合に、読みやすいように打つ
これらの句読法をもとにした明確な句読意識を規範とし、そのうえで工夫をこらすことで、句読点の効果的な使い方をすることができると大類(1974)では提言しています。
川上蓁(1974)「点の問題点―補助記号論―」(『言語生活』277、pp.20-33、筑摩書房)では、読点の打ち方として「息の切れ目」と「意味の切れ目」の2種類をあげ、それぞれの問題点について、分析と考察を行っています。
「息の切れ目」については、「息を切って新しく吸った場所」と「息は継がずに発音を休止した場所」が無分類であることを問題として取りあげ、現実の発音において生じた息の切れ目を示した読点を「写音的読点」、読み手を意識し、その文を読んでくれるに人はここで息を切ってくれることが望ましいということを示すために書き手が打った読点を「指定的読点」として分類しています。
意味の切れ目については、係り受けの関係からその距離の遠い箇所に読点を打つべきだとしながら、意味の切れ目の深さにおうじてテンだけでなく、コンマやコロン、セミコロンを使用したら便利なのではないかと提案しています。それ以外の方法としては、意味が深い(係り先が遠い)場所には全角の読点を打ち、意味が浅い(係り先が近い)場所には半角の読点を打つ、もしくは、半角の空白を挿入することで示すことを提案しています。
書きことばの文章のなかでも今までにない対象を研究しているのが、土屋信一(1974)「新聞広告の句読点―キャッチフレーズを中心に調べる―」(『言語生活』277、pp.61-67、筑摩書房)です。土屋(1974)では、新聞広告(特にキャッチフレーズ)に使用される句読点に焦点をあてて、その効果を記述しています。句点がキャッチフレーズに使用されはじめたのは、昭和46年(1971年)ごろであり、昭和49年(1974年)までにおいて句点がある広告が増えてきていると、調査の結果をまとめています。
キャッチフレーズにおける句点は、当初、名詞(句)の直後に使用されることが多かったものの、その後は、ですます口調で読み手に訴えかける感じを出すさいに、句点が使用されるケースが多くなってきたこと挙げています。なお、この句点については、キャッチフレーズを生の文として印象づける機能があると土屋(1974)では考えています。
なお、句点が使用されているキャッチフレーズにおいて、読点が打たれるところを改行で示しているものや一字あけの形式が多いと報告しています。
本多勝一(1976)『日本語の作文技術』(朝日新聞社) は、多くの人が読んだことがある一般書なのではないでしょうか。句読点の諸問題を一般に広めつつ、句読点にかんする二つの原則「長い修飾語が二つ以上あるとき、その境界にテンをうつ」、「語順が逆順の場合にはテンをうつ」を示したうえで、「筆者の思想としての自由なテン」を類別し、提示しています。この原則は明確でわかりやすいため、これまでの句読点の研究において一定の方向性を示すことに成功していると言えるのではないでしょうか。
まとめ
ここまでの研究史をまとめてみると、『くぎり符号の使い方』や「公用文作成の要領」をいった一応の規則をもとに独自の句読法を提案したり、国語(作文)教育においてどのように句読法を指導するべきかといった提案、新聞や小説、なかには広告といったさまざまなジャンルにおいて使用される句読点の使われ方を分析する研究が見られました。これは、やはりしっかりと句読法が確立していないなかで、どのような傾向があるのか、どう指導すればいいのかといった疑問に端を発しているように思われます。
すみません、やはり連載一回分だけでは、句読点の研究をまとめることができませんでした……。次回も句読点の研究史のお話です。1980年代、1990年代、2000年代以降の研究を取りあげます。
参考文献
- 岩淵悦太郎(1967)「新聞文章の変転の方向」『新聞研究』195、pp.44-51、日本新聞協会
- 内田武雄(1957)「句とう法の指導について−特に小学校1、2年においての−」『ことばの教育』86、pp.17-19、日本ローマ字教育協議会
- 大類雅敏(1974)「句読点の効果的な使い方」『国文学 : 解釈と鑑賞』39-7、pp.292-325、至文堂
- 樺島忠夫(1970)「特集 悪文矯正の手帖 悪い文章からよい文章ヘ―効果的な句読法」『国文学 解釈と教材の研究』15-2、pp.125-132、学灯社
- 川上蓁(1974)「点の問題点―補助記号論―」『言語生活』277、pp.20-33、筑摩書房
- 近藤益雄(1957)「精薄児の作文と句とう点の指導」『ことばの教育』86、pp.13-16、日本ローマ字教育協議会
- 権田直助(1895)の『増補訂正 国文句読法』(井上頼圀・逸見仲三郎 訂正)、近藤活版所
- 武田孝(1969)「句読点は現状のままでよいか」『文法』01-03、pp.110-115、明治書院
- 土屋信一(1966)「雑誌「太陽」(明治28−昭和3)に見る表記の変遷」『言語生活』182、pp.36-42、筑摩書房
- 土屋信一(1974)「新聞広告の句読点―キャッチフレーズを中心に調べる―」『言語生活』277、pp.61-67、筑摩書房
- 栃内和男(1957)「句とう法の指導はローマ字文でこそやれる」『ことばの教育』86、pp.23-25、16、日本ローマ字教育協議会
- 永野賢(1957)「句とう点のうち方」『言語生活』66、pp.62-66、筑摩書房
- 西池和己(1973)「句読法の一基準」『作文教育』22,pp.39-44,全日本国語教育学会作文部会
- 日吉透雲(1957)「句とう法の指導について−中学生のばあい−」『ことばの教育』86、pp.20-22、日本ローマ字教育協議会
- 本多勝一(1976)『日本語の作文技術』朝日新聞社
- 三上章(1954)「クエスチョンとコンマ」『ことばの教育』16-7、p.31、日本ローマ字教育協議会(三上章(2011)『三上章論文集』くろしお出版に再録(pp.106-105))
- 三上章(1956)「句読法私案」『IZUMI』18-27、いずみ会(三上章(2011)『三上章論文集』くろしお出版に再録(pp.175-143))
- 文部大臣官房図書課(1906)『句読法案・分別書キ方案』
- 八木橋雄次郎(1957)「作文指導と句とう法」『ことばの教育』86、pp.9-12、日本ローマ字教育協議会