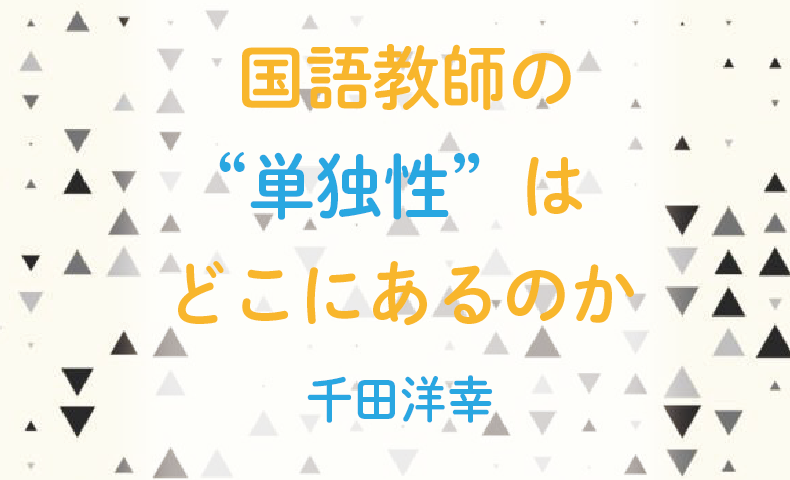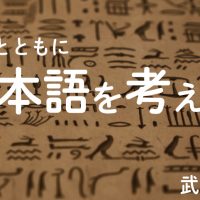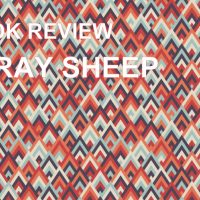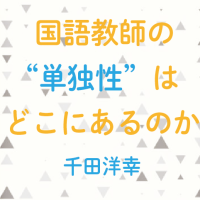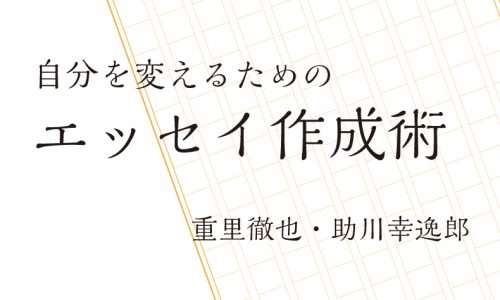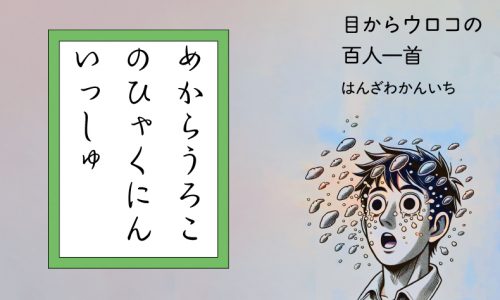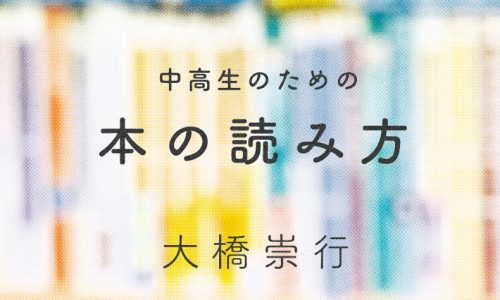みずからの教材論を授業実践とどう有機的にむすびつけるか、というテーマは教師にとって永遠の課題だろうが、教材論に文学研究や批評における成果をどう導入するか/しないか、ということも悩ましい問題であるにちがいない。コンピテンシーベース、スキルベースを信条とする教師、教材をあくまでも授業のねらいを達成するための材料、媒体、道具として位置づけようとする教師にとってはあまり意識の上にのぼらない問いであろうが、教材のポテンシャルを最大限に拡張したいと考える教師にとっては切実な問題となりうるのである。
たとえば私が「ごんぎつね」をたんなる一作品として読書する場合、「もともと他者への認識を欠いていたごんが、兵十を自分の同類と勝手に思い込み、彼から承認されたい欲望の塊と化した結果、みずからが他者の他者である現実(=人間にとっての異類・害獣であること)を見うしない、悲惨な結末を迎える物語」として読むことになるだろう。だが、この教材の対象学年である小学校4年生を想定した場合、当然、この解釈をそのまま教室に持ち込むわけにはいかない。だがそれでも、自分が編み出した解釈可能性を部分的にであれ生かすべく、教材研究と授業設計に腐心することになるだろう(実際、兵十にとってのごんの他者性に気づかせようとする実践はいくつも存在する)。結局、教材のポテンシャルを生かすも殺すも教師自身の教材解釈力と授業構想力しだい、というごく平凡な結論にいたるのである。
しかし数ある教材のなかには、研究史を踏まえた解釈と授業実践の折り合いをどう見いだすべきか、なかなか悩ましい小説や評論文も存在する。たとえば、学校という場でタブーとされやすい性の表現にそういう問題はしばしば顕在化する。定番中の定番教材である夏目漱石「こころ」、森鷗外「舞姫」などはその典型的な例だろう。
先生の宅は夫婦と下女だけであった。行くたびに大抵はひそりとしていた。高い笑い声などの聞こえる試しはまるでなかった。或る時は宅の中にいるものは先生と私だけのような気がした。
(上―八)
「子供でもあると好いんですがね」と奥さんは私の方を向いて云った。私は「そうですな」と答えた。然し私の心には何の同情も起らなかった。子供を持った事のないその時の私は、子供をただ蒼蠅いものの様に考えていた。
「一人貰って遣ろうか」と先生が云った。
「貰ッ子じゃ、ねえあなた」と奥さんは又私の方を向いた。
「子供は何時まで経ったって出来っこないよ」と先生が云った。
奥さんは黙っていた。「何故です」と私が代りに聞いた時先生は「天罰だからさ」と云って高く笑った。
結婚後の先生が性的な問題をかかえこんでいること(現在では性的不能という語は使わず、性機能障害とかSDなどと呼ぶべきなのだろう)を、かつてあからさまに指摘したのは橋本治であった(注1)。「私は妻と顔を合せているうちに、卒然Kに脅かされるのです」(下―五十二)と先生自身が遺書のなかで語っている通り、静と二人になった途端にKの死が脳裡に蘇るとあれば、そういう事態に陥ってしまうのも無理はないといえる。「こころ」の研究史をそれなりに踏まえている研究者や実践者のあいだでこのことは常識であり、皆あえて公言することはないものの、いわば暗黙の了解事項として扱われている(注2)。
この文章を読んでいる人のなかには、もしかすると「とんでもない解釈だ!」と腹を立てる純真な(?)読者も存在するのだろうか。そういう人は、「奥さんは黙っていた」という一文に着目するといい。この一文は、「子供は何時まで経ったって出来っこない」理由が静にも共有されており、同時にその具体的な内容は口に出せないことを示しているのだから、そこにどういう種類の困難が存在しているのかはあきらかだろう。あえて婉曲な記述がされているのは、書き手の漱石が検閲の網にかからないよう用心しているからで、そのことを差し引いて考えるなら、先生がかかえる性的な問題はほぼ明瞭に書き込まれているとさえいえるのだ(注3)。
ちなみに、上記引用部分は教科書に掲載されていない部分である。だから教科書本文を読解する授業では直接触れることなしに済ませることももちろん可能だが、たとえばつぎのような部分の解釈が変容をせまられることはありえないだろうか。
……私は今でもその光景を思い出すとぞっとします。いつも東枕で寝る私が、その晩に限って、偶然西枕に床を敷いたのも、何かの因縁かもしれません。私は枕元から吹き込む寒い風でふと目を覚ましたのです。見ると、いつも立て切ってあるKと私の室との仕切りの襖が、この間の晩と同じくらい開いています。けれどもこの間のように、Kの黒い姿はそこには立っていません。私は暗示を受けた人のように、床の上にひじを突いて起き上がりながら、きっとKの室をのぞきました。ランプが暗くともっているのです。それで床も敷いてあるのです。しかし掛ぶとんは跳ね返されたように裾のほうに重なり合っているのです。そうしてK自身は向こうむきに突っ伏しているのです。
(下―四十八 引用は大修館書店『文学国語』による)
私はおいと言って声を掛けました。しかし何の答えもありません。おいどうかしたのかと私はまたKを呼びました。それでもKの身体はちっとも動きません。私はすぐ起き上がって、敷居際まで行きました。そこから彼の室の様子を、暗いランプの光で見回してみました。
その時私の受けた第一の感じは、Kから突然恋の自白を聞かされた時のそれとほぼ同じでした。私の目は彼の室の中を一目見るやいなや、あたかもガラスで作った義眼のように、動く能力を失いました。私は棒立ちに立ちすくみました。それが疾風のごとく私を通過した後で、私はまたああしまったと思いました。もう取り返しがつかないという黒い光が、私の未来を貫いて、一瞬間に私の前に横たわる全生涯をものすごく照らしました。そうして私はがたがた震えだしたのです。
Kの自死について、荒井洋一は「なぜKは自室で、頸動脈を切るという、激烈な自殺の方法を選んだのであろうか。残された人々の受ける衝撃や迷惑も考えずに」とその不可解さを表明しているが(注4)、この場面を読んだ読者がいずれもいだく当然の疑問だろう。過剰な独立心にとらわれているKであれば、自裁という行為に及ぶときですら、他人に絶対に迷惑をかけない方法を選択するはずである。だが、Kは入水とか飛び降りとかの手段をえらぶことはなかった。荒井はKが「行為それ自体によって、「先生」を暗に告発している」と指摘するが、「暗に」どころではなく、Kはあきらかにみずからの自死そのものによって先生に暴力的なダイイングメッセージをつきつけたのである。それはいうまでもなく、「この無惨な死を生涯お前の記憶に焼きつけろ」という伝言――というより命令だ。
このメッセージを直接的に伝えるためには先生を第一発見者にすることが必須なので、「仕切りの襖」を開けておき、ランプをともし、頸動脈を斬って果てた自分の死に様を先生が真っ先に確認するようしむける。結果として先生は、「もう取り返しがつかないという黒い光が、私の未来を貫いて、一瞬間に私の前に横たわる全生涯をものすごく照らしました」という事態に立ちいたることになる。自死した者の肉体――しかも自分のほぼ唯一の友人――を目のあたりにしてしまった衝撃は生涯消えるものではない。Kの目論みはほぼ完全に遂行されたといっていい。
Kの自死については、これまでのさまざまな研究が語っている通り、たんにお嬢さんへの失恋にのみ理由を求めるべきではなく、K自身の実存にかかわる問題がむしろおおくを占めていたと考えなければならない。だが、そういう対自的な動機とともに、みずからの死が波及させる効果を隠微に予測した上での決断だったこと、すなわち先生の人生そのものに決定的なダメージをあたえる意図が存在していたことは明白だろう。Kはおそらく、「精神的に向上心のない者は、馬鹿だ」という言葉を逆用して彼の生涯の思想を否定し、失意の隙に乗じてお嬢さんとの結婚を申し込んだ先生に対し、その行動の根底をすべて見ぬいた上で、手きびしい裁きを下そうとしたのである。ただ、死を決意した時点でなにも持ちあわせていなかったKは、ただひとつ所有している自己の肉体を賭け金とするしかなかった。だがそれは功を奏し、先生の生涯に消えない刻印をのこすとともに、先生と静の性生活を破綻に追いやるという結果を招き寄せたのだ(注5)。
しばしば指摘される静と母親の「策略」の存在をも前提とするなら、先生の遺書において、先生、静と母親、Kがくり広げるどす黒い抗争が浮き彫りにされていることが理解できるだろう。ここには素朴な意味での「善人」などひとりも存在しない。恋愛する、結婚する、家庭を持続させる、他人の財産を手中にする……等々の欲望を達成するために、他者を利用し、陥れ、排除し、それがまた他者からの呪いと報復を呼び起こす。そういうきわめて現実的な個別の人間の葛藤を、あたかも近代人の苦悩を普遍化した“大きな物語”であるかのように語ろうとするのが先生の遺書の方略であった。「こころ」を解釈する際は、そういう出来事の層と語りの層の落差に注意しながら読み進めなければならないだろう。
さて、「こころ」の読みについて語ってきたが、ここまではたんなる前置きにすぎない。以上のような、性をめぐる視点を組み入れた解釈がかりに成り立ちうるとして、それを授業に導入することが果たして可能なのか、ということが本題である。
たとえば、「舞姫」の物語の根幹にも性をめぐる問題がある。
余はしばし茫然として立ちたりしが、ふとラムプの光に透かして戸を見れば、エルンスト・ワイゲルトと漆もて書き、下に仕立物師と注したり。これ過ぎぬといふ少女が父の名なるべし。内には言ひ争ふごとき声聞こえしが、また静になりて戸は再び開きぬ。さきの老媼は慇懃におのが無礼の振る舞ひせしをわびて、余を迎へ入れつ。戸の内は厨にて、右手の低き窓に、真白に洗ひたる麻布を懸けたり。左手には粗末に積み上げたる煉瓦の竃あり。正面の一室の戸は半ば開きたるが、内には白布をおほへる臥床あり。伏したるはなき人なるべし。竃の側なる戸を開きて余を導きつ。この所はいはゆるマンサルドの街に面したるひと間なれば、天井もなし。隅の屋根裏より窓に向かひて斜めに下がれる梁を、紙にて張りたる下の、立たば頭のつかふべき所に臥床あり。中央なる机には美しき氈を掛けて、上には書物一、二巻と写真帖とを並べ、陶瓶にはここに似合はしからぬ価高き花束を生けたり。そが傍らに少女は羞を帯びて立てり。
(引用は大修館書店『文学国語』による)
彼は優れて美なり。乳のごとき色の顔は灯火に映じて微紅を潮したり。手足のかぼそくたをやかなるは、貧家の女に似ず。老媼の室を出でし後にて、少女は少しなまりたる言葉にて言ふ。「許したまへ。君をここまで導きし心なさを。君は善き人なるべし。我をばよも憎みたまはじ。明日に迫るは父の葬り、たのみに思ひしシャウムベルヒ、君は彼を知らでやおはさん。彼はヴィクトリア座の座頭なり。彼が抱へとなりしより、はや二年なれば、事なく我らを助けんと思ひしに、人の憂ひにつけ込みて、身勝手なる言ひかけせんとは。我を救ひたまへ、君。金をば薄き給金をさきて返しまゐらせん。よしや我が身は食らはずとも。それもならずば母の言葉に。」彼は涙ぐみて身を震はせたり。その見上げたる目には、人に否とは言はせぬ媚態あり。この目の働きは知りてするにや、また自らは知らぬにや。
前田愛は、豊太郎が案内された部屋を飾り立てている「美しき氈」「書物一二巻と写真帖」「価高き花束」といった装いに、「エリスの貞操を要求するヴィクトリア座の支配人を迎え入れるために用意されたにわか作りの舞台装置」を見いだしている(注6)。要するにエリスは、座頭に体を任せなければならないベッドの前までわざわざ豊太郎を引きずっていき(しかも隣の部屋には父親の遺体が安置してある)、自分をこの悲惨な境遇から救い出してくれるよう全身で訴えたのだ。それ故、「鈍き心」の持ち主である豊太郎でさえ、「その見上げたる目には、人に否とは言はせぬ媚態あり」と、エリスの企みを感知せざるをえなかったのである。
現在、豊太郎を一途に愛する純粋な少女としてのみエリス像をとらえる解釈はほとんど存在しない。クロステル巷の古寺の門前で出会う場面から、豊太郎をつなぎとめ籠絡するため、エリスが身体的な技巧と演技を行使していることはあきらかに読み取れる。その技巧はおそらく、男たちの欲望の視線に日夜曝される踊り子としての仕事(注7)によって身につけられたスキルであろう。エリスにとって豊太郎との恋愛とは、みずからの生存を獲得するための抗争の場にほかならず、そこでは経験の蓄積によって手に入れた身体技法も駆使されるのだ。
友人の自死によって妻とのあいだに性的な断絶をきたしてしまった「こころ」の先生と、みずからが生きぬくために豊太郎との性的な融合を望んだ「舞姫」のエリス。おそらく、こうした性表象の層を視野に入れなければ、「こころ」「舞姫」を読んだことにはならない。性にかかわる思想がこの二つの小説の中核部分を構成している以上、そこから逃亡することは、骨抜きの読解行為に甘んじてしまう妥協を意味するのである。
高校生対象に授業をしている教師からすれば、そんなことを言われても無理に決まってる! というのが本音だろう。性にもっとも敏感な年代である高校生の前でそういうナイーブな話題をうかつに持ち出すことはできないし(どんな反応を示されるか恐ろしい)、また自分に妙なレッテルを貼られるのも御免こうむりたい(「性の話題が好きな先生」などと噂されたら後々まで尾を引きそう)。同僚や管理職に情報が漏れるかもしれないし保護者の目もうるさい。それに現代の高校生は多様な性的指向をもっているから、「こころ」「舞姫」のようなロマンティック・ラブ・イデオロギーど真ん中の時代の性の問題を持ち出すことにどれほどの意味があるのか。アロマンティック、アセクシュアル、ノンセクシュアルなどさまざまな自認がありうるなかで、「こころ」「舞姫」に表象されたジェンダー/セクシュアリティの規範はすでに前時代の遺物なのではないか……等々。卑近な理由から現代における多様な性的指向の問題にいたるまで、さまざまな壁が立ちはだかることだろう。
結局、学習者とのあいだで落とし所を探りつつ、より高い水準での授業を模索するというありきたりの回答しかひねり出せないのだが、もし私なら、上記の解釈そのままを持ちこむことは不可能であるにせよ、「これが教育の枠に収まらない近代文学の“危うさ”だ」ということをほんの片鱗でも伝えるべく、あれこれ策を練るだろう。また、性の問題を客体視できる成熟したリテラシーをそなえた学習者たちであれば、研究レベルの解釈を大胆に導入することを考えるだろう。とにかく、教材にポテンシャルを発揮させることは即座に授業の変革につながる、という認識をもつことが大事だと思う。研究史を十分に踏まえながら教材の解釈可能性を追求し、その成果を実践に生かすことは、うたがいなく授業者としての充実につながるのだ。
終わりに、もうひとつだけ教材例を掲げておこう。
レモン哀歌
(引用は東京書籍『新編 新しい国語3』による)
そんなにもあなたはレモンを待つてゐた
かなしく白くあかるい死の床で
わたしの手からとつた一つのレモンを
あなたのきれいな歯ががりりと嚙んだ
トパァズいろの香気が立つ
その数滴の天のものなるレモンの汁は
ぱつとあなたの意識を正常にした
あなたの青く澄んだ眼がかすかに笑ふ
わたしの手を握るあなたの力の健康さよ
あなたの咽喉に嵐はあるが
こういう命の瀬戸ぎはに
智恵子はもとの智恵子となり
生涯の愛を一瞬にかたむけた
それからひと時
昔山巓でしたやうな深呼吸を一つして
あなたの機関はそれなり止まつた
写真の前に挿した桜の花かげに
すずしく光るレモンを今日も置かう
◯……父の死とつづいてちゑ子の病状悪化とで殆と寧日なく今年も既になくならうといたして居ります、ちゑ子の狂気は日増しにわろく、最近は転地先にも居られず、再び自宅に引きとりて看病と療治とに尽してゐますが連日連夜の狂暴状態に徹夜つづき、さすがの小生もいささか困却いたして居ります、何とか方法を講ずる外ないやうに存じます。一片づきつき、尚それでも御詩集にまだ間に合ふやうでしたら書きますが、只今はそんな事で頭がめちやくちやになつてゐて何を書くか知れません故あぶなくてお送り出来ません、此点幾重にも御わび申上げます、此を書いてゐるうちにもちゑ子は治療の床の中で出たらめの嚀語を絶叫してゐる始末でございます、看護婦を一切寄せつけられぬ事とて一切小生が手当いたし居り殆と寸暇もなき有様です、御無沙汰の失礼平におゆるし下さい、
(上から1934年12月28日、1935年1月8日、1月22日、2月8日、3月12日書簡。いずれも中原綾子宛)
◯……一日に小生二三時間の睡眠でもう二週間ばかりやつてゐます、病人の狂操状態は六七時間立てつづけに独語や放吟をやり、声かれ息つまる程度にまで及びます、拙宅のドアは皆釘づけにしました、往来へ飛び出して近隣に迷惑をかける事二度。器物の破壊、食事の拒絶、小生や医師への罵言、薬は皆毒薬なりとてうけつけません、今僅かに諸岡存博士の発熱療法といふのにたよつてゐます、もう三回注射しました。注射すると熱が四十度近く出て、其で幾分でも恢復の途につくのだといふ事です、まだ効果は見えませんが四五回はやってみるつもりです、女性の訪問は病人の神経に極めて悪いやうなのであなたのお話をきく事が出来ません、手がミでお教へ下さるわけにはゆきませんか。今大急ぎでこれだけ。乱筆御免下さい。(中略)〈病人は発作が起ると、まるで憑きものがしたやうな、又神がかり状態のやうになつて、病人自身でも自由にならない動作がはじまります、手が動く首がうごくといつたやうな。〉〈病人の独語又は幻覚物との対話は大抵男性の言葉つきとなります、或時は田舎の人の言葉、或時は候文の口調、或時は英語、或時はメチヤクチヤ語、かかる時は小生を見て仇敵の如きふるまひをします、〉
◯……チヱ子は今日は又荒れてゐます、アトリエのまん中に屹立して独語と放吟の法悦状態に没入してゐます、さういふ時は食物も何もまったくうけつけません、私はただ静かに同席して書物などよんでゐます、仕事はまったく出来ません、
◯……此頃はちゑ子は興奮状態の日と鎮静状態の日とが交互に来てゐます、ひどく興奮して叫んだり怒つたりした日のあと急に又静かになり、大きに安心してゐると又急に荒れ始めるといふ状態です、よく観察してゐますと智恵子の勝気の性情がよほどわざはひしてゐるやうに思ひます、自己の勝気と能力との不均衡といふ事はよほど人を苦しめるものと思はれます、智恵子に平常かかる点で徹底した悟入を与へる事の出来なかつたのは小生の無力の致すところと存じます、
◯仕事といふ使命さへ無ければ一生をチヱ子の病気の為に捧げたい気がむらむらと起ります、チヱ子、チヱ子と家でくりかへし呼びます、チヱ子の病気はどうしても突発したものではなくて子供の時からの萌芽がだんだん延びて来て今日に及んだものと思ひます、病気の足跡が実に堂々としてゐます、この歩みをとどめ得るものはまづ無いでせう、もし治る事があつたら其は病気自身の自然治療による事と思ひます、もう一度平常にかへつたチヱ子を此世で見たいと切願します、実に純粋に私を愛してくれた、二十年前に私を精神的廃頽から救つてくれたあのチエ子にせめて一日でもいつものやうにして会ひたい願で今一ぱいです。
こちらはよく知られた取り合わせだろう。前者は周知の高村光太郎「レモン哀歌」(現行版では東京書籍『新編 新しい国語3』(中学3年)に掲載)、後者は吉本隆明によって取りあげられ(注8)注目されるようになった、智恵子の病状を伝える光太郎の書簡である。
はじめに「レモン哀歌」本文のみを読ませ、その後に資料として中原綾子宛書簡を提示した場合、学習者の内部にどのような揺れ動きを生み出せるだろうか。両者の落差について、光太郎による美化・虚構化の手法とその是非について、光太郎の献身ぶりについて、二人の恋愛の形について……などさまざまな感想がありうるだろう。(ちなみに大学の授業で上記二種のテキストを示した際、「レモン哀歌」に「看病や介護の責任から解放された作者の安堵感が読み取れる」という学生の感想があり、なるほどと思った記憶がある。)おそらく詩のみを単体で読ませるより、学習者たちの解釈のモチベーションは高まるのではないだろうか。
だがここでも、精神疾患(ここでは統合失調症)をかかえる人物のなまなましい資料を授業で取りあげることはできない、というクレームが聞こえてきそうである。そういう病をかかえている家族をもつ学習者を傷つける恐れがある、というのがこの場合の表向きの理由だろうか(注9)。以前、中学校教科書の編集業務の際、作中人物の両親が離婚する内容の小説を掲載候補作としてあげたところ(江國香織「メロン」だったと思う)、「クラスに離婚家庭の子どもが必ずいるから駄目だ」という理由で却下されたことがある。上記のような資料を持ち込もうとすると、同様の懸念が示される可能性は大いにある。
ならば、井上ひさし「握手」(中学3年教材)に登場する癌におかされたルロイ修道士の場合はそういう問題は発生しないのだろうか。結核で死にいたる妹へのレクイエムである宮沢賢治「永訣の朝」はどうか。担当クラスに自死した家族をもつ生徒が在籍している場合、「こころ」を扱うことはできないのか。――明確な線引きをすることはきわめてむずかしい。
こういう教室内のタブー意識について考えるとき、私は菅谷明子『メディア・リテラシー』で取りあげられているイギリスの小学校の事例を想い起こす(注10)。4年生のメディアの授業で、CMに登場する家族にジェンダーのステレオタイプが見いだされることが話題となった際、教師が「このクラスで両親が揃っていない子は?」と自然な流れのなかで質問し、半数近くの子どもが手を挙げる、という場面が紹介されていた。日本の小学校なら、「子どもとその家族に対する人権侵害ではないか」とか「子どものプライベートに踏み込むな」とかいったクレームがただちにやって来ることだろう。自己の経験や立場を授業の場でメタ的・論理的にとらえる成熟度において、日本の教室は、この二十数年前のイギリスの教室にとおく及んでいない。とくに義務教育段階である小学校・中学校の教科書において、さまざまな「忖度」を強いられる結果、毒にも薬にもならない微温的な教材ばかりがはびこってしまう要因でもあるのだ。
これは教室ごと、学習者ごと個別に解決しなければならない困難な問題ではあるのだろう。だが教師が教材開発や資料探索において、教室のタブーにすこしも触らないようその都度自粛し、教材が本来主張しうるポテンシャルを失わせるなら、その教材は事実上死んだも同然である。重要なのは、教師が教室の規範や約束事の方を向くのではなく、あくまでも教材の可能性の側にまず着目する、ということだ。学習者も教師自身も囚われている学校的・教室的な規範にぎりぎり抵触することにこそ国語教材の価値がある、という認識だけは手放さないようにしたいのである。
(注1)橋本治『蓮と刀――どうして男は“男”をこわがるのか?』(1982 作品社)。
(注2)たとえば石原千秋は、「結婚した〈先生〉はお嬢さん(静)と性交渉は一度もなかったと、私は考えている」とのべている(『教科書の中の夏目漱石』2023 大修館書店)。
(注3)引用した上巻八章に引き続く九章で先生と静の諍いのエピソードが挿入されている。「妻が私を誤解するのです。それを誤解だといって聞かせても承知しないのです。つい腹を立てたのです」「妻が考えているような人間なら、私だってこんなに苦しんでいやしない」という先生の言葉は、性的不和のあげく、静が先生の不貞を疑ってしまったことを示していると考えられる。
(注4)荒井洋一「夏目漱石の『こころ』における嫉妬の構造」(『東京学芸大学紀要 人文社会科学系II』61集 2010.1)。
(注5)近代文学6作品をアニメ化した「青い文学シリーズ」(2009年10月~12月 日本テレビ放映)中の一作『こゝろ 夏』(脚本:阿部美佳、監督:宮繁之。11月22日放映)のラストは、「私はKに負けたのです。お嬢さんと結ばれる一番幸せな瞬間にさえ、私の体からは血の匂いがしました。私は一生、Kの囚われの身となったのです」という先生の言葉で締めくくられている。同作では、静の母親が「ねえ、どうなってるの。けさKさんが娘を嫁に欲しいと言ってきたわ。勘弁してほしいのよね。娘が間違ってあんな甲斐性なしとできちゃったら、どうしてくれるんです」「あなたもしっかりしなさい。娘が好きなんでしょ」というセリフを語るなど、各キャラクターの性格と役割を露呈させようとする脚色の意図がうかがえる。
(注6)前田愛『都市空間のなかの文学』(1982 筑摩書房)。
(注7)この時代、小劇場につめかける男たちのおおくは踊り子を物色することを目的としており、大部分の踊り子たちも貧困層に所属していたため、売買春の取り引きは容易に成立した。豊太郎の手記にも「彼等(注・踊り子)の仲間にて、賤しき限りなる業に堕ちぬは稀なり」と書き込まれている通りである。渡辺善雄「「舞姫」と売春」(『鷗外』91号、2012.7)、鈴木晶『バレエの魔力』(2000 講談社現代新書)などを参照のこと。
(注8)吉本隆明『高村光太郎』(1957 飯塚書店。のち春秋社などから増補版を刊行)。
(注9)ちなみに東京書籍版教科書の教師用指導書は、中学3年生対象ということもあってか、智恵子の統合失調症についてはほとんど触れられていない。過去に「レモン哀歌」を採録していた高校教科書でも、筑摩書房版教科書の指導書で中原綾子宛書簡がごくわずかに紹介されている程度である。
(注10)菅谷明子『メディア・リテラシー――世界の現場から――』(2000 岩波新書)第1章を参照。