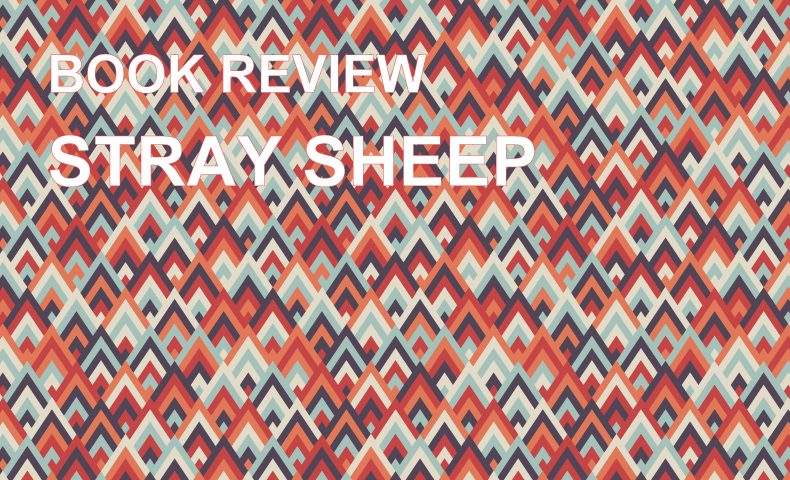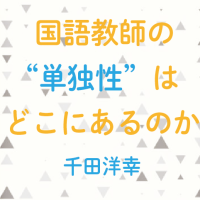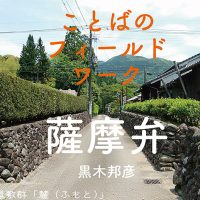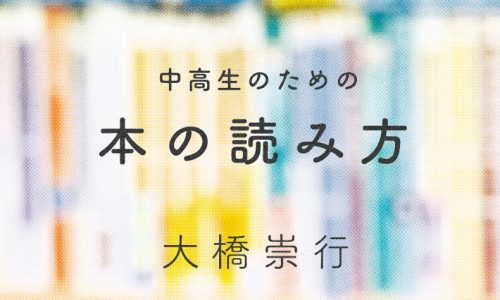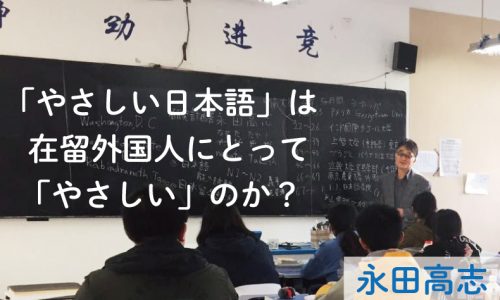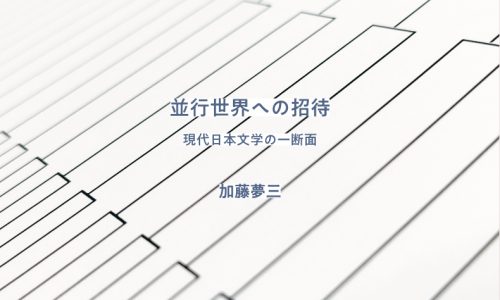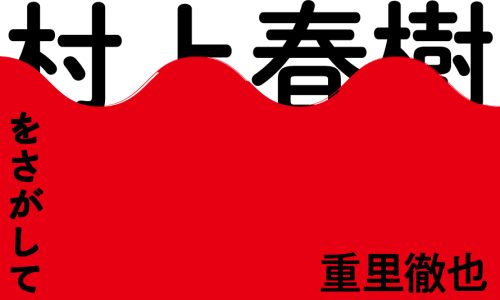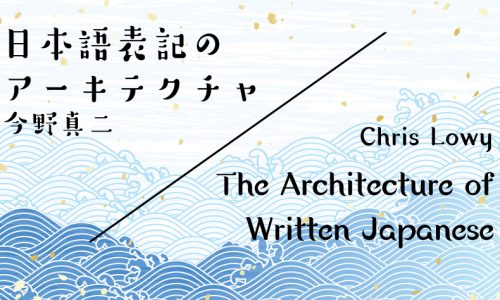佐渡島紗織(早稲田大学教授)
本書は、10人の実践者によるライティング領域での取組を島田康行氏と渡辺哲司氏が報告したものである。両者は2017年にも『ライティングの高大接続︱高校・大学で「書くこと」を教える人たちへ―』を同社から刊行するなど、一貫してライティング指導の在り方を追究してきた。
本書を貫く特徴は二つある。「書くこと」を教えるにあたり「生徒も教師も実践を振り返る」ことに重きを置いている点、そして「生徒と教師が人間同士としてかかわる」大切さを説いている点である。これら2点がくり返し、明示あるいは暗示されながら熱く伝わってくる一冊である。
生徒も教師も実践を振り返ることが重要
本書では、10人の優れた実践者がそれぞれに特徴的な指導を報告している。しかし単なる実践報告集ではない。一つの実践報告のあとに、編者がコメントしたり実践者と対談したりして、実践の振り返りをしているのである。つまり、指導そのものの報告に重ねて指導が意味づけられ、その価値を評価する場面がはさまれている。読者がこれらニつのレベルを行き来できる、非常に豊かな本である。
では、「書くこと」の実践で、振り返りの大切さはどのように語られているか。
澤田英輔氏は、中学校の実践で、「生徒は半年間の自分の作品や読書歴を全て振り返り、…読み手・書き手としての自分について『自己評価票』[A4で八枚程度]に記入する。」(p.18)という。そして、米国のWriting as a Process Movementにおける「カンファレンス(個別面談)」を取り入れた活動のなかで、教師が「自己評価票に沿って、その子の歩みや成長を一緒に」振り返る。これが「これから半年間のその子の読み手・書き手としての目標を一緒に設定する時間」となるという(p.19)。同時に、教師に求められる姿勢として、「作文指導の本を読むより前に、まずは、書き手としての自分を、丁寧に読みとくこと。それが、書くことを教える第一歩です。」(p.22)と言い切る。
渡邉久暢氏は、単元構想のなかで、高校生が「主体的に学習に向かう態度」を育成するには、生徒自身による自己評価が重要だとする。そのため、「提出した意見文を再度クラスメイト同士で回覧させるとともに…『ふりかえり』記述を促した。」(p.49)という。記述例には、苦労した点、クラスメイトの文章からの学び、新たな疑問などが率直に綴られている。
国際バカロレア認定校で教える杉本紀子氏は、「人が本当に『伝えたいこと』は、疑問や葛藤を経て獲得した『気付き』や『苦しみながらそれでも出した答え』からしか生まれないのではないだろうか。」(p.67)という。だからこそ氏は、単元学習の終盤で「学びの確認シート」で振り返りをさせ、「自己の理解の言語化」を促す(p.65)。記述からは、社会で異なる立場の人がそれぞれに苦しんでおり「不思議だ。」や加害者の中に被害者がいることを知って「驚いた。」などの学びが見られる。こうした、感情とともに語られる気付きが確かな知を生み出していることは明らかである。
本書の題にもある他教科の一つ中学校理科を教える羽田徳士氏は、「自由記入型実験シート」(以下、実験シート)を開発、使用してきた。「生徒が自ら実験をし、そこで得た生のデータを基に彼らが自分の考えを『実験シート』に書き、教員がそのシートを「『ルーブリック』を基に評価し」…コメントを添えて返却する」実践だ(p.106)。実験シートには、実験の中身だけでなく、そこから得た理解の深まりや疑問、新たな問いなどが記されており、生徒の思考が深まっている様子がわかる。この実践を始動したのは、羽田氏の先輩である高城英子氏で、高城氏は、中学校の全実験114テーマについて研究仲間とともにルーブリックを作成し、「ルーブリックを活用した実験シート」の実践を千葉県教育部会、千葉大学教育学部、学会へと広めた(pp.121–123)。氏の功績は、一校で始まった実践を振り返り、研究というスタンスで磨き、発展させたことにあるだろう。「実践の伝播」については、渡辺氏が詳細に解説している(pp.177–180)。
こうした実りある実践は、本書の教師たちが惜しげもなく時間を使って生徒に言葉を返すという営みに支えられている。文章評価にかかる手間は、「書くこと」の指導における永遠の課題である。そこをいかに効率よく切り抜けるかについては、大内康宏氏が具体的な提案をしている。そして「まずは、素早く理解できる文章を書かせ、読む時間を短縮し、書く回数を増やして、内容の指導を充実させるという順番が合理的である。」(p.74)と述べる。
生徒と教師が人間同士としてかかわる大切さ
本書を読んでいてたびたび感動させられたのは、教師の生徒を見るまなざしの温かさである。駒形一路氏は、「まず生徒の心が[教員に]開かれていなければならない。」(p.83)という。氏は、コロナ禍で受け持ったばかりの生徒に、「休校見舞い」の葉書を手書きで表書きして全員に出し「アナログな試みを再評価する必要」(p.84)を実感したという。コロナ禍後は、「HR日誌」を交代で自宅に持ち帰らせて書かせ、翌日、担任に提出させるという「日常の営み」を続ける。生徒は、出来事の記録を越えて様々な思いを綴り、生徒同士で思いを書き合うため、日誌帳はぼろぼろになるという。
高校の校長である宮原清氏は、「他者との関係を含めて自分自身の人生に意識を向けることができれば、自己指導能力(自分自身を教え導く力)は自然に高まる。」(p.171)を前提に、校長自ら生徒たちに一年前を振り返らせたり「なりたい自分」を考えさせたりする文章課題を出してコメントを返す。全生徒とスマホで交流するのである。ここから始め、「様々な社会課題や特定分野のテーマに結び付けた小論文の作成へと発展させ」(p.173)るのがよいとする。学校のリーダーとして校長自らが個別に生徒たちが自己を振り返る環境をつくり、それを教師たちに見せているのである。
農業高等学校で教える宮田晃宏氏は、「学力的に厳しい状況」(p.141)の生徒たちの、「体幹」に対応する「心幹(しんかん)」を鍛える。「人の生涯にわたって心の部分における根幹となるもの」(p.142)である。3年間で、列挙されるだけでも24種類もの文章作成(年ごとや月ごと)を課し、膨大な量の「書かせる指導」をする。その結果、「学習成績、出欠、行事、生徒会活動、各種競技大会、そして進路決定に多大な好影響を」、「卒業後の人生にまで好影響を及ぼし続けている」という(p.142)。とりわけ、生徒―教師の文通目的である「最近の出来事」では、教師が生徒を次のステップに誘導する励ましによって生徒が大きく変わっていったという(p.150)。氏の「あくまで生徒を理解し生徒と心を通わせるための手段である」(p.156)「書かせる指導」を継承した田中江利子氏は、それが「生徒の心に刺さるワケ」として「大人への信頼を持つ」、「自己肯定感や自己有用感の向上」、「学習意欲や主体性の向上」を挙げる(p.157)。また自作の「個人面談カード」では、「生徒が知恵と力をふり絞って書き出した部分にこそ、生徒自身が気付いていない長所や短所が表れることが多いと感じている。」(p.161)という。
これらの実践からは、教師が一人ひとりの生徒を、大切な個性をもった人として見守り、応援する想いがひしひしと伝わってくる。私たちが実践報告を読んで感動するのは、その実践が優れているときだが、とりわけ教師の、生徒への想いが指導にあふれているときであろう。
本書は、「書くこと」の指導には単純な正解が存在しないことを改めて思い出させてくれる。指導は難しく、工夫が求められる。しかし、だからこそ、教師の信念や工夫によって生徒の心を育てる豊かな土壌となり得るのであろう。そこで蒔かれた種からは、生徒との信頼関係が生まれ、生徒同士が尊重し合う姿勢が枝を伸ばし、生徒それぞれが自分や社会を見る目が育まれていく。「書くこと」の指導は、「よい文章」を書かせることが目標なのではなく、島田氏が述べるように、「よい書き手」を育てることが目標(p.54)である。
※編集部注
本記事は、『指導と評価』2025年4月号(刊行:図書文化)に掲載されたものを、図書文化様の御許可を得て転載したものです。転載に際して、体裁を変更しております。
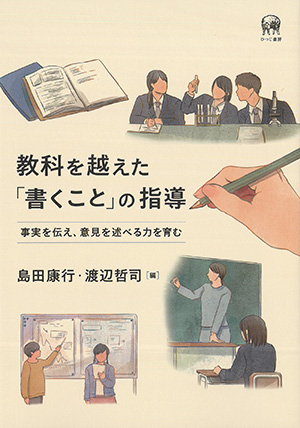
『教科を越えた「書くこと」の指導 事実を伝え、意見を述べる力を育む』
島田康行・渡辺哲司編
ひつじ書房
2024年刊行
ISBN978-4-8234-1238-7
定価2400円+税