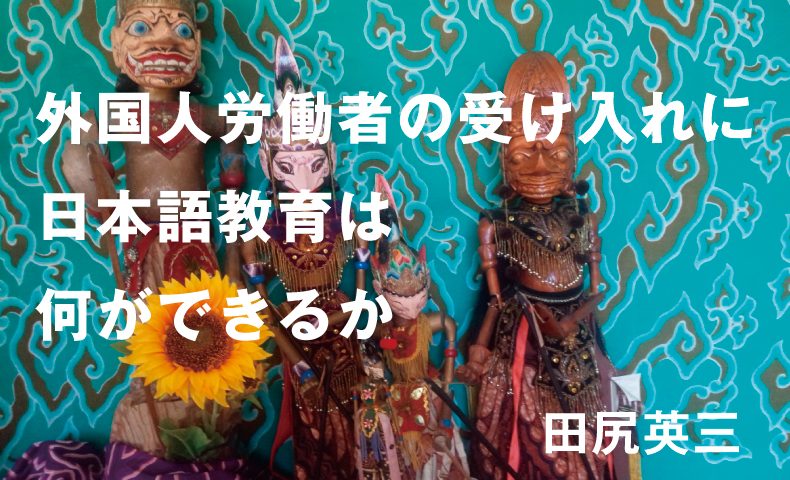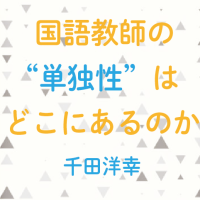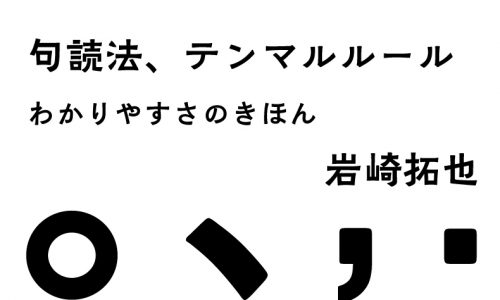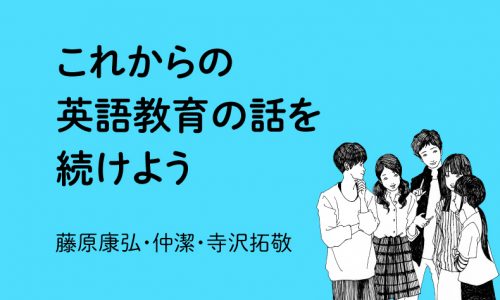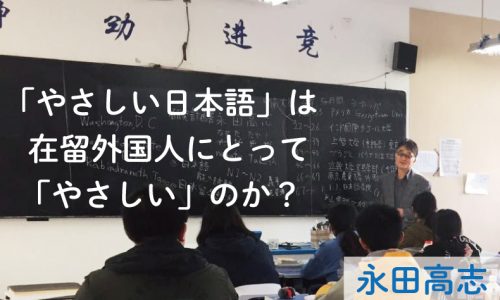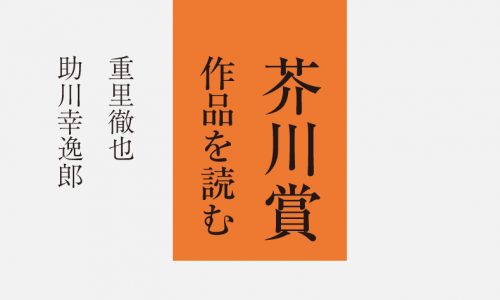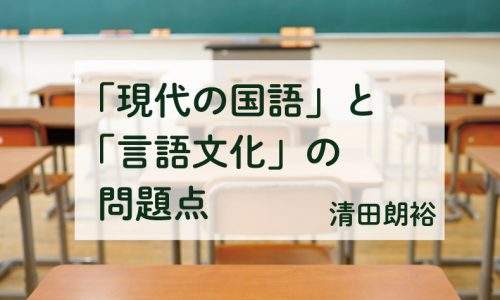★この記事は、2025年10月30日までの情報を基に書いています。
高市総理は、初めて内閣に外国人政策担当大臣を創設しました。これは、日本政府の外国人政策の大きな変更を意味します。今までは、「ステルス移民」と言われるように、人手不足対策としてなし崩し的に外国人を受け入れてきましたが、東京都議会議員選挙・参議院選挙を通じて外国人政策の問題点がクローズアップされました。
特に、参議院選挙で自由民主党・公明党が議席を減らし、立憲民主党は議席を増やさず、国民民主党のような右寄りの中道政党や保守色の強い参政党・日本保守党が議席を伸ばしました。このような流れに対し、自由民主党は保守層を取り戻すべく、高市早苗議員を自由民主党総裁に選びました。公明党は外国人との共生社会構築などの3点の政策協議が自由民主党と折り合わず、連立を解消しました。その後、自由民主党は日本維新の会と連立を組むことにしました。そのような経緯で成立した高市内閣は、保守色を強めただけでなく、外国人に厳しい対応を取る内閣を作りました。
今回は、このような流れの中で外国人政策の扱われ方を詳しく述べようと思います。日本語教育関係者はこのような動きに興味を持ちませんが、今後の外国人政策の方向によって日本語教育施策が影響を受けることは十分に予想されますので、きちんとこの流れを把握しておいてほしいと強く願っています。
以下では、外国人政策や日本語教育施策に関係する情報のみを取り上げます。田尻は政治ジャーナリストではないので、政府の政策全般は取り扱いません。
なお、高市内閣では「外国人政策」という語を使っていますが、田尻の考えでは、政府には外国人をどの程度受け入れ、入国後はどのように支援するかを考えた「外国人政策」は作られておらず、政府が作っているのは個別の状況に対処する「外国人施策」ですが、ここでは政府の考えに沿って説明します。
1. 高市内閣成立までの経緯
日本維新の会は自由民主党との連立合意のための12項目を提示しました。
その提言の9番目は、以下のような内容になっています。
9.人口政策・外国人政策
外国人比率上昇抑制及び外国人総量規制を含む人口戦略策定
外国人政策担当大臣設置並びに司令塔強化
対日外国投資委員会創設並びに外国人及び外国資本による土地取得規制の厳格化
この日本維新の会の提言は、自由民主党が厳しい外国人政策を取るようにさせることを意図していると田尻は考えます。
10月20日、自由民主党と日本維新の会との間で連立合意文書が交わされました。
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/information/211626.pdf
その中の外国人政策に関する箇所を抜き出します。この合意書が、今後の高市内閣の外国人政策の方向性に影響を与えると考えられます。
九.人口政策および外国人政策
▽わが国最大の問題は人口減少という認識に立ち、25年臨時国会中に、政府に人口減少対策本部(仮称)を立ち上げ、子ども子育て政策を含む抜本的かつ強力な人口減少対策を検討、実行する。
▽ルールや法律を守れない外国人に対しては厳しく対応することが、日本社会になじみ貢献している外国人にとっても重要という考えに基づき、以下の対策を講じる。
(1)内閣における司令塔を強化し、担当大臣を置く。
(2)外国人比率が高くなった場合の社会との摩擦の観点からの在留外国人に関する量的マネジメントを含め、外国人の受け入れに関する数値目標や基本方針を明記した「人口戦略」を26年度中に策定する。
(3)外国人に対する違法行為への対応と制度基盤を強化する。
(4)外国人に対する制度の誤用・濫用・悪用への対応を強化する。▽26年通常国会で、対日外国投資委員会(日本版CFIUS)の創設を目指す。また、26年度通常国会で、外国人および外国資本による土地取得規制を強化する法案を策定する。
2. 高市内閣成立後の動き
(1)高市総理の所信表明演説
https://www.kantei.go.jp/jp/104/statement/2025/1024shoshinhyomei.html
10月24日、国会での高市総理の所信表明演説での関係個所のみを示します。
9 地方と暮らしを守る
(人口政策・外国人問題)
日本の最大の問題は人口減少であるとの認識に立ち、子供・子育て政策を含む人口減少対策を検討していく体制を構築します。
人口減少に伴う人手不足の状況において、外国人材を必要とする分野があることは事実です。インバウンド観光も重要です。
しかし、一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じていることも、また事実です。
排外主義とは一線を画しますが、こうした行為には、政府として毅然と対応します。政府の指令塔機能を強化し、既存のルールの遵守を求めるとともに、土地取得等のルールの在り方についても検討を進めてまいります。そのため、新たに担当大臣を置きました。
総理大臣の国会での所信表明演説に外国人問題が取り上げられたことは、特筆すべきことです。今後、高市内閣では、このテーマが重要事項として取り上げられることが明らかにされました。
なお、高市総理は外国人観光客の増加に伴うマナー上の問題点は、次の「指示書」で触れています。
(2)高市総理の指示書
高市総理は、国会での所信表明演説の前日10月23日に、各閣僚に対して総理からの詳しい施策を記した指示書を示しました。従来は政策全般についての指示書であり、各省庁の政策は担当大臣の下で作成されるものなのですが、今回は各大臣宛に細かな指示が出されました。これは、極めて異例のことのようです。このことは、今回の高市内閣では行政が総理主導・官邸主導で進められようとしていることを示していると考えられます。
田尻は、この指示書を日本経済新聞のニュースサイトで入手しました。日本経済新聞の「X」からもリンクされています。一定期間を過ぎると見られなくなる可能性がありますが、URLを掲載します。
日本経済新聞のニュースサイト
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA230EU0T21C25A0000000/
日本経済新聞の「X」
https://x.com/nikkei/status/1981254645092897147
以下では、指示書の内容を「指示」として示し、その「指示」に関連した事項を大臣が記者会見で触れた場合に、その内容を「大臣」として示します。
【全閣僚共通指示】
指示・・・(2)地方を伸ばし、暮らしを守る
外国人問題に関する司令塔機能を強化し、総合的な対策を推進する。
【平口法相】
指示・・・(5)関係大臣と協力して、一定の専門性、技能を有する外国人材を円滑に受け入れるとともに、在留管理を徹底する。観光立国に相応しい入国管理の実現(田尻注:どういうことを指すのか不明。インバウンド外国人を今後も増やすという方向なのであろうか)を図るとともに、長期収容・送還忌避の課題解消及び難民に準じて庇護すべき者に対する適切な支援に取り組む。
大臣・・・記者会見では、高市総理から8項目が指示されたことに触れましたが、記者からの外国人政策についての質問については、従来からの政府の見解を述べただけでした。
【茂木外相】
指示・・・(4)外国人との秩序ある共生社会に向けて、査証に関する事務を適切に実施するとともに、国際人材の育成、在日外国人を含めた幅広い分野での人材交流を進める(田尻注:査証の発行は在外大使館・領事館で、在留資格に関わるものは法務省出入国在留管理庁が担当。ここではその違いがはっきりしていない)。
大臣・・・高市総理からの「指示」には触れませんでした。
【松本文部科学相】
指示・・・外国人政策・日本語教育についての言及はありません。
大臣・・・外国人政策・日本語教育についての言及はありません。
日本語教育についての「指示」もなく、文部科学大臣からの言及もなかったということです。
【上野厚生労働相】
指示・・・(5)関係大臣と協力して、高齢者・女性・障碍者・外国人の就労促進など、支え手(田尻注:どのような人たちを指すかは不明)を最大限増やす取組を進める。
大臣・・・外国人政策についての言及はありません。
【金子国交相】
指示・・・(3)関係大臣と協力して、観光業の振興を通じた地域の活性化を進めるとともに、持続可能な観光業を目指してオーバーツーリズム対策を推進する。
大臣・・・オーバーツーリズムについての言及はありません。
【黄川田地方創成相】
指示・・・(13)アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するため、関係大臣と協力して、総合的かつ効果的に施策を推進する。
大臣・・・アイヌの人々への施策についての言及はありません。
【小野田経済安全保障相】
指示・・・(9)関係大臣と協力して、国・地方児一体の情報連携や制度の適正利用、国土の適切な利用・管理など、外国人との秩序ある共生社会に向けた施策を総合的に推進する。そのために、必要な推進体制の強化を図る。
大臣・・・外国人施策についての記者からの質問に対しては、今後関係大臣と協力して進めるというに留めて、この時点での司令塔としての具体的な発言はありませんでした。ただ、ルールを守らない人たちへの厳格な対応や、外国人をめぐる情勢に十分に対応できていない制度の見直しを進め、国民が不安や不公平を感じる状況が生じているので、排外主義とは一線を画しつつ、こうした行為には政府として毅然と対応するとも述べていますので、今後は厳しい外国人施策が取られることが予想されます。
小野田大臣は、経済安全保障担当、外国人との秩序ある共生社会担当、内閣府特命(クールジャパン戦略、科学技術政策、宇宙経済、人工知能戦略、経済安全保障)担当の大臣でもあります。外国人政策だけを担当する大臣ではありません。
鈴木隼人外国人担当副大臣は、今までに、外国人受け入れは多くの課題が生じているので受け入れに関するグランドデザインを描く必要があるとか、経営管理ビザ・外免切り替え・外国人の土地取得の課題解決に取り組むべきとの発言をしていています。
外国人政策担当の小野田大臣と鈴木副大臣は、厳しい外国人施策を取る可能性があります。
なお、内閣総理大臣補佐官(外国人政策担当)の松島みどり議員は、日本語教育推進議連のメンバーです。
高市内閣では、外国人政策担当大臣が新たに作られて、外国人政策を正面から取り上げる姿勢は評価できますが、具体的には厳しい外国人施策が作られていくのではないかと田尻は予想しています。
3. 現在進められつつある外国人施策
〇「経営・管理」の許可基準に日本語能力が加えられた
2025年10月10日出入国在留管理庁公表、10月16日施行の「『経営・管理』の許可基準の改正案について」では、「申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります」として、「経営・管理」の在留資格を得るために日本語能力の要件が加えられました。
「注2」として、「相当程度の日本語能力とは、『日本語教育の参照枠』におけるB2相当の日本語能力を指し、日本人又は特別永住者の方を除き、以下のいずれかに該当することが必要になりました。
- 日本語能力試験N2以上
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
- 中長期在留者として20年以上我が国に在留
- わが国の大学等高等教育機関卒業
- わが国の義務教育を修了し高等学校を卒業
上記の要件が在留資格「経営・管理」の要件になり得るかどうかの判断は田尻にはできませんが、出入国在留管理庁でこのような基準がどのようにして決められたかが示されていないことが気になります。「相当程度」はあいまいな表現ですので、今後の運用に注目していこうと思っています。
〇永住許可取り消しの運用案が示された
出入国在留管理庁において、2025年9月29日に第7回の出入国在留管理政策懇談会が開かれました。その会議資料①は、「永住許可制度の適正化について」となっています。
適正化のガイドラインは、次のようです。
- ガイドライン策定の趣旨・目的及び位置づけ(法的性質)について
- ガイドラインに盛り込むべき事項について(故意に公租公課の支払いをしないこと、入管法上の義務違反・特定の刑罰法令違反)
- 「故意に公租公課の支払いをしない」の考え方
- 通報の判断の考え方(「通報相当」と考えられる事例/「通報不要」と考えられる事例)
- 職権変更/取り消し(在留不可に係る判断の考え方(公租公課)
- スケジュールについて(令和9年4月運用開始)
すでに運用開始時期が決定している永住者取り消しは、運用次第では918,116人(在留外国人の24.4%)の永住者にとって死活の問題となります。
会議資料②は、「高度外国人材の受入れについて」です。
この会議資料によると、在留資格「永住者」を有する者で、永住許可申請時点で「高度専門職」であった者は2,706人、高度外国人材等に帯同する親であることで在留資格「特定活動」で在留する者は3,575人、高度外国人材に「家事使用人」として雇用されることで在留資格「特定活動」で在留する者は634人と報告されています。
〇不法在留外国人の強制送還が前年比で倍増
出入国在留管理庁のまとめで、「不法滞在者ゼロプラン」で2025年6~8月に護送官付きで強制送還された外国人は119人で、前年の58人から倍増したことが分かりました。内訳は、トルコ34人、スリランカ17人、フィリピン14人、中国10人、ベトナム6人でした。
強制送還の増加は人権問題に抵触すると述べた意見も出されています。
〇高校授業料無償化で外国人学校は除外される案を検討
10月29日、自由民主党・公明党・日本維新の会の3党は、高校授業料を巡り月内の実務者協議で高校授業料無償化の制度設計について合意しました。
この制度案では、日本の高校に相当する外国人学校や留学生は除外されました。30日の朝日新聞によれば、自由民主党の柴山昌彦議員は「まず自国民を優先する必要がある」と説明したと書かれています。柴山議員は、日本語教育推進議連の会長です。
田尻は、教育における外国人排斥の方針には反対です。
4. 大事な資料
〇2024年度 外国人の子どもの就学状況調査の結果
10月2日の文部科学省報道発表で、2024年度の外国人の子どもの就学状況調査の結果が公表されました。この調査対象は、市町村教育委員会です。
概要は、以下のとおりです。
- 学齢相当の外国人の子どもの人数(住民基本台帳上の人数)は163,358人で、前回調査より12,663人増加で、8.4%の増加となります。
- 不就学の可能性のある外国人の子どもの数は、8.432人です。
不就学の外国人の子どもへの対応が必要です。
〇出入国在留管理庁の関連資料
以下は、いずれも10月10日公表の資料です。
・2025年上半期における外国人入国者数(新規入国者数と再入国者数の合計)は、2,137万6,170人で、前年同期に比べて355万5,541人の増加です。その内、新規入国者数は、1,972万8,405人で前年比331万4,380人の増加です。
- 2025年6月末現在における在留外国人は、396万6,619人で、前年比18万7,642人、5.0%の増加です。国籍・地域別では、中国、ベトナム、韓国、フィリピン、ネパール、インドネシア、ブラジル、ミャンマーなどの順です。
在留資格別では、永住者932,090人(+13,974人)、技術・人文知識・国際業務458,109人(+39,403人)、技能実習449,432人(-7,163人)、留学435,203人(+33.069人)、特定技能336,196人(+51,730人)です。 - 2025年7月1日現在の不法残留者数は、7万1,229人で、2025年1月1日に比べ3,634人(4.9%)の減です。
在留資格「特定技能」での人数が大幅に増えていることに注目してください。
- 第8回「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」が、10月6日に開かれました。ここでは、育成就労制度における本人意向による転籍の制限案が検討されました。転籍に当たっては、日本語教育の参照枠A1からA2の間の日本語レベルはどのように確認するのかが問題になりました。
日本語能力については、日本語教育の専門家にヒアリングをしてほしいと思っています。
〇介護福祉士養成施設入学の留学生が初めて全入学者の半数を超えた
日本介護福祉士養成施設協会が10月14日に発表した2025年度の入学者7,356人のうち、留学生が4,074人となり、初めて留学生の入学者が全入学者数の55.3%になりました。なお、養成施設全体の入学定員は11,001人なので、定員充足率は66.9%となり極めて厳しい状態です。
留学生の内訳は、ネパール1,899人、ミャンマー717人、ベトナム490人、中国239人、フィリピンン192人、インドネシア170人、スリランカ127人などです。
2025年3月卒業生のうち、留学生の卒業生は1,707人、国家試験受験者1,648人で、国家試験合格者は822人で合格率は49.9%です。ちなみに、全卒業生の国家試験合格率は80.7%です。
介護福祉士養成施設自体の存続が問題となっています。国家試験合格の留学生も少なく、それに対応するための猶予措置も問題化しています。
〇大学院の入学者数がほとんどの分野で大幅に減
留学生とは直接関係ありませんが、田尻にとっては大変興味深い数字が公表されました。
9月30日の文部科学省大学院部会で、各分野における大学院教育の現状の資料が公開されました。
日本語教育などの「人文科学」の分野では、2003年に1,648人いた入学者が、2024年では930人となり44%の減です。このままでは、日本語教育や日本語学の研究者が育っていかなくて、当該学会の存立も厳しくなります。各学会の執行部の方々は、この問題をどう捉えているのでしょうか。
ちなみに、社会科学分野は47%、理学分野は30%、工学分野は18%の減です。
5. 読んでほしい論文等
〇『世界』(岩波書店) 2025年11月号の「特集1あなたと移民」の掲載論文はどれも読んでほしい論文です
以下は、特にお薦めする論文です。
- 小井土彰浩さんの「移民政策の『失われた三〇年』を超えて」は、移民政策の流れを簡潔に述べていますので。必読の文献です。
- 望月優大さんの「トランプさんに足並みを揃えて」は、現在の政治状況の説明をしています。
- 特集ではありませんが、中村一成さんの「外国籍教員 教育現場に残存する『差別の壁』」も、ぜひ知ってほしい内容です。日本国籍を持たない韓国や中国の人は、公務員試験の採用上の不利益や教員に採用されても主任になれないなどの差別を現在も受けていることを知ってほしいと思います。
〇月刊「公明」 2025年11月号の「特集 多文化共生への道」の掲載論文
特に、是川夕さんと公明党参議院議員の石川博崇さんの「〈対談〉 外国人政策で大事なのはエビデンスと現場の声」をお薦めします。
人口問題が専門の是川さんが国会議員と外国人政策の問題点を討論しています。
〇是川夕『ニッポンの移民―増え続ける外国人とどう向き合うか』(2025年10月ちくま新書)
移民政策の流れや現在の問題点を、具体例を挙げながら説明している本です。
日本語教育関係者は、必ず買って読んでください。ただ、この本には、国内の日本語教育については触れていません。
現在の日本語教育施策については、田尻編の『外国人受け入れへの日本語教育の新しい取り組み』(ひつじ書房刊)を見てください。この本は、2025年3月時点の最新のデータが示されています。
6. 日本語教育関係者に今すぐ読んでほしいサイト
認定日本語教育機関や登録日本語教育機関(日本語教員試験を含む)について、文部科学省が実務説明会の資料を最近公開しました。
いまだに「日本語教育の参照枠」が分からずに悩んでいる人は、必ず見て勉強してください。
〇「認定日本語教育機関の認定申請に係る実務説明会動画及び資料」はすでに公開
https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_03308.html
2025年8月19日・28日に実施した動画と資料を見ることができます。
「第一部 申請手続きに関する説明」には、認定日本語教育機関についての説明が分かりやすく書かれています。特に、「令和6年度1回目(初回)の認定審査後の部会長所見」を読めば、日本語教育機関の認定審査のための準備不足がよく分かります。
「第二部 日本語教育課程に関する説明」には、「日本語教育の参照枠」の説明が書かれており、そこには「期待される効果」も書かれています。
そもそも、「日本語教育の参照枠」を使うことは2020年6月23日の閣議決定に書き込まれているのですから、今ごろになっても「日本語教育の参照枠」が分からないという態度は、日本語教育関係者にとってはありえないということを知るべきです。
第二部には、「日本語教育の参照枠」の評価の考え方や、「認定日本語教育機関日本語教育課程編成のための指針」を踏まえたコースデザインのポイントまで書かれています。
第一部は事務担当者向け、第二部は主任教員向け」と書かれていますが、日本語教育関係者なら全部を読んで理解しておく必要があります。現場で教える日本語教員がこの仕組みを知っていなければ、授業ができるはずがありません。
〇「登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関の登録申請に係る実務説明会」の資料は今後公開
2025年10月22日に開かれた実務説明会では、登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の登録申請の仕方だけではなく、「日本語教育の参照枠」の基礎知識・教育デザイン・登録申請のポイントまで示されており、登録申請に十分な情報が書かれています。
文部科学省がここまで詳しく丁寧な資料を出すのは、認定申請や登録申請を早くしてほしいからです。特に、日本語教育機関の中には、ぎりぎりの申請をすれば多量の審査が難しくなり、もしかすると審査が甘くなると考えている機関があるように聞いています。それは後ろ向きの考え方です。まず必要なことは、しっかり申請書類を準備し、審査を受けて、必要な場合は書類を取り下げて再審査の準備をした上で、認定されることです。
※高市政権が生まれたことにより、国の外国人政策が動き出します。まだ現時点ではどのような施策が作られるかは不明ですが、十分に注意しておくべきです。
日本語教育学会の2025年度秋季大会の一般公開プログラムのテーマは、「共生社会と日本語教育―何のために日本語教育はあるべきかー」は、なんともおっとりとしたテーマであると田尻には感じられます。このシンポジウムは11月22日に開かれるので、評価は次の『未草』の記事に書きます。ただ、残念ながらこのシンポジウムは対面の公開のみで、オンラインでの視聴はできません。富山まで行ってシンポジウムに参加できるのは、東京などでの開催に比べれば少ない人数であると予想されます。田尻も参加できません。大会委員会がこのようなテーマが大事だと考えるならば、オンライン参加も可とすることを検討してほしかったと思います。
今回も、書きたいことがもっとありましたが、すでにいつもの分量に達していて省略せざるをえませんでした。
2025年10月に、日本政府の外国人政策が転換したことを記憶に留めてください。