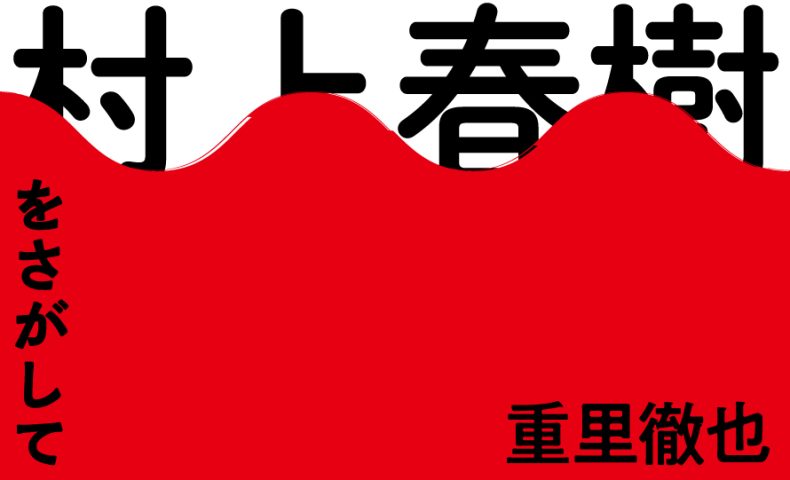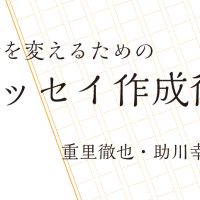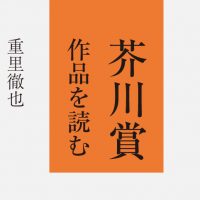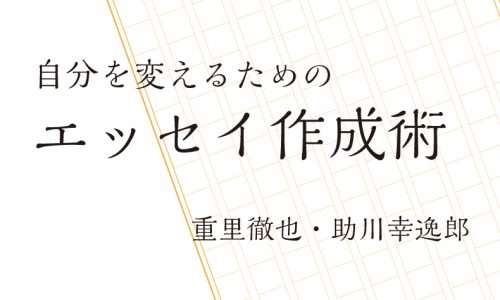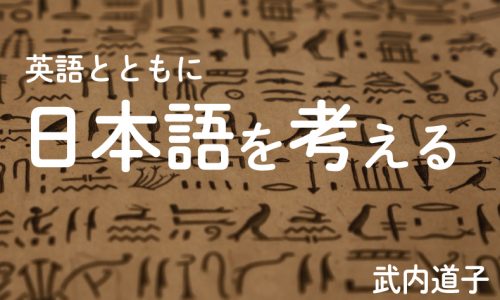村上春樹の文学の原点とは何なのか。いくつか、思い浮かぶ。早稲田大学在学中の大学紛争の経験。父親が体験した中国での戦争。女性たちとの経緯。世界中の文学と映画。ジャズからクラシックまでの幅広い音楽。
ただ、原点の一つとして、十代までの日々を過ごした神戸市や芦屋市という土地も見逃せないだろう。村上の初期作品について、「無国籍」とか、「どこにでもあるような都市」とか、「土のにおいを感じさせない場所」とか評されることがある。でも、そうなのだろうか。
彼が当初、描いたのは、まぎれもなく、日本の固有の土地ではなかったのだろうか。「無国籍」の皮を一枚はぐと、ある時期の兵庫県南東部の風土が浮かび上がってくるのではないだろうか。
そんなことを考えたのは、映画「風の歌を聴け」をほんとうに久々に観たからだ。公開時に映画館で楽しんで以来だ。公開されたのは一九八一年なので、私は大学生だ。大阪のどこの映画館で観たのかも、記憶が薄れている。ただ、あちこちの断片が妙に印象に残る映画だった。以来、観る機会はなかったが、好感を持っていた。
ATG(アート・シアター・ギルド)映画。監督の大森一樹は、芦屋市立小学校の村上の後輩になる。この時期、私はATG映画をかなり観ていた。大森監督作品は「ヒポクラテスたち」に続いてのものだったか。
原作はいうまでもなく、村上春樹の同名のデビュー作(一九七九年)。一九七〇年夏の八月八日から八月二十六日までの日々が描かれている。東京の大学生の主人公が「海辺の街」に帰省して、友人の鼠(と呼ばれる同世代の男性)と遊んだり、女の子と親しくなったりするストーリーだ。
四十数年ぶりに映画「風の歌を聴け」を観て、ああこういう映画だったのだなと感慨を新たにした。そして、映像は逆に、村上作品の成り立ちを照らし出すもののように思えた。大森監督の村上作品の解釈が前面に出ているといえばいいか。村上の小説が彼の育った土地と濃厚にかかわっていることを物語っているように感じた。
映画のストーリーは原作をかなり踏襲している。やはり、舞台は一九七〇年。主人公の「僕」(小林薫)は東京の大学生。夏休みで故郷に帰ってくる。なじみのあるジェイズ・バーに入ると、友人の鼠(巻上公一)が待っていた。鼠の父親は大金持ちで、鼠は大学を中退している。
二人の夏の日々が描かれる。「僕」は左手の小指を失った女性(真行寺君枝)と出会い、親密になる。父親を憎む鼠は風変わりな8ミリ映画を撮っている。やがて、夏は終わり、それぞれが自分の場所に戻っていく。十年後に「僕」はジェイズ・バーを訪れるが、そこには誰もおらず、廃墟になっていた。
原作と映画の違いを見てみよう。真っ先に思うのは、神戸市や芦屋市の具体的な土地が撮影されていることだ。原作には具体的な地名は「東京」以外には出てこない。しかし、映画では当然のことながら、実際の街が映像に出現する。
東京から長距離バスが到着する三宮駅前。西宮球場(西宮市。今はもうない)。神戸の港。埠頭に停泊する船。女性の家があったのはこの地域の山側に位置するだろうか。神戸・元町商店街のレコード店。彼女がフランス語を習っている教会。南京街。それから、新神戸駅。あるいは主人公が電話で話す大学職員の関西言葉。
神戸や阪神間の街が鮮やかにとらえられている。その結果、久々に帰郷した青年の孤独と喪失を描いた青春物語という性格が強くなっているのだ。喪失したのは何だろう。大学紛争と関係があるのだろうか。孤独は自分の生き方を通したために、仕方なく得たものだろうか。付き合っていた女性の自殺とも関係があるだろう。
一方、原作のテーマは複雑だ。コミュニケーションの不全も描かれているし、文学論も軽快な会話の中でかわされる。背景に孤独や喪失があるのは想像できるが、巧みに抽象化されていて、なかなか尻尾をつかませない。
大森一樹の映像はそんな村上のデビュー作の根底に、神戸や阪神間の風土で培われた青春があるのを顕在化させたように思える。それがとても面白かった。村上の初期作品の作風についてよく、世界中の都市と共通している街を描いていると指摘される。
しかし、大森の映画によって、その正体があらわにされているように思える。村上の初期作品には、まぎれもなく神戸と阪神間が描かれている。神戸や芦屋や西宮とともにある文学。それが村上の初期作品だったのではないか。それを抽象化していたのではないのか。
ネットでよく村上春樹の作品世界を歩く文章を読む。それらを読むと、神戸や芦屋の風土が村上の初期作品に影響を及ぼしているのが感じられるのだが、映画で謎解きをするようにそれを再確認し、実感するのは格別の経験だった。
村上はキャリアを積むことによって、神戸や阪神間だけではやっていかなくなる。生まれた街の京都が示す歴史や伝統や無常観。そして、東京、北海道、日本の各地、ヨーロッパ、世界へと小説の舞台は広がっていく。
大森一樹の映画は村上春樹の原点を示すものだった。村上作品の根っこにあるものの一つは、「無国籍」ではなく、神戸や芦屋の街なのではないかということを忘れないでいたいと思う。
余談を一つ。原作の鼠の口癖に「はっきり言って」というのがあることに再読していて気づいた。これは、岡田彰布・前阪神タイガース監督と同じではないか(岡田は「はっきり言うて」だが)。確かに関西人というのは、「はっきり」と言いたい人たちかもしれない。それをいちいち断っていうのは、彼らの都会人ならではのマナーだろう。