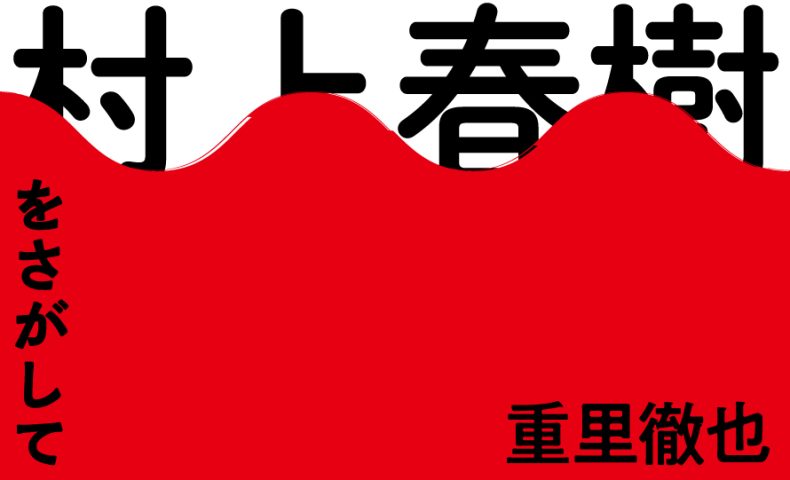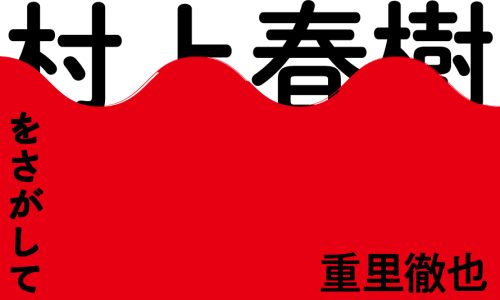今回は村上春樹と関西言葉とのかかわりを書こうと思う。京都に生まれて、兵庫県で育った村上にとって、関西弁は母語ということになる。村上と関西弁のかかわり方を考えると、見えてくるものがあるのではないだろうか。
最初に二つのエピソードを挙げ、それについて思いついたことを書き連ね、その後、短編小説『イエスタデイ』について考えよう。
前回紹介した小島基洋『村上春樹と《鎮魂の詩学》』(青土社)のうち、「『辺境・近境』と《デート》の詩学」と題された章は、衝撃的な書き出しで始まる。引用しよう。
「私のこと忘れんといてな」――直子が僕に残したのは、本当はこんな言葉だったのかもしれない。『ノルウェイの森』に登場する彼女に、僕が初めて出会ったのは高校二年の春のことである。共に関西で育った僕と直子は、高校時代はもちろん、大学進学で上京した後も、実際には関西弁で会話しているはずなのだ(一三七頁)
作品中で実際に直子が話す言葉は「本当にいつまでも私のことを忘れないでいてくれる?」というものだ。関西弁を話し出した途端、なんだか、直子がとても生命力の強い女性に変わったような印象を受ける。これだと、なかなか自殺しないんじゃないか。たとえ男性とセックスができなくても、生き続けるのじゃないか。阿美寮に入っても、けっこう楽しく日々を過ごすのではないか。
関西弁をしゃべるからといって自殺をしないわけではないのに、そんな乱暴な妄想に駆られてしまう。生活に根づいた言葉だからだろうか。
小島の本で、この章は「断章」と名づけられていて、第三章と第四章の間にはさまれている。短い章なのだが、興味深い指摘がいくつもうかがえる。たとえば、なぜ、村上春樹は一年浪人していたのに、小説の主人公は現役で東京の大学に受かったのか、というのもその一つ。小島は村上の出身校の県立神戸高校や村上ゆかりのピザハウスにも足を運んだようだ。
関西弁をめぐる二つ目のエピソード。
川上未映子の『夏物語』を読んでいて、唐突に聞こえるかもしれないが、私は直子を主人公にした小説みたいだなと思った。これは自殺せずに生き延びた直子じゃないのか。『夏物語』の主人公は夏子。「お」を「つ」に変えただけで、生命力をチャージしたように感じる。とにかく直子と夏子が、なんだか、とても共通点のある二人のように思えたのだ。ひょっとして、転生?
『夏物語』は二〇一九年に二回にわたって「文學界」に掲載。同年、文藝春秋から刊行された。私は文春文庫版で読んだのだが、村上春樹が帯に文章を寄せている。こんな具合だ。
「一人ひとりの読者に、それぞれの大事な意味を問いかける、鋭く、そしてチャーミングな小説です。主人公がしっかりと生きて、しっかりと息をしている」
村上の文章が他の日本人作家の本の帯に使われることは珍しい。一体、何があったのだろう。そう思いながら、読み進めた。前半は芥川賞受賞作『乳と卵』を下敷きにしている。
主人公の夏子は大阪の「笑橋」(京橋のことかもしれない)という下町で生まれ育った。小説家をめざして上京し三十代後半になった。五年前に小さな文学賞を受賞した。短編連作集を出し、テレビで紹介されて、ヒットした。新聞や雑誌にコラムやエッセイを書いて、ときどき、短編を発表して、長編小説に取り組んでいる。そんなふうにして、暮らしている。
夏子には著しい特性がある。セックスが好きではないのだ。付き合っていた男性はいたが、セックスは苦痛だった。でも自分の子供に会いたいと思い、セックスをしないで済む、精子提供の方法を模索するというストーリーだ。
生命のあり方や親子の関係をめぐるシリアスな小説だが、全体を通して不思議な熱気を帯び、地上の生を肯定する感覚がある。それはリズミカルな文体によるところが大きいように思う。そして大阪弁の会話。大阪で暮らす姉や姪との会話だけではない。印象的なベテラン編集者が登場するのだが、彼女の母親も大阪の出身で、主人公と時に半分漫才のようなノリのいい会話をかわす。
こういったものが、しぶとく生き続け、新しい生命の誕生を模索する夏子の姿を浮き彫りにする。ひょっとしたら、『ノルウェイの森』の直子は実はこんな人生を送りたかったのではないかという妄想にかられる。私には村上春樹から川上未映子へと渡されたバトンが幻視できるような気さえしたのだ。
村上春樹の短編『イエスタデイ』は短編集『女のいない男たち』に収められている。六編の短編のうち四編は月刊「文藝春秋」に掲載された。単行本は二〇一四年に刊行されている。
『イエスタデイ』を最初、「文藝春秋」の二〇一四年一月号で読んだ。一読して、ものすごくいい作品なのではないかと思った。
こんなストーリーだ。主人公の「僕」は早稲田大学の二年生。大学近くの喫茶店でアルバイトをしていた。同僚に同い年の「木樽」という男がいた。彼は早稲田大学をめざして浪人二年目だ。木樽には小学校の頃から付き合っている「えりか」という美人のガールフレンドがいた。彼女は上智大学仏文科の二年生だ。率直な生命力が全身からあふれているような女の子だった。
実は木樽とえりかは長い付き合いなのだが、セックスをしたことがない。木樽によると、子供の頃からよく知っているから、性的な行為をするのが「決まり悪い」という。そして、木樽は「僕」にえりかと付き合うことを勧める。それで、二人で映画を見て、食事をすることになる。それから二週間ぐらいして木樽はアルバイトを辞め、全く連絡が途絶えた。
十六年後、「僕」は偶然にえりかに会う。彼女は広告代理店に勤めていて、まだ独身だった。木樽は結局、大学へ行かず、米国のデンバーで鮨職人をしているという。
この小説には印象的な仕掛けがある。言葉をめぐる問題だ。「僕」は関西出身だが標準語を話す。一方、木樽は東京の田園調布出身なのに、完璧な大阪弁を話す。それも、大阪市南部の天王寺あたりの。大阪弁を話す理由が面白い。
木樽は阪神タイガースの熱狂的なファンで、阪神の試合をよく見に行っていた。タテジマのユニフォームを着て外野の応援席に行っても、標準語をしゃべっていたら相手にしてもらえない。阪神ファンのコミュニティーに入るために、血のにじむような苦労をして関西弁を習得したというのだ。
この『イエスタデイ』という短編を読んでいて、どうも、『ノルウェイの森』が思い出されて仕方なかった。『ノルウェイの森』もいわば三角関係を描いている。幼なじみのキズキと直子のカップル。キズキの友人だった「僕」(ワタナベ・トオル)。三人は関西の出身だ。
『イエスタデイ』と大きく違うのは、キズキは高校時代に自殺していることだ。大学進学のために上京していた「僕」と直子は偶然に久しぶりに会い、デートをするようになる。一度だけセックスをするが、直子は処女だった。直子は姿を消して、京都の山にある療養施設、阿美寮に入り、そこで自殺する。
なぜ、『ノルウェイ』では三人のうち二人が自殺し、『イエスタデイ』では三人とも生き延びたのか。この対比が興味深い。
もちろん、感じやすい直子と、生命力にあふれた前向きのえりかのキャラクターの違いは歴然とある。ただ、直子も体力は抜群で、実は自分の生命力をうまく発揮できていない印象を受ける。キズキは自殺してしまったが、木樽はしぶとく生き続ける。大学受験には何度も失敗しているが、彼はなぜ、自殺しなかったのだろうか。大阪弁と阪神タイガースを中核とするコミュニティーが彼を守ったのではないだろうか。
プロ野球のクラブチームを応援するというのは考えてみれば、不思議な行為だ。暮らしている現実と直接には関係があまりないプロ野球のリーグ戦。その勝敗に一喜一憂する。利害関係はない。ただ、好きか嫌いかだけだ。
プロ野球のリーグ戦では日々の日常と接しながらも、実はけっこう距離のある世界の物語が繰り広げられている。チームの姿が毎日の暮らしにちょっとした喜怒哀楽をもたらし、束の間、生活に起伏を与える。それは日常の苦しみやつらさを少し相対化するものだ。思い切り水で薄めた宗教のような働きがあるといったら、いい過ぎだろうか。
木樽の親しみやすい一方で、どこかぶっきらぼうなようすは、この世以外にもう一つ、心のよりどころのような世界を持っている人の姿ではないのだろうか。木樽はえりかとセックスができなくても死なない。早稲田大学への進学をあきらめて、異国で鮨を握り続ける。えりかも死なない。広告代理店の社員として時代の風俗の先端を歩きながら、生き続ける。
村上春樹は死んでしまった(いなくなってしまった)少女(直子)のことを繰り返し書き続ける作家だ。そんな中で、生き続ける男女の姿を描いた作品として心に残った。ビートルズの名曲「イエスタデイ」を関西弁の替え歌にしたけったいな歌とともに記憶に刻まれた。
昨日は/あしたのおとといで
おとといのあしたや