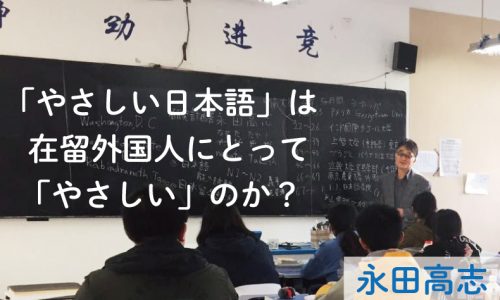沖縄問題入門のガイドブック
助川幸逸郎 選評では三島由紀夫が貶していますね。私は結構、三島の意見に同調するところがありました。この小説、当時の沖縄の問題が端的に語られていて、沖縄にあんまり詳しくない人間が、この時代の沖縄の状況を知るうえではひどく便利というか、これ一冊読めばいいみたいな、「沖縄問題入門」のガイドブックとしてはたいへんよくできています。
そういうガイドブックとしての価値はすごくある。けれでも、これは長編にしないとダメだと思いました。要するに問題がマッピングされたというか、今ある諸々の問題が綺麗に配置されたところで物語が終わっていますよね。そんな風に問題がマッピングされてできた構図をどう動かしたいのか。そういう意志を作品なり作者なりが示していくことによって、思想や文学が生まれるわけです。ですから私は、この『カクテル・パーティー』から、文学がはじまる準備段階で終わってしまったという印象を受けます。本当にこれが文学であり思想であるためには、ここから話を転がさないとダメ、というふうに感じたんです。
重里徹也 大城は一九二五年生まれ。三島と同い年ですね。そういう意味でも、三島の選評は興味深く思いました。おっしゃったことはよくわかります。同意する人は少なくないでしょう。
でも、大城はそれを聞いても、「ああ、あなたはそっちの方ですか」と言うような気がします。大城はそんな読み方など承知のうえで書いているのだと思います。わかったうえで、書いたのだと考えます。沖縄を理解してもらうためには、沖縄についての共通した基盤を作らなければならない。そういう意識で、大城はこの作品を書いたのではないでしょうか。
助川 うーん。たとえば、松浦理英子っていますよね。彼女はまず、『ナチュラル・ウーマン』ではっきりと、自分が理想とする性愛の像を書いたわけです。その後、『ナチュラル・ウーマン』だけだと、もともと自分に嗜好や感覚が近い人にしか伝わらないと考えて、『親指Pの修業時代』を書いた。『親指P』は、噛んで含めるように説明的です。『ナチュラル・ウーマン』で伝えたくて伝わらなかったことを、『親指P』でわかりやすく図式的に書いたんですね。
私は、大城に詳しくないのでお訊ねしたいのですが、大城に『ナチュラル・ウーマン』に相当する作品があって、松浦理英子における『親指P』みたいな位置づけでこの『カクテル・パーティー』を書いた、というのなら共感できるのですが、大城は『ナチュラル・ウーマン』的な作品をどこかで書いていますか?
重里 私も大城の初期作品をつぶさに知っているわけではありません。ただ、印象として話すと、ある時期から『カクテル・パーティー』の路線、そして『亀甲墓』の路線、この二つぐらいで小説を書いていくことにしたのではないかと思います。政治的要素が強いか、民俗的要素が強いかという違いはありますが、両方とも、「沖縄を描く」という点では共通しています。それを生涯、貫いたのではないでしょうか。個人としての自分ではなく、沖縄を書くのだということを自分に課したのではないかと私は考えます。
助川 つまり、大城には『ナチュラル・ウーマン』はないということですね。どうしてそういう感触を大城に対して持たれたんですか? 大城にインタビューをなさっていますけれど、そのときに何かお感じになったのでしょうか?
気になるレイプの描き方
重里 それは大城の仕事を一望し、大城の発言を拾えば、わかることではないでしょうか。沖縄の運命を描くことを自らの役割にしたのだと思います。自分がブルドーザーで道をならして、その後、沖縄から後進の若い作家がどんどん書いてくれればいいと思っていたのではないでしょうか。
もう一つ。大城の才能の質が図式を描くタイプの小説に向いていたのではないでしょうか。図式的だ、見ての通りじゃないかといった批判は、大城の多くの作品に当てはまるように思います。それは演劇的ということと関係があるかもしれません。その書き方は生涯、通したように思います。嘉手納基地で、米軍機による騒音で苦しむけれど、その下で琉球舞踊を負けないで踊っている、みたいな場面を晩年にも描いていました。図式的といえば図式的だし、わかりやすいといえばわかりやすい。けれども、そこまでして、問題を明確化することが自分の使命だと大城は考えていたのでしょう。そして、そういう作家がいてもいいというのが私の考えです。
助川 たとえば、『カクテル・パーティー』では、主人公の娘がレイプされます。そして、娘は告訴してくれるなって言うわけです。それなのに主人公は告訴する。結果的には娘の方が傷害罪に問われることになる。レイプみたいなデリケートな話柄を、問題を浮かびあがらせるための安易な道具として使っている印象がぬぐえなくて、フェミニズム的に見て、これはたぶん今だったら批判を浴びる可能性を感じてしまいました。
そういう、ひとつひとつのディティールに対する配慮のなさというか、熟慮の不足のようなものを、「図式を明確にするために仕方のない犠牲」といって許容する気には、私はなれません。
重里 そういう批判が、ネットでちょっと検索しただけでも出てきます。ただ、芥川龍之介の『藪の中』にしろ、志賀直哉の『暗夜行路』にしろ、太宰治の『人間失格』にしろ、日本近代文学において、女性はよくレイプされますよね。この点を問題にする研究も散見されます。日本の近現代文学における女性凌辱の歴史っていうのは重い問題で、この『カクテル・パーティー』に出てくるレイプもそこに連なるものでしょう。
助川 芥川とか太宰とか読んでいたら、レイプの話を出さなきゃいけない書き手の側の事情みたいなものはとりあえずわかるんです。だけど、『カクテル・パーティー』の場合、この手を使う以外に方法がなかったのか、疑問を感じてしまいます。
しかも、アメリカ人の男の子が迷子になって、大騒ぎで探しまわっているさなかに、実は主人公の娘が性犯罪に遭っていた、という設定になっています。何か、あまりにもあからさまな図式が、イージーに選択されている印象はぬぐえません。
重里 図式的、見取り図的、アレゴリー的、演劇的なのです。ところが、この小説は図式に収まらない部分も抱えています。たとえば、中国人の登場人物ですね。それで、被害者の加害者性というか、沖縄の人間の加害者性を浮かび上がらせている。そういうところは、この作品の底にある力のように思います。
沖縄という場所は、人々が激しい議論する土地です。そういう感触を持っています。大城もしばしば批判の的になっています。そういう中で鍛えられているのを、この小説を見ても私は感じます。
助川 沖縄には電車がないので、吞むときは終電を気にせず徹底して飲む、という話を聞いたことがあります。だから、呑みながらの議論もエンドレスになる。
重里 いきなり根底的な議論になるところがあるのではないでしょうか。日米関係をどうするのか、リゾートとは何か、中国とどう付き合うのか、沖縄独立論をどう考えるのか。大城もさんざん、自分の思想の根っこを問われたと思います。しかも彼は琉球政府に勤務し、県庁職員もした。論争のターゲットにされやすいわけです。そうした環境に身を置いたせいで、ずいぶん鍛えられている感じがありますよね。
被害者が加害者にもなるのだ、差別されている人間が差別をするのだ、ということをしっかり書いています。その辺のしたたかさは、議論で鍛えられた成果の一つなのかもしれません。そして、図式を重ねていった延長上に、ブラックボックスのような魅力的な中国人の登場人物を描いたのだと思います。
魅力的な中国人の登場人物
助川 「孫」という名前でしたよね。私も彼は魅力的なキャラクターだと思います。弁護士の資格を持っていて、だから専門職なわけですよね。相当に能力もあるんだけれど、異邦人だから公務員とか日本企業の社員とかにはなれないので、医師とか弁護士とかを選ぶわけです。人間的にいっても、主人公の娘の弁護も成算はないのに引きうける誠実さもあります。やれることは一生懸命まわりのためにやる。けれど、やれないことをムリに通すことはしない。そのあたりの見切りのつけ方にも、頼れる相手のいないまま、異国で生きている人間はこうだよな、こうでないと生きのびられないよな、というリアリティーを感じました。
重里 彼は一人で生活をしている。家に山水画があって、それを眺めて暮らしています。なかなか味わいのある人物で、懐の深さも感じます。逆に最も薄っぺらで、魅力を感じないのが新聞記者でした。日本の近現代文学に出てくる新聞や新聞記者というのは、いつもこういう書かれ方です。夏目漱石だろうが、大江健三郎だろうが変わりません。薄っぺらで、都合のいい「正義」を口にして、問い返されたら何も言えなくて、深く物事を考えてなくて、付和雷同する。日本の近現代における新聞って何なのだろう、新聞記者って何なのだろうというのは、小説を読んでいるとよく考えさせられますね。
三島由紀夫が選評で主人公のキャラクタリゼーションを批判しています。堀田善衛の『広場の孤独』(第二十六回芥川賞受賞作、一九五一年下半期)と並べて批判しているのが面白い。「主人公が良心的で反省的でまじめで被害者で」。私は主人公に限らないと思うのです。この『カクテル・パーティー』に登場する人物は、結局、みんないい人ばかりですね。もっと悪いことをするのが人間だと思いますが。
助川 それは感じますね。自分の個人的な怨念から娘の事件を拡大させて、レイプの告発も娘のためと言いつつ自分のためにやっている部分があって、その点について主人公の内面に葛藤があった、という話なら、私も共感できたでしょう。自分がこれまで仕事をしていくなかで、アメリカに対する複雑な思いを抱いていて、そこに整理をつけるために娘のレイプを大ごとにしていくんだけれど、一方ではそんな自分のエゴイズムに傷ついてもいる、みたいな筋書きにするのは、むずかしかったのでしょうか。
重里 直面している問題が重くて大きいので、何とかそれを図式の形であっても、あらわにしたいということではないでしょうか。そして、それは意味のある仕事だと思いますね。小説という表現は、そういうところがあるのではないかと思います。重い題材にこのように挑んだだけでも、意味があると思うのです。たとえば、原爆を描く、戦争を描くということでもいい。そういう題材を真正面から小説にしたということだけでも、意味があるように考えます。
図式を超えるものがあるのか
助川 この図式で書くのだったら、エンターテインメント小説にした方が効果的だったのではなかったでしょうか? たとえば、高村薫みたいな社会派犯罪小説にすれば、読者はこの図式をもっとダイナミックに体感できた気がします。
重里 それこそ、「孫」を主人公にしたら面白いかもしれませんね。『カクテル・パーティー』は、前半が一人称で後半が二人称ですが、これはどうでしたか。
助川 後半部分は結局、「君は」とか「お前は」と書かれているけれど、これ実質一人称と同じですよね。それで、レイプを告発することが、被害者である娘を傷つけているということをどこまで自覚しているのか、みたいなことを一人称で問題化するのは、テクニック的に難しいんですよ。だから後半を二人称にしたんだと思います。そうすれば主人公に対し、「お前はこういっているけれど、本当はこうじゃないか」という感じで語り手が突っこんでいけるわけです。そういう意味でも、この小説は易きに流れているなあ、という気がしてしまいます。
重里 この作品の評価は、図式的だとか、寓話的だとかいった批判を超えるものを見いだせるかどうかでしょうね。
助川 沖縄に『カクテル・パーティー』に書かれたような問題があるのは事実で、それを無視することができないのもわかります。しかし、あえて言いますが、ある小説に書かれた問題が大事だからといって、その小説がその問題にもたれかかっているようなものであっても許されるのでしょうか。
重里 問題が深くて重いものであれば、それを何とか書こうとしただけでも、一定の意味が付与されるべきだというのが私の立場です。何を書いているのかという題材の重さを考慮しない批評の立場を私は取りません。
助川 私にとって沖縄の作家というと、ウルトラマンの生みの親である金城哲夫です。大城は金城と親交があって、何度も金城について書いています。だから大城のことを悪く言いたくはないのですが……。
重里 大城は、「自分は沖縄をめぐる問題の大枠を書くから、そこから先は自分より若い書き手が沖縄から登場して書いてくれればいい」と思っていたのではないでしょうか。
助川 おっしゃる意味は、大城の金城に対するスタンスなんかを見ると、わかる気がします。ただ、クリエイターは何か問題を明らかにするためにものをつくるのでしょうか。ある問題に対し、自分がどうかかわるかということを留保したままで、その問題をめぐる作品を作れるのでしょうか。
重里 おそらく大城は確信犯です。自分の役割を定めていたのだと思います。問題の所在を明らかにするだけでも、自分のその問題に対するスタンスを表明できます。大城の後、又吉栄喜も目取間俊も崎山多美も出てきました、そういう人たちが沖縄の文学をどんどんやればいいじゃないか、と考えていたと思いますよ。助川さんが直接、大城にいまおっしゃった批判を突きつけても、微笑して、「なるほど、図式的か、私の小説は」と答えるだけでしょうね。そんなこと、わかっていてやっているわけです。
背後にある大城のニヒリズム
助川 私の父親が大城より一つ年上で、母親は金城哲夫と同い年です。ですから、大城の世代と金城の世代の、戦争体験の違いがよくわかります。金城の世代は、身体に刻まれた戦争の恐怖はあるのですが、それを知的に解釈するフレームは、戦後になってから植えつけられているんです。いっぽう大城の世代は、生理的な部分と知的な領域と、双方が戦争によって脅かされた体験をしているはずです。
そうすると、この対談でも触れた、井上靖や開高健が抱えていたようなニヒリズムの問題と、大城も直面していたと私は思うんです。そこのところと大城がどう向きあっていたのかが、この『カクテル・パーティー』からは見えて来ない。『ナチュラル・ウーマン』を書かない道を敢えて大城が選んだのとすれば、自分自身のニヒリズムの問題があまりにも大きいので、それを封印したということでしょうか。だとすると大城は、「沖縄文学の不可能性」を受けいれることで、辛うじて沖縄文学の書き手になった、ということになりますね。
重里 ある視点から見れば、戦後の日本はアメリカの「半植民地」のようなものです。ところが、沖縄は「半」抜きの「植民地」なわけです。治外法権なのですから。大城はせめて「半植民地」になりたいといっている。大城の抱えていたニヒリズムの現実的な側面とはそういうものでしょうね。
ところで、この後、九〇年代に一時期、沖縄文学ブームみたいなものがあったのですが、長くは続かなかった。逆にポピュラー音楽やダンスで続々と才能が出て来た。安室奈美恵はその象徴的な存在でしょう。沖縄の表現者の出方が変わったのかもしれません。
助川 ダンスだったら、いろんな要因が入り組んでいたとしても、図式的に交通整理する必要がありませんね。ひと目見れば、すぐにわかりますから。
重里 音感や身体のキレが本土の子どもたちとは何か違うような印象がありますね。物心がついた頃から、英語やアメリカ文化にさらされていることと関係があるのかどうか。ダンスだと、沖縄の置かれている立場がそのままアドバンテージになるような気がします。
助川 中国VS本土VS沖縄VSアメリカみたいな、項の多すぎる連立方程式みたいなものなんです、この『カクテル・パーティー』って。だから、図式的にしないと問題の所在が明らかにできないって、弁護なさるのはある意味わかります。でも、変数がいくつあっても踊りは一つですから。
重里 だけど私なんかが思うのは、だからこそ、新しい小説の書き手に登場してほしいということですね。困難であればあるほど、魅力的な文学が生まれてくるのではないか。抑圧が強ければ強いほど、優れた文学がそれを突破してくるのではないか。文学の原理に基づいて、そんなことを期待したいです。