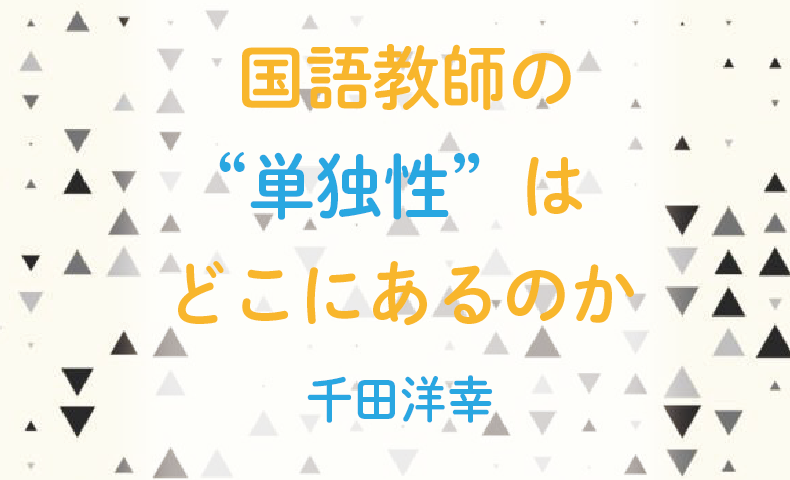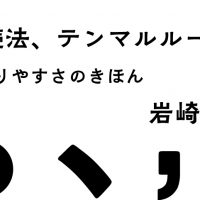私は授業で、物語の両義的な機能について説明するために、ふたつの古典的な論文を紹介することがある。ひとつは内田伸子「絵本の読み手から語り手へ」、もうひとつは本田和子「〈物語〉としての世界把握」である(注1)。内田論文の方から引用してみよう。
絵本は、以上に考察したように、知識や価値観の伝達以上の意義をもつ。物語世界に触れることを通して、子どもは現実の知覚世界の制約を越えて、もう一つの世界、虚構の世界を知ることになる。やがて、自分自身でも虚構性を構成するための枠組みや構造が与えられるようになり、虚構と現実とを自由に操作することができるようになる。これによって、子ども自身や子どもを取り巻く環境内の“もの”や“こと”を整理し、一貫性ある世界を構築する枠組み、「世界づくり」の手段が与えられることになるのである。絵本は、現実とかけ離れた別世界に私たちを誘うわけではない。「今の」自分の経験を整理する枠組みを与えてくれるものなのだ。
人はすべてを自分自身で体験することはできない。他人になることも難しい。しかし、絵本を読み聞かせられ、自分でも物語を生成することによって、登場人物達が自分に代わって、難題を解決し、欠損を補充する様を生き生きと見せてくれる。これにふれることで、未知の現実を想像し、他人の気持ちを理解するようになる。ある“こと”を別の文脈に組み込んでみることで、その“こと”は対象化しやすくなる。新しい局面が見えてきて、解決する術を手に入れることすらできるようになるのである。これによって、自分の問題を解決する糸口が与えられたり、ときには病んだ精神が癒されることもある。
内田の言説は、子どもが虚構の物語世界に触れることによって獲得することができる認知能力のポジティブな側面を示している。内田は冒頭で、染色体異常による重度の障害を負ったクシュラという児童の事例を取りあげながら、物語が読みの主体と世界とをつなぐ有効な架け橋となりうること、ファンタジーをふくむ虚構のストーリーが子どもの「世界づくり」に貢献すること、子どもの不安や恐怖の経験を対象化・構造化して解決や癒しに導く作用をもっていることを強調する。物語を読む行為にこうした価値を付与する論理は、国語科教育の実践・研究の文脈においても有効であるはずで、学習者が物語を読む/学ぶことの意義を考える際にも、重要な手がかりを提供してくれることだろう。
一方、本田論文が事例としてあげているのは、1974年に起こった、冤罪事件として著名な甲山(かぶとやま)事件である。同年、西宮市の知的障害者施設甲山学園の浄化槽から園児二人の遺体が発見され、アリバイなしと見なされた保育士が逮捕されたが、長期にわたる裁判の結果、1999年に無罪判決が確定した。本田は、検察側がこの事件を「立証」する際に重要な役割を果たした園児の証言に着目し(注2)、この裁判の過程における物語の意味についてつぎのようにのべている。
……目撃者を名乗る少年に先ず与えられたのは、「子どもが失綜し、その遺体がマンホールから発見された」ということと、「職員の一人が逮捕され、被告として法廷に立った」という事実の断片であった。異変の出来に収拾もつかぬ混乱に陥った彼は、秘密めかして囁かれる「施設内殺人事件」という枠組みに添って「物語」を構成し、それを内面化することで辛うじて自身の安定を確保した。そして、五年後に、その物語を外化する機会が訪れたとき、彼の言葉は堰を破った水のように物語の完成に向けて水路付けられ、そのために駆り立てられた修辞の数々が、「女子職員が子どもを連れ出して殺した」という、のっぴきならぬ結論へと「物語」を導いたのである。
その職員が、果たして、子どもを殺したのか、否か。それどころか、本当に子どもを外に連れ出したのか、否か。それらは、すべて少年の言葉の陰に覆い隠される。すべては、彼の語りのおどろおどろしさの中に溶解されてしまったのである。彼の語りは、こうして見事なまでのイデオロギー性を発揮し、「ちえおくれの子ども」(原文ママ)という理由から、彼に対して比較的無防備であった関係者たちを、すっぽりとそのイデオロギーで染め付けてしまった。私どもがここに見るのは、修辞のイデオロギー性が語られるもののメッセージを固定化し、ただ一つの意味へと収斂させていく力学であろう。
本田が注視するのは、あきらかな誤謬を内包しているはずの物語が、それを発信/受容する人間たちによる恣意的な合理化と正当化を招き寄せ、強固な「真実」として機能してしまう事態である。いうまでもなく、ある物語が強度をもつイデオロギーと化し、人の意識と行動を根底から支配し、ときにその生死をも左右する権力性をはらむということは、個人のレベルから国家のレベルにいたるまでしばしば起こる。すなわち、子どもの「世界づくり」や「経験の解体と再建」(内田)に奉仕することも、錯誤や虚偽をかたく信仰してしまう呪縛へと人を陥れることも、おなじく物語の機能だということなのだ。
内田・本田の両論文は物語がもつ対照的な作用について語るものだが、これを言語一般の問題にまで拡張していうなら、言葉そのものがヤヌスの双面のごとき相反する機能をもつのは自明のことでもある。言葉は人と人を結びあわせることができるが、同時に分断し離反させることもできる。救いや癒しとして働きかけることもあれば悪意をはらんだ中傷として投げつけられることもある。これは善悪の問題ではなく、そもそも言葉はそういうアンビバレントな方向性を具備しているのである。
国語科教育(学)の場において許容されるのは言葉のポジティブな側面、あるいは規範としての側面であり、憎悪や差別や暴力性をはらんだ言葉などは、その使用はむろんのこと、研究対象にすらなることはなく、あたかもこの世から抹殺されたかのごとくである。しかし、児童・生徒たちは、現実の人間関係のなかから、テレビ等のマスメディアから、さまざまなソーシャルメディアから、そうした言葉を当たり前に受容かつ吸収し、自己の言語体系に直接的に組み込んでゆく。国語教科書がいかにさまざまなヴァリエーションをもつ教材を収録しようと、結局、児童・生徒の言語生活の半面しかカバーすることはない。国語科の実践とそのテキストは規範の言語を学ぶための媒体・手段なのだからそれで当然、というのが世のおおくの国語教師の考え方であろうが、学習者が日常のなかで使用する言葉への働きかけとしてそれで十分なのか、と私は不安をおぼえてしまう。
もちろん、言葉がときに醜悪な意味あるいは行為として他者に突き刺さってしまう、という問題に自覚的な教材も存在する。言語の社会性が習得されてゆく小・中学校期においてとくにこういう視点は重要と思われるが、現行の中学校国語教科書『国語3』(光村図書)に掲載された鷲田清一「それでも、言葉を」は、筆者が朝日新聞に連載している「折々のことば」の執筆経験をふまえながら、現代日本における「言葉そのものの惨状」について語っている。
言葉がまるでうぶ毛をなくしたかのように、むき出しで人にぶつかるようになった。言葉が、露骨な差別や捨てぜりふ、居直りとして礫のように投げつけられたり、アリバイや言い逃れ、時に隠れみのとして巧みに操られたりする場面に、路上で、報道で、頻繁に触れる。
わかりやすさや反応の速さが求められる時代、大量の言葉を前に、じっくり言葉と向き合い思考する時間も、吟味して言葉を選ぶ心の余裕もなくなっている。社会に、隙間という意味での「あそび」がなくなってきている。短絡的な言葉で片づけようとして言葉が先鋭化し、一気に攻撃的になる。法令を遵守しているかいないか、ファクト(事実)かフェイク(でっちあげ)か、ラブ(愛)かへイト(憎悪)か、大声か沈黙かというふうに、両極端に分かれ、グレイな対応を許さない、そうした社会の余裕のなさが、言葉の二極化の背後にあるように思われてならない。
鷲田は、言葉が暴力や憎悪とたやすく癒着するこの社会の現状にくわえ、言葉の「二極化」という事態が発生していることを憂慮し、「両端の「間」に息づく言葉、多様なグラデーションを許容する言葉のありよう」が必要であることをのべる。言葉がはらむ曖昧さや多義性、単純な否定でも無批判な讃美でもない皮肉、アイロニー、ユーモアといった表現の「間合いの幅」の意義を強調し、歴史や社会や人間それ自体をささえてきた「言葉の力」が復権する可能性を探ろうとする。
「それでも、言葉を」は、いま言葉がおかれている状況に即した文章として信頼にあたいする内容であり、ネット/SNSを駆使した言語生活になじんでいる中学校3年生にとっても良質の教材といえるだろう。とくに国語科教育にたずさわる者は、言葉が暴力性と空疎さにまみれている現状、言葉がもつ繊細な「肌理」(鷲田)を平板化してしまうレトリックの蔓延に疑念をいだいているはずであるから、おそらくは肯定的にとらえられる教材だと考えられる。
ただ残念ながら、「それでも、言葉を」には――教科書教材の限界でもあるが――言葉が使用される現状についての肝心なことが書かれていない。このエッセイは、言葉の暴力や「二極化」が倫理的に忌避・批判されるべきであるにもかかわらず、けっしてそれを手放そうとしない人間が数かぎりなく存在する、という事実には触れようとしないのだ。異質な他者を排除するヘイトの言葉、陰謀論のようなわかりやすい虚偽の物語……等々にはまり込んでいる人間にとって、この教材は、「もっと言葉を豊かにしろ」とか「言葉の可能性を信じろ」といった類いの退屈なお説教と同義であるにすぎまい。こういう内容では、単なる学習対象であることを超えて、学習者にパフォーマティブに働きかけるアクチュアルな役割をもつことはむずかしいだろう。
すこし探せばいくらでも見つけられる、SNSで他人にヘイトを投げつける人間、フェイクニュースや陰謀論(その多くは排外的ナショナリズムやレイシズムをともなっている)に没入する人間があとを絶たない単純な理由のひとつは、端的に、それが動物的な快楽と充足感を生み出すからである。他者に罵詈雑言をあびせかけ、傷つけ、惨めさを味わわせて優越を感じること、自己の認知バイアスが無条件で肯定されることは、この上ないドラッグ的な昂揚をもたらす(ついでにそういう言葉がSNSで拡散されれば承認欲求の快感までも満たされる)(注3)。醜悪な言葉を駆使すること、醜悪な物語にはまり込むことは、非言語的な快楽に浸らせてくれる――つまり「気持ちいい」のだ――という身も蓋もない事実を、我々は認めておかなければならない。
ネット/SNS時代においては、こうした邪悪な「言葉の力」が提供する快楽と誰もが無縁ではありえないが、そこに入り込んだまま抜け出そうとしない(抜け出すことができない)心理の底にまで降りていかなければ、学習者の言語生活のリアルに接近することはできないだろう。無害化・無毒化された言葉の半面のみを取り扱う、学習指導要領をただ遵守するごとき貧しい実践では、学校外の言葉と教科内の言葉との乖離を拡大させるほかはないのだ。
ならば、国語科学習の現実的な制約を前提とした上で、この両者のあいだに意味のある連続性を作り出すこと、すなわち我々の周囲に流通しているリアルな言葉に手を伸ばす方策はありうるのだろうか(注4)。結局、月並みな発想に落ち着かざるをえないのだが、文学教材が貢献しうるのはこういう局面においてであると思う。学びの場においてタブーとされる暴力、憎悪、差別、侮蔑の感情などを語りうるのは、かろうじて文学の言葉だけだからだ。
たとえば、魯迅「故郷」。主人公―語り手である「私」は、ヤンおばさんを「コンパス」、ルントウを「でくのぼうみたいな人間」と、あからさまに侮蔑的な言葉で名指している。そこには、異質な他者を貶めることによってみずからの立場を正当化したり、貧しい庶民を目のあたりにした心理的パニックを沈静化させようとする意思が存在しているのではないか。物語の終末において、「私」が「希望」とか「新しい生活」といった抽象的な問題について思惟することが可能になったのは、ノイズと見なした他者に社会的落伍者のレッテルを貼って己れの視界から追放したからではないのか。だとすると、「コンパス」「でくのぼう」という侮蔑語こそ、「私」の語りにおいてもっとも必要とされた言葉であった、ということになるだろう。
あるいは、芥川龍之介「羅生門」。この小説では、主人公である下人の心理が「あらゆる悪に対する反感」→「冷ややかな侮蔑」→「(盗人になるための)勇気」の獲得、という順に変容してゆくが、いうまでもなくこの過程は老婆との対峙のなかで発生したものである。すなわち、「下人は初めて明白に、この老婆の生死が、全然、自分の意志に支配されているということを意識した」と語られている通り、あきらかに自身とは非対称的な弱者である老婆(しかも下人は太刀まで所持している)と相対している状況だからこそ、下人は勝手に正義漢と化したり盗人に変身したりすることが可能となるのだ。だから、「下人が盗人に“成長”した」というよくある解釈はたんなる誤読であり、下人は弱者を見下す卑劣な人間性を一貫して保持したまま、表層のキャラクターのみを取り替えているにすぎない。「おれもそうしなければ、飢え死にをする体なのだ」という正当化のもと、老婆を「手荒く屍骸の上へ蹴倒」す暴力への衝動は、こうした主体のあり方にもとづいて発揮されるのである(注5)。
これらの教材はあくまでも一例であり、また「故郷」も「羅生門」も、それぞれの歴史性を考慮するなら、現代の言語状況や「社会の余裕のなさ」(鷲田)と単純に結びつけられるわけではない。だがこの両者は、ここまでくりかえしのべてきた、言葉/人間のネガティブな領域に積極的にコミットする志向をもつゆえに、他の教材とは異質な学習可能性を主張しうるだろう(もっとも、「故郷」を「希望の文学」として読むなどという浅薄な教材研究がなされては、それも台無しになってしまうわけだが)。そして、国語科教育において不可視化されている、この社会の底部に大量に淀んでいる醜悪な言葉たちについて真剣に問題化し、思考・分析しようとするなら、このふたつの定番教材にとどまらず、さらなる教材研究・教材開発が必要とされるのである。
剝製化した言葉の学習にとどまらない国語科教育、言葉/人間のダークサイドに触れうる国語科教育をめざすのであれば、文学教材の役割はまだまだ終わっていないと考えるべきだろう。
(注1)内田伸子「絵本の読み手から語り手へ――子どもの創造的想像力の発達――」(日本児童文学学会編『研究・日本の児童文学5 メディアと児童文学』2003、東京書籍)、本田和子「〈物語〉としての世界把握――子どもにとっての〈文学〉――」(『日本文学』1995.3)
(注2)内田論文・本田論文がいずれも、物語の役割について語る際に障害をもつ子どもの事例を掲げているのが注意を引かれるところだが、この問題についてはとりあえず措く。
(注3)本来はここで、「匿名」という問題(言葉のみを発話して、語る自己主体それ自体の固有性は隠蔽すること)を取りあげなければならないのだが、今回は準備がなく、後日考えてみることにしたい。
(注4)社会科教育では、たとえばヘイトスピーチについて考察する実践がすでに行われているが、国語科教育においてこうした言説を言語論的に追究する実践は管見のかぎり見当たらない。
(注5)下人は羅生門を去った後、暇を出された主人の家を襲うだろうと推測する解釈もあるが、下人の属性からすれば自分より力をもつ者と抗争することは考えられない。下人が今後襲うのは、自分より力が劣る弱者たちであろう。