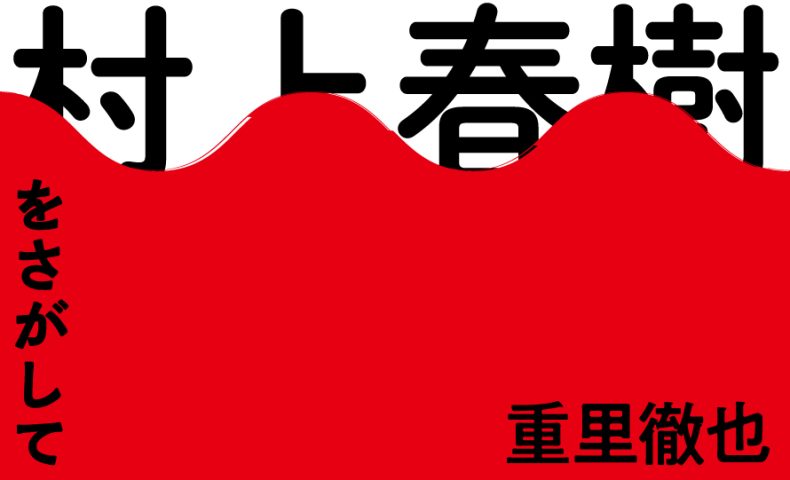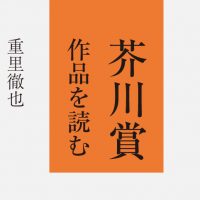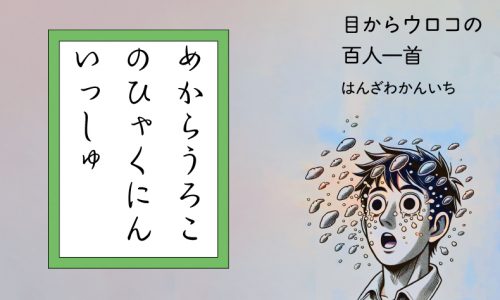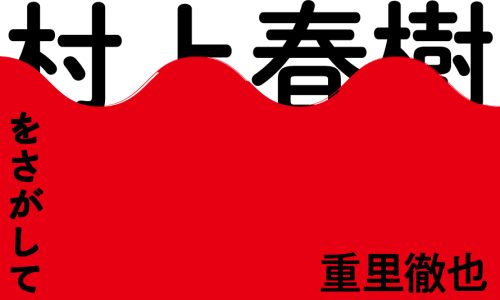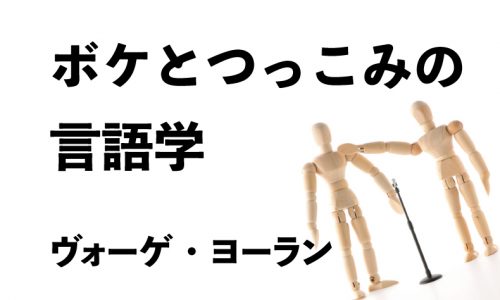この三十年間、私たちは何かいいようのない不安に、生活や心をむしばまれているのではないだろうか。三十年前というのはもちろん、阪神・淡路大震災とオウム真理教による地下鉄サリン事件があった一九九五年である。あれから、大げさにいえば、それ以前とは違う時代を生きているような感じさえする。
二〇一一年には東日本大震災に見舞われた。それ以外にも、大きな地震は何度か起きている。そのたびに甚大な被害が出ている。私たちは、次はどこで起きるのだろう、と疑心暗鬼にとらわれている。首都直下か、それとも、南海トラフか。こういう精神状態は確実に私たちの日々に影を落としている。地震だけではない。記録にない猛暑が続いたり、前例のない豪雨に襲われたりする。
〇月〇日に大震災が起きるという予言のようなものがネットで流れると、私など、ふと、そうかもしれないと思ってしまうのだ。もちろん、冷静な計算もある。これは、不意の震災に襲われる前に、用心と用意をするきっかけにしてしまえばいいだけのことだと考えるのだ。どうせ、そのうち、大震災は起きる。
自然災害だけではない。ネットを使った詐欺は後を絶たない。私は固定電話には出ないことにしている。おそらく、何かの営業か、つまらない世論調査だ。街の治安も三十年前よりよくなったとはとても思えない。どこか国全体が殺伐とした方向へゆっくりと進んでいるような気がしているのは私だけだろうか。
そんなことに改めて思いをはせたのは、井上剛監督の映画「アフター・ザ・クエイク」を見たからだ(十月三日公開)。原作は村上春樹の短編集『神の子どもたちはみな踊る』(新潮文庫)。二〇〇〇年に単行本が刊行されたもので、文芸誌「新潮」発表時は「地震のあとで」という副題を付けて連載された。阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件が起こった後の人々を描いている。
この短編集には、六編の作品が収録されている。このうち四編を原作にNHKが四話から成るドラマを製作して、今年四月に放送された。映画「アフター・ザ・クエイク」はこの四つのドラマを再編集し、再構成して作られた。
NHKのドラマは放送時にすべて見た。友人たちとけっこう批評した。村上の小説にあった深みが失われてはいないか。なぜ、原作にあったあの部分を消したのだろう。キャストが一部、適していないのではないか。
これは愛読している小説が映像化された時に、しばしば感じることかもしれない。活字から想像していた世界が違って目の前に現われたので、戸惑いを感じるといえばいいか。ほんとうは見ない方がいいのかもしれないとさえ思う。
なのに、映画「アフター・ザ・クエイク」の試写を見てしまった。そして、結論をいえば、かなり、いい作品だと思ったのだ。短編が奏でた四つの世界が有機的につながって、私たちが今という時代を生きる感触を表現してくれているように思ったのだ。
原作になった四つの短編とは『UFOが釧路に降りる』『アイロンのある風景』『神の子どもたちはみな踊る』『かえるくん、東京を救う』。それぞれ、舞台になっている年号が示されていて、阪神大震災が起きた一九九五年から、東日本大震災の二〇一一年、それから九年後の二〇二〇年、そして、現在の二〇二五年に設定されている。
つまり、村上作品の魅力を生かしながら、舞台になっている時代設定を大胆に変えて、アレンジしている。その結果、この三十年を振り返り、今後を展望するような映画になっているのだ。
一九九五年。オーディオ専門店で働く小村(岡田将生)が主人公。大震災の映像をずっとテレビで見ていた妻が家出し、離婚することになる。空っぽな心を抱えたままで、小村は同僚から頼まれて北海道の釧路へ行くことになる。そこで二人の女性と会うが、小村はいよいよ、自身の空虚感をかみしめることになる。
ポイントは小村が抱く虚無感だろう。それは大震災がもたらしたものというよりは、以前から小村が持っていて、そのことに大震災で気づかされたものだ。では、その空っぽの自分を抱えて、どう生きていけばいいのか。釧路で待っていた女性たちは、そんな心に浸食してくるように見える。
二〇一一年。家出して、海辺の街のコンビニでアルバイトをしながら、恋人と生活する若い女性(鳴海唯)が主人公。彼女は海岸で毎夜、焚き火をする関西弁の男と知り合う。彼は神戸市に住んでいたことがあって、地震で揺れる中で冷蔵庫に閉じ込められる悪夢にうなされている。二人の空っぽの心が、焚き火の前で交差する。
二〇二〇年。母親が宗教団体の熱心な信者である若い男(渡辺大知)が主人公。「神様」を疑い、心が揺れる彼の姿を描きながら、心のよりどころを持てないで、もがき続ける姿を描く。
二〇二五年。かつて信用金庫に勤め、今は地下駐車場の警備員をしている片桐(佐藤浩市)が主人公。彼はマンガ喫茶で暮らしている。巨大なカエルの姿をした「かえるくん」が現れ、三十年前と同様に再び、一緒に戦ってほしいと頼まれる。片桐は戸惑いながらも、かえる君に協力して不思議な体験をする。
いずれも、大震災が人々に根底から不安をかきたて、そこで彼らはもともとあった空虚感に直面する物語。いくつかの話では、その空っぽな心に神秘的な誘惑が迫ってくる。四つの話を冷蔵庫とか、空っぽの箱とかいった小道具で有機的につなぎ、途中ではさまれる赤い廊下の映像が四つの時代を結びつける。
全体が一つにまとまる工夫はあちこちに見られ、わかりやすいメッセージが浮かび上がってくる映画だった。私は図式的にまとめてしまったが、村上春樹がこの短編集を書いた思いを現代の時点から、確かに表現しているように思った。主人公たちがいずれも、漂いながら、必死で悪戦苦闘しているのが印象的だった。