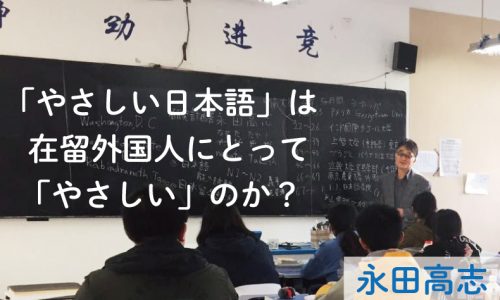固有名を喪失する病気
重里徹也 今回は大いに質問したいと思います。まず、なぜ、古井は『杳子』を、一人称ではなくて三人称の小説にしたのでしょうか。
助川幸逸郎 杳子の病気自体が固有名の消失ですよね。喫茶店に着いても、以前に訪れたのと同じ喫茶店なのに、そういう感じがしなくて中に入れないというのが出てきます。これは病状で言うと境界性人格障がいです。ボーダーライン・パーソナリティー障がい。
重里 平たく言うと何なのですか。
助川 簡単に言っちゃうと、重里先生、今日は変だよねということが、ボーダーライン・パーソナリティー障がいの人って言えなくなっちゃうんです。普通は人間って他者を二重化していて、重里先生っていう名前で重里先生を呼んでいる時には、今見ている重里先生と、これまでずっと付き合ってきて私の中で重里先生はこういう人だっていうイメージと二重重ねにして見ているわけですよ。ところがボーダーライン・パーソナリティー障がいの人は、その時その時のその人しか見られないんです、簡単に言っちゃうと。メンヘラさんの一種です。
今日、重里先生が私に対してちょっと態度が冷たかったとしても、もう芥川賞企画をやめちゃうのかな、とかまでは思わないじゃないですか。それはこれまでのお付き合いがあるからなんですが、ボーダーライン・パーソナリティー障がいの人はそれまでどんなに大事にされても、その日一日心が通い合わないと、もう絶望して死んじゃったりしちゃったり、リストカットをしちゃったりするわけですよね。それは要するにその時の自分、目の前に現前している他者とそれまでの蓄積によってできたその人に関するイメージみたいなものが、普通の人間は二重重ねになるんだけども、ボーダーライン・パーソナリティー障がいの人は二重重ねにならないんです。常にその瞬間を生きている人という感じになってしまうんですよね。だから、先週使ったのと同じ喫茶店に来ても、同じ喫茶店っていう実感が持てない。杳子は多分そういう時間帯を生きている。
重里 自分自身に対してはどうなのですか。
助川 自分の人格もすごく不安定なわけです。
重里 だから、アイデンティティー障がいでもあるわけですね。自己同一性を失っている。
助川 そうなんです。だから他人の感情に移りやすいし、他人の感情が胸に浸透してきやすいのです。もう一つの現代人の病である統合失調症はある意味反対です。統合失調症の人というのは、逆に言うと目の前の現実みたいなものに対する実感がすごく希薄になってしまうんですね。逆に。
重里 なるほど。平たく言えば、杳子がかかっている心の病は、目の前の現実に振り回される病ということですか。
助川 そういうことです。目の前の現実が圧倒的に自分に入りこんできてしまって、それがどういうものかっていうことに形を与えることができなくなってしまう。そういう状況です。だから、この小説で書かれている世界というのは、固有名が成立しない、境界性人格障がいの世界ですね。
この小説は固有名が不成立の世界を描いているのです。だから、本当はすべて匿名でやりたいのだと思います。きっと。ほとんど一人称視点なのだけれど、これ「僕」とか「私」とか、男の一人称にした場合、ニュートラル度(中立性)がなくなってしまいますよね。「私」だとある程度、成熟した大人だろうとか、「俺」だとプライベートな立場で語っているなとか。男性の一人称は、どれを選ぶかというだけで、その人の属性とか立ち位置とかを表してしまうんです。それを古井は避けたかったのだと思います。だからそこで、「僕」とか「私」とかを全部取っ払ったニュートラルな匿名性っていうのを出したかったのではないでしょうか。そこから出てきたのが、「彼」という人称だったのじゃないかなと私は思います。
重里 「彼」も同じ病を病んでいるのでしょうか。読んでいると、そんな感じもうっすらと漂っていますが。
助川 「彼」も病んでいるというよりも、もともとは杳子自身が姉との比較で、この病がうつってきたわけです。そういう人格性障がいの病気をね。そして、杳子と接するうちに、「彼」もこの世界に巻き込まれていくわけです。ボーダーライン・パーソナリティー障がいの症状については、山が崩れて滲み出してくるみたいな描写が散々、この小説の冒頭でありますよね。それで、そういうある境界が崩れて周りの現実が自分の中に侵襲してくる感じというのが杳子の病であって、彼女の病に付き合っているうちに、「彼」と杳子の間の境界みたいなものも崩れ落ちていくという状況ですね。ボーダーライン・パーソナリティー障がいの人と付き合っているとこういうことが起きやすいです。特にディープに付き合っていると。そういう状況を描いた小説なんだと私は解釈します。
「彼」はなぜ、外を向かないのか
重里 「彼」はもともとは健常者なのでしょうか。やはり、境界性人格障がい的な精神の傾向を持っている人なのでしょうか。
助川 「彼」はこういう女性に引き付けられやすい人ですね。おそらく資質はあったんだと思いますね。こういう女性に惹かれてしまう。こういう女性に引っかかりやすいタイプの男っているんですよ。
重里 これは、大学生同士の恋愛を描いた小説とも読めますね。なぜ、「彼」は他のことに興味を持たないで、杳子にばかりのめり込むのでしょうか。杳子はそんなに魅力的なのでしょうか。「彼」はなぜ、こんなに内側にばかりのめり込むのでしょうか。拒否している外側には何があるのですか。外側にあるものが、この小説の隠し味になっているのでしょうか。
助川 精神医学の話ばかりしていますけれども、この状況、このボーダーライン・パーソナリティー障がいの人が混ざり合う状況になってしまうと、完全に密室で二人きりみたいな世界になってしまうわけです。外部が目に入らなくなってくる、完全に。
重里 意識的にか、無意識にか、外部を避けているのではないでしょうか。
助川 外を避けているというか、外がない世界に行ってしまっているんですね、二人で。
重里 外に意識を向けたくないのではないのでしょうか。外に行きたくない理由があるのではないでしょうか。内側を見ているのが心地いいのではないでしょうか。
助川 外に行きたくない理由というか、そういう具体的な何かがあるっていうよりは、この世界がそういう世界なんですよ。だから外に行きたくない。
重里 私には何か、外を避けている感じがします。かたくなに外を嫌っている。
助川 外があったとしても、外がどんどんどうでもよくなるような世界にめり込んでいく感じなんじゃないですかね。
重里 私は読んでいて、かたくなに外を避けている感じがしました。
助川 それは、男の方が?
重里 はい。ただ、それは隠し味になっているのですよ。外にはろくなことがないだろうということを隠し味にして、内側にのめり込んでいっているのではないでしょうか。それで、最初は精神科医のように精神を病んだ人と付き合いながら、患者とデートしたり、セックスしたりして、のめり込むように自分も病んで行く。そういう記録が書かれているのかなあと思いました。
集合的無意識で繋がりたい
助川 ただ古井由吉自身が盛んに書いているのは、集合的無意識みたいなもので繋がり合いたいんだということなんですね。だから、たぶん外を全部、削ぎ落として内面を描く、二人の男女の対を描くことによって、ある種の集合的無意識みたいなところに繋がっていこうとしているのでしょう。完全にこれは新世紀エヴァンゲリオンの世界だと思います、普通にコミュニケーションをするんじゃなくて。個人の内面に閉じこもることによって逆に人類が全部繋がっていくみたいな。そういう線を狙っているんだと思います、古井は。
重里 難しいことがいろいろあるのですね。ただ、フツウに読んでいると、なぜ外へ行かないのか不思議ですよ。いい若い者が、外を忌み嫌っている。おそらく、外へ行くのが嫌なんだろうなと思うわけです。それは一向に構わないのです。外が嫌いな若者もいるでしょう。引きこもりたい人もいるでしょう。そういう小説があっても、全然、構わない。だけどその理由を作者は書いていないですね。読者に目配せもしない。アプリオリな前提として、外を嫌っているわけです。隠し味にしているのです。分かる人には分かるだろう、ということなのかなと思いました。そこは読者との共犯関係で成り立っている小説です。
助川 外に行きなくない理由としては、やっぱり、あれなんですか。政治から逃走しているということですか、この時代の。
重里 外が嫌なのでしょう。よほど、外が嫌いなのでしょう。
助川 大学生で外を見ると、学生運動の末期ですね、これ。書かれているのが。そういうところから逃走しているっていうことをおっしゃっているわけですか。
重里 そう考えるのが妥当でしょうね。だけどそれは書いていないのですよ。描かれていないのです、そのことは。だから想像したり、推測したりするしかないのですが。ただそう思わざるを得ないですね、これは。よほど外が嫌なのだろうって。
助川 ある意味、高橋和己の裏返しなんじゃないですか。作中人物レベルでいえば、指摘されていることはいえると思うんです。小説の方法としていうならば、その学生運動の現実にナマに関与しないで、内側に入り込むことで、逆にその学生運動が終わりつつある日本の現実みたいなものの共通の根っこを掘ろうとしているといえるでしょう。とても民俗学的ですね、この初期古井はね。
『妻隠』だってそうだし、このあと『聖』とか『栖』とか、すべて民俗学的な要素を指摘できますね。
重里 『杳子』の二人はなぜ、山で知り合ったのでしょうか。山にも、民俗学的な意味があるのでしょう。山って何なんですか、日本人にとって。
助川 やっぱり、異界ですよね。平地では出会えないような魔性のモノとか、そういうものと出会う。そういう伝統なんだと思いますよね。
重里 泉鏡花の『高野聖』みたいですね。
助川 そうです。もう一つは、この時期の古井、初期の古井というのは、硬いものが柔らかいとか、どん底が高所恐怖症を呼び起こすとか、イメージのうえでは、そういう逆転の論理を持ってきますよね。それで、この逆転の論理を使うときに、山というのは硬い岩があり、高い際立ったものがあるから、低いところで感じる高所恐怖症だとか、あるいは岩がにじみ出て自分の方によって来るイメージとか、とても書きやすい場所ではありますよね。
重里 場所の話をもう一つします。二人はなぜ、公園でデートをするのでしょうか。場所だけをみていくと、山、公園、喫茶店、旅館の一室、杳子の家ということになっています。公園というのは、山と旅館の間にあるものなのでしょうね。
助川 そうでしょうね。
重里 自然と都市が日常的に混淆している。
助川 模造された自然というか。山の中で見つけてきた女性と、もう一回山の中であったことを都市の中で擬似的に反復するということなのではないですかね。
重里 もう少し杳子を魅力的に描くことはできないのでしょうか。そうしたら、「彼」の独特な恋愛にもっと説得力が出るのだと思います。なぜ、「彼」が杳子に惹かれるのかわからないですね。ほんのちょっとしたディテールでもいいから、杳子の魅力を描くことはできないのでしょうか。何が「彼」の性欲を刺激したのでしょうか。
助川 いやこれはね。私は思いますけど、古井はものすごく力量のある作家ですよ。だけど、重里さんがおっしゃっているような線は敢えて避けているんじゃないですか。「もうちょっと杳子を魅力的に書けるのじゃないか」というのはリアリズム小説に対する見方ですよね。古井はリアリズムで書いていないと思います。
実験小説で書いている。私もこれを読んで思ったのは、言語技術と作品構成の手腕はすごいけれども、結局は学者の書いた小説だなと思いました。要するに頭で構図を作って書いている小説です。そういう意味では評論家的な小説だと思いました。
重里 私はこの小説を五回くらい読んでいます。それも十代のころから今に至るまで四十年以上かけて繰り返し読んでいるわけです。それで、外に何かがあって、それを避けているのが隠し味になっているというのと、杳子をもう少し魅力的に描けなかったのかな、というのは、今回も感じました。
ツッコミだけでボケのない小説
助川 それはおっしゃる通りだと思います。古井には、何とか民俗学的要素を使って、ある種日常的な価値観を反転させて、それで内側を深く掘ることで共通の社会的な根みたいなところに行こうというのが戦略としてあったのだと思うんです。それで書いていって、でもやっていても届かないところが出てくるのはなぜかといった時に、簡単に言っちゃうと、この対談で何度も出てきていますけれど、古井はボケとツッコミでいえば、完全にツッコミの資質で小説を書いているわけです。
どこもボケていない。どうすれば俺はボケられるのかと考えた時に『仮往生伝試文』のような方向に行ったのかな、と思うわけです。古典テクストと対話しながら書いていくみたいなところで、そこでテクストの世界から現実に戻ってきて、往還するとその両方の世界がぐちゃぐちゃになってきて、書いている私がボケてくるわけですよね。そのボケとかブレとか、古典的なテクスト読んでいる私と、現実に生きている私の間のブレの間にちょっとボケが作れるんじゃないかな、と考えて、たぶんそっちに行ったんだと思いますね。
重里 『杳子』の文体というのは、その濃密さが感触として伝わってきますね。それが魅力的なのは、よくわかります。
助川 ブロックで積み上げたみたいな、テコでも動かないような、どっしりしたものをズシズシと持ち上げてくる安定感のある文体ですね。突飛な例えかもしれないけど、谷崎に似た資質を感じますね。古山高麗雄のような、飄々と流れていく文体とは全然違う。ガチ、ガチと構築していく文体ですね。
重里 古井は若い作家たちに大きな影響力を持っていました。二〇二〇年に亡くなりましたが、その存在感の大きさを実感しました。
助川 私も亡くなった時にいろいろと考えました。生きている時は、本当にリスペクトしていたんですよ。だけど、亡くなってみた時に、他の実作者としては、存在すること自体ですごく助かる作家だったんだと思います。
重里 後輩の作家が、先輩にこういう実作者がいることで助かった?
助川 ものすごく頭の良い人だし、小説技術に関して一生懸命考えていた人だから、たぶん後輩から見ると自分が試みたことを全部きちんとわかってくれて、技術的なことも全部お見通しの先輩、っていう感じがあったのだと思います。私もそういう点をすごく尊敬していました。ただ、作品として幅広い多様性があるのかと言われた時に、高い峰ではあるけども、裾野がどこまで広いのかなと考えた時に、それはそこまでの裾野はなかったのかもしれません。
古井由吉の代表作は
重里 古井の代表作は何だと考えますか。一つ挙げるのは難しいですか。
助川 難しいですね。古井の作品は、民俗的なものが出過ぎると、ちょっと図式的になる危うさがあるんですよね。『野川』とか『辻』なんか、ちょっとそういうものを感じたりもしました。
重里 なぜ、民俗学に寄っていくのですか。
助川 やっぱり、集合的無意識とか、文化伝統とかに繋がりたいという欲求がものすごく強い人ですね。
重里 それは日本人の集合的無意識でしょうか、人類の集合的無意識でしょうか。
助川 日本人だと思います。
重里 それでは、そこに天皇とかも入っているわけですね。
助川 だと思います。古井は西洋古典にも通じていたし、ラテン語もできた人でした。何人かが、古井のベストとして、『詩への小路』という西洋の詩を論じた本を挙げていました、私もあれはものすごくいい本だと思います。詩は結局、民族的なものとか、神話的なものに繋がってきます。ただ、自分の作品の中ではあんまり洋物は出さないで、ずっと日本の古典と日本の民俗学ですよね。結論として、この『杳子』は古井の最高傑作とはいえません。『杳子』は十分魅力的な作品ですが、古井は後年、もっと高いハードルを飛ぼうとした小説を幾つも書いています。
重里 ただ、芥川賞作家が亡くなると、ジャーナリズムはついつい芥川賞受賞作を三つか四つの代表作のうちに入れてしまいますね。
助川 入っちゃいますね。だったら、『この道』でもいいし、連作短編集の『やすらい花』でもいい。あるいは『槿(あさがお)』の方が面白いかもしれないし。本当に難しいですね。谷崎みたいな方向に行こうと思えば行けた人だと思うんですよね。難しいですね。