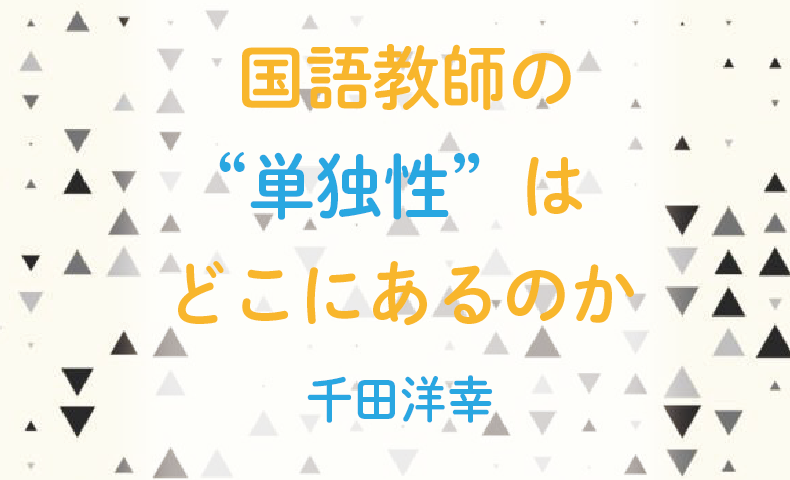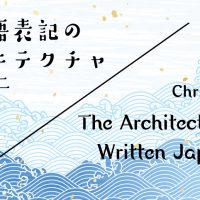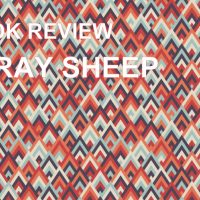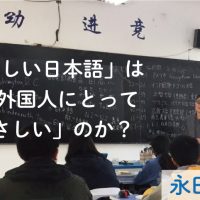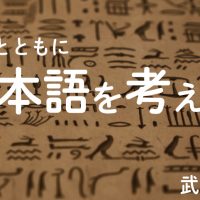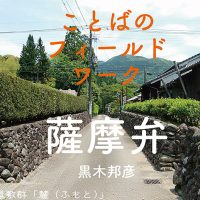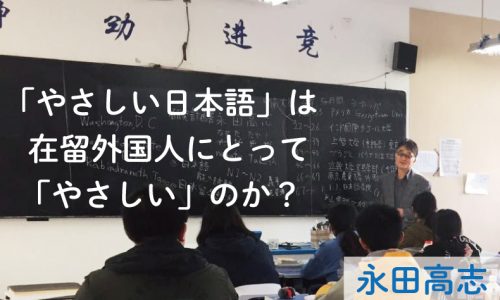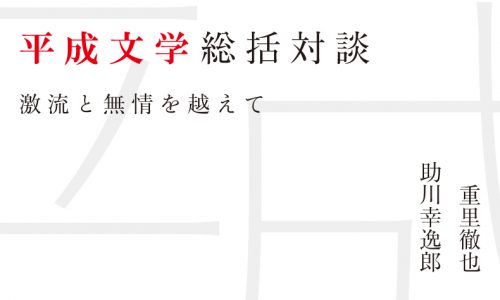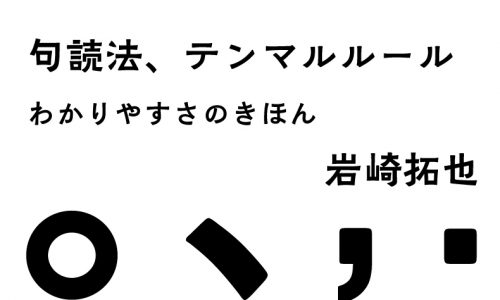「読むこと」の学習に誤読はつきものだ。大方の国語教師は学習者の誤読に日常的につきあわされているだろうし(時にはそのために授業の方向が大きくずれたりもする)、またその頻発に悩まされてもいるだろう。主要な「読むこと」教材について、小・中・高校生が犯した誤読を全国の実践者から収集し、1冊の本に仕立てたらさぞ興味深い著書ができあがるにちがいない、などと夢想したくなる。
個々人の読解・読書の歴史はそのまま誤読の履歴でもある。正読/誤読の境界は文化的・社会的に(そして教育的に)構築されるともいえるが、弁解の余地がないリテラル(字義的)な水準での誤りも時には発生してしまう。私は小学校高学年のころ、高村光太郎「道程」と出会ったが、「僕の前に道はない/僕の後ろに道は出来る」という冒頭の詩句を「自分の行く手にもう道はないから、後ろの道へ退却していくしかない」というまったく逆さまの意味に解釈していた(そういう致命的な誤読にもかかわらずこの詩にいたく感動してしまったのは、我ながら摩訶不思議というほかない)。「レモン哀歌」の冒頭は「そんなにもあなたはレモンを『持』っていた」、梶井基次郎「檸檬」の冒頭は「えたいの知れない不吉な『魂』が……」だとしばらく思いこんでいて、なんと大学生になってからようやく読み違いに気づいた(いまでいう「空目」である)。つい十年ほど前も、「舞姫」の考察のなかで、エリスが豊太郎を父親の遺体が安置してある部屋に招き入れたというひどい間違いを書いてしまっている(映画版『舞姫』のイメージが脳裡にあったか、あるいはアクロバティックな解釈を好む悪癖が作用したものであろう)(注1)。文学あるいは国語教育の研究者・実践者にとってこうしたミスリードは恥辱を意味するので、正直に語られることはまずないが、じつは研究者とか教師と呼ばれる立場になっても、誤読と完全に縁を切ることはなかなかむずかしいのだ。
一方、字義レベルの誤読とは異質な水準で、誤読の創造性に着目する研究、批評も存在する。著名なところでは、ハロルド・ブルーム『影響の不安』(1973)『誤読の地図』(1975)が、先行文学者を後続文学者が超え出ていく方略としての誤読(という名の格闘と創造)に着目している(注2)。入不二基義『哲学の誤読』(注3)は、大学入試に出題された哲学の文章がさまざまな誤読に曝されていく様相をあきらかにし、そこから原テクストを逆照射するユニークな試みを行っている。山内史朗は、「哲学史とは真理の探究の歴史とも言われるが、誤読の歴史と言うこともできる」「真理は無数の誤読を惹起し、招き寄せる。真理はそれを可能にする地平や条件の上にのみ咲く」「哲学とは誤読への勇気なのである」とのべる(注4)。ここにあるのは、誤読に積極的な意義を見いだすことによって文学あるいは哲学の歴史をあらたに書き換えることができる、という認識である。
文学史あるいは哲学史という大きなフィールドにかぎらず、国語教育学の領域においても、学習者の誤読をポジティブな行為として読み直す研究が行われている。いくつか例をあげるなら、「〈誤読〉が積極的な意味を帯びるのは、それが既存の価値観を揺さぶる時である」「一次的テクストとしての教材の力に対立するもうひとつのテクストの力を具えているものとなり得ているとき、〈誤読〉は教室に読むという〈出来事〉を誘うための力強い媒体となる」とのべる山元隆春の論(注5)、実践での試みを通じて「誤読をめぐっての読みの対立や交錯が学習者相互、学習者と教師の間でなされることにより、学習者とテクストが、向き合い、ある意味対等な読者として、互いの物語をていねいに確認し合う過程になる」との認識を示す稲井達也の提言(注6)、宮沢賢治の詩「高原」の冒頭を「海より山がいい」の意味ととらえた学習者の読み(いわゆるうなぎ文としての読み)に「推論解釈の多様性」という問題を見いだす難波博孝の論(注7)などがある。学習者の誤読を、たんなるつまずきとして否定や修正の対象とするのではなく、それ自体をリテラシー向上に貢献する価値ある経験としてとらえる視点は、むしろ常識にちかいともいえる。
ただし、ここですこし考えてみたいのは、授業の場で学習者から提示される誤読を、授業者の立場からどう「読む」か、という問題である。
教育実習で「ごんぎつね」を担当した学生から、こんな報告があった。第2場面のふり返りの際、ある児童から「ごんはおじいちゃんだと思う。『わし』って言ってるから」という発言があったのだという。
ごんは本文中で「ひとりぼっちの小ぎつね」と表記されており、たんなる小さい狐と見なされなくもないが、その思考と行動のあり方から、子どもにちかい(幼児性を内面にかかえた)狐と考えられている。すくなくとも「おじいちゃん」でないことはたしかなのだが、授業者としてはこの解釈をどう扱うべきだろうか。
ごんは基本的に「おれ」の一人称を使用しており、「わし」と名乗るのは第2場面、「ところが、わしがいたずらをして……」の一か所のみである。この「わし」の一人称は、草稿での「自分」から修正されている微妙な部分でもあり(注8)、なぜこの一節のみイレギュラーな人称が用いられているのか、明確な理由を探りあてることはむずかしい。
ただ、「わし」の使用に年かさの人間の語りの陰を見いだす学習者の思考が誤りであるわけではない。「おれがくりや松たけを持っていってやるのに、そのおれにはお礼を言わないで、神様にお礼を言うんじゃあ、おれは引き合わないなあ」というよく知られた言葉が明示するように、そもそもごんは人間からの承認欲求に囚われている狐である。そういうごんが、自身を人間の領域にすこしでも接近させるために、「わし」という大人びた人称を用いているのではないか――このような解釈が成り立つとすれば、この児童の発言はけっして的外れとはいえない。もし私が授業者だったら、ごんの人物像を読み解いていく過程でこの発言にふれ、授業の文脈に生かすことを考えるだろう。
これはわかりやすい初歩的な事例であるが、要するに、学習者の誤読をどう読み、授業の場に位置づけるかということは、教師の教材研究の精度と方向性にかかっているということだ。「ごんぎつね」を、動物の思いと人間の思いがすれ違うメロドラマとしか読めないようでは、授業を活性化させる可能性をはらんださまざまな学習者の発想を見落としてしまう。逆に、読みの強度とバリエーションを備えた教師であれば、学習者の発言の価値を即座に判断し、これを効果的に授業の文脈に位置づけることができる。結局、読解力をもつ教師でなければ学習者の読解力を育てることができない、という身も蓋もない当たり前の結論にいたるのだが、誤読の扱い方もむろんその例に漏れないのである。
ところで、「ごんぎつね」の誤読といえば、以前に論議の的となった石井光太『ルポ 誰が国語力を殺すのか』(注9 )のエピソードが想起されるかもしれない。この著書の認識そのものはともかくとして、誤読の扱いに関する格好の話題を提供してくれているともいえるので、あらためてその部分を引用してみよう。
授業で取り上げたのは、ごんが兵十の母親の葬儀に出くわす場面である。そこでは、兵十の家に村人たちが集まり、葬儀の準備をしているシーンが描かれる。家の前では村の女たちが大きな鍋で料理をしている。作中の描写は次の通りだ。
〈よそいきの着物を着て、腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが、表のかまどで火をたいています。大きななべの中では、何かぐずぐずにえていました〉
新美南吉は、ごんが見た光景なので「何か」という表現をしたのだ。葬儀で村の女性たちが正装をして力を合わせて大きな鍋で何かを煮ていると書かれていることから、常識的に読めば、参列者にふるまう食事を用意している場面だと想像できるはずだ。
教員もそう考えて、生徒たちを班にわけて「鍋で何を煮ているのか」などを話し合わせた。ところが、生徒たちは冒頭のように「兵十の母の死体を消毒している」「死体を煮て溶かしている」と回答したのである。
当初、私は生徒たちがふざけて答えているのだと思っていた。だが、八つの班のうち五つの班が、三、四人で話し合った結論として、「死体を煮る」と答えているのだ。みんな真剣な表情で、冗談めかした様子は微塵もない。この学校は一学年四クラスの、学力レベルとしてはごく普通の小学校だ。
おそらく私にとって初めてのことなら、苦笑いして流していただろう。だが、似たような場面に出くわしたのは一度や二度ではなかった。
私は著述業をする傍ら年間に五〇件ほど講演会を引き受けており、子供をテーマにしたノンフィクションや児童書を数多く手掛けていることから、依頼の三割は学校をはじめとした教育機関だ。そのため、この十数年ほぼ毎月、全国のいろんな教育機関を訪れ、実際に授業に参加させてもらったり、教員や保護者と語り合ったりしているのだが、たびたび同様のことを目撃していたのである。
とはいえ、授業に口出しするのも憚られるので、毎回私はその場にいた教員と「困りましたね」と笑って済ませたり、聞こえなかったふりをしてやりすごしたりしていた。だが、この時の授業では、生徒たちから出ていた意見があまりに現実離れしていたこともあって強烈に頭に残り、それまでの体験との関連性を考えずにはいられなかったのである。
石井の著書は、こうしたさまざまな事例を「国語力崩壊」の危機的状況と見なし、青少年の社会性・倫理観の欠如や教育格差の現状を追求するための根拠としているのだが、各事例の解釈もそれを社会的な問題に敷衍する手法もきわめて単調かつ浅薄な水準にとどまっており、ここでわざわざ取りあげるには値しない。ただ、文中で紹介されている誤読のケース(実在した授業であることが前提となるが)についてのみ、ふれておくことにしよう。
そもそも、「ごんぎつね」の葬儀の場面に関し、4年生児童が「兵十の母の死体を消毒している」「死体を煮て溶かしている」と読んだところで、それを重大事と見なす必要などない。これは当該教室を観察したわけではないので推測で語ることになるが、ながい人生の遍歴をいまだもちあわせない児童にとって、物語内に布置されている「そうしき」とか母親の「死」といった記号は、実体をともなわない空疎な文字の羅列にすぎず、大人読者とおなじレベルの認識を前提とすることがそもそも誤りなのである。さらに現代の児童は、身内や近隣の住民が集まって料理を作り、参列者に提供する村落共同体の葬儀の習慣などほとんど知らないだろうから、この場面を想像的にイメージすることもむずかしい。1932年に発表されたテキストを読み解くためには相応の注釈的知識を動員する必要があるが、それは4年生の学習者にとって簡単なことではないのだ。
ならば、さきのような誤読(そもそも「鍋で何を煮ているのか」を話し合わせること自体が不可解なのだが、その疑問はとりあえず措く)はたんなる未熟な解釈として片づけておけばすむのだろうか。もちろん、村の葬儀について紹介する視覚的資料を導入するなどして学習者の思い込みを修正しておく必要があるが、一方では、「ごんぎつね」における村落共同体の意味・役割を話題にすることができる好個の機会でもある。兵十が村落共同体の一員である以上、ごんが想像していたような「ひとりぼっち」とはかならずしもいえないこと(その意味で兵十とごんの位置は対照的でもある)、ごんの死後に彼の物語が営々と語りつがれていく背景には、ごんをめぐる出来事を共同体内に回収しようとする意志が働いているであろうこと(注10)など、「ごんぎつね」の物語世界はこの問題と切り離すことができない。後者の解釈は文学研究的な発想をふくんでいるので4年生にはすこし難解かもしれないが、「ごんは死んでしまったけれど、村の人達は物語をずっと語りつづけて、昔は邪魔もの扱いしていたごんをもう一度村に迎え入れようとしている」というような言い方であれば、ある程度の理解は可能ではないだろうか。いずれにせよ、我々にとっては突拍子もないと思われる誤読にすら、授業にとって有効に作用する契機がはらまれているかもしれないことを、教師は心に留めておくべきだろう。
ついでに、時おり議論となる「ごん生存説」にもふれておくべきだろうか。ネット上ではこの問題に関する投稿が山ほどあり、現職教員からもこの話題を耳にすることがある。遠藤真司の調査(注11)によれば、教員57名、大学生33名を対象にアンケートを実施したところ、ラストシーンでのごんが「死んでいない」「死んだとは限らない」とする回答者の比率は前者が28%、後者が55%に及んだという。スモールサンプルでの調査とはいえ、さすがにこの比率は高すぎるのではないかと思うが、ごんは生きている(かもしれない)と読む読者が一定数存在することはたしかなのだろう。ごんが死んだという直接の記述がない、救いのある結末であってほしい、兵十に殺生の罪を負わせたくない……など、いくつかの理由が推測される。あるいは、旧版の光村版教科書で使用されていたかすや昌宏の絵(図)が、「傷つく生身の身体を持たない」(注12)フラットなキャラクター性を志向する表現であることも、ごん生存のイメージを強化する役割を果たしているのかもしれない。
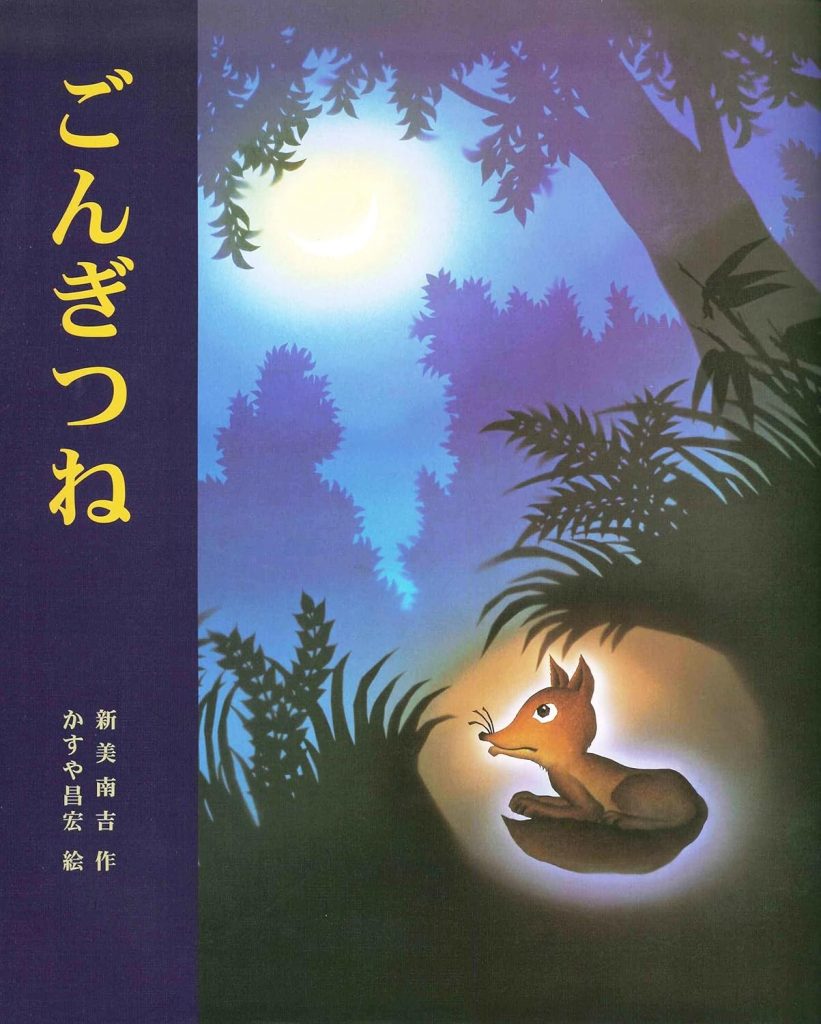
私自身は、「ごん生存説」など許容する気はまったくない。ごんが生きているという読みは、ごんの前に立ちはだかる兵十=人間の冷酷な他者性、主人公の生命の有限性、自分の好意が相手に届かないばかりか逆に厳しい処罰となってはね返ってくる絶望……等々、「ごんぎつね」の教材価値を形づくっているラディカルな要素をほとんど無化してしまう愚挙にほかならないからである。ごんは死なないでほしい、などという甘えた読みが教室内で発生したら、ただちに授業者としての権力を発動し、幼稚な読み方をするなと抑圧するにしくはない。(かりにこの読みに価値をもたせられるとしたら、それが発生してしまう理由をメタ的・読者論的に分析する場合のみであろう。)なんらアクチュアルな効果をもたらさない誤読、教材を扱う意義それ自体を矮小化してしまう誤読は、読解力の向上をめざす授業の障害にしかなりえないのだ。
* * *
すべての学習者には教室で誤読する権利があり、一方、授業者には学習者の誤読の有用性、可能性の如何を判断する責務がある。誤読の発生は、教える側にとって現実的には頭の痛い問題ではあるが、そこでどのような介入をすべきなのか、国語の専門家としての手腕の見せ所でもあるだろう。学習者から誤読が飛び出したその瞬間、事前の教材研究・授業準備は十全であったかどうか、その場での瞬発的な対応を的確になせるかどうか、教師にとって必須といえる二種の力量がまさに試されるといえるからだ。
(注1)千田洋幸「文学教育のリストラクチャー・序説」(『東京学芸大学国語教育学会研究紀要』12号 2016.2)。ちなみに映画版『舞姫 Die Tanzerin』(1989年公開)には、豊太郎がエリスの父親の遺体に祈りを捧げるシーンがある。
(注2)ハロルド・ブルーム『影響の不安――詩の理論のために』(小谷野敦・アルヴィ宮本なほ子訳 日本語訳2004 新曜社)。『誤読の地図』は日本語訳されていない。
(注3)入不二基義『哲学の誤読――入試現代文で哲学する!』(2007 ちくま新書)。
(注4)山内史朗『誤読の哲学――ドゥルーズ、フーコーから中世哲学へ』(2013 青土社)。
(注5)山元隆春「読むという出来事を誘う力――〈誤読〉の豊かさについて――」(『日本文学』1996.1)。
(注6)稲井達也「文学作品の読みの授業における誤読という出来事」(全国大学国語教育学会『国語科教育研究 第114回茨城大会研究発表要旨集』2008.5)。
(注7)難波博孝『母語教育という思想――国語科解体/再構築に向けて』(2008 世界思想社)。
(注8)この部分もふくめ、「ごんぎつね」の本文確定に関しては、府川源一郎『「ごんぎつね」をめぐる謎――子ども・文学・教科書』(2000 教育出版)その他を参照。
(注9)石井光太『ルポ 誰が国語力を殺すのか』(2022 文藝春秋)。
(注10)鈴木啓子は、「ごんぎつね」の語りについて「この世に遺されたものとしての「人の側」の位相から、この世の外の「神の側」の位相へと転位し、本来「人」には知り得ないはずの「神」「死者」の声を一人称的に語っている」と解釈し、そこに「日本の伝統的な鎮魂の文学の、ひとつの特質」を見いだしている(「『ごんぎつね』の引き裂かれた在りよう――語りの転位を視座として――」田中実・須貝千里編『文学の力×教材の力 小学校編4年』2001 教育出版)。また府川源一郎は、草稿「権狐」について、「「権狐」の話は、茂助爺が「私たち」に伝えようとした共同体の文化遺産なのだ」とし、「茂助爺の語りという行為は、この世から消え去った「権狐たち」に向けた村人の鎮魂歌であり、自分たちの殺生の罪を浄化する祭儀でもあった」と指摘する(注8前掲書)。
(注11)遠藤真司「小学校国語科教材の読み方~文学と説明文の違いから~」(『開智国際大学紀要』17号 2018)。
(注12)大塚英志『アトムの命題――手塚治虫と戦後まんがの主題』(2003 徳間書店)。同書は古典的なマンガ表現論・マンガ史研究であるが、挿絵やイラストの効果を考える際にも有用である。
なお光村図書現行版では「ごんぎつね」の挿絵担当があべ弘士に変更されており、これが今後、学習者の読みに影響を及ぼすことも考えられる。