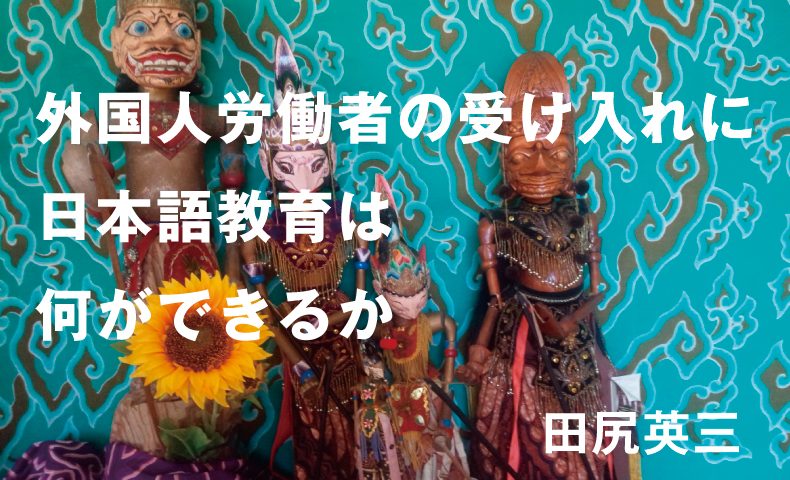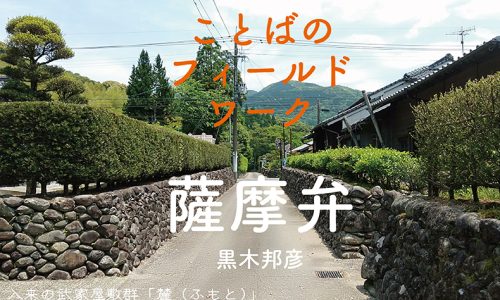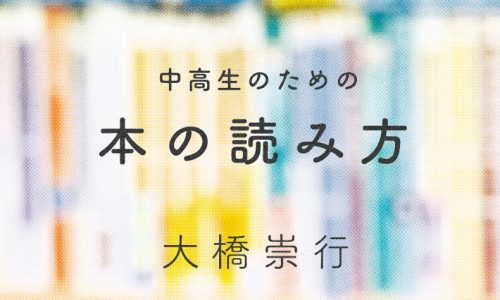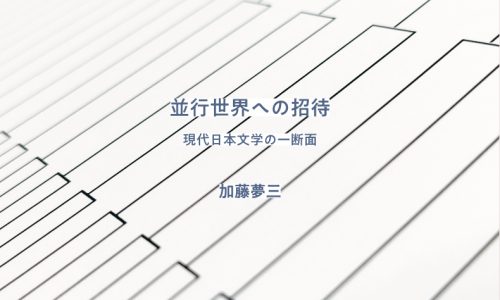★この記事は、2025年7月28日までの情報を基に書いています。
7月20日に参議院選挙結果が出ました。田尻は政治ジャーナリストではないので結果の分析はしませんが、外国人政策がこの選挙の争点の一つになった理由を、日本語教育に関わっている者の視点から考えます。
今回の選挙は、国政選挙としては初めて外国人政策が選挙の争点になった歴史的な選挙でした。その結果、日本人の一定数が外国人について何らかの不満・不安を持っていることが明らかになりました。この点について、日本語教育関係者は注意すべきです。
なお、詳しい選挙結果については、ここでは扱いません。
1. 外国人政策が選挙の争点になるまでの経緯
今回の参議院選挙の争点は、当初物価高対策や消費税値下げなどが争点になると思われていましたが、7月23日朝日新聞3面の見出し「外国人政策 いつの間にか争点」とあるように、選挙後半は参政党の発言を中心に外国人政策が争点化していきました。
マスコミでは、このテーマを扱うときに外国人問題というように、常に外国人の存在が問題と結びつく表現はある種の偏見を生む可能性があることから、外国人政策という表現で統一されました。
田尻は政治ジャーナリストではありませんから、選挙期間中のマスコミの報道を中心にして経緯を捉えます。
参政党の選挙公約が注目されるようになったのは、東京都議選あたりからだという印象を持っています。都議選での参政党の票の伸びの分析が行われ始めたころに、マスコミで外免切り替え・外国人の土地所有・500万円での「経営・管理」ビザ取得等々の問題が取り上げられるようになりました。そのあたりから参政党が外国人政策を選挙の争点に取り上げるようになりました。Xでの外国人関係の投稿が増えたのは、7月11日以降ということです。都議選での参政党の選挙公約では、外国人政策は6番目の「外国人の不正・犯罪の取締まり」という漠然としたものでした。参議院選挙の公約でも、「4. 国防・外交」の中で「外国人に関する諸問題を一括して取り扱う『外国人総合政策庁』を設置」があり、参政党の公約のトップではありませんでした。選挙期間中に参政党の重点項目のような動きになりました。残念ながら、この時期に外国人政策を取り上げたことは、参政党の選挙戦略のうまさと言えるでしょう。なぜ外国人政策がマスコミを含めたテーマとなったかについての私見は、後で述べます。
その参政党の動きに合わせるように、他の政党も外国人政策に言及し始めました。
自民党は外免切り替えの厳格化、国民民主党は外国人の社会保険の見直しなどを主張し、公明党も外国人政策でのルールの厳格化を言い出しました。15日に出された公明党の「党声明」でも「多文化共生社会の土台は、『安心・安全』の確保です」とあり、田尻には従来の外国人との共生社会実現に最も熱心であった従来の動きとは少し違うように感じました。このような場合には、公明党の声明のインパクトは弱まるかもしれませんが、厳格化と言わずに適正化と言ってほしかったと思っています。
参政党の外国人政策で言及している点の多くは間違いであったという指摘が相次ぎましたが、むしろ参政党はそのバッシングをエネルギーに代えて、票を伸ばしました。比例区での得票数の順位は、自民党、国民民主党、参政党、立憲民主党。公明党、日本維新の会などの順となっており、参政党は第三位につけています。これだけの得票数をあげたことの意味を重く受け止めなければいけません。この動きは、今後の外国人との共生の在り方にも影響を与えかねません。
2. 外国人政策が参議院選挙の争点の一つになった理由を考える
外国人がテーマとして扱われる時に、インバウンドの外国人旅行者や日本の土地購入をしている外国人と、労働者として滞在している在留外国人を一緒に扱っていることは、問題です。
インバウンドで多数入国している外国人のマナーの悪さが気になるのなら入国を制限すればいいのですが、それでは観光で生計を立てている人が困ることになります。
外国人で日本の土地を購入している外国人が、どの地域にどの程度の土地を購入しているかという詳しいデータはありません。他人名義で購入しているケースもあり、詳しい実態は分かっていません。
500万円で「経営・管理」のビザを取得している外国人についても、具体的な詳しいデータは出ていません。
外国人の運転免許切り替えについては、警視庁がこの件に関してはずいぶん手早く対応をしました。
以上の例は、直接外国人排斥に向かうことには無理があります。
今回の参議院選挙で争点になった在留外国人については、多くの間違ったデータがSNSなどで流されました。移民・難民政策研究者の橋本直子(国際基督教大学准教授)さんたちの正確なデータに基づく発信も、一度間違った情報を信じた人たちには届いていないことが選挙結果から分かりました。
外国人が増えると治安が悪くなるというイメージは、川口市のクルド人問題で増幅されました。実際には、むしろ外国人犯罪は入国数に対して減っているのが現実です。
健康保険料未納についても、実際にはごくわずかであることが報告されています。
住民税未納の問題も、徴収制度が古いままで、在留期間と徴収時期が合っていないために起こることが分かっていますが、総務省が実態調査をする方向で検討が始まっています。
これらの誤解が広まったのは、日本人の多くが在留外国人の状況を知らなかったことが最大の原因だと田尻は考えています。
政府は、人手不足を補うために十分な制度設計をしないまま受け入れを拡大してきました。そして、長期在留しても「移民」とは認めず、「定住」や「永住」という在留資格を与えることで対応してきました。
田尻がここで特に問題にしたいのは、多くの日本語教育関係者がこの件について興味を持たずに日本語教育に従事してきたことです。その状況を少しでも改善するために、田尻は『外国人受け入れへの日本語教育の新しい取り組み』(ひつじ書房)を出版しました。
参政党の神谷宗幣さんは、参議院議員として外国人や日本語教育について数回質問主意書を出しています。そこでは、日本語教師の待遇についても質問主意書を出していますが、今回の参議院選挙ではこのテーマは取り上げませんでした。それに対して、これも以前質問主意書で扱った外国人労働者のテーマを争点化して、多くの票を獲得しました。
神谷さんが外国人政策を争点化できたのは、その背景に日本人の在留外国人への理解不足があったからだと田尻は考えます。
普通の日本人は、コンビニの窓口で外国人をみかけることしかないかもしれませんが、すでに建築、農業、漁業、ホテル等々の現場で多くの外国人が働いていて、その人たちがいないとすでに日本人の生活は成り立たない程度になっているのです。日本の総人口の3%の外国の人たちを日本人は見てこなかったのです。田尻に言わせれば、むしろ見ようとしなかったのです。
外国人受け入れ拡大に反対をしている政党が多くの票を獲得した理由のひとつに、この外国人の現状を見ようとしない日本人の意識があると考えています。
3. 政府の動き
政府は、7月14日に外国人に関する施策を省庁横断で取り組む「外国人との秩序ある共生社会推進室」の発足式を15日に行うと発表し、15日首相官邸で発足式が行われました。この推進室は、内閣官房副長官補(内政・外政)のもとに設置されました。このような部署の設置は以前からも言われてきましたが、今回は実に早い動きだという印象を持ちました。参政党の動きに与党として対応したと考えられます。
石破総理の発足式訓示の要点を箇条書きにします。
- 少子化や人口減少が進む日本が成長型経済へ移行するために、一定の範囲で外国人労働者の受け入れ、インバウンド消費の拡大などは重要である。
- 他方で、一部の外国人による犯罪や迷惑行為、各種制度の不適切な利用など、国民が不安や不公平を感じている状況も生じている。
- 国民の安全・安心の確保は経済成長の前提で、ルールを守らない人たちへの厳格な対応や外国人に関わる現状に対応できていない制度・施策の見直しは、政府の重要な課題である。
- こうした問題意識の下、内閣官房に外国人施策の司令塔として「外国人との秩序ある共生社会推進室」を設置した。
- 取り組むべき課題は、出入国在留管理の一層の適正化、外国人の社会保険料の未納付防止、外国人の土地取得を含む国土の利用管理などである。
- 省庁の枠を超えて連携し、外国人の懸念すべき活動の実態把握、国・自治体の情報基盤整備、各種制度・運用の点検・見直しなどに取り組む。
この訓示によれば、この推進室は「秩序ある」という名目の下、在留外国人の規制を主として担当する部署であると考えられます。「共生社会」という視点はあまり感じられません。
選挙後の政府の下で、この推進室がどのような動きをするかに注目しましょう。
5月23日に出入国在留管理庁から出された「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」に対して、日本弁護士連合会は「国際人権法に反する『国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン』に反対する会長声明」を出しました。
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2025/250722.html
7月15日には、「日本ペンクラブ緊急声明」が出されています。これは、入管行政の問題を扱った『やさしい猫』の作者で、日本ペンクラブ常務理事の中島京子さんの呼びかけで急遽作られたものです。参議院選挙中の外国人への攻撃に反対する声明です。ぜひ読んでください。
参議院選挙の際に、中国人留学生に返済義務のない奨学金1000万円が支払われていて、日本人が不利益を被っているという間違った情報がSNSで広まりました。
この奨学金は「次世代研究者挑戦的研究プリグラム(SPRING)」というもので、2021年に始まりました。博士課程進学を促すためのもので、1年最大290万円を3年間(4年制は4年間)支給するもので、外部専門家による審査を経て決定されています。実際に中国人留学生が全体の3割を占めていますが、決して国籍で優遇されているものではありません。
しかし、文部科学省は6月に支援金290万円のうち生活費に相当する240万円については、支給対象を日本人に限定する方針を明らかにしました。これでは、国籍で差別することを認めることになってしまいます。
日本のいくつかの大学がアメリカでの留学生締め出し政策で進学できない留学生を受け入れるという姿勢と、このSPRINGでの支援限定の姿勢は、ずれているように田尻には感じられます。
7月25日に文部科学省高等教育局参事官付企画係から、「大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示案及び国際競争力けん引学部等の認定等に関する規定案」のパブリックコメントが公表されています。
https://mailmaga2.mext.go.jp/cc/0ylgApwCV0x36K343GE
これは、学部の留学生を増やすための施策で、2026年度からの実施を目指しています。学部の定員の1.15倍までの留学生受け入れを1.20倍まで認めるというものです(入学定員に応じて倍率が異なります)。従来は、この基準を上回ると私学助成金の一部がカットされていました。日本語教育機関に勤める日本語教師にとっては、留学生が受験する大学の受け入れ枠が拡大されるのですから、大いに興味を持ってほしいと思っています。締め切りは、8月24日です。
2025年2月29日の日本総研経済政策レポートに石川智久さんの「内閣官房に外国人の司令塔設置~欧米の失敗から学び、なし崩しではなく、国家分断を回避できる戦略性を持った外国人政策を」があります。
https://www.jri.co.jp/report/economistcolumn/detail/15950/
7月22日には、全国知事会議では、「外国人との受入と多文化共生社会実現に向けた提言」を出しています。
https://www.nga.gr.jp/conference/item/fa3153b6ab4f31add0ba07149897a270_1.pdf
4. 選挙後のマスコミの分析
自民党・公明党の与党が参議院で過半数を獲得できなかった原因の分析が、マスコミなどで盛んに行われています。特に、外国人政策が争点になった理由として、上に述べた在留外国人の日本社会での存在を見えなくしてきたことが背景にあることを触れたものは、管見の限りではありませんでした。
例えば、7月27日の朝日新聞25面(関西版)では、「『日本人ファースト』に共感 深層にあるのは 訪日客増、物価高・・・生んだ外国人嫌悪」にあるように、日本人の日本の現状に不満があることが深層にあるというものが多いのではないでしょうか。田尻の見方とは違うことは、上に述べたとおりです。
同日の朝日新聞26面(関西版)では、人口の2割以上が外国人という群馬県大泉町の現状に触れている大変興味深い記事があります。執筆者は染田屋竜太さんです。
この記事には大変気になる点があります。日系人が「定住」ビザで在留できるようになった入管法の改正を1990年としている点です。これは、誤りです。この入管法の改正は、1989年です。1990年は、改正入管法施行の年です。こんな基本的な間違いが全国紙の署名執筆記事で行われることは、いかに外国人政策が日本人の関心を引いてこなかったかということを証明しているように感じます。執筆者だけでなく、校正にあたった人たちの誰も気づかなかったのです。
1989年は、天安門事件とベルリンの壁崩壊があった年です。全国紙がこの二つの事件の年を間違えるということは、あり得ないということと比較して考えてみてください。
5. 参議院選挙結果で日本語教育関係者に考えてほしいこと
今回の参議院選挙で外国人受け入れ拡大反対を訴える政党が多くの票を獲得しました。今回の当選者と非改選議員全員に外国人受け入れ拡大について共同通信社がアンケートをして、その結果が7月25日に公表されました。「賛成」・「どちらかといえば賛成」を「賛成」とし、「反対」・「どちらかと反対」を「反対」として数えた結果(%)を以下に示します。
| 賛成 | 反対 | その他 | 無回答 | |
| 全体 | 50.3 | 31.3 | 17.8 | 0.6 |
| 自由民主党 | 55.3 | 15.8 | 28.9 | 0 |
| 立憲民主党 | 73.3 | 6.7 | 16.7 | 3.3 |
| 国民民主党 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0 |
| 公明党 | 77.8 | 5.6 | 16.7 | 0 |
| 日本維新の会 | 28.6 | 71.4 | 0 | 0 |
| 参政党 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 共産党 | 51.7 | 0 | 42.9 | 0 |
| れいわ新選組 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 日本保守党 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 社民党 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| チームみらい | 0 | 100 | 0 | 0 |
外国人政策については、政党間で明瞭に差が出ています。この違いは、今後の国会運営に影響を与えると思います。
日本語教師は、日本社会の中で在留外国人に最も近い関係にある集団の一つだと思います。日本語教師は、現在、日本語教育機関に在籍している留学生だけでなく、大学や専門学校へ進学・卒業して、これからも日本で働こうとしている人たちをよく知っているはずです。
その日本語教師が、今回の参議院選挙で広まった外国人への偏見を見過ごしていいのでしょうか。
今こそ、日本語教師が日本に広まった外国人への偏見を無くす社会的な活動をすべきだと田尻は強く思っています。外国人を支援しているボランティア・行政書士・弁護士などの人たちと協力することも大事です。どのような活動をするかは、各自のできる範囲で無理なく、しかし長く続けてほしいと願っています。このままでは、日本人と在留外国人との分断が進んでしまいます。
日本人の大多数が外国語でのコミュニケーションができず、日本に住む外国人は日本語を習得しないと日常生活に支障をきたすという状況が、日本語教師の存在を支えているというおかしな関係についても、日本語教師は自覚すべきです。日本語教師の仕事が、外国人に日本への同化を押し付けているという危険があることに気が付いてほしいと考えます。
6. 在留外国人政策に対する田尻の立場
改めて、在留外国人政策についての田尻の立場を述べておきます。
(1)人権の視点
基本的には、日本にいる外国人は日本人と同様に、その人権は守られなければならないと考えます。難民認定中で拘留されている人も、犯人の可能性のある人も、人権は保障されるべきものです。最近起こっている、中国でのスパイ容疑のために民間の日本人が拘束されている事件のことを考えてみてください。
在留外国人の人権は、マクリーン事件での判決で、外国人在留制度の枠内でしか保証されないことになっていることを知ってください。
田尻は、そのことを理解したうえで、やはり外国人の人権は保障されるべきという考えで活動しています。
(2)日本人の人手不足への対応策としての視点
日本人の生産年齢人口の減少は、歯止めがききません。介護福祉士不足による老人介護の問題、生産現場での人手不足により収益をあげている会社倒産による経済的損失、運転手不足によるバスの減便等々は、最近ニュースになっています。
しかし、ニュースにはなっていませんが、日本の農業・漁業・観光業・サービス業など多くの分野で、日本の社会は外国人労働者なしにはすでに成り立たなくなっている現実があります。
人手不足は日本だけではなく、先進国共通の問題で、すでに労働者の奪い合いも始まっています。日本もその流れに競り勝つためには、外国人労働者の労働環境の整備が急がれます。
外国人は日本の生活習慣を知らないと言う前に、彼らにそれを伝える制度を整備すべきです。ここでは、日本語教師ができることがたくさんあります。むしろ、日本語教師は積極的に関わっていってほしいと田尻は考えています。「生活」分野への日本語教師の参加です。
また、外国人労働者が安定的に長期滞在するためには、家族の帯同も不可欠です。その家族の日本語習得支援も必要な施策です。
外国人児童生徒等への日本語教育だけでなく、外国人の家庭内のヤングケアラーも今後は問題になっていきます。ヤングケアラーはこども家庭庁が担当していますが、その実務者会議に文部科学省日本語教育課は入っていません。
田尻は、在留外国人の施策全般に日本語教育は関わっていかなければいけないと考えています。
7. パブリックコメント「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001431&Mode=0
このパブリックコメントは、6月2日に開かれた第10回日本語教育推進関係者会議で検討されたものを事務局が整理したものです。
この検討内容については、第61回の「未草」の記事で扱っています。
ただ、その回では、まだ言及していない多くの問題点があります。例えば、難民の問題です。田尻は、この点についてあまり詳しくないので、関係者会議では触れませんでした。これについては、橋本直子さんの『なぜ難民を受け入れるのかー人道と国益の交差点』(2024年、岩波新書)という優れた本がありますので、ぜひ読んでください。ただ、この本は難民問題全般を捉えていますので、難民の日本語教育については詳しく触れていません。関心のある方は、ぜひパブリックコメントに意見を提出してください。
青年海外協力隊で日本語教師として参加した隊員のキャリアパスとして、国内の日本語教育体制への組み込みも、ぜひ検討してほしい項目です。
8. 大事な会議
大事なパブリックコメントの締め切りが迫っていますので、その他の大事な情報を詳しく説明する余裕がなくなりました。最低限必要な情報のみお知らせします。
(1)第5回 外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議
7月25日に文部科学省総合教育政策局国際教育課で、上記の会議が開かれました。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/196/siryo/1418919_00005.html
ここで注目してほしいのは、配布資料の中の「資料2 指導体制の確保・充実に関する主な検討事項〈事務局作成メモ〉」です。以下のような項目が列挙されています。
- 指導体制の在り方
集住地域・散在地域における支援の在り方、校内体制の整備 - 日本語指導担当教師の配置やキャリアパス
- 日本語指導補助者(登録日本語教員を含む)や母語支援員との連携
- 関係機関との連携
このような項目について今後この会議で検討されていくので、ここではコメントはしません。
「資料3 登録日本語教員制度について」の中に、1月から始まった登録申請の状況がでています。
合格者11,051人のうち、10,248人が登録申請し、6月2日現在9,418人が登録済みということです。まだ申請していない人の中には、登録の緊急性がない人もいると思います。
8月17日に大阪大学箕面キャンパスで開かれる「政策提言シンポジウム 多文化多言語の子どもの学びの保証―公正な教育の実現に向けて―」の提言2と3はこの会議で検討されることが明らかになりましたので、わざわざ提言する必要もなくなったのではないかと思われます。
(2)第134回 生涯学習分科会
7月25日に文部科学省生涯学習分科会が開かれました。
この会議の配布資料の中の「資料1-1経済財政運営と改革の基本方針2025における主な生涯学習分科会関連記載」に外国人関係の記載が見られます。
https://www.mext.go.jp/content/20250725-mxt_syogai03-000043950_01.pdf
第2章 賃上げを起点とした成長型経済の実現
4.国民の安心・安全の確保
(1)外国人との秩序ある共生社会の実現
ここには、「出入国在留管理の一層の適正化」が出ています。
第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現
2.主要分野ごとの重要課題と取組方針
(3)公教育の再生・研究活動の活性化
ここには、「外国人児童生徒への支援体制の強化」が出ています。
※参議院選挙の結果、衆議院・参議院ともに与党が過半数割れという状況になっています。厳しい外国人政策を取ろうとする政党も、選挙で躍進しました。
比例区の得票結果を見ると、かなりの数の国民が在留外国人への不安・不満を持っていることが明らかになりました。これまで外国人との共生が当たり前のように語られてきた状況も変わるかもしれません。
今こそ、日本語教育に関わる人たちは、同じ思いを持っている他の分野の人たちと協力して、人権意識を持ち、在留外国人なしには成り立たない日本社会の実態を前提に、在留外国人への支援を積極的に行うべきだと考えます。
日本語教育の真価が問われています。