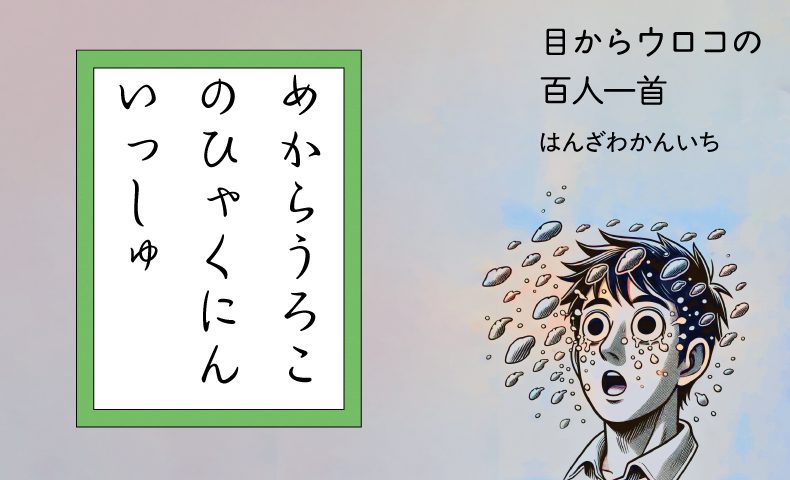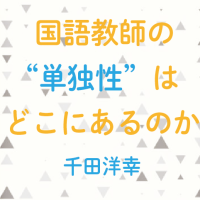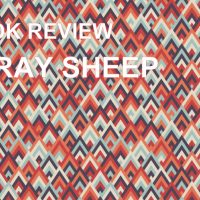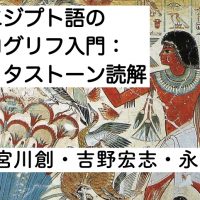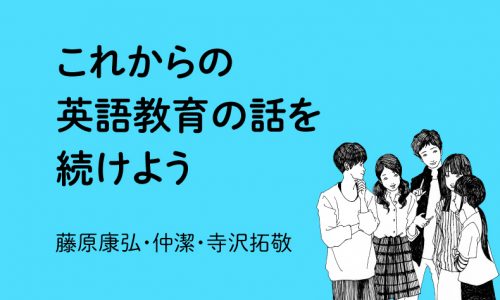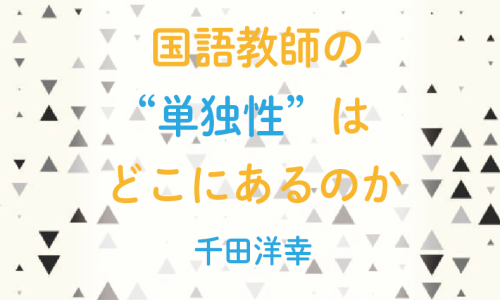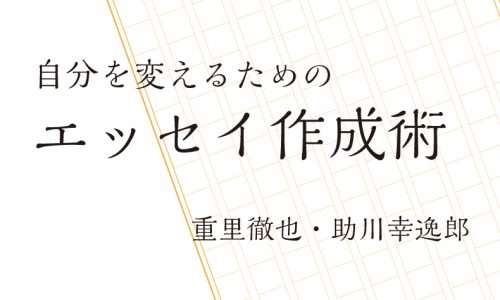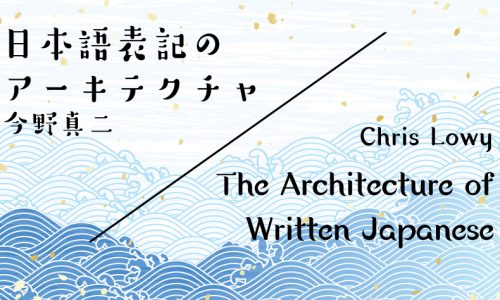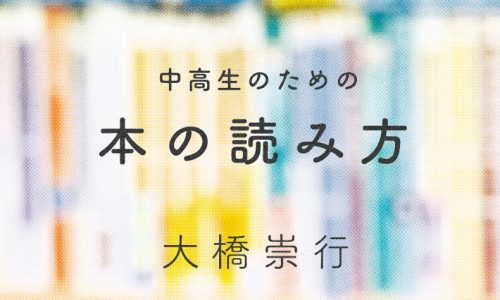天つ風雲の通ひ路吹きとぢよをとめの姿しばしとどめむ
この歌が、五節会(ごせちえ)という宮中儀式の際に、乙女たちが舞を披露するという状況で詠まれたということを知らなくても、天女というイメージは浮かんでくるのではないでしょうか。
もし夢のような天女が地上に舞い降りてきたら、めったにない機会ですから、その姿をできるだけ長く見ていたいという気持ちになるのは、ごく自然なことです。とくに男性なら。
〔ウロコ1〕「天(あま)つ風」
ただの風ではなく、「あまつ」が付くと、地上付近ではなく空高く吹く風ということになります。それだけでなく、7番歌でも指摘したように、「天」は、神様の世界ですから、神様の支配する物は人間の及びもつかない力が発揮されます。風もまたしかりで、人間がコントロールできるものではありません。
〔ウロコ2〕「吹きとぢよ」
そのような風に対して、「吹きとぢよ」なんて人間が命令するとしたら、畏れ多いことです。神様が知ったら、怒り狂うかもしれません。しかし、この命令は、11番歌と同様、あくまでも詠み手の願望を示すための表現です。
「吹きとづ」というのは、この歌のために作られた、臨時的な複合語でしょう。主語はどちらも風で、「吹く」ことと、「通ひ路」を「とづ(閉)」ことを、1語で表わしています。
「雲の通(かよ)ひ路(ぢ)」という表現は、そのままなら、雲が移動する道となりそうですが、この歌では成り立たないので、雲の中にある通り道とするしかありません。それが誰(何)の通路かと言えば、「をとめ(乙女)」つまり天女が天上と地上を行ったり来たりする道ということになります。
こういう設定を認めるには、2つの前提が必要となります。
1つは、すでに雲の間に隙間が見えること、もう1つは、天女の往来はその隙間を通るということです。雲は風に吹かれて移動しますから、風の加減によっては、雲に隙間ができたり、それが埋まったりすることも、一時的にはありえるでしょう。その意味で、前者は現実にありえますが、後者はあくまでも空想です。たまたま雲の隙間が見えたので、そう思い付いただけのことかもしれません。そのような伝説もないようですから。
〔ウロコ3〕「しばし」
「しばし」は、すこしの間という意味です。留まるのはすこしの間でいいから、ということです。これは遠慮でもあり、せめてもの願望でもありますが、それというのも、そもそも天女は地上界に長く留まってはいない存在とみなされていたからです。
とはいえ、この歌が100%空想の歌だったとしたら、「しばし」などと言わず、天女を思いのままにできたはずです。そうでないのは、歌の表現を制約する、詠む時点での現実の状況をふまえているからでしょう。
その状況とは何よりも、天女にも見まがうような舞姫たちの存在です。その様子の素晴らしさをいかに表現するかというところから、このメルヘンチックな歌は詠まれたのです。
あえて言えば、この歌は、その舞姫たちを賞賛する挨拶の歌、リップサービスの歌とも言えます。しかし、挨拶あるいはリップサービスが目的だから、歌としての価値が下がるということには、まったくなりません。なにせ、定家が百人一首に選んだくらいなのですから。
ただし、この歌を詠んだのが僧正遍昭なると、何やら生臭い感じがしなくもありません。江戸時代の川柳にも、「遍昭は乙女に何の用がある」という句があるそうな。