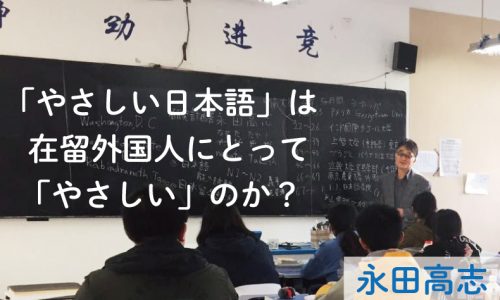渡辺哲司(文部科学省教科書調査官(体育))
本書は、(1) ビジネス・ライティング教本としては読者の“ウケ”がいま一つかもしれないけれど、(2) 実際にビジネス界で生きて働く言葉のわざ(言語技術)を析出した本としてはキラリと光る。そして、(3) 言語技術に関心のある読者(評者のような者)をインスパイアしてくれる。
以上 (1) (2) (3) について、それぞれに1節を設けて順番に、論評していくとしよう。
(1) ビジネス・ライティング教本としては読者の“ウケ”がいま一つかもしれない
――と、そのように評者が案ずる理由は2つある。
1つ目は、列挙された技術的事項の多くが、わりあいと“あたりまえ”のものであること。例えば、横書きは算用数字/縦書きは漢数字(p. 34);言い換え可能な外来語は和語や漢語に(p. 74);抽象的な大きな情報から具体的な小さな情報へ(p. 106);適切な敬語の使用(pp. 153-165)などは、他の類書にもたいてい挙がっていそうな事項だ。その一方、目新しいかもしれないのは、統計に基づく具体的な数字群――タイトルの長さは60文字以内(p. 114);箇条書きの項目数は18個以内(p. 119);空白行は全体の35%以内(p.120)など――だけれど、それらもしょせんは目安にすぎない。つまり、すでに適切な数や割合を「これぐらい」と感覚的に心得ている人はいるし、実際にそのていどの心得でも十分に事足りるはずだ。
そもそも、“あたりまえ”の事項が多くなってしまうこと自体が、本書の場合、原理的にあたりまえでもある。なぜなら、どの事項も、現に世間で生きて働いた実績のある文書群から抽出されたもの――すでに誰かが実際に使って用を為したものばかり――であるからだ。もし仮に、世の中のたった一人が知って/使っているすばらしい技術的事項があったとしても、統計的な分析・処理のなかでは例外、すなわち一般性のないものとして、切り捨てられてしまうだろう。その結果として、あたりまえの事項が多くなることは避けられない。
そうすると、本書の表立っての“売り”(特長)は「10万件」というデータベースの規模(基にした文書の数)ぐらいになる。たしかに、その数字は1人や2人の手ではとうてい扱いきれぬものであり、100件や1000件の文書を基にした本に比べると、結果の信頼性も高そうだ。しかし、そうした特長も、他の類書(より少数の文書を基にしているため信頼性では劣るビジネス・ライティング教本)を何冊かめくれば消失してしまうかもしれない。つまり、文書数の多さだけでは、おそらく、実用書として抜きん出たものとはなれそうにない。
理由の2つ目は、「ビジネス文書」という語でカバーされる文書の範囲が広くないこと。自慢のデータベースがクラウドソーシング(企業による、外部事業者への仕事の発注)文書のコレクションであるため、これまた原理的に、分析結果を適用できる範囲がそのあたり――厳密にいえばクラウドソーシング文書のみ――に限られてしまう。そこから範囲を広げるにしても、せいぜい社内・外にあてたメールや手紙、同僚たちとのチャットぐらいまでだろう。
ところが、もちろん、クラウドソーシング文書がビジネス文書のすべてではない。とりわけ評者にとって気になるのは、企業や各種団体、政府・自治体、地域住民などの間で交わされる、交渉、合意、報告、説明、申し立てなどのための文書群である。それらの文書は、総じてクラウドソーシング文書よりも形状は長大・重厚、内容は厳密・詳細、雰囲気は厳粛・荘重である。そのため、クラウドソーシング文書ではあまり求められない技術的事項(要約のし方、章・節・段落レベルの組み立て、見出し・小見出しのつけ方など)が別して求められる。
そうした(クラウドソーシング文書と近縁ではない)文書群を作成する機会は、ビジネスの現場ではあまり多くないのかもしれないが、そうであればこそ、むしろ作成者たちは大いに苦しみ、優れた教本による助けを切実に求めるのではないだろうか。ひょっとすると、その点を次なる課題――例えば「ビジネス文書の応用・発展技術」――として、すでに本書の執筆(研究)チームは取り組み始めているかもしれないが。
(2) 実際にビジネス界で生きて働く言葉のわざを析出した本としてはキラリと光る
本書は、現に世間でよく機能したクラウドソーシング文書の特徴を、AI(人工知能)を活用して探り、明らかにしたものだ。「世間でよく機能した」とは、この場合、公開されて多くの応募者を集めたという意味である。
実際に生きて働く言葉のわざは、よい文書のなかにこそ表れている――と誰もが直感的・経験的に知っているため、まずは、よい文書を手本とすることが学びの王道になる。古くは江戸時代、寺子屋で作文の教科書として使われていたのも、たいていは「往来物」と呼ばれる書簡集(じょうずな手紙のコレクション)であった。すでにわざを持っている教師・先輩たちの教示にしたがって生徒・後輩たちが学ぶことも、教育方法としては本質的に変わらない。
しかし、そうした学びの王道には(またもや)原理的な限界がある。なぜなら、生きて働く言葉のわざのすべてが一つの手本のなかに表れていることはない(多くの手本のなかに散在している)し、一人が出会える手本の数はたかが知れているし、手本を選ぶ人の目には必ずバイアス(偏りのもと)があるからだ。
そのため、人間がつくるものである限り、完全無欠のライティング教本などというものはこの世に存在し得ない。ある人がある時点で、それまでに集めた手本を基にまとめた教則や教本には、必ずいくらかの偏り(不足や過剰)が含まれる。とはいえ、そうした偏りを完全になくそうとすれば、いつまでも手本の探索をやめられず、一つにまとめることもできない。そこはもう、根本的な限界である。
そうした限界を突破するために、本書の執筆(研究)チームはAIを活用し、一定の成功を収めた――と評者は見る。
AIとは要するにコンピューターであり、その最も基本的な能力は、人間には及びもつかないほどの計算、とくに繰り返し(反復)計算の能力である。AIは、人間とは違って「それは何か」「なぜそれをするのか」といった作業の本質や意味はわからぬままでも延々と、疲れを知らず、迅速かつ正確に「それ」を行い続ける。人間なら気の遠くなりそうな「10万件」さえ、AIにとっては驚くほどの数字ではない。そうしたAIの能力を使えば、膨大な数の手本(よい文書)を集めて吟味することも可能である。そして、吟味できる手本の数が多いほど、そこから引き出される教則、つくられる教本の偏りは小さくなるのが道理である。
つまり本書は、人間がほんらい(原理的・根本的に)持っている弱みをAIの強みで補う――という形での計画的な作業によって、実際にビジネス界で生きて働く言葉のわざを析出してみせたものだ。そして、いまだ類書が存在しない(巻頭言:pp. 3-4)というのが本当であれば、稀有の一冊としてキラリと光る。
◆
ところで、AIによく働いてもらうためにも、その前に、まずは人間のほうで「よい文書」を大量に用意する必要があった――ものごとの良し悪しは今のところ人間にしか判断できない――わけだが、そこで突き当たる壁が、何をもって「よい文書」とするのかという問題だ。将棋の差し手の良し悪しは最終的な勝敗を基に決められるが、文書の良し悪しのほうはそうもいかない。人間は、明確な基準がなくても物事の良し悪しをそれなりに判断できるが、だからといって、少数の人間たちが個々の文書を採点して仕分けるのもあまりよい手ではない。なぜなら、そこには必ず主観(個人的な好き嫌いなど)が入り込んで、バイアスを生じてしまうからだ。
その壁を、本書の執筆(研究)チームは、ある合理的な手段によって乗り越えようとした。すなわち、すでに現実のビジネス界で、一定数の人々の目を通ったうえで、文書としてよく機能することが確かめられたものだけを材料とした。「一定数の人々の目を通」すことによって、いわゆる間主観(主観と主観の間)を積み重ねて客観へ、そしてバイアスの縮小へと近づける。そのやり方は、ひとまず理に適っていると言えよう。
ただし、最後に少々うるさいことを言えば、この場合「よい文書」の基準となり得るものは、応募者の多寡(多い/少ない)の他にもあったのではないか――と評者は疑う。そもそも、多くの人が応募したというだけでは、応募者(受注)側の勘違いや企業(発注)側のミスリードによって多くの人が手を挙げただけの文書を排除できないだろうし(といって、他の基準はなかなか見つからないかもしれないが)……。
(3) 言語技術に関心のある読者をインスパイアしてくれる
ここまで書きつづってきた評者の頭にふと思い浮かんだのは、古代ローマの弁論術教師にして、今日まで西洋社会に受け継がれる言語技術教育の祖ともされる、クインティリアヌスの言葉だ。彼いわく、弁論術は技術であると。技術とは、取り立てて言葉で示せるもの、練習すれば上達するもの、それを学んだ者のほうが学ばなかった者よりもうまく実行できるもの。そして「技術が仕上げたものはすべてその端緒を自然のうちにもっている」のだと[1]。
クインティリアヌスがいう自然とは、本書に当てはめるなら、よいビジネス文書が実際に世間で生きて働くようすである。そのなかで生きて働いている言語技術は、まさに自然のうちにあるがゆえに、人々によって認識されにくい。そうして認識されることなく見逃されてしまった言語技術は、当然ながら、取り立てて教示されることもなく、その代わりに「見て覚えろ」「習うより慣れろ」などといった、学習者を突き放すような指導が多くなる。結果として、自然のうちを見抜けるだけの目も忍耐力も持たぬふつうの学習者たちは、混迷と苦難のなかに陥っていく。
そうした意味での自然のうちを見抜くために、現代のわれわれがとり得る方法の1つを、本書の執筆(研究)チームは示してくれた。それが、AIの活用である。ものごとの意味はわからないけれど膨大な計算を迅速・正確にこなせるAIと、ものごとの意味はわかるけれども少数のサンプルに基づいて偏った判断をしがちな人間。そうした両者の相補的な共同作業は、AIの専門家(熊野氏ら)と言語学の専門家(石黒氏ら)とによるコラボレーションの賜物だ。
そうして生まれた本書によって、言語技術とその教育に関心をもつ評者のような人たちはインスパイア(知的に刺激、あるいは鼓舞)される。なぜなら、そのような人たちこそが、まさに自然のうちに表れているオーセンティック(真正)な技術とその学習・指導法を日夜追い求めているからだ。
欲を言えば、10万件の文書とAIの活用とによって、これまで人間が気付かなかったような言語技術が発見されてほしかった(と執筆チームも思っているに違いない)のだが、それは残念ながら果たされなかったと見える。しかし、それはまたそれで、古代ギリシャ以来2500年にもわたって、ひたすら生身で、言語技術――他者と言葉で情報や感情を伝え合うためのわざ――を探究し続ける人間たちのすごさを証明してくれているようであり、面白い。
注
[1]マルクス・ファビウス・クインティリアヌス著、森谷宇一・戸高和弘・渡辺浩司・伊達立晶訳『弁論家の教育1』京都大学学術出版会、2005年:pp. 208-219

ビジネス文書の基礎技術
実例でわかる「伝わる文章」のしくみ
石黒圭・熊野健志編
定価1400円+税
四六判 208頁
ISBN978-4-8234-1085-7