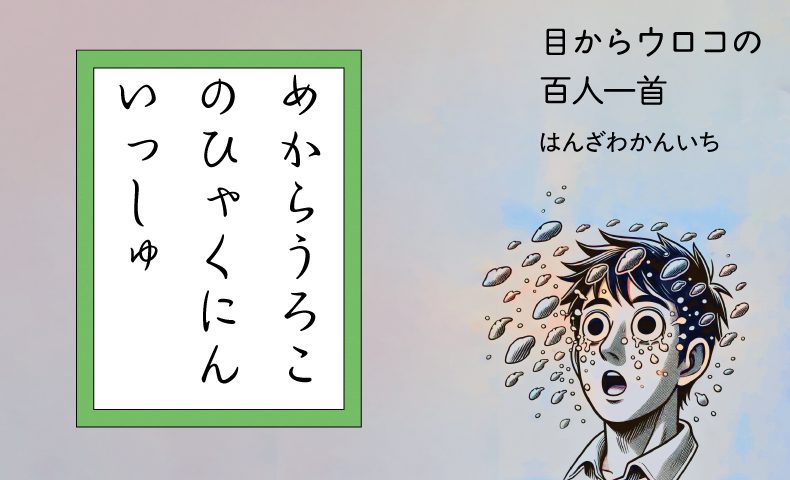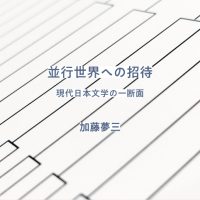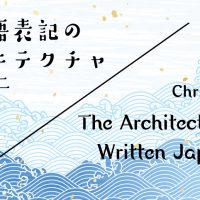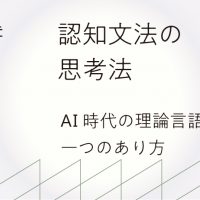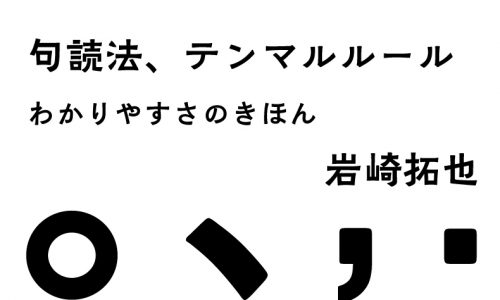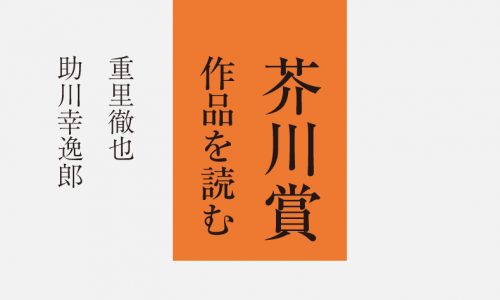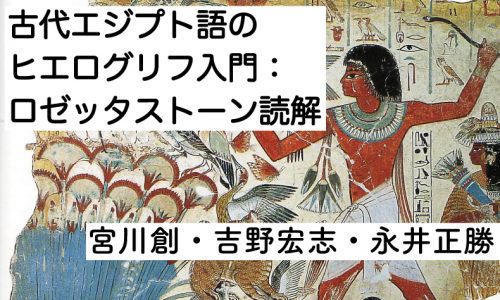浅茅生の小野の篠原しのぶれどあまりてなどか人の恋しき
この歌は、後撰集(巻9・恋一・577番)から採られたものですが、古今集(巻11・恋歌一・505番)の「あさぢふのをののしの原しのぶとも人しるらめやいふ人なしに」を本歌取りした歌とされています。
上三句までが本歌取り、つまりそのままの引用で、下二句がオリジナルということです。このオリジナル部分の、本歌との違いのありようがウロコになります。
〔ウロコ1〕「浅茅生(あさぢふ)の小野の篠原(しのはら)」
この表現は、ほとんどワンセットの表現です。「浅茅生の小野」と「篠原」という野原が別々にあるわけではなく、浅茅や篠がともに生えているような野原一般を表わします。
「浅茅生の」を「小野」にかかる枕詞とする見方もありますが、「浅茅」と「篠」のどちらも植物同士として、篠のほうが浅茅に隠れているという関係と見れば、「しのぶ」というイメージに結び付けやすいでしょう。
どちらにせよ、表現技法としては、この二句までが、第三句の「しのぶ」という言葉を、「篠原」の「しの」との同音反復で導く序詞とみなされています。
〔ウロコ2〕「しのぶれど」
「しのぶ」は、耐え忍ぶの意です。誰ガ何ヲ「しのぶ」かと言えば、詠み手ガ恋心ヲ「しのぶ」、つまりその気持ちを表に出さずに、我慢しているということです。
なぜ忍ばなければならないのか。恥ずかしがり屋だからということではなく、それを相手に打ち明けるチャンスがないからです。本歌の古今集では、「いふ人なしに」とあり、自分のことは棚に上げて、その思いを相手に伝えてくれる人がいないせいにしています。この歌では、原因には触れることなく、「しのぶ」という自分の心境のみを表わしています。
ただ、気になるのは、本歌の「しのぶとも」が「しのぶれど」のように変わっている点です。どちらも、逆接条件の表現としては同じですが、違いは「とも」はあくまでも仮定であるのに対して、「ども」は現実をふまえているというところです。
つまり、この歌は本歌の仮定を現実に置き換えたということになります。その分だけ、恋心のリアリティが増すことになるでしょう。
しかし、それならば、なぜ「しのぶれば」という順接条件にしないのでしょうか。忍んでいるからこそ、恋心は募る、つまり「あまり(余)て」になるのであって、忍ばずにさっさと打ち明けることができたら、気持は収まるはずではありませんか。
〔ウロコ3〕「などか人の恋しき」
「などか」は理由を問う疑問詞であり、理由が問われているのは、「人の恋しき」こと、それ自体に対してです。忍ぶことによって募る恋の度合いに対する疑問ではありません。あらためて、なぜその人を好きになってしまったのかという疑問です。
じつは、「しのぶれど」という逆接のウロコは、このように捉えることによって、きれいに落ちるのです。つまり、「しのぶ」ことの現実の苦しさを、今は余るほどに感じているのだけれど、そもそもそういうことになってしまったのは一体なぜか、と我ながら不思議に思っているわけです。
こういう疑問に対して予想される、ありきたりな答えとしては、誰のせいでもなく、そういう運命だった、でしょうか。しかし、どんな答えが出るにせよ、それによって、恋い忍ぶ苦しさが解消されるわけでもなく、諦められるということにもならないはずですよね。