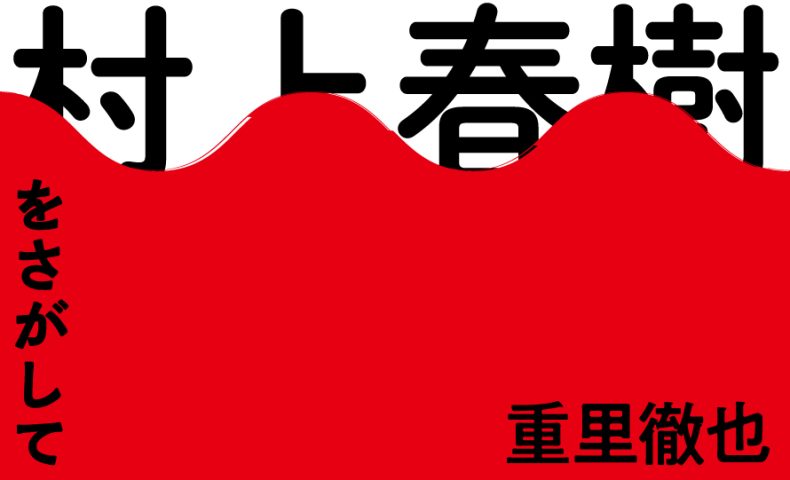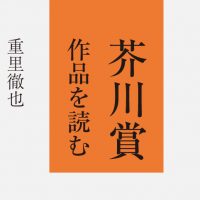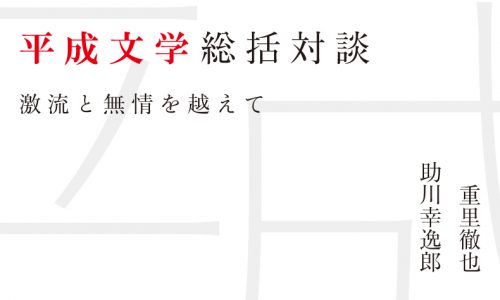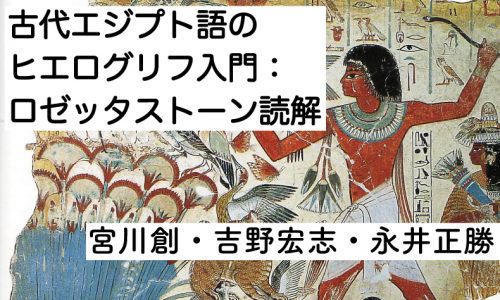人が何ものかにとらわれるとは、どういうことか。何かに憑(つ)かれるとは、どんな状態を指すのだろうか。実は世間にけっこうあることなのではないか。
たとえば、宗教教団や政治セクトの洗脳はその例だろう。神秘思想やイデオロギーは今日もどこかで誰かを獲物にしているのではないだろうか。
拡大解釈すれば、恋愛にだってそういう面はあるし、推し活だって、深刻なものになると、とらわれるという形容をしたくなるものだってあるだろう。そもそも、人間は常識や道徳にとらわれて生きているのではないだろうか。
人間は「自由が大切」だとか言っているわりには、少なくない人が自らとらわれたがる傾向を持っているように見える。自分の判断を放棄して、誰かにマインドコントロールされて暮らすのは、自らの意思で生きるよりも、楽な面だってあるはずだ。
何かにとらわれてしまった人々。その運命を描く小説として真っ先に思い浮かぶのは、ドストエフスキーの長編『悪霊』だ。革命家を自称する連中が悲惨な結末を迎えて自滅する姿は、連合赤軍によるリンチ殺人事件を予言したとも、オウム真理教による数々の凶悪事件を見通していたともいわれる。
大きな事件が起こるたびに、私など、ああこれはドストエフスキーが書いていたやつだな、と思うことが多い。ロシアの文豪が書いた小説を思い浮かべて、事件の当事者を登場人物と重ねることも少なくない。それは、人間という存在がそうそう進歩していないということだろうか。
村上春樹はドストエフスキーについて、しばしば言及している。五大長編の一つである『悪霊』についても、インタビュー集などで名前が出てきて、『カラマーゾフの兄弟』とともに、別格の作品としてリスペクトしていることがわかる。最近、ドラマ化、映画化されて話題になっている短編集『神の子どもたちはみな踊る』では、エピグラフに『悪霊』の一節が使われている。
村上の新作『夏帆とシロアリの女王』(「新潮」十一月号)も人間がとらわれる物語だ。「夏帆」シリーズは『夏帆』(「新潮」二〇二四年六月号)、『武蔵境のありくい』(「新潮」今年五月号)と続いて、今回が第三作になる。主人公が共通した連作で、最終的には何作まで続くのだろうか。
今作では女性主人公の夏帆(イラストレーター、絵本作家)の母親が問題になる。久々に浦和(「さいたま市」という呼び方を夏帆は受け入れられなかったという)の実家に帰った夏帆は、五十代前半になる母親の変貌ぶりに驚く。
服装が随分と派手になった。見るからに高級で凝った作りの下着をつけるようになった。自動車はシルバーのトヨタ・カローラからマダーレッドのレクサスに変わっていた。頻繁に「ランチ」に出かける。化粧も派手になった。もともと美人だった母親だが、若返ったような感じがする。性格も洗練された印象を受ける。
夏帆はこれまでにもアドバイスを受けていた、ありくいの奥さんに相談する。ありくいの奥さんは、シロアリの女王が夏帆の母親に取り憑いたと指摘する。ジャガーの敵討ちをするためだというのだ。ありくいの奥さんが言うには、シロアリの女王は若い女王シロアリとの戦いに敗れ、ブラジルのジャングルから逃れてきたらしい。ジャガーとシロアリの女王は親しい友人関係にあったという。
このことをきっかけに夏帆は改めて、自身と母親との関係を振り返る。自分は母親のことをそれほど好きではないかもしれないこと。一方、母親にとっても、自分を妊娠したことは不本意だったのではないかということ。
母親の半生をたどっておこう。福島県会津若松近郊の地主の娘に生まれた。幼いころは裕福だったが、父親が先物相場で失敗して没落した。地元の短大を卒業し、東京都内の不動産会社に就職した。そこで小児科医の父親と出会った。父親は母親が好きになるタイプではないが、きっと「医師の妻」というステイタスに惹かれたのだろうと夏帆は推測する。しかし、結婚後しばらくして、それは優雅で満ち足りた生活ではなかったことに気づく。でも、夏帆を身ごもっていて後戻りできなかった。
この物語のクライマックスは最後の方に用意されている。夏帆が、母親に取り憑いたシロアリの女王と対話する場面だ。問い詰める夏帆に対して、シロアリの女王は言う。異様に心に残ったので、引用しておこう。
あんたのお母さんはといえば、あたしと一体になったことで、長期にわたる束縛から解放されたように感じている。繋がれていた重い鎖がようやく手足から外されたみたいにね
私は読んでいて、この文章で立ち止まってしまった。これまでの前提が半ば崩れるような気がした。シロアリの女王は母親に取り憑いた悪者だと読んでいた。ところが、どうだろう。シロアリの女王の言い分にも、一理あるのではないだろうか。そんなことを思ったからだ。
夏帆の母親は堅実に地味な生活を送ってきた。自分が過去のある時点で選んだ道とはいえ、自身の欲望を抑えて、五十歳を過ぎるまで暮らしてきた。娘が自立して、自分の人生を考えた時に、突然、性愛に夢中になることが、百パーセント悪いことだろうか。いや、夫のある身で不倫行為をするのは悪だという考えはあるだろう。ただ、なんだか、彼女やシロアリの女王を一方的に裁いていいのだろうかという疑いも生じるのだ。
もちろん、それが依存性の強い薬物のようなものなら、やはり悪い存在だという方に傾くだろう。当事者を破滅に導くようなもの、生きる喜びから遠ざけるものなら、やはり、悪というべきだろう。しかし、この場合はどうか。一概にいえるものだろうか。
だいたい、アリクイの奥さんは全面的に信用できるのだろうか。夏帆を使ってジャガーを殺させたのは正当なことなのだろうか。シロアリの女王は悪霊なのか、それとも、少し違う存在なのか。
善悪がはっきりと区別できず、悪の中に善があり、善の中に悪があるというのが、村上春樹の世界ではなかったか。醜い姿をしているというシロアリの女王は、ほんとうに悪なのか。最後になって、私は複雑な味わいをかみしめることになった。
あと二つ、この作品について書いておこう。一つは夏帆の叔父(父親の弟)が何度か出て来て(というより、夏帆に電話をかけてくるのだが)、意味ありげなことを話すのが気になった。この人、何でもわかっているようなのはどうしてなのだろう。夏帆シリーズの続編で、彼の姿が前面に出てくることがあるのだろうか。
もう一つは、メールとか、闇サイトとか、ネットメディアが何度か出てくることだ。そして、ネットメディアが現実離れした設定の村上ワールドに実によく合っているように思われた。それは私たちの現在の生活の不安感や緊張感とも通じている。村上は物語を動かすにあたって、ネットというメディアを今後どんどん使っていくような気がする。