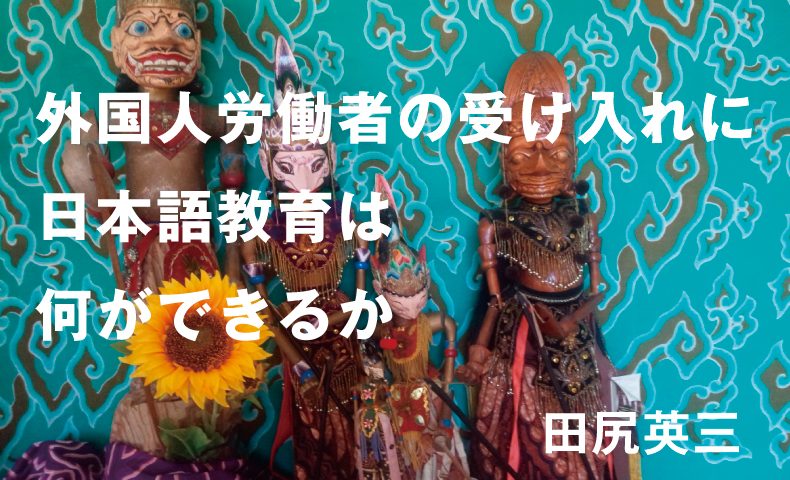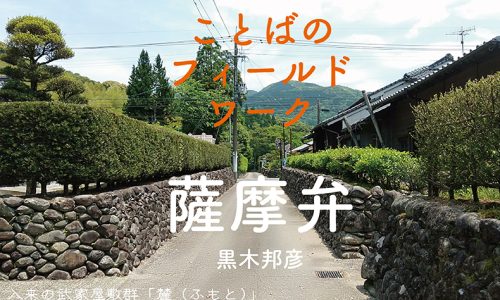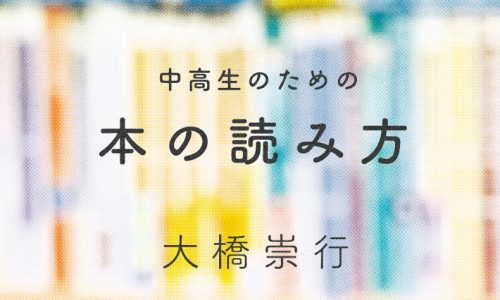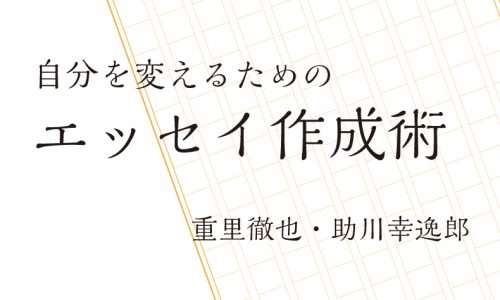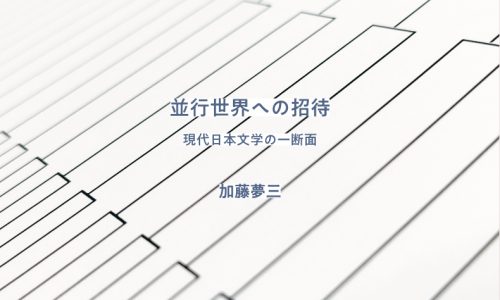★この記事は、2025年9月5日までの情報を基に書いています。
参議院選挙以降、外国人排斥の動きは高まっていませんが、相変わらず不確実な情報に基づいたニュースは流れています。そのような時期に、法務大臣勉強会が外国人受け入れの論点整理を行い、今後省内にプロジェクトチームを立ち上げることになったようです。
今回は、この内容を取り上げます。また、これに連動していると思われる2026年度予算概算要求を取り上げます。参議院選挙期間中の政党の動きについては、前回の第62回の記事を見てください。
「受け入れ」という語の表記は、引用する資料の表記に依ります。田尻は「受け入れ」を使用します。
1. 「外国人の受入れの基本的な在り方の検討のための論点整理」(以下、「論点整理」と略称)の説明と問題点
(1)「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下、「ゼロプラン」と略称)
「論点整理」が公表される前に、その前身と言える「ゼロプラン」が2025年5月23日に公表されています。このプラン作成の意図は、以下のように書かれています。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/others/05_001390.html
昨今、ルールを守らない外国人に係る報道がなされるなど国民の間で不安が高まっている状況を受け、そのような外国人の速やかな送還が強く求められていたところ、法務大臣から、法務大臣政務官に対し、誤用・濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含め、ルールを守らない外国人を速やかに我が国から退去させるための対応策をまとめるよう指示がありました。
ここでは、報道により国民の不安が高まっていて、ルールを守らない外国人の送還が強く求められているというような根拠を示さない情報に基づいて、また難民申請を繰り返し求めている人もひとまとめにして、速やかに国外退去させることを目的とした対応策をまとめたとなっています。田尻は、この対応策は偏った情報に基づいた対応策だから、今後にあまり影響が出ないだろうと考えて『未草』の記事では扱いませんでした。この見通しは、間違っていました。
「ゼロプラン」の難民認定については、三つの団体から以下の見直し要望書が出ています。
https://www.refugee.or.jp/wp-content/uploads/2025/06/JARcomment250611_FNL.pdf
法務大臣は、2025年2月から私的勉強会を開いていました。田尻は、この勉強会開催の情報は得ていましたが、法務省のサイトには出ていないのでフォローできませんでした。
(2)法務大臣勉強会の「論点整理」の内容
これは、2025年8月29日の法務大臣記者会見(9月3日概要公開)で触れ、同日出入国在留管理庁のサイトで公表されました。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/others/05_001390_00001.html
これについては、8月30日の朝日新聞(田尻が見たのは大阪本社版)の1面トップと3面に関連記事が出ました。この記事を図書館などでぜひ見てください。
3面の記事には、以下のような記述があります。
複数の政府関係者によると、当初は一大臣による論点整理という位置づけだった。しかし、7月の参院選で外国人政策が大きな争点となったことで、政府内で急速に問題意識が共有され、「政府方針」に近い文書に変わっていったという。
朝日新聞の記事には、すでに外国人比率が10%を超えた27市町村名が挙げられています。
「論点整理」(概要)に、七つの「今後の外国人受入れにあたって考えられる視点」が挙げられています。
①経済成長の観点
②産業政策の観点
③労働政策の観点
④税・社会保障等の観点
⑤地域の生活者としての観点
⑥治安の観点
⑦出入国及び在留管理の観点
日本語教育については、⑤で書かれています。大事な箇所を引用します。
上記の許容度(田尻注:当該地域における外国人受け入れ許容度。これをどのように計測するかは不明)を上昇させ、共生社会の実現について検討する際、日本語能力の必要性(日本語教育の必要性を含む。)(田尻注:「日本語能力」と「日本語教育」の二つを並べた意図は不明)や日本文化・慣習への理解の促進が課題となり得ることや、入国前にこれらに関する試験の合否や日本語講習の受講を課すことや、入国後にこれらに関する講習等の受講を課すことにつき、国費によりこれらを行うかも含めて検討することが考えられる。
(中略)
外国人に対する日本語教育の在り方(漢字圏・非漢字圏(簡体字を含む)それぞれの者に対する日本語教育(田尻注:この箇所は意味不明。漢字圏・非漢字圏それぞれの学習者のことか)、日本語教育と母国語教育(田尻注:母語教育のことで、ここでは継承語教育のことを指すと思われる)の両立、技能レベルの高い外国人や日本への貢献度の高い(田尻注:「貢献度」をどのように図るか不明)外国人への日本語教育への要否等や、外国人の子どもを対象とする学校教育の在り方(教育機会の確保、日本語指導等の実施方法、等)について、地域社会や財政等への影響を踏まえつつ検討することが考えられる。
地域社会において外国人との共生を図る上で、こうした外国人への教育のみならず、日本人が外国人への理解を深めることも重要であるとの指摘もあることから、例えば、地域住民を対象として当該地域社会における人口比の高い国籍の言語・文化・宗教等に関する理解を深める機会を設けるなど、地域社会での先進的取組を参考としつつ、地域の実情に応じて、日本人に対し、外国人との共生に向けた意識啓発等のために取り組むべき方策について検討することが考えられる。
(後略、基礎自治体等での取り組みなどに触れている)
出入国在留管理庁には、この「論点整理」を踏まえて、庁内に「外国人受け入れの基本的な在り方の検討のためのPT」が作られることになりました。また、「出入国在留管理政策懇談会」でも検討するそうです。ここに書かれているように、外国人受け入れ全般を出入国在留管理庁が扱うのなら、政府全体の方針との整合性が問題になると考えます。7月15日に内閣官房にできた「外国人との秩序ある共生社会推進室」との分担範囲も、現時点では不明です。
また、この「論点整理」に関わった有識者名が公表されていないのも、問題だと感じています。分野としては、「経済学、社会学、諸外国の外国人政策、さらにはこの受け入れをされている自治体、この現状に精通した有識者の方々」とだけ記者会見で述べています。
脚注に「法務大臣の私的勉強会における有識者の発言等」として引用されている発言がしばしば引用され、それが「論点整理」の項目として採用されているので、どのような人がメンバーであったのかは重要な情報です。例えば、以下のような発言は問題ならないのででしょうか。
注17 「諸外国において受入れ外国人増加により住宅価格が上昇しているとの指摘」には、客観的な資料が付いていません。
注23 「高技能移民」や「低技能移民」という語の使用は、不適当であると考えます。
注36 「高度人材については、日本語能力を問わず、むしろ外国語を中心とした環境を残すことで、海外とのつながりを維持してもらった方が有益な場合がある」としていますが、どのような場合が有益というのか、田尻には分かりません。
注43 (田尻注:最初に留学生のアルバイト制度の説明をしている)「就労を目的として本邦に在留する外国人留学生は相当数存在する等、制度の趣旨に沿わない悪用がなされているとの指摘がなされている」という発言の客観的な資料が示されていません。そのため、「論点整理」に「『留学』の在留資格の資格外活動許可による就労許可の在り方の見直し」が項目として加えられました。その検討結果によっては、留学生の受け入れ施策に大きな影響を与えます。
「論点整理」の本文の「(6)(田尻注:上記の説明では⑥にあたる)治安の観点」にある「数字では表されない外国人集住地域または国民に与える不安感(体感治安)」という記述は、外国人排斥の動きと軌を一にしていると考えられます。「体感治安」は警察庁なので使われる語であり、「論点整理」のように一般的な外国人施策に使うのは不適当と考えます。
8月31日のフジテレビの「日曜報道」に出演した鈴木法務大臣は、外国人は最速2040年に日本の人口の10%になる可能性があるという発言をしました。まだ在留外国人への支援体制が整っていなくて、外国人が日本の総人口に占める割合が2.8%の段階で10%になるとどうなるのかの検討を始めることの危うさを感じます。
これについては、2024年7月に出されたJICA緒方貞子平和開発研究所の「2030/40年の外国人との共生社会の実現に向けた調査研究に係る外国人労働需要予測の更新業務 最終報告書」に触れる必要がありますが、今回はスペース的に扱う余裕がありません。次回に扱う予定です。
(3)すでに実施されている外国人管理行政の厳格化
法務省関係以外に、参議院選挙の途中で外国人への厳格化の施策が短期間で実行されました。
-
国外運転免許証からの切替え手続き
報道では「外免審査」と呼ばれているもので、5月16日の坂井内閣府特命担当大臣の記者会見で公表されました。検討は内閣府国家公安委員会で行われ、警察庁から報告されるもので、10月1日から実施されることが決まりました。改正のポイントは、以下の三つです。
・知識確認の出題数を現行の5倍の50問とし、9割以上の正答を要件とする。
・技能確認では、横断歩道や踏切通過時などの項目を追加。
・住民票の写しの提出を原則とし、住民票を持たない観光客らは制度の適用外とする。
-
博士後期課程の奨学金SPRINGでの留学生支援打ち切り
6月26日の文部科学省の「人材委員会 次世代人材ワーキング・グループ」の会議で、「博士後期課程学生支援等に関する現状・課題・今後の具体的な取組(案)について」という議題で、SPRING枠の留学生への奨学金が打ち切りになりました。この件は、3月に自民党の有村治子参議院議員が国会質疑で扱ったもので、2024年度の受給者の4割が留学生で、かつ中国人留学生が全体の3割に当たることを問題にしました。それに対して文部科学省が、いち早く対応したものです。研究奨励費という生活費に当たるものをカットしました。
トランプ大統領がアメリカの留学生へのビザ発給厳格化の方針を示したことを受けて、多くの日本の大学がそれらの留学生を受け入れることを決めた流れと齟齬するのではないかと考えています。ちなみに、トランプ大統領は8月26日に中国人留学生を60万人受け入れると発表しました。中国人留学生がアメリカではなく日本にくることを期待した大学や日本語教育機関の計画は、うまくいかなくなると思います。
-
在留資格「経営・管理」の厳格化
出入国在留管理庁が、在留資格「経営・管理」を与える際には、資本金や出資金の要件を従来の6倍の3千万円以上とすることを決め、10月中旬から施行する予定となっています。当初、在留資格「特定活動」のスタートアップビザの取得者には認める方向でしたが、自民党内からの反対で厳格化が決まったと言われています。
2. 2026年度概算要求の内訳
以下で扱うものはあくまでも「概算要求」ですので、実際に施行されるものは財務省との折衝を経て、例年なら2025年末に「予算案」として決定されます。最終的な結果が分かるのは、国会での審議を経たのちです。この「概算要求」は、あくまでも現時点での各省庁の希望を列挙したものとして理解してください。概算要求で、各省庁の予算案作成の意図は見て取ることができます。
(1)法務省
上述の「1」との関係で、法務省の概算要求を最初に扱います。
https://www.moj.go.jp/content/001445356.pdf
Ⅲ出入国及び外国人の在留の公正な管理の推進
②外国人材の適正かつ円滑な受入れのための体制整備等 22,924百万円
この額は12,970百万円の増で、前年度の2倍になっています。
「施策と期待される効果」では、「外国人材の受入れの促進・公正な在留管理の推進」として18,389百万円が、「不法滞在者対策・難民の迅速かつ適切な保護の推進」として4,535百万円が計上されています。
法務省の概算要求では、すでに上述の「論点整理」を踏まえたものとなっています。
(2)文部科学省
総合教育政策局の概算要求を示します。
https://www.mext.go.jp/content/20250826-ope_dev02-000044427_3.pdf
増減額は、昨年度との比較です。
この中で、日本語教育に関するものは、「外国人等に対する日本語教育の推進・外国人児童生徒等への教育等の充実」で示されています。この枠では44億円となっていて、13億円の増額です。
Ⅰ.外国人等に対する日本語教育の推進 2,246百万円で、648百万円の増額です。
(1)日本語教育の全国展開・学習機会の確保 この枠は日本語教育課の担当です。
〇外国人材の受入れ・共生のための地域日本語教育の推進 652百万円で、102百万円の増額です。
〇日本語教室空白地域解消の推進強化 141百万円で、6百万円の減額です。
〇「生活者としての外国人」のための日本語教育の取組推進 18百万円で、昨年度と同額です。
(2)日本語教育の質の向上等
〇「日本語教育の参照枠」等に基づく教育カリキュラム編成・質向上支援事業 353百万円で、新規事業での増額です。今回の目玉施策の一つです。
〇日本語教師の養成及び現職日本語教師の研修議場 337百万円で、108百万円の増額です。
〇日本語教育のための基礎的取組の充実 25百万円で、1百万円の減額です。
〇日本語教育機関認定法等の施行事務に必要な経費 483百万円で、91百万円の増額です。
(3)難民等に対する日本語教育
〇条約難民等に対する日本語教育 236百万円で、昨年度と同額です。
Ⅱ.外国人児童生徒等への教育等の充実 2,153百万円で、698百万円の増額です。
〇日本語指導を含むきめ細かな支援の充実 1,911百万円で、662百万円の増額です。
〇日本語指導が必要な児童生徒等の教育支援基盤の整備 12百万円で、6百万円の減額です。
〇外国人児童生徒に対する指導および支援体制の充実に関する調査研究 40百万円で、新規事業です。ここだけ「外国人児童生徒」に「等」が付いていないのは深い意味があるのでしょうか。
以上の3事業は、総合教育政策局国際教育課の担当です。この枠での大幅な増額が目立ちます。
〇夜間中学の設置促進・充実 117百万円で、1百万円の増額です。
この事業は、初等中等教育局初等中等教育企画課の担当です。
〇高度外国人材子弟の教育環境の整備 71百万円で、昨年度と同額です。
この事業は、大臣官房国際課の担当です。事業内容も限定的ですし、担当部署も別枠です。
それぞれの事業の詳しい内容については、資料を見てください。
日本語教育課も国際教育課も、概算要求を増額していてがんばっています。
(3)厚生労働省
外国人介護人材と外国人労働者の受け入れ拡大の二本柱となっています。
〇地域医療介護総合確保基金 97億円で、昨年度と同額です。
この枠の中に、外国人介護人材の支援が入っています。
〇介護の日本語学習支援事業 2.2億円で、0.9億円の増額です。
訪問系サービスの支援事業は、ここに入っています。
〇外国人介護人材受入・定着支援事業 3.1億円で、1.2億円の増額です。
〇外国人介護人材獲得強化事業 2.3億円で、新規事業です。
〇外国人労働者の適正な雇用環境等に関する体制整備等 1.3億円で、0.1億円の増額です。
〇外国人求職者への就職支援 1.5億円で、0.1億円の増額です。
〇外国人雇用対策に関する実態調査事業 3.5億円で、1億円の減額です。
8月29日に、厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課から「令和6年外国人雇用調査」の結果が公表されています。ここで詳しく扱う余裕はありませんので、各自で調査結果を確かめてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61317.html
8月4日の出入国在留管理庁の「第6回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」の資料に、「平均賃金(一般労働者全体・特定技能外国人・技能実習生)」が挙げられています。大変重要な資料です。出典は、厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」です。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001445022.pdf
外務省・経済産業省・総務省などでの所管団体・機関で日本語教育を扱っているものがありますが、概算要求では項目として挙がっていませんので、ここでは扱いません。
3. 外国人児童生徒等への教育について
(1)第6回 外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議
この会議は、8月28日に開かれました。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/196/siryo/1418919_00006.html
今回は横浜市国際交流協会が紹介されました。大変積極的でよく考えられた取組だと感じましたので、ぜひ「資料2」を熟読してください。
ここでは、詳しい内容を紹介する余裕がありません。
また、この後質疑応答もありましたが、これもここでは取り扱いません。
また、参考資料5は、現在の外国人児童生徒等への日本語教育を考える時の基礎資料ですので、プリントして手元に置いておいてください。
(2)政策提言シンポジウム「多文化多言語の子どもの学びの保証」について
8月17日の大阪大学箕面キャンパスでのシンポジウムに、田尻も参加しました。200名以上集まった熱気あふれるシンポジウムでした。
ここで出された提言2と3については、第62回の「未草」の記事で扱いました。
提言2と3は、今後上記の有識者会議で扱われることになりました。
提言3は、母語支援員が当該地域へ通勤可能な地域に住んでいる場合には有効でしょうが、そのような条件が満たされない多くの地域では実現可能性が下がります。
ここでは、提言1を扱います。
提言1を主張する根拠として憲法26条2項の「保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」を挙げ、次に「普通教育」については2016年の「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」を挙げていますが、これでは提言1の法的根拠にはなりません。ここでも引用されていますが、憲法26条の1項でも2項でも「すべて国民は」で始まっています。26条は、日本国民を対象にしたものです。法体系上、憲法はすべての法律の上位に位置しています。したがって、ここで挙げられている法律では、外国人児童生徒等への教育義務化の法的根拠とはなりません。
憲法では、「国民」が教育を受ける義務を負っているので、外国人児童生徒等の教育は義務化できません。だからこそ、今まで国際人権A規約13条や児童の権利条約28条を援用して、日本の学校に外国人児童生徒等を受け入れてきたのです。
もし、提言1を実際に行おうとしたら憲法改正をしなければいけません。
日本語教育推進法や日本語教育機関認定法に関わってきた田尻としては、これは大変大きな壁です。提言1の実現可能性は感じられません。田尻は、憲法改正にかけるエネルギーは、実際の学校現場での外国人児童生徒等への日本語教育の改善にかけるほうが成果が出ると考えています。
このシンポジウムに参加した人の多くは、「ことばの力のものさし」に関わった人たちではないかと感じました。それなら、まずは「ことばの力のものさし」を普及させることに力を注いではいかがでしょう。「ことばの力のものさし」で日本語能力を測定できても、その次には教科学習との連携という大きなハードルが待ち受けています。
これからの日本を考える時には、外国人児童生徒等の人権が守られ、日本語の壁を乗り越えて日本の学校制度に中で自己実現を目指せる環境作りが絶対に必要です。そのために、関係者の力を結集しましょう。
4. お薦めする二つの文献
(1)橋本直子さんの「『外国人デマ』に向き合う 参院選の重い教訓」(『世界』9月号 No.997 岩波書店)
橋本さんは、2025年7月20日に投開票が行われた第二七回参議院議員通常選挙中での外国人排斥の動きに、Facebookなどで具体的なデータに基づいて反論をしています。その橋本さんが、改めて今後「外国人デマ」とどう向き合うべきなのかを書いた論文です。
ここでは、「『#日本人ファースト』台頭の下地」として、次のように書かれています。
外国人住民が着実かつ明確に増加してきたにもかかわらず、必要な共生施策(西欧諸国でいう「社会統合」政策)と国民に対する誠実な説明を、政府与党長年怠ってきたツケが回ってきた、ある意味で当然の帰結と筆者は見ている。
この橋本さんの意見は、第62回の「未草」の田尻が述べた意見と同じです。
日本語教育に関わることは、「『平時』からやるべきこと」に次のように書かれています。
日本語学習、生活・文化オリエンテーションなどの外国人支援には、国が責任をもって予算を確保し地方自治体やNPO/NGOなどの実施機関に予算配分を行っていく体制整備が急務である。外国人労働者から実益を得ている雇用主・企業に相応の負担分担を求めるのも合理的であろう。
当然自治体の役割も大きい。従来から国際交流協会やNPO/NGOなどが実施してきた日本語教室、生活支援、文化交流もより充実させる必要がある。どうしてもルールをめぐるトラブルがあるなら、国籍不問で適用されることを大前提として、ルールを明記の上で違反に対する過料つき条例を制定することも一案であろう。
『世界』9月号は「政党政治のはて」という特集で、他に多くの参考にすべき論文が掲載されているので、ぜひ他の論文も読んでいただきたいと思っています。
以上の流れとは関係がありませんが、同書の寺島実郎さんの「脳力のレッスン278 特別編 戦後八0年への沈思塾考」に正田篠枝さんの原爆詩集『さんげ』の中にある詩が紹介されていて、2025年8月6日の広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式で石破総理も挨拶でその詩を引用していますが、その箇所に田尻は疑問を感じています。
大き骨は 先生ならん 小さきあたまの 骨あつまれり
石破総理は記念碑にある「太き骨」の方を使っています。
この詩は、教師の周りに集まるようにして亡くなっていった子どもたちの様子を詠んだ悲惨な詩であるなら、「大き」と「小さき」が対になっていることも考えても『さんげ』の初版の表現にすべきと考えます。以下のようになります。
大き骨は 先生ならん そのそばに 小さきあまたの 骨あつまれり
「大き」は文語調であり「小さき」と対になっているので「太き」ではなく、「あまた」は「あたま」ではなく「たくさん」を意味する語と理解すべきです。「あたま」と「大き骨」では対になりません。
(2)二文字屋修さんの「外国人介護労働者の受け入れと日本語教育」(2025年8月 『日本語教育』191号 日本語教育学会)
二文字屋さんは長年介護福祉士養成に関わってきた人で、二文字屋さんならではの記述が随所に見られます。以下では、申し訳ありませんが、論文の趣旨に関係なく、田尻が印象に残った記述を切り取ります。二文字屋さん、ごめんなさい。「2.外国人労働問題と日本語教育」は必読です。
- どのルート(田尻注:介護福祉士になるための4種類のルート)から入職したにせよ現場に即した指導は欠かせない。
- 多彩な日本語教育の中から専門家一人を検討委員会に招くとなれば大学の研究者になるのだろうが、外国人労働者受け入れ議論に果たして合致するのだろうか。
- 看護師国家試験の合否で同時に当該者の日本語能力は推し量られるが、更にN1合格も必要だという行政は何を危惧しているのかと思う。
- 就労のための在留資格は専門的・技術的労働者として申請者の学歴や経験が重視されるが、技能実習も特定技能1号も申請者の学歴は高校卒業者で経験は実質的には問われない。特定技能1号の資格試験は半年程度学べば合格する内容である。
- ある日本人研究者が、ベトナムの実習生の日本語学校はまるで馴致教育施設のようだと批判的に発表したのを聞いたことがある。しかし筆者は参与観察のおかげでその発表に違和感を持った。
- 双方(田尻注:日本語教師と介護職員)が鬱々としては肝心の学習者がその間に挟まって居づらくなってしまうことがないよう十分な配慮が必要だと思う。
- 日本語の分野から介護へ一歩踏み込んで教えるなら自己投資として130時間の介護初任者研修を受講するとか、身近なところにある介護施設でボランティアをしてみてはいかがだろうか。
- そのような現場(田尻注:介護の現場)で交わされる会話や業務で必要な日本語を知ることは、この分野の日本語教育に関わろうとするにはよい経験になるだろう。
- 日本語教師はこのような情報(田尻注:学習者がどのようなルートで介護福祉士を目指すのかという情報)も仕入れておく必要がある。
- 日本語教師が介護施設に赴いて日本語を教えるなら、ぜひともそこで働いている日本人職員(介護職に限らず)に日本語教育の様子を見学してもらうようお願いしてみてはどうだろうか。
- 現場は日本語力と介護力が必ずしも比例するとは限らない
- より良い高齢者介護のためにお互いに通じ合うマインドを大切にしながら、協働の経験を積み重ねていきたいと思う。
この論文にある「母国語」や「間接法」という語については学会誌の担当者が二文字屋さんにアドバイスすべき点で、「微温等」は「微温湯」の間違いであることは誰でも気づきます。学会誌の担当者は二文字屋さんの原稿をきちんと読んだのでしょうか。学会誌の記述の重さに思いをはせてほしいものです。
※すでに予定のスペースを超えていますが、言及しなければならない情報も、ほかにたくさんあります。『未草』の読者は、各自で調べてください。
外国人を取り巻く事態は、急激に動いています。日本語教育関係者は、それぞれができることを考えて、すぐに実行に動いてください。