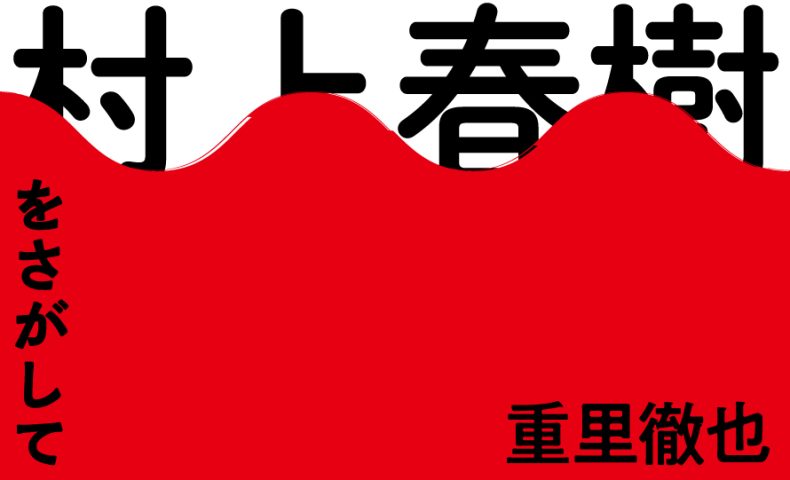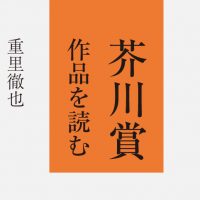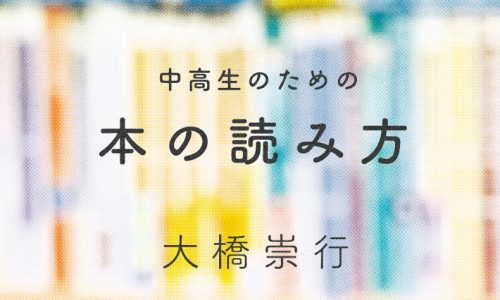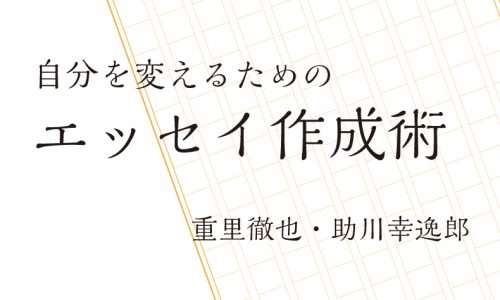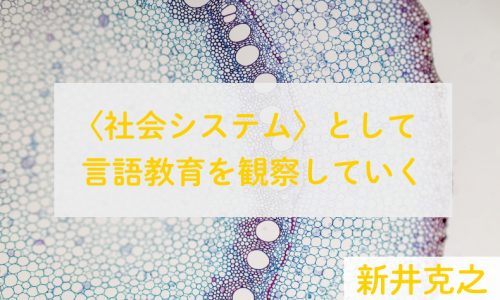大学で「文芸創作」という科目を担当している。学生たちが小説を書く。他の学生たちと私が批評する。学生は批評を受けて書き直し、二稿をみんなに見せて、さらに批評を受ける。そんなことを数回やって、小説を仕上げる授業だ。
今年で四年目になる。この授業で私が書くことを推奨しているのは一人称一視点の小説だ。行動する主人公が見たもの、聞いたこと、話したこと、触ったことで小説を書き進める。主人公が知らないことは書かない。読者は主人公と一体になって、この現実を生きることになる。作者も半ば、そうすることになる。
例として想定している作品の一つが、私立探偵を主人公にしたハードボイルド小説だ。あまり、なじみのない学生も多い。しかし、読み慣れれば、この型がさまざまに可能性のあることに気づくだろう。特に謎に満ちた現実や人間の悪がもたらす犯罪、複雑な社会的背景をうかがわせる事件、人生の不思議をその感触とともに実感させる出来事などを表現するのに、かなり適した構造を持っていることがわかるだろう。
村上春樹は米国の作家、レイモンド・チャンドラーの『ロング・グッドバイ』を「これまでの人生で巡り会ったもっとも重要な本」三冊のうちの一つに挙げている。あとの二つは前回取り上げたスコット・フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』とドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』だ。チャンドラー作品の何が村上を惹きつけたのか。ここにも、村上文学を考えるうえで、きわめて興味深い問題がある。
『ロング・グッドバイ』が刊行されたのは一九五三年。チャンドラーは生涯に、私立探偵のフィリップ・マーロウを主人公とする長編小説を七つ残したが、その代表作と目されている。というより、ハードボイルドというジャンルを代表する作品の一つといってもいいだろう。
ミステリーという性格上、ネタバレにならないように、少しだけ紹介しよう。作品はロサンゼルスが主舞台。マーロウは億万長者の娘の夫であるテリー・レノックスと知り合う。裕福でありながら、暗い影があり、酒に溺れながらも、どこか品のあるレノックスに惹かれ、二人の間には友情がめばえ始める。
ある日、レノックスは妻殺しの容疑をかけられ、マーロウに援助を求める。マーロウのおかげでレノックスは無事にメキシコへ逃亡するが、そこで自殺をしてしまう。けれでも、この事件の背後には深い闇が存在していて、意外な真相が待っていた。
村上春樹訳の『ロング・グッドバイ』は二〇〇七年に早川書房から刊行され、その後、文庫化された。もともと、清水俊二訳の『長いお別れ』の邦題で知られていたが、村上は他の多くの翻訳と同様に、原題をカタカナで表記してタイトルにしている。背景には英語がより大衆化された日本社会の状況もあるように思うのだが、どうだろう。
村上訳は原作の雰囲気をよく伝えているのではないだろうか。なじみやすい、リズミカルな文章。癖の強い人物たちが織り成す人間模様。あらわになる人間という存在の多様な側面。印象的なセリフ。現実の厄介さを反映したような複雑な、しかし最後まで読むとすっきりと理解できる筋。終末に待っている意外な真実。ミステリー小説の魅力が詰まっている。
そして、一人称一視点で動き回るマーロウが魅力的だ。タフなのに、感傷的なところもあり、権力や権威になびかない一匹狼。筋を通し、友情に厚く、世の中の酸いも甘いもわかっている。彼の視点から世界を見て、読者は現実というものの味わいをかみしめることになる。
彼が描く軌跡が紆余曲折を経ながら一本の線として伸びていく。その濃く強い線が現実を切り裂くように見えるのだ。
私にはチャンドラーをめぐる思い出がある。一九八九年のことだ。原尞という作家の『私が殺した少女』(早川書房)という小説を読んだ。当時、私は新聞記者をやっていて、福岡市で美術や文学を担当していた。佐賀県鳥栖市在住の原は管内の作家で、直木賞候補になったので本人に詳しく取材した(原作品はその後、受賞した)。
作品を一読して驚いた。とても面白いのだが、村上春樹の三つめの長編小説『羊をめぐる冒険』と読んだ感じがよく似ていたのだ。一人称一視点の主人公が行方不明の人物を探すストーリー。さまざまな人物と出会い、現実社会の感触がじわじわと迫ってくる味わい。孤独で寂しくて、でも、主人公はなんだかんだいっても芯が強いこと。最後に待っている意外な真相。そして、すべてが終わった後の徒労感。
私は『羊をめぐる冒険』を発表された一九八二年に読んでいた。この年に新聞記者になった私は多忙に追われて、ほとんど小説を読んでいなかったが、村上は気になる作家で、新聞広告を見て、掲載されている「群像」八月号を購入して、すぐに読んだのだ。デビュー作以来、リアルタイムに村上作品を読んできたが、この作品で何とか、この新鋭作家がやろうとしていることがおぼろにわかってきた感じだった。今でも、この作品は大好きで、私にとって、村上文学の原点のような感じがある。
『私が殺した少女』と『羊をめぐる冒険』。新しい直木賞受賞作と、七年前に刊行された新鋭作家の第三作。なぜ、こんなに似ているのだろう。調べると、一つの事実に突き当たった。両方とも共通したアメリカ人作家の影響を受けているのだ。それはチャンドラーという有名な作家だった。
私の読書は偏っていて、それまで、あまりアメリカのミステリーを読んでいなかった。あわてて、フィリップ・マーロウものを購入して、なるほどと、二人の日本人作家が書いた小説の源流を確認した次第だった。
なぜ、村上は『ロング・グッドバイ』に惹かれたのだろう。たくさんあるように思うが、ここでは三つだけ指摘しておこう。
一つはレノックスという人物の魅力だ。少し弱いところがある。でも、身を挺して自分の思いを守る。自分で稼いだわけでもないのに富裕だ。しかし、それに少し閉口している。どこか、品がよくて、潔い感じがする。自分という人間がつまらない存在だと自覚している。洗練された感じはそこからくるのではないか。
『ロング・グッドバイ』にはもう一人、ロジャー・ウェイドというベストセラー作家も登場する。この人はひどい酔っ払いだ。自分がつまらない小説を書いていることを自覚している。この人も心が強いとはいえないが、妙な優しさを感じさせる。
どうでしょうか。『羊をめぐる冒険』の「鼠」という人物に似ていませんか。以下は鼠の言葉。小説も終わり近くになってからだ。
俺は俺の弱さが好きなんだよ。苦しさや辛さも好きだ。夏の光や風の匂いや蝉の声や、そんなものが好きなんだ。どうしようもなく好きなんだ。
(『羊をめぐる冒険』(下、講談社文庫、二百二十八ページ)
レノックスやウェイドと鼠との間に共通点が多いように思えて仕方ない。これは、ギャツビーにもいえることだ。ついでにいえば、カラマーゾフ家の長男、ドミトリーとも共通している。
村上はこういう人物に惹かれるのではないだろうか。そして、こういう人物の魅力を表現するのに、小説は最も適した表現ジャンルの一つではないだろうか。
村上が『ロング・グッドバイ』に惹かれた二つ目の理由として考えが及ぶもの。男同士の友情だ。フィリップ・マーロウがレノックスやウェイドに抱く感情。こんな連中はほっとけばいいのに、そうはしない。損得勘定抜きで相手を思いやる。ニック・キャラウェイがギャツビーに抱く感情もそうだったのではないか。なんだか、不思議に献身的なのだ。この世で最も大切なもののように友情を貫くのだ。『羊をめぐる冒険』で主人公の「僕」が鼠に抱いている感情も似ている。
三つめは小説の舞台となる時代設定である。『ロング・グッドバイ』は第二次世界大戦後のアメリカを描いており、戦争の傷跡は作品に深く影を落としている。『グレート・ギャツビー』は第一次世界大戦後の好景気に沸くアメリカが舞台で、やはり戦争が物語に大きく影響を及ぼしている。それでは村上作品はどうなのか。大学紛争が終わった後の日本を描いているのではないか。学生たちの反乱の経験は、村上作品の登場人物たちの心と身体を大きく左右しているように読める。それがアメリカの二人の作家の小説と響き合っているのではないだろうか。
実は村上は『ロング・グッドバイ』の「訳者あとがき」でチャンドラーとフィッツジェラルドの共通点について、詳しく論じている。チャンドラーがフィッツジェラルドを愛読していたことは確かだし、二人ともアイルランド系で、生涯を通じてアルコールの問題に悩み、ハリウッドで脚本家として仕事をしたというのも共通しているという。そして、『ロング・グッドバイ』は『グレート・ギャツビー』を下敷きにしているのではないかと指摘している。 とても興味深い。
それでは『カラマーゾフの兄弟』はどうなのだろう。重くて、だけどきわめて面白いテーマに行き着いた。やっぱり、カラマーゾフだ。カラマーゾフと村上の関係。いずれ、論じることにしよう。