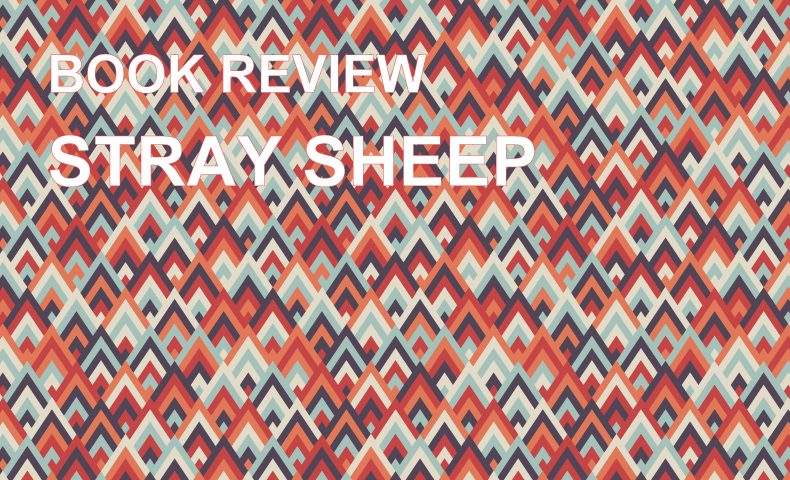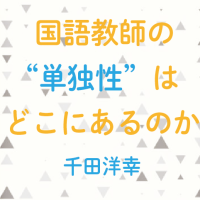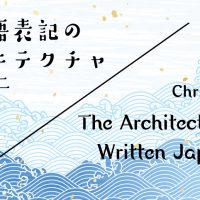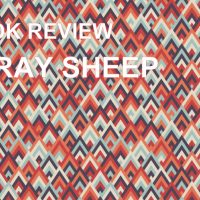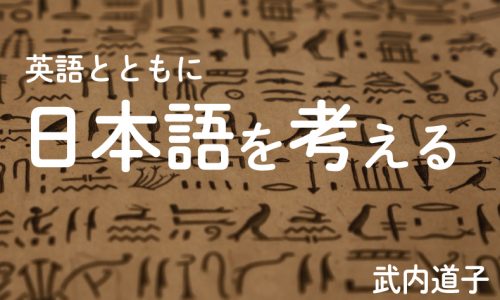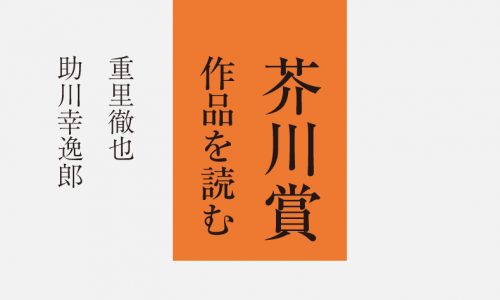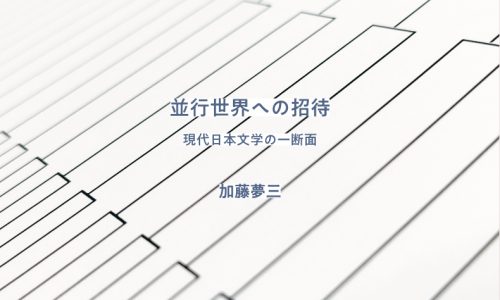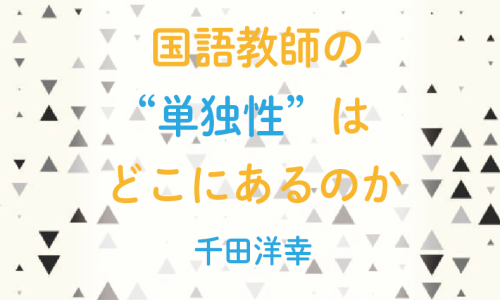藤井友比呂(横浜国立大学教授)
1.
本書は、ジム・ミラー(Jim Miller)によって著された A Critical Introduction to Syntax(原著:2011年)の全訳であり、岸本秀樹(監訳)、吉田悦子、久屋孝夫、三浦香織、久屋愛実(訳)による訳出により、2024年にひつじ書房から出版されたものである。本書の主題は自然言語の統語論であり、「マグナ統語論(magnasyntax)」(後述)の観点から様々なトピックを論じている。全体はまえがき、序文等に続き、本文13章があり、訳者による(第12章のコラムが目次から欠落しているが)第1~12章に付された章末コラム、付録、参考文献、訳者による解説、原著者への追悼と謝辞から構成されている。本書評では、前半で本書の雰囲気を伝えるべく、例を交えながら本書の考察を非常に限られた範囲で紹介し、後半は評価・コメントに割くことにする。なお、評者は生成文法の枠組みで教育研究を行ってきて、今回はじめて「マグナ統語論」に触れる機会を得たが、本訳書の訳者注、各章末コラム、訳者による解説が本書の理解に大いに役立った。
2.
本書は、主に英語を対象言語にした統語論の入門書である。原著タイトルを直訳すれば「批判的な(critical)統語論入門」となる。特に生成文法、とりわけチョムスキー流の言語学の問題点をあげながら、英語の統語分析を試みているが、W. クロフト、M.A.K. ハリデイ、R. クワークなどの言語学者の仕事も批判的に吟味されている。本書は個別言語の文法の記述を「ある特定の言語について、会話・講義・詩・小説・新聞・研究論文・学校や大学向けの教科書など、ありとあらゆる種類のテキストで見いだされるすべての構造を可能な限り網羅的に記述したもの」と考える(第1章:3)。「ありとあらゆる種類の」という言い方に本書の指導理念とも言えるマグナ統語論の考え方を見てとることができる。原著者の元同僚 K. ブラウンの「日本語版への序」は、マグナ統語論とは「マグナ・ボキャブラリの概念を拡張したもので、OEDのような大規模な総合辞書の根底にある伝統的な考え方」と言う(前書き:vi。巻末の「訳者による解説」も参照)。1884年に初版が出版され、20巻に及ぶ英英辞典であるOxford English Dictionary(『オックスフォード英語辞典』)は、「英語圏全体の過去から現在に至る50万語以上の単語や語句について、その意味、歴史、用法を網羅的に示す」(https://www.oed.com/)。本書が繰り返し、作例、書きことばを超えて、自然発話の分析の重要性を謳うことも、この「網羅性」の重視からくるものである。このような用法重視の接近法を、著者は「言語学者の直感に基づく話者の言語能力(competence)の理論化に対する、まさに解毒剤」と評している(第6章: 176)。
本書は、生成文法家はさまざまなデータに基づいて理論構築を行なっているにもかかわらず、そのことに「無自覚だ」と批判する(第5章: 158)。例えば、間接疑問節内で主語助動詞倒置が起こらないという一般則は極めて広く受け入れられているが、必ずしも正しくないことを示唆する(1)のような自然発話の例を軽視しているというのである(第1章: 5)。
(1)This issue about how are we preparing students to flow on seems to me quite important. (いかにして学生に賃上げに向けて備えさせるかというこの問題こそが、非常に重要なことに思える)
この倒置現象は、生成文法の伝統においても方言変異として報告されてきたが、本書は C. ディケンズの小説や1940年代の書きことば資料を紹介し、これを方言差とすることに懐疑的なようだ。
(1)のような例は上述したように方言の現象としてよく言及されるものであるが、ニュージーランド英語のコーパスからの例である(2)に見るような、名詞句(any of my family)と節(how old they are)が1つの動詞の目的語として機能しているような「目的語+節」構文は、評者が初めて知る構文であった(第1章: 39)。
(2) i can never remember any of my family how old they are. (私は家族の誰も思い出せない、歳がいくつなのか)
この構文では書きことばであれば節の前にカンマが入るそうで、著者は、分析としては二重目的語分析を示唆するにとどめている。
本書は、英語以外の言語についてもマグナ統語論の考え方を適用している。ロシア語において、(3)のような分離名詞句と呼ばれる現象が話しことばのみに現れるというのだ(第3章: 99)。書きことばでは形容詞とそれが修飾する名詞は隣接するという。
(3) Interesnuju prinesi mne knigu.
interesting bring to-me book
(おもしろい本を持ってきてくれ。)
分析としては、ロシア語では特定のクラスの形容詞が名詞性をもち、被修飾語と同格の関係にあるという見解を示し、オーストラリアのワルピリ語や英語、フランス語にも言及しながら、話しことばにおいて長い名詞句(の埋め込み)が避けられる傾向を報告する。
以上の紹介からも想像されるとおり、本書は構文文法や用法基盤モデルといった、いわば生成文法に対立する潮流に共感的である。(4)のような話しことばの存在・提示のthere構文においては、通常省略されることのない主格関係詞が省略できることはよく指摘される。本書は、クワーク他による著名な文法書が存在・提示の機能を持つit分裂文における主格関係詞の省略可能性を報告していることを引きながら、それにとどまらず、クワーク他が不可能とするSVO構文における主格関係詞の省略もテレビ番組からの収集された(6)の例のように観察されることを報告する(第4章: 138)。全て存在・提示の構文である点が重要である。
(4) There’s a tree [Ø] has fallen on a very expensive car.(高級車の上に木が倒れている)
(5) It was the President himself spoke to me.(私に話しかけてきたのは大統領その人だった)
(6) I had a witch disappeared down a trap (= trapdoor in the stage).(仕掛け(=舞台落とし戸)から消える魔女がいた)
マグナ統語論の接近法は、このようにテキストの種類を横断的に丁寧に観察することで英語の文法の「よりリアルな」姿に迫るだけでなく、これもOED的と言えようが、縦断的に、言語変化にも関心を払う。例えば、(7)は、スコットランドの新聞の2009年の記事からの用例だが、通常 scatter X on Yという使い方がなされる動詞 scatterが、cover X with Yと同等の用法で用いられている(第5章: 165)。
(7) My fields are scattered deep with chestnut leaves.(わが野にはあちこちに栗の木の落ち葉が積もっている)
諸例を通して著者は、言語変化が起こると、話者間で表現の容認度について意見が一致しないことから(あるいは、一人の話者の中でも時代を経て直感が変容していくことから)、生成文法で用いられている容認度判断に頼りすぎるデータ収集法に限界があると断じる。
第11章と第12章は、複雑な文法の「人工性」あるいは「後天性」に関するものである。複雑な文法構造が、通時的には社会における文化的な要請によって、言語発達においては書きことばの教育によって生じるもので、そのことは生成文法における全ての話者にある生物学的な所与としての言語能力という構想に不都合なのではないか、という疑問を投げかける。「特定の集団の使用者は、記録の保存、法律の起草、多様な様式の詩の言語など、特定の目的のために言語を精緻化する」とし(第11章: 290)、複雑な節の従属構造を発達させる前の紀元前のアッカド語や古フランス語の例をあげながら、問題提起を行う。
3.
以上のように、本書は統語記述というテーマに対して、マグナ統語論の視点から包括的に取り組んだ入門書であり、以下の点で高く評価されるべきであろう。まず第1に、本書は、必ずしもそのようには構成されていないが、文法構築の方法論についての研究と言ってよい。伝統的な統語分析が依ってたち、かなり広く認められてもいる多くの記述的一般化が言語学者の容認度判断に基づいているが、データのソースを話しことばも含めて広く求めることによって、その根幹が揺るがされることがある、と主張する。逆に言えば、本書は自然発話分析が、理論的な研究にインパクトをもつ事例研究に満ちていることを示そうとしていると言うこともできる。
本書の2つ目の特長として、通常の学術論文やテクニカルな入門書にはない、原著者の率直な理論的言語学に対する問題提起の姿勢をあげることができる。生成文法家にとってはナイーブに見えるものもあるかもしれないが、評者としては、隣接科学分野間のコミュニケーションが避けられない昨今、そのような問題提起に向き合ってみることは有意義な経験となった。
例えば、原著者は第1言語獲得においてある規則なり構造なりを含む発話を一定年齢まで使用しない、あるいは理解できないことをもって、「生成文法の一般の信念に反して」いると言う(第12章: 303)。ただし評者の知る限り、生成文法の理論は、特定の文法特性の使用(あるいは理解)開始時期に関する予測はしない。文法的・意味的な特性が知識のレベルで利用可能であっても、作業記憶等の処理能力が未発達であるという理由や、心の理論(theory of mind)—他者、あるいは物語中の登場人物の信念を推測する能力 — が未発達であるという理由で、大人と同等の運用ができないと主張する研究は多い。このような場面こそ、本書が否定する言語能力(competence)と運用(performance)の区別が実質的な意味でなされる場面であろう。当然、問題になるバリアを取り除けば子供が大人と同等のパフォーマンスができるという仮説の検証が伴うことは言うまでもない(注1)。
また、上述した、複雑な文法の後天性、人工性という論点は、アマゾンで話されるピラハ語(Pirahã)に関するD. エヴェレットの「チョムスキーが普遍的だと主張する複文構造がピラハ語には見つからない。したがって、チョムスキーは誤りだ」という有名な主張を想起させる(注2)。 G. プラムの文献調査では、構造的複雑性の欠落はエヴェレット以前から、少なくない少数言語で報告されてきたとあり、それらの言語が書きことばを発達させてこなかったこととの関連が示唆されている(注3)。 チョムスキーは、ピラハ語話者には複雑な構成素構造を構築する能力があるが、それが単に用いられていない可能性を示唆する。類似の可能性として、第1言語獲得の場合と並行的に、複雑な構造の構築の能力が、書きことばという厳しい実時間処理の制約から解放される産出モードを得てはじめて、観察可能になるという仮説も考えられるかもしれない。
最後に、自然発話を文法構築のためのデータに用いることについて感じたことを述べたい。評者が日本語統語論を研究するとき、個々の話者の外(あるいは「社会」)に「日本語文法」という抽象的なシステムが存在し、それを研究している、とは考えない。生成文法の立脚点は、個体心理学(individual psychology)の考え方である。例えば、評者とマリとヒロシが実験に参加し、実験条件について同じような容認度パターンを示したとする。それは、3個体の心的言語システムが当該のタスクに関わる語彙や文法の側面で共通していることを示唆する。それでも、3個体の外部にその3個体が従う『日本語○○方言の文法』が実体として存在するという見方はとられない。日本語の歴史変化について語るとき、「△△構文を受容する話者の割合が増えてきた」とは言えても「△△構文が日本語に定着してきた」と心理学的に正確な意味で言うことはできない。結局は、(1)のような自然発話をコーパス等で得た場合、分析者は倒置がどんな環境で許されて、許されない環境があるのかを容認性判断タスクを使って確定しようとするし、そこに個人差があるのかどうかを確定しようとするであろう。(そして、倒置を頻繁に許す話者群とほとんど許さない話者群に綺麗に二極化しない限り、「個人差がある」とはどういうことなのか、概念の先鋭化が必要となるであろう。)そう考えると、理論家が自然発話を観察することは、データ収集方法を健全にするのに大いに貢献するように思われる一方で、従来の方法論に根本的な変革を迫るわけではないとも思われるのである。
人間のことばの文法に関心を持つ読者にとっては、本書に見られる「非標準的で」興味深いデータと、それに基づくミラーによる問題提起は一読に値するだろう。訳者による脚注や解説を助けとしながら、本書が示す視座に触れてみてほしい。
(注1)従属節を伴う動詞の獲得研究の最近の事例を見ることができる論考を挙げておく。論文名は省略した。V. Hacquard & J. Lidz. Annual Review of Linguistics 8 (193–212), 2022.
(注2)論争の概要について日本語で読めるものに以下がある。折田奈甫・藤井友比呂・小野創(編)、N. ホーンスティン(著)『言語能力は人工知能で解明できるか』岩波書店, 2025.
(注3) G. K. Pullum. In E. Gibson & M. Poliak (eds.) (23-74), 2024.
『これからの言語学 ダイナミックな視点から言語の本質に迫る統語論』
ジム・ミラー著 岸本秀樹監訳 吉田悦子・久屋孝夫・三浦香織・久屋愛実訳
A5判並製カバー装 定価3200円+税 380頁 ISBN978-4-8234-1091-8