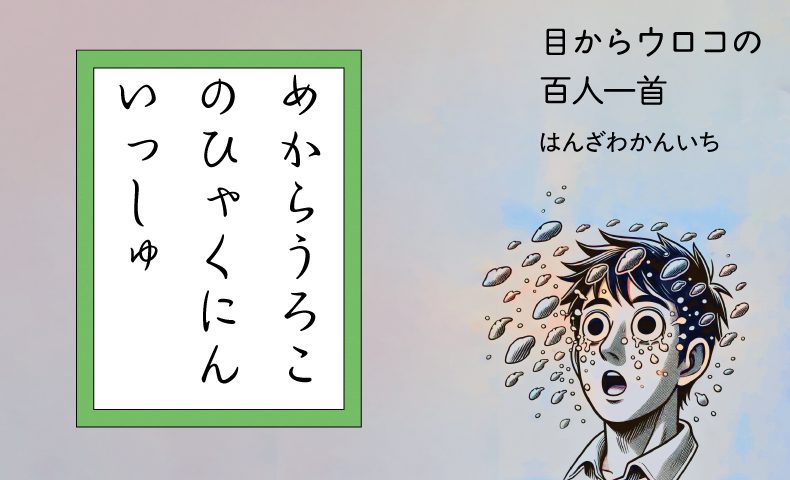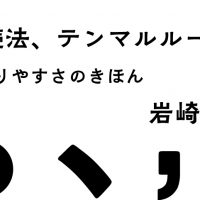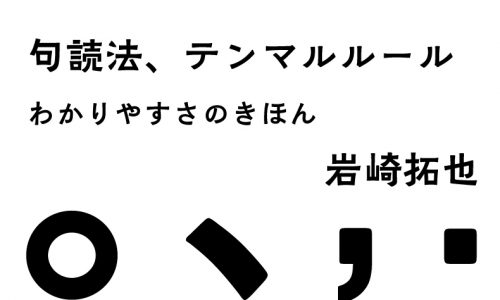これやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも逢坂の関
この歌は、「逢坂(あふさか→おおさか)の関」という、「歌枕(うたまくら)」と呼ばれる地名を詠むためだけに作られたと言っても過言ではありません。
後撰集(巻15・雑一・1089番)には、「相坂の関に庵室をつくりてすみ侍りけるに、ゆきかふ人を見て」という詞書(ことばがき)が付いていて、実際にそこでの体験を元にして詠まれたということになっています。しかし、この説明を鵜呑みにすることができますか。
たとえば、です。その関所のすぐ近くに住んでいたとしても、そこを通る人が「行く」のか「帰る」のか、「知る」同士か「知らぬ」関係か、どうして分かるのでしょうか。いちいち確かめたはずはないでしょうし、見た目だけで判断できるものでもありません。こういうウロコにだまされてはいけません。
〔ウロコ1〕「これやこの」
この表現が歌の初句に来た場合、慣用的な感動表現となります。文法的に、「この」は結句の「逢坂の関」を修飾しているともみなせますが、「これやこの」だけで、「百聞は一見にしかず」の驚きを表わすのです。思いがけず、探していた物を見つけた時に、「これだよ、これ!」と口にするようなものです。
ところが、この句は、多くの注釈書で、「これがまあ、あの、」と訳され、「この」が「あの」に置き換えられているのです。しかし、「この」は昔から「この」のままであって、「あの(古くは「かの」)とは置き換えられません。反復的な語呂も含めて、1つの独立した感動句とみなすゆえんです。
では、「これやこの」のように、驚いたのはなぜでしょうか。それは、「逢坂の関」とは、まさにその名前の通りの場所であるということです。
〔ウロコ2〕「別れては」
「別る」の主語は何だと思いますか。
この歌の語順通りならば、直前の「行くも帰るも」つまり行く人も帰る人もとなりそうですが、しっくりきません。「行くも帰るも」と並列される「知るも知らぬも」のほうは「逢ふ」だけ?ということになってしまいます。
「別れては」と来たら、次に予想される表現は、「また会う」ではないでしょうか。それに相当するのが、結句「逢坂の関」の「あふ」です。そして、この「別れてはまた会う」に当てはまるのが、「行くも帰るも」だけでなく、「知るも知らぬも」の人々です。
それにふさわしい語順にするとしたら、「行くも帰るも、知るも知らぬも、別れては逢ふ、逢坂の関」となります。この歌では、体裁を整え、表現上のバランスを考えて、入れ換えたのでしょう。
〔ウロコ3〕「逢坂の関」
関所としての実態はとっくの前になくなっていたのに、人と人が別れてはまた会う場所を象徴する地名・歌枕、つまり言葉としてのみ生き続けた場所が、「逢坂の関」です。
そこに、「会者定離」という無常観を見る捉え方もありますが、そのような思想とは関係なく、出会いも別れも人生における大きなドラマであり、それが「逢坂の関」だからこそ、そこを舞台に繰り広げられるということでしょう。
このような、さまざまな人生ドラマを、あたかも間近で見て思い知ったかのように見せるところが、この歌のねらいどころなのです。そう考えると、案外、後撰集のもっともらしい詞書も、その演出の1つだったのかもしれません。