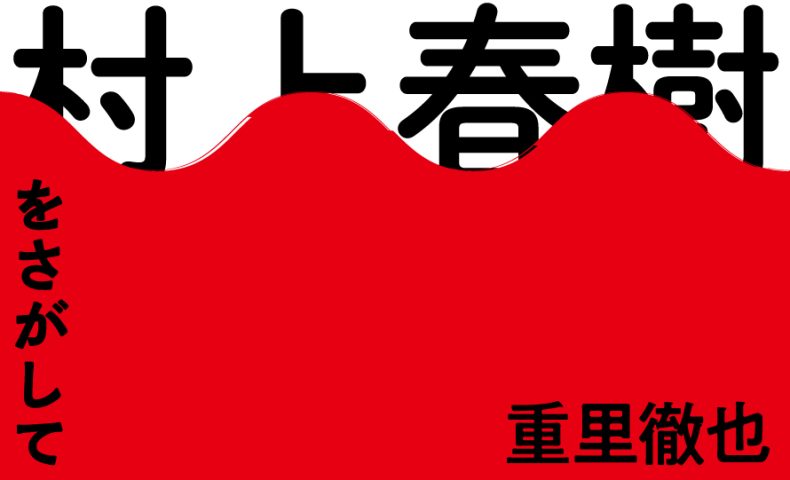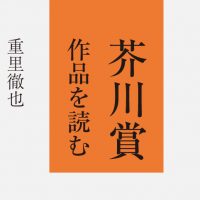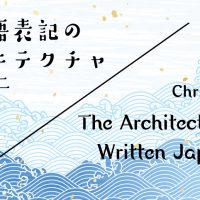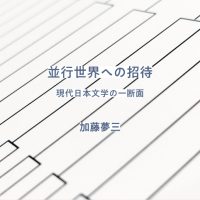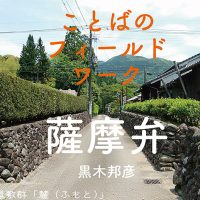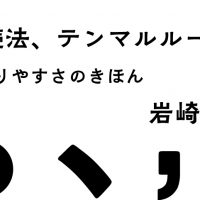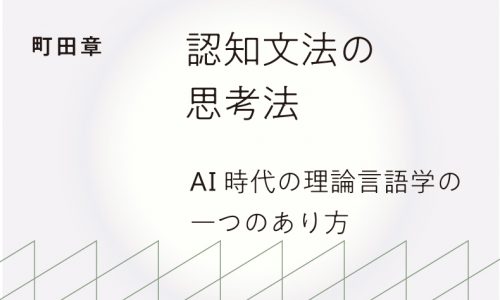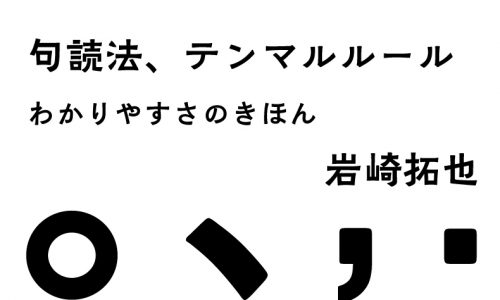村上春樹はなぜ、こんなに人気があるのだろう。今年四月は「村上春樹月間」とでも呼ぶべきにぎやかさである。NHKで『神の子どもたちはみな踊る』所収の短編小説四本がドラマ化、NHKのEテレ「100分de名著」で沼野充義が長編小説『ねじまき鳥クロニクル』を解説、「新潮」五月号に新作短編『武蔵境のありくい』発表、長編『街とその不確かな壁』の文庫化など、話題に事欠かない。
SNSでも、村上のことはよく話題になっている。X(旧ツイッター)のスペース(音声によるコミュニティー)や各地の読書会でも、しばしば、村上作品について語られている。だいたい、文芸雑誌に短編小説が発表されるというだけで、掲載誌が書店で平積みにされたり、話題になったりする小説家は日本で村上春樹だけだろう。
こういった動きについて、全てをフォローし、いずれ、そのいくつかはこの欄で取り上げたいと思う。ただ、今回は村上の人気の理由について、ある意味では素朴な視点から考えたい。
取り上げるのは仁平千香子の『読めない人のための村上春樹入門』(NHK出版新書)だ。仁平は一九八五年、福島県生まれ。東京女子大学卒業後、オーストラリアのウーロンゴン大学で修士号、シドニー大学では村上研究で博士号を取得している。
この本は、なぜ村上春樹はこんなにも人気があるのか、という問いに答える一冊とも読める。この問いを文学の外から、いわば、人生や生活や社会の側から論じているように思えるのが面白い。
この本の主張の一つを思い切り乱暴にはしょっていうと、現代の人々は自由に生きたいと思っている、しかし、なかなかそうはいかず、不自由に耐えて人生を送り、やがて死んでいく。ところが、村上春樹の描く主人公はリスクを覚悟して自分の生き方を大切にし、流されずに自身であり続けようとする。自分の自由に価値を置いている。そこに多くの人が惹かれるというのだ。なかなかできないことだからだろう。少し四十三ページから引用しよう。
村上作品の主人公たちは、自分のルールを尊重し、個であり続けようとする潔さがあります。それは固定されていない自分を引き受ける潔さです。固定されていない不安定な自分を引き受けなければならない不自由な世界で、自由でいることを諦めない意志の強さの表れでもあります。そんな主人公たちの姿に、読者たちは憧れを感じるのでしょう。
これは説得力のある指摘のような気がする。多くの大人はシガラミの中で生きている。自分の偏差値に見合った教育機関で学び、入れる企業等に就職し、組織の一員になったら、組織の規則に従って働く。転職しながらキャリアアップする生き方がよく話題になるが、それは条件のいい組織、少しでも自分の自由を実現できる職場を探している動きと考えられるだろう。
この本は作品中の主人公の生き方だけでなく、村上自身の人生の選び方にも注目する。それも面白い。大学在学中に学生結婚をし、大きな借金を抱えて自らジャズ・バーを開く。こだわりの家具と音楽。ところが三作目の勝負作『羊をめぐる冒険』を執筆するにあたって、店を閉める。東京の住まいも引き払う。生活を根っこから変えて、長編小説に集中する。周囲の反対を押し切って、退路を断って、自分の自由を追求してきたわけだ。世間が肯定する生き方をせずに、世の流れに乗らないで生きてきた。
おそらく、メジャーになってからも、文学賞の選考委員をしないとか、テレビのコマーシャルに出ないとか、あまり講演をやらないとかも、ここに含めていいのだろう。とても自分の生き方を通す人なのだ。自身の自由を大切にする人なのだ。
仁平のいう通り、村上の描く主人公たちは、消費社会や競争社会、マス・メディアから意図的に距離を置き、それらを冷静に観察している。社会や状況をいつも相対化してみている。この視点が自由を得る契機に違いない。
もう一つ。村上が考える自由とは、思考や行動を制限する外部の何かから解放されているという意味での自由の他に、自分が不自由であることに気づき、そこから距離を置くための行動ができる自由も意味しているという仁平の指摘も見逃せない。
仁平によれば、悪しき物語(たとえば、オウム真理教の物語)は単純で、相手に疑問を持たせない。村上の紡ぐ物語は複雑で相手に思考を促す。前者が自由を縛るのに対し、後者は自由の本質を探る旅へと誘うのだ。
村上春樹の小説が世界中で人気を集めているということは、世界中の人々が心の底で自由を求めていることの表れだということだろう。この指摘は単純だが、明快に村上作品の魅力の中心にあるものを照らし出しているように思う。シンプルだが、ズバッと村上作品の魅力の本質を言い当てているのではないだろうか。
身近な生活や人生から、もっと広い社会や政治のあり方まで、意識的か無意識的かは別にして、世界中の人々が胸の奥で抱いている自由というものへの渇望が、村上作品の人気の理由ではないかというのだ。
しかし、自由はとても困難だ。人間という動物は、ほんとうは自由など求めておらず、むしろ何かに従属することを欲しているのではないかとしばしば考えてしまう人は少なくないだろう。私もその一人だ。人間はいざとなったら、苦しい自由より、安楽な不自由を選ぶものだと思っている。困難を耐え忍ぶ自由より、ごはんがしっかり食べられて、寒い夜は暖かい部屋で過ごせる従属を選ぶのではないかと考える。
自分のめざすべき総合小説の例として、『カラマーゾフの兄弟』を挙げる村上が、そんなことに思いが至らないわけがない。人間がいかに自由を忌避し、不自由が好きな存在かということを知ったうえで、自由を求める人物を描くというのが村上の姿勢のはずだ。そして、読者は不自由な人生に不満を感じながらも、村上の小説を読んで、心の底にある自由への願望を刺激されて、共感するのだろう。
仁平の本ではいくつもの長編小説についても、魅力的な指摘がされている。ここでは紹介しきれないが、さらに村上について、この人のまとまった考察を読みたいと思った。
最後に、自由の実践のために村上がどのような意識の習慣を持っているかについて、仁平が主張していることを書きとめておこう。三つある。
直感に従うこと
情報という「荷物」を多く持たないこと
集中力を高めること
いずれも、言うはたやすく、行うは難しいことだ。ただ、村上作品の愛読者なら、なるほどと納得するのではないだろうか。