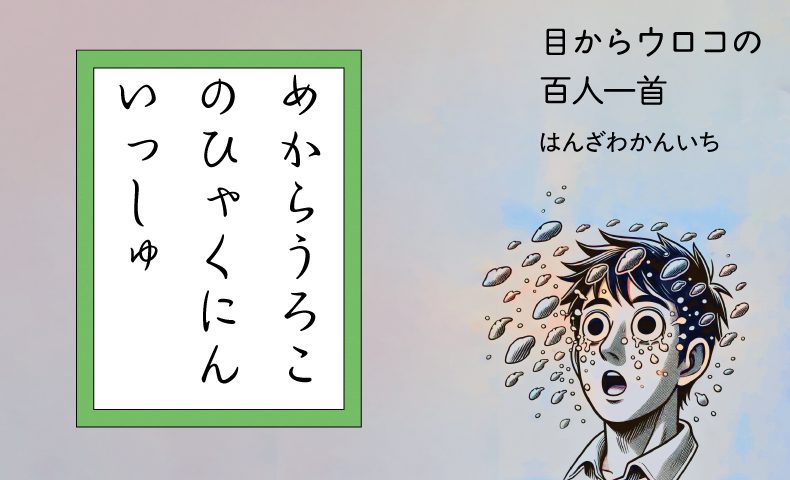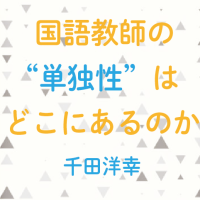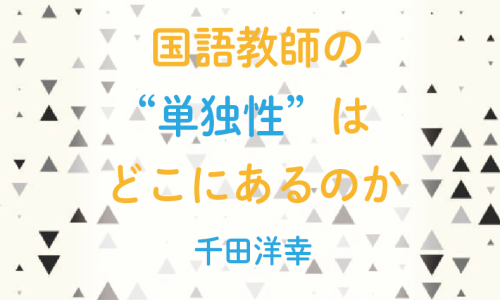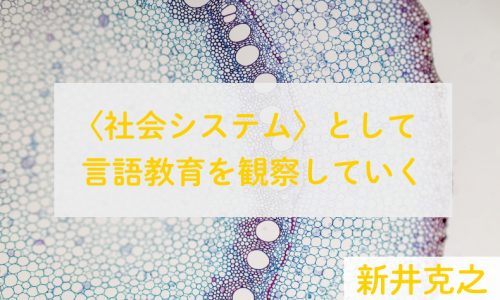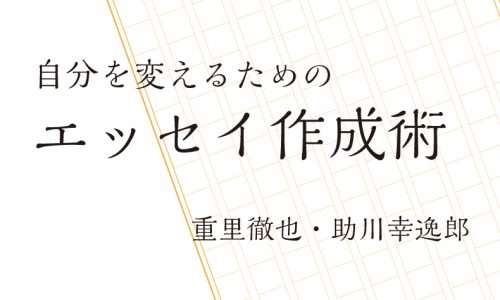山川に風のかけたるしがらみは流れもあへぬ紅葉なりけり
この歌のように、1首全体で、第三句までが「は」、結句が「なりけり」という、「AはBなりけり」という1文の表現形式になっているのは、「なりけり」構文と呼ばれています。この形式によって見立てを表わしますが、見立てられるものがAになることもBになることもあります。この歌ではBに相当する「紅葉」がAの「しがらみ」に見立てられていることになります。
それだけのことなら、大した問題はないのですが、思いがけない逆転があります。
〔ウロコ1〕「風のかけたる」
上三句は、「風」ガ「山川」ニ「しがらみ」ヲ「かける」という関係で成り立つ表現です。「山川(やまがは)」は、山の中を流れる川つまり谷川であり、「しがらみ」は次の〔ウロコ2〕に示すように、川水の流れを塞き止めるための柵です。
その柵は、それによって川の水量を調整し利用するために、人間が作って設置するものです。風がかけるものではありませんが、風が木の葉を大量に吹き散らして、それが川に落ちて1個所に溜まり、流れを塞き止めるということはありえるでしょう。その自然の成り行きを、この歌は、風があたかも意図的に行ったことであるかのように、擬人的に表現しています。
じつは、この表現の中に、この歌が見立ての歌であることをあらかじめ示す仕掛けがあります。人ではなく風がかけた「しがらみ」って、なーんだ、という謎かけです。
〔ウロコ2〕「流れもあへぬ」
この句は、流れ切らないという意味です。流れ切らないというのは、最後までは流れ着かないということではなく、その全部が流れるわけではないということです。
何が流れ切らないかと言えば、普通に予想されるのは、川水のはずです。なにせ、そのために「しがらみ」を設けるのですから。ところが、なのです。
〔ウロコ3〕「紅葉なりけり」
「流れもあへぬ」が連体修飾しているのは、結句の「紅葉」ですから、紅葉が「流れあへぬ」ということになります。しかも、この「紅葉」が上三句の謎かけの答えになります。風が作ったしがらみとは、紅葉のことでしたー、というわけです。
ただ、そうなると、そもそも紅葉が「流れもあへぬ」状態になったのは何によってかが気になります。それは、おのずからとしか考えようがありません。
「山川」は、山間を流れる川の最上流であり、幅が狭く流れが浅く速いのが普通ですから、そこに大量の木の葉が落ちたら、全部は流れずに溜まってしまうことが容易に推測されます。つまり、しがらみがなくても、紅葉は「流れあへぬ」状態になるということです。
それが今度は逆転して、溜まった紅葉がしがらみのようになって、水を「流れあへぬ」状態にしているように見えるということです。まあ、実際の状況としては、紅葉も水も詰まっているわけであって、どちらがどうというのは、見方しだいでしかありません。
さて、この歌における見立ては、自然物の紅葉を、人工物のしがらみとみなすという点で、面白さは多少あるかもしれませんが、なーんだ、それだけ、という感じでもあります。
むしろ、定家のツボにはまったのは、この歌の見立て内容とはうらはらに、表現そのものの、ケチの付けようがないほどの、流れの良さではないでしょうか。