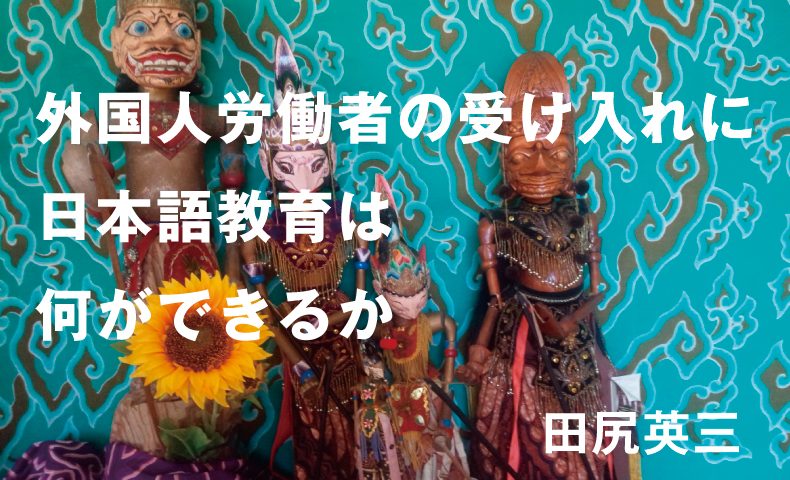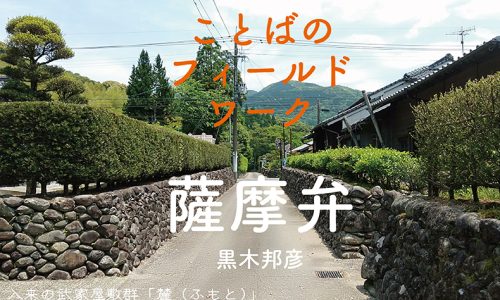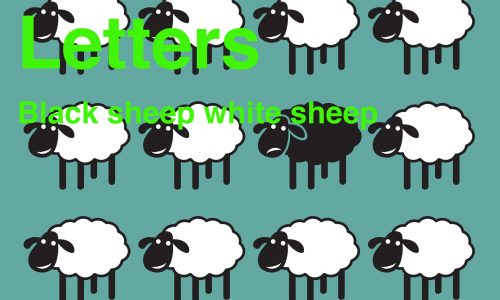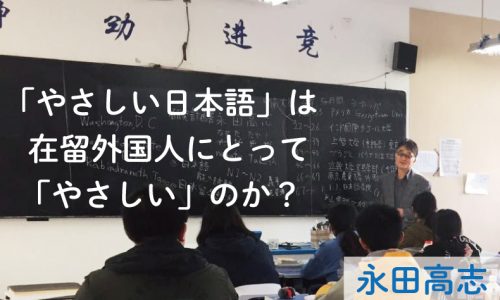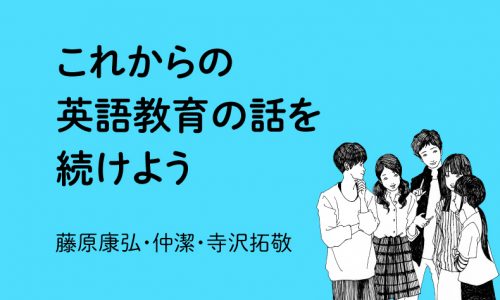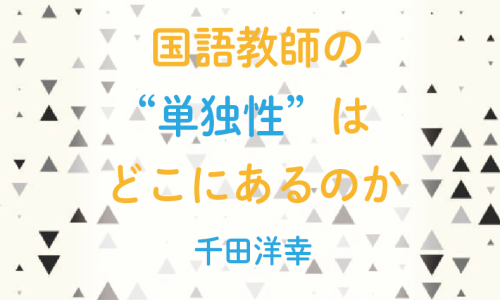★この記事は、2025年5月21日までの情報に基づいて書いています。
田尻が編者になっている『外国人受け入れへの日本語教育の新しい取り組み』(ひつじ書房、以下『取り組み』と略称)出版に関わり、時間的な余裕が無かったために、59回の記事を書いてから時間が空いてしまったことをお詫びします。
今回は、まず千田さんが田尻のコメントに対して意見を書いているので、その件について最初に簡単に触れます。
今回の中心的なテーマは、2024年度に入っての日本語教育施策の整理と、日本語教育施策の新しい動きについてです。
1. 千田さんの意見に対する田尻のコメント
千田さんが「国語教師の“単独性”はどこにあるか」第7回で、田尻の「外国人労働者の受け入れに日本語教育は何ができるか」第59回での田尻のコメントに応えています。ただ、話がかみ合っていません。
たとえば、田尻は千田さんの次のような文章を前提に「現在の日本語教育に理論的な裏付けがないと、どうして言えるのでしょう」と書きました。
このような例が日本語教育(学)の領域でどれほど存在しているのか、私は詳細を知らない。だが、自分のせまい「現場」にひたすら閉じ籠って実践をつづけるかぎり、時世に流されながら、その時々の言語政策の代弁者をつとめて生涯を終えるほかないことは、小出の一事例を観察するまでもなく、日本の言語教育の歴史をふりかえってみればあきらかだ。
(「国語教師の“単独性”はどこにあるのか」「第6回 「ひたすら実践に励むこと」の陥穽」千田洋幸 より)
これに対して、千田さんは「私がまったく書いてもいないことを反論の材料にしている」と書いています。
また、田尻と小出さんの関係性に対して説明しておいたほうが良いと考えて書いたことに対して「田尻はどうしても小出を救い出したいらしく、(中略)というエピソードを紹介したり、(中略)私が記事中でのべたことをまったく理解しなかったらしい。(中略)田尻はことごとく批判の対象としたことをみずからの記事中で実演している滑稽さに気づいているのだろうか。」のように理解している。
そして、小出さんについては「植民地責任・戦後責任という観点からみるかぎり、彼女はなんら責任を果たすことなく、ぬくぬくと戦後社会を生き延びてしまったにすぎない」と、前回と同じ評価をしています。
千田さんがアジア・太平洋戦争中やそれ以後の日本語教育に対して、或る考えを前提にしている限り、田尻の考えとはかみ合いません。その点を言い出せば、相当の量の文章をやりとりする必要があり、その結果お互いの立場が分かりあえるという保証はありません。
したがって、千田さんが「これ以上に言葉を連ねることはしない」と書いているように、田尻もこれ以降千田さんの文章に触れることはありません。ただ、反論が出来ない物故者の業績に触れる時には、それなりの心遣いが必要であるということは言っておきます。
2. 2024年度の日本語教育施策の整理
(1)日本語教育機関の認定状況
2024年度には、2回の認定結果が公表されましたが、以下ではその内容について、田尻の考えを述べます。第1回については、「未草」第56回で詳しく扱っていますが、ここでは1回目と2回目を比較します。
- 第1回目 認定日 2024年10月30日
申請機関数は72機関
課程分野別では、留学70機関、就労3機関、生活1機関
機関種別では、法務省告示機関が20機関、大学別科等が1機関、その他が51機関
認定となった日本語教育機関は22機関(認定率30.5%)
課程分野別では、留学22機関、就労0機関、生活0機関
機関種別では、法務省告示機関7機関、大学別科等0機関、その他15機関
(法務省告示機関とその他の認定率は、それほど差がありません)
不認定となった機関は3機関
課程分野別では、留学3機関
機関種別では、その他3機関
審査中に取り下げを行った機関は36機関(取り下げ率50%)
- 第2回目 認定日 2025年3月31日
申請機関数は48機関
課程分野別では、留学46機関、就労2機関、生活0機関
機関種別では、法務省告示機関16機関、大学別科等0機関、その他32機関
認定となった機関は19機関(認定率39.6%)
課程分野別では、留学17機関、就労2機関、生活0機関
機関種別では、法務省告示機関5機関、大学別科等0機関、その他14機関
(法務省告示機関よりその他のほうが多く認定されている)
不認定となった機関は0機関
審査中に取り下げを行った機関は29機関(取り下げ率60.4%)
法務省告示機関だけでも全国に800機関以上あるのに、第1回・第2回を合わせても36機関しか申請をしていません。また、取り下げ率も大きくなっています。これは、明らかに日本語教育機関の準備不足を示しています。また、多くの日本語教育機関は、他の機関の申請状況を「様子見」しています。
2024年5月の日本語教育機関への留学生の在籍者は、過去最大の107,241人となっているのに、機関の側の新制度への消極的な取り組みがはっきりしています。
(2)日本語教員養成機関の登録状況
登録結果については、「未草」第56回で詳しく扱っています。ただ、そこでは、田尻のコメントは書きませんでした。ここでは、2024年度施策状況として、大学等(大学と大学院を含む)の結果の説明をします。
公表された資料では、いくつの大学等の機関が申請したのか分かりませんが、登録された大学等20機関です。審査中取り下げた機関は3機関で、公開された資料に明示されていませんが引き算をすれば残り4機関が不登録となります。このうち、大学等が何機関かは不明です。登録された機関のうち、京都ノートルダム女子大学は2026年の学生募集の停止を公表しました。第2回目の申請機関は28機関です。
問題は、まだ多くの大学等の機関が申請をしていないことです。これらの大学等は、経過措置期間ぎりぎりまで他大学の申請状況を見てから申請するように見えます。そのような状況は、現在大学等に在学している学生やこれから日本語教員を目指して大学等を受験する学生に対して不親切ではないでしょうか。日本語教員が国家資格となった現在、大学等は基礎試験免除校かどうかをホームページで公表すべきです。日本語教員養成をしている大学等の積極的な取り組みを期待します。
(3)日本語教員試験の結果
詳しい数字は、未草第57回に書いています。ここでは、その時、触れなかった点を述べます。
全試験免除者(経験者講習修了者)は、5,598人で、全試験受験者と応用試験受験者の合計5,093人より多くなっています。現職者がより多く仕事を続けられるように配慮したと思われます。2024年5月1日現在の日本語教育機関での外国人留学生数は過去最多となっています。コロナ禍でかなりの日本語教師が離職し、現在もあまり戻ってきていないことを考えると、できるだけ早く適正な数の有資格の教師を日本語教育機関に送り込まないと授業の質が担保できません。この際、日本語教育機関に在職する登録日本語教員は昇給させるというような対応を取ってもらうと、より多くの教師が日本語教員試験を受ける動機付けになると田尻は考えます。
3.『日本語教育』190号の気になる論文
上に示した日本語教育機関の認定申請や日本語教師養成機関の登録申請の少なさの基底にある考え方は、『日本語教育』190号(2025年4月)の特集の論文にも見られます。この特集は「日本語教師養成・研修の最前線とその課題」となっていますが、田尻の見るところ、浜田さんの「『日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教師養成機関の認定等に関する法律』について」という論文以外は、今実施されつつある日本語教育施策についての言及はあまりありません。
ここでは、全体をまとめる位置にある巻頭論文を扱うことで、日本語教育学会の特集号部会の意図も扱うことにします。
扱う論文は、南浦涼介さん・瀬尾匡輝さん・田嶋美砂子さんの「『教育としての統治』時代の日本語教育―統治への対応か陶冶への応答か―」です。
この論文は、特集部会の長谷川守寿(部会長)さん・木谷直之さん・中俣尚己さんの「本特集の内容」によれば、「南浦ほかの論文は、日本語教育の法整備が進んでいる現場を『就労・入国管理としての統治』から『教育として統治』への変化と捉え、その『統制』的な側面を強めつつある中での日本語教師教育について論じています」と書かれています。つまり、この部会のメンバーは、南浦さんたちと同じように、現在の日本語教育施策が実施されつつある状況を「『統制』的な側面を強めつつある」と捉えていることになります。このことにより、この『日本語教育』の特集は、現在の日本語教育施策について批判的な立場を取っていることが分かります。これは、学会誌の特集号を編集する立場として適正でしょうか。このように、現在を統制されつつある時代と捉えているのは、学会誌編集委員全員の共通した考えでしょうか。田尻は、学会誌としての性格に疑問を感じます。
日本語教育の施策は、今までの文化庁の会議で検討されて来ています。その会議には、日本語教育の専門家が多く入っています。会議の内容も公開されています。突然文部科学省から押し付けたものではありません。その動きに対して、過去数年間長谷川さんたちがこのような意見を表明したことはあったのでしょうか。田尻は長谷川さんの過去10年ほどの論文をチェックしましたが、そのような意見を書いたものは見つけ出せませんでした。南浦さんは、中川祐治さんたちと「民主化のエージェントとしての日本語教育」(『教育学年報12』、2021,世織書房)という論文を書いています。
学会誌の特集担当者が、今まで日本語施策について自分の意見を出さずに、この時期になって、文部科学省の施策に批判的な姿勢を取ることを特集の前提として学会誌の特集を組むのは、いかがかと思います。
この南浦さんたちの論文の最初の部分は、この特集部会の説明に引用された表現が見られます。たとえば、「施策そのものの根底にある統治の論理」、「公共性の面が強まると質の担保のありかたも規制の面が出てくる。近年の機関認定はこうした流れの一端とも見られる」、「公教育としての学校をめぐる質の担保は、どちらかというと『事前統制』という形が取られてきた。既に挙げた日本語学校告示校の設置基準などはまさにそうした事前統制にあてはまる」、「こうした目標を掲げてチェックしていく発想は、新公共管理(New Public Management)や新自由主義・市場主義との接点も大きくある。例えば日本語学校の質の担保を考えたとき、それを単純な数値による成果(大学合格者数や日本語能力試験の通過率など)といったもので測ることは事後統制的であると同時に、市場主義的な発想とも強い結びつきを持っているといえる」など、決めつけと言える表現が多く、もう少し丁寧な論理で説明してほしいと思っています。
この論文ではこの後、クマラヴァディウェル、Kiely、Freman、Gray、Farrell、Hallなどの説を列挙し、最終的にはクマラヴァディウェルを引用し、「『批判性を伴った変革的知識人としての教師』を養成するという目的と、その目的を果たすための内容を検討していかなければならないであろう」という抽象的な結論に達しています。
そして、「近年、そもそもさまざまな公共的な組織の運営は新公共管理やエビデンスにもとづいた政策の発想で行われ、日本語教育の養成においても事前統制による質の管理と事後統制による管理の二重のチェック機能が強化される向きがあった。日本語教師の養成機関に対しても、とりわけ認定日本語教師の養成の機関資格をめぐっては事後統制としての認定チェックが大きな力を持っている」とありますが、その部分の後半は、「認定」と「登録」を間違えていています。「認定」と「登録」を取り違えているのは、施策自体を理解していないことを示しているのではないでしょうか。
そして結論部分ですが、「施策立案者(田尻注:誰のことを指すか不明)と研究者と学会が『今こそ手を取りあって―』と、ともすれば一体化しかねない状況と言説の中であるからこそ、ここが最前線のぎりぎりの際ではないかと考える」となっています。田尻には何を言っているかよく分かりませんが、特に大事な結論と思われる箇所が「ぎりぎりの際」という、論文とは思えない曖昧な口語表現を使っているのは理解できません。
南浦さんたちは、どこかに施策を作っている人がいて、その人と研究者や学会は別の立場にいるという、実際にはありえない構図で、現状を理解しているようです。
田尻には、南浦さんたちが今の日本語教育の現場を高みから見下ろしながら批評しているとしか思えません。この箇所は、執筆者全員だけでなく、特集部会のメンバーも目を通していて問題がないと考えたのでしょうが、はたしてこんな曖昧な態度や間違った記述で「統制」と戦っていくと考えているのが、学会誌の特集の結論でしょうか。田尻には、大いに疑問に感じます。
4. 外国人児童生徒等への日本語教育の方向性
(1)これまでの施策の流れ
外国人児童生徒等の日本語教育はどのように行われて来たのかは、『取り組み』の12章の浜田麻里さんの論文「『児童生徒等』に関わる施策について」を見ていただきたい。特に、201・202ページの「表1 2009年以降の主な外国人児童生徒施策」は、これまでの流れが整理されています。
上に挙げた『日本語教育』190号でも、中川裕治さんが「児童生徒等に対する日本語教育人材研修事業の成果と課題―文化庁委託研修事業を中心に―」が掲載されています。そこでは、2001年からのJSLカリキュラム(田尻注:これには日本語教育学会の外国人児童生徒等の日本語教育の多くの専門家が参加しました。中川論文では扱われていませんが、2014年に「特別の教育課程」が施行されて以降、教員免許を持っていない日本語教師は「日本語教育指導支援員」として単独では教壇に立てないシステムが作られました)、2014年の対話型アセスメントDLAなどを受けて、日本語教育人材研修プログラムが行われて来たのが委託事業の流れだと理解されて来たと思っていました。
外国人児童生徒等の日本語教育は、文部科学省総合教育政策局国際教育課が、担当しています。日本語教育課ではありません。
(2)外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議
この会議は、第1回が4月4日に、第2回が4月25日に開かれています。そして、会議名は「外国人児童生徒等の教育」となっていますが、中心的なテーマは日本語指導です。日本語教育課ができたにも関わらず、外国人児童生徒等の日本語教育は国際教育課となっています。この会議には、日本語教育の専門家として、齋藤ひろみさんや浜田麻里さんが入っています。
田尻が驚いたのは、「資料3 外国人児童生徒等教育の現状と課題」の「1.指導方法の深化・充実」に「文化的言語的に多様な背景を持つ外国人児童生徒等のためのことばの発達と習得のものさし(略して「ことばの力のものさし」)という能力評価の基準が示されたことです。資料全体は、従来の施策を引き継いだとして、それまでの取り組みを列挙しています。そして、この基準は、第2回の会議で詳しく説明されました。「資料6 小島委員発表資料」に「文化的言語的に多様な背景を持つ外国人児童生徒等のためのことばの発達と習得のものさし パッとわかるまるわかりガイド」がそれです。
この基準が出て来た流れを見ておきます。
2022年度と2023年度の予算に「児童生徒の日本語能力把握の充実に向けた調査研究」という項目が予算化されていました。2年間で約7千万円です。そこでは、「文部科学省が開発した『外国人児童生徒のためのJLS対話型アセスメントDLA』のような客観的な評価ツールを活用する学校はまだ少ない。これは、日本語能力評価に時間を要することや、評価ツール活用の経験を積む必要があることが要因と考えられるため、学校において活用しやすいツールとすべく、評価方法の改善が求められる」とあります。田尻は、DLAに対して、ここで書かれているようなまとまった批判が一般化しているとは思っていませんでした。たとえば、前に引用した『日本語教育』190号の中川祐治さんの「児童生徒等に対する日本語教育人材研修事業の成果と課題―文化庁委託研修事業を中心に―」でも、上に引用したような批判は書かれていません。しかし、DLAを開発した同じ東京外国語大学が、また2023~2024年度文部科学省委託事業として「日本語能力評価方法の改善のための調査研究」を行っていました。2025年2月15日には東京外国語大学府中キャンパスで「日本語能力評価方法の改善のための調査研究事業 事業報告会議」が開かれています。報告書は、以下のURLで見ることができます。
https://www.tufs.ac.jp/institutions/cemmer/NEWS/itaku/20250507_1.html
全600ページを超える大部な資料です。
この資料は、4月25日の題2回の有識者会議で東京外国語大学の小島祥美さんによって詳しく扱われました。「文化的言語的に多様な背景を持つ外国人児童生徒等のためのことばの発達と取得のものさし(略して『ことばの力のものさし』)というものがそれです。ここでは、田尻はあえてこの新しい基準に対してコメントしません。まだこれからの流れがはっきり見えていないからです。ただ、国際教育課では、この「ことばの力のものさし」を中心に外国人児童生徒等の日本語教育を進めて行こうとしているように見えます。田尻には、また新しい評価基準を使わなければいけないと考える教育現場の困惑が感じられます。
このような大きな評価基準の見直しは、上述の中川論文では全く扱われていません。学会誌の特集号編集の段階で、執筆者や編集委員は誰一人としてこの基準のことを知らなかったのでしょうか。この論文執筆の時点では、すでに東京外国語大学の委託事業は終わっています。もし知らなかったとすれば、学会誌として最新の情報を提供できていないことになります。これはこれで、また大きな問題です。
この第2回の会議では、もう一つ新しい指導方法が提言されています。それは、「『資質・能力の育成のための新たな日本語指導』(仮称)に向けて~表面的日本語指導からの脱却~」です。これについては、以下で扱います。
(3)教育課程部会での外国人児童生徒等の日本語教育
ややこしいことに、外国人児童生徒等の日本語教育は、また別の部会で検討されています。第5回の中央教育審議会教育課程部会 教育課程企画特別部会の配布資料にその資料が出て来ます。この部会は、学習指導要領の改定に伴って開かれています。担当は、文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室です。
この部会では、第4回までは外国人児童生徒等の日本語教育は扱っていませんでした。ところが第5回になると、「資料1―1」としてトップで扱っています。そこには「ことばの力のものさし」ではなく、「資質・能力の育成のための新たな日本語指導」(仮称)」として、「母語の力も活用しながら、日本語で各教科等を学ぶことができる」と説明しています。従来の外国人児童生徒等の日本語教育は、「表面的な日本語指導」で、「母語では理解できても、日本語では授業に参加できない」と書かれています。従来からも、生活言語能力は習得できても学習言語能力はなかなか習得できないと言われてきました。ただ、ここで書かれているように、母語で学習内容が理解できても日本語では理解できないという状況は、従来の日本語指導の範囲ではないので、対応を考えにくいことです。2025年度この指導方法は、教育内容をまず母語で教えることになりますが、現場ではそのような教員を採用することは難しいのが実情です。
10年に一度の学習指導要領の改定に合わせて、従来の外国人児童生徒等の日本語教育を「表面的な日本語指導」として切り捨てて、新しい指導方法を決定することは現場に混乱をもたらすのは間違いないと田尻は考えます。
(4)夜間中学での日本語指導に関する調査
2025年度予算に「夜間中学における日本語指導ガイドライン作成のための調査研究」(新規、8百万円)が出ています。5月17日の共同通信などでは、この踏査を始めるという記事が出ています。記事では、調査結果を基に指導方針を作成するとなっています。担当は、文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課です。夜間中学については、以下のURLで資料が見られます。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/yakan/index.htm
現在、夜間中学で外国人を教えている教員は経験不足であるから、研修の必要性を訴えています。ただ、指導方針を決めるだけでは、問題は解決しません。
田尻が心配するのは、この事業で指導方針が決まってしまうことです。夜間中学で学ぶ生徒も、集住地区と散在地区に分かれています。教員配置を含めて、地域ごとの細かい支援が望まれます。当然、この事業は日本語教育課との連携が必要です。
文部科学省内だけでも、外国人児童生徒等の日本語教育は、上に述べたように担当部署が分かれています。縦割り行政の弊害が出ないように注目する必要があります。
※今回も書くことが多すぎて、大事な点について触れる余裕がありません。「未草」の読者は、情報を田尻まかせにするのではなく、自分で情報を集めてください。今、日本語教育には大きな変化が起きています。