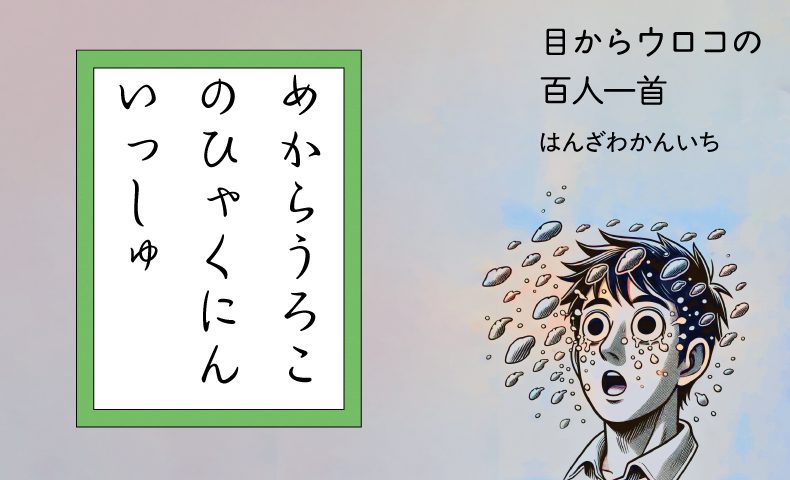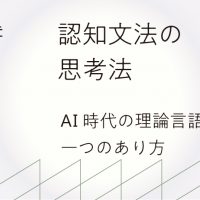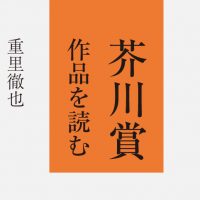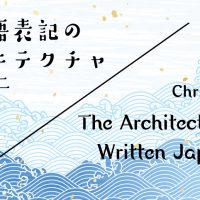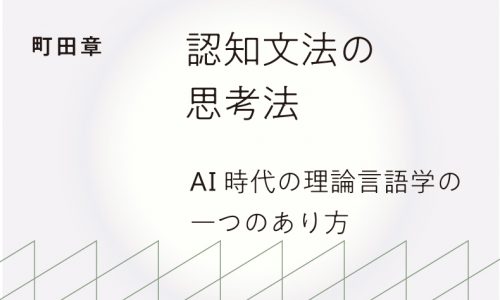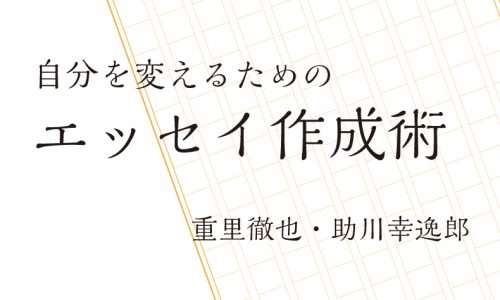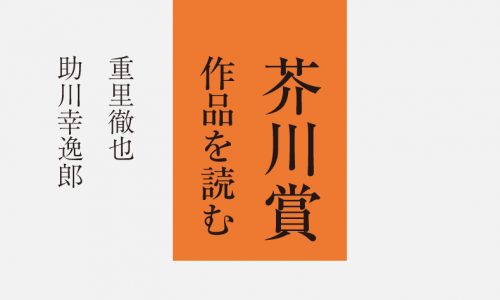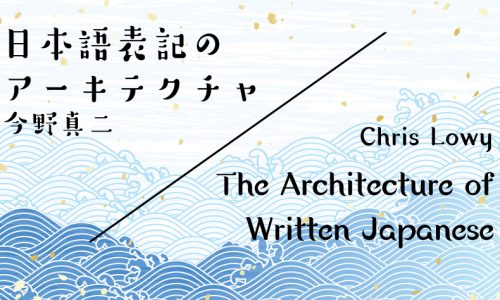花の色はうつりにけりないたづらにわが身世にふるながめせしまに
定家がザ・幽玄体と絶賛したのが、この歌です。伝説の美女・小野小町の作で、古今集の春歌(下)に収められています。春の、しかもその後半の歌ですから、春の代表的な景物である「花」(=桜)を詠むことがメインとなっています。さて、どんなウロコが付いているでしょうか。
〔ウロコ1〕「花の色はうつりにけりな」
「うつる」には、移る、遷る、映る、写るなど、いろいろな意味がありますが、ここでは、遷る、つまり時間的な変化を表わしているととれます。それが色に関してならば、普通は、好ましくない方、つまり色があせて、汚くなるということです。
今や当たり前のソメイヨシノという桜の新品種が作られたのは江戸時代後期で、それ以前の主流はヤマザクラ系の白い花でした。それが変色するとしたら、薄汚れ黄ばむことでしょう。もはや鑑賞には耐えられない状態です。
そのことを、「に」(助動詞)+「けり」(助動詞)+「な」(終助詞)という、完全に終わった感を示す表現で、二句切れにしているのですから、この第二句が当歌の中心ということになります。それにしても、そんな状態の桜の花を詠んで、どうするのでしょうか。
〔ウロコ2〕「わが身」
この歌の表現におけるいちばんの決め手は、第四句の「わが身」です。これがなければ、桜の花を惜しみ悲しむ、春の歌でしかありません。それが、たった1つ、「わが身」という表現があることによって、単に花を詠むものではなく、人の心を歌った歌になるのです。
今でも、女性はよく「花」にたとえられます。「花の色はうつりにけりな」が「わが身よ(世)にふる(経)」と重ね合わされれば、それは、そのまま加齢に伴う、女性の見た目の衰えを表わすことになります。
「わが身」とは、女性である詠み手自身に他なりません。
〔ウロコ3〕「ながめ」
「ながめ」とは、長雨のことです。長雨が続けば、桜の花は色が衰え、ついには散ってしまいます。ここに、第三句の「いたづらに」が利いてきます。この語は、無駄に、空しくという意味で、それでなくても、花期の短い桜なのに、降り続く雨のせいで、盛りを全うすることもなく、花は色変わりしてしまったということです。
そして、この「ながめ」に「わが身」が結び付くと、「眺め」の意味が生れます。「ながめ」が、長雨と眺めの掛詞になるのです。「眺める」と言えば、今は遠くを見ることですが、元は、ぼんやりと物思いをすることでした。物思いをする理由はいろいろあるものの、やはり恋愛関係でしょう。
これが「花の色はうつりにけりな」と、どのように関わるか。もう分かりますよね。恋愛に関して、ぐずぐずと思うばかりで決断しないでいるうちに、その機会を逸して、気が付けば、すでに容色は衰えてしまい、もう誰も相手にしてくれない、というわけです。トホホ。
このような、1首全体にわたる、「花」と「わが身」の照応ぶりは、自然と人事の重ね合わせが古典和歌における表現方法の基礎になっていますが、見事と言うしかありません。
ただし、あまりにも見事すぎて、何だか嘘っぽい感じがしなくもありません。そう思ってしまうのは、やはり詠み手が他ならぬ、小野小町だからという、思い込みのウロコのせいかもしれません。しかし、これがもし普通の女性が詠んだ歌だったとしたら、あんまりマジすぎて、ちょっと怖いかも?