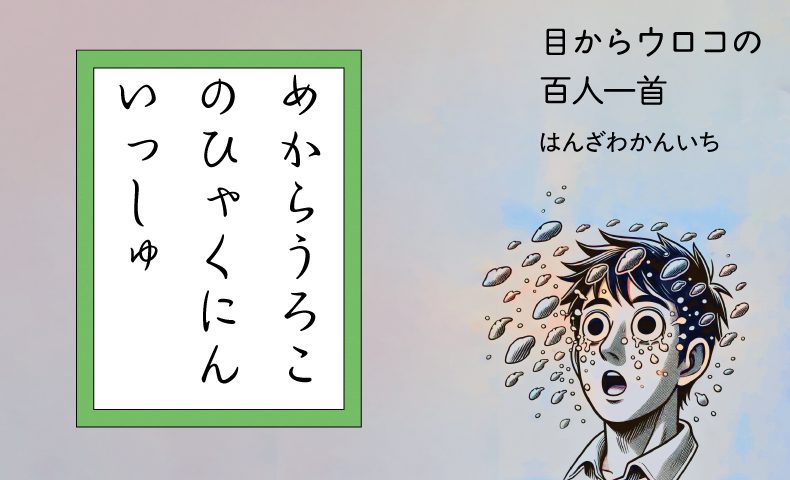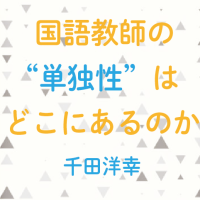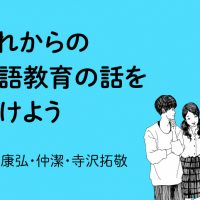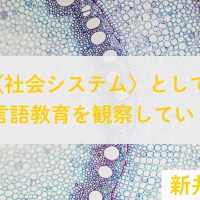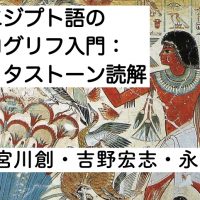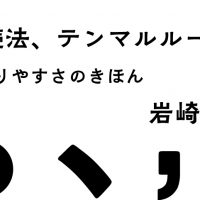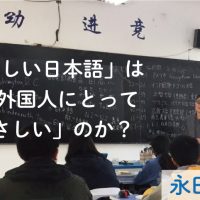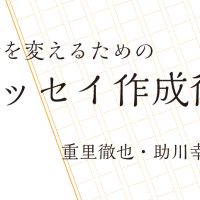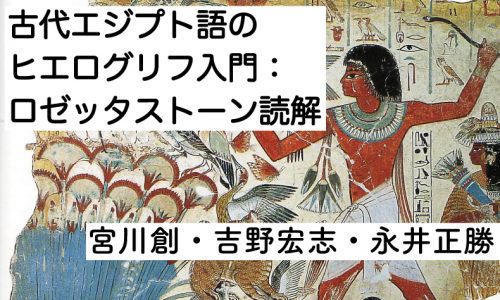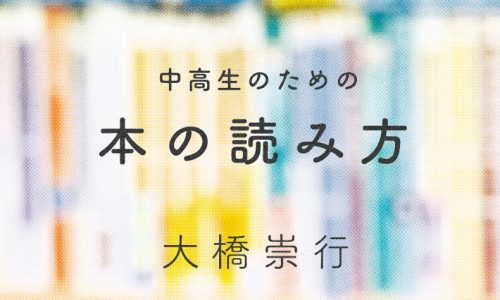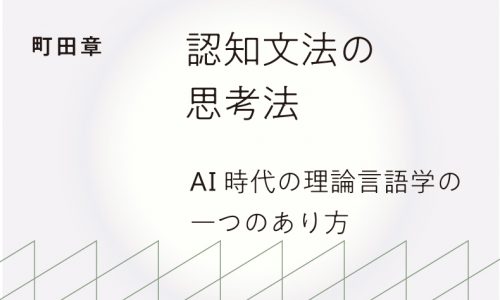天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも
あまりにも有名な歌であり、とくに説明が必要な言葉も見られない、じつに分かりやすい歌のように思われるかもしれません。しかも、この歌の詠み手が、遣唐使の阿倍仲麻呂であることも知っていれば、なおさらです。
以上、終わり。では、話になりませんから、何とか表現上のウロコを挙げてみましょう。
〔ウロコ1〕「天の原」
「天(あま)の原」は、大空のことです。わざわざこの表現を用いるのには、5音1句を構成するという、表現構成上の都合以外にも、それなりの理由があるはずです。2つ考えられそうです。
1つは、「天」のもつ、天つ神の世界というイメージです。地上に住む人間界とはまったくの別世界です。そこは、有為転変の激しい人間界とは異なる、永久不変の世界です。
もう1つは、「原」のもつ、広大というイメージです。それは人知・人力の及びようのない規模の領域です。
このような「天の原」だからこそ、この歌における気付きが実現しえたと言えます。
〔ウロコ2〕「ふりさけ見れば」
「ふりさけ見る」というのは、遠くのほうを、ちょっと上を向いて見ることを表わします。その対象がなにせ「天の原」なのですから、まさにその通りです。
ただし、以下に続く表現との関係から、次の2点に注意が必要です。
その1つは、天上の月は、ふりさけ見なくても、存在しているのに、なぜわざわざ「ふりさけ見れば」と表現したのか、という点です。それは、月そのものではなく、そのような行動をとった、他ならぬ詠み手自身にとっての月ということを示すためです。
もう1つは、そもそもそのような行動をとったのはなぜか、という点です。それは決して意図的・積極的な行動ではなく、たまたま何げなくだったと見られます。そうしたら、思いがけずも、月が目に入ったのでした。だからこそ、感じ入ることにもなったのです。
天上における月の位置は、「三笠の山に出でし月」のように、山と結び付けていますから、まだ上がって間もない頃と想定されます。真上を見て、ということではなく。ついでに言えば、その月はやはり満月こそがもっともふさわしいのではないでしょうか。
〔ウロコ3〕「出でし」
「出でし」の「し」は、過去の助動詞「き」の連体形です。「き」は現在と隔絶した過去であることを示します。つまり、三笠の山の月を見たのは、現在とはまったく異なる時期・状況にあったということです。この「き」1語だけで、それを物語っているのです。
そして、歌末の「かも」は、「き」による、そのような時期や状況の違いを越えて、月だけは昔と変わらないことに対する、格別の感慨を表わしています。それは、はるか昔への懐かしさからかもしれませんし、今も生きて、同じ月が見られることへの喜びからかもしれません。
以上のウロコをふまえて、押さえておきたいのは、その時の詠み手の心そのもののありようは表現されていないということです。どこで、いつ見ようが、月は月であって、変わりはないということだけなら、身も蓋もありません。その心のありようをうかがわせるのは、時間的・空間的なへだたり、つまり奥深さです。
紀貫之は古今集にこの歌を採用しただけではなく、土左日記にも、少し表現を変えて引用し、それをネタにして、歌心というものの普遍性を説いたのでした。