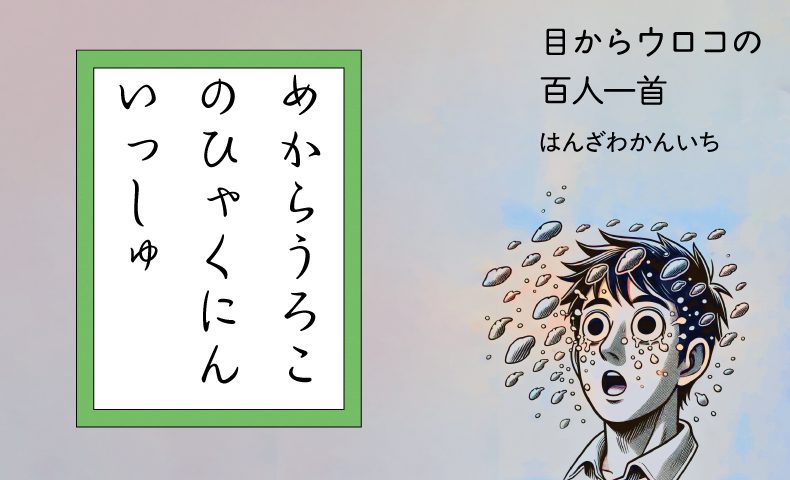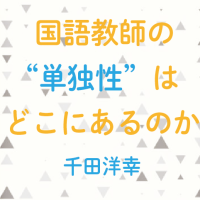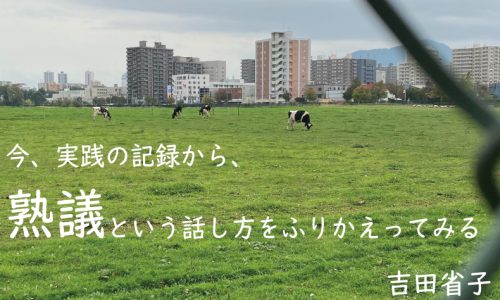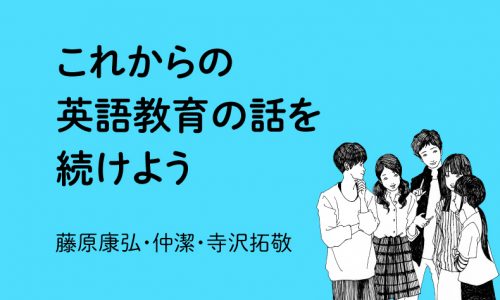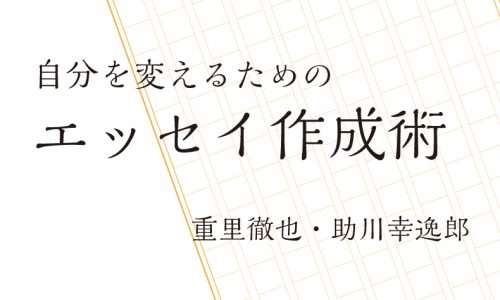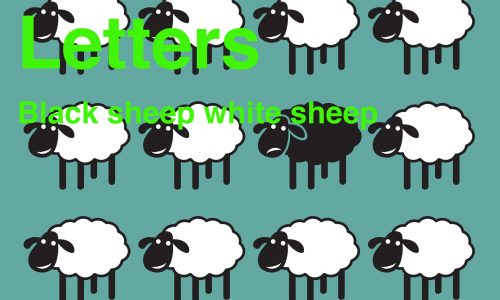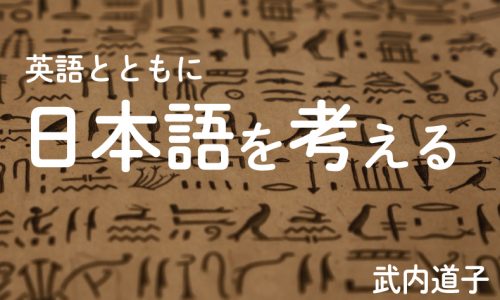みかの原わきて流るるいづみ川いつみきとてか恋しかるらむ
結句の「恋しかるらむ」という表現から、この歌が恋の歌であるのは明らかでしょう。出典となる新古今集にも「恋歌一」に載っています。「恋歌一」は、恋愛成就前の片恋の段階で、その思いがどれほど強いかを訴える歌が並んでいます。
この歌も同様なのですが、そのために用いられている「みかの原」や「いづみ川」という歌枕の関係付けにいろいろと問題があります。
〔ウロコ1〕「みかの原」と「いづみ川」
どちらも今も、京都府南部の、奈良県と接するあたりに実在する原と川(現在は「木津川」)です。とはいえ、この歌には、そこを詠歌の現場とするだけの必然性はとくに認められません。あくまでも歌枕としての使用です。
そのため、「いづみ川」までの上三句は、第四句の「いつみ」を同音反復によって導く序詞とされています。ただ、「みかの原」のほうは、地理的に「いづみ川」とつながるというだけの位置付けがされてきました。
〔ウロコ2〕「わきて」
「わき」には、「分き」と「湧き」の2説があり、掛詞とする説もあるようです。ただ、どちらにせよ、「みかの原」とは、意味・文法的にうまく結び付きません。
「湧き」のほうは、「いづみ(泉)川」が「みかの原」沿いを流れてはいても、そこが水源というわけではありませんから、みかの原から湧き出た川とはなりません。
いっぽう、「分き」は、下二段活用の「分け」とは違って、区別することを表わすので、川をはさんで「みかの原」を対岸の原と区別するという意になりうるとしても、なぜわざわざそのような区別をするのか、意図が分かりません。
となれば、「みかの原」と「わきて」以降は切り分けて考えるしかないでしょう。それに対して、「わきて流るる」という第二句は、続く「いづみ川」と、泉が「湧きて」、それが川となって「流るる」というつながりとして、何の問題もありません。
では、なぜ「みかの原」を持ち出したのか。それは「みか」(甕)という語のイメージを生かすためでしょう。「みかの原」からは、原のように大きい水甕が連想されます。初めは水量わずかだった泉が川となり、やがてそれがたっぷり溜まる水甕というイメージです。しかも、これを歌の冒頭にポンとおいて、そのイメージを印象付けているのです。
〔ウロコ3〕「いつみきとてか」
「いつみき」は「いつ」+「見」+「き」(助動詞)で、いつ見た、という問いであり、誰ガ誰ヲかと言えば、詠み手ガ恋する相手ヲ、ということでしょう。その相手を見たのは確かなのに、それがいつだったかと、自分に問うているわけです。
しかし、その時期を思い出せないというのではなく、じつはおそらくごく最近のことで、それが信じられないという、反語的な疑問です。なぜ信じられないか。恋心が一気に燃え上がってしまったからです。
気が付いたら、恋しさに胸がいっぱいになっていた、そういうプロセスのありようが、まさに序詞における、泉から水甕までに及ぶ変化のイメージと重ね合わされるわけです。
百人一首の歌の中にも、序詞を用いた歌がいくつかありますが、序詞によく用いられる地名からのイメージを、これほど巧みに、しかも新たな形で生かした歌はないでしょう。