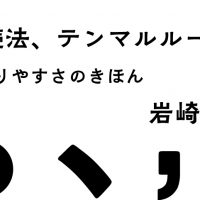中井好男
先日ようやく『Codaあいのうた』(https://gaga.ne.jp/coda/)を観に行くことができた。『Codaあいのうた』は2022年1月21日に日本で公開された映画で、ろう者である両親と兄を持つ聞こえる子どもの世界を描いた内容となっている。説明するまでもないが、CodaというのはChildren of deaf adults(聞こえない両親を持つ子供)の頭文字語である。原題は『CODA』であり、邦題ではなぜCのみをキャピタライズした形にしたのか気になったが、それよりもなぜわざわざ「あいのうた」と付け加えたのかがいまだに引っかかっている。そんなタイトルの小さな違いはさておき、『CODA』は3月27日(日)にアメリカで発表されたアカデミー賞で作品賞、助演男優賞、脚色賞の3部門を受賞したことに加え、助演男優賞については、ろう者の男性俳優として初の受賞であったことが話題になっている。以下に、この映画を観て考えたことについてまとめてみたいと思う。
文頭で私が「ようやく」と表現したのは、観たいけれど観ないほうがいいんじゃないか、観るとしても誰と観たらいいのかという問題に悩まされてしまい、踏ん切りがつかずにいたためだ。そうなってしまったのは、私自身が映画の主人公であるルビーと同じCodaだからである。とにかくこの映画は、私にとっては観に行くのも観ている最中も観た後も非常にエネルギーを要する映画だった。そこで、このエネルギーについて、可能な限りネタバレにならないように、映画の公式チャンネルで公開されているあらすじや本編映像を超えない範囲で説明していきたい。
まず、私がこの映画を知ったのはTwitterの誰かのつぶやきからであったが、その時はどうせインスピレーションポルノなんじゃないかと懐疑的に見ていた。この懐疑的な思いが映画を観に行く決断を遅らせた原因の一つとなっていたのであるが、そのように思ってしまったのは、障害者やその家族がインスピレーションポルノの題材として消費されることをよく目にしてきたからである。しかし、自身のCodaとしての経験を分析する自己エスノグラフィーを行い、言語文化教育研究学会ではディスアビリティ・インクルージョンをテーマとした年次大会を企画し、それを実現させたばかりであるにもかかわらず、この期に及んで辛さから逃げるというのも情けない話だし、その辛さと向き合うのが既に私の仕事になっているのだからと割り切って観に行くことにした。そして何よりも、これまでの活動を通じて私の状況を理解してくれている伴走者が背中を押してくれたことが大きな後押しとなっていた。
映画が始まってしばらくは、観る前から恐れていた感情移入は起こらず、他人の家族の物語としてスクリーンを眺めている自分がいた。ほっとしたような、なんだかハズレくじを引いたかのようなアンビバレントな気持ちだった。それはルビーの家族を取り巻く環境が私の置かれていた環境と全然違っていたからである。ルビーの家族は自然豊かな港町で漁業を営みながら、2階建ての一軒家で生活している。ルビーは学校に通いながらろう者の父と兄とともに漁に出かけ、家族の生計を支えている。他方、私の家族は3人家族で大阪の下町にある小さなアパート暮らしだった。私の父は職人で、聴者である父の弟と2人で働いていた。母は専業主婦としてその父を支え、私は家族の仕事を手伝うことなく、子供の本業に専念していればそれでよかった。このような家庭環境以外にも、日本社会とアメリカ社会における聴覚障害の捉え方や聴覚障害者の位置付け、福祉制度といった価値観や社会保障体制などにも違いがある。そのため、ルビーと私は同じCodaというカテゴリーに属していても、歩んできた人生は全く違うのである。こんなことは考えるまでもなく当然のことではあるが、寝落ちしがちな映画の序盤で、映画を観に来る前の心のざわつきがただの取り越し苦労でしかなかったことを改めて振り返っていた。
しかし、ルビーが音楽好きであることが描かれ始めたあたりからから、状況は変わり始めた。私はスクリーンに映し出されるルビーの姿に自身の過去を見出すようになっていった。私にはルビーのような音楽の才能は全くなかったが、私も音楽が好きだった。いろんな楽器が奏でる表情豊かな音に触れたり歌を歌ったりすることが好きだったため、学校の音楽の授業は楽しかったし、ハーモニカやリコーダーの練習も全然苦ではなかった。そして、家の中ではルビーと同じように、毎日好きな音楽をかけては歌を歌っていた。当然のことながら音が聞こえない両親から文句を言われることもなかったため、私は家の中の全ての音を好きなように管理、支配しているような感覚を持っていた。いずれにしても、私とルビーとの間には音楽好きという共通点がある。しかし、両親の音楽に対する態度については違っている。ルビーの家族は2ドルの中古のレコードプレーヤーを無駄遣いだと考えていたり、合唱クラブに入ったルビーに対して母親がろう者にはわからないものを選んだと皮肉を言ったりしていた。一方で、私の家族の場合、母親は私が吹いているリコーダーに関心を持つだけではなく、両親にとっては何の意味もないエレクトーンまで私に買い与え、高価な無駄使いをしてくれた。
次にルビーに自身を投影したのは、ルビーが通訳をしている場面である。私自身もルビーがしていたように、子供ながらに大人の言い分を伝え合う際の通訳に入らされることがあった。そして、通訳の場面では、両親がろう者であることに加え、通訳をするのが子供であることから軽く見られてしまうということが日常茶飯事に起きていた。両親のためによく頑張っているんだねといった同情だけではなく、必要な情報が提供されなかったり、いい加減な扱いをされたりするなど、多数のマイクロアグレッションに晒され続けてきた。そんな状況であっても、社会での交渉役としてずっと両親に頼られるのである。ルビーが家族と口論になるシーンがあるが、その中でルビーは、生まれた時からずっと通訳をしてきたことに疲れたと言い放ち、その後さらに次の言葉を続けている。
“I can’t stay with you for the rest of my life.”
このシーンは私に苦しみを伴う深い共感をもたらし、様々な記憶を呼び起こした。ルビーが家族に伝えた気持ちは、私にとって言語化することが怖くてできないものであった。そのため、ルビーによってはっきりと力強く発せられたセリフと残りの人生という手話表現によって、私は心をひどく抉り取られた気がした(結果的に私の場合はルビーとは違って、父に三行半を突きつけられる側になったのであるが)。
このように、取り巻く環境は違っていてもルビーや私のようなCodaは、家族関係に向き合うことで家族との絆にさえ影響を及ぼしかねない状況に置かれているのかもしれない。家族との関係はまるで陽の光のように心地いいが、その光を直視すれば目に傷を負ってしまうし、その光から逃げようと思っても逃げ出すことができない。だからこそCodaは、自分がいない間に両親がどんな扱いを受けているのかと考えてしまうし、自分の気持ちを抑えてでも両親のそばにいようとしてしまう。ルビーがマイルズとデュエットしていたMarvin Gayeの“You’re All I Need To Get By”でルビーが歌ったパートに以下のような歌詞がある。
“With my arms open wide, I threw away my pride. I’ll sacrifice for you. Dedicate my life to you.”
これはもちろんマイルズへの想いであるとは思うが、私にはろう者の家族への想いでもあるように響いた。そして、以下のルビーのセリフには、そのようなCodaが置かれている社会的不平等と心情が見事に詰め込まれているように感じた。
“I’ve never done anything without my family before.”
しかし、やはり映画は映画である。主人公であるルビーには歌の才能があるし、ルビーのことを理解した上でその能力を育てようとする先生との出会いもある。もちろん、大学の試験にも合格する。Codaだけではなく、その両親であるろう者が置かれている社会的不平等を描き出し、それに向き合うきっかけをもたらしてくれるのがこの映画の持つ力であると思うが、一方ではこういったプロットとストーリー展開が私にとっては過剰な感情移入を阻止するストッパーともなっていた。映画ならではのストーリー展開はインスピレーションポルノとして消費される物語にしてしまう恐れもあるが、私の場合はそれによって映画の世界から現実の世界に一旦引き戻されている。良くも悪くも映画が持つ力を思い知った部分でもあった。
私の感情が引き摺り回されたシーンは他にもまだある。それはルビーが歌を歌う際の気持ちについて合唱クラブの顧問であるV先生に聞かれ、手話を用いて表現していた場面だ。私はASL(American Sign Language)はわからないが、歌う時の気持ちを表したルビーの手話から、ルビーは歌うことで心の奥に閉じ込めている感情を解き放つことができるのだと理解した。さらに、私の感情を掻き乱したのは、大学進学のためのオーディションで歌っている最中に、オーディション会場の階上席に忍び込んだ両親とお兄さんが座っているのを見て、途中から手話をつけて歌うようになった場面である。ルビーの歌声は確かに力強いものであった。しかし、私には、歌唱力を示すためだけに審査員に放たれた無味乾燥な歌詞であったのが、手話を伴うことによって鮮やかな色を帯び、水を得た魚のように生き生きと光を放ちながら両親に向かっていくように映った。言葉に命が与えられ、生きられた言葉へと昇華していく。まさにその瞬間を見ているようであった。その時ルビーが歌っていたのはJoni Mitchellの“Both Sides Now”という曲である。
“Don’t give yourself away. I’ve looked at love from both sides now.”
“Well, Something’s lost, but something’s gained in living every day. I’ve looked at life from both sides now”
ルビーが手話と共に奏でた歌は、ルビーの家族への思いだけではなく、それを見ている私自身の両親への想いも描き出してくれたように思った。上記の場面でルビーが使った手話はルビーのメッセージを確実に届けてくれたのである。
私はルビーのように手話ができるわけではない。それでも私にもルビーのように、言葉にはできず「映像」としてしか相手に伝えられないことがある。それはもしかするとろう文化との接点を持たない人々にもあるかもしれない。だからこそ音楽や絵画などの言葉以外の表現があり、それが芸術として確立されているのだろう。私の場合、それは例えば、桜が咲き乱れる校庭で両親と写真を撮ったこと、通訳しているにもかかわらず目の前でこの人は嫌いだと手話で言われて「今は黙っていてくれ」と目力だけで伝えようとしたこと、目の前に座っている母がご飯を美味しそうに食べる私を微笑みながら眺めていることなど、俯瞰映像として記憶されている数々の場面である。一つずつ切り取って言葉で説明することはできるが、そのように言葉にしていくことで焦点化され削ぎ落とされてしまうものが生まれる。その場に同時に存在している手の温もりや温かい視線、感情を剥き出しにした表情、間に挟まれておろおろしている自身の様子など、言葉では表現しきれないもの、また同時に表現しがたいものがそこに共存している。このような音響映像ではなく視覚映像による記憶とそれを言葉では表現できないもどかしさを解決してくれるのが、目の前の空間を使って表現できる手話なのである。この手話は、表現はさることながら思考をも司る一つの言語である。ルビーが歌う際の気持ちを手話で示したように、音声言語で考えることができるコーダにもそのような感覚は染み付いていているが、ろう者にとっては、この手話での思考や表現がろう者たらしめるものであり、ろう者の存在そのものなのである。自身の母語や第一言語の重要性について内省できる人、あるいはこの映画を観た人であれば、その事実を否定することはないだろう。しかし、ろう者の思考言語である日本手話を剥奪しようという事態が成熟を装う日本社会で起こっているというのだから、本当に恐ろしいことである。札幌聾学校では、やっと取り入れられるようになった日本手話による教育をなくす流れにあるという。ろう者の教育現場を支配する聴者である教育者が、教育を受けるろう児たちの思考言語を奪うことによって自身の教育のビリーフや正当性を保とうとする権力による抑圧に努めている。あろうことか教育の現場において、あるまじき人権侵害がそれを防ぐべき教育者によって行われているのである。日本手話はろう者の言語であり、その言語権を認める必要性についてはすでにいろんなところで指摘されている。どうすればろう者の言葉とその世界への理解が進むのだろうか。このような事態に風穴を開ける手段の1つにこの映画がなりうるのではないかと思える場面があった。ここからは少々ネタバレになる恐れがあるため、映画をご覧になっていない方は読み飛ばしていただきたい。
それはルビーがマイルズと学校のコンサート大会でデュエットを披露する場面である。その場面では全ての音が消え、劇場内がしばらく静寂に包まれる。スクリーンではルビーとマイルズが歌い、コンサート会場の人たちが笑顔に溢れ、涙を流す姿のみが映し出されている。ここで一つハッとする。それは音もなく社会活動が行われている世界の存在に気づくからである。聴者の観客であれば、あの場面でろう者の世界を垣間見ることになるのだろう(そう思わされるのだろう)と想像する。ルビーの両親にはルビーの歌声は届かない。ルビーが舞台上で歌っている今、この瞬間に何が起こっているのかを知りたければ観客の動きを頼りに想像するしかない。そんなルビーの家族の姿を見て、ろう者の苦悩に否が応でも引き込まれる。ずるい演出である。そして、ルビーとマイルズの歌が終わると劇場内に音が戻る。このような仕掛けが音のない世界を演出するには必要なのであろう。それは聞こえる人には聞こえる世界との対比でしか聞こえない世界を考えることができないからである。しかし、ろう者は中途失聴や難聴(程度にもよるが)の方以外、聞こえない世界との対比で聞こえる世界を知ることはできない。映画の中でもルビーの父がルビーの喉に手を当て、彼女の歌声に触れようとしていたが、ろう者は音を振動として触覚を通して聞くことで聞こえる世界に近づくことができるのである。コンサートのシーンにあった音のオン、オフという演出は、単純に聞こえる、聞こえないという世界ではなく、実は聴者が優位となる非対称な世界を作り出している、ずるい演出になっている。つまり、音を消すことだけで聴者がろう者の世界を理解できるのかというと全くそうではないということである。この映画で描かれるような聞こえない世界や聞こえないことによる生きづらさの描写は、所詮は聴者の想像の域を出ないのではないか。私は、聴者がこのような視点を持たない限り、この映画がインスピレーションポルノに成り下がってしまうだろうと思っている。そして、それだけではなく、聴者によるろう者の思考言語の剥奪を止めることも難しくさせてしまうだろう。皮肉なことに、この映画の字幕には「聾唖者」と「健聴者」という日本語が登場する。いずれも聴覚障害への理解不足と認識の誤りを背景にした言葉であり、現在ではそれぞれ「ろう者」と「聴者」と表現されている。いずれにしても、映画は人々の感情を支配する非常に強い力を持っている。ろう者である俳優や彼らを起用した監督の思いを多くの人々に伝えることができるのと同時に、同じ映画関係者によってその思いが容易に捻じ曲げられて伝えられる危険性も孕んでいる。そういえば映画ではなくドラマの話になるが、日本ではコーダを取り上げたドラマがNHK BSプレミアムで放送されている。日本でもろう者の俳優は活躍しているが、あいにくそのドラマにその姿はない。この映画をご覧になった方であれば尚更、ドラマ制作に尽力されたろう者やCodaの方たちの思いをも呑み込んでしまう日本社会の闇を見て取れるのではないかと感じている。
実は正直に言うと、この文章をまとめるのにも相当のエネルギーを要した。それは映画のレビューをいつかはやるべきであるが、まずはコーダとして何が伝えられるのか慎重に考える必要があると思っていたからである。そんな中、映画のレビューの依頼をいただき、非常に驚いたし、身に余る光栄であった。これを機に積読状態だった書物にあたった。しかし、どうしてもコーダとして見てきたもの、持っている感覚や思いとは異なるものが多く、筆を執るきっかけを見つけることはできなかった。そのため、締め切り前日の夜になって映画館に再び足を運び、この原稿を仕上げた。しかし、この原稿を仕上げた今でもルビーの歌が頭を駆け巡っている。
“I’ve looked at clouds from both sides now. From up and down and still somehow. It’s cloud illusions I recall. I really don’t know clouds at all.”
2回目は一人で映画を観たのだが、一人で映画館に行くのは後にも先にもこの映画だけだろう。ただでさえ混沌としているが、2回目を観終えた今でもうまく整理できないのが、映画の最後で聞いた台詞である。その台詞はルビーの父親が声を出して言う“Go”である。なぜ最後の最後にルビーの父親に声を出させたのか。私はこの意図がわからない。オーディズムへの理解が日本より遥かに進んでいる(と思っている)欧米の社会で生まれたこの映画の最後がなぜデフボイスなのか。単にこの映画が聴者による聴者のための映画であるからなのか。いずれにしても、特権を持つマジョリティであり非当事者である聴者がろう者やろう者と関わりを持つ人の世界とその課題を消費することの意味や危険性とともに、この映画が伝えようとしているメッセージをどのように解釈すべきなのかをもう少し考える必要がありそうだ。