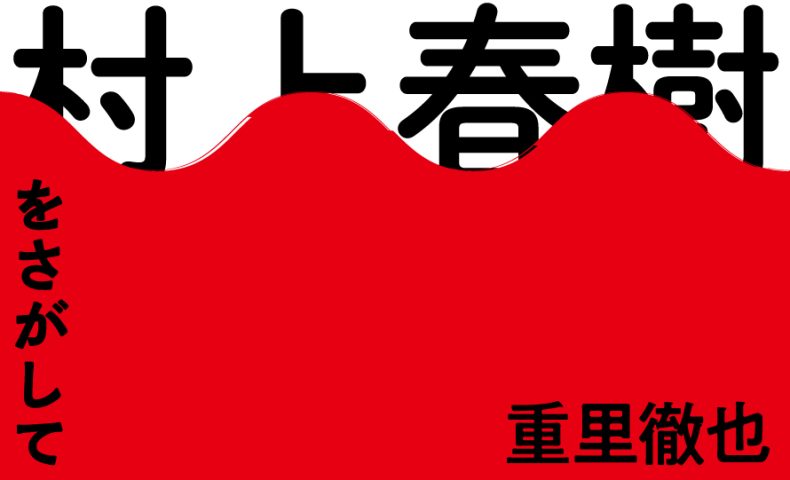初期の長編小説『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』が舞台化された。村上作品のシュールな幻想性と霊的な感覚を強調した舞台で、心の底の無意識の迷宮をまさぐっていく。とても興味深いものだった。私が楽しんだのは二〇二六年一月二十三日。東京芸術劇場プレイハウスでのマチネだ。
一九八五年に書き下ろしで発表された作品。村上は三十六歳だった。谷崎潤一郎賞を受賞した出世作で、村上の実力が広く認められることになった小説だ。「世界の終り」(偶数章)と「ハードボイルド・ワンダーランド」(奇数章)の二つの物語が交互につづられ、並行して進んでいく。
「世界の終り」のパートでは、高い壁に囲まれた静謐な街で、主人公の「僕」は図書館に通って、そこに棲んでいる一角獣の頭骨に溜められた人々の古い夢を読んで暮らしている。この街には心の本体である影を捨てないと入れないという掟がある。暮らしている人々は誰もがエゴを失ったように優しく親切だ。みんなが平等で、誰も傷つけ合わないし、争わない。
「ハードボイルド・ワンダーランド」のパートでは、主人公の「私」は情報を管理する組織に所属し、計算士という、自分の脳を暗号装置として使う仕事をしている。「私」は老いた科学者によって、ある思考回路を意識の核に埋め込まれている。その回路をめぐって、次から次に派手な事件が起こり、翻弄されることになる。
静と動。二つの世界が対応しながら、最後には二つはつながっていて、一つの世界を作っていたことに気づかされる。
私の友人の三輪太郎は、「私」の脳をいじくって、「世界の終り」に引きずり込んだ老博士に、村上は自分の父親を重ねたのではないかという興味深い推測をしている(『村上春樹で世界を読む』祥伝社 八十六頁)。ここでは、壁に囲まれた街で暮らすのも、情報戦に巻き込まれるのも、自分にはどうしようもない不可抗力の力がもたらすものとして、受け取っておこう。
さて、舞台の話に戻ろう。この長尺の大作をどのように演劇として見せるのか。力業が必要なことは明らかだろう。演出・振付をしたのはフランス人のフィリップ・ドゥクフレ。アルベールビル冬季オリンピック(一九九二年)の開閉会式の演出で注目され、「空間演出の魔術師」と呼ばれているという。確かに、ダンス、映像、音楽をふんだんにちりばめた舞台は、私たちを現実とは違う別次元の世界にいざなった。
脚本は高橋亜子。長大な小説から、エッセンスを取り出していた。二つの世界を歯切れよく組み合わせるのも見ていて感じた。両者の往還はこの演劇の可否を決める一つだったと思うが、スムーズな展開だった。
この舞台を見て、最も印象的だったのは、一角獣たちのダンスだった。長い角を頭に装着し、トゥシューズをはき、両腕には長い杖のようなものを持っている。鍛えられた身体と、どこかぎこちない動き。変な言い方だが、霊的な官能性を感じたのだ。
軽やかな身のこなしで、重力は消している。それでいて、美しい肉体が確かな存在感を訴える。一角獣たちがステージに現われるたびに、観ていて自身の心の底に誘われるような感じがしたといえばいいか。もちろん、自覚が及ばない無意識の闇は、そのまま迷宮といっていいだろう。私たちは理性がすぐにはたどりつかない場所へ連れていかれる。
影のダンスも異様に印象的だった。「世界の終り」の「僕」は壁に囲まれた街に入るときに影を切り離す。この本体を離れた影が踊り出すのだ。影を演じたのは宮尾俊太郎。黒装束の彼が舞台で見せるダンスは私たちの心の行方を問うようで、絶えず、気になった。
演技ではやはり、「ハードボイルド・ワンダーランド」の「私」を演じた藤原竜也がずば抜けていた。芸達者の藤原にしては、抑えた演技のように見えた。しかし、確かなオーラがあり、あらがいようのない宿命を生きる現代人の姿を好演していた。
音楽では「アズ・タイム・ゴーズ・バイ(時の過ぎゆくままに)」が何度か流れ、記憶に残った。映画「カサブランカ」で使われて有名になった曲だ。時がいくら流れても変わらない愛を歌っているが、この劇の中で使われるのはどういう意味あいを持っているのだろう。
無常観(この世のすべてのものは変化を続け、とどまることはないという仏教的な思想)が村上文学の底にあるように思っていたのだが、ここでは逆に、愛の確かさが歌われている。村上文学に潜む、永遠なるものへの希求を演出家が読み取ったのだろうか。
それは、はかなさを超えるものなのだろうか。実はそういう求心性が村上文学の別の魅力でもあるのだろうか。演出家がそういう解釈を踏まえたのであれば、興味深いことだ。
舞台終了後、何か、美しい夢を見たような気持ちになった。美しい幻想。心の行方への問いかけ。そして、一筋の求心性。演出家の力と特性が、村上文学の側面を確かに見せてくれたように思った。