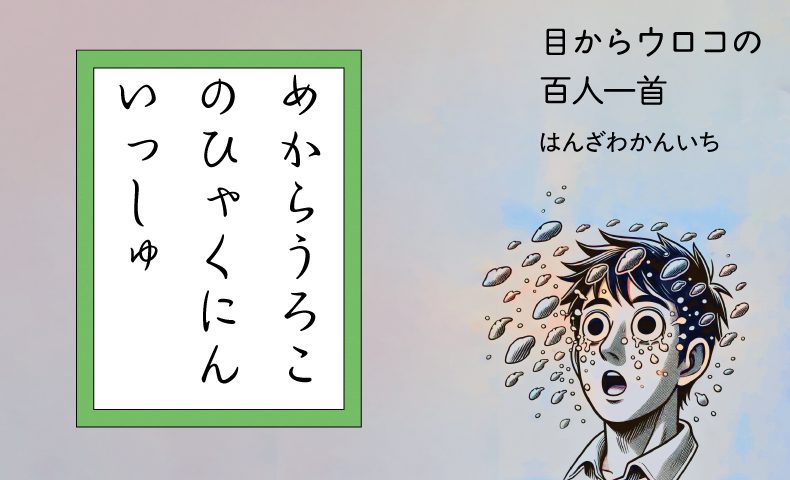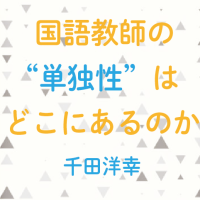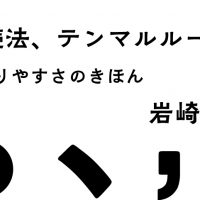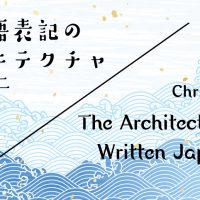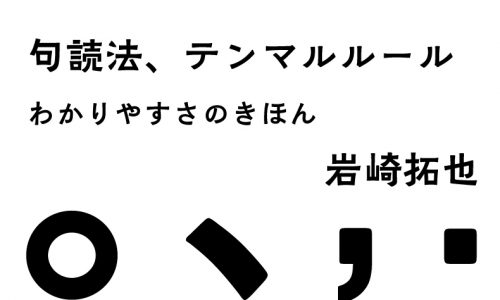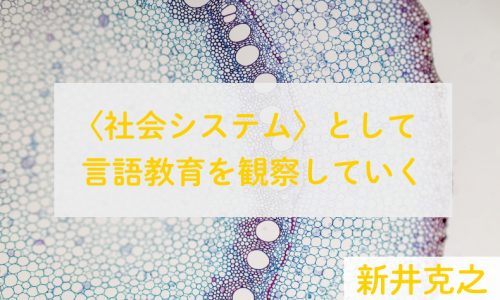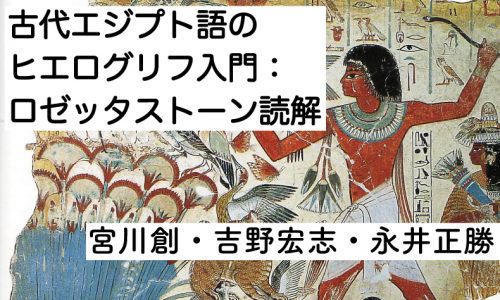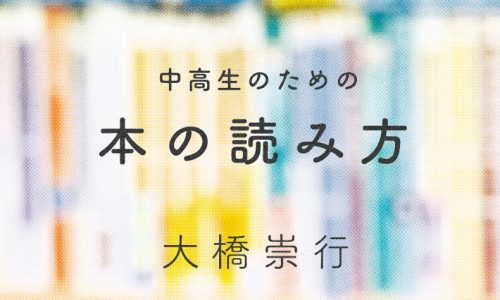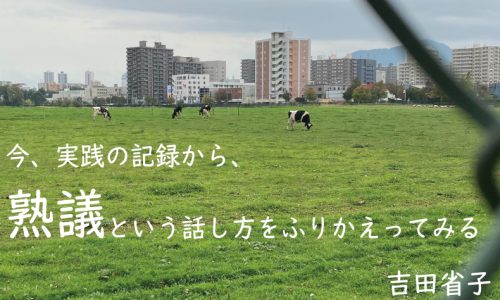人はいさ心も知らずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける
古今集(巻1・春歌上・42番)には、「初瀬に詣づるごとに宿りける人の家に久しく宿らで、ほど経て後に至れりければ、かの家のあるじ「かく定かになむ宿りはある」と言ひいだして侍りければ、そこに立てりける梅の花を折りてよめる」という、長々しい詞書が付いています。
つまり、古今集での歌は、宿主(おそらくは女性)の、詠み手の長らくの御沙汰を皮肉る、宿主の言葉に対する返事として詠まれたことになっているということです。
しかし、ここでは、そのような事情はまずは脇に置いて、歌の表現だけを考えてみましょう。
〔ウロコ1〕「人は」
冒頭の「人は」と同じく、第三句に「ふるさとは」があり、ともに助詞の「は」によって取り立てられていますから、「人」と「ふるさと」つまり人間と場所が対比されていることになります。
問題は、どういう点で対比されているか、です。
〔ウロコ2〕「いさ心も知らず」
人間のほうについては、「心も知らず」とのみ表現され、そのありようがどうかまでは示されていないのに対して、場所のほうは、下二句に「花ぞ昔の香ににほひける」のように、「花」を取り上げ、そのありようが具体的に表現されています。
ここから推測すれば、人間についても、それに相当することが「心」にあるかどうか、ということになるはずです。一般的には、人の心は変わりやすいものとされているからこそです。
手掛かりになるのが、「昔」という言葉です。この歌では、香りのある花(たとえば梅)については、その香りが年によって変化するとは考えられません。つまり「昔」と同じということです。
それと対比される人間の「心」のほうはと言えば、「昔」と同じかどうか、分からないというわけです。気を付けたいのは、分からないと言っているのであって、昔とはもう違う、とはっきり言っているのではないということです。
これが一種のはぐらかしであることは、「いさ」という感動詞から知れます。相手に対して一応の配慮を示す、現代語の「さあ」と同じです。「知らず」と明快に言い切るのではなく、それをはぐらかして言っているということです。
〔ウロコ3〕「ふるさと」
「さと(里)」は人が集まって住む場所のことであり、「ふるさと(古里)」は、「ふる」の捉え方によって、いくつかの意味に分かれます。この歌では、「昔」という言葉もありますから、自分にとっての「ふる」であり、かつて住んでいた、あるいは通い慣れた場所ということでしょう。
現代語の「ふるさと(故郷)」にも、ただ場所というだけでなく、そこに住む人々やそこにある風物などに関する、懐かしさという好ましいイメージが伴っています。この歌でも、詠み手が「ふるさと」という語をあえて用いたのには、そこの花だけでなく人についても、そのような好ましいイメージを持っているからでしょう。
この歌で、本当に対比されているのは、「ふるさと」における「人」と「花」であり、どちらも懐かしいものであることに変りありません。それを、「人」と「ふるさと」の対比のように見せかけて、相手の心のありようを試すような、親しみのあるかまい方をしているのが、この歌ということになります。その相手も、すぐに笑って反論したことでしょう。