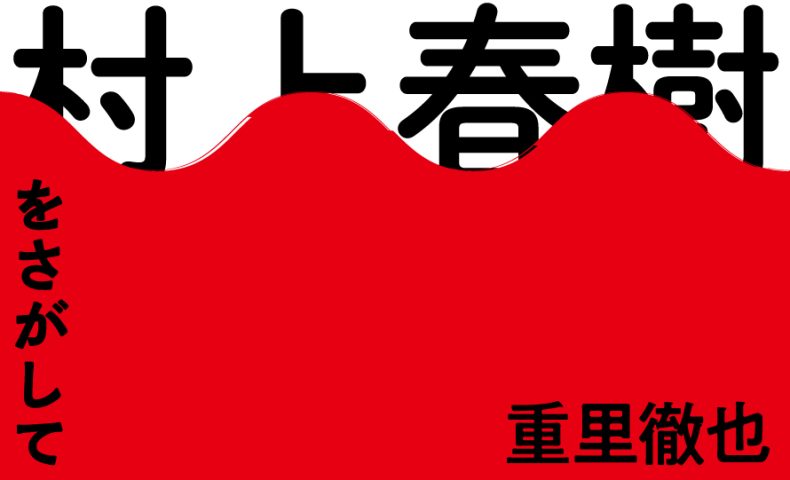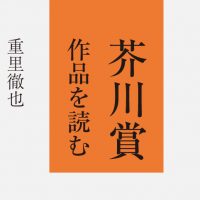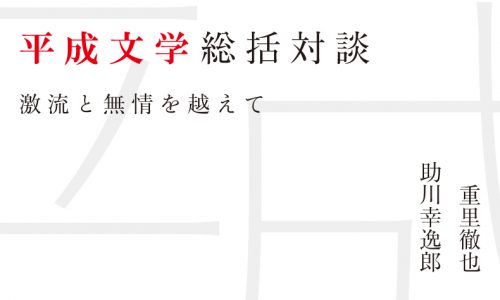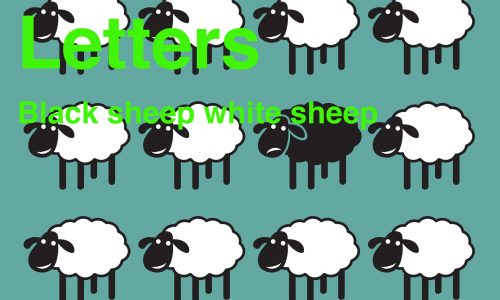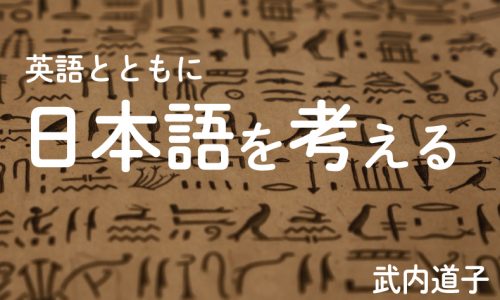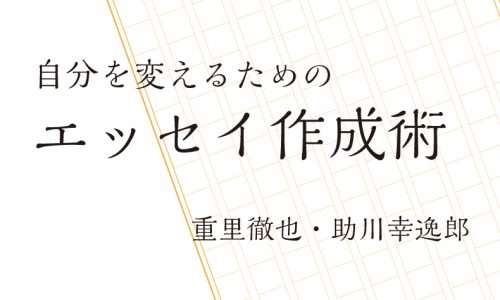村上春樹の代表作は何だろうか。よく話題にのぼる。私見では、『海辺のカフカ』(二〇〇二年)、『ねじまき鳥クロニクル』(一九九四~九五年)、『街とその不確かな壁』(二〇二三年)あたりになるのではないかと思うのだが、どうだろう。
もちろん、人によって、選ぶ作品に違いがあるかもしれない。『ノルウェイの森』(一九八七年)を推す人は少なくないだろう。私にとっては『羊をめぐる冒険』(一九八二年)は忘れられない作品だし、短編集にも好きなものがいくつもある。けれども、キャリアを積んだうえでチャレンジした作品であり、その作品の大きさや深さからいえば、この三つが順当な感じがする。
『海辺のカフカ』をめぐって、内外の研究者たちが語り合う国際シンポジウムが八月九日に高松市で開かれた。主催するのは東アジア村上春樹研究会(会長は権慧)。私はオンラインで参加したが、五人の発表がいずれも興味深いものだった。
サダ(高知でサーフショップをやっている大島の兄。小説の末尾近くで登場)の役割に注目したのは楊炳菁(北京外国語大学准教授)だった。サダは一見目立たない登場人物にも思えるが、実は作品において重要なカギを握っているという考察だ。
サダは主人公の田村カフカに対して、サーフィンの比喩を使って人生を説く。サーフィンは自然の力に逆らわずに、恐怖に負けず、死と向かい合って、いろいろなことを考えて、乗り越えていく行為だという。
楊は、自然の力を運命に読み替えて、運命を受け止めつつも、思考をやめないのが「開かれた自我」のあり方なのだと話した。つまり、自我とは運命と対立し拮抗するものではなく、「むしろその流れに即して生成されていく、動的かつ可変的な存在」と解説した。
興味深い議論だ。楊も主張した通り、村上はいわゆる近代的自我に対して否定的だということになる。人間は遺伝子などの運命にあらがうことはできない。近代的自我の閉鎖性は人々に「自己表現しなくてはいけないという強迫観念」を植えつける。その結果、人と運命との対立が生じ、みんな苦しむ一方で、生きるということの意味も見失われてしまう。
サダという人物はこういう状況に対して、生きる意味を洞察する根本的な方法を提示しているというのが、楊の考えだ。説得力があるように思った。
周鈺(国際基督教大学研究員)は、この作品において、雷が「兆し」「悪の媒介」「異世界への通路」などさまざまな役割を担っていることを論じた。『オイディプス王』や『雨月物語』など古典文学の雷のイメージを受け継いでいることにも触れた。
他にも、作品の舞台や登場人物のルーツについての考察、村上春樹にとっての四国という土地が持つ意味、村上作品に「四」や「四」の倍数が頻出するのはどうしてか、などについて、興味深い論考が続いた。
最も印象的だった発表は、この作品における第二次世界大戦の政治的メタファーを論じた小島基洋(京都大学教授)の発表だった。まず、作品に出て来る映画「サウンド・オブ・ミュージック」や映画内で歌われる「エーデルワイス」がナチスに対するレジスタンスの表現であることに注意を向けた。また、主人公のカフカがスペイン戦争に言及しているが、ここにはカフカの反ファシズムの志向が表れていると指摘した。
これらの要素は作品内では、いずれも個人の愛情や感情の次元に収められているように見える。しかし、読者は国家の歴史のレベルで受け止めないといけないのではないかと提案した。
それではこの小説は第二次世界大戦について、どう表現しているのか。作品に登場する人物、ジョニー・ウォーカーが英国のメタファーであること、ネコのミミはドイツに支配されているイタリアのメタファーであることなどをいくつかの根拠を挙げて指摘した。
また、田村カフカやホシノ、さくらなど、登場する日本人の多くがアメリカのブランドを身に着けていること(アメリカは何かを偽装するモチーフになっていると小島は表現)、一方、佐伯はドイツのブランドとともにあることに注意を向けた。
佐伯がカフカに言う「絵を見なさい」という言葉を「ドイツを忘れてはいけない」、つまり、戦前の帝国日本とナチスドイツの歴史を忘れてはいけない、両国の戦争責任を忘れてはいけない、というふうに解釈した。
最も気になったのは、それではもう一人の気になる登場人物、カーネル・サンダーズの格好をした男性は何のメタファーなのかということだった。アメリカ人のふりをした日本人で、自分は神でも仏でもないと話す人物。その答えを聴いて、背筋が寒くなったことを記しておこう。
小説にメタファーを読み取ることは楽しい。しかし、どこまでも進んでしまい、作品から離れてしまう危うさもある。どれだけ説得力があるのかが問われるだろう。小島の発表を聴いて、この長編小説の読みを広げ、深めることができた。