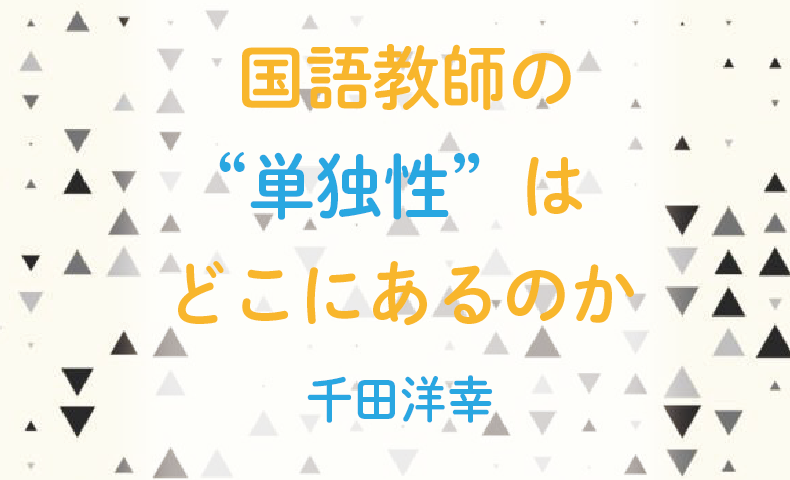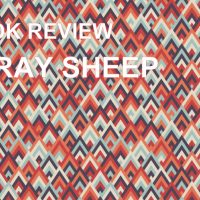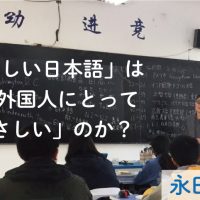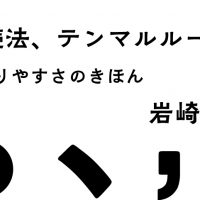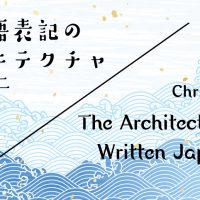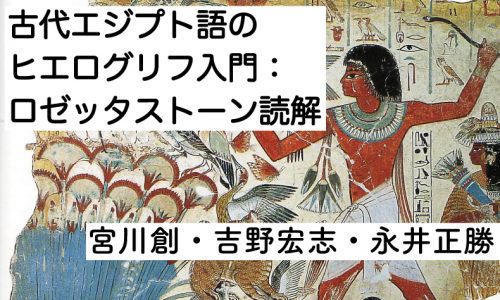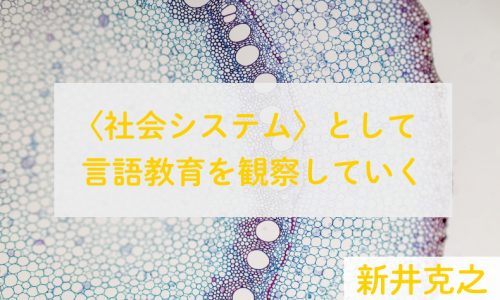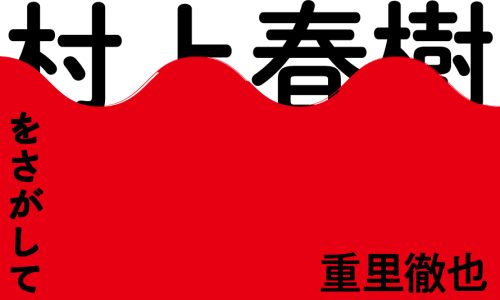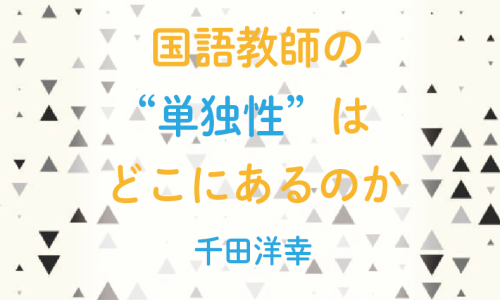私たちはしばしば、「◯◯理論を使用して△△を研究する」という言い方をする。語り論の観点から小説教材を分析する、読者論の方法を生かして詩教材を分析する、といったぐあいだ。日々の実践にむけて教材研究を行う際、また授業設計をする際に、文学理論や認知理論などさまざまな知見がたえず導入される。「実践と理論は車の両輪」という耳慣れたテーゼは、国語科教育において疑われることのない常識と化しており、さらには、実践に奉仕することによってはじめて理論は価値をもつ、という断言がなされたりもする。
このようなテーゼは、実践の場に理論をもたらす効用をもつ反面、理論の水準に一定の歯止めをかけてしまう危険性もはらむ。このようにいうと、実践ひと筋(?)の教師からは反発を招くかもしれないが、おおくの理論は、実践にすべて吸収されてしまうような底の浅い代物ではない。さきの連載第6回でもふれたように、理論は、実践に回収しきれない余剰の部分をもつこと、実践を超越する志向をそなえていることによって存在意義をもつのである。
わかりやすい事例として、おおくの国語教師が耳になじんでいる「テクスト」という概念をとりあげてみることにしよう。たとえば第一学習社版『論理国語』の「評論キーワード一覧」では、つぎのように説明されている。
何らかの意味を読み解く対象。多くは文章をさす。「テクスト論」とは、読者が作品をどう読むかという視点を取り入れた読解の考え方。文章は一旦書かれると、作者自身との連関を断たれた自律的なものとなり、多様な読まれ方を許す。こうした考え方を、ロラン・バルトは「作者の死」と呼んだ。また、デリダは「言いたいこと」は純粋にそれだけとしてあるのではなく、言葉と不可分に結びついて成り立つと考えた。こうした「テクスト論」は、文章というものに絶対の真理(著者が言いたかったこと)を求める姿勢への批判であり、「形而上学批判」の一つと見ることができる。
東京書籍版『精選論理国語』巻末付録の用語集でも、「言葉によって書かれたもの。書かれたものの解釈について、読むという行為の中で、読者のさまざまな解釈を肯定するという意味合いで用いられることが多い」と記述されており、第一学習社版とほぼ共通する認識のもとに「テクスト」の概念が説明されていることがわかる。そして、ほとんどの国語教師にとっても、「作者の支配からの解放」「読者の主体性の回復」「多様な読みの復権」といったあたりが、おそらく最大公約数的な把握だろう。
ところが、「作者の死」(1968)と並称される重要なエッセイ「作品からテクストへ」(1971)においては、「テクスト」の要件のひとつとしてつぎのような命題が語られているのだ。
「テクスト」は複数的である。ということは、単に「テクスト」がいくつもの意味をもつということではなく、意味の複数性そのものを実現するということである。それは還元不可能な複数性である(ただ単に容認可能-アクセプターブル-な複数性ではない)。「テクスト」は意味の共存ではない。それは通過であり、横断である。したがって「テクスト」は、たとえ自由な解釈であっても解釈に属することはありえず、爆発に、散布に属する。実際、「テクスト」の複数性は、内容の暖昧さに由来するものではなく、「テクスト」を織りなしている記号表現の、立体画的複数性とでも呼べるものに由来するのだ(語源的に、テクストとは織物のことである)。「テクスト」の読者は、(自分のなかの想像的なものをすべて取り払った)無為な主体に比べられよう。適当に空虚なこの主体が、ワジ〔北アフリカの水なし川〕の流れる谷間の中腹(ワジがここに出てくるのは、ある種の異郷感-デペイズマン-を保証するためである)を散歩する(これはこの拙文の筆者にもあったことで、筆者が「テクスト」の生きた観念をつかんだのは、そうした場所においてである)。彼が知覚するのは、互いに異質でちぐはぐな実質や平面に由来する、多様で還元不可能なものである。光、色、草木、暑さ、大気、わきあがる小さな物音、かすかな鳥の鳴き声、谷間の向こう岸の子供たちの声、すぐ近くや非常に遠くを通りすぎる住民たちの往来、身振り、衣服。これらの偶発的なものは、どれも半ばしか同定できない。それらは既知のコードから来ているのだが、しかしその結合関係は唯一であって、これが散歩を差異にもとづいてつくりあげ、差異としてしか繰りかえされないようにするのだ。「テクスト」に起こるのも、これと同じことである。つまり、「テクスト」は、その差異(ということは、その個性という意味ではない)においてしか、「テクスト」でありえない。「テクスト」の読書は、一回性の行為である(このことが、テクストに関するいかなる帰納的=演繹的科学をも幻想に変えてしまう。テクストの《文法》は存在しないのである)。
「還元不可能な複数性」という重要なワードが出現するため、よく知られている部分でもあるだろう。興味ぶかいことに、バルトはここで「テクスト」の読者を散歩する主体になぞらえている。散歩をする行程では、風景、気候、遭遇する人々や生き物の様子、視覚や聴覚によって感知される出来事など、すべては偶然かつ唯一の関係を作り出すのであり、それゆえ散歩は何度くりかえされようともそのたびに“差異”となる。「テクスト」の読者もこれとおなじように、偶然性に支配されつつ、読むことをその都度「一回性の行為」として行う。たんに「テクスト」が多様な意味をもっているということではなく、散歩がつねに差異を生成するように、「テクスト」を読む行為はかならず「還元不可能な複数性」を実現することになるのだ(注1)。
このことがなにを意味するのかというと、自己の読み「について語ること」は、つねにその不可能性とともに在るということである。国語の授業では教材を反復して読むことが強いられるが、読む行為はその都度一回的であり、差異をふくむ解釈として生成されるので――つまり初読も再読も再々読もすべて異質な解釈として立ちあがるので――「これが自分の読みである」という同定はたえず裏切られてゆく。我々は、そうした不可能性をとりあえず棚上げすることによって、自己の読みを感想文として記述するとか、「多様な」読みを前提として他者と交流するとかいった活動をなしえているにすぎない。すなわちバルトの理論は、「テクスト」の学習可能性を拡張するどころか、「読むこと」の授業が、「還元不可能な複数性」を「容認可能な複数性」にすり替える欺瞞によって成り立っている事実を暴き立ててしまうのである(注2)。
「テクスト」が、読む行為によって新たに書き換えられていく動的なプロセスそのものだとすれば、そこにジャック・デリダの「引用可能性」「反覆可能性」の提言や、それを踏まえたジュディス・バトラーの「パフォーマティヴィティ」概念を想起することも可能かもしれない(ちなみにデリダが「すべての記号は、所与のいかなるコンテクストとも手を切り、絶対的に飽和不可能な仕方で、無限に新たなコンテクストを発生させることができる」と語った古典的な論文「署名 出来事 コンテクスト」は、「作品からテクストへ」とおなじ1971年の発表である)。ここでこの三者の理論的連関(?)の問題に深入りすることはできないが、いずれにせよ、「テクスト」概念が、「作者の権威を否定して読みの多様性を許すこと」などという水準にとどまっていないことは明白である。
同時に、これもしばしば誤解されているが、バルトは、〈作者の死〉が読者の主体性を復権させるなどと語っているのではない。バルトの語る〈作者の死〉とは、「作者」が「書き手〔スクリプトゥール〕」に取って代わられることであり、その「書き手」とは「もはやおのれのうちに情念も、気質も、感覚も、印象ももたず、ただこの果てしない辞書をもち、いかなる停止もありえないエクリチュールを、この辞書から生み出す」存在とされる。「作者」という主体に疑義が突きつけられるのであれば、「読者」という主体も解体を余儀なくされるのは必然だろう。バルトは「読者」について、つぎのように語っている。
読者とは、あるエクリチュールを構成するあらゆる引用が、一つも失われることなく記入される空間にほかならない。あるテクストの統一性は、テクストの起源ではなく、テクストの宛て先にある。しかし、この宛て先は、もはや個人的なものではありえない。読者とは、歴史も、伝記も、心理ももたない人間である。彼はただ、書かれたものを構成している痕跡のすべてを、同じ一つの場に集めておく、あの誰か(原文傍点)にすぎない。だからこそ、偽善的にも読者の権利の擁護者を自称するヒューマニズムの名において、新しいエクリチュールを断罪しようとすることは、ばかげているのだ。
バルトが提示する「読者」はもはや「個人」ではありえず、「人間」を構成するもろもろの要素ももちあわせてはいない(注3)。エクリチュールが「一つも失われることなく記入される空間」とはほとんど虚構の存在にほかならず、むしろエクリチュールを現前させるためのひとつのシステムととらえる方がふさわしいかもしれない。〈作者の死〉は人格的存在としての「読者」の消滅をも意味しているのであり、だから、「主体としての読者の成長を促す」とか、「学習者の内面を涵養する」とかいった観念ほどバルトの思考から縁遠いものはない。そこに「人間」を想定してしまった瞬間、バルトの理論からはかぎりなく遠ざからざるをえないのである。
ならば、バルト自身は「テクスト」をどのように「解釈」しているのだろうか。『記号の国』で印象的な俳句についての言及を参照してみよう。
蛙が水にとびこむ音が芭蕉を禅の真理に目ざめさせたのだと言われるとき、つぎのように理解することができる(このような言いかたは、まだまだ西欧的すぎるのだが)。芭蕉が水音を耳にして発見したのは、もちろん「啓示」とか象徴への過敏とかいった主題ではなく、むしろ言語の終焉である。言語が終わる瞬間(大いなる修業ののちに得られる瞬間)というものがあり、反響のないこの断絶こそが、禅の真理と、俳句の短くて空虚なかたちとを作りあげている。ここでは「展開」はきびしく否定される。なぜなら重要なのは、重く、充満し、深遠で、神秘的な沈黙の状態のうえに言語を押しとどめることではないからである。
……解釈という方法では、俳句をとらえそこなうことしかできない。なぜなら、俳句にむすびついた読解の作業とは、言葉を誘発することではなく、言葉を中断することだからである。
俳句においては、意味は一瞬の閃光、光の浅い傷跡にすぎない。シェイクスピアは「見えない世界を照らしだした閃光とともに、意味の光が消えゆくとき」と書いていたが、俳句の閃光はなにも照らしださないし、明らかにもしない。とても注意ぶかく(日本人のように)写真を撮るときのフラッシュなのだが、そのカメラにはフィルムが入っていない。あるいは、こうも言えるだろう。俳句(描線)とは、小さな子供が「これ!」とだけ言って、なんでも(俳句は主題の選り好みをしないから)ゆびさすときの、あの指示する身ぶりである。その動作はきわめて直接的になされるので(いかなる媒介も――知識や名前や所有さえも知識や名前や所有さえも――ないので)、指示されるのは、対象を分類することいっさいの空しさとなる。
石川美子が指摘する通り(注4)バルトは日本語文学としての俳句ジャンルを十分に理解した上でこの批評を書いているわけではない。だが、季語、区切れ、切れ字、比喩、象徴、余韻や余情……といった解釈の経験にまみれている我々からすると、俳句の俳句性とは言語の「終焉」「中断」であり、子供の直接的な「指示」の身ぶりであるとするバルトの断言は爽快だとすらいえる。書かれていないことへの想像力を働かせるのが俳句解釈の要諦だとする国語教育的な慣習に対し、バルトはいっさいそれをせず、ただ「反響のない断絶」を見いだすだけだ。バルトの方法によって、我々は、余白、余韻、余情に意味を見いだすことを強いる俳句解釈の規制にみずからが囚われていること――それは十七音の短詩型文学になんとしても価値を付与しようとする強迫観念のあらわれともいえる――を知らされるのである。
* * *
さて、ここまでくれば、バルトの理論がきわめて反学校的な性格をもつことが理解できるだろう。それは、伝統的な「作者」「読者」の理念を解体―更新しながら、同時に、解釈する/について語る行為そのものに不可能性をつきつける。バルトの理論に忠実であろうとするなら、必然的に、国語科における「文学教育の死」あるいは「読むことの授業の死」を受け入れざるをえなくなる。
ならば、国語科教育の場においてバルトの理論は忌避の対象とされるべきなのだろうか。もちろんそうではあるまい。「作者というのは、おそらくわれわれの社会によって生みだされた近代の登場人物である」「テクストとは、無数にある文化の中心からやって来た引用の織物である」「作品は物質の断片であって(たとえばある図書館の)書物の空間の一部を占める。「テクスト」はといえば、方法論的な場である」――二つのエッセイにおけるいくつかの提言が、ある時期に蔓延していた作家論的解釈や「近代的自我」という概念の権威化などに対し、有効な批判として機能したこともうたがいない。バルトの理論をわかりやすく縮約することによって、教材研究や実践の場における解釈行為との接続が可能になることもたしかなのだ。
バルトの言説の細部に分け入ることをせず、一見明瞭な断片としてのみそれを受容することは、彼の理論が達成している水準を矮小化し通俗化する堕落行為にほかならない。だが、あらゆる理論が所詮そういう「翻案」をまぬがれないとすれば、理論の強度を徹底的に追求する試みの一方で、あえて汎用化をめざす方略も時には必要となる。実践の場での可塑性・導入可能性と、実践を超越し時にはその破壊にすら及ぶラジカリズムと――そのいずれをも探究し、自己の認識に組み込んでおくことが理論を知る―使うということなのだ、と考えるべきだろう。
たとえば、「ポリフォニー」あるいは「カーニバル」というミハイル・バフチンの著名な理論が存在するが、これらはスターリン体制下の苛酷な思想統制のなかで生み出された(バフチン自身も政治犯として流刑に処せられていることは周知の通り)。おおくの知識人が政治犯や思想犯として恣意的に粛清されてゆく当時のロシア社会のなかで、バフチンが「ポリフォニー」理論を提唱したことの重さを真に踏まえるなら、これらの用語をうっかり口にすることすら許されない。だが我々は、バフチン理論が生まれ出た背景に畏怖とリスペクトを送りながら、それを元の歴史的文脈から切断して文化研究や教育研究の場に移植することができる。あえていうなら、この両者の隔たりを把握できている者だけが、研究と実践の場で理論を行使する資格をもつのだ。逆にいえば、理論を「役に立つ」レベルでしか理解していないのなら、そもそもその理論に触れてすらいないのかもしれない、ということである。
(注1)こういう指摘ははやくからなされている。「一つのテクストに関して複数の読み(読解)(lecture)があるのではない。書かれたもの、あるいは支えとしてのテクスト(texte-tuteur)は一つであるにせよ、そこから織りなされるテクストは、読者ごとに、いや読書ごとに異ったものなのである。テクストは始めから複数なのであり、だから他との差異(différence)はテクストにとっては本質的である」(浅沼圭司「作者、その生と死――ロラン・バルトの所説をめぐって――」『美學美術史論集』1984.8)。
(注2)バルトはこのことを、「作品からテクストへ」の結びにおいてつぎのように語る。「以上、いくつかの命題=提言は、必ずしも「テクスト理論」の逐条的陳述を意味しない。(中略)それは「テクスト理論」がメタ言語的陳述に満足できないことによる。メタ言語を破壊すること、あるいは、少なくともメタ言語を疑うこと(というのも、一時的にはめた言語に頼る必要がありうるからである)が、理論そのものの一部をなすのだ」。
(注3)中井秀明はこの「読者」について、「これらの文学理論(注:イーザー、ブース、フィッシュ、エーコなど)における「読者」と、「読者の誕生は、『作者』の死によってあがなわれなければならないのだ」とバルトが記すときの「読者」との間には、相当な開きがある」「この「読者」は、自分の原初的な読みの行為から、最高度の喜びを引き出している。「作者の像」なんて思い浮かべることのない、解釈にも解読にも関心を抱かない、こうした無教養で、反文化的で、非人称的な読者、「作者の死」の手前を生きる、「テクストの快楽」しか知らない野生の「読者」こそが、バルトの「読者」なのである」(「「作者の死」?――ロラン・バルト雑感その3」https://nakaii.hatenablog.com/entry/20111126/1322294546 ※2025年4月15日参照)と解釈している。バルトの「作者の死」「作品からテクストへ」を文学理論の一角に位置づけたがる人は、まずこの中井の記事を参照すべきだろう。
(注4)石川美子「俳句に誘われて――断章と写真と小説〔訳者あとがき〕」『ロラン・バルト著作集7 記号の国』(2004 みすず書房)。
※バルトのテキストについては以下の翻訳を用いた。
「作者の死」「作品からテクストへ」:『物語の構造分析』(花輪光訳 1979 みすず書房)
『記号の国』:『ロラン・バルト著作集7 記号の国』(石川美子訳 2004 みすず書房)
★ ★ ★
このウェブマガジン『未草』に、私の前回の記事「「ひたすら実践に励むこと」の陥穽」(2025.3.11)への批判をふくむ田尻英三の記事「千田さんの記事と「就労」に係る日本語記事について」(2025.3.31、https://www.hituzi.co.jp/hituzigusa/2025/03/31/ukeire-59/)が掲載されている。私の記事と田尻の批判の衝突についてどう見るか、読者の判断に任せておけばよいとも思うが、このようなメタ言説を生んでしまう要因が私の記事に内在していたのかもしれないので、以下の文章を書いて最低限の責任は果たしておくことにする。(本来、研究者同士の応酬はより広い文脈に接続されていかないと意味をもたないのだが、その点はあまり期待できないであろうことをあらかじめ読者にお詫びしておく。)
そもそも私の記事は、日本語教育とか国語科教育とかいった個別の領域を相手にしているのではない。自己が拠って立つべき理論を欠いたままひたすら指導に打ち込むことがどういう危うさを招き寄せるのか、という問題は初等教育から高等教育にいたるすべての実践の場に遍在する。田尻は、自身の足場である日本語教育学が攻撃されているという意識に囚われたのか、「現在の日本語教育の実践に理論的な裏付けがないと、どうして言えるのでしょうか」と、私がまったく書いてもいないことを反論の材料にしているが(現在の日本語教育に理論がないなどという馬鹿なことがあるはずなかろう)、私の記事が対象にしたのはあくまでも小出詞子という一個人が描いた実践者・研究者としての軌跡である。その軌跡にこそ、あらゆる教育実践に拡張されうる歴史的・現在的な問題が内在していることを追求したのであり、日本語教育(学)という一領域に理論があるとかないとかの話をしているのではない。(念のためにつけくわえておくが、1990年代以後にポストコロニアル理論やカルチュラル・スタディーズを学んだ者にとって、田中克彦、イ・ヨンスク、安田敏朗、川村湊、長志珠絵、酒井直樹など一連の国語―日本語ナショナリズム研究を視野に入れておくことは常識である。小出の個人史を焦点化する今回の記事とは無関係であるから言及していないにすぎない。)
田尻は小出をどうしても救い出したいらしく、「田尻にとって、小出さんの存在感は、まさに「先生」でした」というエピソードを紹介したり、『小出記念日本語教育研究会論文集』(29号)中の特集「小出詞子先生と日本語教育・教員養成」で、小出が教え子や関係者たちの尊敬を集めていることに注意をむけさせようとしているのだが、私が記事中でのべたことをまったく理解しなかったらしい。「「ひたすら実践に励むこと」の陥穽」では、学習者のことだけを考えて懸命に指導に励むこと、教え子が教師に敬意と愛情をもって接すること、教師が教え子に自己の知見を継承すること……等々、師―弟の関係において「美徳」あるいは「当然」と見なされている行為について言及し(本文ならびに注5、7、8)、それらがしばしばイデオロギー的誤謬を隠蔽する温床と化すこと、教育という場がかかえる構造的な問題がそこにあること、を指摘しているのだ。田尻は、私がことごとく批判の対象としたことをみずからの記事中で実演している滑稽さに気づいているのだろうか。(田尻がそういう構造にどっぷり浸かっていたいのなら話は別で、どうぞご自由にというほかないが。)
ちなみに、国語教育者の戦争責任について私はすでに考察を発表している(「歴史からの逃亡と乖離――戦後国語教育と文学史への視点――」『日本近代文学』106集 2022.5、https://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonkindaibungaku/106/0/106_64/_pdf/-char/ja)。敗戦直後の国語教科書に文学史教材が数おおく掲載され、実践された背景には、戦争責任から逃亡したい国語教師たちの屈折した衝動がひそんでいるのではないか――という仮説を検証した論文である。ただし、国語教育(学)の戦争責任・植民地責任・戦後責任の研究はまだ個々の研究者の単発的な試みにとどまっていて、体系的な整理からはおよそ遠い状態であることは認めておこう。これは私ひとりの力ではどうにもならず、おおくの国語教育研究者がこのテーマに関わるべきだということをとりあえず付言しておく。
最後に。田尻は、私が引用した小出の発言について言及しながら、そこに戦争責任を自覚する「内面的葛藤」が存在したことはあきらかだと反論している。当該の小出の発言を再度引用する。
私が大学一年生の時、小出詞子先生が「日本語Ⅰ―B」の授業で話されたことを思い出します。戦時下、フィリピンの小学校へ日本語教師として派遣され、日に三校以上もの小学校を転々としながら日本語教育を行っていたこと。戦局がいよいよ悪化してきたため、軍の命令により帰国したことなど。そうしたことを踏まえた上で、 先生は静かにそして力強くお話くださいました。「私が日本語教育を行っていた頃は、日本の国家が強制的に、その国の人々に対して日本語教育を推進していました。〔そこに住む人々の言語というアイデンティティを奪って。〕そして現在、あなたたちは日本語教師を目指しています。今は、あの当時の日本語教育ではありません。全く違うのです。強制するのではなく、その国の人々から来てくださいと、請われて行くのです。求められれば、どこへでも行きますという姿勢が大切です。また、日本語教育の主体はあくまで学習者にあるのです。この意味を噛みしめてほしい」とおっしゃった。
(前出・濱田有紀子「韓国での四年間」)
このような生ぬるい言い訳など、戦時下の日本語教育実践にむけた根本的な自己批判とはほど遠い。戦争中、内地あるいは植民地で皇国思想の教育や言語教育をさんざん実践しながら、敗戦後には民主主義者づらをして変わらず教壇に立ちつづけた教師は山ほど存在した。その教師たちがほとんどなにも語らなかったことも問題だが、すくなくとものちに研究者として生きていった小出は、みずからの「転向」について自己分析し、論理化し、その内容を公にする義務と責任があったはずだ。戦中―戦後の実践経験を踏まえて研究者となった以上それは当然のことなのであり、戦後における責任の明視と問題の共有=社会化への意志こそが求められていたのである。だが小出がそういうことを試みた形跡はなく、植民地責任・戦後責任という観点からみるかぎり、彼女はなんら責任を果たすことなく、ぬくぬくと戦後社会を生き延びていったにすぎない(さきの記事では、「こういう実践者・研究者が激動の時代を生き延びていったことをいまさらあげつらうつもりはない」などと書いてしまったが、こんな甘いことをいうべきではなかった)。そういう意味でいえば、引用したさきの発言は、いま・ここで自己が行う日本語教育の実践を正当化したいがために語られた言葉でしかなく、より悪質ですらある。結局、「実践する私」の根底を形づくるべき理論も思想もついに所有しえなかったことを露わにしているにすぎないのである。
私の回答は以上ですべてであり、これ以上に言葉を連ねることはしない。読者には、実践を支える理論、思想はどうあるべきかという問題とあわせ、国語教育(者)の戦争責任・植民地責任・戦後責任の研究がどうなされるべきかについて、すこしでも考える契機としていただければ幸いである。