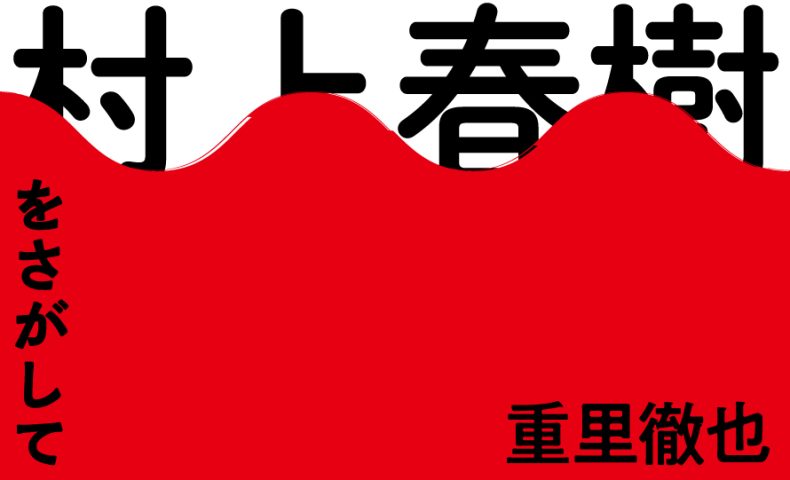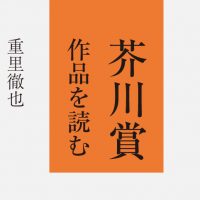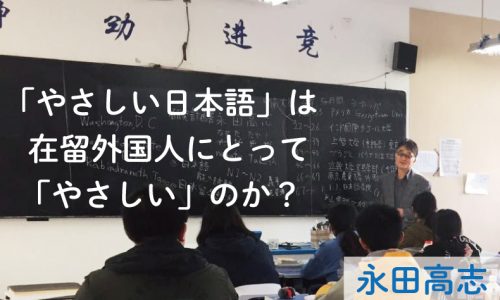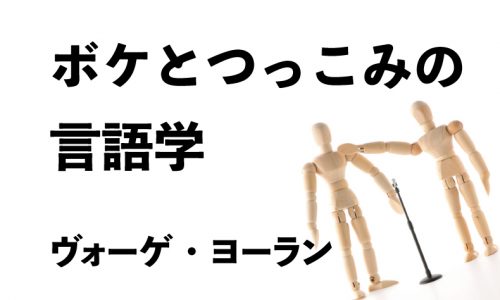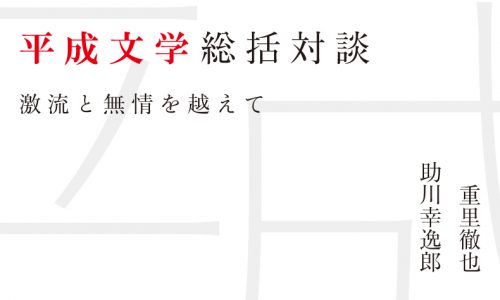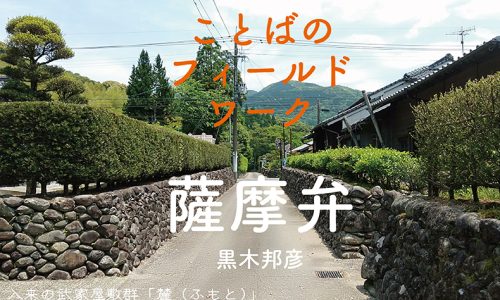今回も河合俊雄『村上春樹で出会うこころ』(朝日選書)を読みながら、村上作品の一つの側面を考えよう。取り上げるのは短編小説『ウィズ・ザ・ビートルズ With the Beatles』。「文學界」の二〇一九年八月号に発表された作品で、やはり短編集『一人称単数』(文春文庫)に収録されている。「僕」の一人称で物語られるのだが、少し複雑な構成で書かれている。
まず、最初に「僕」が一九六四年、関西の高校一年生だった時に会った一人の女の子のことから小説が始まる。彼女は同じ高校に通っていて、学校の廊下ですれ違った。彼女は「ウィズ・ザ・ビートルズ」というLPレコードをしっかりと抱き抱えていた。美しい少女で、「僕」は強く惹かれた。
村上は巧みな比喩で「僕」が少女に引き込まれたようすを描写するのだが、河合はそれを「永遠のものとの瞬間での絶対的出会い」が見事に描かれていると評する。出会いは衝撃的なのだが、瞬く間に失われてしまう。ここで河合はビートルズのレコードに私たちの注意を向ける。少女の鮮烈な印象はビートルズとともにあったからだ。
それで、人と人が出会うためには介在するもの(多くは芸術作品)を共有するという、河合の村上作品(特に短編集『一人称単数』の収録作品)の読み解きが生かされる。しかし、この少女との出会いは一瞬で終わる。「僕」は当時、ビートルズがいかに人気を博したかを詳述するのだが、実はクラシックとジャズを好んでいて、このアルバムを聴き通したのも三十代半ばになってからだったというのだ。
これは、少女と「僕」がビートルズを媒介にして出会いそうになりながら、本当はリアルタイムでは出会えなかったエピソードにも思える。しかし、河合は小説中の「そこにあったのは、音楽を包含しながら音楽を超えた、もっと大きな何かだった」という部分に注目する。河合は「もっと大きな何か」を「聖なるもの」と言い換え、思春期に現れる聖なるものは予兆に終わるというのだ。
小説は次に「僕」が高校二年の時に付き合った最初のガールフレンドの話になる。「僕」は彼女とキスをしたり、乳房を触ったりするのだが、二人の心は出会わない。「僕」はすっかり彼女に夢中になるのだが、二人の間を媒介するものがないのだ。
彼女が好んで聴いたのはイージーリスニングのレコードだった。「僕」は(歳を重ねた)今でもパーシーフェイス楽団の「夏の日の恋」は甘い追憶と結びついているという。しかし、それは心と心の出会いではない。このことを河合は興味深い言葉で説明している。引用しよう。「しかしそれは全く別次元の深みに誘うものではないようである」。人と人が出会うとは、「別次元の深みに誘う」ものなのだ。
二人の女性と真に出会わなかった「僕」なのだが、小説は意外な展開を見せる。「僕」は一人の人物と出会うのだ。それは、このガールフレンドの兄だった。
ガールフレンドと一緒に図書館で勉強するという名目で彼女の家へ迎えに行った「僕」だったが、彼女は不在で、彼女の四歳年上の兄と初めて会う。彼は「僕」を家へ上げてくれる。彼女は帰ってこない。その兄に頼まれて、「僕」は国語の副読本に収められていた芥川龍之介の短編小説『歯車』の一部を朗読することになる。
この兄は精神に深刻な疾患を抱えていた。本人が話す症状は、ときどき、記憶が飛んでしまうというものだ。それで学校へもあまり行かなくなったという。河合はこの症状を解離性障害だと指摘する。結局、「僕」はこの日は彼女に会えなかった。
小説は思わぬ結末にたどり着く。約十八年後、「僕」が三十五歳になった時、この元ガールフレンドの兄に偶然に東京で会うのだ。彼は精神疾患がすっかりよくなっていた。『歯車』の朗読を聴いてから、快復したというのだ。
芥川の小説という介在物を通して、「僕」とガールフレンドの兄の二人の心が出会ったと考えられる。なぜ、『歯車』にそういう力があったのか。この問題を最後に考えよう。
『歯車』は芥川龍之介の晩年の作品。第一章は生前に発表されたが、全章は三十五歳で自殺した後に遺稿として雑誌に掲載された。自身の死の直前の心情がつづられているものと読める。幻視や妄想が頻繁に出てきて、差し迫った危機にある主人公の不安のありようが、鮮やかに描かれている。小説の最後は次の一文で締めくくられる。
「誰か僕の眠っているうちにそっと絞め殺してくれるものはないか?」
『歯車』の何が、ガールフレンドの兄に響いたのだろう。あるいは心を病んだ自身を客観視している記述が、快復につながったのだろうか。
村上春樹は芥川龍之介についてまとまった文章を書いている。村上作品の翻訳でも知られるジェイ・ルービンが編んだ『芥川龍之介短篇集』に序文を書いているのだ。英訳本はペンギン・クラシックスの一冊として二〇〇六年に刊行され、日本語版は新潮社から二〇〇七年に発行された。
村上はここで、芥川を日本における国民的作家の一人と位置づけている。そして、芥川とともに夏目漱石、森鷗外、島崎藤村、志賀直哉、谷崎潤一郎、川端康成、太宰治、三島由紀夫を国民的作家として挙げている。計九人と半端なのは、あと一人が思いつかなかったらしい。(徳田秋声や横光利一や宮沢賢治は入っていない)
さらに、この中で芥川を夏目漱石、谷崎潤一郎についで個人的に愛好すると打ち明けている。そして、芥川が文体と文学的センスに優れていること、文章の質が良くて流れがいいこと、モダニズムと土着性のせめぎ合いの中で物語を作り出したことなどに言及している。
また、私小説的な方法に移った晩年の作品にも芸術的孤高性は保たれていると指摘し、特に、『歯車』を絶賛している。二カ所引用しよう。
主人公の視線の切実さには、そしてまたどこまでもスタイリッシュに削がれた文体には、まさしく鬼気迫るものがあるし、そこに丁寧に的確に描き込まれた心象風景は、独特の存在感をもって、読むものの心に長く、深く留まることになる
自らの人生をぎりぎりに危ういところまで削りに削って、もうこれ以上は削れないという地点まで達したことを見届けてから、それをあらためてフィクション化したという印象がある
『ウィズ・ザ・ビートルズ』に登場するガールフレンドの兄は、『歯車』から何を得たのだろうか。天才的な作家の命がけの創作が、彼を「別次元の深み」に誘ったことだけは確かなようだ。