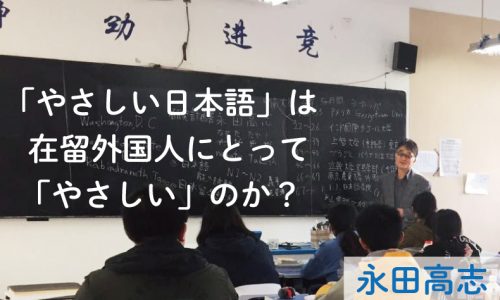知的に制御された作品
助川幸逸郎 中上健次は二十代で芥川賞をとって、確かこれが戦後生まれ初の芥川賞ってことで、当時大変話題になったみたいですね。重里さんとしては、この作品の文学史的な意義みたいなところを、どのようにお考えになっていますか?
重里徹也 今回、改めて読み返して、やはり非常に魅力的な作品だと思いました。芥川賞受賞当時は、何か圧倒的な力は感じるのだけれど、どう受け止めたらいいのかわからず、ちょっと距離を置いて眺めていました。
今読むと、とてもすぐれた作品です。特に心にのこった点は二つあります。一つは非常に知的な作品、知的な企みに満ちた作品だということです。もう一つは、静かな、クールな作品だという印象です。燃えたぎるものが満ちているのですが、知的に制御された小説といえばいいでしょうか。
リアルタイムで読んだときには、エネルギーに圧倒されて、渦に巻きこまれるような感じを受けたのですが、今回は、静かで知的で、しみじみとしたいい作品だなと思ったわけです。
助川 この作品が知的だっておっしゃいましたけれど、たとえばどんなところにそれを感じられたんでしょうか?
重里 まずは全体の構成ですね。多数の登場人物たちの群像劇が、実はわかりやすく整理されて織り成されている感じです。
細部をいっても、出てくる数字を12と24で合わせたりしていますね。あと、ソーセージが入ったコンドームが流れてくるなんていうのは、『古事記』の援用ですね。
助川 川の上流から箸が流れて来るのを見て、そっちに人間が住んでることをスサノオが嗅ぎつける。そういうくだりが確か、『古事記』にありましたね。
重里 古典に詳しい人なら、そういうものをたくさん見つけられるかもしれません。
それからもう一つは、全体が短いセンテンスの積み重ねから成り立っていて、静かに抑えた感じで、いろんな感情やエネルギーを統括している、そういう印象を非常に強く受けたのです。
助川 中上自身、『岬』を書く際には、短いセンテンスの間に句読点を入れて、ポエティカルなスタイルを意識したといっています。長いセンテンスでうねるように盛り上げていく路線は狙っていないのですね。
それからもう一つ、ギリシャ悲劇みたいなものを書きたかったとも中上は言っています。発表された当初、中上の家族をモデルにした話なので、『岬』は自然主義的な私小説みたいな感じで受けとめられました。しかし今、これを見ると、リアルな人間関係の中から非常に抽象的な「人間の原点」とか「ドラマの原光景」みたいなものをすくい取ろうとしているのを感じます。「ギリシャ悲劇」という言いまわしは、そんな「原型志向」から出ているのかもしれません。そういう意味でも、重里さんがおっしゃるとおり、知的な小説であることはまちがいないでしょう。
自由意思と宿命
重里 それから人間にとって、自由意思とは何か、宿命とは何か、両者はどのようにかかわるのか、そこを考えさせる作品だということも強く思いました。
自由というのは、戦後社会の非常に重要なエレメントだと思うのですが、吉行淳之介の『驟雨』を読んで、それからこの中上の『岬』を読むと、自由というものには必ず葛藤がつきまとう、それが普遍的な問題としてあることが見えてきます。性とか恋愛というものを文学で描こうとすると、必ず自由と不自由の問題に突きあたると思うのですが、いかがでしょうか?
助川 恋愛って、吉本隆明がいう「関係の絶対性」が典型的に現れる場なんだと思います。どの相手を好きかというのは多分に偶然です。しかし、いったん好きになったり、関係を結んだりすると、抜きさしならない事態になってしまう。だから、恋愛を真剣に描こうとすると、 偶然と必然だとか、自由と宿命という問題と向きあわなくてはならなくなるわけです。
重里 戦後社会の表層には、「何にでも自由意思で参加できて、そのことにとても価値がある」みたいな風潮があります。中上には、そういうものに対するある種の違和感があって、そこにアンチテーゼを突きつけようとしていたのではないでしょうか。
助川 文芸雑誌がやっている新人賞に応募してデビュー、というのが今では一般的ですけれど、六〇年代ぐらいまでは、プロ作家が主催する同人誌で鍛えられるうちに世に出るチャンスをつかむ、というのが「王道」でした。中上は、この「王道」パターンでプロになったほとんど最後の作家です。『文芸首都』という同人誌に所属し、津島佑子なんかといっしょに修業していました。
一方で中上は、被差別部落の出身ですし、自分が支配階級の言葉を語る人間でないことを強く意識していました。「うちの母親は、芥川賞とテレビ番組の『アフタヌーン・ショー』の区別がつかないんだ」と中上はくり返し発言しています。一般的な作家たちは知的エリートで、そういう集団の内側だけで通用する「暗黙の了解」を共有している。自分は、その外側に立つんだという思いがあったのでしょう。
中上は二重三重の意味で、戦後的な価値観や文壇ジャーナリズムに同化できないものを抱えていたと感じます。
重里 中上はしきりに徳田秋声を話題にしていましたね。秋声って、戦後的な枠組みを超えていますよね。
助川 自然主義作家の代表みたいに見られていますけど、もともとは尾崎紅葉の弟子だった人ですし、たしかに一筋縄では語れないところがあります。
重里 英語ができたので、若いときに徹底的に英訳でドストエフスキーを読んでいます。そういう体験を通過して、あのような小説を書いていたことは忘れてはいけないポイントでしょう。
助川 江藤淳なんかも、秋声についてはかなり高く評価していますね。
重里 野口冨士男の評伝も印象に残っています。野口と中上が対談して、秋声を語っているのを読んだ記憶もあります。男性週刊誌だったかな。しゃぶしゃぶを食べていたのは覚えています。野口がロッテファンだというのも話題になっていた。
助川 秋声は、漱石に推薦されて新聞小説を書いたりもしていますし、川端からも称賛されている。古井由吉なんかも熱をこめて論じています。「自然主義対反自然主義」みたいなよく語られる図式が、秋声を前にするとすっかり無効になってしまう。
重里 秋声に惹かれていた事実は、中上の作品世界を考えるうえで見過ごせないですね。
あと、気になったのは、『岬』が受賞したときの芥川賞の選評です。吉行淳之介はラストを絶賛していて、安岡章太郎はその部分を否定しています。この対立が私には非常に興味深かった。吉行と安岡の資質が、『岬』をリトマス紙にして克明に浮かびあがっている印象を受けました。
吉行淳之介と安岡章太郎
助川 吉行と安岡の意見が割れたのは、どういう背景からなのでしょう? 面白いポイントなので解説してください。
重里 『驟雨』で吉行は、娼婦との関係がいつのまにか自由より大事になってしまうという状況に迫っています。自由意思より女性に規定される姿を描いている点で、『岬』と重なる面があるのを感じるのです。ですから『岬』のラスト、主人公が腹違いの妹と交わる場面に、吉行は自分のテーマに通うものを見出していたと推測します。
助川 たしかに『驟雨』も『岬』も、宿命に憑かれたように性愛にのめりこんでいく男を描いています。
重里 その点、安岡はもうちょっと冷めているのかなあ。不条理な情熱に駆られ、みずから危機の方へ向かう人物というのは、安岡文学の中心的な対象ではありません。それで『岬』の、最後の場面に向けて、文体が勢いを増していくところに、距離感を感じたのかもしれないです。
助川 重里さんの今のお話をうかがって、絶望的な状況に陥ったとき、吉行と安岡がそれぞれどうするのか、想像してしまいました。吉行は、進退きわまってまったく活路が見いだせない事態になったら、自己破壊的な行為に走ると思うんです。これに対し、安岡ならたぶんそういう場合、何もしないでポカーンとしている。
自由とは何か、運命とは何かを問いつづけて、これ以上どこにも行き場がなくなったら、腹ちがいの妹と寝てしまうのもわかる。吉行はそう思ったのでしょう。追いつめられた人間は、ただ立ちすくんでいるだけのはずで、そんなメロドラマじみた行為に出られないだろうというのが安岡の感覚です。
重里 吉行のいうのは、腹違いの妹と思うから、童貞の主人公・秋幸がセックスできるのだという読み方ですね。一方安岡は、『岬』のラストを「小説を終わらせるためのやや不自然なたくらみ」と感じたのでしょうか。
吉行と安岡は、文学史的には、「第三の新人」という括りでひとまとめに語られることが多いです。しかし、作家としての資質は相当ちがっていた気がします。
助川 たぶん、吉行よりも安岡の方が、根源的に生命力が強いんだと思うんです。吉行が最後に自己破壊的になっちゃうのは、生存本能がどこか壊れているからじゃないでしょうか。
村上春樹が、吉行って実は不器用な作家で、あんまりうまくないって言ってますよね。
重里 『若い読者のための短編小説案内』ですね。そういう不器用なところがむしろ魅力になっている作家だという論調でした。
助川 吉行の生存本能が壊れているというのは、敗戦後の社会を目の当たりにして、ニヒリズムを抱えこんでいることと直結しています。そういう虚無感があるから、物語をスムーズに運ぶとか、文章を整えるとか、そういうことはどうでもいいと思う部分があったのではないか。
一方、身動きのできない状況でじっとしていられる安岡は、どんくさいように見えて、危機に対処する能力が無意識レベルで高いのでしょう。だから作品を書くときも、直観的に破綻を避けることができた。村上が「実は吉行より安岡の方が小説がうまい」といったのは、そこの部分を指しているんだと思います。
重里 村上春樹はどっちのタイプなのでしょう?
助川 やっぱり、吉行ではないですよね。
その点中上は、吉行に近いのかもしれません。この『岬』を読むとわかるとおり、複雑なパズルのピースを精密に組みあわせる力があるひとなのに、ツジツマの合わない部分を抱えた作品もたくさんのこしています。
重里 生活が荒れていたという話は様々な人が書いていますし、編集者たちからも聞きました。その無理が、四十六歳で早世する原因の一つになったともいわれています。
助川 中上にも、自己破壊的にならざるを得ない事情があったのですね。先ほどお話ししたとおり、文壇ジャーナリズムや、戦後的な価値観に安住できない人でしたから。中上と吉行の資質に共通点があるとおっしゃった重里さんのご指摘は、鋭いと思います。
鮮やかで魅力的な女性像
重里 それから、『岬』の選評を読んでいて、ちょっと困ってしまったのが中村光夫です。
助川 どういうことですか?
重里 読み違いをしているのです。「病気で寝ている母親」というのは誰のことでしょうね。この小説で病気がちなのは、秋幸の異父姉の美恵ですね。母親は元気いっぱいです。だからこそ、次々に夫を替えて、この人物群像が生まれたのです。愛憎が渦巻く血縁の世界ができたわけです。母親は作品中でどう読んでも、生命力にあふれたしっかり者です。
助川 中村光夫は、個々の作品をきちんと読まず、出来あいの物差しで対象を語ってしまうところがあります。村上春樹が芥川賞候補になったときも、頓珍漢なことを言っていました。
重里 逆に丹羽文雄は「母親がよく描かれていた。この母親によって賞をうけたようなもの」と指摘している。確かに鮮やかだと思いました。
助川さんと以前、中上の作品では『鳳仙花』がとてもいい、という話をした記憶があります。苦労した女性を描かせると、中上はとても筆が冴えるような気がするのですが。
助川 そうなんです。しかも若い女性よりも、おばちゃん、おばあちゃんたちを生き生きと描くのが上手です。男目線で見た女性ではなく、女性同士で集まってべちゃくちゃ喋ってる感じをリアルに表現してます。
重里 『岬』でも、工事現場ではたらく男女の会話が魅力的です。
助川 主人公の秋幸にしても、「身のまわりのインテリ男性に辟易したインテリ女性が、頭の中で作りあげた肉体派男性」みたいなところがあります。カッコいいのだけれど、今ひとつリアリティーがない。
重里 女性の方が男性よりリアルに描ける男性作家というのは珍しいですよね。
助川 絓秀実が、「中上健次は実は女性なのではないか」と言っていたのを思い出しました(笑)。金井美恵子も中上の追悼文で、彼の微笑みを「お産したての牝犬」に喩えています。
重里 それにしても中村光夫は、どうして、批評家として唯一、芥川賞選考委員になれたのでしょうか?
助川 映画の『シンゴジラ』に、東京を核攻撃しようとするアメリカを、フランスとドイツの協力を仰いで思いとどまらせる場面がありました。戦後の日本は、軍事と外交では、アメリカの意向を無視した決定はできません。これは、現在においても克服されていない日本の生存条件です。このため、ヨーロッパの力を借りてアメリカに対抗できたら、という、何重にも捩れたナショナリズムを日本人は抱えこんでいます。その「こじらせ愛国主義」に、中村光夫のような「フランス通」は妙に訴えるところがあるのです。
重里 村上春樹の登場時には全く読めていないですね。中村光夫はフランスには詳しかったのでしょうが。
助川 アメリカに興味関心を向けず、フランスの側からばかり物事を語るところが、「こじらせ愛国主義」にはかえって心地よいのです。
中村光夫自身は、あるべき純文学の側から、サブカルチャーに過ぎない日本文学を批判しているつもりだったのでしょう。しかし、日本の現状を否認したい大衆の欲求の上に文業を成りたたせていたわけですから、現在の目で見ると、中村光夫こそ「ぬるいサブカルチャー」のようにも映ります。
重里 流行の図式に引きずられるのではなく、愚直に個々の作品に向き合った読みは、歳月を経ても色あせないということを、丹羽文雄の選評を読むと感じます。「頭のいい人には、文学と政治は向かない」というのが私の持論ですが、中村光夫は「頭のいい人」の代表のようにも見えます。
助川 吉行や中上が違和感を覚えていた「戦後的なもの」、それに自分が守られていることに、中村光夫は気づけなかったのです。