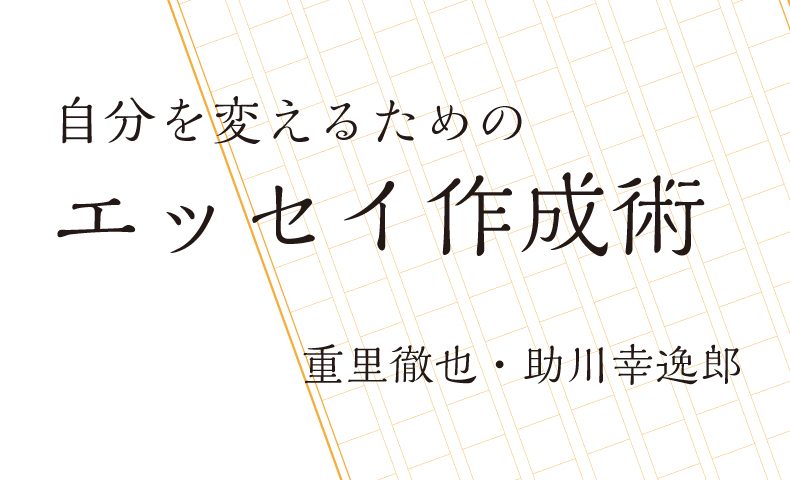「悪口」を、むやみにいわないほうがいいのはたしかだけれど・・・
「他人の悪口はいわない、書かない。」
文章指南書にも、自己啓発本にも、たいていそんな風に書かれています。実際、大部分の「悪口」は、語っている当人の嫉妬やコンプレックスに根ざしている。
私自身の「イタイ思い出」を書きます。
吉本ばななは、デビュー作の『キッチン』がベストセラーとなり、有名作家の仲間入りをしました。一九八七年のことです。ばななはまだ、二十三歳の若さでした。
そのころ私は十九歳で、くすぶりきった日々をすごしていました。じぶんと年齢が幾らもちがわないばななが、すでに物書きとして大ブレイクしている。しかも彼女は、吉本隆明という高名な詩人兼批評家を父にもち、創作するうえで圧倒的にめぐまれた境遇でそだっている。
おこがましくも私は、ばななに猛烈に嫉妬したのです。
私は『キッチン』の愛読者カードに、こんなメッセージを書いて送りました。
「たしかにおもしろく読めました。でも、『台所』で『家庭』を象徴させるなんて陳腐です。『一家の大黒柱』が、ただの『おとうさん』では古いから『おかまのおとうさん』を出す。これもミエミエ過ぎですね。『ありきたり』に怯まない厚顔無恥が、成功の秘訣でしょうか。」
ほんとうに独創的なアイデアは、提示された瞬間には人を唖然とさせ、じっくり検討したあとでは「当たりまえ」に映る。前人未踏でありながら、もっとも合理的なルートをたどった思考の産物だからです。
『キッチン』の設定には、「ほんものの独創」がありました。にもかかわらず私は、それを素直に認められなかった。
私が『キッチン』の感想カードに書いた言辞には、毒を吐いた当人の「鬱屈」だけがにじみ出ています。こういう「悪口」は100パーセント、いうべきではありません。
あるイタリアン・レストランについての会話—「裸の王様」に遭遇したとき
けれども、「悪口」を書くことが、他人の「救い」になる場合もあります。
先日、十五年ほど前に予備校で教えていた元・生徒と、ひさしぶりに会って話をしました。
「先生って、味覚に自信はあるほう?」
「うーん、料理するのは好きだけど、かなり趣向はかたよってると思うなあ・・・正直、万人うけするものをつくる自信はない。」
「わたしはさ、いまは金融とかで働いてるけど、将来はじぶんでベーカリーやりたいわけ。だから、味覚に問題あったら、夢がジ・エンドになるわけじゃない?」
「そうだね。私なんかがパンをつくっても、たぶんまったく売れないし。」
「それでね、このあいだ友だちといっしょに、西麻布のイタリアンに入ったの。その店すっごく高くて、けっこう有名な店で、友だちはグルメ自慢のタイプだったから、超厳選してそこにアポ入れたらしいの。」
「じゃあ、さぞかしおいしかったでしょう? 」
「それがさあ、なんかどの皿も「高級レトルト」って感じで。たとえばトリュフのスパゲッティはトリュフの味がむんむんするんだけど、それだけなのよ。ひとくち食べると、わかりやすく肩書どおりの味がして、それ以上の余韻とかはぜんぜん伝わってこなくて・・・。」
「私がその店入っても、たぶんおいしいかどうか判定できないなあ・・・イタリアンなんて、サイゼリヤみたいなとこしか行かないし。」
「わたしもね、じぶんの理解を越えた味、というのはわかるつもりなのよ。でも、その店の料理はそういう感じじゃなくて、ほんとに、いかにも過ぎてニセモノくさいの。なのに、家に帰ってからネットで調べてもわりと評判よくて、じぶんの味覚がおかしいんじゃないかって落ちこんじゃった。」
「ふーん。私は味覚が鈍いことが判明したぐらいじゃ傷つかないけど。やっぱり、食のプロになりたいひとは意識がちがうんだね。」
「もうそのあと、何のためにいっぱい残業してお金貯めてきたんだろうって、会社辞めたくなっちゃって。
でね、わたしがすごく尊敬してるパティシエのひとがいるの。そのひとが、わたしが食べにいった二週間ぐらいあとに、ブログにその店のこと書いてたわけ。
〈『高級コンビニめし』のような味、一年にいっぺんしか行けない値段で食べさせる料理じゃない〉って、もうボロクソ。わたしはまちがってなかったんだって、速攻で自信、回復しちゃった。」
権威があったり、有名だったりするのに、それに見あう実質がない。そういう対象に出会ったとき、事実を公に指摘すると、「悪口」ととられることもあります。
けれども、口をとざしたままでいたら、他の「実質のなさに気づいた人びと」が「おかしいのはじぶん」と感じるかもしれない――こういう場合は、「悪口」と見なされることをおそれずに、「正論」を語ってよいのです。
裸の王様を見かけたら、裸といえばいい。それが原則だと私は思います。
「悪口」は、対象の個性をきわだたせる
もうひとつ、「悪口」には効能があります。
ホメことばというのは、「一般的によいとされているもの」の寄せあつめです。それをつみかさねて、対象の個性や本質を浮かびあがらせるのはむずかしい。
「眼光するどく、知性を感じさせる風貌は、いかにも〈才気溢れる人〉という印象を見る者に与えた。」
芥川龍之介のルックスを肯定的に記すなら、こんな感じになるでしょうか。ただし、この言いまわしは、北野武やイチローにも当てはまります。
対するに「上手な悪口」は、生き生きと「言われているそのひと」をイメージさせる。次にかかげるのは、中野重治が書いた芥川龍之介追悼文の一節です。
この人は湯になどはいらぬのか、じつにきたない手をしていた。顔なども洗わなかったのかもしれない。その手が、顔同様、もともとは美しい手なのだったから、よごれ加減がいっそう目立って私には不思議だった。わりに大きな手で、頑丈なつくりではなかったが、指の節が長く、指の皮膚も甲の皮膚も皺がよっていて、大小のその皺に黒くなって垢がたまっていた。色の白い人だから、手の皮膚もすっかり白くて、だから指の背も甲も一面にうすずみ色に見えていて、皺のところは言葉どおりに黒い筋になっていた。
追悼文にはふつう、故人の欠陥は記しません。こんなにはっきり、相手の「ダメなところ」を述べてしまうのは「反則」です。
しかし。
溢れるばかりに、非凡な資質をそなえている。にもかかわらず、暮しに必要な「当たりまえの何か」を欠いている。
そういう死者のありようを、中野による「暴露話」は読者に実感させます。
芥川にとって、「生きつづけること」がどれほど高いハードルだったか――大部な研究書より雄弁に、中野の短い「悪口」は、「芥川が自殺した必然」を語っているのです。
「知らない相手の悪口」は書いてはいけない
逆にいうと、対象の核心にせまるつもりがないのに、「悪口」をいうのはご法度である。私はつねづねそう感じています。
よく知っているわけでも、興味があるわけでもない物ごとについて、否定のことばを投げかける。そこから生まれるのは、だれかを傷つけたり、苛立たせたりという不毛な結果だけです。
「虚名にあぐらをかく組織や人間の実態をあきらかにしたい。」
「ある対象の特性を何としてでも伝えたい。」
「悪口」が効果的にはたらくには、そうした「正義」や「つよい関心」の支えが必須です。
「地下アイドルのファンって、何となく気味が悪そう。」
「デートでイケアに行くカップルって、貧乏くさそう。」
こういう「イメージだけにもとづく反感」を言語化しても、他人が読むに値する文章にはなりません。
「地下アイドルのファンには好感をもてないだろうと予期していたが、ライブにいってみたらこうだった。」
「イケアでデートするカップルは貧乏くさいだろうと思っていたが、観察してみたらこんな結果が出た。」
「漠然とした反感」から出発するにしても、そこまで書かないと「よいエッセイ」にはならない。この点を、肝に銘じたいものです。