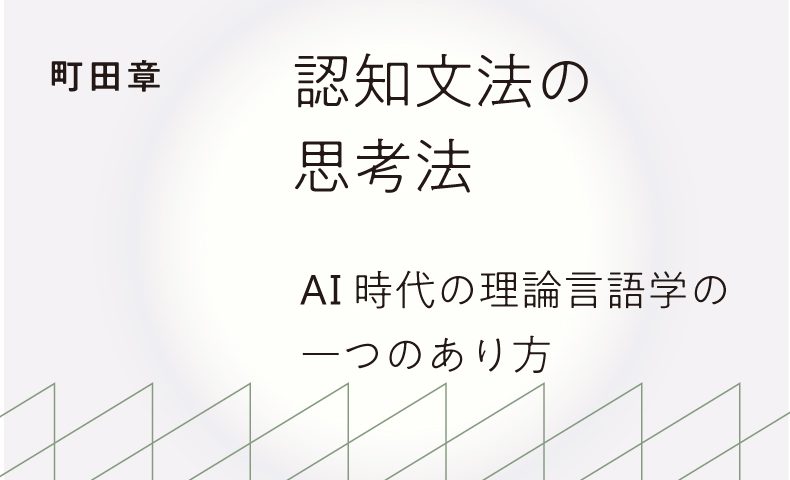はじめに
よく、“強いものが勝つ”なんて言いますが、勝負の世界では“ルールを味方につけたものが勝つ”という側面もまた無視することはできません。例えば、フィギュアスケート。フィギュアスケートでは、技術点や演技構成点など、様々な要素を勘案して総合的に採点されることになります(詳しくはココ)。そして、どんな要素を評価項目に入れるかや配点の仕方によって順位が影響されることになりますので、これらが変更されれば、順位も変わってくることになります。つまり、勝敗は思った以上にルールに依存しているのです。そのため、スポーツ界ではルール変更は死活問題になります。かつて1990年代に常勝軍団と言われた日本のノルディックスキー複合チームはこのことを痛いほど経験しています。ノルディック複合競技では、前半ジャンプの飛距離を時間に換算して、後半のクロスカントリーのスタート時間に差をつけるのですが、この換算式がちょっといじられただけで、常勝軍団が苦戦を強いられることになったのです。
科学理論にも勝敗はあります。有名なのは地動説と天動説の争いです。同じ現象を説明する理論が複数あった場合、どの理論が最も妥当性が高いか勝敗を決めるのです。ところが、科学理論上の勝敗には、意外にも、スポーツの場合と同じく、ルールによって左右される部分があります。そして、そのルールを誰が決めるかというと、トマス・クーンが『科学革命の構造』という著作で指摘しているように、その時々の学問的風潮であるパラダイムが決めることになります。そこで今回は、理論の勝敗を決めるルールについて皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
二つの説明
さて、前々回取り上げたプラトンの問題を思い出してください。その中に、「人間が持っている言語知識には、耳にした表現からは到底学習できないような性質を持った知識が含まれているのに、こどもがことばを習得することができるのはなぜか」という問題がありました。例えば、(1a)は言えるのに(1b)は言えないということは英語母語話者であればだれでも知っていますが(*は容認されない表現であることを表しています)、このことは、少なくとも、(1a)では、wantとtoの間に何もないのでwant toが縮約されてwannaと発音されるのに対し、(1b)では、wantとtoの間に発音されない痕跡tがあるので、want toの縮約はできないということを英語母語話者は知っていることを意味しています(詳しくはココ)。
(1) a. Who do you wanna meet?(誰に会いたいの?)
b. * Who do you wanna meet Bill?(誰にビルに会ってもらいたいの?)
これを受けて、チョムスキーは問います。なぜ、(1b)のwantとtoの間には発音されない痕跡tがあることを母語話者は知っているのか?この痕跡tは発音されないわけですから、話者にはその存在を知る由もありません。そのため、このような知識は習得できないはずなのです。そして、このように習得できない知識を用いて人間はしゃべっているという事実は、この知識が予め脳内に埋め込まれていることを強く示唆しているのです。
さて、これに対して、認知文法ではどのように反論するのでしょうか。認知文法的な思考法を用いると、まず、wannaは単なる音声だけの縮約ではないことになります。wantとtoという2語が、wannaという1語になったのだと考えるのです。では、なぜ1語になったのかと言えば、それは文法化grammaticalizationと呼ばれる現象だと考えます。例えば、be going toが未来を表すことは中学校で学びましたね。厳密にはイコールではないのですが、will=be going toのように。この場合のgoingは文字通りの「行く」という移動を表していませんが、もともとは、(2a)の「手紙を出しに行く」のように、移動を表す動詞のgoの進行形だったわけです。それが、徐々に、移動の意味が無くなり、(2b)の「明日は雨が降る」のように、未来の出来事を表すようになります。そのようになると、be going toはもはや3語ではなく1語の助動詞であるかのように見なされ、最終的には、(2c)のように本当に1語gonnaになってしまいます。先ほどのwill=be going toという中学校で習う書き換えの公式が図らずも意味しているのは、be going toは意味的には1語だということです。意味的に1語であるなら、形の上でもgonnaという1語になってしまうのもうなずけます。このように、普通の単語(内容語と言います)が助動詞のような文法要素としてみなされるようになる現象のことを文法化と言います。
(2) a. I am going to post the letter.
b. It is going to rain tomorrow.
c. It gonna rain tomorrow.
同様に、want toという2語が意味的に1語に感じられるようになれば、wannaという1語になってしまうのも無理のないことです。(3a)のwillと(3b)のwannaは、さすがに意味的にイコールとまでは言えませんが、似ている点はありますよね。例えば、ともに直後の動詞goが原形になっている点やパーティーに行くのはともに文の主語Iである点。パーティーに行くという出来事はまだ起こっていないというところも似ています。つまり、(3b)のwannaは意味的に助動詞に似ているのです。
(3) a. I will go to the party.
b. I wanna go to the party.
では、なぜ(1b)の*Who do you wanna meet Bill?は容認されないのでしょうか。それは、(1b)の*wannaは、意味的に助動詞に似ていないということに尽きます。つまり、(1a)のwannaは助動詞に似ているが、(1b)の*wannaは助動詞に似ていないということが、(1)の容認性の差異を生みしていると考えるわけです。実際、(1b)の*wannaは決定的に助動詞に似ていないところがあります。それは、通常の助動詞は必ず直後に来る動詞の主語が文の主語になっているということです。(1a)のmeetの主語はyouであり、これは文の主語でもあるわけですが、(1b)のmeetの主語はwhoであり、文全体の主語であるyouとは一致していないのです。
当然、この他にも様々な分析がありえますが、とりあえず、以上の議論をまとめると次のようになります。
生成文法:(1b)ではwantとtoの間にある痕跡tが縮約を阻害している。
認知文法:(1b)のwant toは助動詞らしさに欠けるため1語とはみなされない。
もちろん、文法化からの説明に対する反論はあります。wantはあくまでも動詞であって、(1a)や(3b)のwannaも助動詞ではないと。もし仮にこれらが助動詞であるのであれば、(4)に示すように、疑問文では主語-助動詞の倒置Subject-Aux Inversionが起こるはずだ。しかし、実際にはdo you wanna ~ ?になり*wanna you ~ ?になっていないではないかというものです。
(4) a. Who will you meet?
b. *Who wanna you meet?
このような反論に対しては、wannaは助動詞っぽい性質を持ってはいるが、厳密には助動詞とは言えないと答えるしかありません。ただ、このように動詞と助動詞の間にグレーゾーンを認めるというのは苦しい言い訳にすぎないというわけでもありません。動詞か助動詞かという二者択一の答えだけを良しとすること自体が現実に即していないと考えられるからです。実際、他にも、ought toやhave toなど、動詞と助動詞の中間のような例はたくさんありますし(Quirk et al. 1985: 137)、助動詞が動詞から徐々に変化したものであるという英語の歴史を考えると、グレーゾーンの存在は、むしろ、積極的に取り入れていく必要があるのです。
重要なことは、上記の説明では、チョムスキーの言うプラトンの問題「人間が持っている言語知識には、耳にした表現からは到底学習できないような性質を持った知識が含まれているという問題」自体が生じないということです。音を伴わない痕跡tを仮定する必要がないからです。こどもは(1)の容認性の違いをwannaの助動詞っぽさの違いから容易に推測することができるのです。
審判の日
ここでは、二つの異なった説明の例を示しました。それでは、みなさんはどちらの説明に軍配を上げるでしょうか。「助動詞っぽい」なんていうあいまいな説明を用いる認知文法の負けでしょうか。いや、むしろ、グレーゾーンを仮定する方が現実に即していると考えるでしょうか。
そこで、冒頭で取り上げた勝敗を決めるルールが重要になってきます。要するに、どのような採点基準(評価基準)を用いるかによって勝敗が変わってくるということです。そして、その基準を決めるのがパラダイムということになります。
認知文法のパラダイムでは、勝敗の基準をことばの成り立ちつまり言語の進化にまで掘り下げて次のように考えます。言語の進化について議論する場合、人間という種の生物学的進化について考えることはよくあります。ただ、その一方で、言語それ自体が進化(変化)していることも事実です。言語は、単純な叫び声の段階から徐々に複雑な構造を持つ現在の言語へと進化してきたのです。つまり、言語学者は人間の生物種としての進化を見るのと同時に言語それ自体の進化も見なければならないのです。
一般に、進化を議論する場合、自然淘汰を促す淘汰圧というものを考える必要があります。この淘汰圧が何かによってどのような子孫が残されるかが決まってくるわけですから、淘汰圧が何かを特定することは極めて重要な課題です。では、言語進化における淘汰圧とはなんでしょうか?どんな言語が生き残るのかという言語全体の話になると、政治力、経済力、軍事力、文化力、などが生き残る言語の淘汰圧ということになりますが、言語内の個別な表現や文法にかかる淘汰圧はいったい何でしょうか。もちろん、一概には言えないことですが、習得のしやすさという条件はかなり強い淘汰圧となるはずです。つまり、どんな子にも習得できるという特徴を持った表現や文法が後世に引き継がれるということです。当たり前のことですが、一部の優秀なこどもにしか習得できないような表現や文法は、次世代には受け継がれていかないのです。例えば、仮に知能指数IQ 130以上のこどもにしか習得できないような文法が偶然生まれたとしても、そのような文法を用いて話す話者の数は次第に減っていき、最終的には消えてしまうでしょう。つまり、言語進化を考えると、どんな子にも習得できる文法だけに落ち着くはずなのです。言い換えると、習得できない文法はないということになります(詳しい議論はDeacon 1997を参照)。このように考えた場合、習得できない要素である痕跡tを用いた説明は、認知文法のルールではそもそも採点対象になりません。サッカーで言うと、手を使ったゴールのようなものですから。
パラダイム
今回、みなさんと考えたかったのは、認知文法が正しくて生成文法が間違っているということではありません。認知文法と生成文法では採点基準が違うということです。スポーツで喩えるならば、同じ競技なのに採点基準が異なっているということになります。これでは、勝敗を決めても意味がありませんよね。どちらの採点基準を用いるかによって、どちらに軍配が上がるかが決まってしまうわけですから。では、その採点基準を統一すればよいではないかということになりますが、なかなかそうはいきません。なぜなら、この採点基準は恣意的に決められているわけではなく、それぞれの学派がよって立つパラダイムに従っているからです。
よく、認知文法(認知言語学)の説明はあいまいであると批判されることがあります。この批判の背後には、「ゆえに、認知文法は反証可能性がない。ということは、認知文法は経験科学ではない」という意味が込められています。科学である以上、あいまいな記述や説明はご法度だからです。ただ、この批判も認知言語学のパラダイムから見たら、必ずしも妥当なものとは言えません。今回取り上げた動詞と助動詞のグレーゾーンの話からもわかる通り、カテゴリーの境界線上にはあいまいなグレーゾーンがあるものなのです。グレーゾーンがいたるところにあることは周知の事実ですし、認知言語学のパラダイムでは、このグレーゾーンを適切に扱える理論の方がむしろ高得点が与えられるわけです。
同じ現象を異なったパラダイムで見る
ちなみに、言語はどんな子でも習得できるようにできているはずだと考えるパラダイムから見ると、チョムスキーが普遍文法の根拠の一つとしている以下の言語事実にも異なった捉え方が与えられます。チョムスキーは後天的な学習には通常個人差があり、算数が得意な子がいる反面、苦手な子がいたり、絵が上手に描ける子がいる一方で、下手な子もいると指摘しています。このように、通常、後天的に習得する技術や知識には個人差が生じるのです。ところが、言語に関しては、そのような個人差がありません。ある言語共同体の中で育てば、ほぼ一様にすべてのこどもがしゃべれるようになるのです。これを受けてチョムスキーは、それは、どの子にも一律に生得的な言語能力が備わっているからだと結論づけます。二足歩行に上手い下手がないのと同じように人間の生得的な本能である言語能力にも高い低いがないというわけです。
これに対し、言語自体の進化を考えるパラダイムでは、同じ事実に関して全く異なった説明を与えることができます。それは、どの子にも習得できるような表現や文法だけが進化の過程で生き残ってきたので、言語習得に落ちこぼれは存在しないという説明です。つまり、言語習得が一様に行われるのは、普遍文法UGの仕業ではなく、言語進化の結果だというわけです。
このように、異なったパラダイムを通して同じ現象を見ると異なった帰結が出てきてしまうということがあります。これも言語研究を難しくしているところです。
まとめ
今回検討した二つの異なる説明のどちらがどれほど真実味を持っているかということは、言語学内で議論している限りにおいては、なかなか決められません。そこで外部からの意見を参考にするわけですが、この連載で再三強調しているように、ここでもAI(人工知能)研究の知見が大変参考になるわけです。
では、AI研究は僕たちに何を示してくれるのでしょうか。まず、本連載の第3回、第4回で議論したように、あらかじめインストールされたプログラムなしに、与えられたデータだけから知識を学習するというディープラーニングの試みは、認知文法のパラダイム(用法基盤主義)を強力に後押ししていますね。また、あいまいなカテゴリー境界をどのように扱うかという問題は、AI研究が長年苦労してきた課題です。そして、人間の神経細胞のネットワークを模したディープラーニングは、経験から獲得される概念(カテゴリー)は、そもそもそのようなあいまい性(程度問題)を備えているものであることを予測しています。ですので、助動詞を「助動詞らしさ」の程度の問題と考えることは、ディープラーニングからも支持されていると考えてよいと思います。
サッカーでは手は使えません。これはルールで決まっています。ですので、どんなにピンチでもゴールキーパー以外のサッカー選手は手を使えないのです。そのことを知らずに、「手を使えー!」などとヤジを飛ばしても、(もちろん、反則を承知で手を使うこともありますが)意味がないのです。それと同じで、どんな難問にぶち当たっても、どんなに説明のために便利であったとしても、認知文法研究者は習得できない要素を用いて説明することはできません。これは、認知文法研究者の自由度をかなり制限することになります。しかも、ここではwannaの縮約可能性だけを論じましたが、当然、これ以外にも習得できない要素を用いた生成文法の説明はたくさんあります。そして、認知文法研究者は、その一つ一つに対し習得できる要素だけを用いた代案を示していかなければならないのです。スポーツのルールと研究上のルールはその存在理由が全く異なりますが、厳しい制約の中でプレーするからこそ生まれる創造的なプレーを期待したいところです。