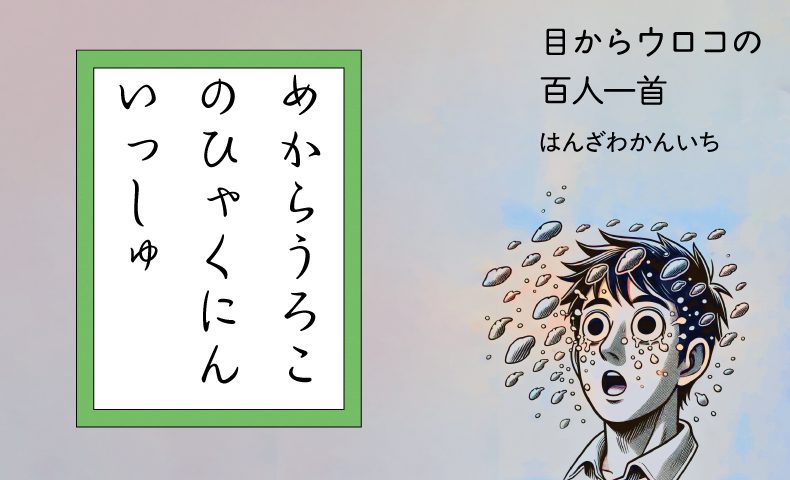「しのぶ」と「恋」という言葉がありますから、前回の39番歌と同じ設定です。古典和歌では、恋の中でも「しのぶ恋」というお題で詠むことが盛んに行われていました。それだけ、恋歌としては魅力的な状態ということだったのでしょう。
では、この歌に詠まれた「しのぶ恋」のありようは、どんなものでしょうか。
〔ウロコ1〕「しのぶれど」
39番歌の「しのぶれど」には、逆接条件として、続く表現とのつながりのうえで、不審な点がありましたが、この歌の場合は、続く「色に出でにけり」との関係が、すんなり受け入れられます。
「しのぶ」というのは、色に出さない、つまり表にはっきり見せないことであり、そのつもりでいたのに、「色に出でにけり」なのですから、まさに逆接の関係が成り立ちます。
〔ウロコ2〕「色に出でにけり」
「色に出でにけり」の「けり」は、無意識に色に出てしまっていたことに気付かされたということを示しています。その気付きの驚きようが、表現そのものにも表わされています。
この歌は第二句で切れ、下三句は上二句と倒置の関係にあると見られます。ただし、その関係が他とはやや異なっています。
それは、この下三句がひとまとまりとして、上二句と倒置になっているわけではないからです。どういうことかと言うと、上二句の表現に対し、第三句の「わが恋は」はその主語として、第四・五句の「ものや思ふと人の問ふまで」はその連用修飾句として、それぞれ別々の働きで結び付いているということです。
つまり、この歌は、あたかもつかえつかえしながら、後から言葉を付け足してゆくような歌い方になっているということです。
普通に考えたら、思い付きそのままの、いかにも稚拙な歌い方かもしれません。しかし、あえてそのように見せたのだとしたら、なかなかの技です。実際に、それが認められたからこそ、拾遺集にも百人一首にも選ばれたのでしょう。
その技とは、忍ぶ恋を周りに気付かれてしまったことに対する、詠み手の動揺と驚きのさまを表わすために他なりません。おそらくはごく親しい友人に、「あなた、このごろ、ちょっと変よ、恋でもしたんじゃないの?」といきなり聞かれたら、うろたえることでしょう。まして、本人が意識していないならばともかく、うまく忍んでいると思っていたとしたら、なおさらです。
〔ウロコ3〕「ものや思ふと」
「もの思ふ」と言えば、古典和歌の世界では、たいてい恋の思いのことですから、「ものや思ふ」という問いは、恋をしているのかという意味を表わします。
この歌の表現において、きわめてユニークな点は、「「ものや思ふ」と人の問ふ」のように、会話文を直接話法で取り入れているところです。和歌の中に会話文を引用することはめったにないのですが、それによって、その時の状況がリアルに再現されることになります。
さて、このようにリアルな歌が、詠み手の想像による創作だったとしたら、もっとすごいということになりませんか。
じつは、この歌が載っている拾遺集(巻11・恋一・621番)の詞書には「天暦御時歌合」とあります。もともとが歌の技量を競い合う場で、お題に即して詠まれた歌なのでした。