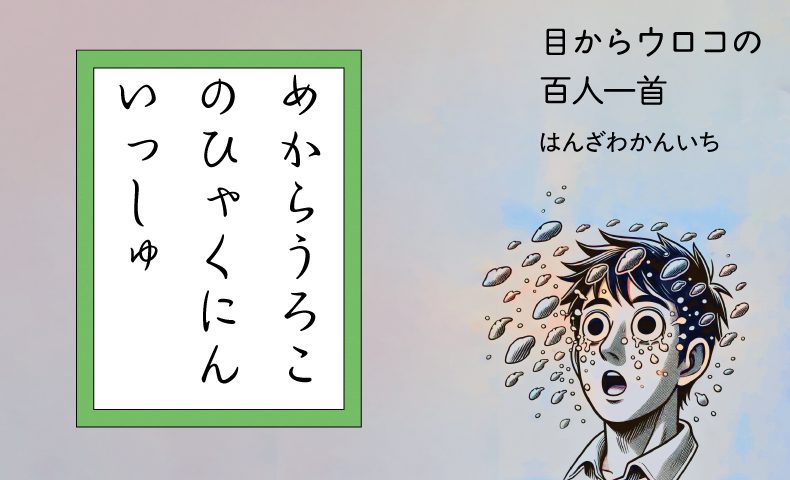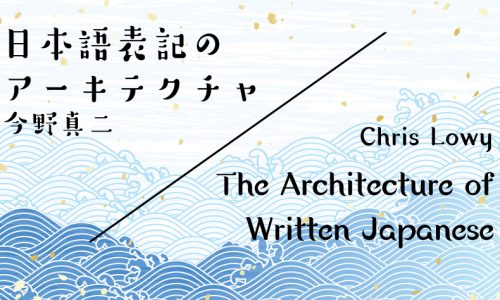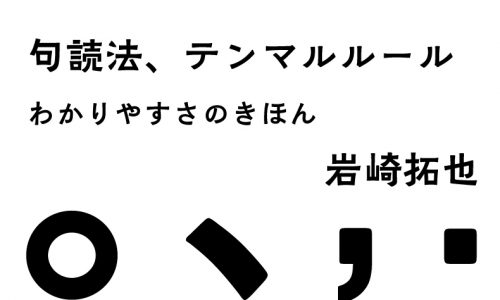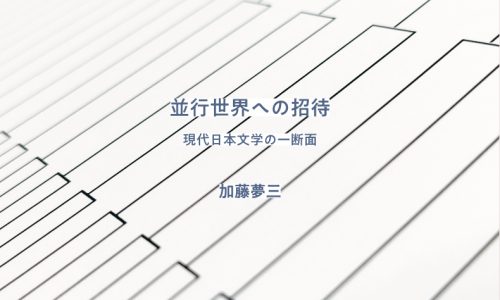忘らるる身をば思はず誓ひてし人の命の惜しくもあるかな
このような歌が、訳ありの相手から送られてきたとしたら、その当人はどういう反応をするでしょうか。嬉しいと思うか、重い…と感じるか。
〔ウロコ1〕「忘らるる身」
「忘らるる」の「るる」は助動詞「る」の連体形ですが、意味は、受け身、可能、自発、尊敬のうちのどの可能性もあります。中でもっとも可能性が高そうなのが受け身です。
それは、1首の中に、「身」と「人」という2つの言葉が用いられているからです。この対比関係においては、「身」は自分自身のこと、「人」は相手のことを意味します。自分と相手との関係から、「忘らるる身」ということならば、受け身として、相手に忘れられる自分という捉え方ができます。
〔ウロコ2〕「誓ひてし人」
そのような自分に対する相手が「誓ひてし人」です。「忘らるる身」という表現と対比して、異なる点が2つあります。
1つは、その行為の時点が異なるという点です。「誓ひてし」のほうは、「誓ふ」という動詞に、完了の「つ」と過去の「き」が付いていて、それがあくまでも過去であることが示されています。ということは、今はもう違う、つまりその誓いは一方的に破棄されているということです。
いっぽう、「忘らるる」は、過去のこととしてではなく、現在あるいは今後のこととしても表現されています。誓いを反故にされた結果としての「忘らるる」です。
もう1つは、表現としての完結性の違いです。「忘らるる」は自分が相手に「忘らるる」という関係だけで表現が成り立ちますが、「誓ひてし」のほうは、相手が自分に対してというところまでは分かるものの、何を誓ったのかが示されていません。
まあ、恋愛関係を前提とすれば、男女が誓うのは永遠の愛、とだいたい相場は決まっていますから、省いたのかもしれませんが。
〔ウロコ3〕「思はず」と「惜しく」
「思ふ」対象は「忘らるる身をば」という表現が直前にありますから、自分ということになります。主語は省かれていますが、詠み手でしょう。それに対して、「惜し」と思うのも詠み手ですが、その対象は直前に「誓ひてし人の命の」とありますから、相手しかありません。
これをまとめれば、詠み手は、自分の命は惜しいと思わないが、相手の命は惜しいと思う、ということになります。もし捨てられたのなら、相手を恨んだり憎んだりするのが普通でしょうに。
さて、問題は、なぜそう思うのか、ですが、注釈書によれば、なんと、相手は誓いを破ったために、神罰を受けて死ぬから、なのだそうです。
しかし、もしそういうことが実現していたとしたら、古典和歌の恋歌の半分は無くなってしまいそうです。罰が当たって、ザマーミロ、で終わりですから。そうはならないからこそ、嘆きの恋歌が詠まれたのではないでしょうか。
やはりこの歌の鍵は、「誓ひてし」にあります。過去にたった1度でも、そしてたぶんたった1人だけ、自分に愛を誓ってくれた相手のことを今でも愛おしく、ずっと生きていて欲しいと思っているということです。相手に忘れられてしまうくらいの自分なんかよりも。
相手の反応はともかく、世の中には、そんなタイプの人間もいると思いませんか。