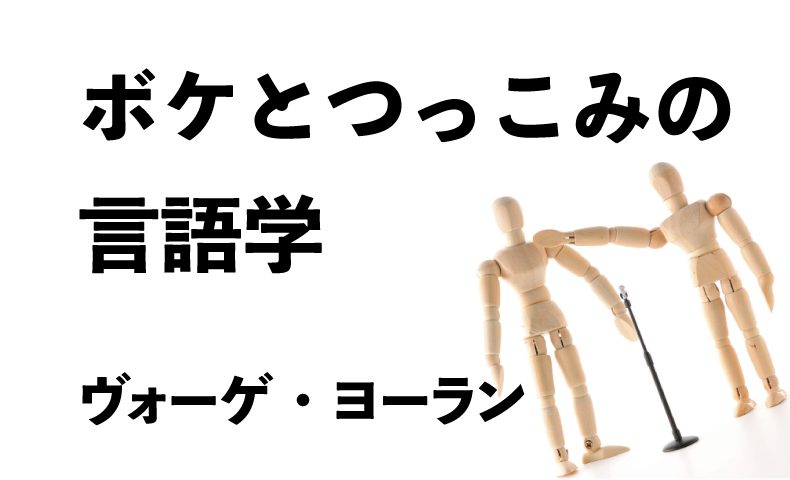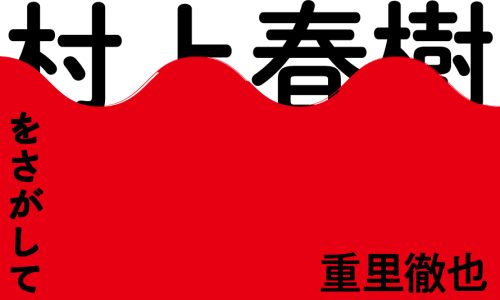アチャコ:また体重がちょっと増えました。
エンタツ:いくらくらいあります?
アチャコ:最近、62キロですわ。
エンタツ:足も入れて?
アチャコ:あたりまえやがな。タコ買いに行くんやなし。足だけ別に掛けるかい。
(秋田他2008『昭和の漫才台本』pp.22-23より)
1 社会言語学の研究と日常
社会言語学を専門とする人はよく周りの日常的なコミュニケーションから研究のアイデアをもらう。例を挙げよう。私自身はノルウェー出身だが、20年ほど前に留学生として初めて日本に来た時に映画館を訪ねた際、自分が笑うところは日本人と違うことに気が付いた。また、バーに行ってみて周りの人にふざけたことを言われて、ただ「は~」と答えると、その人に「そこつこっまなあかんで」とよくからかわれた。
これらの経験からいくつかの疑問や研究課題が湧いてきた。「日本と欧米の笑いはどこが違うのか」「日本の笑いにはどの特徴があるのか」「関西文化と笑いにはどのような関係性があるのか」「関西のバーではどの会話術が求められるのか」など、挙げればきりがない。
ちなみにその後はどうなったかというと、日本に来て1、2年が経つと、つっこむところは分かるようになったが、妥当な返事を思いつくまで数秒がかかり、笑いを取るタイミングを逃してしまっていた。しかし今ではほとんどのボケに対して適切につっこめる自信はある。近所の子供に「○○でギャグを作って言ってみて」と頼まれたら2秒以内答えられるようになった。自分で言うのもなんだが、大阪で生まれ育った関西人に負けない。
2 笑いの研究
このようなきっかけで10年ほど前にボケとツッコミの言語学を研究するようになり、「ボケとつっこみの構造」「ボケとつっこみの習得」「ボケとつっこみの地域差」「笑いと文化の関係」「笑いと大阪学」「笑いとタブー」など、様々な観点から笑いを調べ、研究論文を10稿ほど執筆してきた。
日常的なコミュニケーションから研究のアイデアをもらうのだが、研究にはオリジナリティーがなければ、意味がない。では、長い歴史があるユーモア研究の中で、何が新しく言えるのだろうか。確かに、日本の笑いの伝統は際立ち、私自身もよく引用してきた南原清隆の本『狂言でござる』(2010)のサブタイトルは「ボケとツッコミには600年の歴史があった」になっているほどである。
一方欧米でも、啓蒙時代の初期から哲学者たちはユーモアの仕組みについて様々な観点から考えてきている。イギリスの哲学者トマス・ホッブズ(1588年~1679年)は代表作『リヴァイアサン』でユーモアの本質をこのように分析している。
とつぜんの得意は、笑いとよばれる顔のゆがみをおかせる常念であり、それは、自分のあるとつぜんの行為に喜ぶことによって、あるいは、他人のなかになにか不恰好なものがあるのを知り、それとの比較で突然自己を称讃することによって、ひきおこされる。
(水田訳1954、p.107)
しかしながら、ユーモアの比較研究、あるいは欧米と日本の笑いの間に橋を架けるものはそれほど存在しないのは事実である。日本語訳も出るほど人気を得た『世界の“笑いのツボ”探し』(2015)では、世界の笑いを求めて旅に出るアメリカ出身の作者のマグロウとワーナーは日本については「さまざまな要素によって『何をおもしろいと感じるか』が違うのはなぜか。この謎を解明するのにうってつけな地として、僕らは日本を選んだ。なぜかと言うと、かの地ほど僕らと異なる笑いを持つ国を、僕はほかに知らないからだ。」(p.171)と述べている。私自身も外国人の日本語日本文化の研究者として、多くの研究課題が残っていると感じ、このコラムを通して、日本の笑いの位置づけを明確にし、そして日本の笑いで欠かせないと言われるボケとつっこみの核心を少しでも突くことが出来たら嬉しく思う。
3 笑いの相違点:笑いの構造について
本題に戻る。そもそも、なぜ多くの外国人は日本の笑いを理解できないのか。そして日本人はなぜ欧米の笑いは面白くないと思うかの。この問いを答えるには主に、3つの仮説がたてられるだろう。①ユーモアや笑いの構造が異なるため、お互いに通じ合わない。②日本と欧米の文化は異なるため、ユーモアや笑いに対する価値観が異なる。③言語の壁が高く、外国語でユーモアや笑いを理解するには相当な能力が必要である。それに伴って、ユーモアや笑いの通訳・翻訳は困難である。答えは…おそらくどれも検証する必要がある。
順番に3つの仮説を見ていきたいと思うのだが、まずはここで欧米という言い方について少し説明しておきたい。欧米とは、言うまでもなくヨーロッパとアメリカを表すのだが、当然2大陸に渡って様々な文化や笑いの価値観が存在する。もちろん欧米全地域を調べつくしたわけではないが、大局的に見ればいくつか傾向が目立ち、これらの傾向がまた日本の事情と異なるという主張は無茶ではないと思う。いずれにしても、色々あることを認めながら、必要に応じて詳細な地域を特定して分析を進めていく。
日本の笑いの構造の特性への足掛かりは前陳の南原清隆の書籍タイトルにある。やはり、つっこみは一つの中心的な概念であることを認めざるを得ない。その歴史は600年前の狂言までもさかのぼると考えられる。つまり、能と並行して、ボケとつっこみに似たようなやりとりに基づいた笑いを取るのが目的とする伝統芸能ができたと考えられる。これほど古いものは世界で類を見ないだろう。
伝統が時間とともに変化していくわけだが、この対話及びやりとりの構造がそのまま引き継がれて現在でも流行りのしゃべくり漫才に残っている。それどころか、ボケとつっこみの構造は漫才の見どころにまで発展してきた。よく考えてみれば、落語でも落語家が一人で高座の上に座り噺を進めるが、そこで落語家が上下をつけて、つまり右を向いたり左を向いたりするやりとり形式で二人の人物を演出するのもこれである。
ちなみに、現在のボケ役とつっこみ役(いわゆるコンビ)が定着したのは昭和初期における第一漫才ブームのころだったと考えられるが、笑い用語としてのボケとつっこみはもっと新しいと考えられる。私が持っている笑いに関する書籍の中で最初にボケとつっこみが笑いの専門用語として出てくるのは1975年に出版された岩城未知男『コント55号のコント』である。
また、ボケとつっこみは頻繁に関西人および関西文化と結びつけられる。「大阪人が二人寄れば漫才が始まる」と言われるほどである。これにも歴史的社会的な理由があるだろう。冒頭にも紹介したエンタツ・アチャコの漫才はラジオを通して、関西から全国にまで放送されるようになったし、今でもテレビに出ている漫才師の過半数は関西出身である。
私が2013年に実施した笑いに関する意識調査では関西人は他の地域の人より「会話のなかでつっこむ」「場合に応じてボケたり、つっこんだり、両方できる自信がある」「会話にオチが必要に思う」、そして「日常生活において、笑いを重視する」という統計的に有意な結果を得た。また笑いの地域差および大阪と東京の比較調査については稿をあらためて論じたいと思う。
4 文化と笑い
次は文化と笑いの関係について論じていきたい。アメリカの笑いに関して南原(前掲)は非常に的確に述べているためここで改めて引用する。
アメリカには「スタンドアップコメディ」というジャンルがありますが、あれが日本人にまったくウケないのも、「ボケ」だけで「ツッコミ」がないからでしょう。たとえば、こんな感じです。」「おれのカミさんは最高だぜ。と~っても頭が良くて、最高に美人で、おおまけに特徴的だ。なぜなら喉仏が出てるからさ」アメリカ人は、これで「ワーッハッハ」と大笑いします。でも、日本人は笑えません。ぜんぜん、面白くない。ところが同じネタでも、最後に別の人が「男じゃんか!」とツッコミを入れると、それなりに笑えるようになるのです。
(p.30)
このように日本人はつっこみがないと笑わないと言われているが、アメリカ人はおそらく真逆で、せっかく誰かが面白いジョークを言っているのに、それに対して他の人がつっこんで、割り込むのが極めて失礼な行為になると考えられる。ジョークの展開のハイライトであるパンチラインの衝撃が薄れるからである。パンチラインとはストーリーの中の思いがけない展開であり、ボケに近いと言える。アメリカの笑いにおいて、ジョークはパンチラインがどれぐらいおかしくて他の人をびっくりさせるか、またはどれぐらい賢く捻っているかによって評価される。
人間は自分の文化にあるものを当たり前のものと考える傾向はある。欧米につっこみという概念が発達していないのは日本人には不思議に思われるかもしれないが、よく考えてみれば、変わっている部分はボケであり、つっこみ役は大体正論を言う。笑い、つまり笑い声及び笑顔を招くにはボケだけで十分のはずである。
冒頭のエンタツとアチャコの漫才では、おかしいところは人の体重に対する「足も入れて?」というセリフである。私の日本での経験で言えば、このようなボケのセリフで笑う人はいないことはないが、やはりつっこみのセルフ、つまりおかしいところに対する指摘の方が笑いを取る。是非次に漫才を見る時にこれに注目してもらいたい。
次に構造の延長線上にある文化による笑いへの習慣や価値観に目を向けたい。アメリカを始め、多くの欧米の地域で主流なスタンドアップコメディでは、一人のお笑い芸人がステージに立って、数多くのジョークを混ぜ合わせたストーリーを語る。それに対して日本ではやりとりに基づいたものの方が観客を笑わすというわけである。いうまでもなく、日本にも一発ギャグやコントなどやりとりに依存しない笑いはあるが、それと同時に掛け合いを評価する、いわゆる対の文化が続いている。
先行研究には笑いが行われている場面及び文脈を取り上げるものがある。これらによれば、日本では多くの面白い話やストーリーはプライベートな場面において、つまり家族や友達同士で語り合われているという(大島2006、山口2018)。それに対してウチとソトの間の境界がより曖昧なアメリカではフォーマルな場面や見知らぬ人同士でジョークを言うのが許されている。急に見知らぬ人と落ち着きのない状態に置かれたらジョークを言う作戦が一番無難とされている。
さらに、マグロウ(前掲)に、日本のテレビでお馴染みのアメリカ出身のお笑い芸人ハーラン・パトリックは日本の笑いの内容について以下のように述べている。
「アメリカでコメディの中枢となるような笑い―たとえば政治ネタなんかは、日本ではほとんど見られません」(中略)日本の政治はあまりに安定していて、選挙もあまりにあたり障りがなく退屈なため、政治が笑いの種にならないだという。(それに、天皇はジョークにするにはあまりに神聖すぎる)。
(p.202)
確かに、突っ込みたくなる時が多いにもかかわらず、政治家及び隣接国を馬鹿にしたお笑い番組は日本になさそうだ。ヨーロッパにこそ、サタイア(諷刺)という権威を持つ人に対して、面白く批判する習慣が少なくとも古代ギリシャから続いている。日本のテレビで見られる、もう一人の外国人お笑い芸人、オーストラリア出身のムレーン・チャドは、このように文化が異なる理由に関して興味深い仮説を提案する。いわゆるエスニックジョークなどを含めて、批判的ジョークが多い欧米に対して、日本の笑いの中心となるのはどちらかと言えばポジティブなもので祝福芸のようなものという(チャド2017 p.66)。日本のことわざの「笑う門には福来る」はこれの現れかもしれない。
その他に、本稿と関連性が高いタイトルの『日本の笑いと世界のユーモア』(大島前掲)で、大島は、体験談及びやりとりに基づいた笑いは日本などの高コンテキスト文化にはよく見られると主張している。それに対して、アメリカが代表する低コンテキスト文化ではジョークが主流だという(p.46)。コンテキストとは文脈という意味だが、日本のような高コンテキスト文化では共有性が高いため、すべてを明確な言葉に表現しなくても、その文化のメンバー同士は通じ合うと言われている。
ただ、大島の仮説には、いくつか問題があると思われる。まずは、日本のつっこみはどちらかと言えば、物事を明確な言葉に表現した笑いと言える。さらに、多くのジョークはコンテキストに依存しており、隣接国や政治について共有している知識があるからこそ笑いが生まれる。
私は以前、この笑いの内容の違いを説明するにはウチとソトの対立が有効と主張してきた(Vaage 2020)。要するに、日本人は権威を持つ人などソトの人を馬鹿にしたジョークより、自分の失敗談や例えばオカンの面白いエピソードなど「ウチ」についての笑いを好む傾向があるのではないだろうか。日本は笑いにおいても「謙譲の美徳」が評価される文化と言えるかもしれない。
結局ことばは難しいものである。本稿では構造的、文化的、歴史的な理由で日本と欧米の笑いは異なるところを見てきたが、当然異国の笑いを理解するには相当な語学力が必要となる。私は日ごろ大学で働いており、授業で様々な方法を使って学生にアメリカンジョークを教えてきているが、これはやはりなかなか困難な課題である。研究結果公開はこれからだが、アメリカのダジャレ及び文の曖昧性によるジョークであれば、パターンを覚えて理解を比較的早く得る事が可能であることは分かったが、文化やその土地の言葉の言い回しの知識を求めるジョークはやはり何年かその地域に住んでから面白く思えるようになる。
そして長年大阪大学日本語日本文化教育センターで日本文化及び言語に深い知識のある国費留学生に日本の笑いの文化を紹介してきたが、私のように、日本の笑いを病みつきになる人とならない人に分かれる。
最後に、つっこみの有無の話に戻る。日本の笑いにツッコミは欠かせないと言ってもいいぐらいだが、欧米ではほとんど見られないと述べた。とは言え、国際学会で時々日本の笑いを紹介する機会がある。参加者は大体日本の文化に興味を持ってくれて、つっこみにも関心を寄せる。「私の文化でもつっこみに似たものはあるよ」としばしば言われることもある。これらの例は社会言語学の研究をしている私にとって大変貴重である。将来取り組んでいきたい研究課題の一つは「世界のつっこみ表現と事例」を集めることである。あぁ、研究人生が3回分ぐらいあればなぁ。なんと悲しや!
参考文献
秋田實他 2008『昭和の漫才台本』文研出版
岩城未知男1975『コント55号のコント』サンワイズ・エンタープライズ
ホッブズ・トマス1651『リヴァイアサン』水田洋訳(1954)岩波書店
マグロウ&ワーナー2015『世界の“笑いのツボ”探し』CCCメディアハウス
マレーン・チャド2017『世にも奇妙なニッポンのお笑い』NHK出版
南原清隆2010『僕の「日本人の笑い」再発見 狂言でござる ボケとツッコミには600年の歴史があった』祥伝社
大島希巳江2006『日本の笑いと世界のユーモア』NHK出版
山口治彦2018「パブリックな笑い、プライベートな笑い―ジョークと体験談に見る笑いの種類と文化の関係」定延利之編『限界芸術「面白い話」による音声言語・オラリティの研究』ひつじ書房
Vaage, Goran 2020 Taboos of Storytelling in Japanese. In A. Jarosz & A. Jaworowicz-Zimny (Eds.), Japan Fictions and Reality. Nicolaus Copernicus University Press.