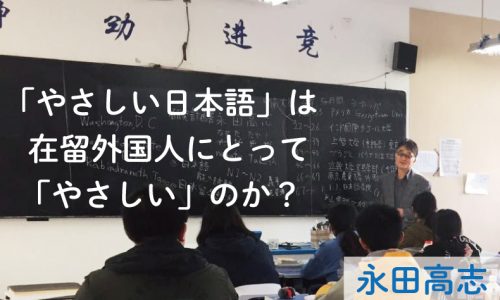平成文学を代表する辻原登
助川幸逸郎 平成文学を考える時に「物語の復権」というテーマははずせないですね。
重里徹也 このテーマで語るべき作家としては、辻原登の名前が最初に頭に浮かびます。質も量も、平成期の最も重要な書き手の一人のように思います。
助川 辻原という作家は、第一回の対談で「辻原第一形態」「辻原第二形態」という感じで成長していったと話しましたが、とにかく作品が多様です。『翔べ麒麟』は、唐代の中国が舞台の歴史小説。『寂しい丘で狩りをする』はミステリー仕立で、重里さんがベスト10にあげておられる『冬の旅』では中年男の転落を描いています。プルーストとかドストエフスキーについての評論もあって、これだけいろんなタイプの著述を手がけながら、どれも水準が高い。辻原登は何人もいるのではないか、と疑ってしまいます(笑)。
重里 辻原登のファンは多いですね。それも、よく本を読んでいる人に多い。大学の同僚から、仕事で知り合った人まで、いろんなところで「辻原登を愛読しています」という声を聞きます。ミリオンセラーになるような作品はまだ出していませんが、読書家の間で根強い人気のある小説家です。
助川 これだけの質と量と多様性。辻原の創作活動には、単に「このひと才能がある」では済まない秘密がある気がします。
重里 辻原が芥川賞を受賞したのは平成二年(一九九〇)で、四十五歳になる年でした。三島由紀夫が自決した年齢なのですね。
遅くデビューした小説家には、大江健三郎みたいに、学生からすぐに作家になったタイプにはない強みがあります。社会人経験が豊富で、世のなかのことを知っているのです。特に辻原は、教師や研究者ではなく、商社マンなど、実業の世界を経験していて、この世のことをよく見聞している。そのことが間違いなく、作品世界を豊かにしているように思います。
助川 デビューが遅い作家というのは二パターンあって、ひとつは「じぶんの世界はこれです」というのが完成した状態でデビューして、そこを書いたらおしまいというタイプ。この種の作家は、ひとつのテーマを突きつめて芥川賞ぐらいまではたどりつくのですが、ちがうひき出しがないので長く活躍できません。
もうひとつのタイプは、社会人生活を送るなかでいろんなネタや方法を仕込んでいて、いったんデビューしたら、ため込んだものを活用して多彩な作品をどんどん送りだす。辻原さんは完全にこっちのケースだと思います。
重里 限られた「自分の世界」を熟成させて、それをある年齢になって公にしたというタイプは、芥川賞受賞作が代表作になります。歴代芥川賞のリストを見ればわかりますが、こういう作家はかなり多い。品のない言い方をすると、一発屋ですね。
ところが辻原の場合、芥川賞を受賞した『村の名前』は出発点に過ぎません。題材や方法だけでなく、思索や経験を深めてからのデビューで、それが平成期に活躍する土台になっているのだろうと思います。
もう一つ。辻原を語るうえで見逃せないのは、比較的早い時期から、新聞連載小説を積極的に手がけていたことです。
新聞小説の効用
助川 辻原の最初の新聞小説は『翔べ麒麟』です。あるインタビューで辻原は、「『翔べ麒麟』の連載を始めるときは、じぶんで企画書つくって新聞各社に売りこみをかけた」といっています。漱石や谷崎のようなスケールの小説を書くには、新聞連載をやって作品世界をひろげないとダメだ、と感じたからだそうです。
重里 当時、私は毎日新聞の記者をしていましたが、九州で勤務していて、読売に取られてしまいました(笑)。新聞連載の利点を三つ挙げましょう。原稿料が高いこと。日頃は文学にあまり関心のない読者の目にも触れる(読者層を広げられる)こと。新聞社ならではの取材のサポートができる場合があること。いろいろな意味で、作家がジャンプするチャンスを用意できるかもしれません。
助川 新聞小説は、広い読者の目に触れるぶん、文芸誌に載る作品とはちがうものがもとめられます。辻原は、社会人の経験があるから、「顧客のニーズ」と「自分のやりたいこと」をすりあわせるのが得意ということはいえませんか?
重里 すりあわせる、というより、新聞というメディアの性質を積極的に利用して、自分のやりたいことにチャレンジしながら、結果として新聞読者にとっても面白いものを提供することができたのではないでしょうか。
助川 そういう建設的な仕事をやっているというのに、辻原の作品は、人間に対し肯定的な作品ばかりとはいえません。重里さんが最も評価する『冬の旅』も、かなりダークな小説です。
重里 辻原の作品を乱暴に評すると、当初の作品には寸止めというか、余韻を残して終わるような小説作法を感じたのです。すべてを書かないで、ほのめかすことで高い芸術性を実現しているといえばいいでしょうか。谷崎賞を受賞した『遊動亭円木』は評価する人のとても多い作品ですが、奇妙な味わいのある作品です。中国を描いた『ジャスミン』、出身地の和歌山を舞台にした『許されざる者』といずれも力作ですが、最後はオープンエンディングなところがあって、読者を迷路に残すような印象があった。それがまた、抜群に面白かったわけです。ジャスミンの香りのように、芸術的な香気を感じさせたといえばいいでしょうか(笑)。
ところが、『冬の旅』となると、主人公の運命を書ききってしまっている。彼の転落していくさまを突き放すように描いているのです。私は作者の筆が、人間という存在の運命そのものに触れているのが切々と感じられて、寒気がしました。たとえば、レールモントフの『現代の英雄』を思い出したといえば、わかりやすいでしょうか。平成の日本文学を挙げるとしたら、欠かせない小説でしょう。
助川 刑務所にこそ入ったことはありませんが、私も何度か、とりかえしのつかない愚行を犯したことがあります。そういうことをやらかすときって、失敗にむかう一本路にはまりこむ感じがするものです。まわりの人間からは「いくらでも途中で引きかえせたはずなのに」という風に見えると思うのですが、当人の実感としては、磁石に吸いよせられるようにまっすぐ破局にはまりこんでいく。『冬の旅』を読んでいると、そういうときの記憶が生々しくよみがえります。
重里 私はぬるい人間で、きちんとした信仰を持っていませんが、『現代の英雄』を読み進めると、運命というものがあるのかなという気がしてくる。それと同じような心情に『冬の旅』は引きずりこむのです。辻原はある深みに到達したのではないでしょうか。
中上健次の代表作は
助川 辻原は文壇主流の私小説系とは異なる物語作家で、紀州出身。「紀州に生まれた物語作家」というと、私なんかはまず中上健次が頭にうかびます。
重里 私の学生時代や二十代のころには非常に大きな存在でした。
助川 平成に入ってわりとすぐ亡くなってしまったので――一九九二年(平成四年)没です――、中上は昭和に活躍した人ということになると思うのですが、ここでも触れないわけにはいかないでしょう。
中上は、一方でみずからの複雑な出自を問題にしながら、それを、神話や王朝物語からつづく日本文学の構造のなかに位置づけていく。私小説系と物語系のハイブリッドというか、非常にスケールの大きなことを試みていました。けれども中上は、辻原がデビューした年齢と変わらない若さで亡くなってしまった。そのぶん、辻原ほどの多様性や完成度には到達できなかった気がします。
重里 中上の代表作は、やはり『枯木灘』でしょうか。
助川 私は、意外にルポルタージュの『紀州 木の国・根の国物語』がいちばんいいのではないかと思っています。中上はたぶん、自分の理想とする小説のカタチを完成させるまえにこの世を去った。そのせいで、ルポルタージュにいちばん「らしさ」がつまっていることになったのではないかと。
重里 意外に『鳳仙花』の評判がいいですね。
助川 わかります。『鳳仙花』は、完成度という点では相当なレベルです。
中上の小説世界の中核になっているのは、『岬』『枯木灘』『地の果て至上の時』の「秋幸を主役とする三部作」ですが、『鳳仙花』は、その秋幸のお母さんであるフサがヒロインです。
重里 『鳳仙花』も新聞連載小説なんですよ。
助川 中上は、連載が途中で中絶したり、ストーリーに破綻をきたしたりした作品もありました。初の新聞連載となると、最後までていねいにまとめる必要にせまられたということでしょうか。
そういう話を聴くと、夏目漱石以来、新聞小説というフレームが日本の近代文学におよぼしてきた影響をあらためて感じます。辻原が新聞小説を書くことにこだわったのも納得です。
重里 中上健次も意識をしていた徳田秋声の『新世帯』『あらくれ』『縮図』といった代表作はみんな新聞小説です。芥川龍之介の『地獄変』、森鷗外の『渋江抽斎』。新聞が初出の名作は少なくないです。
助川 さきほど「中上が、私小説と物語を統合しようとした」っていいましたが、中上ほど壮大な構想をもっているひとは稀にせよ、「私小説作家」と思われている書き手も、けっこう物語を書いています。さっき名前が出た徳田秋声なんかも、中間小説っぽい作品も書いていますね。
重里 やはり新聞は文芸誌とちがって読者層がひろい。「伝わりやすい面白さ」が求められるので、私小説作家でもストーリーテイリングを意識したりするのでしょう。
文芸誌の連載は、新聞よりも書き手の自由を許しますから、作家は喜びます。けれども、いい作品を生むためには当人の自制心か、編集者の辣腕が必要なのかもしれません。
助川 中上は、もっと新聞連載をすればよかったのかもしれません。辻原は、積極的に新聞という枠にはまっていくことで、自己改造に成功したんですね。
重里 辻原は、本名は「村上」というのですよ。村上春樹と村上龍がいるから、辻原というペンネームを使ったのでしょう。
助川 紀州出身の物語作家としては、中上健次がいる。「村上」という名前の作家だと、春樹と龍が人気になっている。ナチュラルに自己を主張できない状況が、辻原をいっそう意識的な作家にさせたのでしょうか。
重里 それが彼の多様性や深みにつながった。やはり遅いデビューの効用かなと思います。
村上龍は日常の裂け目を描く
助川 村上龍も「壮大な物語を構築する作家」というイメージがあります。けれども私は、土地成金の息子がテニスとセックスをくり返してるだけの『テニスボーイの憂鬱』がいちばん好きなんです。
重里 同感です。昭和期の作品なので、今回は挙げなかったのですが。福田和也も、あの作品を高く評価していましたね。村上龍が輝きを放つのは「日常」を描いた時ではないか、と思っています。こういう褒めかたをすると、世間の定評に反するだけでなく、村上龍当人も不満かもしれませんが。
助川 『テニスボーイ』のなかに、土地成金の主人公が愛人と高級ホテルに泊まって、翌日、二日酔いで朝ごはんに食べたパパイヤを吐いて、「今吐いたパパイヤいくらするか知ってんのか? 八百円だぞ、八百円」とかじぶんに突っこんでる場面があります。分不相応の大金をもつようになった主人公の、「断ち切れない小市民感覚」を一瞬にして照らしだしていて、最高です。
重里 『半島に出よ』で、私がいちばんすばらしいと思ったのは、高級官僚が都内の上品なバーで、福岡に上陸した北朝鮮軍を映像で見ているシーンです。非常事態のなかの日常、日常のなかの非日常というのに迫真の深みがあって、こういうシーンを書いたら日本一だと思いました。
助川 龍は、日常の裂け目にすごく敏感な作家です。時間の持続のなかでふっと心に引っかかってくる瞬間をすくいあげるのがうまいというか。その意味で、短歌とか俳句とかの、短詩型文学に適した資質を感じます。「物語」といっても、『源氏物語』みたいな大河小説より、『伊勢物語』みたいな歌物語のほうが得意なタイプ。
重里 一時期、会う人会う人に「村上龍の最高傑作は何だと思いますか」と尋ねたことがあります。吉本隆明は『料理小説集』、河野多惠子は『映画小説集』と答えてくれました。これは示唆することが多いような気がします。龍は「短編が抜群に鮮烈な作家」なんです。
助川 『料理小説集』と『映画小説集』、どちらも「お題になっている料理なり映画なりがあって、それをみじかい物語が取りまく」という構造になっている。歌物語とか芭蕉の紀行文と形態がよく似ています。
重里 龍は、細部をとらえる力をもっと意識的に活用すると、さらにすごい作品を書けるのかもしれません。『半島を出よ』も大長編ですが、登場人物の一人がバズーカ砲を撃つ場面とか、ディテールの面白さの積み重ねが魅力的でした。
宮本輝は空間の作家
助川 「長大な物語」といえば、宮本輝の『流転の海』が昨年、完結しました。三十年以上わたって書きつづけられた超大作です。
『流転の海』には、自伝的な要素も濃厚にありますが、宮本輝といえば「ストーリーテイリングの達人」みたいな定評があります。「物語作家としての宮本輝」について、重里さんはどのように評価しておられますか?
重里 『流転の海』は偉業ですね。すごく貴重な作家だと思います。宮本輝では『骸骨ビルの庭』という作品も好きなのですが、戦後の混乱期と現代の日本社会を対応させながら、庶民の群像を巧みに描き出していました。
助川 村上龍が「瞬間」の作家だとさきほど言いましたが、この表現を踏襲すると、宮本輝は「空間」の作家という印象があります。『流転の海』シリーズでも、幽霊アパートみたいなところが舞台になった五巻目が、私にはいちばん印象的でした。『骸骨ビル』も奇妙な形をしたビルが舞台でしたね。ある「閉ざされた空間」を設定すると、神話的なイメージと時代の風俗が絶妙に交錯して、魅力的な物語が走りだす。そこが、宮本輝の魅力のひとつだと私は思います。
重里 たしかに宮本輝の作品では、「河に浮かんだ舟の中」とか、「日常にまぎれこんだ異空間」がくり返し、非常に効果的に使われています。
助川 「ありふれた日常の一部が、異空間に接続している」というイメージは、子どものころから人間が抱きつづける「物語への憧憬」の原点です。そういうものにしっかりつながっているところが、宮本輝の強さだと思います。
宮本はつらい時に押し入れに引き込もって本を読んでいたようです。「閉ざされた空間」と「小説」の力によって、つらい日常から離脱する。宮本輝の文学全体を象徴するようなエピソードです。たしか、『流転の海』シリーズにもそういった場面がありました。
ニヒリズムと詩情
重里 押し入れで読んだ本のなかでも、井上靖の『しろばんば』に、宮本輝はとりわけ感銘をうけたようです。宮本は大人になってからも、井上を大切に思っています。
井上靖というのも、魅力的な作家ですね。若いころはそうでもなかったのに、近年になって井上の貴重さや大切さがひしひしとわかるようになってきました。面白い小説が多いのです。この面白さの正体は何なのか。それをこのところ、ずっと考えています。一般的には、井上靖の魅力の中心は「ポエジー(詩性)」だといわれるのですが、どうもそれだけではないのではないか、というのが私の仮説です。もし、ポエジーだけなら、私がこんなに惹かれるわけがない(笑)。
助川 井上靖は、初めは詩を書いていて、のちに小説に転向しました。「ポエジー」だけを表現したいのなら、ずっと詩をやっていればよかったはずです。詩では描けないものにもこだわりがあったから、小説に手を染めたのでしょう。
重里 私はそれを、「ニヒリズムや無意味と紙一重のところにある、人間の営みへの深い関心」ではないかと考えています。井上の研究者はこのあたりのことをどう考えているのでしょうか。ここが井上文学の急所ではないかと思っています。そして、そうした関心は、井上から宮本輝にも引き継がれているのではないでしょうか。
井上靖の系譜を継ぐ作家として、もう一人、辻邦生を挙げたいと思います。辻は井上から「ポエジー」を引き継いだのではないでしょうか。
助川 西行だとかボッティチェルリだとか、辻はしばしば、芸術家を主人公に小説を書きます。辻が書きたいのは、ある美しいイメージというか、美がこの世に立ちあがる様子であって、それを提示するための枠組として物語がある、というのが私の印象です。
重里 宮本輝は、そういう詩的なものよりも、もっと物語のひだに表れる、世俗とぎりぎりの、もう一つのポエジーに惹かれているのではないか。いわば、詩情をはぎ取ったところに現れる詩ですね。
三人の物語作家
助川 宮本輝と辻邦生をたすと、井上靖になるのかもしれません。
重里 なるほど。井上靖の魅力が宮本と辻に分かれたと考えるとわかりやすいですね。三人の物語作家のありようは眺めても、内実を考えても楽しいです。三人が長い年月にわたって、多くの読者を得ているのは、貴重なことを示唆しているように思います。
助川 井上靖がつむぐことばは、淡いというか、平明です。レトリックの力でうならせるようとする文章の対極で、村上春樹流にいえば「物語の乗り物」として最適化されているというか。
同じことが宮本輝の文体についてもいえます。ある編集者から聞いた話ですが、「女のぬばたまの黒髪がうんぬんかんぬん」とかいっていないで、ビシッと「私はその女と寝た」と書くのがプロだ、というのが、宮本輝の持論だそうです。
重里 ただ、宮本は純文学をエンターテイメント小説と区別するものは文章だと考えているでしょう。
助川 平明で、「物語の乗り物」として過不足なく、それでいて品格をうしなわない――そういう文章を書くことに、宮本輝は細心の注意をはらっているのだと思います。仰々しいレトリックにたよって、物語全体の見とおしが悪くなっているような作品は、「悪しき通俗」と考えているのでしょう。
重里 辻邦生がどうしてポエジーにこだわるのかといえば、それによってニヒリズムに対抗しているからです。辻の魅力は生を全面的に肯定する意思にあります。しかし、それを裏返すといかに深いニヒリズムに浸食されながら物語を紡いだか、ということにもなるでしょう。
井上靖がつむぐ物語の面白さというものも、彼の根底にニヒリズムがあるからです。ニヒリズムや無常観が、手垢にまみれた「詩情」を破砕し、そのうえで、どんな光景が見えてくるのかを探っている。
助川 たしかに、芥川賞受賞作の『闘牛』なんかには、おっしゃることがあてはまりますね。人間の、決してうるわしいといえない側面を、裁くことなくそのまま描く。倫理のようなものを信じていないから、それが可能になったということでしょうか。
重里 逆説的にほんとうの倫理とは何かと問いかけているともいえる。『蒼き狼』にもそれを感じます。この作品を大岡昇平が批判しましたが、今から振り返ると、大岡はニヒリズムに過剰に反応したのではないか。私は大岡の批評にあまり魅力を感じません。
井上靖も遅く文壇デビューした作家ですね。
助川 サラリーマンを長く経験しています。学者や教師というのは、「あるべき道理」が現実化すると本気で思っているところがあるんです。自分の属する組織とか、身のまわりの他者とかが、理想どおりに動くものだと期待している。ひとたび学校の外に出ると、もちろんそれでは生きのびていけません。私も基本的にずっと教員をやってきたので、他人のことはいえないのですが(笑)
人間は、絵に描いた理想やモラルでは動かない。辻原や井上はそのことを、「学校の内側しか知らない作家」にくらべ、骨身にしみてわかっている。彼らが人間を見る目は、冷たくはないけれど突きはなしているというか、過剰な思いいれも反発もなく、ニュートラルです。
重里 井上靖は新聞記者をしていました。事件現場に駆けて行って取材する新聞記者とは、ニヒリズムを職業にしたようなところもありますね。
ニヒリズムを通過しているからこそ、人間をリアルにとらえ、面白い物語を構築できるのでしょう。人生の知恵やこの世の掟を表現することもできるのでしょう。
助川 今日は平成の時代相にはあまり触れませんでしたが、時代を超える普遍的な面白さというのも文学にとっては重要です。ジェーン・オースティンの小説は、ナポレオン戦争の時代に書かれたのに、まったくその話は出て来ない。そして、時流にとらわれなかったからこそ、オースティンは小説の普遍的な魅力を表現できたといわれます。時代を如実に映しだすのも文学の一方の魅力ではありますが、それをすべての作品に求める必要はないのでしょう。
重里 文学は普遍的なものを描こうとして、おのずから時代を表現する。時代を表現しようとして、普遍に達する。むしろ、そんなメカニズムがあるように思います。