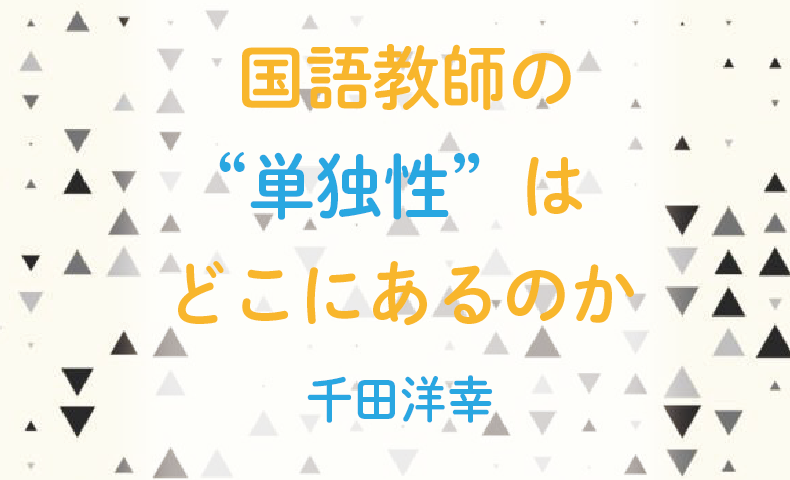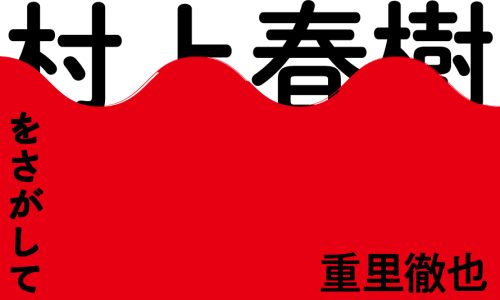予備校や塾の講師、高校での非常勤講師などもふくめると、教師という立場に自分をおいてからすでに40年以上が経過しているが、いまだに「先生」と呼ばれることにかすかな違和感がぬぐえない――などと口にしたら笑われてしまうだろうか。高校での講師時代、「いつまでたってもちっとも先生らしくならないね~」と生徒達にからかわれた日から、定年まであと2年あまりとなった現在にいたるまで、教師「である」とはどういうことかについて明瞭な解答を見いだしえているわけではない。だが一方で、こういう懐疑から逃れていないことそれ自体、教師という職業について考えるための重要な問題ではないかという気もする。そして、自分はなにゆえに教師たりえているのか、という素朴な問いをかならずしも放棄する必要はないようにも思う。
表題はいうまでもなく、丸山真男の著名な教材「「である」ことと「する」こと」から借りているが、教師「である」ことと教師「する」ことがなにを意味するのか、じつは教育基本法第九条にはっきりと書き込まれていることはご存じだろうか。
1.法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2.前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
丸山真男にならってこの条文を敷衍するなら、教師は「である」ことに安住しないため、研究と修養に励み、職責を遂行「する」ことにより、みずからが尊重されるべき身分「である」ことをたえず作り出さなければならない、ということになるのだろう。もちろん、こんなことを四六時中脳裡にとどめて日々の業務をこなす教師は存在しないだろうが、すくなくとも法の水準においては、教師という存在/教師としての行為を形づくる理念は明瞭なのだ。
だが、教師「である」ことと、教師「する」ことの関係はそれほど単純ではない。日本の教育の理念を最上位の審級において示す法律とはいえ、「崇高な使命を深く自覚し……」などという権威的かつ大時代的なワードに白々しさを感じ、敬遠するか苦笑するか無視するかする教師は多いことだろう。すなわち教師にとって、教師「である」ことと教師「する」ことのあいだには、根源的なずれが存在し「うる」のではないか。
私たちは法の権力によって教師「である」ことを保障されており、自身の内にストックしている知識それ自体も教師としての権威と権力を構成している。だが国語教師であれば、「研究と修養」の過程でさまざまな人文知を吸収することにより、日々行使している指導のあり方に迷いや葛藤をいだくのが当然ではないか。学校が秩序を強いる場であるのは自明のこととはいえ、それなりの水準の知識を内面化した教師であれば、児童と生徒を囲い込む規律・訓練の行使を「権力の謙虚でエレガントな使用」(注1)になるべく近づけたい素朴な願望をもちあわせているはずだ(それがなかなか上手くいかず、警察的な権力をふるってしまうこともままあるわけだが……)。
このような問題について考察しようとする際にすぐ想起されるのは、お馴染みともいえるジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル』(注2)のパフォーマティヴ理論である。
たとえばジェンダーを、身体的形式と考えてみたらどうだろう。つまり「パフォーマティヴ」という言葉が、意味の演劇的で偶発的な構築を示唆するのであれば、ジェンダーを恣意的で、かつパフォーマティヴな「行為」と考えてみたらどうだろう。
<もしもジェンダー・アイデンティティの基盤が、時をつうじて繰り返される様式的な反復行為であり、継ぎ目がないアイデンティティでないならば、「基盤」という空間的なメタファーは、じつはそれが様式的な配置――実際には、その時代のジェンダーの身体化――にすぎないものであることが明らかにされ、放遂される必要があるだろう。したがってジェンダー化された永続的な自己とは、アイデンティティの実体的な基盤の理想に近づくように、反復行為によって構造化されたものであることが判明するが、他方でその反復行為は、ときおり起こる不整合のために、この「基盤」が暫定的で偶発的な〈基盤ナシ〉であることも明らかにするのである。ジェンダー変容の可能性が見いだされるのは、まさにこのような行為のあいだの任意の関係のなかであり、反復が失敗する可能性のなかであり、奇―形のなかであり、永続的なアイデンティティという幻の効果がじつはひそかになされる政治的構築にすぎないことをあばくパロディ的な反復のなかなのである。
バトラーのパフォーマティヴ理論が、ジャック・デリダとジョン・R・サールの言語行為をめぐる論争(この論争自体はJ. L. オースティンとE. バンヴェニストを踏まえている)を読み換えることによって成立しているのは周知のことである(注3)。やや入り組んだバトラーの言説を解きほぐすため、ここでは森山至貴の明晰なパラフレーズ(注4)を借りることにしよう。
デリダは、オースティンがコンスタティヴという表現を用いる時に想定している、辞書的な意味というものに疑問を投げかけます。語や句は繰り返し使用され、かつその使用は一度として同じ文脈を持ちません。私たちは何度でも「猫」という言葉を使えますが、その文脈はいつも違います。さっきはミケ、今度はタマというように、指している「猫」が違うだけではありません。いつどこで誰に向かって発するか、呼びかけなのか質問なのか独り言なのか、それらの要素が全て一致することは絶対にないのです。一度使用されたきり二度と使用されない「使い捨て」の語や句を想定しても、それはどんな状況でも習得できないので(さっき使ったその語句を繰り返し用いて意味を尋ねることすらできないのです、なにせ一度しか使えないのですから)、そもそも無意味です。であるならば、語や句は、その意味が異なる文脈に流用されてしまう、つまり安定した辞書的な意味が綻びることによってむしろ成立可能となっているのです。
言語が、辞書的な意味の綻びによって成立可能となるのならば、言語の根本的な特徴はむしろ、辞書的な意味を越えてしまう、そのパフォーマティヴな側面ということになります。想定ないし意図されている意味にとどまらないような意味を伝達してしまうことこそ、言語が言語として成立しているということの証拠だからです。(中略)繰り返されることで通常の用法を外れたものが伝達されてしまうという言語のパフォーマティヴな特徴は、ジェンダーにも当てはめられるとバトラーは考えました。バトラーは、言語のコンスタティヴな意味とされるものは、絶えずずれを生みつつ反復される、すなわちパフォーマティヴに産出される言語使用の最大公約数的特徴にすぎない、と考えます。しかし、この「意味」はあたかも実際の言語使用の前から存在している、すなわち辞書に先に書かれてあったかのように見えるのです。バトラーは、「男らしさ」「女らしさ」もまた、まさにそのような、あらかじめ決まっていたかのように見えるものにすぎないと考えました。
『ジェンダー・トラブル』はジェンダー・アイデンティティ/パフォーマティヴィティをめぐる思想書であり、教育研究とはむろん直接の関連はないが、上記引用部分における「ジェンダー」の語を「教師」に置き換えてみれば、教師のパフォーマティヴな主体性――ここではエージェンシーと呼ぶべきだろう――が浮かびあがってくるだろう。教師は、「教師らしい身体」を模倣・反覆することによって、みずからのアイデンティティを構築しようとする。だが、それはしばしば「失敗」や「不整合」を招き寄せ、自身が「永続的な」教師主体であろうとすることを裏切る。バトラーの理論を導入することによって顕在化するのは、教師「である」ことが、教師「する」ことによって「守られる」(丸山真男)どころか、逆にその政治的・社会的構築性を露わにされ、「基盤」を揺るがせてしまう事態である。
そして、私たちの記憶のなかに住まっている魅力的な教師たちは、みずからの立場をずらしたり異化したりするパフォーマンスをしばしば演じることによって、教師「である」ことに「失敗」することを愉しんでいた人々ではなかったか。授業の本筋とはかかわりのない雑談にひたすら興じたり、授業の出来よりも冗談の受けの方に一喜一憂したり、自分の関心のふかい分野のみやたらと雄弁に語り出したりする困った先生たち。一見あまり役に立たない情報や身ぶりを過剰に授業内にもちこんでしまう教師の姿を、かつて児童・生徒の立場にあった多くの人が印象に刻みつけているだろう。ユニークな教師は、教師「である」ことそのものを無意識的に脱構築する作法を心得ているのではないだろうか(注5)。
雑談や冗談というのはやや卑近な例ではあるが、教師が意図せず表出するノイズや逸脱行為が学習者の注意や集中を喚起する役割をもつことは経験上誰でも知っている。それは授業に間(ま)をもたらすアイスブレイク的な役割を果たしたり、教師と学習者との関係をフラットにし、教室の空気を緊張や倦怠から解き放ったり、時には授業本来の目的を超えて学習者にインパクトをあたえたりする。と同時に、目的的でない語りの言葉は、授業の文脈に異化あるいは侵犯として作用することによって、教師としての立場それ自体を相対化する。目の前の教師が、授業中に突然非―教師として立ちあらわれる意外性と面白さを、これまた誰もが記憶していることだろう。(ちなみに私は、授業における逸脱行為(雑談や冗談等をふくむ)の有効性についての本格的な研究がなされるべきだと真面目に考えている。国語科ではいまのところこのテーマを追求している人はいないようだが……。)
教員養成大学にながく勤めていると、時として、生まれ落ちたときからの教師のように振る舞う人――すなわち教師「である」ことと教師「する」ことが隙なく密着している人――に出会う。そういう人は、教師「である」ことに「失敗可能性」が内在するなどとは露ほども考えていないか、あるいは学校においてパフォーマティヴな自己が露出することをひたすら抑圧しているのだろう。この連載でさんざん批判してきた――というより侮蔑してきた――学習指導要領を忠実に遂行することを使命と考えている教師(教科教育の内情にあまり通じていない方は、「そんな教師本当にいるの?」と思うかもしれないが、恐ろしいことに実在するのである)はほとんどこういうタイプだが、それで教師人生は楽しいのか? と他人事ながら心配になってしまう。
バトラーは、ジェンダー―言語行為のパフォーマティヴィティを理論化する過程において、秩序を攪乱する存在としてのエージェンシー=行為体の理念を編み出した(注6)。教育の主体があらかじめ確固として存在すると考え、それを「正しく」反復することが職務であると考える教師は、所詮、既成の秩序の強化に荷担することしかできない。教師として在ることの偶然性、教えるという行為を反復することの「失敗可能性」、授業を構成する雑多な言語行為の一回性と逸脱性――そういう教育のパフォーマティヴィティに価値を見いだしうる教師こそが、教科教育の規範を書き換え、更新する行為者でありうる。自己の研究領域を特権化することは慎むべきだとはいえ、やはり人文知に接近した場所で仕事をしている国語教師は、エージェンシーたりうる可能性をもっとも豊かに内在させているといえるのではないだろうか。
(注1)稲葉振一郎「ニッポン言論のタネ本15冊+α フーコー『監獄の誕生』」(『論座』2002.6)。
(注2)ジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル――フェミニズムとアイデンティティの攪乱』(竹村和子訳 1999 青土社)。
(注3)ジャック・デリダ「署名 出来事 コンテクスト」より関連する部分を引用しておく。「言語的であれ非言語的であれ、話されたにせよ書かれたにせよ(この対立は通常の意味において言うのだが)、またユニットの大小にかかわらず、いかなる記号も、引用されうるし引用符で括られうる。まさにそのことによって、すべの記号は、所与のいかなるコンテクストとも手を切り、絶対的に飽和不可能な仕方で、無限に新たなコンテクストを発生させることができる。このことが前提としているのは、マークがコンテクストの外でも有効だということではなく、逆にいかなる絶対的な投錨中心もない諸々のコンテクストしかないということなのである」(引用は高橋哲哉・増田一夫・宮﨑裕助訳『有限責任会社』2002 法政大学出版局 による)。
ちなみに授業という行為について厳密に研究しようとするなら、言語のパフォーマティヴについて考えておくことは必須である。言語行為の一回性を当然の前提とするなら、授業の「再現可能性」という概念などは吹き飛んでしまうからだ。
(注4)森山至貴『LGBTを読みとく――クィア・スタディーズ入門』 (2017 ちくま新書)。
(注5)矢野利裕『学校するからだ』(2022 晶文社)の3章「教員」には、そうしたユニークな教師たちの姿が活写されている。
(注6)OECDがEducation2030プロジェクトで「エージェンシー」の概念を提案して以来、この語が教育界でしばしば用いられるようになってきた。「エージェンシー」とは、OECDによって「変化を起こすために,自分で目標を設定し,振り返り,責任をもって行動する能力」と定義されており、「結果を予測すること(目標を設定すること)」「みずからの目標達成に向けて計画すること」「自分が使える能力や機会を評価・振り返ること,自分をモニタリングすること」といった能力の集合であるという(白井俊『OECD Education2030プロジェクトが描く教育の未来――エージェンシー,資質・能力とカリキュラム――』2020 ミネルヴァ書房)。万一の誤解がないよう念のためにつけ加えておくが、この「エージェンシー」は、個々の成員=生徒の自己管理と生産性をいかに高めるか、という発想にもとづく概念であり(OECDの提案であるから必然的にそうなる)、フーコーのいう規律・訓練権力並びに生権力の典型的産物である。バトラーが示したエージェンシーの理念とはまったく無縁であり、むしろ対極にあることはいうまでもない。