2025年3月刊行
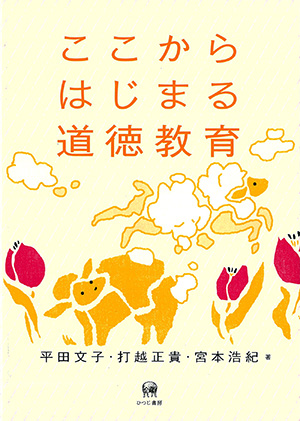
ここからはじまる道徳教育
平田文子・打越正貴・宮本浩紀著
定価2,900円+税 A5判並製カバー装 364頁
ISBN978-4-8234-1288-2
装丁者 三好誠(ジャンボスペシャル)
The First Steps in Moral Education
Hirata Fumiko, Uchikoshi Masaki, and Miyamoto Hiroki
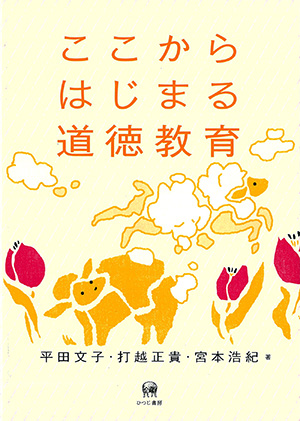 |
ここからはじまる道徳教育平田文子・打越正貴・宮本浩紀著 定価2,900円+税 A5判並製カバー装 364頁 ISBN978-4-8234-1288-2 装丁者 三好誠(ジャンボスペシャル) The First Steps in Moral Education
|


