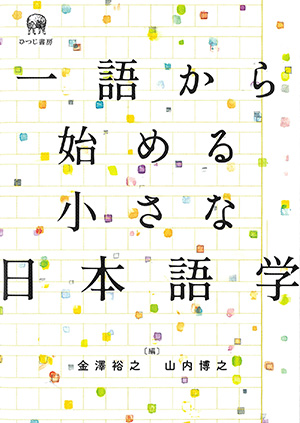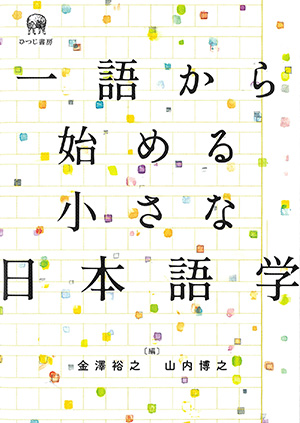はじめに
「小さな政府(limited government)」という考え方がある。「小さな政府」とは、「大きな政府(big government)」の対概念であり、経済活動への政府の介入をできるだけ小さくすることによって、経済活動を活性化するという考え方である。
1929年の世界的な大恐慌以降、「政府は市場に積極的に介入すべきである」という考え方が主流となり、政府は積極的に経済活動に介入してきた。しかし、1970年代になり、経済活動への介入が重荷となって慢性的な財政赤字を抱えたり、政府の介入が効率的な資源配分をかえって妨げることになったりという弊害が生じるようになった。
そこで登場したのが「小さな政府」、つまり、政府の役割をできるだけ小さくしようという考え方である。大恐慌への対応策としては、「大きな政府」は効果的だったのだが、時が経つにつれ、「大きな政府」は身動きがとれなくなってしまったのである。
日本語学研究においても、この「大きな政府」のように、文法研究の役割があまりにも大きくなりすぎてはいないだろうか。そして、そのために、活発な日本語学研究が妨げられてしまってはいないだろうか。
この30年ほどの間に文法研究が大きく進展し、その大まかな骨格がだいたいできあがった。そのため、今から文法研究に参入しようとしても、概ね組み上がった体系に挑んでいかなければならない。それを組み替えることも、また、入り込む隙間を探すことも、研究の初心者にとってはとても難しいことである。
では、語彙研究はどうかと言えば、語彙研究もそう簡単ではない。語彙とは「語の集まり」のことなので、語彙研究を行なうためには、計量的な手法を避けては通りにくい。計量的な手法は、文系研究者にとっては、なかなか敷居の高いものである。また、この30年ほどに限って言えば、文法研究に比して研究論文の数が少なく、ロールモデルとなり得るような研究も多くはない。語彙研究という山に関しては、もっといろいろな登山ルートが示されて然るべきである。
本書の提案は、いわゆる文法研究や語彙研究ではなく、1つの実質語に着目して、「小さな日本語学」の研究を行なってはどうか、ということである。1つの実質語を扱うのみだと、学会発表や学会誌掲載に値する研究にはなりにくい。しかし、1つの実質語を対象とした研究を続けていくうちに、その研究が思いがけず広がりを見せ、学会発表ができたり、学会誌に掲載されたりということもあるだろう。
これまでに積み上げられてきた文法研究の隙間を探せと言われても、なかなか難しいが、一語の研究を続けていくうちに、たまたまそれが見つかるかもしれない。また、語彙研究という山を登るためのきっかけや新たな手法が、たまたま見つかるかもしれない。内野ゴロでの凡退が5打席続いたとしても、6打席目に、打球がショートの頭をぎりぎり越えればいいのではないか、という考え方である。たまたま出たヒットでもかまわない。そのうち、ヒットを打つコツがつかめてくるだろう。それに、ショートの頭をぎりぎり越えたヒットが、試合の中ではホームランと同等の価値を持つこともあるのではないだろうか。
1つの実質語から始める研究を、本書では「小さな日本語学」の1つであると考えるが、「小さな日本語学」研究を行なうメリットは、主に次の5点である。
1 日本語学者を志す人が「文法研究」や「語彙研究」という舞台で勝負するためのきっかけがつかめる。また、いい練習にもなる。
2 日本語学や日本語教育の卒業論文を書くのに最適である。
3 大学の初年次教育や日本語学に興味を待たせるための授業で使用でき、効果が期待できる。(日本語学のファンを増やせる。)
4 日本語教育に役立つ。(日常のコミュニケーションでは機能語より実質語の方が重要だが、これまで実質語を研究する研究者がほとんどいなかった。)
5 日本語学研究の新しい領域を開拓できるかもしれない。
本書には、17名の執筆者による17本の論文が掲載されている。1つの論文の長さは、いわゆる「研究論文」より少し短いので、「研究ノート」と呼ぶ方がふさわしいかもしれない。17名の執筆者に対しては、本書の論文執筆に際し、以下のような依頼をした。
◆ある「一語」に着目し「自分らしさを出した研究ノート」を書く。その「一語」に対して抱く違和感や「気になる」「面白い」という気持ちから研究をスタートさせ、結論も、その「一語」に収束させる。また、その「一語」は、機能語ではなく、実質語であると望ましい。多くの人に「ことばの楽しさ」を実感してもらえるような研究ノートを書いていただきたい。
◆ネタ・素材を大切にした研究を行なっていただきたい。発想・着想はとても重要である。論証は最小限でよい。
◆コーパスやアンケート調査など、データとして依拠できるものをもって研究を進めていただきたい。
本書に掲載した17本の論文タイトルは以下のとおりである。いずれのタイトルにも、研究対象となる一語が含まれている。そして、「当該の語との出会いの場」もしくは「発想の源」というような観点から全体を5部に分け、それらの中に17本の論文を収めた。
第1部日常のやりとりから
・「わーい」っていつ使う?
・もう3杯でもひょっひょっひょって感じ。・私、現国すごい苦手で、それこそセンター試験の小説のセクションと
か
第2部 学生とのやりとりから
・教授のおっしゃるとおりです。
・大学生って生徒なの?
・夏休みにアルバイトを始める子が増加する。
第3部 日本語学習者とのやりとりから
・母は親切です。
・どうぞよろしく。
・愛ってやっぱ難しいじゃないですか
・あんばい、どうですか?
第4部 趣味の中から
・さっくり混ぜる
・「ヘイトを稼ぐ」から「ヘイトを買う」へ
・「どんな週末でしたか?」「ええと、いろいろです……」
第5部 副産物いろいろ
・きっかり10時
・「考えを深めましょう!」「え、どうやって…?」
・まさにジャスト
・選手たちのたゆま( )努力
これらを見ると、執筆者たちが日々の生活や学生とのコミュニケーションの中の何気ない「一語」から、研究の着想を得ていることがわかる。また、料理やゲームなどといった自らの趣味の中から見つけた「一語」もあるし、さらに、元々の専門領域の研究を行なっている中から副産物的に出会った「一語」がきっかけとなって始まった研究もある。
いずれの論文も「一語」に始まり「一語」に終わる「小さな」ものなのであるが、読んでみると、何らかの発見があることがわかる。いわゆる「大きな日本語学」では見いだせなかったであろう文法現象もあるし、また、文法書に記述されるべき内容と国語辞典に記述されるべき内容の中間にあるような現象が存在していることもわかる。小さなことに着目し、その小さなことをいろいろな角度から眺めていると、ある時、それが突然広がることがある。研究とは、本来そのようなものなのではないだろうか。
最後に、この本の共編者である金澤裕之氏に関して一言触れる。本書は、氏の『留学生の日本語は、未来の日本語日本語の変化のダイナミズム』(ひつじ書房、2008)の考え方をダイレクトに受け継ぐものである。ネタ・素材に触れた時の発想・着想がとても重要で、一方、論証は最小限でよい。それが「小さな日本語学」の生命線であり、この「小さな日本語学」によって、日本語学全体に大きな活力がうまれないものかと考えている。
2022年1月26日
山内博之