
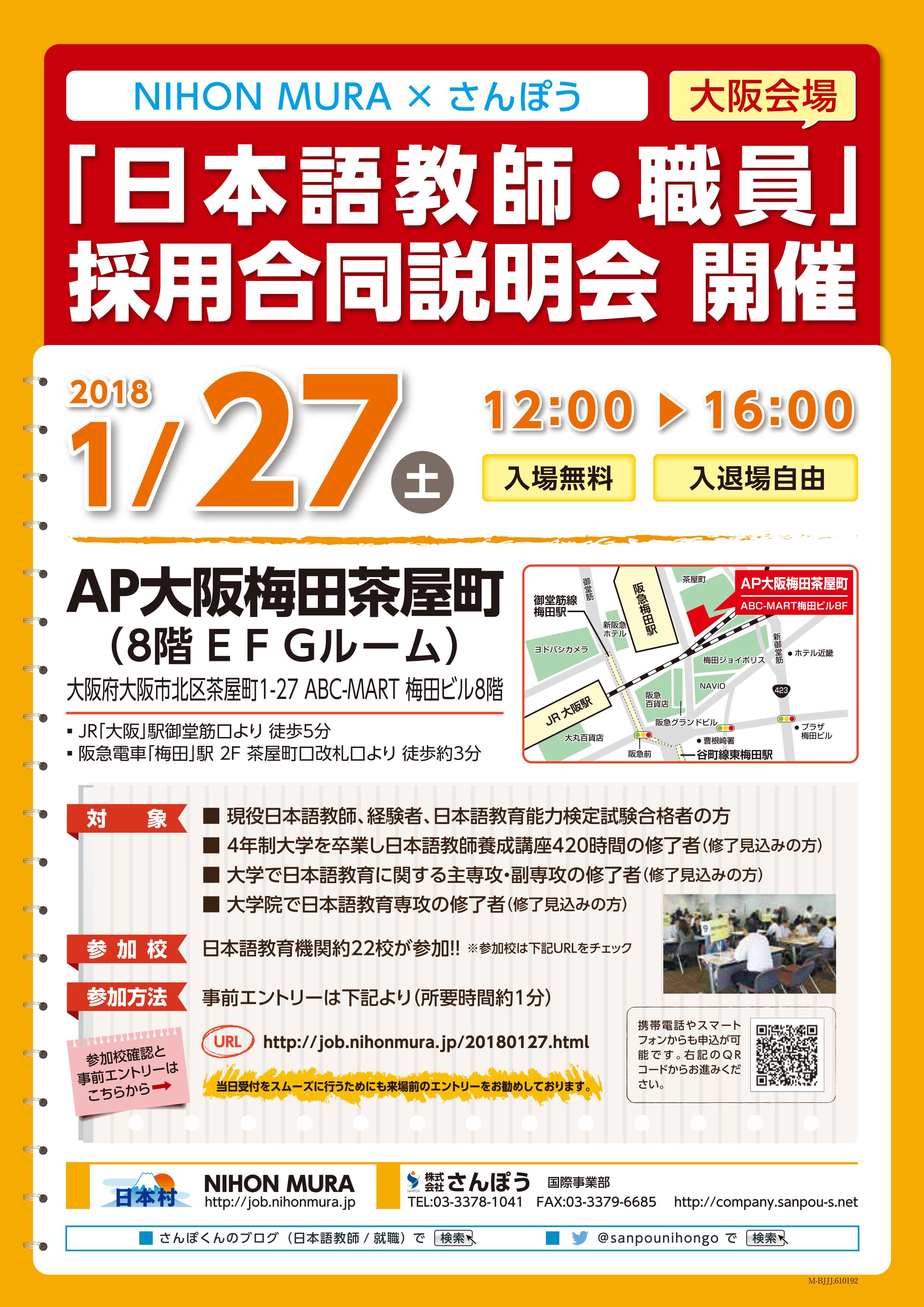
ひつじ書房は、社員を募集中です。詳細は以下をご覧ください。
2017年春卒と既卒の方、2018年春卒予定の方へ 正社員の募集・求人・採用(編集+出版業務)ページ

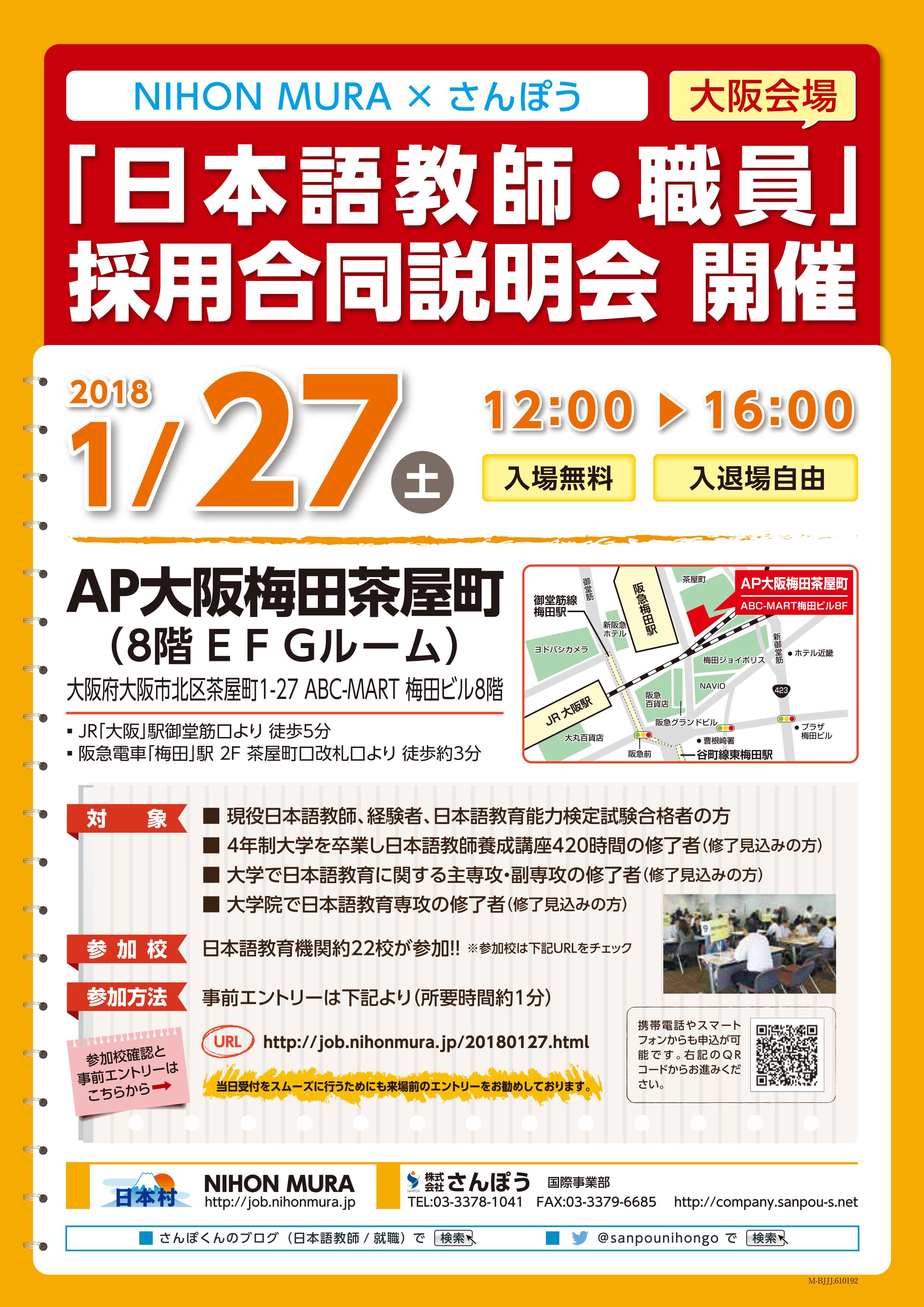
株式会社さんぽうより、イベントのご紹介です。
日本語教師・職員を目指す方のために採用説明会を大阪と東京で開催するとのことです。詳細は以下のURLをご覧ください。
■NIHON MURA × さんぽう「日本語教師・職員」採用合同説明会
[東京会場] 2018年1月20日(土)12:00〜16:00
http://job.nihonmura.jp/20180120.html
[大阪会場] 2018年1月27日(土)12:00〜16:00
http://job.nihonmura.jp/20180127.html
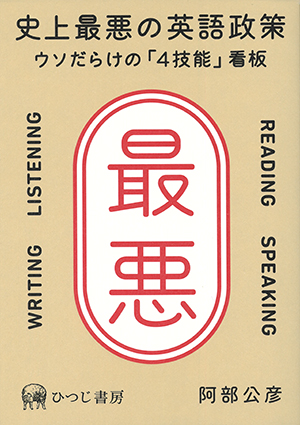
「大学入試の英語が4技能!」とのニュースがメディアに流れた。しかし、多くの人は「え、4技能?」「どこがあたらしいの?」と思ったことだろう。それもそのはずで、この「4技能」看板は実態のないブラックホールのようなものである。しかし、このニセ看板を大義名分にして、大学入試は大きな変更を強いられようとしており、多くの人が確実にその影響を受ける。本書は迷走する日本の教育行政を検証し、教育の暗黒時代から身を守るための方法を模索する。
阿部公彦著『史上最悪の英語政策—ウソだらけの「4技能」看板』詳細
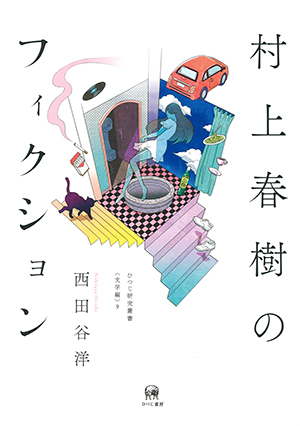
小説にとどまらず、エッセイ、ルポルタージュ、評論等多彩なジャンルにおいて様々な活躍を見せる現代日本文学を代表する作家・村上春樹のフィクションの様相を、短編小説を中心としつつ、それ以外のジャンルのテクストにも目配りしながら、物語論とイデオロギー批評を始めとする諸理論にもとづき、〈修辞的構成〉〈物語と主体性〉〈物語性と視覚性〉〈倫理とイデオロギー〉の四つの部立てで論じる新たな村上春樹研究。
西田谷洋著『村上春樹のフィクション』詳細

近年、書きことばに基づく文法記述では説明できない「話しことば」の諸現象に注目が集まっている。本書は、話しことばの言語学を概説する第1部と、その応用編として同じ談話データをアプローチの異なる話しことば研究者が分析するとどのような考察が得られるかという野心的な試みに挑戦した第2部で構成されている。各章に重要キーワードの解説付き。
執筆者:岩崎勝一、遠藤智子、大野剛、岡本多香子、片岡邦好、兼安路子、鈴木亮子、中山俊秀、秦かおり、東泉裕子、横森大輔
鈴木亮子・秦かおり・横森大輔編『話しことばへのアプローチ』詳細

日本語研究と語用論研究が通い合う広場(フォーラム)となることを目指して編まれたシリーズの第2巻。語用論の研究は、多様な領域と接触しながら、新たな研究テーマとその成果が生み出されていくとき、最も活性化した姿を見せるだろう。本書は、各領域の第一線で活躍する研究者や新進気鋭の研究者の最も新しい論考を捉えた、熱い論文集である。
執筆者:加藤重広、小松原哲太、椎名美智、柴?礼士郎、時本真吾、野田春美、藤本真理子、吉川正人
加藤重広・滝浦真人編『日本語語用論フォーラム 2』詳細
『月刊 国語教育研究』2017年12月号(No.548)「新刊紹介」掲載
・渡辺哲司・島田康行著『ライティングの高大接続』評者:安部朋世
『日本語音声コミュニケーション 5』を公開しています。
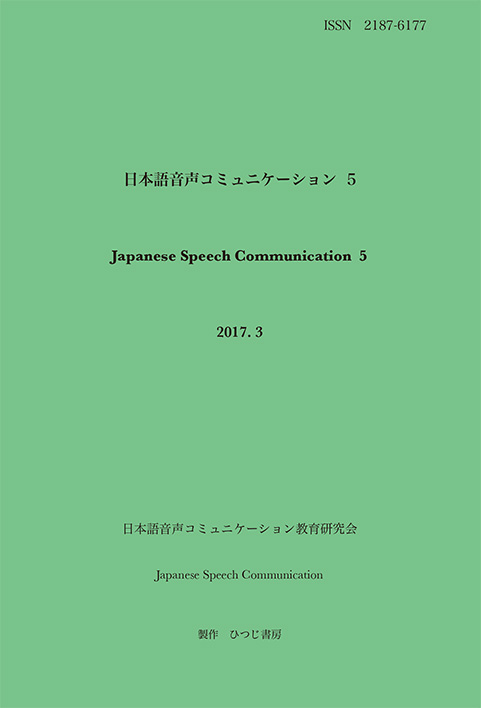
『日本語音声コミュニケーション』は、オンラインジャーナルです。音声や動画を含む、インタクティブPDFで公開しています。
以下からご覧ください。
『日本語音声コミュニケーション』
『日本語音声コミュニケーション 5』
・『リポート笠間』No.63(2017.11)「面白かった、この三つ」の記事内で紹介
渡辺哲司・島田康行著『ライティングの高大接続』評者:根来麻子
・『日本教育新聞』2017念12月4日(月) 第6126号
渡辺哲司・島田康行著『ライティングの高大接続』評者:都筑学
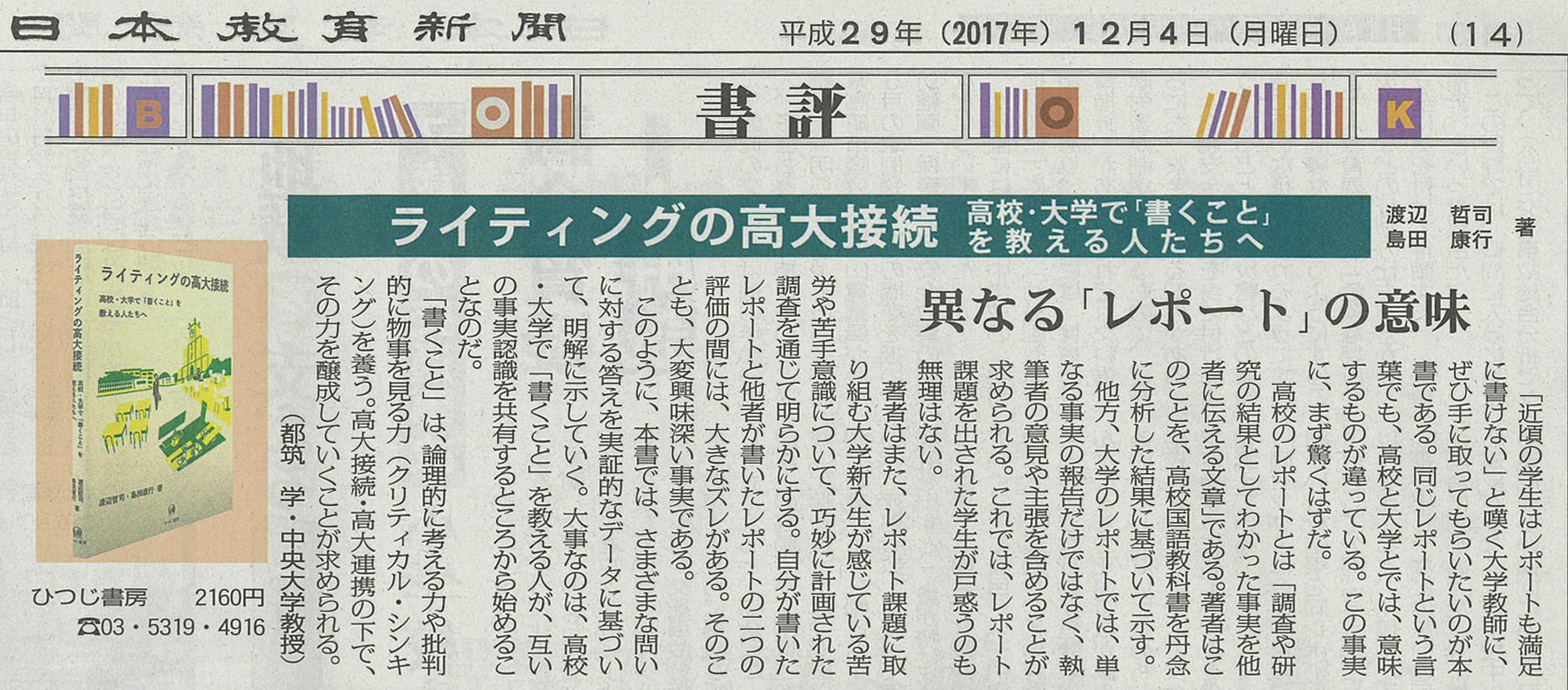
(本記事の著作権は日本教育新聞社に帰属します。無断転載を禁じます)
『社会新報』2017年12月6日(水) 第4961号
長沼豊著『部活動の不思議を語り合おう』
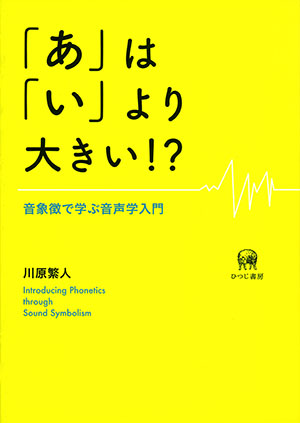
「ワマナ」さんと「サタカ」さんは、どちらが優しく、どちらが気が強くサバサバしているだろうか? 聞いたことの無い名前からでもその印象を感じることができる、この現象は「音象徴」と呼ばれ、ことばの音と意味の関係を考える上でいま注目を集めている。本書では、「メイド喫茶のメイドさん」「ポケモン」「ピコ太郎」など音象徴の身近な題材を例にしながら、音の科学である「音声学」という学問へと誘う。これまでにない楽しく分かりやすい音声学入門。
川原繁人著『「あ」は「い」より大きい!? -- 音象徴で学ぶ音声学入門』詳細

本書は学校教育の中で用いられる言語について、選択体系機能言語学を理論的な枠組みとして解説する。学校教育の言語的特徴、言語とコンテクストの関係、学問的なテクストの言語的特徴、文法と作文、科目ごとのテクストの特徴、学校での言語発達が述べられている。学校教育の中で必要な言語能力とその特徴、そしてその教育に言及されており、多くの示唆に富んでいる。語学教育だけでなく、教育全般についても参考となる良書である。
メアリー・シュレッペグレル著 石川彰、佐々木真、奥泉香、小林一貴、中村亜希、水澤祐美子訳『学校教育の言語 機能言語学の視点』詳細

2017年11月17日(金)現在、Amazonでは品切れとなっており、古書のみしかないような表示になっておりますが、Amazon以外のオンライン書店、全国の最寄りの書店様では問題なくお買い求めいただけます。
目から鱗がでる、英語辞書活用秘技が満載です。
関山健治著『英語辞書マイスターへの道』詳細
週刊教育資料No.1454 2017年11月13日号に「自著を語る」掲載
・長沼豊著『部活動の不思議を語り合おう』
『図書新聞』3326号(2017年11月11日)掲載
・西田谷洋編『文学研究から現代日本の批評を考える』評者:米村みゆき
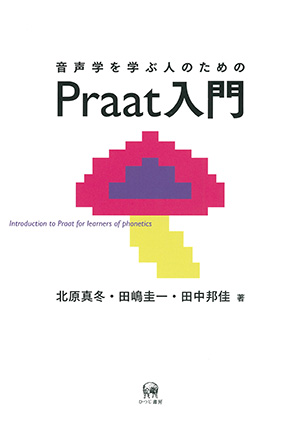
Praatは、音声学的研究に必要な機能を数多く備えた画期的なフリーのソフトウェアである。しかし、そのメニューやヘルプ、解説文書が英語という壁がある。また、反復作業の省力化を目指すと、プログラミングという壁が立ちはだかる。本書は、音声分析を始めようとする人にとって、それらの壁を乗り越える梯子の役割を果たす日本初の解説書である。ぜひ、壁の向こうにある音声学の楽しさと深みを味わってほしい。
北原真冬・田嶋圭一・田中邦佳著『音声学を学ぶ人のためのPraat入門』詳細
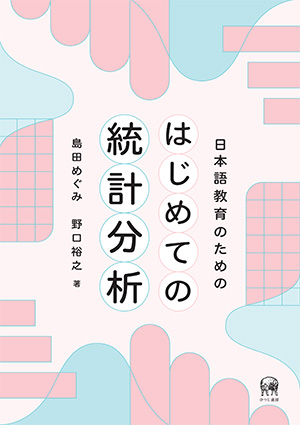
統計的方法は日本語教育に関する重要な知見を得るために必要不可欠な道具の一つである。本書では、日本語教育を専攻する学生や研究者を対象として、統計的方法の基礎的な部分を分かりやすく解説。統計的な記述や推測の方法について、その論理構成の説明のほか、分析ソフト(SPSS)の使い方と、実際の研究に用いられた例を示した。何よりも読者に「考え方」を身に着けてもらえるように配慮した、これからの日本語教育のための一冊。
島田めぐみ・野口裕之著『日本語教育のためのはじめての統計分析』詳細

早津恵美子著『現代日本語の使役文』が平成29年度新村出賞を受賞しました。
早津恵美子先生、おめでとうございます!
新村出記念財団ウェブサイト ◆平成29年度 新村出賞、新村出研究奨励賞の受賞者
『現代日本語の使役文』詳細

新刊・近刊のご案内の冊子『未発ジュニア版』を発送し始めました。近々みなさまのお手元に届く予定です。
『未発ジュニア版』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、ひつじ書房までどうぞご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いいたします。
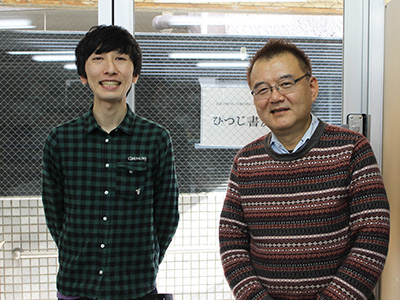
てんしん書房さんは、ひつじ書房のすぐそばにオープンした絵本・児童書専門の書店です。
神戸の児童書専門店「ひつじ書房」さんにて、絵本と出会い育っていらっしゃったという店主の中藤さん。ひつじ繋がりで弊社へもご挨拶にお越しくださいました。ありがとうございます!
こどもの本屋 てんしん書房
〒112-0002
東京都文京区小石川5丁目20-7 1F
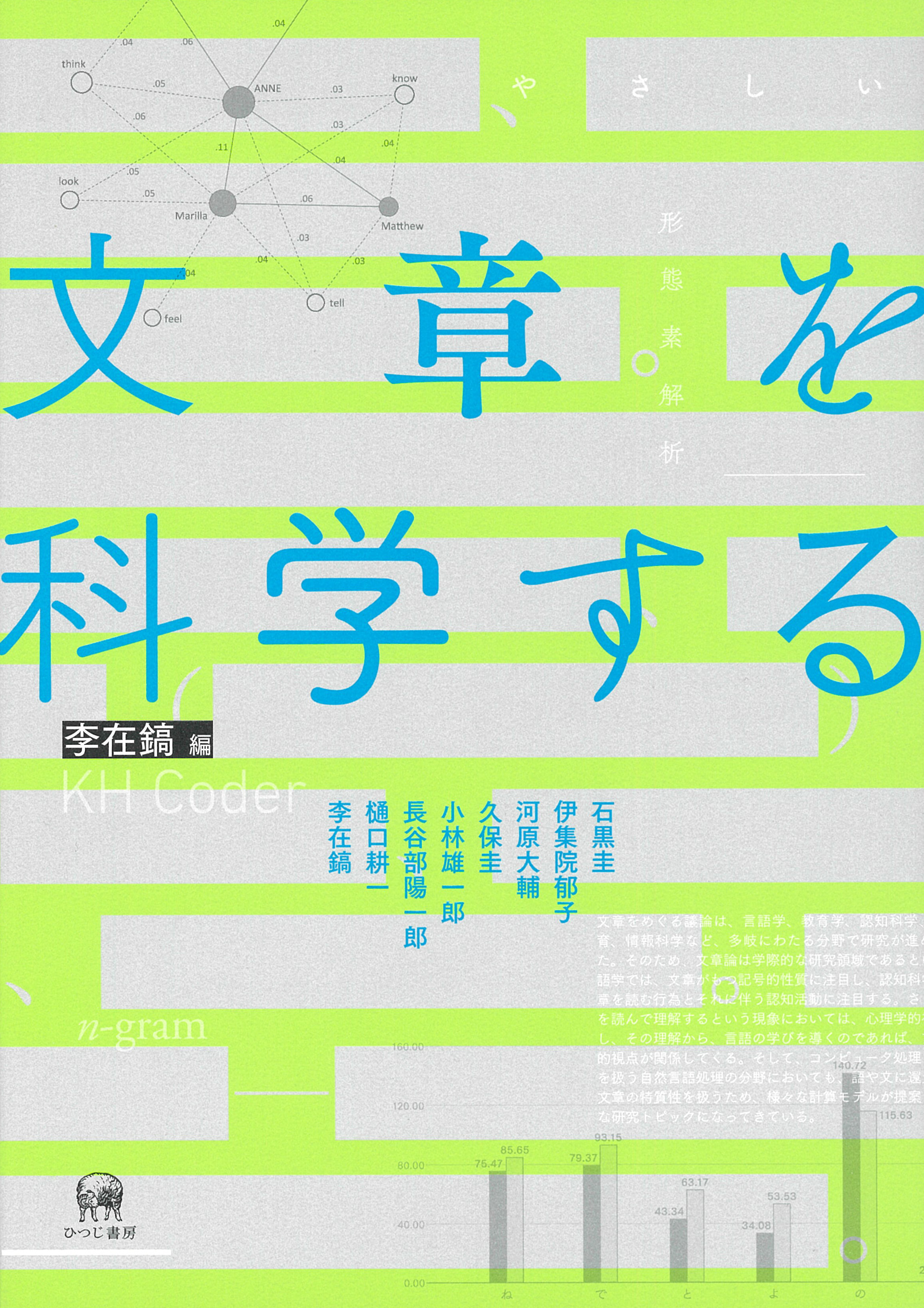
李在鎬編『文章を科学する』を刊行しました。
言語教育への応用を目論んだ文章の実証的研究。「文章とはなにか」という根本的な疑問から始まり、文章の計量的分析ツール「KH Coder」の作成者自身による実践を交えた解説ほか、文章研究の理論と技術を紹介。日本語学、日本語教育、英語教育、社会学、計算言語学、認知言語学、計量国語学の専門家がそれぞれの知見から、文章研究の新たな地平を拓く。
執筆者:李在鎬、石黒圭、伊集院郁子、河原大輔、久保圭、小林雄一郎、長谷部陽一郎、樋口耕一
李在鎬編『文章を科学する』詳細
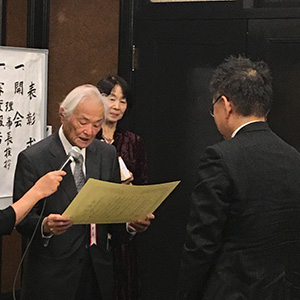
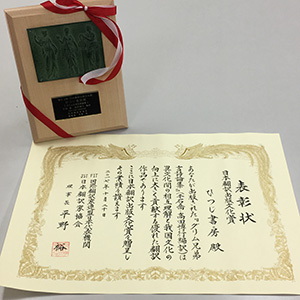
『グリム兄弟言語論集 言葉の泉』(ヤーコプ・グリム、ヴィルヘルム・グリム著 千石喬、高田博行編)が、日本翻訳家協会主催の第53回日本翻訳出版文化賞を受賞し、10月20日(金)に、受賞式が行われました。
日本翻訳出版文化賞は、過去1年で最も優れた翻訳書を刊行した出版社に対し贈られる賞です。

『グリム兄弟言語論集 言葉の泉』
ヤーコプ・グリム、ヴィルヘルム・グリム著 千石喬、高田博行編
ロマン主義の思潮に連なるグリム兄弟の言語思想は、言語を考古学や歴史学への門戸と考え、究極的には人間精神を追求する普遍的・総合的なものであった。全400頁に迫る本書で訳出するのは、ドイツの国民的業績とされる『ドイツ語辞典』の序文、『ドイツ語文法』の序文の他、子音推移、ウムラウトと母音混和、言語浄化主義、言語起源論、語源論、指の名称に関する論考である。(言語起源論を除き)本邦初訳。
訳者:千石喬・木村直司・福本義憲・岩井方男・重藤実・岡本順治・高田博行・荻野蔵平・佐藤恵
『グリム兄弟言語論集』詳細
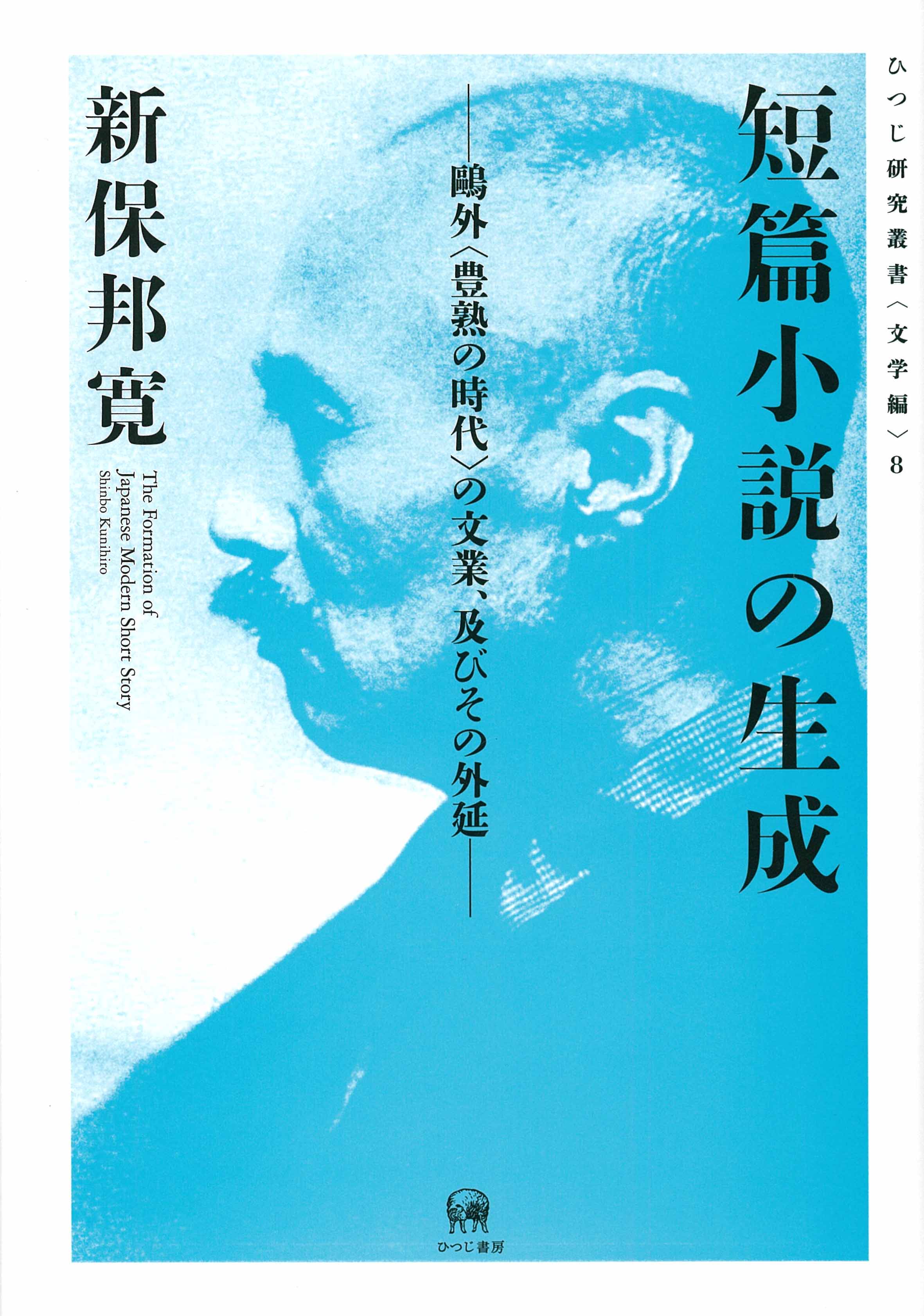
新保邦寛著『短篇小説の生成—?外〈豊熟の時代〉の文業、及びその外延』を刊行しました。
日本近代において、短篇小説がいつ、どのように生成されたのか。これまでの文学研究では短篇と長篇が別ジャンルであるということすら認識されてこなかった。本書では、短篇小説の特質に迫りながら、日本近代の短篇小説の内実を形作った森?外がどのように短篇小説を独自の文学ジャンルに押し上げていったのかを、谷崎や芥川など関連する作家とともに論じる。従来の文学史にはない、新たな近代文学の様相を露わにする。
新保邦寛著『短篇小説の生成—?外〈豊熟の時代〉の文業、及びその外延』詳細

堀正広・赤野一郎監修 赤野一郎・堀正広編、英語コーパス研究シリーズ 第7巻『コーパスと多様な関連領域』を刊行しました。
英語コーパス学会20周年を記念した網羅的なコーパス研究シリーズ「英語コーパス研究」第7巻。本巻は、第2巻から第6巻で扱わなかった、生成文法、認知言語学、体系機能文法、法言語学とコーパスとの関係を論じ、コーパス構築のためのテキスト処理、コーパス分析の方法として、統計分析の手法とコンコーダンス分析を概観している。
執筆者:赤野一郎、伊藤紀子、大谷直輝、大名力、小原平、小林雄一郎、堀田秀吾、堀正広、吉村由佳
堀正広・赤野一郎監修 赤野一郎・堀正広編 英語コーパス研究シリーズ 第7巻『コーパスと多様な関連領域』詳細
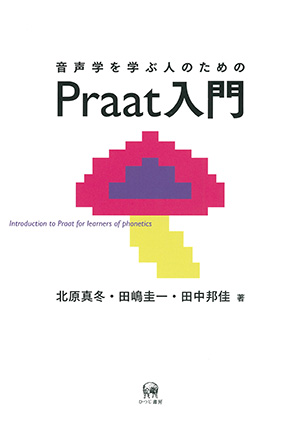
『音声学を学ぶ人のためのPraat入門』(北原真冬・田嶋圭一・田中邦佳著)10月下旬刊行予定です
Praatは、音声学的研究に必要な機能を数多く備えた画期的なフリーのソフトウェアである。しかし、そのメニューやヘルプ、解説文書のほとんどが英語という壁がある。また、反復作業の省力化を目指すと、プログラミングという壁が立ちはだかる。本書は、音声分析を始めようとするひとにとって、それらの壁を乗り越える梯子の役割を果たす日本初の解説書である。ぜひ、壁の向こうにある音声学の楽しさと深みを味わってほしい。
北原真冬・田嶋圭一・田中邦佳著『音声学を学ぶ人のためのPraat入門』詳細

日本方言研究会編『方言の研究 3 特集 ことばのひろがり』を刊行しました。
ことばの地域差に関わる研究動向に注目し、その成果や方法を紹介する。「ことばのひろがり」をテーマとして、単に「言語地理学」にとらわれることなく、新しい視点による言語変化、方言の地域差や世代差などについて多角的観点からのアプローチを展開する。
執筆者:大西拓一郎、熊谷康雄、福嶋秩子、小林隆、三井はるみ、鑓水兼貴、都染直也、李仲民、岩田礼、沖裕子、峪口有香子、椎名渉子、塩川奈々美、日高貢一郎
日本方言研究会編『方言の研究 3 特集 ことばのひろがり』詳細
『トルコのもう一つの顔』(中公新書)の著者、小島剛一さんがラズ語の辞書の刊行を計画しています。賛同者を募る講演会を開催しますので、ふるってご参加ください。
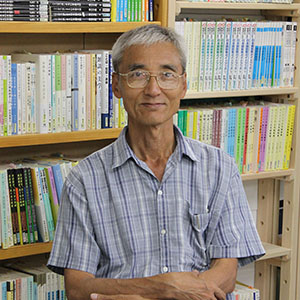
■日時……2017年9月20日(水) 18:30開場 19:00開演
■講演時間…1時間半程度を予定
■会場……アジア文化会館 地下 101研修室
(都営地下鉄三田線 千石駅(A1 出口)より徒歩3分
JR 山手線 駒込駅(南口)または巣鴨駅より徒歩10分
東京メトロ南北線 駒込駅または本駒込駅より徒歩10分)
■参加費…1,000円
■申込方法…事前申込 または 当日受付
概要今回の講演では、書き進めている「ラズ語辞書」についての解説をしていただきます。 |
『グリム兄弟言語論集 言葉の泉』(ヤーコプ・グリム、ヴィルヘルム・グリム著 千石喬、高田博行編)が、日本翻訳家協会主催の第53回日本翻訳出版文化賞を受賞することが決まりました。
日本翻訳出版文化賞は、過去1年で最も優れた翻訳書を刊行した出版社に対し贈られる賞です。

『グリム兄弟言語論集 言葉の泉』
ヤーコプ・グリム、ヴィルヘルム・グリム著 千石喬、高田博行編
ロマン主義の思潮に連なるグリム兄弟の言語思想は、言語を考古学や歴史学への門戸と考え、究極的には人間精神を追求する普遍的・総合的なものであった。全400頁に迫る本書で訳出するのは、ドイツの国民的業績とされる『ドイツ語辞典』の序文、『ドイツ語文法』の序文の他、子音推移、ウムラウトと母音混和、言語浄化主義、言語起源論、語源論、指の名称に関する論考である。(言語起源論を除き)本邦初訳。
訳者:千石喬・木村直司・福本義憲・岩井方男・重藤実・岡本順治・高田博行・荻野蔵平・佐藤恵
『グリム兄弟言語論集』詳細
白井氏は、世界中で高く評価されているデザイン誌「アイデア」のアートディレクションを10年に亘り手がけたデザイナーさんです。
ひつじ書房では、「ひつじ研究叢書(言語編)」(101巻以降)やHituzi Linguistics in Englishシリーズ(No.24以降)、Hituzi Language Studiesシリーズなどのブックデザインをお願いしています。現在使用中の名刺や封筒も、白井氏によるものです。
ギンザ・グラフィック・ギャラリー第362回企画展
組版造形 白井敬尚
2017年09月26日(火)〜11月07日(火)
会場:〒104-0061 東京都中央区銀座7-7-2 DNP銀座ビル1F
ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)
TEL:03-3571-5206/FAX:03-3289-1389
11:00am-7:00pm
日曜・祝日休館/入場料無料
『トルコのもう一つの顔』(中公新書)、『トルコのもう一つの顔・補遺編』(ひつじ書房)の著者、小島剛一さんがラズ語の辞書の刊行を計画しています。賛同者を募る講演会を今年も開催しますので、ふるってご参加ください。
■日時……2017年9月20日(水) 18:30開場 19:00開演予定
■会場……アジア文化会館 地下 101研修室
(東京都文京区本駒込2-12-13 http://www.abk.or.jp/access/index.html
都営地下鉄三田線 千石駅(A1 出口)より徒歩3分
JR 山手線 駒込駅(南口)または巣鴨駅より徒歩10分
東京メトロ南北線 駒込駅または本駒込駅より徒歩10分)
■参加費…1000円
■申込方法…事前申込(toiawaseアットマークhituzi.co.jp tel:03-5319-4916)
または 当日受付
(人数の把握のため、事前申込にご協力ください)
■計画中の「ラズ語辞書」についての解説、ラズ語の特徴、トルコにおける少数民族の現状について等をお話いただく予定です。詳細が決まり次第、お知らせします。

ひつじ書房ウェブマガジン「未草」(ひつじぐさ)の公開を開始しました。
言語学や文学、その他ことばに関わる幅広いテーマについて研究者による連載のほか、ひつじ書房の刊行物やイベントの紹介をしてまいります。
ウェブマガジンでは、紙の本では難しい音声や動画の分析についても掲載することが可能になります。
これから様々な連載を掲載してまいりますので、楽しみにお待ちください。
ひつじ書房ウェブマガジン「未草」(ひつじぐさ)
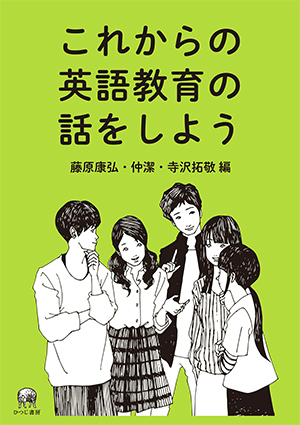
藤原康弘・仲潔・寺沢拓敬編『これからの英語教育の話をしよう』を刊行しました。
英語教育の「抜本的改革」は成功するのか? 2017年3月、次期学習指導要領と英語教員養成・研修のコア・カリキュラムが発表された。この「改革案」を、異なるバックグラウンドを持った3人の新進気鋭の研究者が斬る。社会学・国際英語論・批判的応用言語学の観点から、改革案の問題点を論じ、対案を示す。高校教員と高等教育研究者を交えた座談会も収録。英語教育の未来はどうあるべきか。さあ、これからの英語教育の話をしよう。
藤原康弘・仲潔・寺沢拓敬編『これからの英語教育の話をしよう』詳細
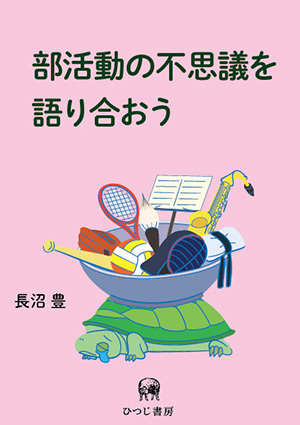
長沼豊著『部活動の不思議を語り合おう』を刊行しました。
部活動は、教員の人生を破壊するブラックなものになってしまった。教員は、授業とは別に過重な労働を強いられ、断ることができない。過労による自殺者まででてしまっている。本来、生徒を育み、人生を豊かにするはずであったものが、ブラック部活とまで言われている。どうしてそうなってしまったのか。部活動の変革の機運の高まる中、部活動の歴史を振り返り、その重要性を認めつつ、打開策を様々な立場から考える。
長沼豊著『部活動の不思議を語り合おう』詳細
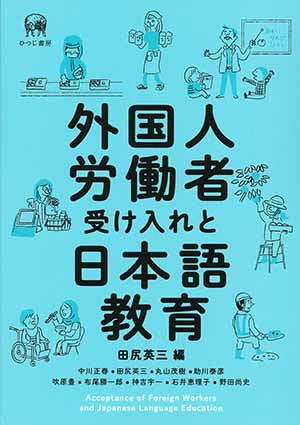
田尻英三編『外国人労働者受け入れと日本語教育』を刊行しました。
勉強しないでアルバイトばかりの留学生が問題とされた。留学生や日本語学校がいいかげんという個別の事例が問題なのか。日本語学校の存在を軽視して、行き当たりばったりだったこれまでの政策に問題があるのではないか。外国人労働者を受け入れなければ、日本社会は運営できないという指摘もある中で、日本社会は、いままでのように「見ない振り」をしていられるのか。日本語教育の視点から、外国人労働者と日本社会、日本社会のあり方を考え、問題提起する。元文部大臣中川正春氏も寄稿。
田尻英三編『外国人労働者受け入れと日本語教育』詳細
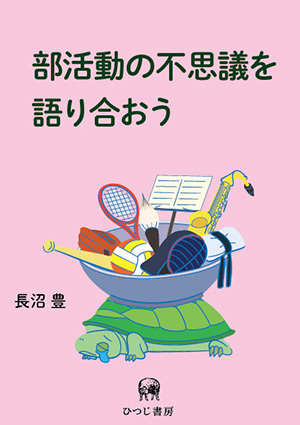
『部活動の不思議を語り合おう』(長沼豊著)8月10日刊行予定です
部活動は、教員の人生を破壊するブラックなものになってしまった。教員は、授業とは別に過重な労働を強いられ、断ることができない。過労による自殺者まででてしまっている。本来、生徒を育み、人生を豊かにするはずであったものが、ブラック部活とまで言われている。どうしてそうなってしまったのか。部活動の変革の機運の高まる中、部活動の歴史を振り返り、その重要性を認めつつ、打開策を様々な立場から考える。
長沼豊著『部活動の不思議を語り合おう』詳細

柳町智治・岡田みさを編『インタラクションと学習』を刊行しました。
近年のコミュニケーション研究はインタラクションという視点の下、大きな転換を遂げつつある。 同時にその転換は、人々の学習という概念の見直しをも迫っている。本書では、国立国語研究所共同研究のメンバーが、日常会話・スポーツ・科学実験・授業・SNSなどさまざまな活動場面における日本語母語話者あるいは第二言語話者による相互行為を分析し、考察を展開する。
柳町智治・岡田みさを編『インタラクションと学習』詳細

新入社員1名を迎え、入社式をおこないました。
たいへん申し訳ありませんが、2017年7月29日(土)に開催を予定していた『脱文法 100トピック実践英語トレーニング』ワークショップは、都合により中止とさせていただきます。今後の開催日は未定です。
Tweet

新シリーズ刊行開始!
ちょっとまじめに英語を学ぶシリーズ1(シリーズ監修 赤野一郎・内田聖二)、関山健治著『英語辞書マイスターへの道』を刊行しました。
まじめな英語学習は「辞書に始まり、辞書に終わる」。誰もが辞書を持っているのに、ほとんどの人は「知らない単語の意味を調べる」ためにしか使っていない。本書では、紙の辞書はもちろん、電子辞書、スマートフォンの辞書アプリなど、最新の辞書メディアも含めた辞書の活用法を、練習問題を解きながら身につける。語源欄の読み方、英語母語話者向けの英英辞典や類義語辞典の読み方など、従来の辞書活用書にはあまり見られない辞書の使い方も満載。
関山健治著『英語辞書マイスターへの道』詳細
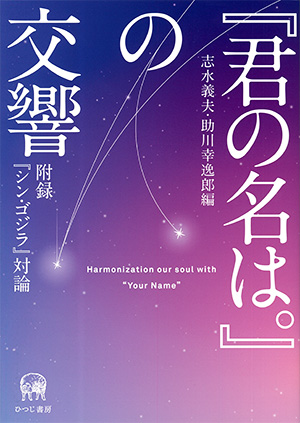
志水義夫・助川幸逸郎編『『君の名は。』の交響』を刊行しました。
歴史的ヒットを記録した映画『君の名は。』の核心に、民俗学、日本文学史、物語論を動員して迫る! 〈映像〉の分析を通じて浮かびあがる〈日本の文化の現在〉。2017年1月、東海大学で開催されたシンポジウムの記録に気鋭の論者による報告を追加。さらに『シン・ゴジラ』との比較を通したオタク化する社会に関する編者の対談講義も収録。執筆者:志水義夫、堀啓子、助川幸逸郎、三輪太郎、安達原達晴、倉住薫
志水義夫・助川幸逸郎編『『君の名は。』の交響』詳細
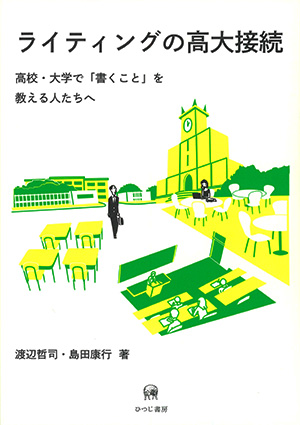
渡辺哲司・島田康行著『ライティングの高大接続 高校・大学で「書くこと」を教える人たちへ』を刊行しました。
一人の学生にとって一連・一体のものであるべきライティング教育が、高校と大学の双方で、独立的かつ自己完結的に、断絶や重複を露呈しつつ行われている。そこで本書では、高・大の間でつながりの悪いところはどこか、なぜそうなっているのか、どうつなげばよいかを、教師の視点から考えてみる。高卒者の半数以上が大学生となる現代日本のライティング教育の内容を、高校から大学へと続く一体のものとして、単なるハウツーを超えて論じる空前の試み。
渡辺哲司・島田康行著『ライティングの高大接続 高校・大学で「書くこと」を教える人たちへ』詳細
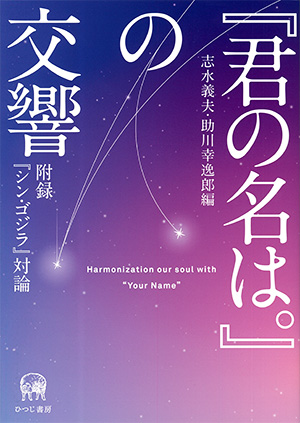
『『君の名は。』の交響』(志水義夫・助川幸逸郎編)7月上旬刊行予定です
歴史的ヒットを記録した映画『君の名は。』の核心に、民俗学、日本文学史、物語論を動員して迫る! 〈映像〉の分析を通じて浮かびあがる〈日本の文化の現在〉。2017年1月、東海大学で開催されたシンポジウムの記録に気鋭の論者による報告を追加。さらに『シン・ゴジラ』との比較を通したオタク化する社会に関する編者の対談講義も収録。執筆者:志水義夫、堀啓子、助川幸逸郎、三輪太郎、安達原達晴、倉住薫
志水義夫・助川幸逸郎編『『君の名は。』の交響』詳細
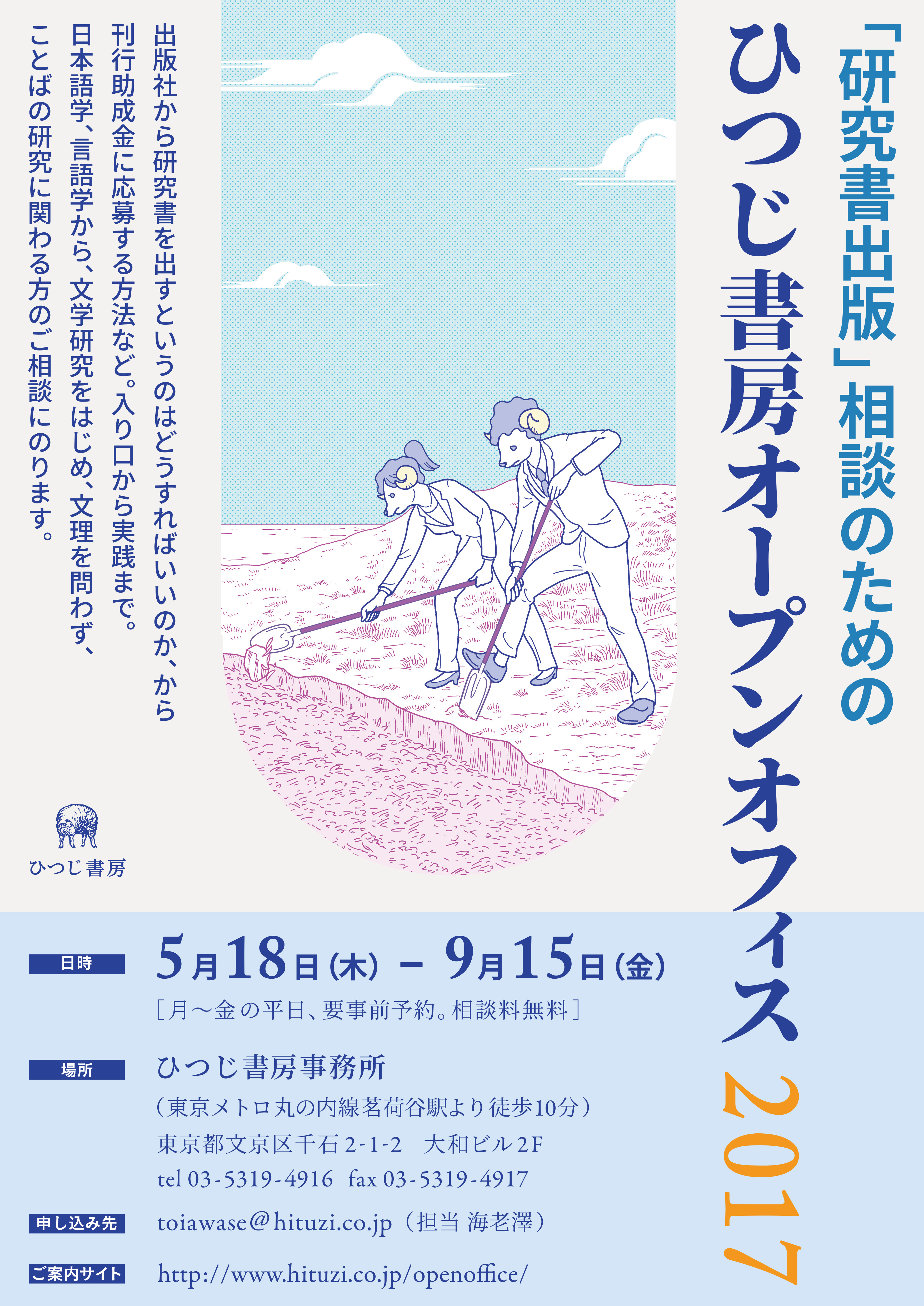
今年も研究書出版についての相談のためのオープンオフィスを行います。
出版社から研究書を出すというのはどうすればいいのか、から、
刊行助成金に応募する方法など、
入り口から実践まで。
日本語学、言語学から、文学研究、文化研究、脳研究、心理学など
文理を問わず、ことばの研究に関わる方のご相談にのります。
*ポスターを作成しました。大学・研究機関等で掲示して下さる方がいらっしゃいましたらお送りします。toiawaseアットマークhituzi.co.jpまでご連絡ください。
オープンオフィス詳細
2017年6月19日に創立27周年を迎えました。創立といいますのは、法人の登記をしたということです。有限会社でした。その時は資本金が300万円で、その内、70万円は父からもらった赤いシビックでした。1990年ということですが、1冊目が1991年で、それまでは、パンフレットを学会で配って、宣伝をして予約をお願いしていました。第一冊目は村木新次郎先生の『日本語動詞の諸相』という書籍でした。2冊目は仁田義雄先生の『日本語のモダリティと人称』でした。お二人ともまだ40代の前半でした。私も会社を作りましたのは29歳の時でした。新しい日本語研究の研究書を刊行していきたいというのが出発点でした。90年代の前半は、くろしお出版さんの後をおっている段階でしたが、現代日本語の研究書を出す出版社がなく、学会では書籍売り場に列ができる程でした。その後、旧来の教科書や辞書などを出している大手出版社が、言語の分野にも参入し、90年代後半には市場は過当競争と呼べる状況になりました。
ひつじ書房は、より学術書の要素の強い書籍を刊行するという趣旨を明確にし、教科書的あるいは一般書的な書籍よりも研究書、学術書を出していくという方向、出発時に持っていた方向に再度軸を据えることにしました。特に盤石というよりも、新しい研究、挑戦的な研究に関与していきたいという思いで刊行してきました。おおむねその方向は間違っていなかったと思います。学術書のあり方は変わってきているところもあります。なにより、大学制度や学生気質などは大きく変化してきました。その中でも、学術書の公共性ということを護りつつ、言語研究のより豊かなありかたを研究者の方々と模索し続けていきたいと思います。27周年を迎えまして、28年目に入りますこの機会に発端の決意をあらためて思いをいたします。これまでのご支援を感謝申し上げますとともにこれからも叱咤激励いただけますようお願い申し上げます。
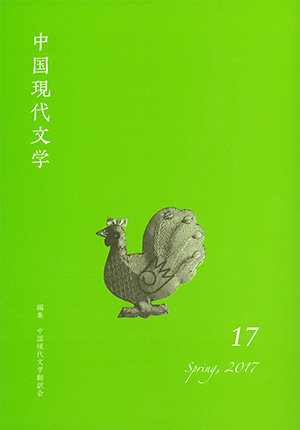
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 17』を刊行しました。
現代中国の文学作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第17号。李文方「怪猫」(恐ろしい猫の幻影を見る少女の話)、葉広芩「外人墓地」(安定門外の外人墓地で遊んでいた幼少期の思い出)、鍾求是「二人の映画」(三十年におよぶ密かな逢瀬の物語)、韓東「いい天気だ」「この世での一日」「季節の讃歌」(詩人としての成熟が感じられる詩三篇)などを掲載する。
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 17』詳細
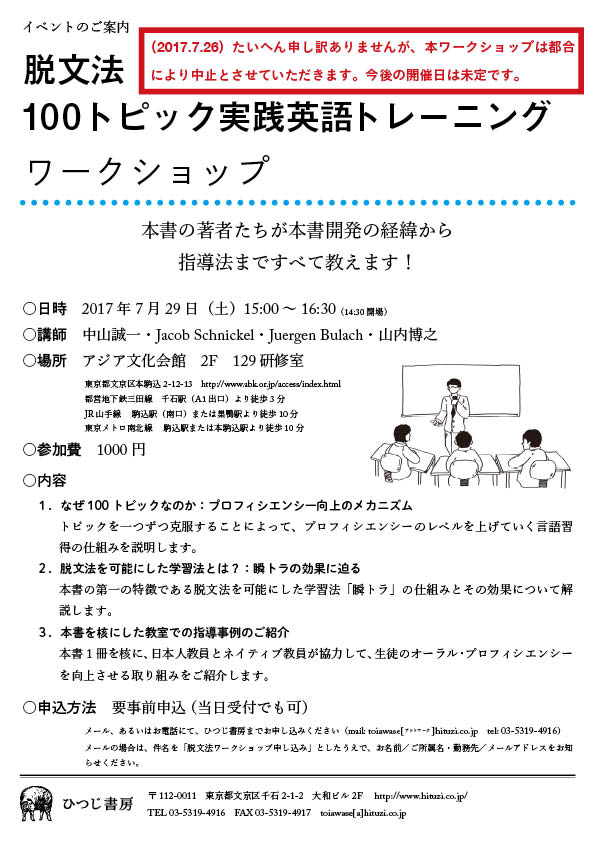
『脱文法 100トピック実践英語トレーニング』ワークショップを開催します。
本書の著者たちが本書開発の経緯から指導法まですべて教えます!
○日時 2017 年7 月29 日(土)15:00 〜 16:30
○講師 中山誠一・Jacob Schnickel・Juergen Bulach・山内博之
○場所 アジア文化会館 2F 129 研修室
○参加費 1000 円
中山誠一・Jacob Schnickel・Juergen Bulach・山内博之著『脱文法 100トピック実践英語トレーニング』書籍の詳細
ワークショップ詳細
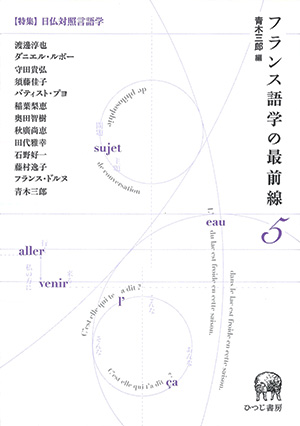
青木三郎編『フランス語学の最前線 5 【特集】日仏対照言語学』を刊行しました。
フランス語学の最新の成果を世に問うシリーズ第5巻。フランス語と日本語の対照研究を特集。比べて見えてくる日本語の姿とフランス語の姿。言葉の違いが世界の捉え方を変える。日本語学とフランス語学。認知論にも異文化理解にもヒントが満載の論文集。執筆者:青木三郎・渡邊淳也・ダニエル=ルボー・守田貴弘・須藤佳子・プヨ=バティスト・稲葉梨恵・奥田智樹・秋廣尚恵・田代雅幸・石野好一・藤村逸子・ドルヌ=フランス
青木三郎編『フランス語学の最前線 5 【特集】日仏対照言語学』詳細
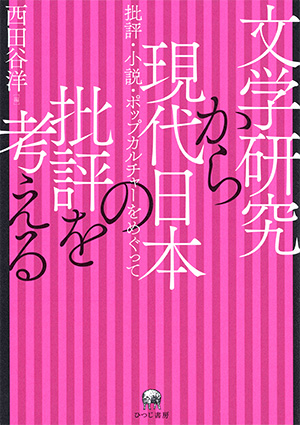
西田谷洋編『文学研究から現代日本の批評を考える 批評・小説・ポップカルチャーをめぐって』を刊行しました。
文学や文化について伝統的に批評は大きな見取り図を示してきたが、文学研究の蓄積は参照されてきたとは言いがたい。本書は、文学研究と批評の接点として、ゼロ年代批評がその対象としたポップカルチャーを中心に、現代の文学・文化の展開やそこに現れるジェンダー秩序、文芸批評や理論導入をめぐる力学を取り扱うことで、文学研究・文化批評の更新を目指す。
西田谷洋編『文学研究から現代日本の批評を考える 批評・小説・ポップカルチャーをめぐって』詳細

佐藤勝明・小林孔著『続猿蓑五歌仙評釈』を刊行しました。
『続猿蓑』は、芭蕉晩年の志向と境地をよく示す撰集でありながら、芭蕉の死をはさんで刊行が遅れたこともあり、研究が十分にされているとは言いがたい。その反省から、同書所収の五歌仙全体にわたり、各付合がどのように成り立っているかを分析し、各歌仙の傾向から同書成立の問題まで明らかにする。
佐藤勝明・小林孔著『続猿蓑五歌仙評釈』詳細
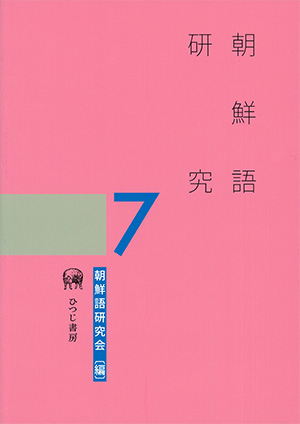
朝鮮語研究会編『朝鮮語研究 7』を刊行しました。
本書は1983年4月に発足し、1999年からは正式に学会組織として活動してきた朝鮮語研究会の不定期刊学会誌『朝鮮語研究』の第7号である。本書には、音声と発音の指導法に関する論文1篇、色彩語に関する論文1篇、現代朝鮮語文法に関する論文1篇、中期朝鮮語の語彙に関する論文1篇、吏読文に関する論文1篇の計5篇が収められている。
朝鮮語研究会編『朝鮮語研究 7』詳細
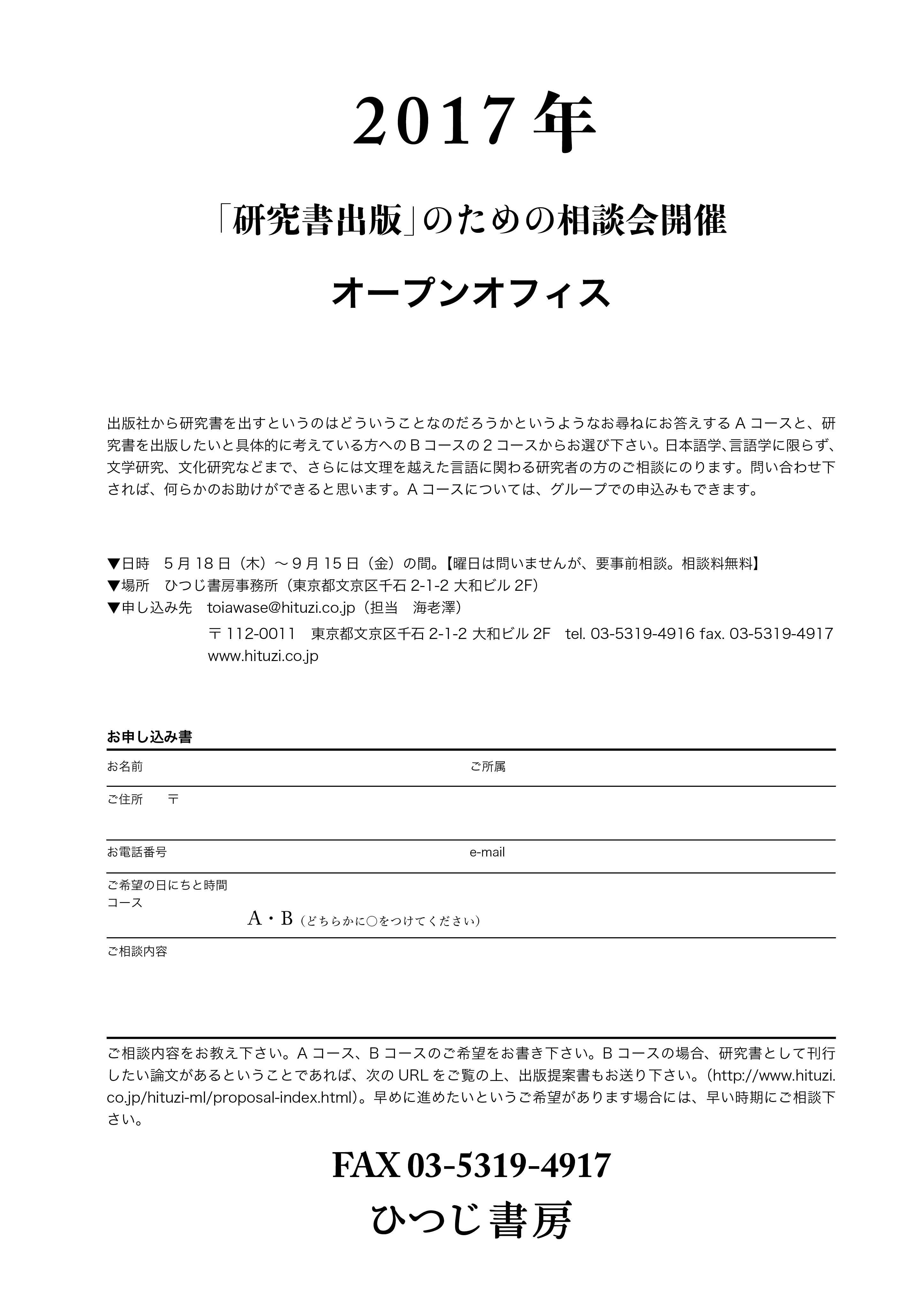
今年も研究書出版についての相談のためのオープンオフィスを行います。
出版社から研究書を出すというのはどうすればいいのか、から、
刊行助成金に応募する方法など、
入り口から実践まで。
日本語学、言語学から、文学研究、文化研究、脳研究、心理学など
文理を問わず、ことばの研究に関わる方のご相談にのります。
オープンオフィス詳細
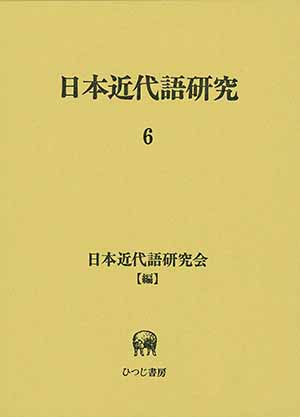
日本近代語研究会編『日本近代語研究 6』を刊行しました。
近代日本語の歴史と構造を、音声、文法、語彙といったパースペクティブから分析するとともに、その際用いられる辞書、教科書、文学作品などの資料性に検討を加えた論文集第6弾。
執筆者:佐藤武義、ジスク・マシュー、孫建軍、村上雅孝、飛田良文、荒尾禎秀、小野正弘、新野直哉、服部隆、岩澤克、上野隆久、遠藤佳那子、神作晋一、木下哲生、櫛橋比早子、小島和、杉本雅子、田貝和子、中野真樹、八木下孝雄、山田里奈、山田実樹
日本近代語研究会編『日本近代語研究 6』詳細
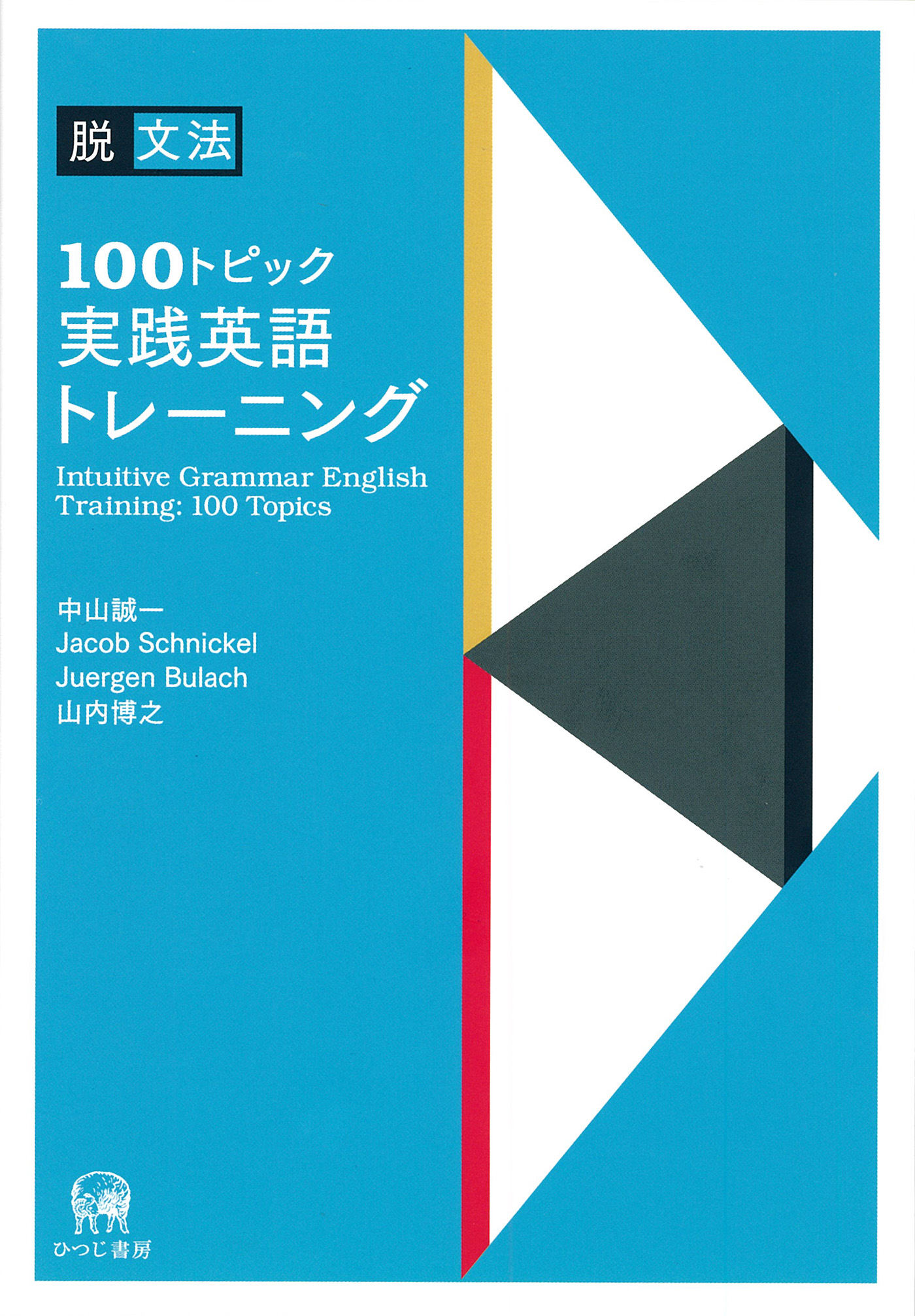
中山誠一・Jacob Schnickel・Juergen Bulach・山内博之著『脱文法 100トピック実践英語トレーニング』を刊行しました。
「食」「旅行」「美容・健康」などの身近な話題から「宗教」「政治」「テクノロジー」などの抽象的な話題に至るまで、100種類の話題で英語の「話す・聞く」トレーニングを行う。トレーニングの方法としては、並んでいる日本語の単語を逐語訳していくだけで、英文が自然に口から出てくる「瞬間トランスレーション法」という独自の手法を採り入れている。また、それぞれの話題に、難易度の異なる三段階の練習を配置し、CEFRのA1、A2、B1のレベルに対応できる工夫も施されている。
★音源はネットで提供
中山誠一・Jacob Schnickel・Juergen Bulach・山内博之著『脱文法 100トピック実践英語トレーニング』詳細
鳥飼玖美子・大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史著 座談会 林徹×鳥飼玖美子×大津由紀雄×斎藤兆史『英語だけの外国語教育は失敗する 複言語主義のすすめ』を刊行しました。
日本の外国語教育における英語の偏重、英語の実用性ばかりを重視する風潮に、4人が異議を唱える。英語だけを用いる授業や様々な異論をおしきっての小学校での英語の教科化が狙いとする、実用的な英語の習得だけを目指すのではなく、子どもの「ことば」への疑問や関心を大切にし、ことばの面白さや母語への気づきを育むべきではないのか。英語だけではなく、様々な言語への気づきが大事なのではないのか。日本学術会議言語・文学委員会の「提言」や座談会も収録。
鳥飼玖美子・大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史著 座談会 林徹×鳥飼玖美子×大津由紀雄×斎藤兆史『英語だけの外国語教育は失敗する 複言語主義のすすめ』詳細

『手話を言語と言うのなら』への久松氏の批判とそれに対する反論のページ
『手話を言語と言うのなら』に対する久松三二氏の批判について、著者たちが集まり日本手話で議論をおこないました。このときの議論をもとに、反論のページをまとめました。

新刊・近刊のご案内の冊子『未発ジュニア版』を発送しました。
『未発ジュニア版』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いいたします。
小林隆・川﨑めぐみ・澤村美幸・椎名渉子・中西太郎著『方言学の未来をひらく オノマトペ・感動詞・談話・言語行動』を刊行しました。
オノマトペ、感動詞、談話、言語行動…これらの分野の地域差はどう研究するのか。近年の学界の関心を踏まえ、方言学の未開拓の分野を切り拓く先導役を果たすのが本書である。初めてこの分野に触れる人たちのために、先行研究の概観や課題の整理を行い、方法論や資料論を検討しながら実践例を示す。すぐに使用できる調査項目の案も掲載した。方言学に限らず、言語学・日本語学にとっても本書はこの分野の基礎的な文献となるにちがいない。
小林隆・川﨑めぐみ・澤村美幸・椎名渉子・中西太郎著『方言学の未来をひらく オノマトペ・感動詞・談話・言語行動』詳細
大木一夫著『文論序説』を刊行しました。
文はいかに成立するのかという問題は、文法論の基本的で重要な問題であるが、なかなか解決にいたらない文法論のアポリアである。この問題に対して、行為としての言語という視座から考えることを試みる。文の成立には、文が文としてもつ言語行為的意味が関わることを説き、そのような立場の射程を示すために、いくつかの文法概念の再構築について論じ、さらに、この立場にもとづく現代日本語の時間表現の精細な記述におよぶ。
大木一夫著『文論序説』詳細
松村文芳著 神奈川大学言語学研究叢書8『現代中国語の意味論序説』を刊行しました。
本書は現代中国語を、①動詞と時間体系、②語彙が構成する意味と論理、③構文が構成する意味と論理、④語彙が規制する論理の4部立てで論じた。①動詞の時間体系を整理しその全体像を記述。②は辞書では十分に説明されない“很” “把” “给” “得”を有する構文を論理式で記述。③は反語文、疑問詞の量化、比較構文を詳述。④は語気助詞“了”と“呢”の文の論理に対する規制を論じる。現代中国語の意味を総体的に示した。
松村文芳著 神奈川大学言語学研究叢書8『現代中国語の意味論序説』詳細
山梨正明著『自然論理と日常言語—ことばと論理の統合的研究』を刊行しました。
日常言語には、創造的で柔軟な思考・判断を可能とする〈自然論理〉(Natural Logic) のメカニズムが密接に関わっている。本書では、日常言語の文法現象や意味現象の具体的な考察を通して、自然論理のメカニズムと日常言語のメカニズムの諸相を明らかにしていく。また、従来の論理学と言語学の研究の統合を目指す認知科学的な視点から、言葉と論理に関わる人間の創造的な知のメカニズムの諸相を明らかにしていく。
山梨正明著『自然論理と日常言語—ことばと論理の統合的研究』詳細

ひつじ書房で花見をしました。
夏海燕著 神奈川大学言語学研究叢書7『動詞の意味拡張における方向性—着点動作主動詞の認知言語学的研究』を刊行しました。
「買う」「食う」「かぶる」のような動詞は、他動詞でありながら動作が動作主から出発し動作主において終結するという特徴を持つ。本書はこのような動詞を「着点動作主動詞」と呼び、それらの動詞に〈自分の領域へのモノの移動〉というイメージ・スキーマによって、〈不快な経験をする〉という意味拡張が起こることを示す(例:本を買う→不信を買う)。日本語・中国語・韓国語・英語などの多言語データをもとに議論を展開する。
夏海燕著 神奈川大学言語学研究叢書7『動詞の意味拡張における方向性—着点動作主動詞の認知言語学的研究』詳細
髙橋輝和著『ドイツ語の様相助動詞 その意味と用法の歴史』が第14回日本独文学会賞(日本語研究書部門)を受賞しました。
髙橋輝和先生、おめでとうございます!
日本独文学会 第14回日本独文学会賞選考結果のページ
髙橋輝和著『ドイツ語の様相助動詞 その意味と用法の歴史』詳細
石川慎一郎著『ベーシック応用言語学 L2の習得・処理・学習・教授・評価』を刊行しました。
外国語はどのように習得されるのか,どのように指導するのが効果的なのか,どうすればその能力を正しく測定できるのか……。近年,外国語教育をめぐる議論はますます盛んになっているが,求められるのは,幅広い学問的視野である。本書は,従来,個別的に論じられることの多かった,第2言語(L2)の習得・処理・学習・教授・評価の問題を統合的に位置づけ,平易な解説でその全体像を示したものである。英語教育や日本語教育に関わる実例も豊富で,読者は,実例と理論の両面から理解を深めることができるだろう。
石川慎一郎著『ベーシック応用言語学 L2の習得・処理・学習・教授・評価』詳細
イェルク・キリアン著 細川裕史訳『歴史会話研究入門』を刊行しました。
「歴史会話研究」、すなわち虚構の会話もふくめた「あらゆる年代の(文字化された)会話」を対象とした言語研究のための手引き書。本書の内容は、第1 章と第2 章が歴史会話研究における術語や概念の紹介、第3 章から第6 章が具体的な分析例の紹介となっている(会話の言語構造、語用論的機能、規範、歴史的変遷)。先行研究や分析例が豊富に紹介されているため、過去におこなわれた会話に関心のあるすべての学生・研究者にとって有意義といえる。
イェルク・キリアン著 細川裕史訳『歴史会話研究入門』詳細
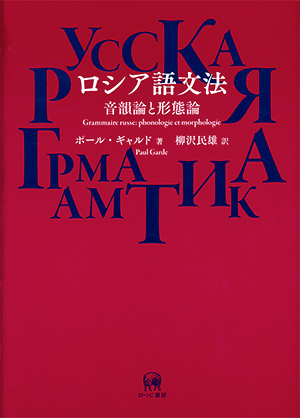
ポール・ギャルド著、柳沢民雄訳『ロシア語文法 音韻論と形態論』を刊行しました。
本書は、スラヴ語アクセントの歴史的研究で世界的に著名な Paul Garde のGrammaire russe: phonologie et morphologie(1998、第2版)の翻訳である。現代標準ロシア語を共時的に記述、首尾一貫した原理によって分析する。音韻論を土台に形態論を体系的に記述していく構成で、特に音韻論は類書にないほど分かりやすく、ロシア語の音韻構造を理解するための入門として最適。
日本で出版されているロシア語の文法書や教科書には『80年アカデミー文法』をはじめとする世界のロシア語研究の定説とは異なったことが書かれていることが多い。この日本のロシア語学の現状を考え、『80年アカデミー文法』等を用いて、詳細な訳注を付けた。
ポール・ギャルド著、柳沢民雄訳『ロシア語文法 音韻論と形態論』詳細

小野寺典子編『発話のはじめと終わり 語用論的調節のなされる場所』を刊行しました。
「話す」ことは、人の基本的・原始的営みである。なかでも発話頭・末(周辺部)は、話者が「会話管理」「談話方略」「対人機能」などの「語用論的調節」をしている場所と考えられ、注目されている。人は、「発話のはじめと終わり」で何をしているのだろうか。周辺部研究の基礎知識から、英日語それぞれの例、最新の文法化・構文化研究まで、第一線の研究者たちが論じる。
執筆者:小野寺典子、澤田淳、東泉裕子、Joseph V. Dias(岩井恵利奈・訳)、Elizabeth Closs Traugott(柴﨑礼士郎・訳)
小野寺典子編『発話のはじめと終わり 語用論的調節のなされる場所』詳細
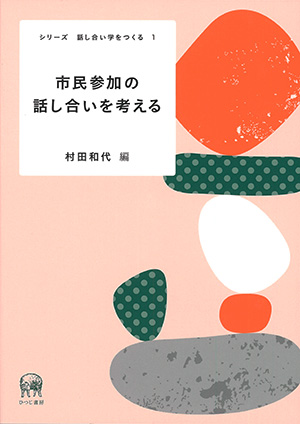
村田和代編『市民参加の話し合いを考える』を刊行しました。
「シリーズ 話し合い学をつくる」第1巻。まちづくりの話し合いやサイエンスカフェ、裁判官と裁判員の模擬評議など、専門的知見を持たない市民と専門家が意見交換や意思決定をする「市民参加の話し合い」を考える。話し合いの場で行われる言「語や相互行為に着目したミクロレベルの研究から、話し合いによる課題解決・まちづくりをめぐる話し合いの現場での実証研究や話し合い教育をめぐる研究まで。「市民参加の話し合い」の現状と課題について学問領域を超えて論じる実証的研究論文9本と座談会を収録。
執筆者:福元和人、高梨克也、森本郁代、森篤嗣、唐木清志、馬場健司、高津宏明、井関崇博、三上直之、西芝雅美
座談会:村田和代、森本郁代、松本功、井関崇博、佐野亘
村田和代編『市民参加の話し合いを考える』詳細
『学生を思考にいざなうレポート課題』の刊行を記念して、成瀬尚志先生が講演会を行います。ふるってご参加ください。
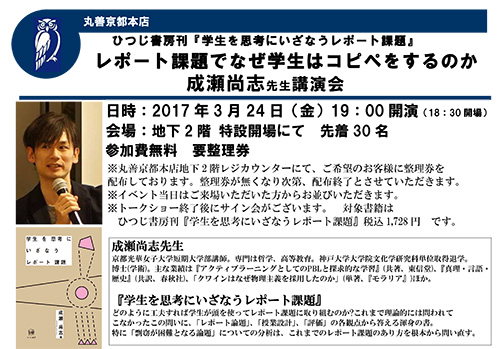
■日時……2017年3月24日(金) 18:30開場 19:00開演
■会場……丸善京都本店 地下2階特設会場
■参加費…無料(要整理券)
※丸善京都本店地下2階レジカウンターにて、整理券を配布しております。整理券がなくなり次第、配布終了とさせていただきます(定員30名)。
※イベント当日はご来場いただいた方からお並びいただきます。
※講演会終了後にサイン会がございます。対象書籍は『学生を思考にいざなうレポート課題』(税込1,728円)です。
丸善京都本店 トークイベント ひつじ書房『学生を思考にいざなうレポート課題』刊行記念 成瀬尚志先生講演会 レポート課題でなぜ学生はコピペをするのか
成瀬尚志編『学生を思考にいざなうレポート課題』詳細
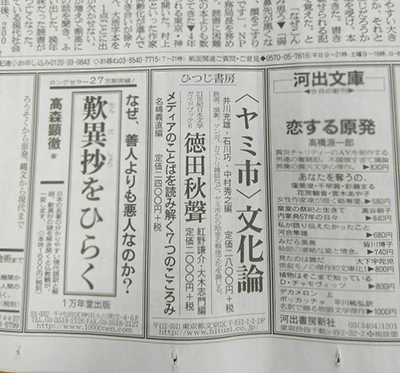
『朝日新聞』(3月7日朝刊)に広告を掲載しました。1面の下、三八つ広告です。『〈ヤミ市〉文化論』、『21世紀日本文学ガイドブック6 徳田秋聲』、『メディアのことばを読み解く7つのこころみ』を掲載しました。
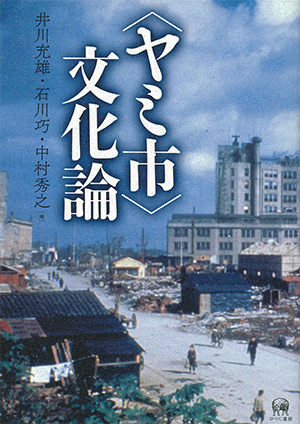
井川充雄・石川巧・中村秀之編『〈ヤミ市〉文化論』を刊行しました。
ヤミ市は欲望と暴力が支配する混沌であると同時に、欲望と暴力が秩序を確立していく世界だった。戦後日本の都市文化、メディア、風俗はそうした逆説とともに出発した。本書は、その誕生から解体までを都市開発の観点から検証するとともに、同時代の新聞、映画、文学、演劇、マンガ、カストリ雑誌、探偵小説、メロドラマを多角的に論じることでヤミ市から始まる戦後文化を多角的に論じている。
執筆者:吉見俊哉、マイク・モラスキー、川本三郎、初田香成、石榑督和、井川充雄、石川巧、落合教幸、後藤隆基、河野真理江、中村秀之、山田夏樹、渡辺憲司、渡部裕太
井川充雄・石川巧・中村秀之編『〈ヤミ市〉文化論』詳細
ひつじ書房は、社員を募集中です。詳細は以下をご覧ください。
2017年春卒と既卒の方、2018年春卒予定の方へ 正社員の募集・求人・採用(編集+出版業務)ページ

服部隆著『明治期における日本語文法研究史』を刊行しました。
明治時代は、江戸時代の伝統的国語研究が「発見」した日本語文法を、西洋的なフィルターを通して「語り直す」時代であった。本書は、伝統的国語研究と西洋文典の利用法の検討から、品詞論・統語論において品詞の分類法や文法論上の諸概念が確立していった過程を明らかにするとともに、西周・松下大三郎による文法研究の背景、さらに文法用語の変遷を取り上げ、今日に通じる文法論の基盤が明治期に成立してゆく過程を、系統的・総合的に記述することを目指す。
服部隆著『明治期における日本語文法研究史』詳細

ヤーコプ・グリム、ヴィルヘルム・グリム著 千石喬、高田博行編『グリム兄弟言語論集 言葉の泉』を刊行しました。
ロマン主義の思潮に連なるグリム兄弟の言語思想は、言語を考古学や歴史学への門戸と考え、究極的には人間精神を追求する普遍的・総合的なものであった。全400頁に迫る本書で訳出するのは、ドイツの国民的業績とされる『ドイツ語辞典』の序文、『ドイツ語文法』の序文の他、子音推移、ウムラウトと母音混和、言語浄化主義、言語起源論、語源論、指の名称に関する論考である。(言語起源論を除き)本邦初訳。
訳者:千石喬・木村直司・福本義憲・岩井方男・重藤実・岡本順治・高田博行・荻野蔵平・佐藤恵
ヤーコプ・グリム、ヴィルヘルム・グリム著 千石喬、高田博行編『グリム兄弟言語論集 言葉の泉』詳細

今村泰也著『所有表現と文法化 言語類型論から見たヒンディー語の叙述所有』を刊行しました。
所有は抽象的な概念であり、世界の言語の所有表現は具体的な表現から発達している。例えば、ヒンディー語には英語のhaveに相当する動詞がなく、叙述所有(X has Y)は、X ke paas Y honaa「Xの近くにYがある」、X kaa Y honaa「XのYがある」のように存在文で表される。本書は所有を文法化の流れの中で捉えたHeine (1997)Possessionの理論的枠組みに基づき、ヒンディー語の6つの所有構文と各構文に見られる文法現象を言語類型論の観点から考察した。本書は50を超える言語の例と研究の知見を含み、さまざまな言語を研究する際のヒントを提供する。
今村泰也著『所有表現と文法化 言語類型論から見たヒンディー語の叙述所有』詳細

名嶋義直編『メディアのことばを読み解く7つのこころみ』を刊行しました。
2015年3月22日に仙台にて開催された国際シンポジウムの講演内容に加筆修正を施して刊行。まず執筆者たちは、言語学者・言語教育者がいまなぜメディア談話を批判的に分析するのか、その意義はどこにあるのかについて自らの意見や立場を語った。そしてさまざまなアプローチでテレビ・新聞・記者会見・インターネット上の情報等のメディア談話を批判的に分析した。それらの論文を読み込むことで市民性教育においても重要な批判的リテラシーが得られることを期待する。執筆者:庵功雄、今村和宏、大橋純、神田靖子、名嶋義直、野呂香代子
名嶋義直編『メディアのことばを読み解く7つのこころみ』詳細
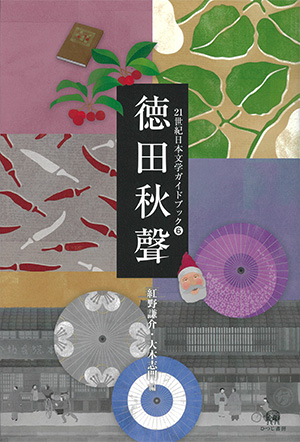
紅野謙介・大木志門編『21世紀日本文学ガイドブック6 徳田秋聲』を刊行しました。
徳田秋声は日本の自然主義文学の代表的な作家のように言われてきた。同時に広津和郎や林芙美子、野口富士男、古井由吉、中上健次といった一筋縄ではいかない作家たちが秋聲受容の系譜を支えている。近代日本の散文をめぐる新たな冒険家であり、かつまた物語的想像力の伝統をくみ上げながら、「文学場」の生成に立ち会ったひとりの作家の軌跡を、その受容史とともにたどる。執筆者:紅野謙介、大木志門、大杉重男、西田谷洋、梅澤亜由美、小林修
紅野謙介・大木志門編『21世紀日本文学ガイドブック6 徳田秋聲』詳細
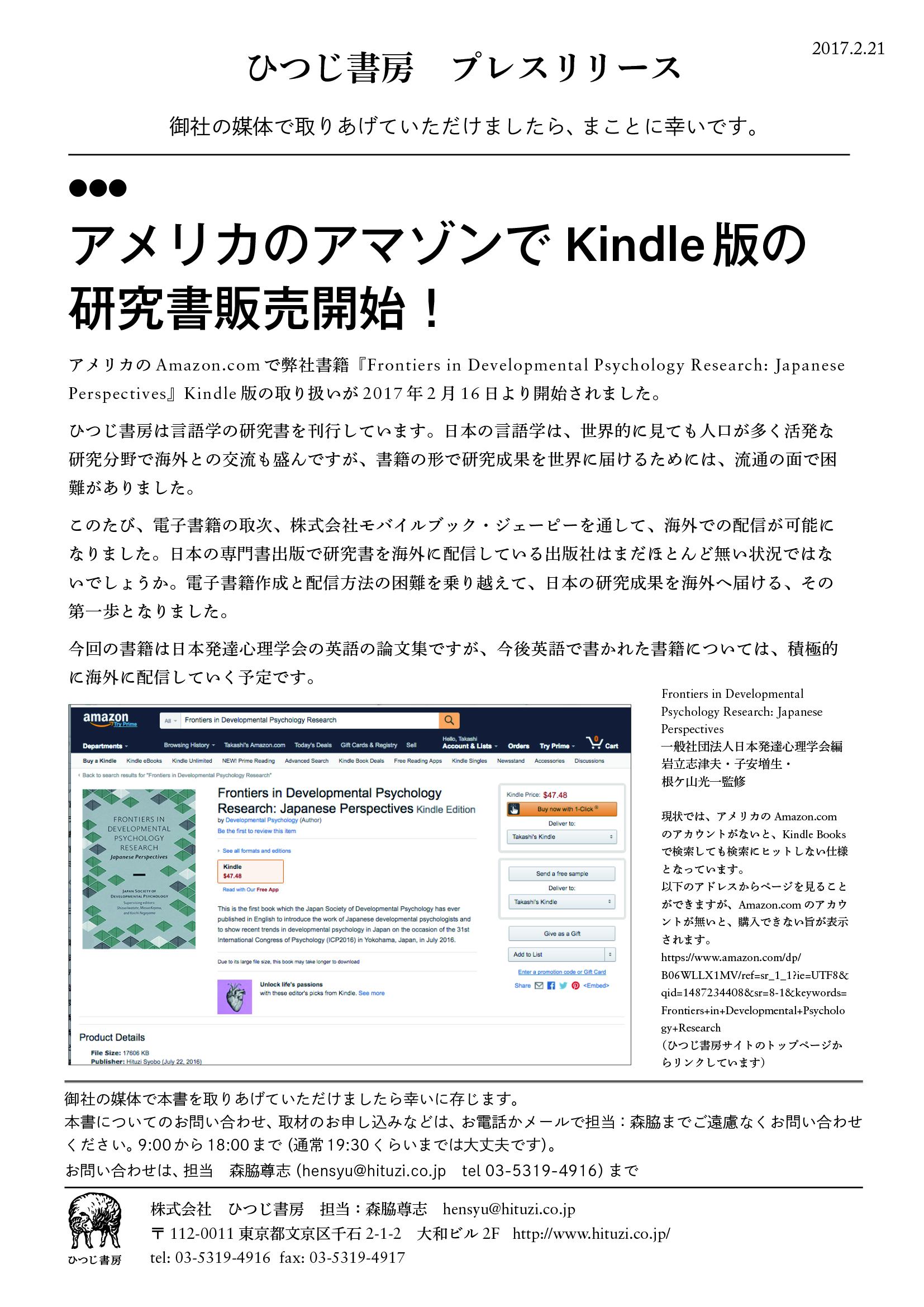
プレスリリースを作成をしました。アメリカのアマゾンでKindle版の書籍を販売しています。英語で書かれた研究書を海外で販売していきます。
プレスリリース(PDF)
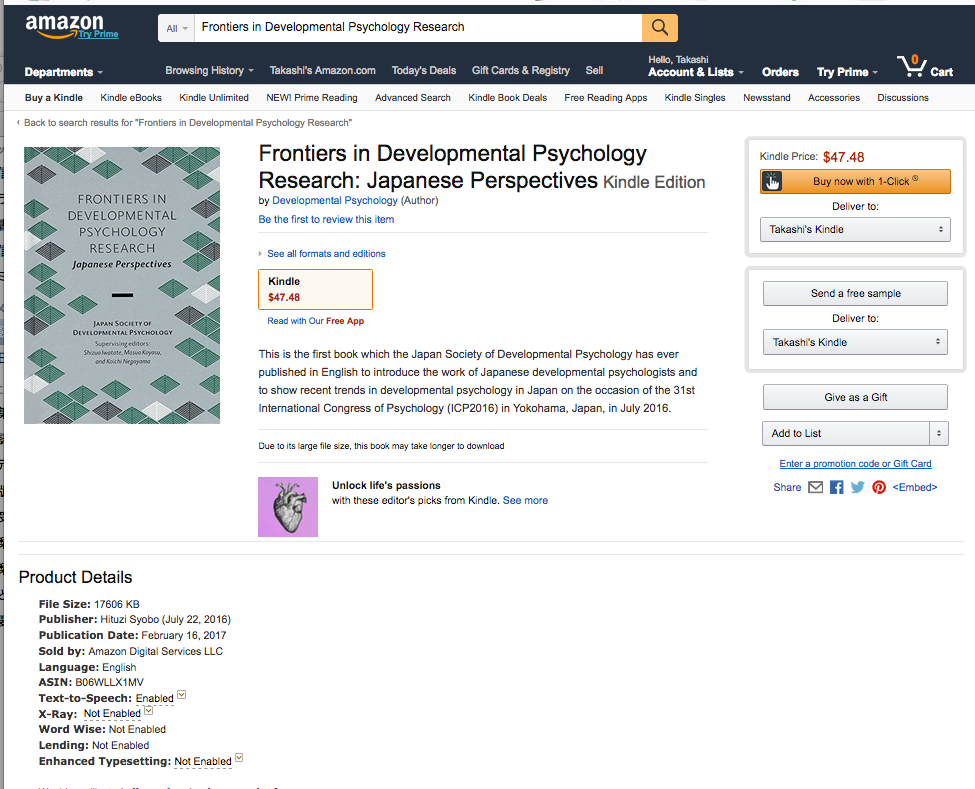
アメリカのAmazon.comでKindle版の『Frontiers in Developmental Psychology Research: Japanese Perspectives』の取り扱いが開始されました。海外で日本の研究書を販売していくはじめの一歩となります。
なお、本書は日本のAmazon.co.jpではすでにKindle版の販売がされています。
Amazon.comでは、日本のアマゾンとは別に、アメリカのAmazon.comのアカウントが無いと、Kindle Booksで検索しても検索結果にヒットしません。また、以下のアドレスからページを見ることができますが、アカウントが無いと「This title is not currently available for purchase」という表示になります。
Amazon.com Kindle Books Frontiers in Developmental Psychology Research: Japanese Perspectives

小石川植物園で梅見をしました。

平塚徹編『自由間接話法とは何か』を刊行しました。
自由間接話法は、文学においても、言語学においても、多大な関心を引いているテーマである。本書は、さまざまな分野の研究者がそれぞれの立場から自由間接話法について論じ、その諸相を立体的に捉えるものである。収録論文は、平塚徹「自由間接話法とは何か」、赤羽研三「小説における自由間接話法」、阿部宏「作中世界からの声―疑似発話行為と自由間接話法」、三瓶裕文「心的視点性と体験話法の機能について―ドイツ語の場合」。
執筆者:赤羽研三・阿部宏・三瓶裕文・平塚徹
平塚徹編『自由間接話法とは何か 文学と言語学のクロスロード』詳細
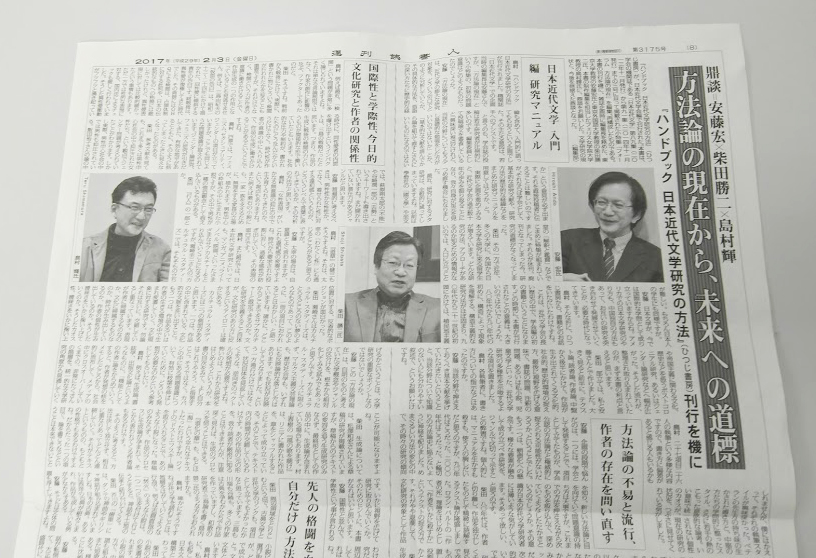
「週刊読書人」2017年2月3日号に、「鼎談=安藤宏×柴田勝二×島村輝「方法論の現在から、未来への道標」『ハンドブック 日本近代文学研究の方法』(ひつじ書房)刊行を機に」が掲載されました。週刊読書人のウェブサイトからも読むことができます。ぜひご覧ください。
方法論の現在から、未来への道標
『ハンドブック 日本近代文学研究の方法』(ひつじ書房)を機に
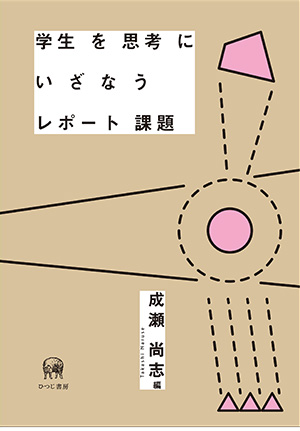
大学生協の新刊人文書ランキングで『学生を思考にいざなうレポート課題』が第2位に入っています。
大学生協書籍インターネットサービス 新刊ランキング 人文書
成瀬尚志編『学生を思考にいざなうレポート課題』詳細
ひつじ書房は、社員を募集しています。詳細は以下をご覧ください。
2017年春卒と既卒の方へ 正社員の募集・求人・採用(編集+出版業務)ページ

森壮也・佐々木倫子編『手話を言語と言うのなら』の重版が出来上がりました。
手話の公認は世界的な潮流であり、現在日本でも「手話言語法」制定への動きが活発化している。しかし、日本での法制化の状況は、むしろ日本手話の危機言語化につながるものと危惧されている。「手話は言語」と声高に叫ばれるわりには、世界の他国と異なって「言語」であることの意味が認識されていない。ろう者と日本語話者が、「手話が言語と言うのなら」何が考えられるべきかを、多方面から問題提起するブックレット。
執筆者:森壮也、赤堀仁美、岡典栄、杉本篤史、戸田康之、森田明、佐々木倫子、秋山なみ、玉田さとみ、高橋喜美重、木村晴美
森壮也・佐々木倫子編『手話を言語と言うのなら』詳細
・週に数日働ける方
・仕事内容は編集補助全般(例えば参考文献や注のチェックなど)
・詳細はメールにてお問い合わせください(kyujinアットマークhituzi.co.jp )
Tweet
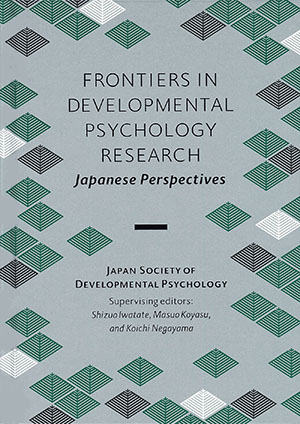
一般社団法人日本発達心理学会編『Frontiers in Developmental Psychology Research Japanese Perspectives』Kindle版
『Frontiers in Developmental Psychology Research Japanese Perspectives』詳細
本年もよろしくお願い申し上げます。

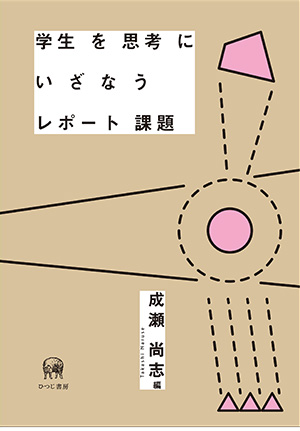
成瀬尚志編『学生を思考にいざなうレポート課題』を刊行しました。
どのように工夫すれば学生が頭を使ってレポート課題に取り組むのか?これまで理論的には問われてこなかったこの問いに、「レポート論題」、「授業設計」、「評価」の各観点から答える渾身の書。特に「剽窃が困難となる論題」についての分析は、これまでのレポート課題のあり方を根本から問い直す。
執筆者名:井頭昌彦、石井英真、河野哲也、片山悠樹、笠木雅史、児島功和、崎山直樹、髙橋亮介、成瀬尚志
成瀬尚志編『学生を思考にいざなうレポート課題』詳細

青木博史・小柳智一・高山善行編『日本語文法史研究 3』を刊行しました。
本書は、日本語文法の歴史的研究を標榜する、隔年刊行の論文集の第3号である。研究手法や時代、テーマを問わず、若手から中堅、ベテランまで、幅広い研究者の交流の場となっている。研究論文10本に加え、テーマ解説、文法史の名著、文法史研究文献目録、といった様々な内容が盛り込まれた、当該分野の最先端の成果を示す一書である。
執筆者:青木博史、一色舞子、小木曽智信、小柳智一、近藤要司、坂井美日、高山善行、竹内史郎、ハイコ・ナロック、藤井俊博、藤本真理子、宮内佐夜香、宮地朝子
青木博史・小柳智一・高山善行編『日本語文法史研究 3』詳細
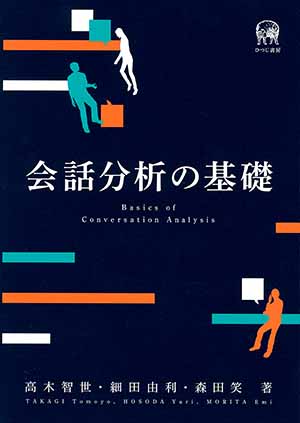
高木智世・細田由利・森田笑著『会話分析の基礎』を刊行しました。
会話分析は、日常会話の詳細な分析により、社会的な相互行為の秩序を明らかにすることを目的として社会学から生まれた学問分野である。近年その研究方法を言語学や言語教育学の分野で用いようとする試みも増えている。本書は、そうした状況を踏まえて、相互行為としての会話を分析する際の視点や会話分析が目指すものをわかりやすく解説し、豊富な事例と各章末の課題を通して会話分析の基礎を学べるようにした入門書である。
高木智世・細田由利・森田笑著『会話分析の基礎』詳細
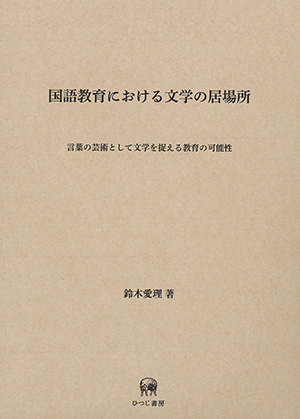
鈴木愛理著『国語教育における文学の居場所 言葉の芸術として文学を捉える教育の可能性』を刊行しました。
文学が「教材として」読まれることによって、読み落とされることがあるのではないか――言葉の芸術として文学を捉える教育を探ることは、 文学という芸術がひとの生にどのような役割を果たすのかを考えながら文学教育を考えるということである。これまでの文学教育の理論と実践を跡づけながら、言葉の芸術として文学を捉える文学教育の独自性、および現代における文学教育の存在意義を理論的に考察するとともに、国語科教育における文学の居場所を探る一冊。
鈴木愛理著『国語教育における文学の居場所 言葉の芸術として文学を捉える教育の可能性』詳細
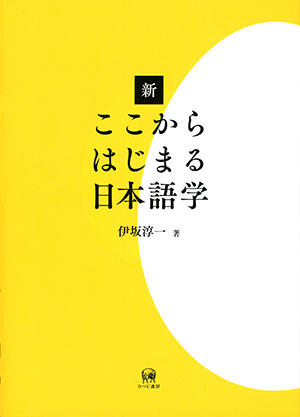
伊坂淳一著『新ここからはじまる日本語学』を刊行しました。
入門テキストとして好評を博した1997年初版を大幅改訂。近年の言語資料を追加し、内容を全面的に改めた。現代の生きた言葉遣いを出発点に、日本語の仕組みを考える。
伊坂淳一著『新ここからはじまる日本語学』詳細

森壮也・佐々木倫子編『手話を言語と言うのなら』を刊行しました。
手話の公認は世界的な潮流であり、現在日本でも「手話言語法」制定への動きが活発化している。しかし、日本での法制化の状況は、むしろ日本手話の危機言語化につながるものと危惧されている。「手話は言語」と声高に叫ばれるわりには、世界の他国と異なって「言語」であることの意味が認識されていない。ろう者と日本語話者が、「手話が言語と言うのなら」何が考えられるべきかを、多方面から問題提起するブックレット。
執筆者:森壮也、赤堀仁美、岡典栄、杉本篤史、戸田康之、森田明、佐々木倫子、秋山なみ、玉田さとみ、高橋喜美重、木村晴美
森壮也・佐々木倫子編『手話を言語と言うのなら』詳細
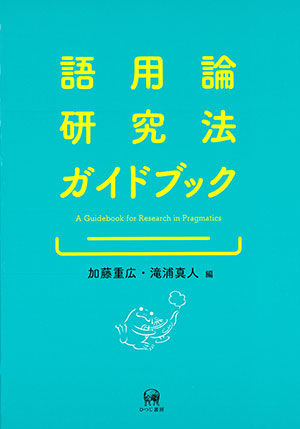
加藤重広・滝浦真人編『語用論研究法ガイドブック』を刊行しました。
一見とっつきやすいかに見える語用論研究の鍵は「方法」にある。 本書は、理論・枠組み・方法論などの基礎を正しく理解して研究を進めるためのガイドブックとして企画された。総説、ダイクシス、社会語用論、対照語用論、実験語用論、 会話分析、応用語用論、統語語用論、語用論調査法にわたり、第一線の専門家が詳しく実践的に解説する必携の一冊!
執筆者:澤田淳、椎名美智、堀江薫、松井智子、清水崇文、熊谷智子、木山幸子、加藤重広、滝浦真人
加藤重広・滝浦真人編『語用論研究法ガイドブック』詳細

日本近代文学会編『ハンドブック 日本近代文学研究の方法』を刊行しました。
日本近代文学会の学会誌「日本近代文学」誌上で行われた「フォーラム 方法論の現在」の書籍化。これまで文学研究で積み重ねられてきた研究方法を若い世代に伝えるため、日本近代文学会が総力を挙げて振り返り明らかにする。研究の営みの中から生まれるために共有されにくい研究方法について、成り立ちの経緯やその検証、展望を明示的に示すことで、将来の研究者の育成、文学研究発展の礎となる書を目指す。
日本近代文学会編『ハンドブック 日本近代文学研究の方法』詳細

青木博史著 『日本語歴史統語論序説』を刊行しました。
本書は、日本語史上における重要な文法現象について、統語論的観点からのアプローチを意識的に用いて考察を行なったものである。伝統と革新、理論と記述、一般性と個別性、これらのバランスをとりながら、言語の動的な歴史(ストーリー)を描くことを目的としている。どのような説明が、日本語における文法変化を必要十分な形で説明したことになるのか。歴史叙述の窮極の課題の解決を目指した、歴史統語論的研究の序説である。
青木博史著 『日本語歴史統語論序説』詳細
布尾勝一郎著 『迷走する外国人看護・介護人材の受け入れ』を刊行しました。
少子高齢化を背景に、看護・介護人材の受け入れの必要性が叫ばれている。本書は、経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士候補者の受け入れを題材に、日本における日本語教育政策や言語文化観の問題点について論じた書である。国会や厚生労働省での議論や新聞報道の分析を通して、候補者受け入れがいかに場当たり的であったか、日本語学習やイスラム教についていかに粗雑な議論が行われてきたかを浮き彫りにする。今後の外国人受け入れについての示唆に富む1冊。
布尾勝一郎著『迷走する外国人看護・介護人材の受け入れ』詳細
篠原進・中嶋隆編 『ことばの魔術師西鶴 矢数俳諧再考』を刊行しました。
江戸前期に流行した、一昼夜に詠みこめる句数を競う「矢数俳諧」を中心に、「ことばの魔術師」西鶴に迫った一書。西鶴の「速吟」を可能にした談林俳諧の論理や技法、あるいは貞門俳諧や元禄初期俳諧、蕉風俳諧を視野に置いた西鶴俳諧の再検討等々、俳諧史的観点からの論考や、元来異なった創作方法を採る浮世草子と俳諧がどのように架橋されたのかという小説史的観点からの論考など、多様なアプローチが展開する。
執筆者:デイヴィッド・アサートン、有働裕、大木京子、大野鵠士、尾崎千佳、佐藤勝明、篠原進、染谷智幸、塩崎俊彦、ダニエル・ストリューヴ、中嶋隆、永田英理、早川由美、深沢眞二、森田雅也
篠原進・中嶋隆編『ことばの魔術師西鶴 矢数俳諧再考』詳細
斎藤兆史・鳥飼玖美子・大津由紀雄・江利川春雄・野村昌司 著 鼎談 養老孟司×鳥飼玖美子×斎藤兆史 『「グローバル人材育成」の英語教育を問う』を刊行しました。
現在の日本の英語教育行政は、「グローバル化」を旗印に暴走を続けている。「グローバル化」のために英語教育を強化するとのスローガンは俗耳に入りやすいが、具体的な政策には、言語学、異文化コミュニケーション論、教育学、言語習得論をはじめ、さまざまな学理に照らして理不尽と思われる点が多い。本書は、このような問題意識の下で行われた公開講座の講演を、適宜修正を施しつつ、その臨場感のままに書き起したものである。養老孟司、鳥飼玖美子、斎藤兆史による白熱の鼎談も収録。
斎藤兆史・鳥飼玖美子・大津由紀雄・江利川春雄・野村昌司 著 鼎談 養老孟司×鳥飼玖美子×斎藤兆史 『「グローバル人材育成」の英語教育を問う』詳細
早津恵美子著『現代日本語の使役文』を刊行しました。
現代日本語の「使役」という文法現象の性質の解明にあたり、本書では「使役文」の性質と「使役動詞」の性質とを意識的に分けつつ相互の関係を探ることにつとめた。それによって使役文の全体像を捉えることを目指し、使役文の意味・文法構造の種々相、使役文のヴォイス性(原動文・使役文・受身文の関係)、使役動詞の動詞性およびその変容(語彙的意味の一単位性、他動詞化、後置詞化、判断助辞化)等について実証的に論じた。
早津恵美子著『現代日本語の使役文』詳細
大木一夫・多門靖容編『日本語史叙述の方法』を刊行しました。
日本語史はいかに叙述されるべきか。これまでの日本語史研究は、日本語の歴史を歴史として叙述することに、あまり自覚的ではなかった。しかし、それが歴史的な研究である以上、そこには、歴史としての何らかの叙述の方法があるだろう。本書は、日本語史の叙述方法についての理論や考え方を提示し、また、具体的な叙述の実践を試みる。執筆者:青木博史、乾善彦、大木一夫、小野正弘、小柳智一、高山知明、多門靖容、鳴海伸一、肥爪周二、福島直恭、矢島正浩、矢田勉、山本真吾
大木一夫・多門靖容編『日本語史叙述の方法』詳細
工藤浩著『副詞と文』を刊行しました。
《副詞》の 機能システムと 《文》の 叙法形式との 相互関係の 分析を めざした、論文の 集成である。山田文法と 時枝文法とに 理論的な ひずみ(非両立的な 類縁関係)が あった 「副詞」の 構文的な 諸機能は、「かざし」(冨士谷成章) または 《小詞(=制限詞)》の 機能的な システムと みる ように かわり、それが 文の 叙法階層と、《様相限定・陳述呼応》の 二重の 構文関係を もつに いたる。「みとり図」を 参考に 付した。
工藤浩著『副詞と文』詳細
松本和也編『テクスト分析入門 小説を分析的に読むための実践ガイド』を刊行しました。
小説を「分析的」に読むためには、どのような学習やトレーニングが必要だろうか。ストーリー読解やテーマ理解だけでは拾いきれない、小説に固有の仕掛けや技術は、いかなるアプローチによって明るみに出せるのか。本書は、ナラトロジー(物語論)を中心とした方法を採用することで、テクスト分析を実践的に学ぶための入門書である。
執筆者:松本和也、八木君人、友田義行、水川敬章、乾英治郎、小谷瑛輔、平浩一、小林洋介、井原あや、斎藤理生
松本和也編『テクスト分析入門 小説を分析的に読むための実践ガイド』詳細

新刊・近刊のご案内の冊子『未発ジュニア版』を発送しました。
『未発ジュニア版』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いします。
中森誉之著『Foreign Language Learning without Vision: Sound Perception, Speech Production, and Braille』を刊行しました。
外国語の認知と学習過程で、聴覚・視覚・触覚はどのような働きを担うのか。多感覚処理に注目をして、外国語理解と表出のメカニズムを一望する。視覚障害者には切実に必要とされる、英語音声学習指導理論構築に向けた国指定研究の成果である。音楽と言語の知覚、英語音声の記述と学習困難性、調音コントロール、視覚と空間認知、触覚と点字、認知と言語の発達、音声チャンクと外国語学習、視覚特別支援学校での調査結果を論じる。
中森誉之著『Foreign Language Learning without Vision: Sound Perception, Speech Production, and Braille 』詳細
堀正広・赤野一郎監修 堀正広編『英語コーパス研究シリーズ 第5巻 コーパスと英語文体』を刊行しました。
英語コーパス学会20周年を記念した網羅的なコーパス研究シリーズ「英語コーパス研究」第5巻。本巻は、コーパスに基づく英語文体研究の歴史と現状を概観した後、具体的な事例研究として、写本、著者推定、レキシコン作成、文学作品の文体、スピーチの文体、英国の新聞の文体等の言語・文体研究へのコーパスの応用例を提示した論文集である。
堀正広・赤野一郎監修 堀正広編『英語コーパス研究シリーズ 第5巻 コーパスと英語文体』詳細
小島剛一著『トルコのもう一つの顔・補遺編』を刊行しました。
1988年にヒマラヤの麓でペンの走る速さで書き上げた草稿は、新書一冊に収めるには長過ぎ、かつ激昂する文言で満ちている、と評された。穏当な表現に改めて全体を短くするという条件を呑んで1991年2月に『トルコのもう一つの顔』が世に出た。折しも遅まきながらトルコに多数の非トルコ民族がいることの報道が日本でも始まった時期である。草稿から割愛した部分が、著者の胸でくすぶり続け、25年の時を経てこの『補遺編』にて日の目を見ることになった。
小島剛一著『トルコのもう一つの顔・補遺編』詳細
日本方言研究会編『方言の研究 2』を刊行しました。
〈講演録〉日本方言研究会の50年をふり返る 佐藤亮一/方言研究の研究動向と隣接他分野との接点 日高水穗/計量方言学の研究動向 井上史雄/社会方言学の研究動向 真田信治/記述方言学の研究動向 木部暢子/方言地理学の研究動向 大西拓一郎/対照方言学的研究のこれまでとこれから 小西いずみ/文献国語史の研究動向と方言研究の接点 青木博史/社会言語学の研究動向と方言研究との接点 松本和子/民俗学の研究動向と方言研究との接点 島村恭則/方言談話におけるあいづちの出現傾向 舩木礼子/シティズンシップ教育としての方言教育 札埜和男/創立50周年記念企画 中井精一
日本方言研究会編『方言の研究 2』詳細
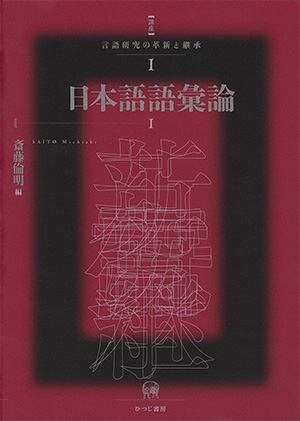
斎藤倫明編『日本語語彙論 I』を刊行しました。
言語研究における語彙論の成立根拠やその有する意味合い、研究の広がりや課題を概観する。「日本語語彙論I」では、語彙論の内部に関するテーマを扱う。目次:第1章 語彙総論(斎藤倫明)、第2章 語彙体系(久島茂)、第3章 語彙調査(靏岡昭夫)、第4章 語彙の量的構成(山崎誠)、第5章 語形(石井正彦)、第6章 語の意味論(山田進)、第7章 語構成(山下喜代)、第8章 語種(田中牧郎)、第9章 位相と位相差(田中章夫)
斎藤倫明編『日本語語彙論 I』詳細

斎藤倫明編『日本語語彙論 II』を刊行しました。
言語研究における語彙論の成立根拠やその有する意味合い、研究の広がりや課題を概観する。「日本語語彙論II」では、語彙論と他分野との関わりをテーマとして扱う。第1章 語彙と文字・表記(田島優)、第2章 語彙と文法(村木新次郎)、第3章 語彙と文章(甲田直美)、第4章 第二言語としての日本語の語彙習得と学習(秋元美晴)、第5章 語彙と文化(前田富祺)、第6章 新語・流行語(橋本行洋)、第7章 方言の語彙(高橋顕志)、第8章 語彙史(小野正弘)
斎藤倫明編『日本語語彙論 II』詳細
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 16』を刊行しました。
現代中国の文学作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第16号。【脚本】彭鉄森「オイラの名前は馬翠花」(女の名前をつけられた青年の物語)、【小説】陳応松「太平―神農架の犬の物語」(出稼ぎに出た主人を追う犬の話)などを掲載。今号には歌劇の脚本を収録している他、『中国現代文学』第1〜16号までの翻訳作品目録も掲載する。
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 16』詳細

山梨正明他編『認知言語学論考 No.13』を刊行しました。
認知言語学の最先端の論文を継続的に掲載するシリーズ第13巻。国内外の第一線の研究者の論文を掲載し、多岐にわたる認知言語学や関連する言語学の最新研究成果が交流する。
山梨正明他編『認知言語学論考 No.13』詳細
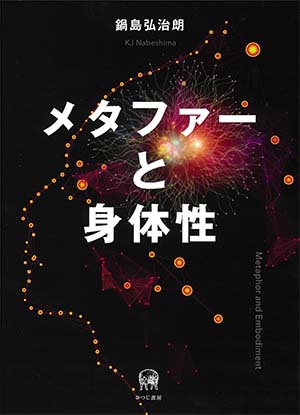
鍋島弘治朗著『メタファーと身体性』を刊行しました。
日本における認知メタファー理論研究の第一人者による最新作。認知科学の重要なキーワードになりつつある “身体性” を、アフォーダンス、ミラーニューロンなどを含めて脳科学の研究成果を紹介しながら概説。さらにアリストテレスからレイコフに至る理論を鳥瞰し、身体性メタファー理論の原理を提示する。メタファーとシミリ、メタファーの実験的パラダイムの紹介、進化との関連、コーパスを利用したメタファー研究、政治、マーケティングなど、幅広い研究動向にも切り込んだ好書。
鍋島弘治朗著『メタファーと身体性』詳細
『トルコのもう一つの顔』(中公新書)の著者、小島剛一さんがラズ語の辞書の刊行を計画しています。賛同者を募る講演会を開催しますので、ふるってご参加ください。
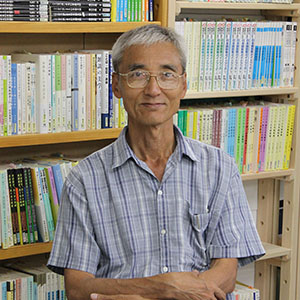
■日時……2016年9月21日(水) 18:30開場 19:00開演
■講演時間…1時間半程度を予定
■会場……文京シビックホール3階 会議室1
(丸ノ内線・南北線 「後楽園」駅より徒歩2分)
■参加費…1,000
■申込方法…事前申込 または 当日受付
概要トルコの政情を読み解く鍵はいくつもあるが、最大のものは複雑な言語事情だ。オスマンル帝国の廃墟の上に成立したトルコ共和国は、当然、大帝国の多言語・多民族性を受け継いでいる。にもかかわらず、建国に際して「単一民族国家」という虚構を国是としたのがトルコ共和国の悲劇だ。1991年に『トルコのもう一つの顔』でその実状を明らかにしたが、その際新書一冊の分量に収めるため、草稿の随所を割愛した。また、当時の編集長に過激と評された表現を穏当なものに置き換えた。あれから25年。草稿のうち1991年には伏せた部分に焦点を当てたのが『トルコのもう一つの顔・補遺編』である。前述のような事情を抱えたトルコで最近起こった「クーデター未遂事件」は、誰が何のために起こしたのか。事件の真相を読み解こうとした時、政府が病的に恐れる少数民族諸言語の実状を記録に残す作業の重要性が浮かび上がる。小島剛一はウェブ上にラズ語辞典を公開しているが、ウェブ上の辞書だけでなく、並行して紙の辞典を作る必要がある。小島は、そのための資金援助を公に募っている。 |
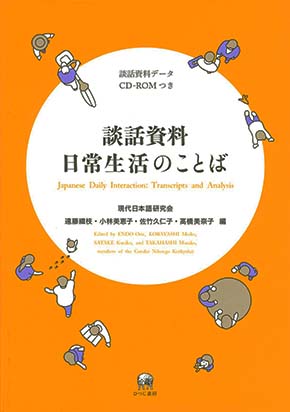
現代日本語研究会 遠藤織枝・小林美恵子・佐竹久仁子・髙橋美奈子編『談話資料 日常生活のことば』を刊行しました。
『女性のことば・職場編』『男性のことば・職場編』につぐ、待望の第3の談話資料が完成した。家族・友人・職場などでの日常の自然談話を忠実に文字化した資料は、前2書と同様、現代日本語の話しことばを研究する研究者・大学院生に大きく貢献できると考える。談話資料とともに、この資料に基づいて研究分析した13編の論文を収めている。執筆者:遠藤織枝、小林美恵子、斎藤理香、佐々木恵理、佐竹久仁子、孫琦、髙橋美奈子、高宮優美、中島悦子、本田明子、牧野由紀子、増田祥子、谷部弘子★談話資料データCD-ROM付
現代日本語研究会 遠藤織枝・小林美恵子・佐竹久仁子・髙橋美奈子編『談話資料 日常生活のことば』詳細

斎藤倫明著『語構成の文法的側面についての研究』を刊行しました。
本書は、「語構成の文法的側面」に関し、語構成内部の問題(語構成要素の分類と品詞分類との異同、語構成要素間の関係とシンタックスとの異同)と語構成論と文法論との関わりの問題(語形成・活用・言語単位といった語構成の一側面に従来の文法論がどう向き合ってきたか)という観点から論点を絞って論じたものである。日本語学における語構成論の立場から、今、文法論との関わりで何を問題にしうるかの一端を提示した書である。
斎藤倫明著『語構成の文法的側面についての研究』詳細


円山拓子著『韓国語citaと北海道方言ラサルと日本語ラレルの研究』を刊行しました。
受身・非意図・可能・状態変化等の用法を持つ韓国語の助動詞citaの多義を支えるメカニズムについて考察し、スキーマ的意味と文法的特徴の相互作用によって、citaの多義性が成り立っていることを論じる。また、citaと同様に1つの形態でアスペクト・ヴォイス・モダリティにまたがる意味を表す日本語ラレル、北海道方言ラサルとの対照分析をおこない、3つの形式の共通点・相違点を意味地図によって提示する。
円山拓子著『韓国語citaと北海道方言ラサルと日本語ラレルの研究』詳細
ひつじ書房は、社員を募集しています。出版に関わる業務全般。仕事内容は、商品管理から編集までを含みます。経験者は優遇しますが、未経験者でも、一から教えます。30歳くらいまでの方を探しています。
正社員あるいは2年間の契約社員(勤務開始時期は2016年10月ごろ)。試用期間あり。契約社員から正社員登用の可能性もあり。
*勤務開始時期については、ご相談に応じます。
詳細は以下をご覧ください。
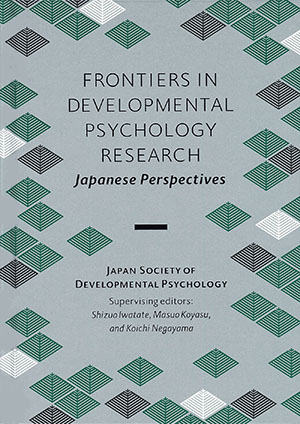
一般社団法人日本発達心理学会編『Frontiers in Developmental Psychology Research Japanese Perspectives』を刊行しました。
一般社団法人日本発達心理学会が、2016年7月開催の国際心理学会第31回横浜大会(ICP2016 Yokohama)に向けて、わが国の発達心理学のこれまでの成果と現状を世界に問うために編集・刊行する英文書籍である。発達心理学の各領域での日本の研究を概観し、先端的でオリジナルな発達研究の広範な成果を報告する。
執筆者:岩立志津夫、上村佳世子、岡林秀樹、柿沼美紀、梶川祥世、柏木惠子、子安増生、酒井厚、菅原ますみ、千住淳、辻晶、外山紀子、中澤潤、仲真紀子、中邑啓子、根ケ山光一、能智正博、針生悦子、藤村宣之、松𥔎敦子、松本聡子、皆川泰代、山本淳一
一般社団法人日本発達心理学会編『Frontiers in Developmental Psychology Research Japanese Perspectives』詳細
ひつじ書房は、社員を募集することにいたしました。出版に関わる業務全般。仕事内容は、商品管理から編集までを含みます。経験者は優遇しますが、未経験者でも、一から教えます。30歳くらいまでの方を探しています。
2年間の契約社員(勤務開始は2016年夏)。試用期間あり。正社員登用の可能性もあり。
詳細は以下をご覧ください。
6/18付「東京新聞」夕刊の「大波小波」で、『太宰治ブームの系譜』(滝口明祥)が紹介されました。
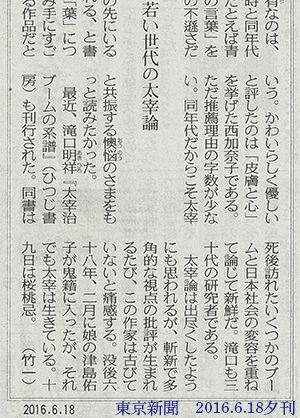
ハワイ大学のクック(峰岸)治子先生による、言語社会化についての講演会を開催いたします。
■日時……2016年6月22日(水) 14:30開場 15:00開演
■会場……文京シビックホール3階 会議室1
(丸ノ内線・南北線 「後楽園」駅より徒歩2分)
■参加費…500円
(極力釣り銭のないよう、ご協力いただけますと幸いです)
概要1980年代アメリカの文化人類学者OchsとSchieffelinにより提唱された言語社会化理論(Language Socialization)は、言語習得を社会化過程の一部と位置づけ、社会的コンテクストのなかでどのように言語習得が行われるかの過程を談話分析により検証するものである。この理論は、エスノグラフィーの伝統を継承し、近年西欧においては第二言語習得研究にも広く応用されている(Zuengler and Cole 2005)。しかし、日本においては、エスノグラフィーに基づく文化人類学関係の研究が盛んでないため、言語社会化理論はまだあまり知られていない。本講演は、言語社会化理論の概略、また特にこの理論に基づく日本語関係の研究を紹介する。最後に、その理論の中核をなす指標(index)の機能を考察する。指標は言語の象徴機能(symbolic function)と異なり、相互行為のなかで周囲のコンテクストを含めることにより、始めて意味をなすものである。故に、コンテクストの変化とともに、指標の社会的意味も変化する。つまり、指標は複数の社会的意味がある。指標がどのコンテクストでどんな社会的意味を帯びるかを習得することがすなわち言語社会化であるとされる。特に『丁寧体』と『普通体』という指標を通してのどのような社会化が見られるかを談話分析により検証する。複数の社会的意味がある指標の『丁寧体』をポライトであると最初から限定せず、会話の参加者がどのような意味で『丁寧体』を使用しているか考察する。このように観点から、日本語学習者が日本語母語話者との会話でどのように、『丁寧体』と『普通体』を習得するか、また、それによってどのような言語社会化が見られるのか研究することができる。日本語学習に関して言語を指標の観点から分析し、言語社会化理論を使うことにより、学習者がある言葉、表現をどの程度習得したかという事実を明らかにするだけでなく、それがどのような社会化につながっているか、第二言語習得研究を広い視野に置くことが可能になる。 |

斎藤兆史著『Style and Creativity Towards a Theory of Creative Stylistics』を刊行しました。
20世紀中期、英文学研究と言語学との専門分化を背景として、逆にその溝を埋める学理として英語文体論が登場した。1980年代以降は、英語・英文学教育をも視野に収めた教育的文体論も登場した。しかしながら、従来の英語文体論は、あくまで既存のテクストを前提とし、それを分析の対象とする点において記述的であった。本書は、従来の文体論の枠組みを整理した上で、ある文学的意匠を出発点として、それをテクストとして実現させるために規範的に機能する新しい創作文体論の理論を提示する。
斎藤兆史著『Style and Creativity Towards a Theory of Creative Stylistics』詳細
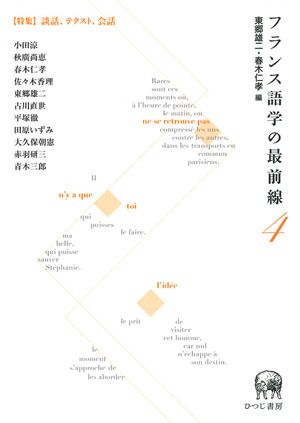
東郷雄二・春木仁孝編『フランス語学の最前線4 【特集】談話、テクスト、会話』を刊行しました。
フランス語学の最新の成果を世に問うシリーズの第4巻。今回、文よりも大きな言語単位である談話・テクストと会話を対象とする研究を特集する。取り上げるテーマは、人称代名詞、従属節、接頭辞re-、外置構文、転位構文、時制、名詞の機能語化、ne … que 構文、アイロニー、文連鎖、自由間接話法など。
執筆者 : 小田涼、秋廣尚恵、春木仁孝、佐々木香理、古川直世、東郷雄二、平塚徹、田原いずみ、大久保朝憲、赤羽研三、青木三郎
東郷雄二・春木仁孝編『フランス語学の最前線4 【特集】談話、テクスト、会話』詳細
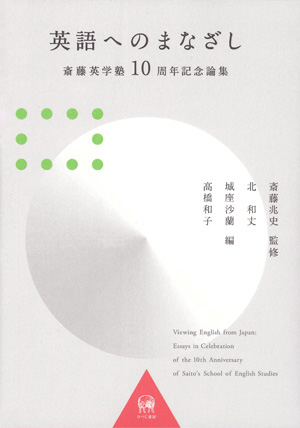
斎藤兆史監修 北和丈・城座沙蘭・髙橋和子編『英語へのまなざし 斎藤英学塾10周年記念論集』を刊行しました。
英語をめぐる研究が過度に高度化・細分化していくなかで、その核たるべき英語そのものへの眼差しを取り戻すべく立ち上がった「斎藤英学塾」が、2005年の発会から10周年を迎えた。英文学・英語学・英語教育といった従来の枠組みにとらわれることのない幅広い視点から、日本における新たな「英学」のあり方を模索する異色の論集。
執筆者:青田庄真、麻生有珠、生谷大地、井田浩之、奥聡一郎、笠原順路、ショルティ沙織、北和丈、久世恭子、小泉有紀子、河内紀彦、斎藤兆史、城座沙蘭、鈴木哲平、髙橋和子、畑アンナマリア知寿江、林田祐紀、早瀬沙織、柾木貴之、森田彰、山内久明、山田雄司、和田あずさ
斎藤兆史監修 北和丈・城座沙蘭・髙橋和子編『英語へのまなざし 斎藤英学塾10周年記念論集』詳細
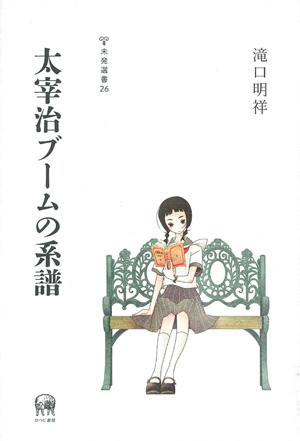
滝口明祥著『太宰治ブームの系譜』を刊行しました。
太宰治が人気作家になったのは、その死後のことだった!? 生前は基本的にマイナーな作家であった太宰は、スキャンダラスな死によって一躍ブームが訪れる。だが、それで人気作家としての地位が確立したわけではなかった。太宰が人気作家となるには、もう幾度かのブームを経なければならなかったのである。-〈太宰治〉という作家イメージの変遷を辿る本書は、それを受容した戦後の日本社会の変貌をも映し出していることだろう。
滝口明祥著『太宰治ブームの系譜』詳細

金智賢著『日韓対照研究によるハとガと無助詞』を刊行しました。
本書は、現代韓国語と日本語の談話における無助詞、及び、それと関連する有形の助詞「eun/neun」「ハ」と「i/ga」「ガ」の語用論的体系を対照的に分析したものである。両言語の自然談話における各助詞類の使い分けの実態を計量的に調査、さらに、質的に対照分析することで、各助詞類の語用論的意味や日韓の類似点及び相違点を明らかにし、韓国語と日本語のそれぞれにおける助詞類の体系を語用論的な枠で再整備することを目指した。
金智賢著『日韓対照研究によるハとガと無助詞』詳細
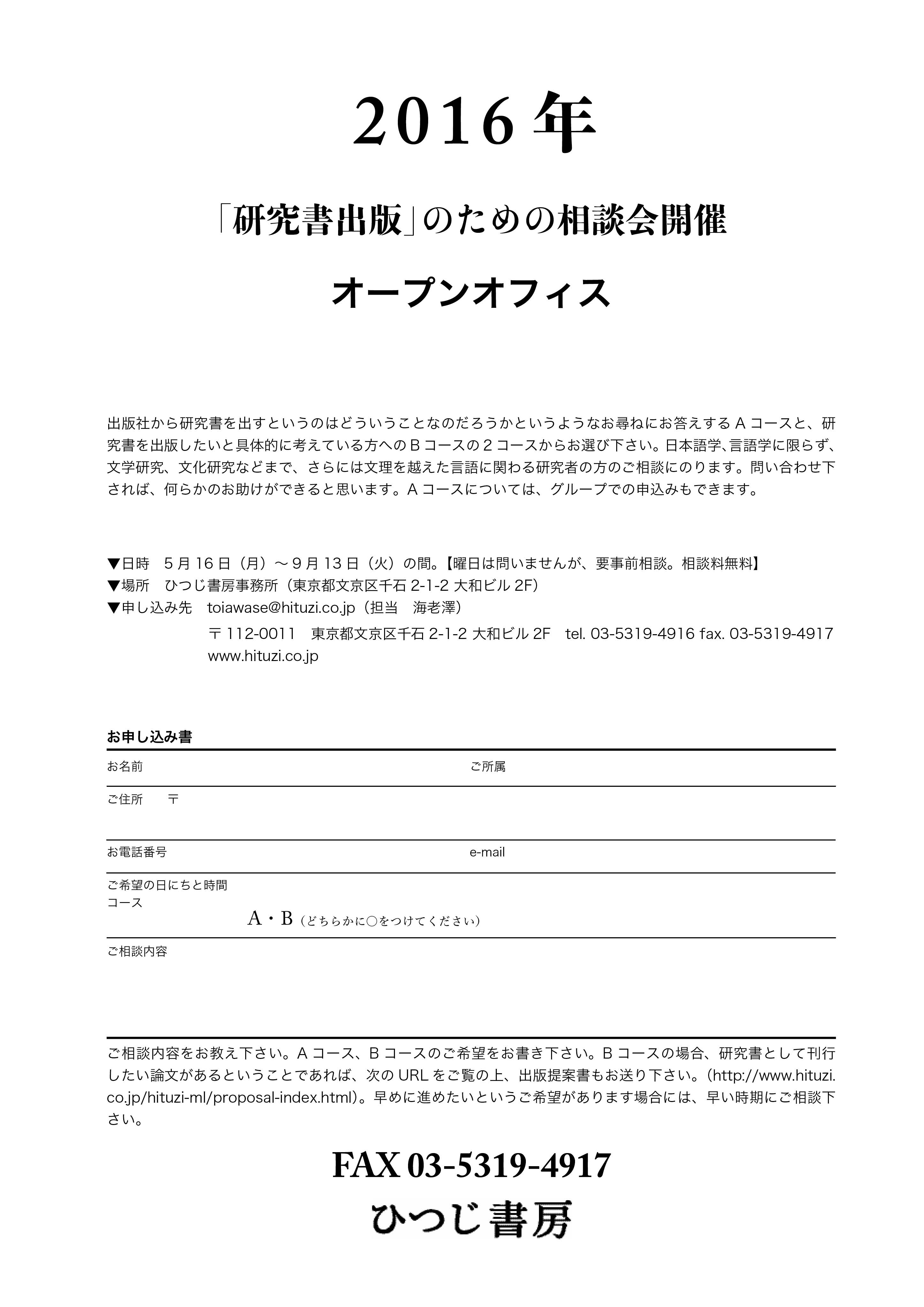
今年も研究書出版についての相談のためのオープンオフィスを行います。
出版社から研究書を出すというのはどうすればいいのか、から、
刊行助成金に応募する方法など、
入り口から実践まで。
日本語学、言語学から、文学研究、文化研究、脳研究、心理学など
文理を問わず、ことばの研究に関わる方のご相談にのります。
オープンオフィス詳細

影山太郎編『レキシコンフォーラム No.7』を刊行しました。
語彙(レキシコン)および語彙的知識に関する研究をまとめた専門ジャーナル第7弾。
今号では6号に引きつづき「日本語レキシコン入門 PART II」と題した特集を掲載する他、チュートリアルとして語彙研究におけるコーパスの検索・活用の仕方に関する解説を掲載する。
執筆者:影山太郎、秋田喜美、小林英樹、伊藤たかね、杉岡洋子、中川秀太、陳奕廷、于一楽、中村渉、Kazuhiko Fukushima、玉岡賀津雄
影山太郎編『レキシコンフォーラム No.7』詳細

中山誠一・Jacob Schnickel・Juergen Bulach・山内博之著『100トピックで学ぶ 実践英語トレーニング』を刊行しました。
「食」「旅行」「美容・健康」などの身近な話題から「宗教」「政治」「テクノロジー」などの抽象的な話題に至るまで、100種類の話題で英語の「話す・聞く」トレーニングを行う。トレーニングの方法としては、並んでいる日本語の単語を逐語訳していくだけで、英文が自然に口から出てくる「瞬間トランスレーション法」という独自の手法を採り入れている。また、それぞれの話題に、難易度の異なる三段階の練習を配置し、CEFRのA1、A2、B1のレベルに対応できる工夫も施されている。
中山誠一・Jacob Schnickel・Juergen Bulach・山内博之著『100トピックで学ぶ 実践英語トレーニング』詳細
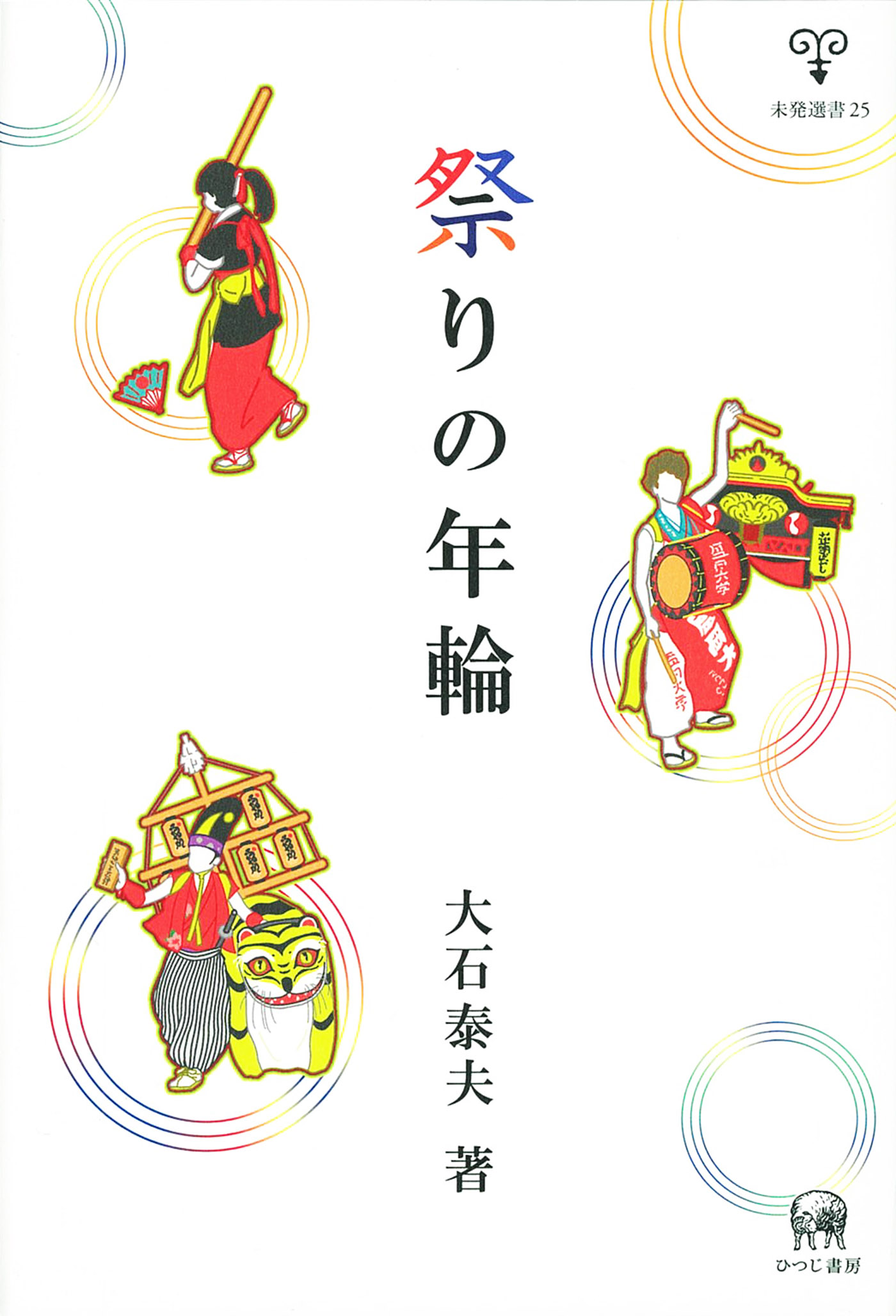
大石泰夫著『祭りの年輪』を刊行しました。
「祭り」は、語源からしてカミを抜きにしては存在しない行為であった。しかし、今日ではこの言葉は実にいろいろな行為に対して用いられており、それぞれが現代社会に重要な意味を持っている。これら現代の祭りには、あたかも〈年輪〉のように、伝承の過程で積み重ねられた行為が存在する。本書は、奈良県の葛城一言主神社の秋祭りや陸中沿岸の虎舞、岩手県のチャグチャグ馬コなどの様々な祭りをとりあげ、現代の視点に立って、その〈年輪〉を解きほぐすものである。
大石泰夫著『祭りの年輪』詳細
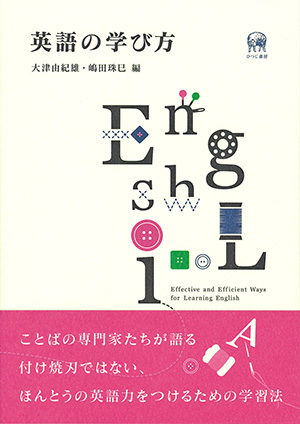
大津由紀雄・嶋田珠巳編『英語の学び方』を刊行しました。
英語が使えるようになりたいと思っている人は多いが、悩みを抱える人もまた多い。本書では、英語学習を効果的かつ効率的に進めるために必要なことを、わかりやすく解説。英語の構造や機能、辞書の利用法のほか、類書ではあまり触れられることのない世界の諸英語やノンバーバル・コミュニケーションの視点も取り入れ、英語を学ぶ秘訣に迫る。
執筆者:大津由紀雄、瀧田健介、高田智子、津留崎毅、小林裕子、嶋田珠巳、原和也、遊佐昇、安井利一
大津由紀雄・嶋田珠巳編『英語の学び方』詳細
2016.4.5

新入社員1名を迎え、入社式をおこないました。
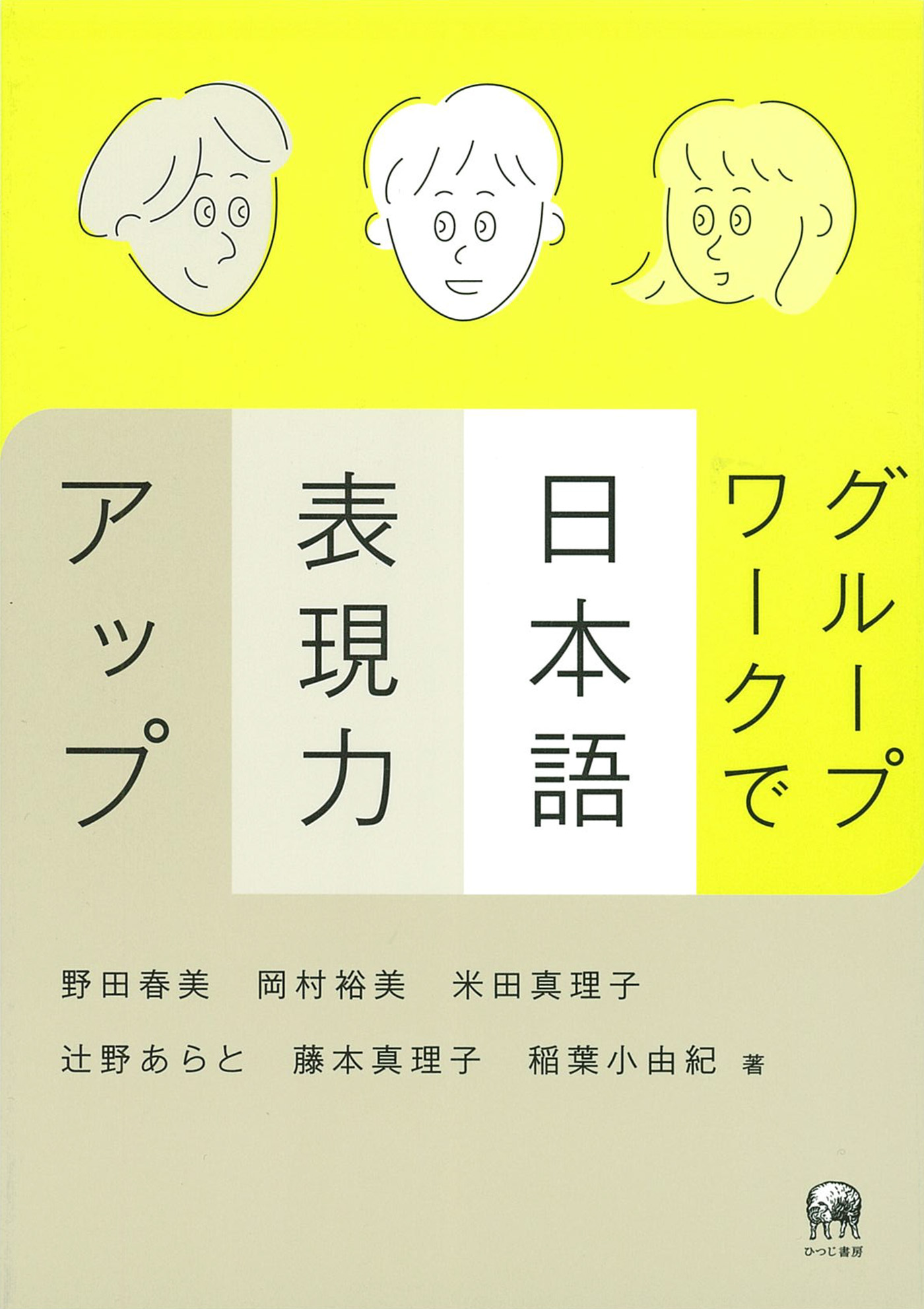
野田春美・岡村裕美・米田真理子・辻野あらと・藤本真理子・稲葉小由紀著『グループワークで日本語表現力アップ』を刊行しました。
グループワークを活用した大学1年生向けの文章表現のテキスト。豊富な課題に取り組むことで情報発信力・コミュニケーション力・アピール力を高める第I部と、アカデミック・ライティングを学びながらレポートを完成させる第II部からなる。文章表現の基本的な知識や姿勢からレポート執筆まで、グループワークで楽しく学び、効果的に習得できる。初年次に必要な内容を盛り込むとともに、将来社会で役立つ力の基礎も身につけさせるテキストである。
野田春美・岡村裕美・米田真理子・辻野あらと・藤本真理子・稲葉小由紀著『グループワークで日本語表現力アップ』詳細

王其莉著『判断のモダリティに関する日中対照研究』を刊行しました。
判断のモダリティを表す日本語と中国語の対訳上対応関係にある形式の意味用法の共通点と相違点、および相違点が生じる要因を明らかにし、判断のモダリティから日本語と中国語の違いを提示する。文法カテゴリーに属する個々の形式に対して対訳上対応関係にある形式の比較を一貫して行い、形式間の違いを明らかにすることで、そこから言語間の違いを見出していく。言語の対照研究に有益な視点を提供する。
王其莉著『判断のモダリティに関する日中対照研究』詳細


小西いずみ著『富山県方言の文法』を刊行しました。
西日本方言域の東端に位置する富山県方言の文法について、臨地調査、筆者自身の内省、談話資料にもとづいて総合的に記述した書。富山県方言の文法特性と形成過程について地理的分布という側面から論じる第Ⅰ部、県の行政・経済の中心地である富山市の方言の文法体系全体を記述する第Ⅱ部、形容詞の副詞化、引用標識、提題・とりたて助詞といった特定の文法事象・文法形式の詳細な記述を行う第Ⅲ部で構成される。
小西いずみ著『富山県方言の文法』詳細

藤井洋子・高梨博子編『コミュニケーションのダイナミズム 自然発話データから』を刊行しました。
シリーズ「文化と言語使用」第1巻。日本語の言語使用にみる「場」の共創、感情表出の指示詞、反応発話、即興的に生まれる遊びや身体化の視点から言語コミュニケーションのメカニズムや多様性、ダイナミズムについての考察を展開する。
執筆者:熊谷智子、菅原和孝、鈴木亮子、高梨博子、成岡恵子、藤井洋子
藤井洋子・高梨博子編『コミュニケーションのダイナミズム 自然発話データから』詳細
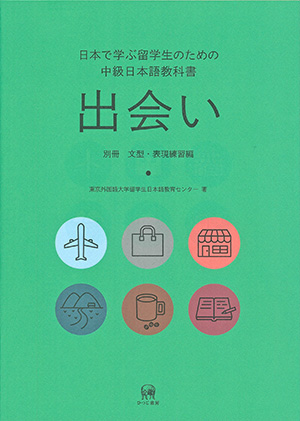
東京外国語大学留学生日本語教育センター著『日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書 出会い【別冊 文型・表現練習編】』を刊行しました。
『出会い【本冊:テーマ学習・タスク活動編】』の別冊。本冊でのテーマ学習とタスク活動に必要な文型や話し言葉の表現・ストラテジーを取り上げ、本冊だけでは明示的に学べない言語知識が補完できるようになっている。本書を使って勉強することにより、本冊での読解活動や聴解活動がスムーズに進み、テーマについての理解が深まるだけでなく、より自然な日本語を用いてタスクを遂行することができるはずである。
東京外国語大学留学生日本語教育センター著『日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書 出会い【別冊 文型・表現練習編】』詳細

片岡喜代子・加藤宏紀編『言語の意味論的二元性と統辞論』を刊行しました。
命題構成要素が節周辺部要素と如何に関わり、周辺要素の働きが節構造に如何に反映されるかを探り、更には文脈における発話としての働きも視野に入れた研究の成果である。時制やアスペクト、格素性の付値、数量詞解釈、否定現象から見た周辺部構造のあり方、そして疑問を含む文末助詞による命題態度表明などを、日本語・英語・中国語・スペイン語を材料に論じる。
執筆者:相原昌彦、上田由紀子、片岡喜代子、加藤宏紀、佐藤裕美、辻子美保子、武内道子
片岡喜代子・加藤宏紀編『言語の意味論的二元性と統辞論』詳細

定延利之著『コミュニケーションへの言語的接近』を刊行しました。
本書は、現代日本語の話しことばの観察を通じて、「コミュニケーションとはお互いを理解するためのメッセージのやりとりだ」といった言語研究に広く深く浸透しているコミュニケーション観の問題点を明らかにし、それに取って代わる新しいコミュニケーション観の姿を追求したものである。言語研究がコミュニケーション研究にどのように貢献でき、コミュニケーション―言語―音声をつなぐ架け橋となり得るかが具体的に示されている。
定延利之著『コミュニケーションへの言語的接近』詳細

山下里香著『在日パキスタン人児童の多言語使用 コードスイッチングとスタイルシフトの研究』を刊行しました。
日本に暮らす移民児童については、日本語教育の文脈で語られがちであるが、本書は移民コミュニティ内でバイリンガル児童がどのような言語使用を行っているのか、社会言語学の観点から記述し分析する。実際の移民児童の自然会話データを扱った初の研究書であり、日本語・ウルドゥー語バイリンガルのパキスタン人児童らの、家と学校の「間」にあるモスク教室という場での言語間・スタイル間の切り替え現象に注目し、言語使用の実態を明らかにした。
山下里香著『在日パキスタン人児童の多言語使用 コードスイッチングとスタイルシフトの研究』詳細

堀田英夫編『法生活空間におけるスペイン語の用法研究』を刊行しました。
スペイン語は、地球上の広大な地域で日常的に使われている。スペインと中南米各国の法は、成り立ちを異にするゆえの多様性と歴史的共通部分がある。本書は、法学者と言語学者の研究グループによる成果として、公的な「法的場面」と地域差や歴史を踏まえた「市民社会領域」の観点から、法にかかわるスペイン語(とカタルーニャ語)の用法を明らかにする。
執筆者:糸魚川美樹、アナ=イサベル・ガルシア、川畑博昭、リディア・サラ=カハ、塚原信行、堀田英夫
堀田英夫編『法生活空間におけるスペイン語の用法研究』詳細

森勇太著『発話行為から見た日本語授受表現の歴史的研究』を刊行しました。
現代日本語では「やる」「くれる」「もらう」などの授受表現があり、これらを適切に運用して聞き手や現話題の人物を待遇することが重要であるが、古代語においては待遇面で同様の機能を持つ敬語の運用が重要であった。本書では、聞き手への言語的な配慮が必要となる、行為指示表現(依頼・命令等)や行為拘束表現(申し出等)といった策動の発話行為に注目し、通時的に授受表現の運用が重要視されていく過程を示す。
森勇太著『発話行為から見た日本語授受表現の歴史的研究』詳細
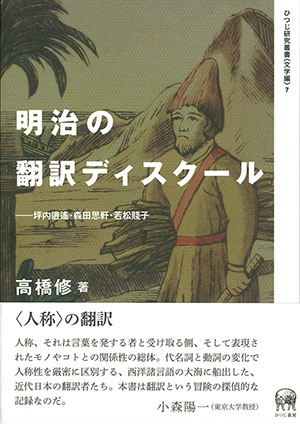
2016年3月3日付けの山梨日日新聞紙上にて、高橋修先生が第24回やまなし文学賞を受賞されたとの発表がされました。
山梨日日新聞web版です。
高橋修先生、おめでとうございます!
新聞に掲載された選評には、「明治文学史における翻訳文の位置と役割に光を当てた」との評価が掲載されています。
『明治の翻訳ディスクール 坪内逍遙・森田思軒・若松賤子』高橋修著
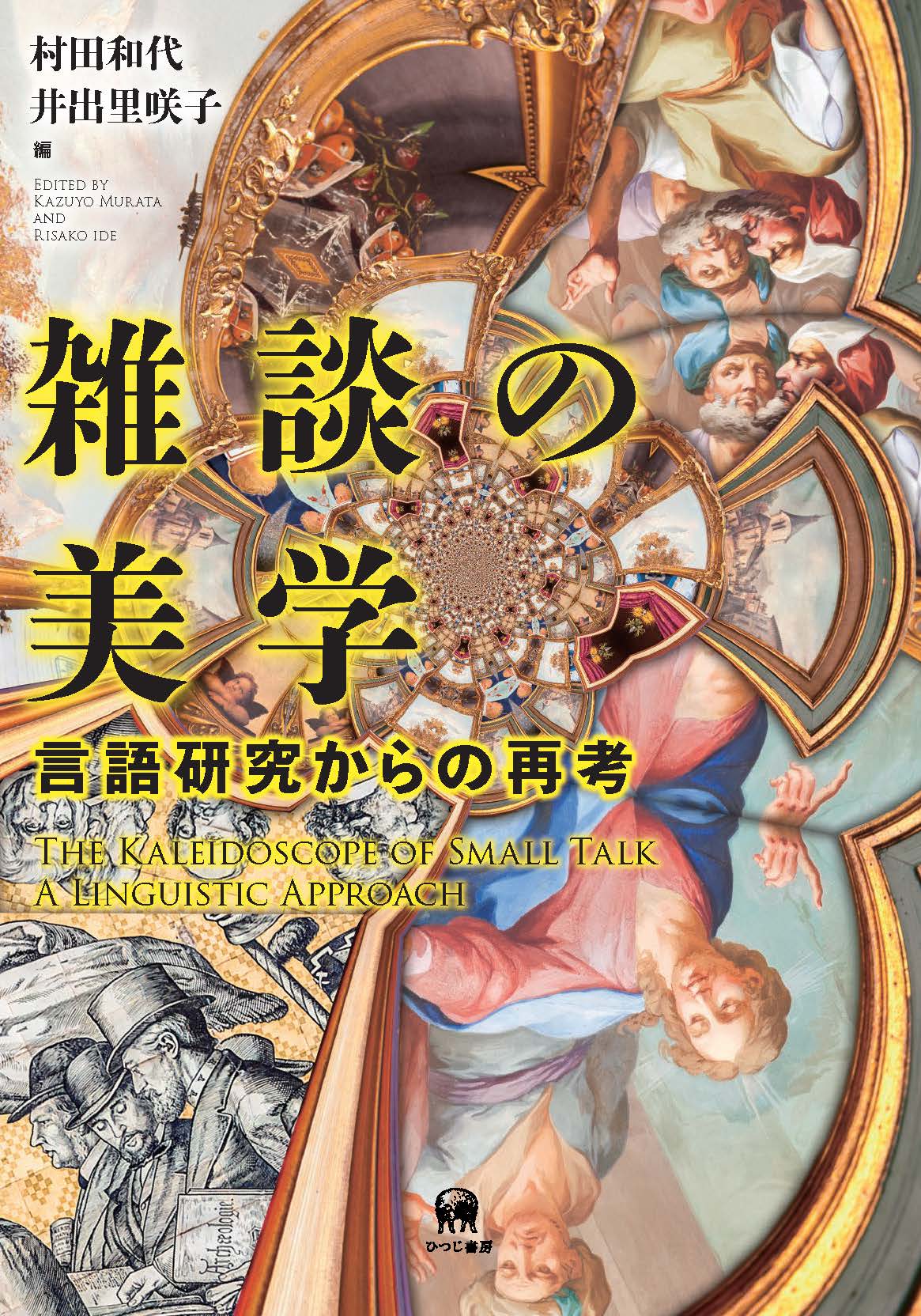
村田和代・井出里咲子編『雑談の美学—言語研究からの再考』を刊行しました。
待望の「雑談」の言語学。雑談とは何か? 雑談とそうでないものの境界線は? 政治家の演説や裁判員評議、鮨屋のカウンターから、登山者仲間内のゴシップ、アフリカ狩猟採集民グイの人々の雑談的おしゃべり、LINEやチャット、手話による雑談的相互行為まで。人間社会を形づくる日常生活のさまざまな雑談の本質に切り込む実証的研究論文13編を収録。
村田和代・井出里咲子編『雑談の美学—言語研究からの再考』詳細

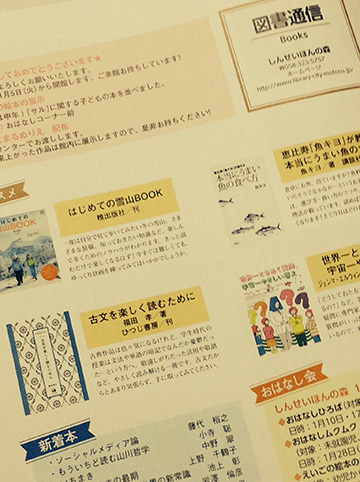
『古文を楽しく読むために』の紹介を、広報もとす(岐阜県本巣市広報誌)2016年1月号の「図書通信」のコーナーに掲載していただきました。
【『古文を楽しく読むために』のご紹介】
「これって本当に日本語?」「意味がわからない」「文法の丸暗記ばっかり」…とかく敬遠されがちな古文の授業。歴史的仮名遣いの読み方からなぜ動詞の活用を覚える必要があるのか、易しい敬語の理解の仕方、平安和歌の読み方まで、古代の人々の心情を感じ取りながら和文の性質にしたがいつつ古文を立体的に面白く読むための数々の“いろは”。古文を楽しく読んでみたい人、生徒に楽しくなる読み方を生徒に教えたい国語教師の方におすすめ。
『古文を楽しく読むために』詳細
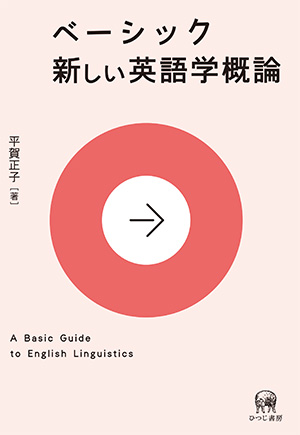
平賀正子著『ベーシック新しい英語学概論』を刊行しました。
異文化コミュニケーションという観点から、今や世界の共通語として認識されるに至った英語について概説する新しいタイプの英語学概論教科書。世界英語の諸相、英語コミュニケーションの特徴、音韻・語彙・文法の仕組みについて、母語英語、国際共通語の両面から、わかりやすく楽しく解説した。各章末の推薦図書・練習問題、事例へのメディア・リンクなどを通して、さらなる学習ができるよう配慮した。
平賀正子著『ベーシック新しい英語学概論』詳細
本年もよろしくお願い申し上げます。

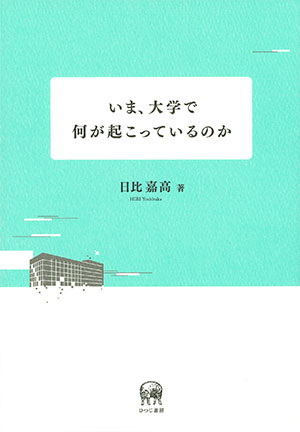
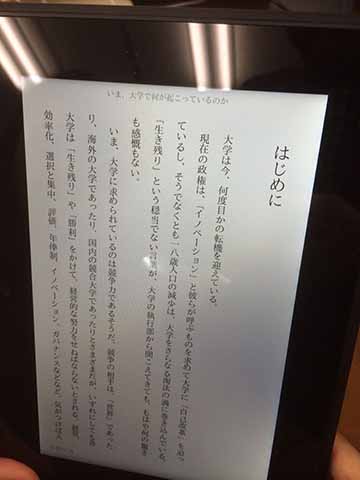 (kindleの画面)
(kindleの画面)
2015年5月に刊行した『いま、大学で何が起こっているのか』(日比嘉高著)を電子書籍化しました。販売は、Amazonと大日本印刷系の運営するhontoです。
財界や政府から国立大学に対し、産業振興を主たる目的として、「競争」をうながし、「自己改革」を求める声が大きくなっている。現在の国立大学が、非効率的な方法で運営されているから、大変革をするというのだ。しかし、その批判は当たっているのだろうか。それは大学が持ってきたはずの知的な活動拠点としての役目を殺してしまい、ひいては多様な創造の芽を育くむという重要な機能を破壊することではないのか。現在の潮流に異を唱え、国立大学のみならず、これからの大学のあり方について、議論を巻き起こそうと訴える書。
日比嘉高著『いま、大学で何が起こっているのか』詳細
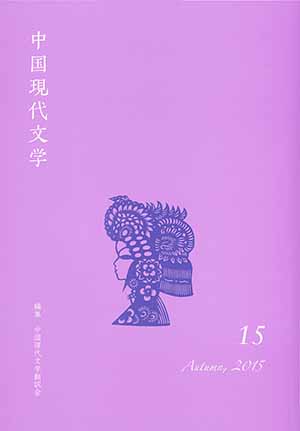
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 15』を刊行しました。
現代中国の文学作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第15号。
蒋韻「心愛樹」(黄土台地の秘所の伝奇)、馮驥才「木彫りのパイプ」(画家と花造りの老人の交流)、裘山山「どしゃぶり」(見合い相手の本性とは?)、蒋一談「もう一つの世界」(中国に助けられたユダヤ人一家の愛憎)、残雪「梅保の地盤」(ちがう場所に通じる一本の山道がある)などを掲載する。
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 15』詳細

加藤重広編『日本語語用論フォーラム 1』を刊行しました。
今までの日本語の文法や談話の研究の中には、場面や文脈など語用論的な観点が既に含まれ、客観的に見て「語用論」的なものが多くあった。一方、語用論研究では欧米の研究の摂取を主軸にしており、日本語の「語用論」的な研究と触れあうことが少なかった。本書は、日本語の研究と語用論の研究が通じ合う広場(フォーラム)となることを目指し、新しい研究成果を紹介する。
加藤重広編『日本語語用論フォーラム 1』詳細

ひつじ研究叢書(言語編) 第132巻、秋元実治・青木博史・前田満編『日英語の文法化と構文化』を刊行しました。
本書は、「構文化」および「文法化」、さらにそれらの間の関係について、理論・記述の両面から新しい知見を示したものである。日本語と英語を対象とし、共時的・通時的双方の視点からアプローチを行うことにより、その本質に迫ることを目的としている。日本語学と英語学のコラボレーションによって研究の新たな地平を拓く、斬新な試みである。
執筆者:秋元実治、高見健一、早瀬尚子、前田満、柴﨑礼士郎、秋元美晴、志賀里美、三宅知宏、青木博史、吉田永弘
秋元実治・青木博史・前田満編『日英語の文法化と構文化』詳細
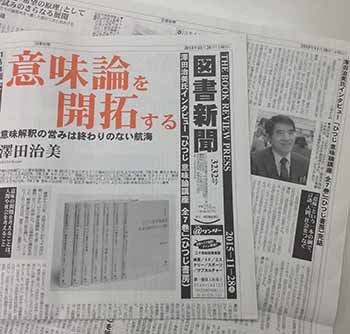
『図書新聞』2015年12月21日発売号に、「ひつじ意味論講座」完結を記念して編者の澤田治美先生へのインタビューが掲載されました。
「ひつじ意味論講座」シリーズ詳細はこちらをご覧下さい。
2015.11.16
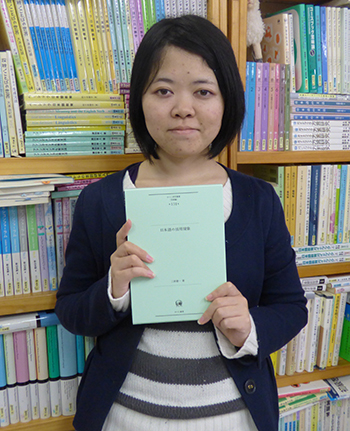
三原健一著 『日本語の活用現象』ができあがりました。

ひつじ研究叢書(言語編) 第131巻、三原健一著『日本語の活用現象』を刊行しました。
本書は、現代日本語における動詞の活用形を切り口として、活用形が絡む統語・意味現象を解明することを目的としている。筆者の長年の信条である、生成文法と日本語学の「相互乗り入れ」にも十分に配慮し、日本語学に興味を持つ読者にも読んでいただけるように、生成文法的なことについては随所に解説を加えた。現段階では秤量が極めて少ない活用の統語論研究に対して、何らかの貢献ができればという思いで本書に取り組んだ。
三原健一著『日本語の活用現象』詳細

城田俊・尹相實著『ことばの結びつきかた 新日本語語彙論』を刊行しました。
語は音と意味を持つだけではない。固有の文法と慣用的結合特性を保有する。普段意識しないこの文法と結合特性を本書は明晰にえぐり出し、意識化することを目的とする。意識化は語彙を豊富にし、運用能力を向上させ、自己鍛錬のみならず、教育に多大の寄与をもたらす。本書は語彙文法・結合特性の初めての研究書であると共に新しい語彙教育の体系的実用参考書である。辞書編纂者、語彙・文法研究者、日本語教師、日本語学習者必携。
城田俊・尹相實著『ことばの結びつきかた 新日本語語彙論』詳細

ひつじ研究叢書(言語編) 第127巻、近藤泰弘・田中牧郎・小木曽智信編『コーパスと日本語史研究』を刊行しました。
日本語史研究にどのようにしてコーパスを用いるかについての日本最初の概説書。具体的な研究方法も満載。また、オクスフォード大学の古典語コーパスについても開発者自らが詳しく解説。その他、古典語コーパス関係の文献解題も付載。なお、国立国語研究所の「日本語歴史コーパス」の開発に関わった研究者による共同研究の成果でもある。
執筆者:近藤泰弘・田中牧郎・小木曽智信・山元啓史・山田昌裕・高山善行・岡﨑友子・横野光・ビャーケ=フレレスビッグ・スティーブン=ホーン・ケリー=ラッセル・冨士池優美・鴻野知暁・間淵洋子
近藤泰弘・田中牧郎・小木曽智信編『コーパスと日本語史研究』詳細

シリーズ日本語を知る・楽しむ1、福田孝著『古文を楽しく読むために』を刊行しました。
「これって本当に日本語?」「意味がわからない」「文法の丸暗記ばっかり」…とかく敬遠されがちな古文の授業。歴史的仮名遣いの読み方からなぜ動詞の活用を覚える必要があるのか、易しい敬語の理解の仕方、平安和歌の読み方まで、古代の人々の心情を感じ取りながら和文の性質にしたがいつつ古文を立体的に面白く読むための数々の“いろは”。古文を楽しく読んでみたい人、生徒に楽しくなる読み方を生徒に教えたい国語教師の方におすすめ。
『古文を楽しく読むために』詳細
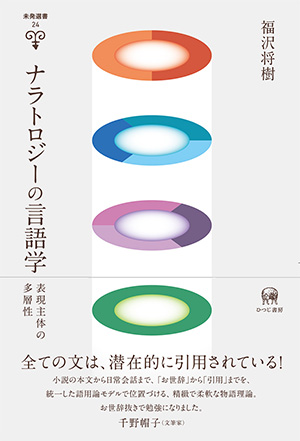
福沢将樹著『ナラトロジーの言語学 表現主体の多層性』を刊行しました。
言語学における語用論・統語論と文学理論におけるナラトロジー(物語論)とを融合し、「作者」「語り手」「視点」といった「表現主体」の多層性(垂直分業)の観点と「人格」の乖離という概念を組み合わせた統一的な枠組みを構築する。この枠組みに基づき、嘘・虚構・お世辞、引用、時制のそれぞれにつき、様々な微妙な区別を図式化し、それらが相違を持つにもかかわらず類似することをも説明する。
『ナラトロジーの言語学 表現主体の多層性』詳細
2015.10.16

新刊・近刊のご案内の冊子『未発ジュニア版』を発送しました。
『未発ジュニア版』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いします。

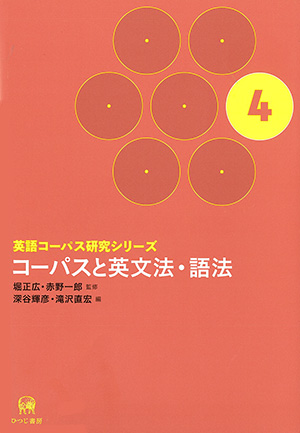
堀正広・赤野一郎監修、英語コーパス研究シリーズ第2巻『コーパスと英語教育』(投野由紀夫編)、ならびに第4巻『コーパスと英文法・語法』(深谷輝彦・滝沢直宏編)を刊行しました。
本シリーズは、英語コーパス学会20周年を記念した網羅的なコーパス研究のシリーズです。
第2巻『コーパスと英語教育』では、コーパスの英語教育への応用に関して歴史的経緯を概説し、英語教育とコーパスに関する理論的な枠組みを提示します。扱われる分野は、英語学習語彙表、英語教授、学習者コーパス、EAP/ESP教育、言語テスト、そしてコーパス・ツールについてです。
第4巻『コーパスと英文法・語法』は、「コーパスと語彙・語法」、「コーパスと文法」、「コーパスと構文」の3つの潮流を概観し、コーパスに基づく英文法・語法研究の方法論とその可能性を提示した後、様々な語法・文法について具体的な事例研究を納める論文集です。
英語コーパス研究シリーズ シリーズ詳細
投野由紀夫編 第2巻『コーパスと英語教育』詳細
深谷輝彦・滝沢直宏編 第4巻『コーパスと英文法・語法』詳細

日本方言研究会編『方言の研究 1』を刊行しました。
日本方言研究会の機関誌『方言の研究』創刊号。特集「方言研究の新しい展開」。
口唇の特徴から見た東北方言の合拗音の諸相 大橋純一/富山市方言における終助詞「ヨ」 小西いずみ/群馬県方言における粉食に関する語彙 新井小枝子/言語行動の地理的・社会的研究 中西太郎/琉球諸方言における有標主格と分裂自動詞性 下地理則/医療・福祉と方言 今村かほる/海外の日本語と方言 白岩広行/共生タイプについて 有元光彦/トル形の表す意味 津田智史/方言を撮る 櫛引祐希子/石川方言におけるノダ相当形式 野間純平/「方言」とは何か ダニエル・ロング/地方議会会議録による方言研究 二階堂整・川瀬卓・高丸圭一・田附敏尚・松田謙次郎/沖縄久高島方言の特殊な舌頂音の音声記述と音韻解釈 新永悠人・青井隼人
日本方言研究会編『方言の研究 1』詳細
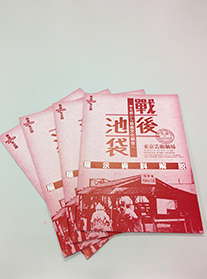
戦後70年企画「戦後池袋―ヤミ市から自由文化都市へ―」
現在池袋の東京芸術劇場を中心としてイベントが開催されています。ひつじ書房はギャラリー展示解説のパンフレット作成のお手伝いをいたしました。
本イベントは、展示の他にもギャラリートークやホッピー祭り、落語や映画やのど自慢など様々な催しが行われていますので、ぜひお越しください。
本イベントのシンポジウムに論考を加えた書籍と、展示写真その他の図録をひつじ書房より来春刊行予定です。
ひつじ書房では、日本発達心理学会編 Frontiers in Developmental Psychology in Japan(邦題:『日本の発達心理学の成果と最先端』(仮))を2016年春に刊行の予定です。日本の発達心理学における最先端の研究を集めた英語の論文集です。
2016年7月、横浜で国際心理学会議(ICP2016)が開催されます。この期に日本の発達心理学の成果を世界に発信する1冊となります。
*本書は、紙の書籍の他に、日米AmazonでのKindle版の発売、丸善の電子図書館サービスである、Maruzen eBook Library版等、電子媒体での発売も予定しています。
『トルコのもう一つの顔』(中公新書)の著者、小島剛一さんがラズ語の辞書の刊行を計画しています。
賛同者を募る講演会を開催しますので、ふるってご参加ください。今年は、神戸、秋田、東京の三箇所で講演会を行います。
名著『トルコのもう一つの顔』には、トルコ共和国で言語を調査している時に出会った、ラズ人たちやラズ人たちの言語のことが述べられています。ラズ語を研究されてきた小島剛一さんが、ラズ語の辞書の刊行を計画しています。
辞書の刊行は、絶滅危惧言語を保存するために大切なことであり、言語学にとって、人類にとって重要であることはもちろんですが、何よりラズ語話者にとって、ラズ語を保存し、持続させていくために、ラズ語の辞書が刊行されることは重要な意味を持ちます。そのために、ラズ語トルコ語日本語を対照した辞書の刊行を実現したいと考えます。
しかしながら、辞書刊行については、日本国内においての需要が、大きいとは思われず、商業的な出版は困難です。何らかの支援を求めることが必要です。ラズ語の辞書を刊行することに賛同下さる方に呼びかけ、ご支援によりまして、刊行を目指したいと思います。ご支援をお願いします。
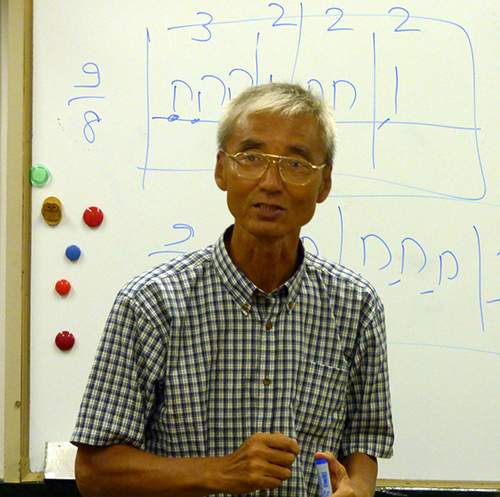
■9月1日(火)神戸 海外移住と文化の交流センター 5階ホール
18時30分開場 19時開演
■9月18日(金)秋田 秋田県生涯学習センター
18時30分開場 19時開演
■9月20日(日)東京 アジア文化会館 101研修室
13時30分開場 14時開演
概要シャルリー・エブド襲撃事件について、日本の大手メディアがそろって誤訳による誤報をしたために大多数の日本人はこの事件を誤解している。シャルリー・エブド紙の2015年1月14日発売号の表紙に「私はシャルリー」と訳すべき文言は無い。日本語として意味をなさないこの大誤訳がなぜ罷り通っているのだろうか。この誤訳が生じた原因として、フランス語とフランス社会への無理解があるが、フランス在住の言語研究者としてその背景を述べる。 |
詳細はこちらをご覧下さい。 ご賛同を募集しております文章も作成いたしました。
先月刊行しました『ひつじ意味論講座 第7巻 意味の社会性』にて、「ひつじ意味論講座」シリーズが完結いたしました。
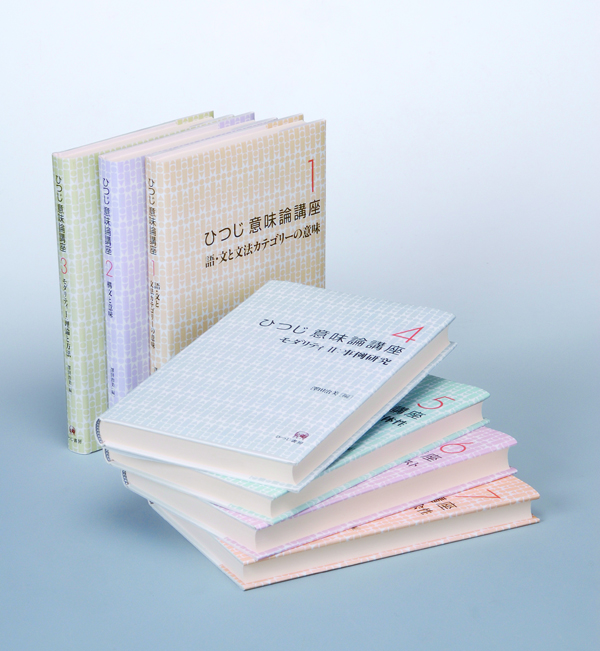
シリーズ完結のお祝いを編者の澤田治美先生と弊社にて行いました。
ツイート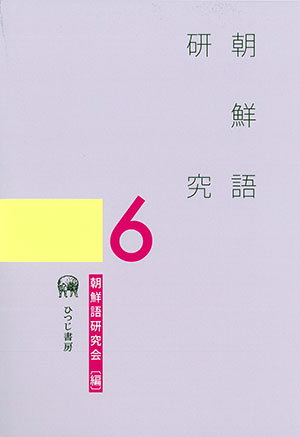
朝鮮語研究会編『朝鮮語研究 6』を刊行しました。
本書は1983年4月に発足し、1999年からは正式に学会組織として活動してきた朝鮮語研究会の不定期刊学会誌『朝鮮語研究』の第6号である。本書には、ソウル方言の音声に関する論文1篇、方言のピッチアクセントに関する論文2編、現代朝鮮語文法に関する論考2篇、文字論に関する論文1篇、中期朝鮮語のアスペクトに関する論文1篇の計7篇が収められている。
朝鮮語研究会編『朝鮮語研究 6』詳細

澤田治美編『ひつじ意味論講座 第7巻 意味の社会性』を刊行しました。
言語学のほか、様々な分野の第一線の研究者によるあらたな「意味」研究のシリーズ「ひつじ意味論講座」第7巻。意味は、社会の様々な場においてどのように伝達されているのか。本巻では、翻訳、医療、司法、スポーツなどにおける言語使用を通して、意味とコミュニケーションをめぐる問題に光を当て、従来の意味論の枠を超えた新しい考察を展開する。ひつじ意味論講座総目次・総索引付。
執筆者:山口節郎、亘明志、児玉徳美、堀井令以知、リリアン テルミ ハタノ、クレア・マリィ、影浦峡、北山修、野呂幾久子、堀田秀吾、名嶋義直、東海林祐子、森山卓郎
澤田治美編『ひつじ意味論講座 第7巻 意味の社会性』詳細
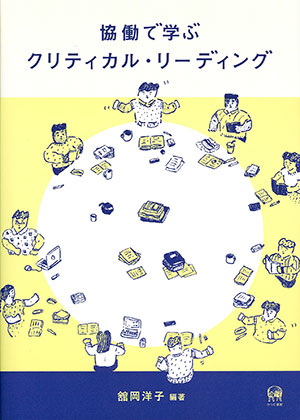
舘岡洋子編著『協働で学ぶクリティカル・リーディング』を刊行しました。
ピア・リーディング(対話による協働的読解活動)を具現化するための読解テキスト。文章理解のための設問に対して正しい答えをさがすという読解ではなく、学習者(読者)がテキストの各テーマを自分の問題としてとらえ、筆者の主張、学習者自身の考え、クラスメイト(ほかの読者)の考えを対話を通して明らかにし、自らの思考を深めるものである。留学生の日本語のテキストに、また大学の理解表現科目のテキストにも利用できる。
舘岡洋子編著『協働で学ぶクリティカル・リーディング』詳細

音声収録の様子です。7月上旬より出荷を開始します。
日本社会・文化に関する6つのテーマと、テーマに関連する4つのタスクからなり、日本語力の養成のみならず、思考力や、社会・他者と積極的に関わる力を身につける、テーマとタスクを融合させた新しい中級日本語総合教科書。
東京外国語大学留学生日本語教育センター著『日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書 出会い【本冊 テーマ学習・タスク活動編】』詳細

武内道子著『手続き的意味論ー談話連結語の意味論と語用論』を刊行しました。
関連性理論は、語用論を解釈の学ではなく、認知科学として位置づけた。本書は、この認知語用論の枠組みによって、言語表現には、発話の命題内容に寄与するのでなく、解釈の方向を聞き手に指示する意味に特化している言語表現があることを示し、新しい意味論を提示する。日本語の談話連結語に例を求め、発話の命題内容ではなく、その解釈過程にいかなる制約を課すかという意味を論証している。著者の20年におよぶ研究の集大成である。
武内道子著『手続き的意味論ー談話連結語の意味論と語用論』詳細
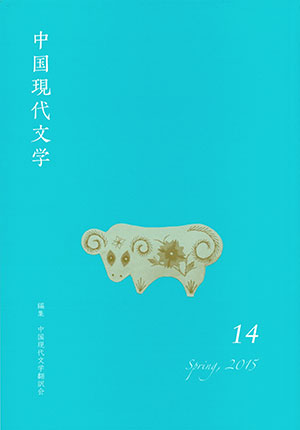
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 14』を刊行しました。
現代中国の文学作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第14号。
姚鄂梅「狡猾な父親」(父と息子の意地の張り合い)、丹増「ギャンゴン」(転生ラマとなった牧童の物語)、沈石溪「狐狩り」(ハニ族少年の狩りでの葛藤)、翟永明「上書房、下書房」「仙台へ小野綾子へ」「行間の距離・ひとつの序詩」(日中両国の震災を糸口にした詩三篇)などを掲載する。
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 14』詳細
研究書出版の相談会、オープンオフィス、開催中です。
オープンオフィス、詳細。
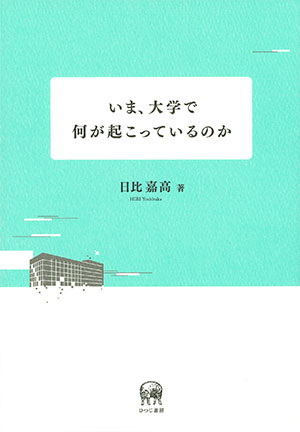
日比嘉高著『いま、大学で何が起こっているのか』を刊行しました。
財界や政府から国立大学に対し、産業振興を主たる目的として、「競争」をうながし、「自己改革」を求める声が大きくなっている。現在の国立大学が、非効率的な方法で運営されているから、大変革をするというのだ。しかし、その批判は当たっているのだろうか。それは大学が持ってきたはずの知的な活動拠点としての役目を殺してしまい、ひいては多様な創造の芽を育くむという重要な機能を破壊することではないのか。現在の潮流に異を唱え、国立大学のみならず、これからの大学のあり方について、議論を巻き起こそうと訴える書。
日比嘉高著『いま、大学で何が起こっているのか』詳細

川口順二編『フランス語学の最前線3』を刊行しました。
フランス語学の最新の成果を世に問うシリーズ第3巻。本巻はモダリティを取り上げ、多様な方法論による分析を展開する。論じられるテーマは法形容詞、蓋然性副詞、強意、動詞接続法、コネクター、反実仮想、所有形容詞、命令、論証、アイロニー、主観性そして呼びかけ、一般言語学レヴェルでも有効な問題提起が行われる。
執筆者:川口順二、山本大地、芦野文武、春木仁孝、守田貴弘、小熊和郎、曽我祐典、中尾和美、フランス・ドルヌ、渡邊淳也、西脇沙織、阿部宏
川口順二編『フランス語学の最前線3』詳細
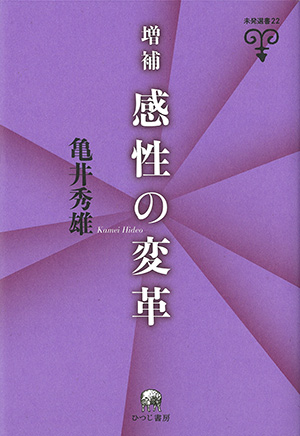
未発選書 22、亀井秀雄著『増補 感性の変革』を刊行しました。
1983年に刊行され絶版となっていた本書に、2002年の英訳版のために書いた自著解説、これまで単行本に収められなかった関連論文を大幅に盛り込み、4部構成とした増補版。「第1部 感性の変革」、「第2部 文学と歴史」、「第3部 小説の発明」、「第4部 文学生産の様式」。表現論の観点から、柄谷行人や前田愛との方法論的な対峙と共に、インターテクスチュアルな語り手の分析へと近代文学研究を一変させた金字塔の待望の復刊。解説:西田谷洋(富山大学教授)
亀井秀雄著『増補 感性の変革』詳細

大野眞男・小林隆編『方言を伝えるー3.11東日本大震災被災地における取り組み』を刊行しました。
東日本大震災の発生から4年が経過した。本書では、危機に瀕した被災地域(青森・岩手・宮城・福島・茨城)の方言を活性化し次世代に伝えることを通して、社会文化的側面から地域再生の足掛かりを築いていこうとする取り組みを紹介する。方言を次世代に伝えるための記録や学習材の作成、 方言を使用できる場の設定など、言語研究者が考えるべきこと、行うべきことは何かを議論する。
執筆者:今村かほる、内間早俊、大野眞男、神田雅章、小島聡子、小林隆、小林初夫、坂喜美佳、佐藤亜実、杉本妙子、鈴木仁也、竹田晃子、武田拓、半沢康
大野眞男・小林隆編『方言を伝えるー3.11東日本大震災被災地における取り組み』詳細
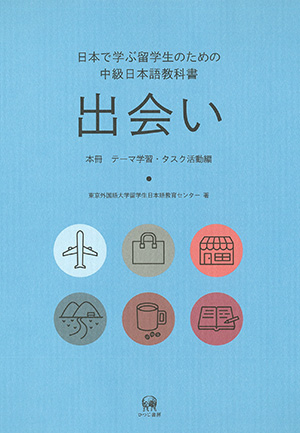
東京外国語大学留学生日本語教育センター著『日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書 出会い【本冊 テーマ学習・タスク活動編】』をまもなく刊行します。
日本社会・文化に関する6つのテーマと、テーマに関連する4つのタスクからなり、日本語力の養成のみならず、思考力や、社会・他者と積極的に関わる力を身につける、テーマとタスクを融合させた新しい中級日本語総合教科書。
東京外国語大学留学生日本語教育センター著『日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書 出会い【本冊 テーマ学習・タスク活動編】』詳細
2015.5.19

新刊・近刊のご案内の冊子『未発ジュニア版』を発送しました。
『未発ジュニア版』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いします。
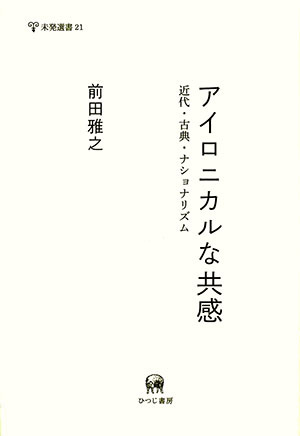
未発選書21、前田雅之著『アイロニカルな共感ー近代・古典・ナショナリズム』を刊行しました。
日本近代は古典を捨てて成立した。だから、近代と古典とは相容れぬ関係にあるわけだ。それなのに、ナショナリズムには古典が導入される。これこそアイロニーでなくてなんだろうか。本書は、古典研究者である前田雅之が、古典と近代のアイロニカルにして、時にシニカルな関係、あるいは、近代・現代批判、そして、現代人がものした古典研究の書評からなっている。古典研究者は古典と闘い、同時に、近代とも戦うのである。
前田雅之著『アイロニカルな共感ー近代・古典・ナショナリズム』詳細
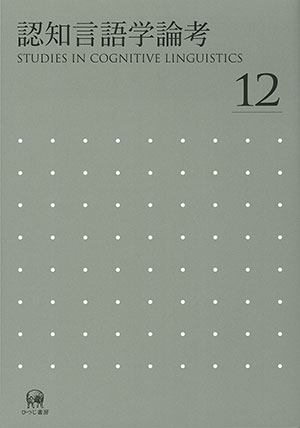
山梨正明他編『認知言語学論考 No.12』を刊行しました。
拡張記号モデルに基づく漢字の合成構造の記号論的分析 黒田一平/換喩的発話行為 小松原哲太/テキスト世界と現実世界の差異 加藤祥・岡本雅史・荒牧英治/指示詞の認知的基盤と選択原理 小川典子・野澤元/指示詞と時間 田口慎也/英語学習におけるCognitive Motivation Mode 今井隆夫/語り内において連鎖する節の音声特徴 甲田直美/英語の3人称小説における過去時制形式の解釈メカニズム 和田尚明/補助動詞「(て)しまう」と感嘆詞「しまった」の意味分析と拡張メカニズムの考察 田村敏広/発話・慣習・社会知に基づいた「まとまり」の認知 土屋智行/二重目的語構文と関連現象の認知言語学的分析 年岡智見
山梨正明他編『認知言語学論考 No.12』詳細

津田早苗・村田泰美・大谷麻美・岩田祐子・重光由加・大塚容子著『日・英語談話スタイルの対照研究ー英語コミュニケーション教育への応用』を刊行しました。
日本人が英会話が苦手な理由の一つに、日・英語間のコミュニケーションスタイルの違いがある。さらにその背後には、各言語話者の間では暗黙の了解となっている円滑な会話のための決まり事の違いがある。本書は英語教育を視野に入れつつ、「自己開示」「質問・応答」「相づち」「他者修復」「ターン」「話題展開」という相互作用社会言語学の観点から、日・英語会話の「暗黙の決まりごと」の解明を試みた意欲的な研究書である。
津田早苗・村田泰美・大谷麻美・岩田祐子・重光由加・大塚容子著『日・英語談話スタイルの対照研究』詳細
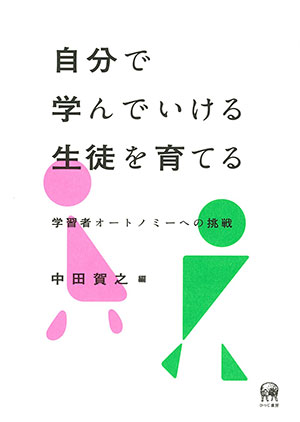
中田賀之編『自分で学んでいける生徒を育てるー学習者オートノミーへの挑戦』を刊行しました。
近年のグローバル化の流れを受け、英語教育現場では、学習者のオートノミーを促進するための模索が続いている。本書は、これまでの実践を新たな視点で見つめ直し、より効果的にオートノミーを育てる方策を考える材料を提供する。自らの実践を振り返りつつ、学習者オートノミーの理論と実践が体系的に学べる書。
執筆者:青木直子、稲岡章代、今井典子、大目木俊憲、小笠原良浩、澤田朝子、高塚純、茶本卓子、津田敦子、徳永里恵子、中田賀之、永末温子、棟安都代子、村上ひろ子、吉田勝雄
中田賀之編『自分で学んでいける生徒を育てるー学習者オートノミーへの挑戦』詳細
2015.4.3

新入社員1名を迎え、入社式をおこないました。
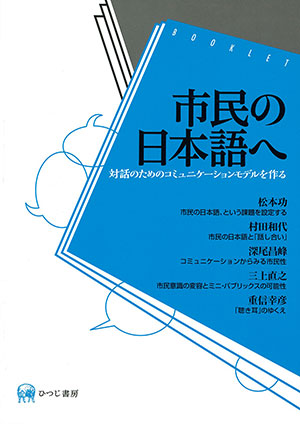
村田和代・松本功・深尾昌峰・三上直之・重信幸彦著、『市民の日本語へー対話のためのコミュニケーションモデルを作る』を刊行しました。
『市民の日本語』での加藤哲夫氏の議論を継承し、民主主義の基盤となる対話や話し合いをどう生み出し、育てていくかの議論。衆議という新しい話し合いの方法を問う三上直之(北海道大学、社会学)、ビジネス会議の談話分析と市民活動の会話分析を行う村田和代(龍谷大学、言語学)、 NPOを運営し、社会を変える社会活動家である深尾昌峰(龍谷大学、京都コミュニティ放送副理事長)、地方都市福岡の街の商売人のことばから、ことばについて考える重信幸彦(歴史民俗博物館客員教授、民俗学)に加え、ひつじ書房房主松本らによる問いかけの書。
村田和代・松本功・深尾昌峰・三上直之・重信幸彦著『市民の日本語へー対話のためのコミュニケーションモデルを作る』詳細

菊地恵太著、神奈川大学言語学研究叢書 5、『英語学習動機の減退要因の探求ー日本人学習者の調査を中心に』を刊行しました。
英語習得のように、なかなか成果の見えにくい活動に取り組むにあたり、学習者が自分の意欲をどうやって維持するのかは、とても重要な課題である。本書は、動機付けに関する諸理論を踏まえた上で、1000人を超える高校生への質問紙調査や大学生とのインタビュー調査を元に英語習得での学習意欲の減退要因を探る。その上で、現場の教員がモチベーションの低い学習者にどのように接したらよいかといった様々な疑問に答えるヒントを模索する。
菊地恵太著『英語学習動機の減退要因の探求ー日本人学習者の調査を中心に』詳細
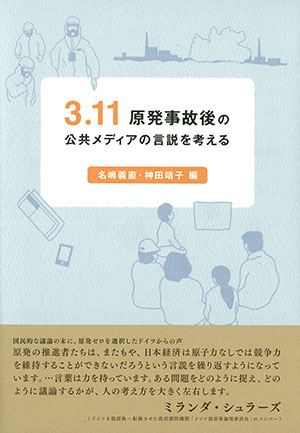
名嶋義直・神田靖子編『3.11原発事故後の公共メディアの言説を考える』を刊行しました。
この本は原発問題をテーマに言語学の立場からメディアを分析した本である。新聞・テレビ・インターネットメディア・政府刊行物・書籍などのメディア言語を言語学的な論証を通して多角的に可視化する。新聞・インターネットメディア・政府刊行物などによる原発問題についての公共メディア言語を分析し、その問題点を指摘。ドイツにおける脱原発の立役者「ドイツ脱原発倫理委員会」委員の一人であるベルリン自由大学ミランダ・シュラーズ教授より巻頭言をいただいている。著者たちは、社会的な課題について研究し、発言する批判的談話分析という言語研究の方法に基づき、メディアの現在を鋭く追求する。
名嶋義直・神田靖子編『3.11原発事故後の公共メディアの言説を考える』詳細
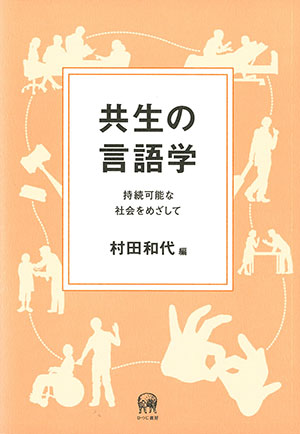
村田和代編『共生の言語学ー持続可能な社会をめざして』を刊行しました。
言語・コミュニケ―ション研究は、持続可能な社会の構築にどのように貢献できるのか。本書は、この課題に取り組む実践的な言語・コミュニケーション研究の報告に、医療・福祉・政策・環境分野からの視点を加えた論文集である。分野を超えた対話を通して、持続可能な社会・共生と言語・コミュニケーション研究を考えるための一冊。
執筆者・座談会参加者:岩田一成、川本充、菊地浩平、高山智子、土山希美枝、バックハウス・ペート、深尾昌峰、松浦さと子、松本功、村田和代、森山卓郎、森本郁代、山田容、渡辺義和
村田和代編『共生の言語学ー持続可能な社会をめざして』詳細

髙橋輝和著、ひつじ研究叢書(言語編) 第126巻『ドイツ語の様相助動詞ーその意味と用法の歴史』を刊行しました。
ドイツ語文法で一般に「話法の助動詞」と呼ばれ、英語の「法助動詞」に対応する極めて特異な助動詞-厳密に言えば本動詞としての特性も合わせ持つハイブリッド動詞-の語形と意味や用法の変遷を考察した初めての研究書。本書は、印欧祖語・前ゲルマン祖語からゲルマン祖語、ゴート語、古期独語、中高独語、初期新高独語を経て新高独語・現代独語に至るまでを対象とし、さらにはこの助動詞の将来の有様も展望するものである。
髙橋輝和著『ドイツ語の様相助動詞ーその意味と用法の歴史』詳細

友定賢治編、ひつじ研究叢書(言語編) 第102巻『感動詞の言語学』を刊行しました。
感動詞研究の広がりを示し、今後の研究の指標となる初めての論文集。感動詞の言語学的性格、応答表現の構造、方言感動詞の記述、「まあ」や「げっ」の記述、日本語非母語話者の運用、会話分析的考察、地理的変異の考察、対照言語学的考察、ビデオ調査法などからなる。執筆者:青木三郎、有元光彦、金田純平、串田秀也、小西いずみ、小林隆、定延利之、大工原勇人、冨樫純一、友定賢治、野田尚史、パウル・チブルカ、林誠、森山卓郎
友定賢治編『感動詞の言語学』詳細
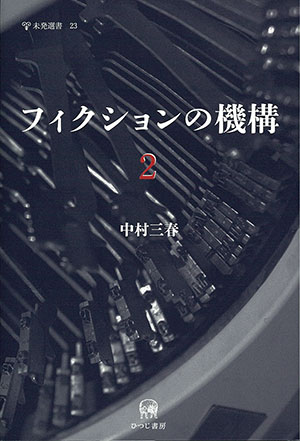
中村三春著、未発選書 23『フィクションの機構2』を刊行しました。
言語は根元的に虚構であり、文芸の虚構はその延長線上に実現される。この根元的虚構論の立場から、〈嘘と虚構のあいだ〉〈近代小説と自由間接表現〉〈第二次テクストと翻訳〉〈カルチュラル・スタディーズとの節合〉〈認知文芸学の星座的構想〉〈無限の解釈過程と映像の虚構論〉〈故郷・異郷・虚構〉など未解決の課題に答え、横光利一・太宰治・村上春樹の小説、安西冬衛・谷川俊太郎・松浦寿輝の詩、今井正の映画について論じる。
中村三春著『フィクションの機構2』詳細
3月22日に「国際シンポジウム 言語学者によるメディア・リテラシー研究の最前線 -- ポスト3.11の視点 --」が開催されます。
本シンポジウムに合わせて、ひつじ書房より『3.11 原発事故後の公共メディアの言説を考える』(名嶋義直・神田靖子編)を刊行します。原発問題をテーマに言語学の立場からメディアの言説を批判的に検討する、いま非常に重要な事柄を扱った書籍です。
当日は本書の販売もおこないます。ぜひシンポジウムへのご参加をお願いいたします。
本書とシンポジウムのご案内

鳴海伸一著、『日本語における漢語の変容の研究ー副詞化を中心として』を刊行しました。
漢語は、日本語に定着する過程で何らかの日本的変容を被る場合がある。そうした現象を「漢語の国語
化」として捉え直し、漢語が副詞化する事例を中心に個別の語史を検討する。それをもとに、副詞化の段階的なプロセスを示し、さらに、副詞における時間的意味・程度的意味発生の、過程と類型を示す。本書は、個別の語史を総合して、漢語の日本的変容や副詞の意味変化といった体系的な視点でまとめることを目指すものである。
鳴海伸一著『日本語における漢語の変容の研究ー副詞化を中心として』詳細
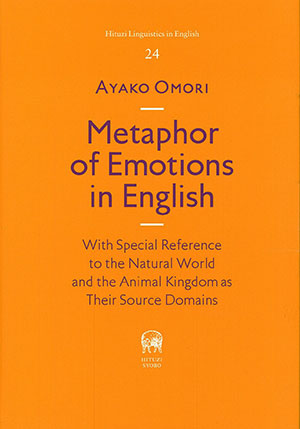
大森文子著、『Metaphor of Emotions in English: With Special Reference to the Natural World and the Animal Kingdom as Their Source Domains』を刊行しました。
本書は、感情を表すメタファーの仕組を認知言語学の枠組で探究するものである。従来の認知メタファー論者が用いてきたような内省に基づく作例ではなく、大規模電子コーパスから抽出された高頻度の例や、英詩などの文学作品、辞書などの小規模コーパスにおける慣用表現を分析する方が、本来の認知メタファー理論の理念に合致するという観点から、広く日常言語、文学の言語を研究対象とし、従来にない認知モデルを提唱する。
大森文子著『Metaphor of Emotions in English』詳細
ツイート
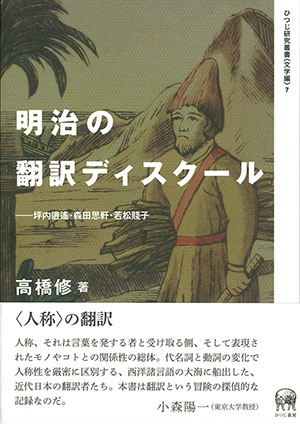
高橋修著、『明治の翻訳ディスクールー坪内逍遙・森田思軒・若松賤子』を刊行しました。
〈人称〉の翻訳とは? 関係指向性の強い日本語の文法において、〈人称〉の問題は歴史的に特別な位置を占めてこなかった。〈人称〉という概念そのものが西洋文化摂取の過程で移入されたといえる。ならば、〈人称〉を意識化することが、表現史的にどのような意味があったか。井上勤訳『魯敏孫漂流記』(明治16年)、坪内逍遙訳『贋貨つかひ』(明治20年)、森田思軒訳『探偵ユーベル』(明治22年)等を取り上げながら解き明かす。
高橋修著『明治の翻訳ディスクールー坪内逍遙・森田思軒・若松賤子』詳細
ツイート
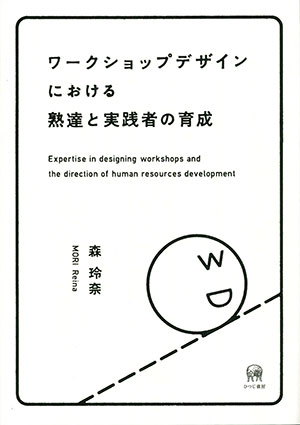
森玲奈著、『ワークショップデザインにおける熟達と実践者の育成』を刊行しました。
生涯学習時代の到来とともに、新しい学びの手法として「ワークショップ」に対する関心や期待が高まりつつある。だが、この方法について、領域横断的な研究書はこれまで乏しかった。本書では、ワークショップの歴史を丁寧に追う。そしてワークショップを創る人、すなわちワークショップ実践者に着眼し、その熟達について様々な手法を用いて迫る。さらに、実践者が学びながら成長する姿に、今後の実践者育成における課題を見出す。未来の教育を考える上で、重要な示唆を与える書と言えよう。
森玲奈著『ワークショップデザインにおける熟達と実践者の育成』詳細
ツイート

武藤彩加著、ひつじ研究叢書(言語編) 第124巻『日本語の共感覚的比喩』を刊行しました。
「甘い声」のような五感内の表現の貸し借りを共感覚的比喩という。基本色彩語等と並び言語普遍性現象のひとつとされてきたが,本書では,日本語の共感覚的比喩の全体系を明確に示す。結論として,オノマトペや動詞も含め包括的に分析されるべきであるということ,メタファーだけでなく複数の意味作用によって成り立つものであること,比喩の一種ではなく感覚間の転用現象に対するラベルづけと捉え直すべきであること等を主張する。
武藤彩加著『日本語の共感覚的比喩』詳細
ツイート

山森良枝著、ひつじ研究叢書(言語編) 第123巻『パースペクティブ・シフトと混合話法』を刊行しました。
我々の言葉は背景となる文脈やパースペクトを介して理解される。Indexicalや他者の発話・信念の報告等は、誰の発話や信念と相対的であるかに即して意味が決定されるため、その理解には文脈やパースペクトの一貫性が重要である。ところが、自然言語には、パースペクトの混在やシフトが関わる現象が少なくない。本書では、日本語の一見奇妙な時制解釈や独特な括弧使用等の観察を通じて、その背後に働くメカニズムをパースペクトの混在という観点から解き明かす。
山森良枝著『パースペクティブ・シフトと混合話法』詳細。
ツイート

中俣尚己著、シリーズ言語学と言語教育 33『日本語並列表現の体系』を刊行しました。
日本語の多様な並列表現を包括的・体系的に記述した初めての研究書。扱う形式は「と」「や」「とか」といった並列助詞、「て」「し」「たり」といった接続助詞、そして「また」「しかも」「そのうえ」といった接続詞と3つのカテゴリーにまたがる34形式。それらを統語的な「網羅性」と意味的な「集合の形成動機」の二軸によって体系的に記述する。心理実験やコーパス調査などの手法も取り込み、意味の違いを客観的に分析する。
中俣尚己著『日本語並列表現の体系』詳細。
ツイート
ひつじ書房は、編集できるスタッフを募集します。2015年4月から働くことのできる人を募集します。本作りの全体に関わる仕事になります。本が好きで、その上、作ること、あるいは売ることも好きになれる人を募集します。基礎から、仕事を教えます。
正社員募集、求人の詳細。
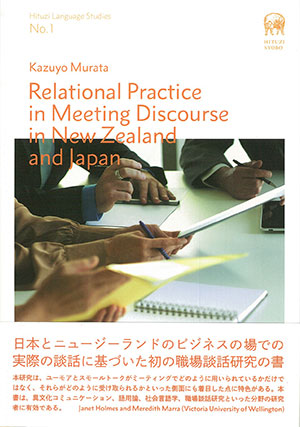
村田和代著、Hituzi Language Studies No.1『Relational Practice in Meeting Discourse in New Zealand and Japan』を刊行しました。
本書は、ビジネス・ミーティング談話を社会言語学の観点から分析した実証的研究である。日本およびニュージーランドでの談話におけるRelational Practice (対人関係機能面に関わる相互行為)、とりわけ、ユーモアとスモールトークを焦点に表出の特徴を明らかにし、異文化間コミュニケーションにおけるそれらの使用の評価を分析する。実際のミーティング談話に基づいた言語研究として待望の一冊。
村田和代著『Relational Practice in Meeting Discourse in New Zealand and Japan』詳細。
ツイート

髙𣘺和子著、シリーズ言語学と言語教育 34『日本の英語教育における文学教材の可能性』を刊行しました。
本書は、近年、日本の英語教育から文学教材が減少した経緯を批判的に分析した上で、文学はコミュニケーション能力育成を目指す英語教育において重要な教材であることを、理論と実践両面から示している。実践面では、中学・高校教員の声や、大学生の意見を踏まえ、文学を活用するための多彩な授業プランを紹介している。英語教育に興味を持つ幅広い読者に薦めたい。
髙𣘺和子著『日本の英語教育における文学教材の可能性』詳細。
ツイート
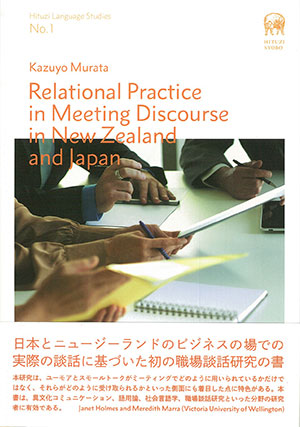
村田和代著、Hituzi Language Studies No.1『Relational Practice in Meeting Discourse in New Zealand and Japan』をまもなく刊行します。
本書は、ビジネス・ミーティング談話を社会言語学の観点から分析した実証的研究である。日本およびニュージーランドでの談話におけるRelational Practice (対人関係機能面に関わる相互行為)、とりわけ、ユーモアとスモールトークを焦点に表出の特徴を明らかにし、異文化間コミュニケーションにおけるそれらの使用の評価を分析する。実際のミーティング談話に基づいた言語研究として待望の一冊。
村田和代著『Relational Practice in Meeting Discourse in New Zealand and Japan』詳細。
ツイート
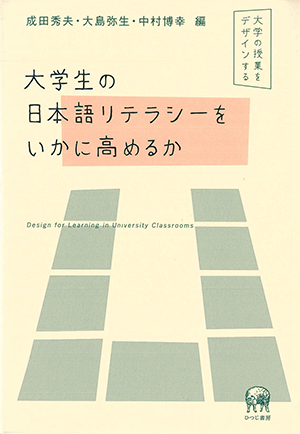
成田秀夫・大島弥生・中村博幸編 大学の授業をデザインする『大学生の日本語リテラシーをいかに高めるか』を刊行しました。
本書は、大学で広がる文章表現科目の担当者に向けて、担当者間の教育観・学習観の共有のためのFDのあり方、プロセスとユニットに着目した具体的なライティング授業の設計方法を示し、さらに能動型学習やジェネリックスキル育成を重視した7事例の紹介を通じて、知識基盤型社会に対応した「日本語リテラシー」教育を提案する。
執筆者:大島弥生、中村博幸、成田秀夫、堀上晶子、吉村充功、山本啓一、桑原千幸
成田秀夫・大島弥生・中村博幸編 『大学生の日本語リテラシーをいかに高めるか』詳細。
ツイート
新しい雑誌を創刊するなどのために社員を増員します。ひつじ書房は、正社員を若干名、募集します。未経験の方でも、学術書の出版に挑んでみたいとの気持ちのある方は、丁寧に一から教えます。
改訂についての詳細は以下のページをご覧ください。
2015年春卒と既卒の方へ 正社員の募集・求人・採用(編集+出版業務)ページ。
2015.1.19

2015年1月9日に、ジュンク堂書店で開催されたトークセッションは多数の方にご来場いただき、満員の中盛況の内に終了いたしました。ありがとうございました。
小平麻衣子・内藤千珠子著『田村俊子』詳細。

野田尚史・森口稔著、『日本語を書くトレーニング』第2版を刊行しました。
第2版では、2003年の初版刊行以降古くなってきた情報を現在に合わせて刷新する形で改訂しました。
改訂についての詳細は以下のページをご覧ください。
野田尚史・森口稔著『日本語を書くトレーニング』第2版詳細。
ツイート

岸江信介・田畑智司編、ひつじ研究叢書(言語編) 第121巻『テキストマイニングによる言語研究』を刊行しました。
本書の特色は、日本語学、英語学を専門分野とする新進気鋭の研究者が中心となり、さまざまな研究事例を提示しつつ、テキストマイニングを援用し、言語分析を試みたもので、日本語学6本、英語学4本の論文からなる。アンケート調査による自由回答の分析方法、膨大なテキストデータのなかに潜む真実を見つけ出す方法などを分かりやすく紹介している。
執筆者:小野原彩香、矢野環、中島浩二、吉田友紀子、岸江信介、西尾純二、阿部新、瀧口惠子、米麗英、清水勇吉、村田真実、内田諭、小林雄一郎、田中省作、後藤一章、阪上辰也 (論文掲載順)
岸江信介・田畑智司編『テキストマイニングによる言語研究』詳細。
ツイート
2014.12.3
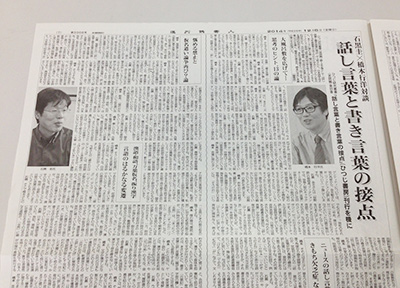
『週刊読書人』(2014年12月5日)に『話し言葉と書き言葉の接点』の編者である、石黒圭先生と橋本行洋先生による対談が掲載されます。
石黒圭・橋本行洋 編『話し言葉と書き言葉の接点』詳細。
ツイート
2014.12.1
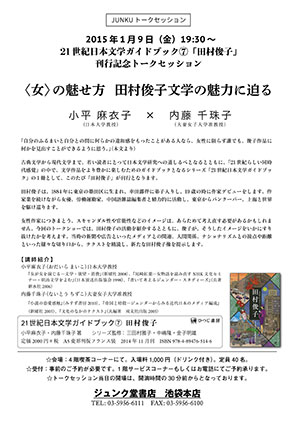
21 世紀日本文学ガイドブック7『田村俊子』刊行記念トークセッション「〈女〉の魅せ方 田村俊子文学の魅力に迫る」をジュンク堂書店池袋本店にて、開催いたします。
古典文学から現代文学まで、若い読者にとって日本文学研究への道しるべとなるとともに、「21 世紀らしい同時代感覚」の中で、文学作品をより豊かに楽しむためのガイドブックとなるシリーズ「21 世紀日本文学ガイドブック」の1 冊として、このたび「田村俊子」が刊行となります。
田村俊子は、1884 年に東京の墨田区に生まれ、幸田露伴に弟子入りし、19 歳の時に作家デビューをします。
作家業を続けながら女優、労働運動家、中国語雑誌編集者と精力的に活動し、東京からバンクーバー、上海と世界を駆け巡ります。女性作家につきまとう、スキャンダル性や官能性などのイメージは、あらためて考え直す必要があるかもしれません。今回のトークショーでは、田村俊子の活動を紹介するとともに、俊子が、そうしたイメージをいかにすり抜けたかを考えます。当時の新聞や広告といったメディアとの関連、人間関係、ナショナリズムとの接点や距離といった様々な切り口から、テクストを精読し、新たな田村俊子像を提示します。
ぜひ皆様お誘い合わせの上ご来場下さいますようお願い申し上げます。
【講師紹介】
小平麻衣子(おだいら まいこ)日本大学教授
『女が女を演じる―文学・欲望・消費』(新曜社2008)、『尾崎紅葉―女物語を読み直す NHK 文化セミナー・明治文学をよむ』(日本放送出版協会1998)、『書いて考えるジェンダー・スタディーズ』(共著 新水社2006)
内藤千珠子(ないとう ちずこ)大妻女子大学准教授
『小説の恋愛感触』(みすず書房2010)、『帝国と暗殺―ジェンダーからみる近代日本のメディア編成』
(新曜社2005)、『文化のなかのテクスト』(共編著 双文社出版2005)
☆日時:2015年1月9日(金)19:30〜
☆会場:ジュンク堂書店 池袋本店 4 階喫茶コーナーにて。
☆入場料1,000 円(ドリンク付き)。定員40 名。
☆受付:事前のご予約が必要です。1 階サービスコーナーもしくはお電話にてご予約承ります。
☆トークセッション当日の開場は、開演時間の30 分前からとなっております。
お問い合わせ先:ジュンク堂書店 池袋本店 TEL: 03-5956-6111
詳細は、こちら(ジュンク堂書店のページ)もご覧下さい。
当ひつじ書房においても、参加申し込みを受け付けます。
TEL: 03-5319-4916 MAIL: toiawase@hituzi.co.jp
小平麻衣子・内藤千珠子著『田村俊子』詳細。
Tweet
2014.11.27

『明治初等国語教科書と子ども読み物に関する研究』(府川源一郎著)が第38回日本児童文学学会特別賞を受賞しました。これまで光が当てられてこなかった膨大な資料を発掘され、児童文化研究の金字塔といえる本書が受賞されましたこと大変嬉しく思います。府川先生おめでとうございます。
第38回日本児童文学学会賞の決定について(画像)
府川源一郎著『明治初等国語教科書と子ども読み物に関する研究』詳細。
ツイート

小平麻衣子・内藤千珠子著、21世紀日本文学ガイドブック7『田村俊子』を刊行しました。
東京からバンクーバーへ、そして上海へ。女優にして作家、編集者。田村俊子の作品は、そうした特異な人生に裏打ちされながらも、一人の女性の経験にとどまらない、複雑な文化状況の解読に向けて開かれている。いかに新聞や広告の言説とかかわり、女性の官能表現の形成に寄与し、国家や階級と斬り結ぶのか。田村俊子を視座に、〈女性作家〉という強固なイメージの構築過程を明らかにし、そのほころびを探る。
小平麻衣子・内藤千珠子著『田村俊子』詳細。
ツイート

ジェイムズ・R・ハーフォード ブレンダン・ヒースリイ マイケル・B・スミス著、吉田悦子・川瀬義清・大橋浩・村尾治彦訳『コースブック意味論 第二版』を刊行しました。
本書は、1983年に出版以来好評を博してきた現代言語学における意味論の入門書の改訂新版(2007年)の翻訳である。意味の基礎概念から、指示と意義、論理的意味、語用論的意味、談話の領域に加え、認知的意味まで、意味論の基本的なトピックが網羅されている。豊富な練習問題と丁寧な解説を軸とした実践的なコースブックとして、独自の構成スタイルを持つ。各章末に学習の手引きと復習課題を整備して、独習用テキストとしての利用価値も高い。
ジェイムズ・R・ハーフォード ブレンダン・ヒースリイ マイケル・B・スミス著、吉田悦子・川瀬義清・大橋浩・村尾治彦訳『コースブック意味論 第二版』詳細。
ツイート
2014.11.5


中学生が弊社に職場体験に来てくれました。右の写真は返品を包む様子です。

Anna Cardinaletti・Guglielmo Cinque・Yoshio Endo編『On Peripheries: Exploring Clause Initial and Clause Final Positions』を刊行しました。
本書は、科学研究費の補助によるワークショップの成果等をまとめた論文集である。内容は、最先端のミニマリズムからカートグラフィー研究に及び、トピックは、認知科学における言語、複合語、発話行為、視点、ラベリング、凍結原理、局所性、テンス、トピック、フォーカス、名詞句の内部構造と多岐に渡る。日本語研究の指南となる解説も含む。
編者:Anna Cardinaletti(アンナ・カーディナレッティ), Guglielmo Cinque(グリエルモ・チンクエ), Yoshio Endo(遠藤喜雄)
執筆者:Anna Cardinaletti, Guglielmo Cinque, Luigi Rizzi, Alessandra Giorgi, Liliane
Haegeman, Ur Shlonsky, Taisuke Nishigauchi, Mamoru Saito, Hiromi Sato, Yoshio Endo, Virginia Hill, Bartosz Wiland, Marco Coniglio
Anna Cardinaletti・Guglielmo Cinque・Yoshio Endo編『On Peripheries』詳細。
ツイート

青木博史・小柳智一・高山善行編『日本語文法史研究 2』を刊行しました。
本書は、本邦初を謳った、日本語文法の歴史的研究をテーマとする隔年刊行の論文集の第2号である。
文法史研究の発展に貢献すべく最新の成果を発信すること、さらに、若手研究者による論文を掲載し、当該分野の活性化を図ることを目標としている。研究論文10本に加え、「テーマ解説」「文法史の名著」「文法史研究文献目録」を付している。
執筆者:青木博史、岡部嘉幸、川瀬卓、衣畑智秀、小柳智一、竹内史郎、西田隆政、仁科明、深津周太、福沢将樹、森勇太、矢島正浩、吉田永弘
青木博史・小柳智一・高山善行編『日本語文法史研究 2』詳細。
ツイート

書籍を作ることに興味のある方、どうぞ以下をご覧下さい。正社員を募集しています。
2014.10.20


このたび、『現代日本語ムード・テンス・アスペクト論』(工藤真由美先生著)について、平成26年度新村出賞の受賞が決まりました。また、『長崎方言からみた語音調の構造』(松浦年男先生著)については、第42回金田一京助博士記念賞を受賞しました。
おめでたいニュースが続き、弊社としても大変うれしく思います。工藤先生、松浦先生、おめでとうございます。
工藤真由美著『現代日本語ムード・テンス・アスペクト論』詳細。
松浦年男著『長崎方言からみた語音調の構造』詳細。
ツイート
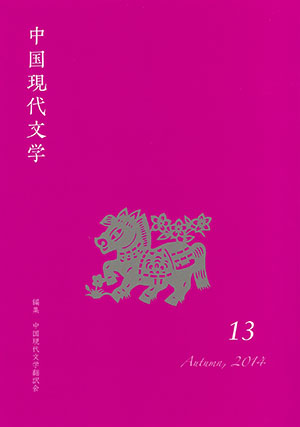
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 13』を刊行しました。
現代中国の文学作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第13号。
韓松「再生レンガ」(SF作家が描く震災後の街)、鮑十「冼阿芳の物語」(広州郊外の庶民の日常)、残雪「旧宅」(かつての家で見た不思議な光景)、梁暁声「鹿心血」(1970年代中露国境での出来事)、于堅「尚義街六号」「紀念堂参観」「故宮参観」(昆明在住詩人の出世作三編)などを掲載する。
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 13』詳細。
ツイート

ひつじ研究叢書(言語編)第122巻、石黒圭・橋本行洋編『話し言葉と書き言葉の接点』を刊行しました。
日本語学会2013年度春季大会(大阪大学)において行われた学会シンポジウムをもとにした論文集である。シンポジウムのパネリストに本テーマに関わる第一線の研究者を加えた、計13名による考察。フィクションの言葉やヴァーチャル方言、語用論的視点やコーパスによる視点をとりあげた共時的研究から、古代語や鎌倉時代、明治時代の言葉などをテーマとする通時的研究まで、言語研究の各方面から書き言葉・話し言葉へ迫る。
執筆者:石黒圭、乾善彦、金水敏、今野真二、定延利之、滝浦真人、田中ゆかり、野田春美、野村剛史、橋本行洋、丸山岳彦、屋名池誠、山本真吾
石黒圭・橋本行洋編『話し言葉と書き言葉の接点』詳細。
ツイート

澤田治美編『ひつじ意味論講座 第3巻 モダリティⅠ:理論と方法』を刊行しました。
言語学のほか、様々な分野の第一線の研究者によるあらたな「意味」研究のシリーズ「ひつじ意味論講座」第3巻。モダリティは、アリストテレス以来、哲学、論理学、言語学、心理学などの分野において、「様相」あるいは「命題のあり方・言表態度」として多くの研究が積み重ねられてきた。本巻では、モダリティの理論的・方法的な側面を論じる。
執筆者:ハイコ・ナロック、飯田隆、堀江薫、仁田義雄、益岡隆志、安達太郎、近藤泰弘、高山善行、澤田治美、安藤貞雄、和佐敦子、阿部宏、宮下博幸
澤田治美編『ひつじ意味論講座 第3巻』詳細。
ツイート

シリーズ言語学と言語教育 32、東眞須美著『比喩の理解』を刊行しました。
本書は比喩の理解にかかわる言語・文化・認知の諸相を認知言語学・応用言語学の観点から解き明かし、言語教育・英語教育に資する提言を行う書である。理論面では比喩の理解に関する国内外でこれまで発信された知見を考察し、比喩の特性と「ひと」の認知とのかかわり、脳内処理の最新の情報、文化的要素が比喩の理解に及ぼす影響などを詳述。理論をふまえた実践面では日本語母語話者と英語母語話者が行う比喩の解釈の類似・相違、その要因について調査データを用いて分析・解説し、日本人英語学習者の言語力向上に役立つヒントを提示している。
東眞須美著『比喩の理解』詳細。
ツイート
『トルコのもう一つの顔』(中公新書)の著者、小島剛一さんがラズ語の辞書の刊行を計画しています。
賛同者を募る講演会を開催しますので、ふるってご参加ください。今年は、大阪、東京、秋田の三箇所で講演会を行います。
名著『トルコのもう一つの顔』には、トルコ共和国で言語を調査している時に出会った、ラズ人たちやラズ人たちの言語のことが述べられています。ラズ語を研究されてきた小島剛一さんが、ラズ語の辞書の刊行を計画しています。
辞書の刊行は、絶滅危惧言語を保存するために大切なことであり、言語学にとって、人類にとって重要であることはもちろんですが、何よりラズ語話者にとって、ラズ語を保存し、持続させていくために、ラズ語の辞書が刊行されることは重要な意味を持ちます。そのために、ラズ語トルコ語日本語を対照した辞書の刊行を実現したいと考えます。
しかしながら、辞書刊行については、日本国内においての需要が、大きいとは思われず、商業的な出版は困難です。何らかの支援を求めることが必要です。ラズ語の辞書を刊行することに賛同下さる方に呼びかけ、ご支援によりまして、刊行を目指したいと思います。ご支援をお願いします。
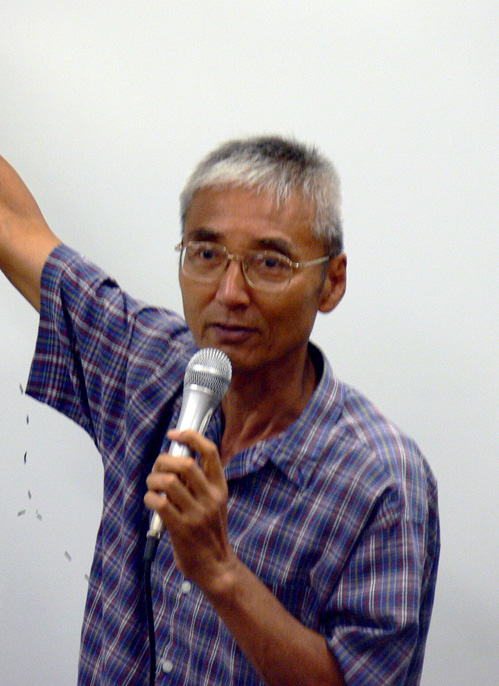
詳細はこちらをご覧下さい。 ご賛同を募集しております文章も作成いたしました。
『国際交流基金日本語教授法シリーズ第2巻 音声を教える』の重版4刷りが出来あがりました。
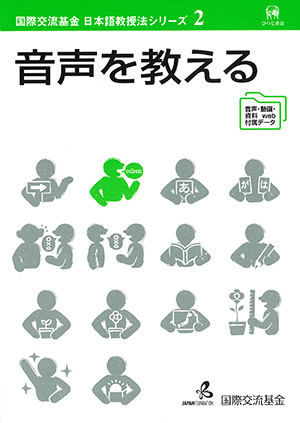
重版のお祝いを著者の磯村一弘先生と十条でおこないました。

『国際交流基金日本語教授法シリーズ第2巻 音声を教える』詳細はこちらをご覧下さい。
ツイート
『トルコのもう一つの顔』(中公新書)の著者、小島剛一さんがラズ語の辞書の刊行を計画しています。
賛同者を募る講演会を開催しますので、ふるってご参加ください。今年は、大阪、東京、秋田の三箇所で講演会を行います。
名著『トルコのもう一つの顔』には、トルコ共和国で言語を調査している時に出会った、ラズ人たちやラズ人たちの言語のことが述べられています。ラズ語を研究されてきた小島剛一さんが、ラズ語の辞書の刊行を計画しています。
辞書の刊行は、絶滅危惧言語を保存するために大切なことであり、言語学にとって、人類にとって重要であることはもちろんですが、何よりラズ語話者にとって、ラズ語を保存し、持続させていくために、ラズ語の辞書が刊行されることは重要な意味を持ちます。そのために、ラズ語トルコ語日本語を対照した辞書の刊行を実現したいと考えます。
しかしながら、辞書刊行については、日本国内においての需要が、大きいとは思われず、商業的な出版は困難です。何らかの支援を求めることが必要です。ラズ語の辞書を刊行することに賛同下さる方に呼びかけ、ご支援によりまして、刊行を目指したいと思います。ご支援をお願いします。
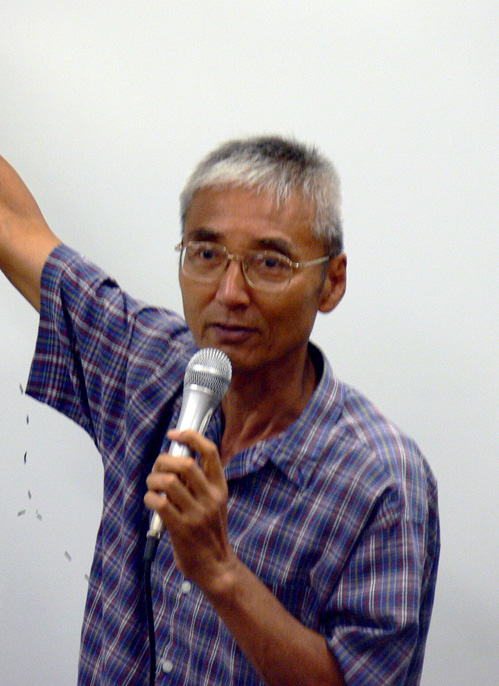
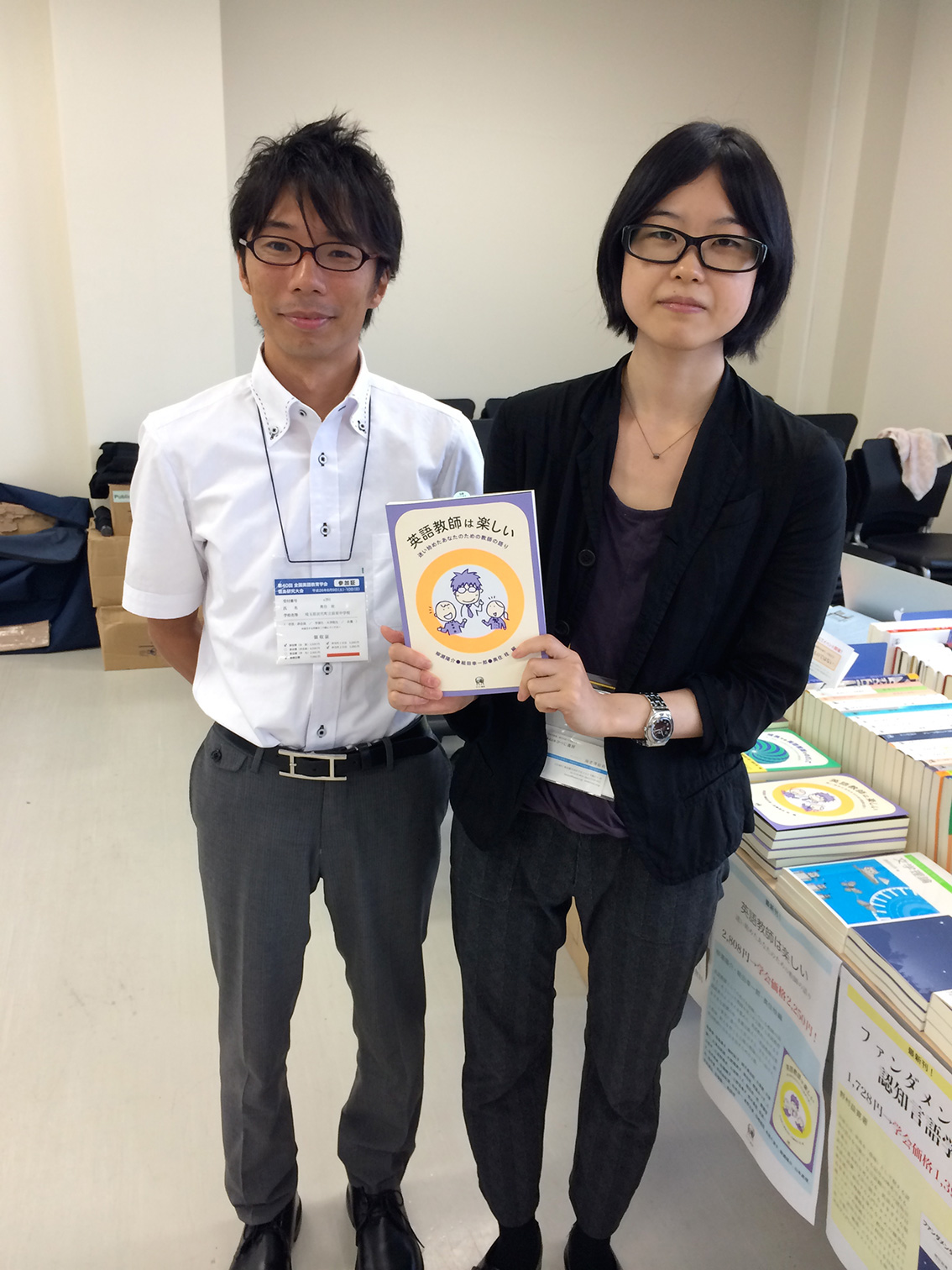
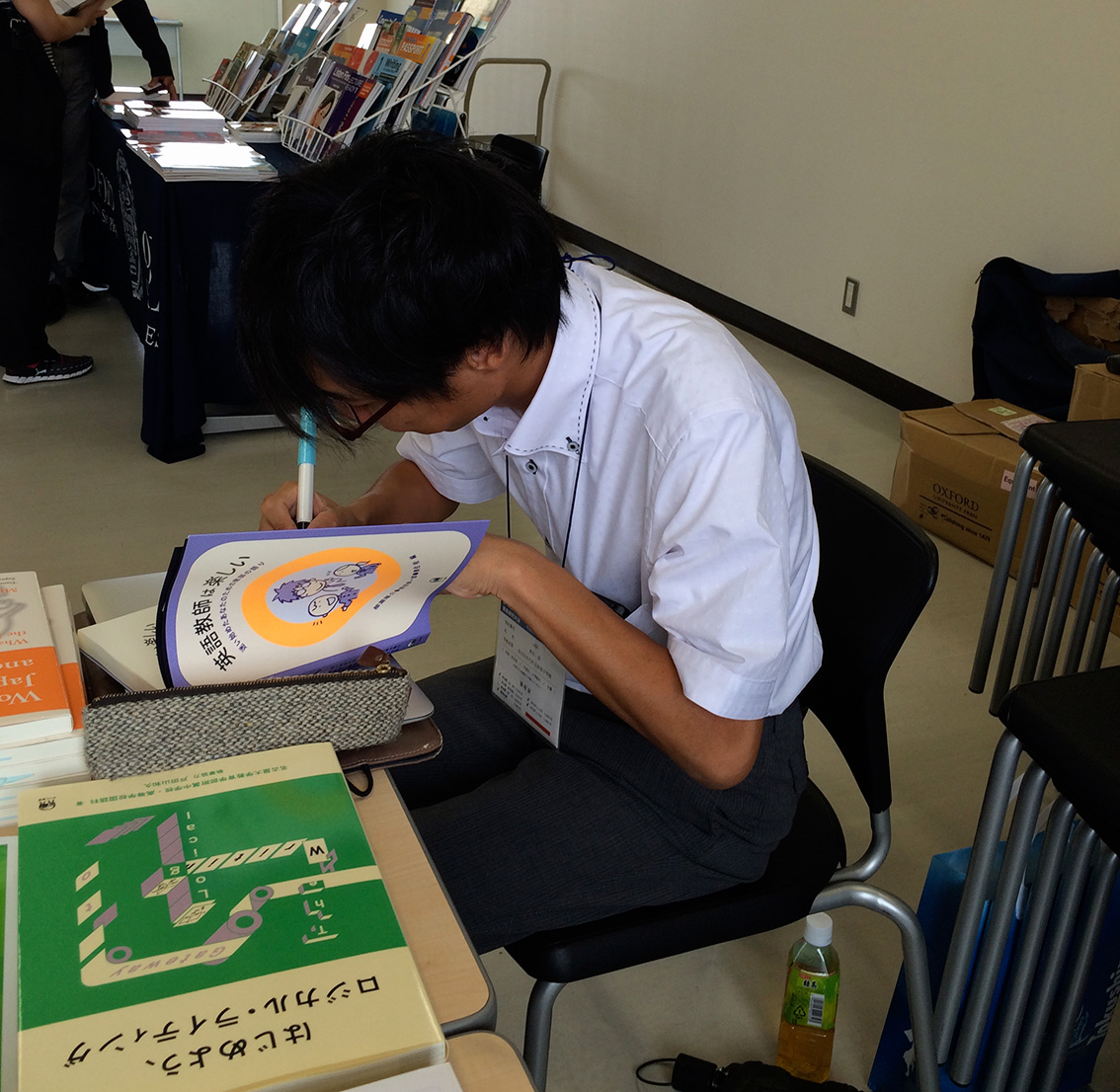
全国英語教育学会第40回徳島研究大会にて、新刊『英語教師は楽しい』を販売しました。ブースでは編者の奥住先生がその場でサインをしてくださいました。
柳瀬陽介・組田幸一郎・奥住桂編『英語教師は楽しい―迷い始めたあなたのための教師の語り』詳細。
ツイート
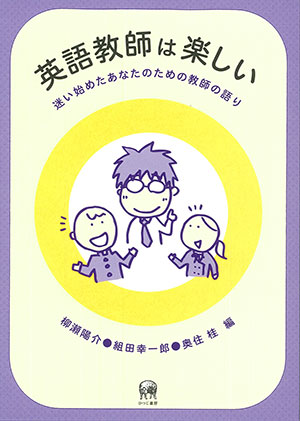
柳瀬陽介・組田幸一郎・奥住桂編『英語教師は楽しい―迷い始めたあなたのための教師の語り』を刊行しました。
英語教師としての喜びを経験している教師の語りと、そういった教師を見つめ支援する英語教育関係者のエッセイを集めた。英語教育におけるさまざまな逆風の中、本書は敢えて「英語教師は楽しい」と事実に基づいて宣言する。学生さん、新人教師、新人を育てる立場の教師の方へ向けた、英語教師の力を引き出すための1冊。
柳瀬陽介・組田幸一郎・奥住桂編『英語教師は楽しい―迷い始めたあなたのための教師の語り』詳細。
ツイート
2014.8.7

8月6日に開催したワークショップは多くの方にご来場いただき盛況の内に終了いたしました。充実した時間をお過ごしいただけたのではないかと存じます。ご参加していただいた方々、暑い中足をお運びいただきましてありがとうございました。
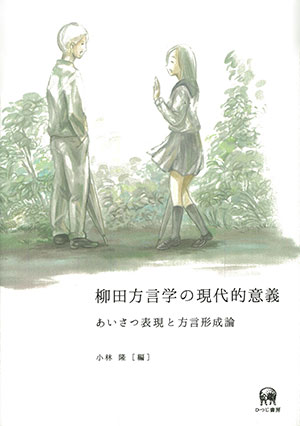

編者の小林隆先生にご来社いただきました。
小林隆編『柳田方言学の現代的意義ーあいさつ表現と方言形成論』を刊行しました。
本書は、柳田国男の没後50年を記念して企画された論文集である。日本の近代方言学に大きな影響を与えた柳田の研究は、その後どのように発展し、現在の方言学に流れ込んでいるのか。本書では、柳田方言学の現代的な意義を、あいさつ表現研究と方言形成論の2つのテーマについて明らかにし、これからの方言研究の新たな可能性を発掘していく。
執筆者:有元光彦、大西拓一郎、小川俊輔、沖裕子、岸江信介、熊谷康雄、小林隆、渋谷勝己、瀬戸口修、田島優、中井精一、中西太郎、灰谷謙二、日高水穂、町博光、鑓水兼貴
小林隆編『柳田方言学の現代的意義ーあいさつ表現と方言形成論』詳細。
ツイート

大島弥生・池田玲子・大場理恵子・加納なおみ・高橋淑郎・岩田夏穂著『ピアで学ぶ大学生の日本語表現ープロセス重視のレポート作成[第2版]』を刊行しました。
2005年の初版刊行後、変化した学生生活に合わせてリニューアル。相手に伝わるレポートの書き方・発表のし方を身につけるための実践的表現活動をタスク化したテキスト。情報収集技術を自分の課題と関連づけて体験し、ピア活動を通して学びのプロセスの共有をめざす。ピア(peer)とは、仲間の意味の英語。授業ではレポートを作成する一連の作業を、学習する者同士で読み合い、話し合いながら進めていく。大学一年生が日本語表現やスタディスキルの基礎を学ぶのに最適の教科書。
★関連イベント開催!
*************************************************
○ピアで学ぶ大学生の日本語表現ープロセス重視のレポート作成
[第2版]刊行記念ワークショップ
改訂版の刊行を記念して、以下の通り模擬授業やプロセスの概要の説明など、ご採用者・ご採用を検討されている方に向けてイベントを行います。
講師 大島弥生、大場理恵子、加納なおみ、岩田夏穂(予定)
日時 2014年8月6日(水) 13時半-16時半(13時開場)
場所 アジア学生文化会館 2階 研修室129
(東京都文京区本駒込2-12-13 都営地下鉄三田線 千石駅(A1出口)より徒歩3分)
参加費 無料(定員50名)
・プログラム
■本書の主旨説明
■プロセスの概要
■模擬授業(ワークショップ)
■事前予約された採用検討者向け相談(アドバイス)
・お申し込み
事前申し込みをお願いします。件名(subject)に「ピア日本語表現イベント」とお書きの上、メールにてお申し込み下さい。
送り先メールアドレス toiawaseアットマークhituzi.co.jp
■お名前
■ご所属名・勤務先
■メールアドレス
■採用をご検討なさっている方向けの相談を受け付けます。相談お申し込みの旨とご相談内容をお書き下さい。
大島弥生・池田玲子・大場理恵子・加納なおみ・高橋淑郎・岩田夏穂著『ピアで学ぶ大学生の日本語表現ープロセス重視のレポート作成[第2版]』詳細。
ツイート

ひつじ研究叢書(言語編) 第28巻、秋元実治著『増補 文法化とイディオム化』を刊行しました。
文法化研究は特に海外で盛んである。本書はマクロ的言語変化理論の構築を超える、史的言語研究としての文法化に関する包括的研究である。今回の改訂では、新たに競合(rivalry)についての論文を2編加え、さらに旧版後の研究成果を補章として盛り込んだ。なお、参考文献も最新のものを加えて充実させた。
秋元実治著『増補 文法化とイディオム化』詳細。
ツイート
2014.7.1

獨協大学で6月29日に行われた講演会は多くの方にご来場いただき、盛況の内に終了いたしました。このテーマに関心を持っている方がたくさんいらっしゃり嬉しく思いました。
先行販売をした『学校英語教育は何のため?』も多くの方にお買い上げいただきました。まことにありがとうございました。
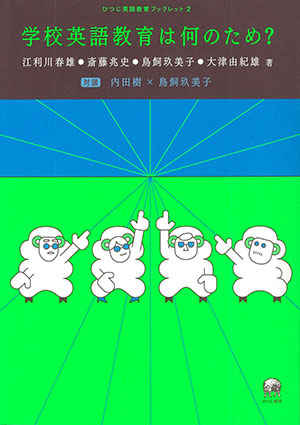
江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子・大津由紀雄著 対談 内田樹×鳥飼玖美子『学校英語教育は何のため?』を刊行しました。
政府や経済界は「グローバル人材」という1割ほどのエリート育成を学校英語教育の目的とし、小学校英語の低年齢化と教科化、中学校英語での英語による授業実施、TOEFL等の外部検定試験の導入などの無謀な政策を進めている。このままでは9割が切り捨てられる。本書では、公教育で英語を教える目的とは何かという根本問題に立ち返り、英語教育の目指すべき方向を提言する。内田樹、鳥飼玖美子による白熱した対談も収録。
★関連イベント開催! 『学校英語教育は何のため?』が初お披露目となります。ぜひふるってご参加ください。
*************************************************
獨協大学創立50周年記念事業 外国語教育研究所 第4回公開研究会
「日本における英語教育の現状と課題」
http://www.dokkyo.ac.jp/event/detail/id/4833/publish/1/
日時:平成26 (2014) 年6月29日(日)13時00分 - 15時30分(開場12時30分)
入場無料・予約不要
会場:獨協大学天野貞祐記念館大講堂
埼玉県草加市学園町1-1 東武スカイツリーライン「松原団地駅」徒歩5分
(上野から松原団地駅まで約30分)
http://www.dokkyo.ac.jp/daigaku/a02_02_j.html
主催:獨協大学外国語教育研究所(通称: AMANO外国語研究所)
講師:(五十音順)
江利川春雄氏
大津由紀雄氏
斎藤兆史氏
鳥飼玖美子氏
なお、研究会終了後、レセプションがございます。ご参加ください。
問い合わせ先:獨協大学外国語教育研究所 048-946-1846
*************************************************
江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子・大津由紀雄著 対談 内田樹×鳥飼玖美子『学校英語教育は何のため?』詳細。
ツイート
2014.6.25
研究書出版の相談会、オープンオフィス、開催中です。
オープンオフィス、詳細。
ツイート
2014.6.20
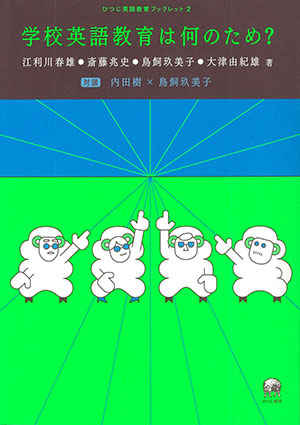
江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子・大津由紀雄著 対談 内田樹×鳥飼玖美子『学校英語教育は何のため?』を刊行します。
政府や経済界は「グローバル人材」という1割ほどのエリート育成を学校英語教育の目的とし、小学校英語の低年齢化と教科化、中学校英語での英語による授業実施、TOEFL等の外部検定試験の導入などの無謀な政策を進めている。このままでは9割が切り捨てられる。本書では、公教育で英語を教える目的とは何かという根本問題に立ち返り、英語教育の目指すべき方向を提言する。内田樹、鳥飼玖美子による白熱した対談も収録。
★関連イベント開催! 『学校英語教育は何のため?』が初お披露目となります。ぜひふるってご参加ください。
*************************************************
獨協大学創立50周年記念事業 外国語教育研究所 第4回公開研究会
「日本における英語教育の現状と課題」
http://www.dokkyo.ac.jp/event/detail/id/4833/publish/1/
日時:平成26 (2014) 年6月29日(日)13時00分 - 15時30分(開場12時30分)
入場無料・予約不要
会場:獨協大学天野貞祐記念館大講堂
埼玉県草加市学園町1-1 東武スカイツリーライン「松原団地駅」徒歩5分
(上野から松原団地駅まで約30分)
http://www.dokkyo.ac.jp/daigaku/a02_02_j.html
主催:獨協大学外国語教育研究所(通称: AMANO外国語研究所)
講師:(五十音順)
江利川春雄氏
大津由紀雄氏
斎藤兆史氏
鳥飼玖美子氏
なお、研究会終了後、レセプションがございます。ご参加ください。
問い合わせ先:獨協大学外国語教育研究所 048-946-1846
*************************************************
江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子・大津由紀雄著 対談 内田樹×鳥飼玖美子『学校英語教育は何のため?』詳細。
ツイート
2014.6.10

金水敏・高田博行・椎名美智編『歴史語用論の世界ー文法化・待遇表現・発話行為』を刊行しました。
時代や文化の異なる社会で、人は場面に応じて言葉をどう使い分けてきたのか? その言葉の使用法は時代と共にどう変わってきたのか? この問いに答えるべく本書では、文法化と待遇表現について論じたあと、人を取り調べる、人を説得する、人に伝えるという観点から英語史・日本語史・ドイツ語史におけるトピックを掘り起こし、新たな研究へと誘う。執筆者:小野寺典子、福元広二、森山由紀子、椎名美智、高田博行、諸星美智直、片見彰夫、中安美奈子、芹澤円、森勇太、高木和子
金水敏・高田博行・椎名美智編『歴史語用論の世界』詳細。
ツイート
2014.6.6
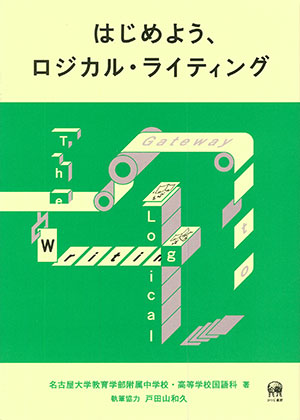
名古屋大学教育学部附属中学校・高等学校国語科著 執筆協力・戸田山和久『はじめよう、ロジカル・ライティング』を刊行しました。
「PISA型読解力」向上を目指し、『論文の教室』の戸田山和久名古屋大学教授と意見交換しながら作った日本語表現の教科書。「論理的」とはどういうことかに始まり、他者の意見やデータを分析し、自己の主張や提案につなげるまでを一冊で身につける。中学生から社会人までを対象とし、自分の言いたいことを伝えるだけではなく、他者の意見と建設的に関わりながら問題解決に当たる、これからの市民社会の担い手に必要な資質を育てる。
名古屋大学教育学部附属中学校・高等学校国語科著 執筆協力・戸田山和久『はじめよう、ロジカル・ライティング』詳細。
ツイート
2014.6.4

神奈川大学言語学研究叢書 4、富谷玲子・彭国躍・堤正典編『グローバリズムに伴う社会変容と言語政策』を刊行しました。
21世紀に入ってから世界の言語事情は大きく移り変わっている。本書は、グローバリズムに伴う社会変容と言語政策について考察した論集である。アジア地域における日本、中国、韓国、シンガポール、ロシア、および移民政策とのかかわりにおけるドイツ、アメリカの言語政策のいまを分析したものである。執筆者:富谷玲子、彭国躍、堤正典、細田由利、デイビット・アリン、近藤美帆、小林潔、石林、徐峰、平高史也、松岡洋子、福永由香
富谷玲子・彭国躍・堤正典編『グローバリズムに伴う社会変容と言語政策』詳細。
ツイート
2014.6.02
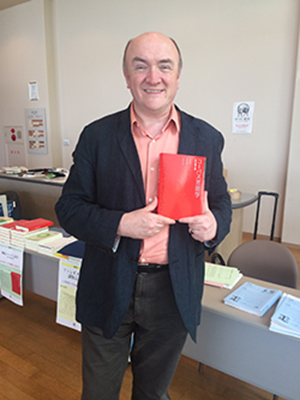
LCSAW2014(第2回学習者コーパス国際シンポジウム)で、『概説コーパス言語学』の原著者のお一人であるトニー・マケナリー先生とお会いして、記念写真を撮りました。
トニー マケナリー・アンドリュー ハーディー著 石川慎一郎訳『概説コーパス言語学』詳細。
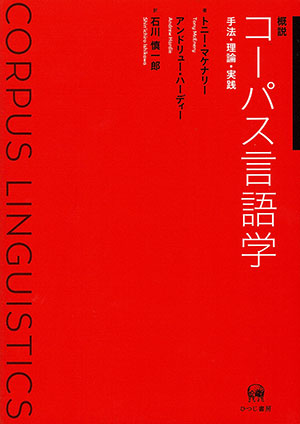
トニー マケナリー・アンドリュー ハーディー著 石川慎一郎訳『概説コーパス言語学ー手法・理論・実践』を刊行しました。
類書にない幅広い視点から、コーパス言語学の本質と展望を俯瞰した斬新な入門書として評価の高いTony McEnery & Andrew HardieのCorpus Linguistics(CUP, 2012)の全邦訳。著者は、コーパス言語学と談話分析・社会言語学・言語類型論・認知言語学・心理言語学等の連携の可能性を鮮やかに描き出す。巻末には詳細な用語解説も用意されており、言語学全般の入門用教科書としても最適。
トニー マケナリー・アンドリュー ハーディー著 石川慎一郎訳『概説コーパス言語学』詳細。
ツイート
2014.5.29
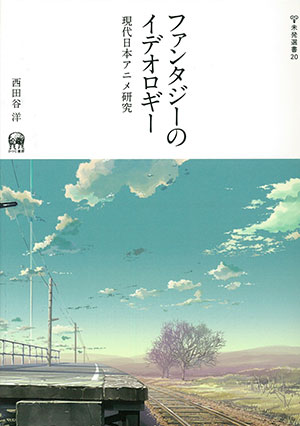
西田谷洋著『ファンタジーのイデオロギー ー現代日本アニメ研究』を刊行しました。
かつては小説や詩の読書経験が文学能力を形作ったが、現在の読み手・書き手にとってはアニメや漫画やゲームなどのポピュラーカルチャーがその基盤の重要な位置を占めている。この日常性を基盤とした文学能力の形成をふまえ、本書は21世紀初頭に発表されたリミテッド・アニメーションすなわちTVアニメの物語表現/物語内容について、現代思想・批評理論に関わる操作概念を援用して分析した、新たな時代の文学研究である。
西田谷洋著『ファンタジーのイデオロギー』詳細。
ツイート
2014.5.28

春木仁孝・東郷雄二編『フランス語学の最前線2 【特集】時制』を刊行しました。
フランス語学の最先端の研究を紹介するシリーズ第2巻。本巻は時制をテーマに、広く一般言語学的視野を射程に収めた論文11本を集める。各時制についての研究だけでなく、時制体系全体や時制と視点に関する研究も収めるが、バンヴェニストに端を発する発話主体や発話態度に注目した論文も多く、時制研究に大きな刺激を与えることが期待される。執筆者は、春木仁孝、東郷雄二、西村牧夫、大久保伸子、渡邊淳也、岸彩子、小熊和郎、井元秀剛、高橋克欣、江川記世子、阿部宏。
春木仁孝・東郷雄二編『フランス語学の最前線2 【特集】時制』詳細。
ツイート
2014.5.26
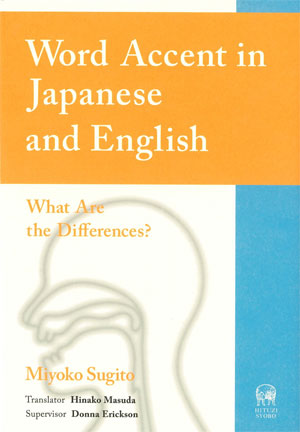
杉藤美代子著 増田斐那子訳 ドナ・エリクソン監修『Word Accent in Japanese and English: What Are the Differences?』を刊行しました。
日本語は高さアクセント、英語は強さアクセントと言われてきたが、本当にそうなのか、両者はいったいどこがどう違うのか。筆者は研究の過程で、日本語(特に関西アクセント)と英語のアクセントには思いがけない類似点があることを見出した。本書はアクセントに関する入門書であり、多くの疑問点への回答書でもあります。ぜひご一読ください。『日本語のアクセント、英語のアクセント』(2012 ひつじ書房)の英語版。
杉藤美代子著 増田斐那子訳 ドナ・エリクソン監修『Word Accent in Japanese and English: What Are the Differences?』詳細。
ツイート
2014.5.19

新刊・近刊のご案内の冊子『未発ジュニア版』を発送しました。
『未発ジュニア版』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いします。
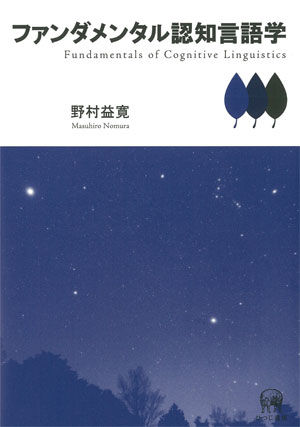
野村益寛著『ファンダメンタル認知言語学』を刊行しました。
言語とは、世界を〈意味〉として捉える認知の営みを可能にする記号の体系である。本書は、このような言語観に立つ認知言語学の基本的な考え方を、英語および日本語の語彙・文法に関するさまざまな現象を通して紹介する入門テキストである。各章末には理解を深めるための練習問題・レポート課題をつけ、教室でのディスカッションや宿題として利用できるようにした。認知言語学のテキストとしての他、言葉に「敏感」になることを目指した英語学入門のテキストとしても使える。
野村益寛著『ファンダメンタル認知言語学』詳細。
ツイート
2014.5.7

西田谷洋著『学びのエクササイズ文学理論』を刊行しました。
文学を読む、論じるための主要な理論を15の章に分けて解説する。文学理論を知ることは、小説の理解を深めるのみならず、それを支える社会や文化を思考することにも繋がり、人生においてより広い視野を持つ助けとなる。本書は国内外の研究成果をコンパクトにまとめ、文学の専門でなくても興味のあるところから文学理論とはどのようなものかを知ることができる、最新の「読むための理論」である。
西田谷洋著『学びのエクササイズ文学理論』詳細。
ツイート
2014.5.1

シリーズ言語学と言語教育 30、筒井通雄、鎌田修、ウェスリー・M・ヤコブセン編『日本語教育の新しい地平を開くー牧野成一教授退官記念論集』を刊行しました。
本書は、2012年5月、プリンストン大学・牧野成一教授の退官記念を兼ねて開かれた「第19回プリンストン日本語教授法フォーラム特別大会」での3つのラウンドテーブルにおいて発表された論文と各ラウンドテーブルの総括をまとめたものである。言語学、文化学、第二言語習得、教授法、およびOPIにおける問題を、牧野先生を含む日米第一線の研究者が日本語教育の観点から論じた論文と討論総括記事(マグロイン花岡直美、筒井通雄、ナズキアン富美子)を掲載する。論文執筆者:ウェスリー・M・ヤコブセン、松本善子、岡まゆみ、當作靖彦、牧野成一、坂本正、畑佐由紀子、ハドソン遠藤陸子、鎌田修、渡辺素和子、ジュディス・リスキン-ガスパロ
筒井通雄、鎌田修、ウェスリー・M・ヤコブセン編『日本語教育の新しい地平を開く』詳細。
ツイート
2014.4.23
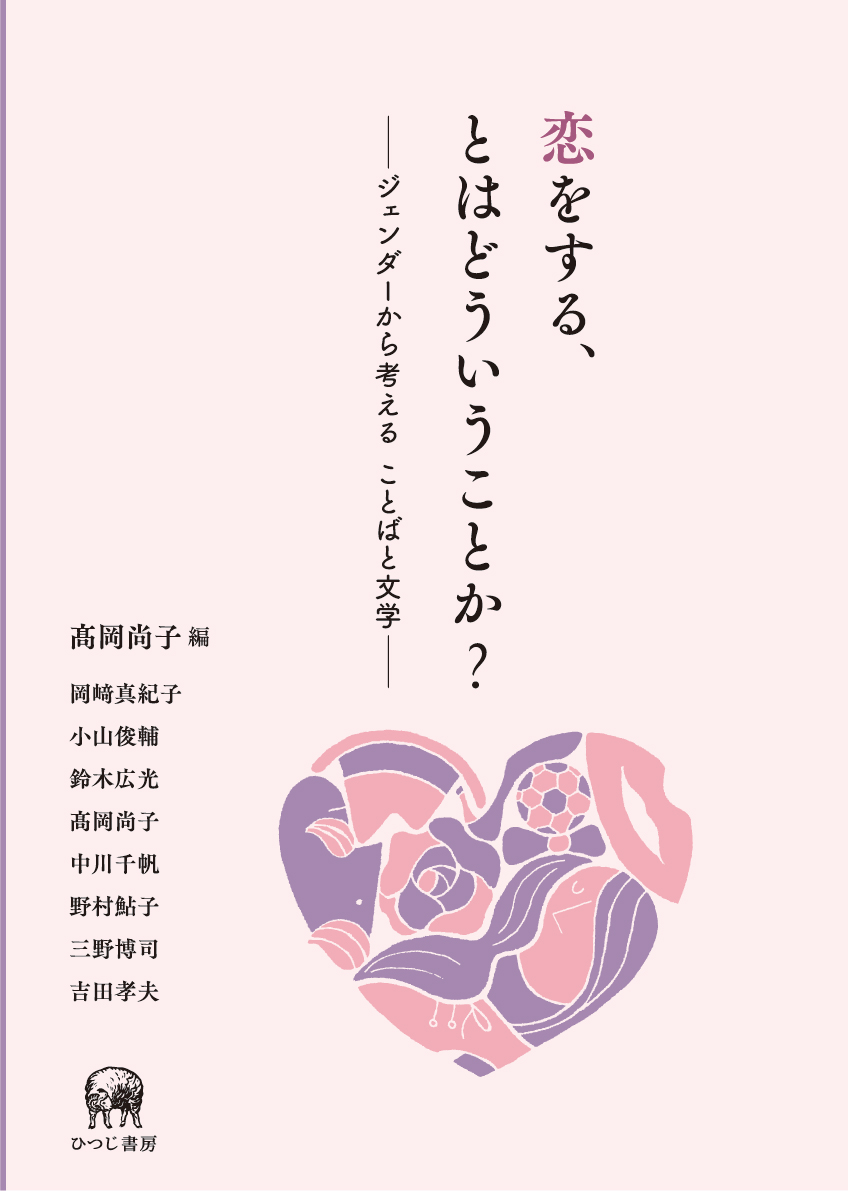
髙岡尚子編『恋をする、とはどういうことか?ージェンダーから考える ことばと文学』を刊行しました。
「恋」をキーワードに、ジェンダーの概念を用いて、文学作品やことばのあり方を考察する方法を示す。第一部は、ジェンダーに関する基礎概念を詳説した6章で構成されている。第二部では、西洋の神話・伝承物語から、近現代の恋愛・ロマンス小説、また、日本の短歌や中国の恋愛映画まで、「恋とジェンダー」をテーマに、各国文化と文学の読み方を提案している。ジェンダーの基礎のみならず、文学の新しい切り口にふれたい読者にとって有益な1冊。
髙岡尚子編『恋をする、とはどういうことか?』詳細。
ツイート

遠藤喜雄著『日本語カートグラフィー序説』を刊行しました。
生成文法の新しい流れであるカートグラフィー研究についての日本初の体系的な解説書。最先端の言語理論であるミニマリズムと相補いあう実りの多い関係をわかりやすく解説。今までの生成文法では扱えなかった、談話、語用論のトピックまでをも広くカバーする。言語学の基礎をゼロから解説するところからはじめて、日本語について卒業論文、修士論文、博士論文を書くところまでを未解決の具体的な問題に触れながら紹介。日本語を中心に、類型論的な広い視点で言語を見るのに最適の書。
遠藤喜雄著『日本語カートグラフィー序説』詳細。
ツイート

金澤裕之編『日本語教育のためのタスク別書き言葉コーパス』を刊行しました。
日本語母語話者と非母語話者(韓国語・中国語)各30名の書き言葉資料(日本語作文等)を収集、評価基準・レイティング方法等について解説を加えた。また、非母語話者における全12 種類のタスクについての総合評価結果をレベル別・母語別にまとめ、特徴を示したほか、本資料を活用した研究の実例も紹介。全作文データを収めたCD-ROM付。執筆者:金澤裕之、嵐洋子、植松容子、奥野由紀子、金庭久美子、金蘭美、西川朋美、橋本直幸
金澤裕之編『日本語教育のためのタスク別書き言葉コーパス』詳細。
ツイート
What's new

シリーズ文化研究 3、竹内瑞穂著『「変態」という文化』を刊行しました。
激動する政治経済と華やかなモダン文化に彩られた日本の1920〜30年代は、奇妙にも「変態」で満ち溢れた時代でもあった。そこには「変態」を治そうと奮闘する者がいる一方で、我こそは「変態」であると声高に宣言する者もいた。本書は、当時の文学・心理学・映画・マスメディア等の多様な領域を「変態」という切り口で分析。それが日常世界を組み替える〈小さな革命〉を垣間見せるものとして〈消費〉されていたことを明らかにする。
竹内瑞穂著『「変態」という文化』詳細。
ツイート
2014.4.1

新入社員1名を迎え、入社式をおこないました。
2014.3.28

篠原和子・宇野良子編『オノマトペ研究の射程』を重版しました。
近年、言語学ばかりでなく心理学や工学更にはアートと、様々な分野から注目されているのが、オノマトペである。音と意味、あるいは身体と言葉の結びつきと関わるこのトピックへの、多種多様な観点からの分析を紹介し、問題の核心へと迫ることを目指す。【1.音象徴】Brent Berlin、篠原和子・川原繁人、平田佐智子【2.文法とオノマトペ】喜多壮太郎、虎谷紀世子、秋田喜美、宇野良子・鍜治伸裕・喜連川優、浜野祥子【3.発達的視点】佐治伸郎・今井むつみ、鈴木陽子【4.創造性の源】井上加寿子、深田智、夏目房之介【5.感覚の構成】大海悠太・宇野良子・池上高志、近藤敏之【6.教育・工学・アートへの応用】渡邊淳司・早川智彦・松井茂;金子敬一・都田青子、坂本真樹・渡邊淳司【7.研究史】秋田喜美
篠原和子・宇野良子編『オノマトペ研究の射程』詳細。
ツイート
2014.3.27
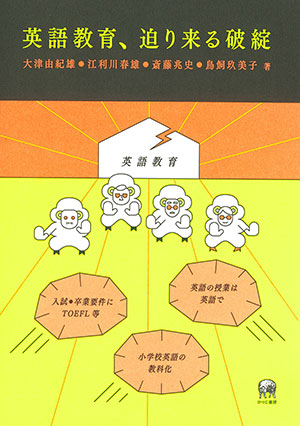
大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子著『英語教育、迫り来る破綻』を重版しました。(4刷です!)
大学の入試や卒業要件にTOEFL等の外部検定試験を導入する案が、自民党教育再生実行本部や政府の教育再生実行会議によって提案された。しかし、もしそれが現実となれば、学校英語教育が破綻するのは火を見るよりも明らか。危機感を持った4人が、反論と逆提案に立ち上がった……。
☆小学校英語教科化の問題点、白熱した座談会、関連年表なども収録。
大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子著『英語教育、迫り来る破綻』詳細。
ツイート
2014.3.25

府川源一郎著『明治初等国語教科書と子ども読み物に関する研究ーリテラシー形成メディアの教育文化史』を刊行しました。
明治期の子どもたちは、どのようにリテラシーを身につけたのか。そのかぎの一つは、明治期のベストセラーである『小学読本』にある。本書は、「読本=国語教科書」をはじめとして、子ども読み物や挿絵、少年雑誌などを「リテラシー形成メディア」と捉え、それらの相互関係を数多くの新資料を駆使して解明した画期的成果である。明治初年の子ども向け翻訳啓蒙書、小学校用の読本、修身教科書と修身読み物などが取り上げられており、教科書研究として教育史研究の進展に寄与するだけではなく、その影響は、日本語史研究、文学史研究、文化史研究にも及ぶだろう。
府川源一郎著『明治初等国語教科書と子ども読み物に関する研究』詳細。
ツイート
2014.3.24

都留文科大学英文学科創設50周年記念研究論文集編集委員会編『言語学、文学そしてその彼方へー都留文科大学英文学科創設50周年記念研究論文集』を刊行しました。
本書は、都留文科大学文学部英文学科創設50周年を記念して専任教員、名誉教授、本学英文学科卒業の研究者が寄稿した26編の論文からなる論文集。最新の言語学(生物言語学、認知言語学、コーパス言語学、語用論、第2言語習得研究など)、英語教育学、英文学、米文学、英語文学また、生物学、物理学と幅広い分野の論文が収められている。執筆者:(専任)今井隆、大平栄子、奥脇奈津美、竹島達也、中地幸、福島佐江子、松土清(名誉教授)窪田憲子、依藤道夫、(本学英文学科卒業の研究者)赤穂栄一、内藤徹、野中博雄、竹村雅史 、沢野伸浩 、斎藤伸治 、宮岸哲也 、澤崎宏一 、松岡幹就 、上原義正 、山田昌史 、髙橋愛 、堀内大 、寺川かおり 、瀧口美佳 、花田愛 、安原和也 (五十音順)
都留文科大学英文学科創設50周年記念研究論文集編集委員会編『言語学、文学そしてその彼方へ』詳細。
ツイート

ひつじ研究叢書(言語編)第120巻、松浦年男著『長崎方言からみた語音調の構造』を刊行しました。
長崎方言の語音調(アクセント・トーン)について、フィールドワークによって得られた資料をもとに、幅広い範囲の語種における分布を体系的に記述する。そして、音調体系の異なる東京方言との比較を通して両方言で共通して見られる特徴を明らかにし、単語トーンと分類される言語にも抽象的なレベルにはアクセントの表示があるという説を唱え、その妥当性を示す。巻末には約2000語からなるアクセント資料を収録する。
松浦年男著『長崎方言からみた語音調の構造』詳細。
ツイート
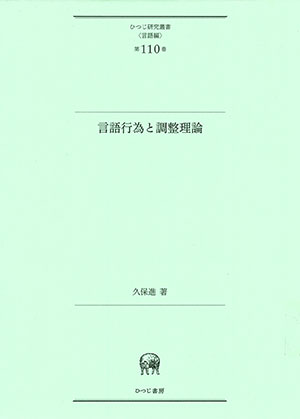
ひつじ研究叢書(言語編)第110巻、久保進著『言語行為と調整理論』を刊行しました。
本書では、調整理論によって補強された新たな言語行為論を構築するとともに、会話の理論へのサールの懐疑的理由に対する反駁を通して、サールが会話の理論に対して求める「単独の発語内行為の理論と同程度の厳密さ」を備えた会話の理論を提案している。この会話の理論は、従来の言語行為論と異なり、情報伝達的会話のみならず調整的会話の構造や志向性との関係、そして、会話の流れをも説明することができる一般理論である。
久保進著『言語行為と調整理論』詳細。
ツイート

植田栄子著『診療場面における患者と医師のコミュニケーション分析』を刊行しました。
本書は、医療コミュニケーションの中でも最も基本となる一般外来診療場面に注目し、計量的・質的アプローチの両面から実証研究を行う。78の実際の診療場面について、患者-医師、東京-大阪、男性患者-女性患者を対照分析し、その分析法(RIAS)のカテゴリー化の問題(多重性、多義性、非明確性)等の批判的検討を行い改善案を提示。さらに、ラポール(絆)構築とコンフリクト回避の構造を相互行為的にケース分析で明らかにした。
植田栄子著『診療場面における患者と医師のコミュニケーション分析』詳細。
ツイート

ひつじ研究叢書(言語編)第115巻、新屋映子著『日本語の名詞指向性の研究』を刊行しました。
日本語の文には名詞を文構成の柱とするものが少なくない。名詞の統語的機能はまず第一に主語や目的語になることであるが、述語としての名詞には名詞の枠におさまらない広がりがある。述語名詞は何を表わし、どのように働くのか。日本語の名詞文は文章のなかでどのような態様を見せるのか。名詞および名詞文の観察を通して、日本語らしさの一端を名詞が担っていることを明らかにする。
新屋映子著『日本語の名詞指向性の研究』詳細。
ツイート

ひつじ研究叢書(言語編)第119巻、高山道代著『平安期日本語の主体表現と客体表現』を刊行しました。
本書は平安期日本語動詞述語文の主要な格である主語表示および対象語表示の形態についての記述的研究の成果であり、この時代の日本語における名詞句の格システムの一端を明らかにしたものである。さらに、名詞句の文法的諸側面について類型学的な観点もとりいれ分析を加えることによって、平安期日本語の主体表現と客体表現の特徴を明らかにし、古代日本語研究への提言をおこなう。
高山道代著『平安期日本語の主体表現と客体表現』詳細。
ツイート
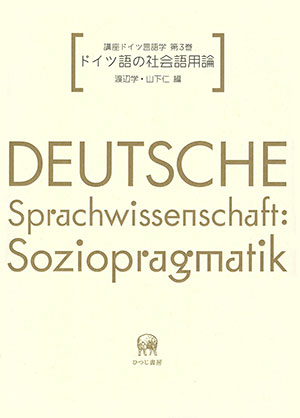
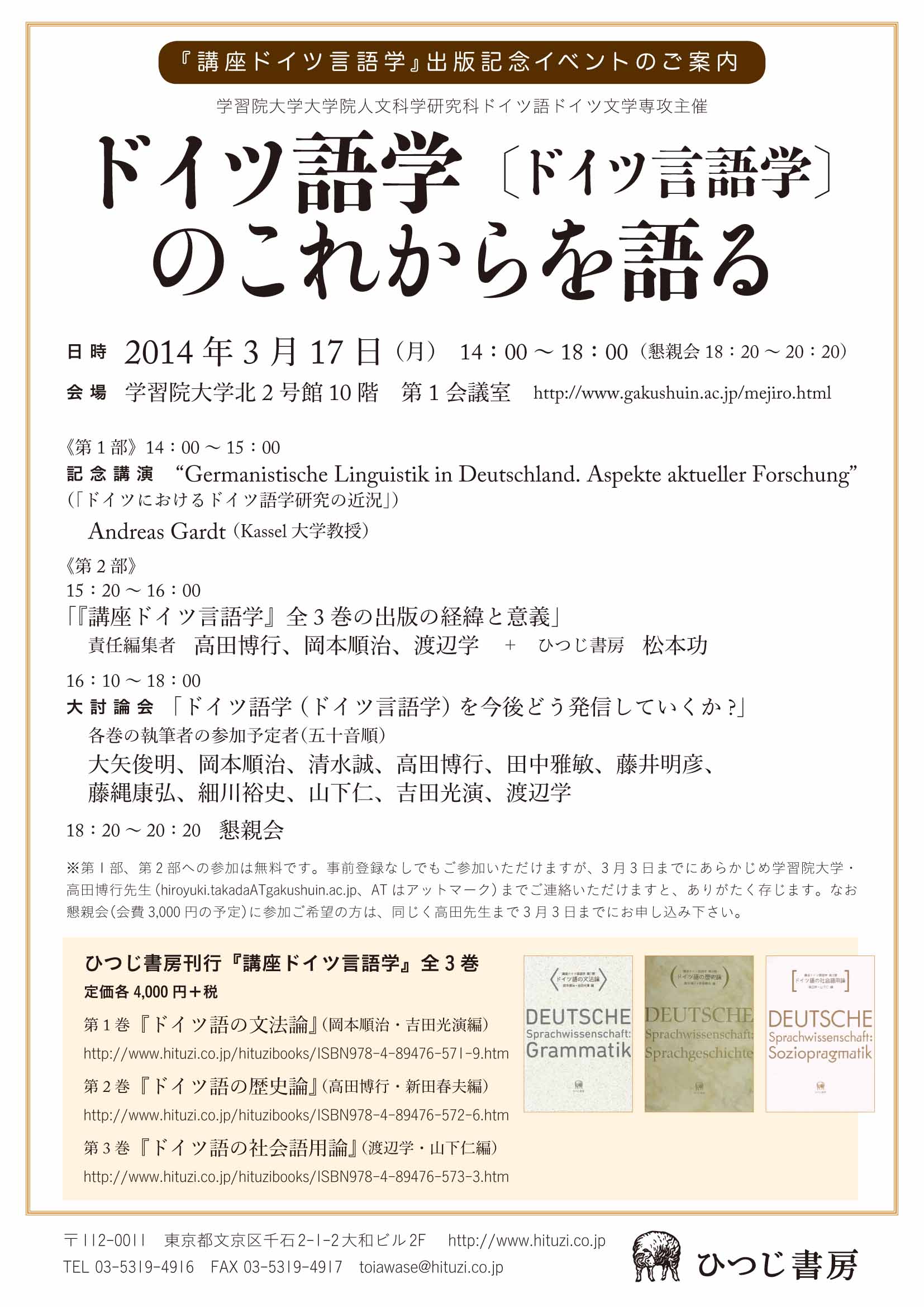
「ドイツ語学 〔ドイツ言語学〕のこれからを語る」
(学習院大学大学院人文科学研究科ドイツ語ドイツ文学専攻主催)
日時 2014年3月17日(月) 14:00〜18:00(懇親会18:20〜20:20)
会場 学習院大学北2号館10階 第1会議室
ご案内(PDF)
渡辺学・山下仁編『講座ドイツ言語学 第3巻 ドイツ語の社会語用論』詳細。
ツイート

ひつじ研究叢書(言語編)第118巻、金英周著『名詞句とともに用いられる「こと」の談話機能』を刊行しました。
日本語の話し言葉には、「ねえ、ちょっとそこの栓抜きとって」「栓抜き?ああ、これのことか」のように、名詞句に一見なんの意味も持たない「〜のこと」が付加された形が頻繁に現れる。本書では、なぜ、このようなノコトが使用されるのかという疑問について検討し、ノコトは談話において、話し手と聞き手が「知らないこと」と「知っていること」を結びつける際に使用される、知識管理の標識であるという明快な答えを見出した。
金英周著『名詞句とともに用いられる「こと」の談話機能』詳細。
ツイート
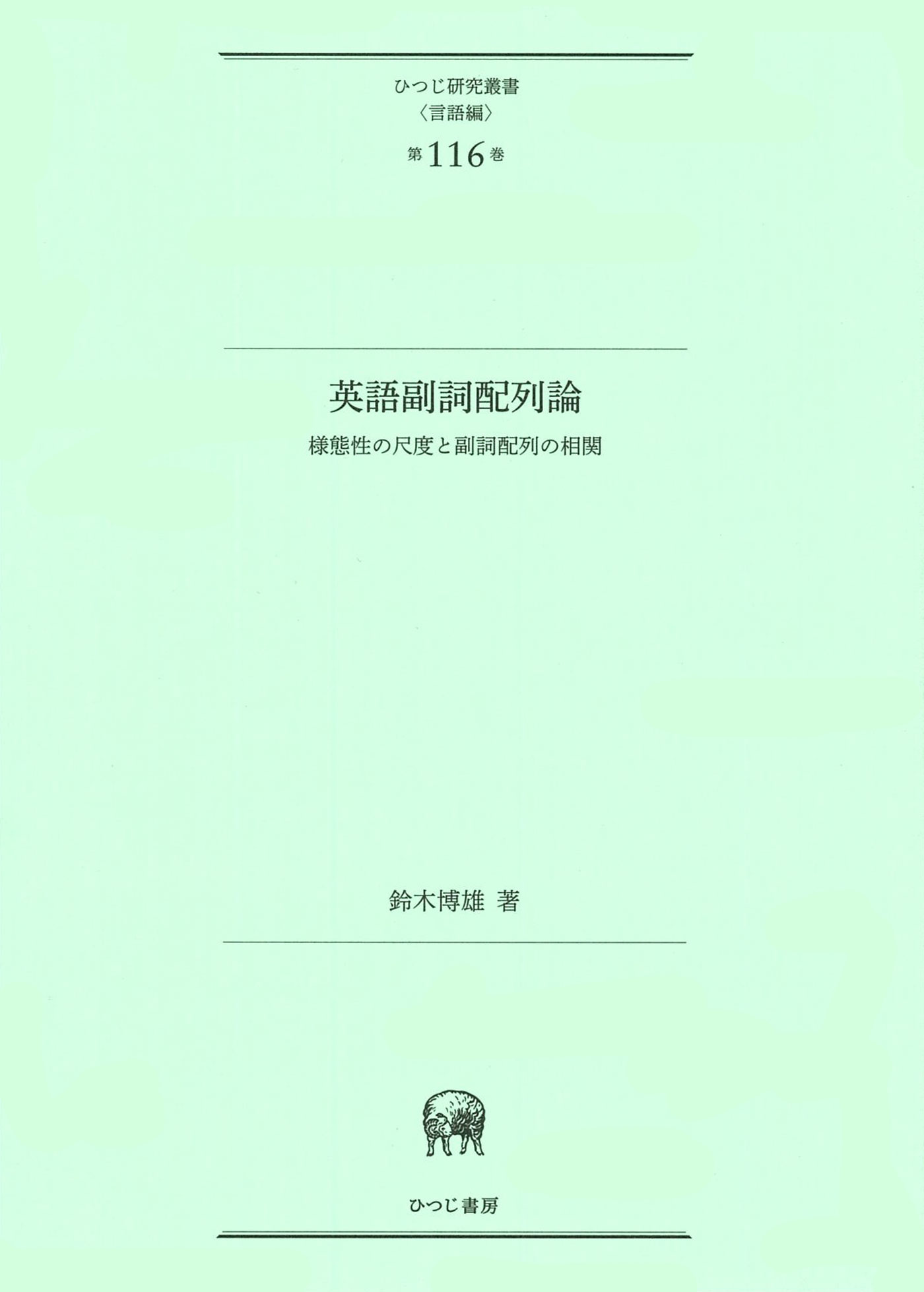
ひつじ研究叢書(言語編)第116巻、鈴木博雄著『英語副詞配列論ー様態性の尺度と副詞配列の相関』を刊行しました。
「様態性の尺度」を中核に据え、豊富な用例の緻密な解釈を踏まえながら、英語副詞の統語的生起実態と意味的連続性を解明する。副詞のカテゴリーや統語・意味現象の違いに応じて、統語論、機能文法論、語彙意味論、形式意味論等の知見を的確に援用し、独創的な叙述・修飾構造論を構築する。副詞のカテゴリー別習得順序を究明するための原動力にも結びつけることができる、英文法論における副詞論を再考する一冊。
鈴木博雄著『英語副詞配列論ー様態性の尺度と副詞配列の相関』詳細。
ツイート
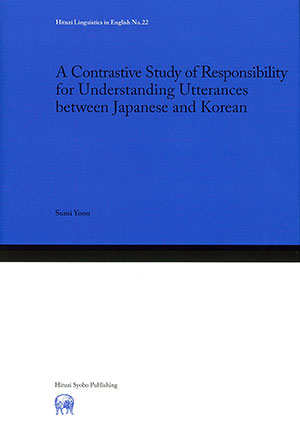
Hituzi Linguistics in English No.22、尹秀美著『A Contrastive Study of Responsibility for Understanding Utterances between Japanese and Korean』を刊行しました。
日本語と韓国語は語彙、語順、敬語など文法面での類似点が多いため、会話レベルでも両言語は同じような振る舞いをすると思いがちである。事実、ハインズは、発話理解の責任主体という観点から英語は話し手責任、日本語と韓国語は聞き手責任の言語だと主張している。しかし、本書では、対応する場面で用いられる日本語と韓国語の具体的な発話データに基づいて、韓国語は、日本語と異なり、話し手責任の言語であることを例証する。
尹秀美著『A Contrastive Study of Responsibility for Understanding Utterances between Japanese and Korean』詳細。
ツイート

Hituzi Linguistics in English No.21、山本尚子著『A Cognitive Pragmatic Analysis of Nominal Tautologies』を刊行しました。
英語の名詞句トートロジーに関する先行研究は豊富にあるが、日本語の多様な名詞句トートロジー表現形式を包括的に説明できるものはこれまでになかった。本書は、日本語の名詞句トートロジー発話の解釈メカニズムについて、認知語用論の視点から分析を行い、名詞句トートロジーが手続き的情報をコード化している表現形式であることを提案する。
山本尚子著『A Cognitive Pragmatic Analysis of Nominal Tautologies』詳細。
ツイート

Hituzi Linguistics in English No.20、守屋靖代著『Repetition, Regularity, Redundancy: Norms and Deviations of Middle English Alliterative Meter』を刊行しました。
チョーサーと同時代の14世紀後半、英国中西部で隆盛を極めた中英語頭韻詩の韻律を解明する。主要な中英語頭韻詩約20作品23,000余行のコーパスを作成し、現代言語学の音韻論、韻律理論に基づき、音韻と統語の関係から全体に共通するテンプレートを構築した上で、逸脱のリミットと個々の作品の特徴を解明する。中英語特有のリズム、強勢と弱勢の拮抗、音調、抑揚、韻律等の考察から、頭韻詩における繰返しの機能と意義を示唆する。
守屋靖代著『Repetition, Regularity, Redundancy』詳細。
ツイート

シリーズ言語学と言語教育 31、藤原康弘著『国際英語としての「日本英語」のコーパス研究ー日本の英語教育の目標』を刊行しました。
日本の英語教育の目標は「ネイティブ英語」か、「日本英語」か? 言語学、応用言語学、第二言語習得論の主流は母語話者目標を前提としてきたが、はたして日本のELTにおいて妥当か。この命題に対し、本研究は国際英語(EIL, WE, ELF)の視点から、日本人英語使用者コーパスを構築し、実証的手法で「日本英語」の潜在的な言語的特徴を同定した。グローバル時代の日本のELTを考える上で、教育目標のパラダイム転換を迫る必読の書である。
藤原康弘著『国際英語としての「日本英語」のコーパス研究』詳細。
ツイート

ひつじ研究叢書(言語編) 第117巻、湯川恭敏著『バントゥ諸語の一般言語学的研究』を刊行しました。
著者の30年以上にわたるアフリカのバントゥ諸語の調査研究の成果の中から、一般言語学的興味をひくテーマを選んで、記述結果を説明したものである。範囲は、音声学・音韻論から文法論、系統論等の広範囲に及ぶ。後半は、言語がどの程度に規則的であるのかという根源的問題を、いくつかのバントゥ系言語の動詞のアクセントの分析を通して考えたものである。言語学者、言語学を志す人々の必読の書である。
湯川恭敏著『バントゥ諸語の一般言語学的研究』詳細。
ツイート
2014.2.13
ひつじ書房では、2014年あるいは2015年春卒の新入社員を募集しています。本を出版したい、本を編集したい、本を届けたい、という気持ちのある方を求めています。気持ちがあれば、不器用でもかまいません。きちんと育てます。詳細は以下をご覧下さい。
2014年・2015年春卒 正社員の募集・求人・採用の詳細
影山太郎編『複合動詞研究の最先端ー謎の解明に向けて』を刊行しました。
「晴れ上がる」や「歩み寄る」のような動詞+動詞型の複合動詞は研究され尽くしたかに見えるが、実はまだまだ謎が多い。このタイプの複合動詞はいつの時代から存在するのか、複合動詞の全貌はどうなっているのか、アジア諸言語と比べてなぜ日本語の複合動詞はかくも多様で複雑なのか。こういった謎に多角的に迫る国立国語研究所共同研究の成果。執筆者:影山太郎、陳 劼懌、長谷部郁子、由本陽子、岸本秀樹、山口昌也、青木博史、阿部 裕、栗林 裕、塚本秀樹、全 敏杞、沈 力、玉岡賀津雄、初相娟、神崎享子
影山太郎編『複合動詞研究の最先端ー謎の解明に向けて』詳細。
ツイート

ひつじ研究叢書(言語編) 第109巻、岸本秀樹・由本陽子編『複雑述語研究の現在』を刊行しました。
本論集は、ミニマリズムや生成語彙論、事象構造論など近年の言語理論の発展により言語に対する知見を深める可能性を秘める「複雑述語」に関しての最先端の研究成果を著した論文を集成する。第I部では、主に日本語の複雑述語を取り上げ、意味的・統語的関係に関わる制約を最新の言語理論により分析する論文を収録する。第II部では、英語、中国語、スウェーデン語など、形態的には分離した複雑述語の事象構造を分析する論文を収録する。
岸本秀樹・由本陽子編『複雑述語研究の現在』詳細。
ツイート

益岡隆志・大島資生・橋本修・堀江薫・前田直子・丸山岳彦編『日本語複文構文の研究』を刊行しました。
本書は、国立国語研究所の共同研究プロジェクト「複文構文の意味の研究」の成果報告書として刊行する。日本語の複文の総合的な研究をめざす本書は、「連用複文・連体複文編」、「文法史編」、「コーパス言語学・語用論編」、「言語類型論・対照言語学編」の4部で構成される全24編の論文に加え、各部に研究動向や今後の課題を記した解説文を掲載する。執筆者:天野みどり、坪本篤朗、松木正恵、前田直子、高橋美奈子、大島資生、橋本修、井島正博、高山善行、宮地朝子、岩田美穂、福嶋健伸、丸山岳彦、蓮沼昭子、長辻幸、加藤重広、益岡隆志、松本善子、下地早智子、米田信子、堀江薫、金廷珉、大堀壽夫、江口正
益岡隆志・大島資生・橋本修・堀江薫・前田直子・丸山岳彦編『日本語複文構文の研究』詳細。
ツイート

ひつじ研究叢書(言語編) 第111巻、工藤真由美著『現代日本語ムード・テンス・アスペクト論』を刊行しました。
標準語、東北から沖縄に至る諸方言、海外移民社会の言語接触現象を視野に入れ、アスペクトやテンス、認識的ムードやエヴィデンシャリティー、さらには話し手の評価感情という側面が、どのように相関性しつつ多様性を生み出しているかについて考察。多様な日本語のバリエーションを記述するための方法論を提示している。前著『アスペクト・テンス体系とテクスト』で使用した文法用語等を再検討し、用語解説としてまとめた。
工藤真由美著『現代日本語ムード・テンス・アスペクト論』詳細。
ツイート

ひつじ研究叢書(言語編) 第96巻、清瀬義三郎則府著『日本語文法体系新論ー派生文法の原理と動詞体系の歴史』を刊行しました。
派生文法とは著者の提唱したもので、用言の活用が無い文法のことである。日本語の膠着言語としての性質に着目、音素を単位に形態素分析すると、動詞の語幹に接尾辞が連接して新しい語幹を次々に派生し、意味を変えてゆく姿が見られる。まずこの原理を説く。次に現代語全般、文論をも含めた文法論を詳述する。最後に史的研究が来る。上代以降の大変化たる音便形の発生、連体形に取って代られた終止形の消滅、二段「活用」の一段化などは、起因を見事に解明している。
清瀬義三郎則府著『日本語文法体系新論ー派生文法の原理と動詞体系の歴史』詳細。
ツイート
『日本エスペラント運動人名事典』の書評が掲載されました。
・「週刊読書人」(2014年1月17日号) 寺島俊穂氏による書評
・「週刊金曜日」(2014年1月17日・975号)「きんようぶんか」 佐高信氏による書評
柴田巌・後藤斉編 峰芳隆監修『日本エスペラント運動人名事典』詳細。
ツイート

柴田巌・後藤斉編 峰芳隆監修『日本エスペラント運動人名事典』が日本図書館協会の選定図書に選ばれました。(第2888回平成25年12月18日選定、日本十進分類表(新訂9版)899.1(国際語[人工語]ーエスペラント))
柴田巌・後藤斉編 峰芳隆監修『日本エスペラント運動人名事典』詳細。
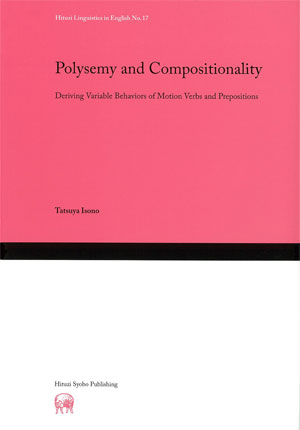
新年となりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
新刊のお知らせです。Hituzi Linguistics in English No.17、磯野達也著『Polysemy and Compositionality: Deriving Variable Behaviors of Motion Verbs and Prepositions』を刊行しました。
語彙意味論、特に生成語彙論(Generative Lexicon)の枠組みで、事象構造、特質構造の精緻化を図り、動詞と前置詞の多義性と意味の合成性を扱う。英語の移動、放出、状態変化などの動詞と前置詞、及び「まで」の意味構造を考察する。また、意味構造の(共)合成の条件を提案し、前置詞句が動詞の項または付加詞になる場合が、これにより区別されることを移動構文、場所格交替構文、場所格倒置構文などで議論する。
磯野達也著『Polysemy and Compositionality』詳細。
ツイート
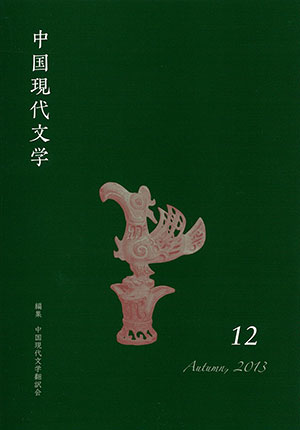
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 12』を刊行しました。
現代中国の文学作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第12号。徐則臣「中関村を駆け抜けて」(憧れの北京へ出てきたものの正規の仕事が見つからない若者たちの青春群像)、朱山坡「魂の授業」(お骨を預かる店で働く青年のもとにやって来た老婆が語る不思議な話)、西川「書籍」「虚構の家系図」(文化や歴史や時間についての詩二編)などを掲載する。
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 12』詳細。
ツイート

大島弥生・大場理恵子・岩田夏穂・池田玲子 著『ピアで学ぶ大学生・留学生の日本語コミュニケーション』の重版が出来上がりました。
大学での学習に必要なコミュニケーション能力とライティング能力を身につけるための実践的表現活動をタスク化したテキスト。各課のタスクは仲間同士の対話(ピア活動)を通じて行われる。前半では学習計画書・志望動機書を書き、口頭発表を行う。後半では、本を紹介し合い批判的に分析するグループワーク(ブック・トーク)からレポート執筆までの流れを通じて、批判的に読み、書く能力を育成する。大学入学後の初年次教育や入試・編入の小論文指導に適した活動型教科書。正確な文や表現を書くためのエクササイズも豊富。
大島弥生・大場理恵子・岩田夏穂・池田玲子 著『ピアで学ぶ大学生・留学生の日本語コミュニケーション』詳細。
ツイート

ひつじ研究叢書(言語編) 第112巻、西山佑司編『名詞句の世界—その意味と解釈の神秘に迫る』を刊行しました。
『日本語名詞句の意味論と語用論』(ひつじ書房、2003)で展開された主張と仮説を基本的に継承しながらも、それをさらに発展させることを目的に編まれた論文集。第1部 名詞句それ自体の意味、第2部 コピュラ文と名詞句の解釈、第3部 存在文と名詞句の解釈、第4部 「変項名詞句」の一般化、第5部 名詞句の語用論的解釈の5部から成る。西山佑司教授古稀記念論文集の意味合いも兼ねる。執筆者:西山佑司、梶浦恭平、熊本千明、小屋逸樹、西川賢哉、峯島宏次、山泉実。
西山佑司編『名詞句の世界』詳細。
ツイート

ひつじ研究叢書(言語編) 第113巻、釘貫亨著『「国語学」の形成と水脈』を刊行しました。
本書は、国語学が18世紀以来の国学系古典語学の業績を継承して成立したことに注目する。国語学は、19世紀後半に言語学と合流して制度として発足したが、伝統の継承を自覚する人々が言語学の理論と対峙しながら独自の理論を形成した過程を叙述する。本書は、山田孝雄、有坂秀世、時枝誠記、奥田靖雄らが理論的正統化の根拠とした知識の水脈を復元する。また、国語学の記述法を普及させた橋本進吉の学説史的位置づけを行う。
釘貫亨著『「国語学」の形成と水脈』詳細。
ツイート
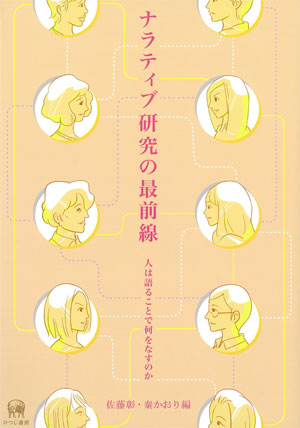
佐藤彰・秦かおり編『ナラティブ研究の最前線—人は語ることで何をなすのか』を刊行しました。
近年、ナラティブを相互行為の実践として捉え、人は語ることで何を成すのかを解明する試みが行われている。本書は、ナラティブ分析理論の概要から、教育現場、異文化体験、震災体験、子どものナラティブなど様々な実践研究を収録し、ナラティブ研究を多角的に捉える一冊となっている。
執筆者:有田有希、井出里咲子、岡本多香子、片岡邦好、小玉安恵、小林宏明、佐藤彰、嶋津百代、西川玲子、秦かおり、濱口壽子、𩜙平名尚子、渡辺義和。「ナラティブ分析」(Alexandra Georgakopoulou著)翻訳収録。
佐藤彰・秦かおり著『ナラティブ研究の最前線』詳細。
Tweet

真田信治監修 岡本牧子・氏原庸子著『新訂版 聞いておぼえる関西(大阪)弁入門』の重版が出来上がりました。
関西(大阪)弁を聞いて理解するための聴解教材。初中級程度の日本語文法をマスターした日本語学習者を対象にしているが、関西(大阪)弁に興味のある日本人にも役に立つ。20のUNITで構成され、各UNITは4コマ漫画、聴解問題、文法ノートからなる。文法ノートでは共通語との違いについて、形、使い方などの面から詳しく解説。また、コラムで関西弁の特徴などにも触れている。1998 年にアルクより出版され、好評を博したものの新訂版で、旧版で別売だった音声カセットテープをCDにして付している。 ★CD付
真田信治監修 岡本牧子・氏原庸子著『新訂版 聞いておぼえる関西(大阪)弁入門』詳細。
ツイート
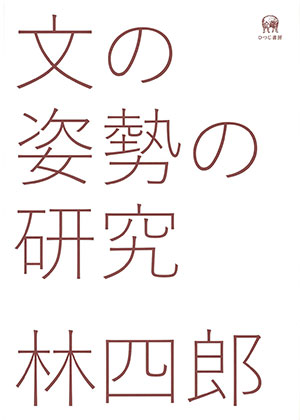
林四郎著『文の姿勢の研究』を刊行しました。
本書は、日本のテキスト言語学の先駆けであり、また、内容的にも同分野で世界的に最も著名なハリディとハサンの『テクストはどのように構成されるか』(ひつじ書房。原題Cohesion in English)に勝るとも劣らない不滅の価値を持つものである。本書は、40年前の出版後、稀覯本として一部の研究者の間でのみその価値が知られてきた。今回本書が復刊されることは日本のテキスト言語学にとっての最大の朗報である。解説:庵功雄、石黒圭
林四郎著『文の姿勢の研究』詳細。
ツイート
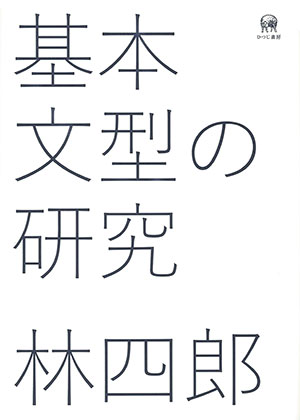
林四郎著『基本文型の研究』を刊行しました。
本書は、国語教育のために、日本語文に「基本文型」が存在するかを検討した本である。学校英文法では全ての単文を5つの文型に分ける。この「5文型」は英語の構造を理解する上で重要な役割を果たしている。日本語文にも同様の「基本文型」が設定できれば、日本語文の理解は大いに促進されうる。ここで提起されている問は、現在でも、国語教育、日本語教育双方において極めて重要な課題である。新たに解説を加え待望の復刊。解説:南不二男、青山文啓
林四郎著『基本文型の研究』詳細。
ツイート
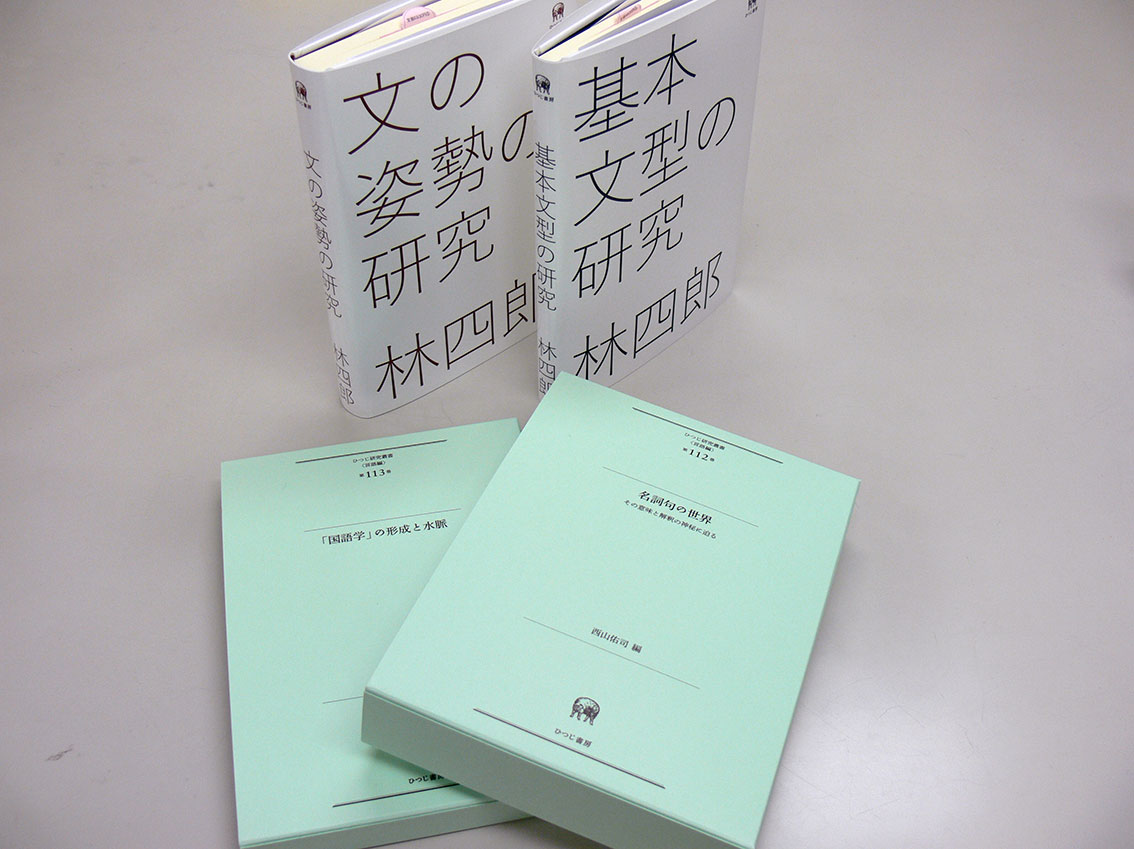
新刊4冊の見本ができあがってきました。明日の日本語文法学会でお目見えします。
林四郎著『基本文型の研究』詳細はこちら(工事中)。
林四郎著『文の姿勢の研究』詳細はこちら(工事中)。
西山佑司編『名詞句の世界』詳細はこちら。
釘貫亨著『「国語学」の形成と水脈』詳細はこちら。

渡部直己著『私学的、あまりに私学的な―陽気で利発な若者へおくる小説・批評・思想ガイド』の重版が出来上がりました。
文芸批評家であると同時に教育者でもある著者の、授業で実際に教えている積年の「ネタ」が詰まった一冊。大学就学前からゼミ、大学院レベルまで、段階ごとに分けて、各種媒体で発表されたネタ元となる氏のテクストを配置し、プロによる思想、批評、文学を読むこと、書くことなどのエッセンスを知ることができる。巻末には解説入りの充実した国内外の小説、批評ブックリスト付き。文学や思想が好き、勉強したい人、さらには国語の先生までオススメ。
渡部直己著『私学的、あまりに私学的な』詳細。
ツイート

津田ひろみ著『学習者の自律をめざす協働学習—中学校英語授業における実践と分析』を刊行しました。
本書は、自律的学習者を育む教授法のひとつとしてメタ認知指導を重視した協働学習を取り上げ、中学校英語授業での実践データに基づいてその効果を分析している。量的調査によって自律的学習態度の涵養に関わる協働学習の効果を示すとともに、質的調査によって協働学習に対する学習者の意識を探る。さらに相互行為の分析により学習者間に内在する社会文化的役割を明らかにするなど、協働学習を多角的に分析しており、英語教員のみならず、広く言語コミュニケーションに関心のある人々にも薦めたい。
津田ひろみ著『学習者の自律をめざす協働学習』詳細。
ツイート

『日本エスペラント運動人名事典』(柴田巌・後藤斉編 峰芳隆監修)を、『サンデー毎日』2013年12月1日号の記事で取り上げていただきました。
☆『サンデー毎日』2013年12月1日号
「佐高信の政経外科」連載717
柴田巌・後藤斉編 峰芳隆監修『日本エスペラント運動人名事典』詳細はこちら(記事の大きな表示あり)。
ひつじ書房は言語学の学術書を出版している出版社ですので、私たちが、いっしょに働きたいのは、ことばに興味を持っている方です。ことばに関心を持つと言ってもそれは人それぞれだと思います。ことばの仕組みということもありますし、コミュニケーションやことばの美的な力について関心を持つということもあるでしょう。広い意味でことばを扱っている研究書の出版に関わっていきたいと考えている方に応募してほしいと思っています。
2013年 ひつじ書房 2013年 正社員の募集・求人・採用(編集+出版業務)ページ詳細。
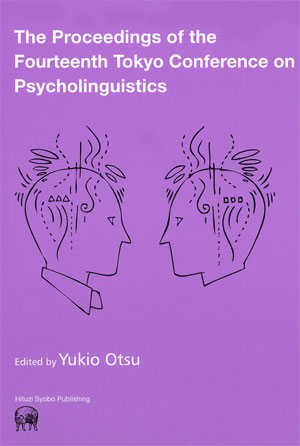
大津由紀雄編『The Proceedings of the Fourteenth Tokyo Conference on Psycholinguistics(TCP2013)』を刊行しました。
慶應義塾大学でおこなわれている東京言語心理学会議(Tokyo Conference on Psycho-linguistics)の第14回大会の研究発表/講演集(英語)。
大津由紀雄編『The Proceedings of the Fourteenth Tokyo Conference on Psycholinguistics(TCP2013)』詳細。
ツイート

『日本エスペラント運動人名事典』をBooksアイ茗荷谷店で販売していただいています。茗荷谷駅から徒歩10秒、ひつじ書房事務所からいちばん近い本屋さんです。パンフレットも置いていただきました。
柴田巌・後藤斉編 峰芳隆監修『日本エスペラント運動人名事典』詳細。
ツイート
ひつじ書房は言語学の学術書を出版している出版社ですので、私たちが、いっしょに働きたいのは、ことばに興味を持っている方です。ことばに関心を持つと言ってもそれは人それぞれだと思います。ことばの仕組みということもありますし、コミュニケーションやことばの美的な力について関心を持つということもあるでしょう。広い意味でことばを扱っている研究書の出版に関わっていきたいと考えている方に応募してほしいと思っています。
2013年 ひつじ書房 2013年 正社員の募集・求人・採用(編集+出版業務)ページ詳細。

石田基広・小林雄一郎著『Rで学ぶ日本語テキストマイニング』を刊行しました。
さまざまな研究領域や実務分野で、テキストマイニングという技術の導入が進んでいる。テキストマイニングとは、特に大規模なテキストデータを対象に、情報科学やデータ科学の技術にもとづいて分析を行い、新しい知見を導こうとする試みの総称である。本書は、テキストマイニングを語学・文学研究に応用するための入門書である。前半では、言語データ分析とRの操作方法について詳細に解説し、後半では、テキストマイニングをさまざまな課題に適用した事例を紹介する。
石田基広・小林雄一郎著『Rで学ぶ日本語テキストマイニング』詳細。
ツイート
2013.10.17

新刊・近刊のご案内の冊子『未発ジュニア版』を発送しました。
『未発ジュニア版』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いします。

柴田巌・後藤斉編 峰芳隆監修『日本エスペラント運動人名事典』を刊行しました。
国際語エスペラントの120年以上の歴史の中で、それを使い、広めるための運動は日本においても多彩に展開された。加わった人の多くは無名であるが、吉野作造、柳田國男、宮沢賢治、梅棹忠夫などの著名人も含まれる。本書は約2900人の物故者を取り上げ、その全体像とエスペラントに関連した活動や著作を紹介することにより、歴史的事実としてのエスペラントを記述する。エスペラントの位置づけに新たな視点を提示する。
柴田巌・後藤斉編 峰芳隆監修『日本エスペラント運動人名事典』詳細。
ツイート
2013.10.9

『日本エスペラント運動人名事典』見本が、できてきました。担当は海老澤です。週末の日本エスペラント大会にお目見えします。日本語教育学会にも持って行きます。 『日本エスペラント運動人名事典』の詳細。
2013.10.2
恐れ入りますが、原稿を書かれます際には、等幅フォントを使って下さるようお願いします。
フォントとしては、プロポーショナルフォント(MSP明朝、MSPゴシック)ではなく、等幅フォント(MS明朝、MSゴシック)をお使い下さいますようお願いします。日本語の組版は等幅フォントを使うようにできておりますため、ご協力をお願い致します。 |
2013.10.1
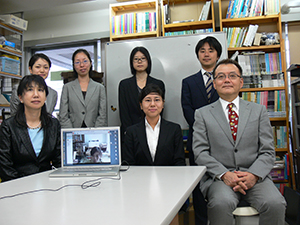
来春入社予定の1名を迎え、内定式をおこないました。
2013.9.30

朝日新聞(2013年9月30日朝刊)に、『日本エスペラント運動人名事典』『英語教育、迫り来る破綻』の広告を出しました。
2013.9.27


先日社員で小石川植物園に彼岸花を観賞しにいってきました。
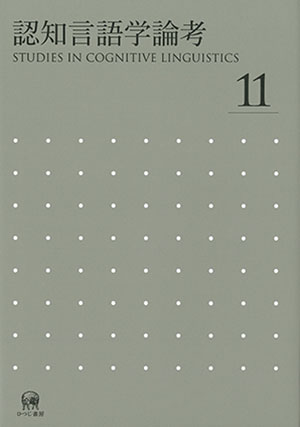
山梨正明他編『認知言語学論考 No.11』を刊行しました。
テミル条件文にみられる構文変化の過程 菊田千春/日英語の事態把握とEvidential Modality 黒滝真理子/言語における「主体化」と「客観化」の認知メカニズム 中野研一郎/指示詞のパラメータ 今井新悟/複合コンテクストに基づき意味づけられる出来事としての発話 名塩征史/脱身体化の潜在性と社会性 寺西隆弘/知識構造の階層性と複文構造 大西美穂/構文の発達による動詞の認知的分業 徳山聖美/カテゴリー化としての語形成プロセス 金光成/2タイプのメトニミーと参照点構造 山本幸一
山梨正明他編『認知言語学論考 No.11』詳細。
ツイート

阿部潤著『問題を通して学ぶ生成文法』の重版が出来上がりました。
生成文法は、人間の言語に内在する文法を解き明かすツールである。このツールは、チョムスキーが創案して以来、様々な言語事象について、新たな視点を提供してきた。研究を押し進め、矛盾に出会い、新たな解決法を探し当てるということの繰り返しであった。本書は、様々な問題を通し、生成文法の基本的概念や考え方について学ぶ。
阿部潤著『問題を通して学ぶ生成文法』詳細。
ツイート

大島弥生・大場理恵子・岩田夏穂編『日本語表現能力を育む授業のアイデア』の重版が出来上がりました。
近年、大学では、留学生のみならず日本語母語話者の学生にも、日本語を読み、書き、聞き、話す技能を養成する授業が広まり、手法の模索が続いている。本書では、「正しい言語知識を教える」というスタイルを脱し、表現産出のプロセスを重視して授業をデザインした各種の実践をまとめた。とくに、参加者が学びあう協働的アプローチ、ことばの学習をキャリア教育などの多様な目的と結びつける統合的アプローチにもとづいた授業デザインを紹介している。
大島弥生・大場理恵子・岩田夏穂編『日本語表現能力を育む授業のアイデア』詳細。
ツイート

シリーズ言語学と言語教育26、王玲静著『第二言語習得における心理的不安の研究』を刊行しました。
第二言語習得における心理的不安の実態と本質を実証で明らかにする。日中両国の学習者の共通点と相違点を取り扱う点が、独創性がある。実践から提案する不安の軽減策は、研究者と教育者にとって非常に有益な情報となる。第二言語習得研究全般及び心理的不安の研究のレビューは、第二言語習得研究及び不安を含め動機づけなどの情意要因に関して勉強を始めようとする人にもぴったりの一冊。巻末に詳細なアンケート調査資料を付す。
王玲静著『第二言語習得における心理的不安の研究』詳細。
ツイート
富田倫生さん、ご自身による略歴
ひつじ書房で刊行させていただいた
『インターネット快適読書術』(刊行時の紹介文)
ひつじ書房では、富田さんの発案によりまして、上記『インターネット快適読書術』の出版とその実際のブラウザーであるT-Timeを書店ルートで発売しました。もともと、富田さんが祝田さんが個人的に使っていたブラウザーを公開するようにすすめたところから、T-Timeははじまったと聞いています。青空文庫については、富田さんのお考えに賛同し、もっとも最初の段階でバナー広告の出稿をはじめ、今でも行っています。多くの誤解がありますが、青空文庫でのテキストを読むのは無料でも、運営にはコストがかかります。
富田倫生さんをもお招きして行ったシンポジウムへの私の感想(14年前で、かなり性急な感じ。)へのリンクを貼っておきます。14年前の私の感想 ほんとうにもっともっともっといろいろと議論したかったです。
ご冥福をお祈りしています。
現在、『インターネット快適読書術』は品切れです。
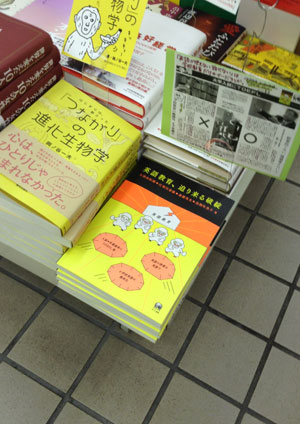
『英語教育、迫り来る破綻』をBooksアイ茗荷谷店で販売していただいています。茗荷谷駅前、ひつじ書房事務所からいちばん近い本屋さんです。ポップもつけていただきました。
大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子著『英語教育、迫り来る破綻』詳細。
ツイート
富田倫生さん、ご自身による略歴
ひつじ書房で刊行させていただいた
『インターネット快適読書術』(刊行時の紹介文)
ひつじ書房では、富田さんの発案によりまして、上記『インターネット快適読書術』の出版とその実際のブラウザーであるT-Timeを書店ルートで発売しました。もともと、富田さんが祝田さんが個人的に使っていたブラウザーを公開するようにすすめたところから、T-Timeははじまったと聞いています。青空文庫については、富田さんのお考えに賛同し、もっとも最初の段階でバナー広告の出稿をはじめ、今でも行っています。多くの誤解がありますが、青空文庫でのテキストを読むのは無料でも、運営にはコストがかかります。
富田倫生さんをもお招きして行ったシンポジウムへの私の感想(14年前で、かなり性急な感じ。)へのリンクを貼っておきます。14年前の私の感想ほんとうにもっともっともっといろいろと議論したかったです。
ご冥福をお祈りしています。
現在、『インターネット快適読書術』は品切れです。
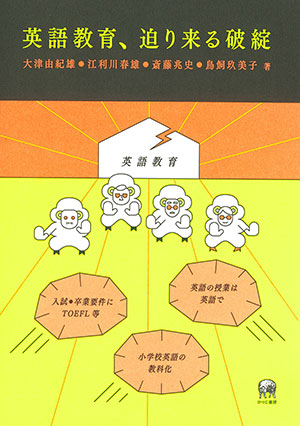
大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子著『英語教育、迫り来る破綻』の重版が出来上がりました。
大学入試にTOEFLを必須とする案が自民党教育再生実行本部によって提案された。参議院選挙では、自民党の公約に採用される可能性がある。この提案は、6年間英語を学んでも英語が話せるようにならないという感覚に基づき、自民党に限らず、広く人々の支持を集めようとしている。しかし、もしTOEFLを導入するようなことがあれば、英語教育が破綻するのは火を見るよりも明らか、と危機感を持った4名が、反論と逆提案を試みようと立ち上がった……。
大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子著『英語教育、迫り来る破綻』詳細。
ツイート
2013.7.31

アジア文化会館で7月29日に行われた講演会は多数の方にご来場いただき、盛況の内に終了いたしました。ご来場くださった方々まことにありがとうございました。
小島剛一氏「ラズ語辞書刊行を祈念する会」詳細。
ツイート

朝鮮語研究会編『朝鮮語研究 5』を刊行しました。
本書は1983年4月に発足し、1999年からは正式に学会組織として活動してきた朝鮮語研究会の不定期刊学会誌『朝鮮語研究』の第5号である。本書には、中国朝鮮族の朝鮮語諸方言のアクセントに関する論文2篇、現代朝鮮語文法に関する論考4篇、日韓対照言語学及び日韓言語接触に関わる論考5篇、コンピュータ言語学による韓国語形態素解析に関する論考1篇が収められている。
朝鮮語研究会編『朝鮮語研究 5』詳細。
ツイート
2013.7.17

郁文館夢学園で7月14日に行われた講演会は多数の方にご来場いただき、盛況の内に終了いたしました。ご来場くださった方々まことにありがとうございました。
大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子著『英語教育、迫り来る破綻』
ツイート

小島剛一氏、ラズ語講演会。「ラズ語は、トルコ共和国北東端とグルジア南西端に主要語域のある非圧迫言語・絶滅危惧言語。...」7月29日アジア学生文化会館にて、6時半開場。
講演会の詳細です。pdf版です。
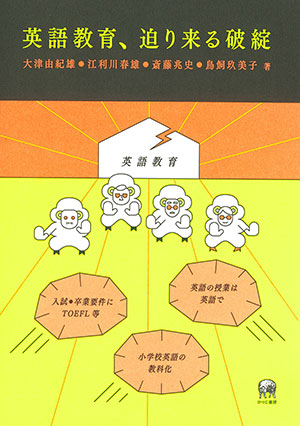
大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子著『英語教育、迫り来る破綻』を刊行しました。
大学入試にTOEFLを必須とする案が自民党教育再生実行本部によって提案された。参議院選挙では、自民党の公約に採用される可能性がある。この提案は、6年間英語を学んでも英語が話せるようにならないという感覚に基づき、自民党に限らず、広く人々の支持を集めようとしている。しかし、もしTOEFLを導入するようなことがあれば、英語教育が破綻するのは火を見るよりも明らか、と危機感を持った4名が、反論と逆提案を試みようと立ち上がった……。
大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子著『英語教育、迫り来る破綻』詳細。
ツイート
2013.7.11

大阪大学で7月1日に行われた 第1回 日本語を衆議する/日本語で衆議する トークイベントには多数の方にご参加いただきました。まことにありがとうございました。
企画・進行:金水 敏(大阪大学大学院文学研究科)
主催:大阪大学大学院文学国語学研究室(担当:金水)/(株)ひつじ書房
協力:大阪大学コミュニケーションデザイン・センター/大阪大学21世紀懐徳堂/国立国語研究所
○第1回:7月1日(月)14時〜17時〈ファシリテーターとは何か?〉(終了)
○第2回:7月18日(木)15時〜17時〈衆議の技法〉
○第3回:7月22日(月)14時〜17時〈公共空間の日本語を設計する〉
詳細はこちら
2013.7.4

立教大学で7月1日に行われた講演会は多数の方にご来場いただき、盛況の内に終了いたしました。ご来場くださった方々まことにありがとうございました。
『主体と文体の歴史』亀井秀雄著
2013.6.26
社会の複雑度が増すにつれて、当事者による衆議・熟議の必要性が一層叫ばれています。エネルギー問題、食の安全、医療問題、憲法改正、人口問題、年金問題等々、どれをとっても人任せではすまないことがらばかりです。しかし一方で日本人は話し合いが苦手とも言われ、また近代日本語そのものが衆議に向いていないのではないかとの意見も聞かれます。しかし、向いていないなら日本人を、そして日本語そのものを作り変えていってもいいのではないでしょうか。このトークイベントは、そのような観点から、言葉とコミュニケーションのプロフェッショナルを囲んで日本語の将来について語り合うイベントです。ふるってご参加ください。
企画・進行:金水 敏(大阪大学大学院文学研究科)
主催:大阪大学大学院文学国語学研究室(担当:金水)/(株)ひつじ書房
協力:大阪大学コミュニケーションデザイン・センター/大阪大学21世紀懐徳堂/国立国語研究所
○第1回:7月1日(月)14時〜17時〈ファシリテーターとは何か?〉
○第2回:7月18日(木)15時〜17時〈衆議の技法〉
○第3回:7月22日(月)14時〜17時〈公共空間の日本語を設計する〉
詳細はこちら
2013.6.21

大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子著『英語教育、迫り来る破綻』が間もなく刊行します。
「大学の入試や卒業要件にTOEFL等の外部検定試験を導入する案が、自民党教育再生実行本部や政府の教育再生実行会議によって提案された。しかし、もしそれが現実となれば、学校英語教育が破綻するのは火を見るよりも明らか。危機感を持った4人が、反論と逆提案に立ち上がった……。」
大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子著『英語教育、迫り来る破綻』詳細。
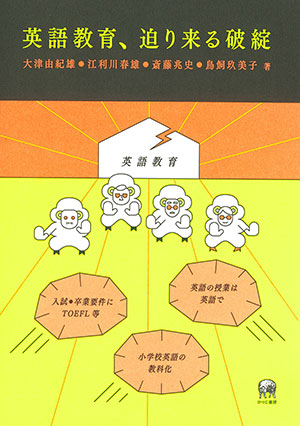
大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子著『英語教育、迫り来る破綻』がまもなく刊行します。
大学の入試や卒業要件にTOEFL等の外部検定試験を導入する案が、自民党教育再生実行本部や政府の教育再生実行会議によって提案された。しかし、もしそれが現実となれば、学校英語教育が破綻するのは火を見るよりも明らか。危機感を持った4人が、反論と逆提案に立ち上がった……。
☆小学校英語教科化の問題点、白熱した座談会、関連年表なども収録。
大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子著『英語教育、迫り来る破綻』詳細。

本年も研究書出版の相談会、オープンオフィスを開催します、といいますか、開催中です。
オープンオフィス、詳細。
2013.6.4
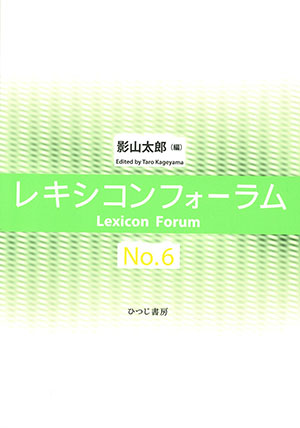
影山太郎 編『レキシコンフォーラム No.6』を刊行しました。
レキシコンすなわち語彙(単語)に関する総合的なジャーナルで、言語学だけでなく心理学や自然言語処理などの研究を掲載する。
第6号の特集は、「日本語レキシコン入門 PART I」
影山太郎 編『レキシコンフォーラム No.6』詳細。
ツイート
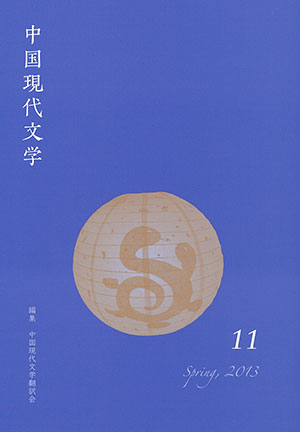
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 11』を刊行しました。
現代中国の文学作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第11号。
笛安「円寂」(都会の片隅で俗世を静かに眺める物乞がいた)、于暁威「円形の精霊」(一枚の銅銭がたどる数奇な運命の物語)、残雪「よそ者」(わたしはどうやって「よそ者」と出会うのか?)、裘山山「臘八粥」(悲しみに冷え切った女性の心を温めたものは?)、裘山山「道聴塗説」(約束の地・天涯海角へ旅立った女性を待っていたものは?)、王小妮「蓮沼鬼月光」「丘に上る」「稲妻の夜」(詩)など。
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 11』詳細。
ツイート
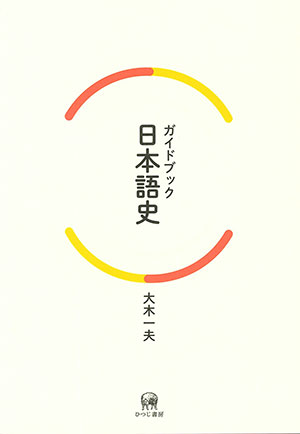
大木一夫著『ガイドブック日本語史』を刊行しました。
通史としてではなく言語の歴史を明らかにするさまざまな方法からみた日本語史の概説書。ことばの移り変わり、すなわち言語の歴史は古い文献を利用することでわかるように思えるが、文献だけが言語の歴史を知る資料になるわけではない。また、古い文献を用いる方法にも、さまざまに考えておくべきことがある。それでは、どのようにして言語の歴史は明らかにされるのか。日本語を例にして、言語の歴史を明らかにする方法を多面的・総合的に概説する。
大木一夫著『ガイドブック日本語史』詳細。
ツイート
2013.5.27

亀井秀雄著 未発選書 19『主体と文体の歴史』を刊行しました。
文学史の時代区分は、国家という枠組みによってリアリティをもち、成長や開花といった生命体の比喩で語られる。そうした中央集権的な思考や制度的な言説を脱構築する様々なテクストと文体の試みは、どのように展開されていたのか。「第1部 発話と主体」、「第2部 時間と文体」、「第3部 近代詩の構成」、「第4部 文体と制度」の4部構成から明らかにしていく。近代文学研究に大きな功績をあげた著者の単行本未収録論文集。
亀井秀雄著 未発選書 19『主体と文体の歴史』詳細。
ツイート
2013.5.24

増田靖著 『生の現場の「語り」と動機の詩学—観測志向型理論に定位した現場研究=動機づけマネジメントの方法論』を刊行しました。
本書は、個々人が日々生きている現場(生の現場)において、いかに互いを動機づけ、未来を語り作りながら生きているのかを明らかにすることを目的とする。経営組織論に属す動機づけの研究であるが、「語り」という言語行為を基底に議論する。また、生命とは何かを数理学・脳科学の知見に基づき定式化した郡司の『生命理論』を「語り」の概念により解読し、かつ現場研究=動機づけマネジメントの方法論として定式化した研究書である。
増田靖著 『生の現場の「語り」と動機の詩学—観測志向型理論に定位した現場研究=動機づけマネジメントの方法論』詳細。
ツイート
2013.5.23

新刊・近刊のご案内の冊子『未発ジュニア版』を発送しました。
『未発ジュニア版』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いします。
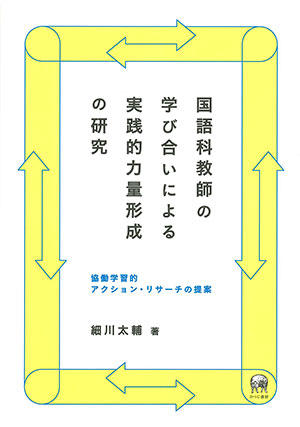
細川太輔著 『国語科教師の学び合いによる実践的力量形成の研究—協働学習的アクション・リサーチの提案』を刊行しました。
著者は、教師が研究者から正しいとされる指導法を押し付けられ、人間性を否定されてきた場面を多く見てきた。本書では「協働学習的アクション・リサーチ」という教師の学び合いを提案する。教師が互いに実践を見せ合い、ライフストーリー(生の語り)を語り合うことにより、実践の根本的な枠組みであるフレームを分析する。実践の違いを違いとして受け止め、個性的な教師として成長していくプロセスを明らかにした。
細川太輔著 『国語科教師の学び合いによる実践的力量形成の研究—協働学習的アクション・リサーチの提案』詳細。
ツイート
2013.5.15

半田智久著 『構想力と想像力—心理学的研究叙説』を刊行しました。
現代社会では種々の構想が語られ、構想力の大切さが指摘されている。だが、構想やその力とは何なのか。辞書や哲学ではしばしば構想とは想像と同義としている。では求められる構想力とは想像力に他ならないのか。否だろう。では心理学は構想をどう捉えているか。記述が見あたらない。本書は想像とその力に関する探究を振り返り考察しつつ、構想とその力との差異と関係性をとらえ、人間精神の根幹で働くその活動に捜査の光を投じる。
半田智久著 『構想力と想像力—心理学的研究叙説』詳細。
ツイート
2013.5.9
出版スタッフを募集します。仕事の中心は、編集と書籍の製作になります。小企業ですので、営業や商品管理も仕事のうちです。仕事をはじめる段階では、ことばについて興味を持っていることと書籍を作ることに人一倍の熱意を持っていることが、重要です。英語の学術書と動画付きの学術書籍をつくっていきますので、英語を読む力とレイアウトソフトを使うことができることが、必要です。
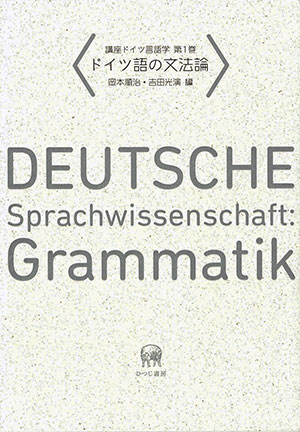
岡本順治・吉田光演編 『講座ドイツ言語学 第1巻—ドイツ語の文法論』を刊行しました。
第1巻 岡本順治・吉田光演編『ドイツ語の文法論』(2012年3月刊行予定)ドイツ語文法の中でも特徴的なトピックをとりあげ、それらがどのように相互に関係しあっているかを示せるように心がける。共時的観点から、他言語との比較だけでなく、意味論や語用論との関連も重視する。取りあげるトピックは、動詞の位置、スクランブリング、中間構文、結果構文、受動態と使役、時制・アスペクト・モダリティ、自由な与格、名詞句の統語論とその意味、複合動詞、情報構造、心態詞である。執筆者は、大矢俊明、岡本順治、田中愼、田中雅敏、藤縄康弘、吉田光演の6名。
岡本順治・吉田光演編 『講座ドイツ言語学 第1巻—ドイツ語の文法論』詳細。
ツイート
2013.5.1

篠原和子・宇野良子編 『オノマトペ研究の射程—近づく音と意味』を刊行しました。
近年、言語学ばかりでなく心理学や工学更にはアートと、様々な分野から注目されているのが、オノマトペである。音と意味、あるいは身体と言葉の結びつきと関わるこのトピックへの、多種多様な観点からの分析を紹介し、問題の核心へと迫ることを目指す。
篠原和子・宇野良子編 『オノマトペ研究の射程—近づく音と意味』詳細。
ツイート
2013.4.23
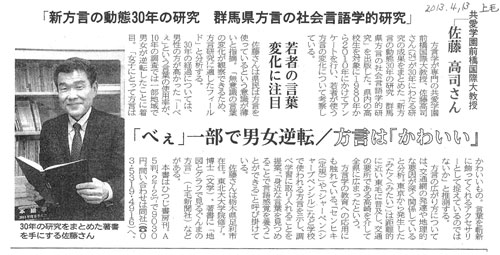
2013年4月13日の上毛新聞に、『新方言の動態30年の研究』が取り上げられました。
佐藤髙司著『新方言の動態30年の研究』詳細。
2013.4.15
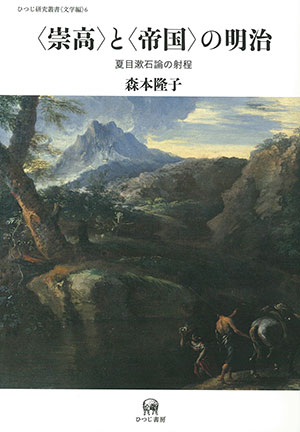
森本隆子著 ひつじ研究叢書(文学編) 6『〈崇高〉と〈帝国〉の明治—夏目漱石論の射程』を刊行しました。
「崇高」(サブライム)は、近代における〈風景の発見〉を導き出す機軸となった美意識である。アルプスに象徴される雄大で荒涼とした自然を前に、死の恐怖と紙一重に獲得されるスリリングな喜びは、自己超越を志向する倒錯的な観念の世界を形成し、やがては明治という男性中心主義的な〈帝国〉を作り上げてゆく快楽的なイデオロギー装置へと化してゆく。始原としての『日本風景論』から『破戒』『野菊の墓』へ、差異として析出されてくる夏目漱石論と重層させながら、その展開の軌跡を辿った。
森本隆子著 『〈崇高〉と〈帝国〉の明治』(ひつじ研究叢書(文学編)6)詳細。
ツイート
2013.4.12

佐渡島紗織・太田裕子編 『文章チュータリングの理念と実践—早稲田大学ライティング・センターでの取り組み』を刊行しました。
大学生は、アカデミックな文章を書く事ができるようになることが求められている。かつては、多くの場合自分で学ぶしかなかった。しかし、現在、大学では、組織的にライティングを教える必要に迫られている。そのような状況の中、独立した機関でライティングを学ぶことの出来る機会を提供することが大学の課題になっている。この課題にいち早く取り組んできた日本におけるパイオニアである早稲田大学ライティング・センターでの取り組みの実践とその裏付けとなる理念を詳述。ピア・チュータリングを行うチューターが実際に困った実例やその解決方法の例を提示。さらに、チューターをどのように採用し、育てていくかといった情報も満載。
佐渡島紗織・太田裕子編 『文章チュータリングの理念と実践』詳細。
ツイート
2013.4.8

児玉一宏・小山哲春編 ひつじ研究叢書(言語編) 第108巻『言語の創発と身体性—山梨正明教授退官記念論文集』を刊行しました。
本書は、京都大学大学院人間・環境学研究科教授 山梨正明先生が、2013年3月に定年を迎えられるに際し、教え子が寄稿した記念論文集である。山梨教授は、言語学者・教育者として活躍され、専門分野は多岐にわたる。認知言語学、語用論を中心に優れた研究成果を次々に発表され、当該分野の第一人者として学会を牽引して来られた。本書は、近年の言語理論に基づく研究成果を踏まえ、同時に山梨教授の学問観を反映する形で、次世代の言語研究に向けての展望を図ることを目指した。
児玉一宏・小山哲春編 『言語の創発と身体性』(ひつじ研究叢書(言語編)第108巻)詳細。
ツイート
2013.4.5
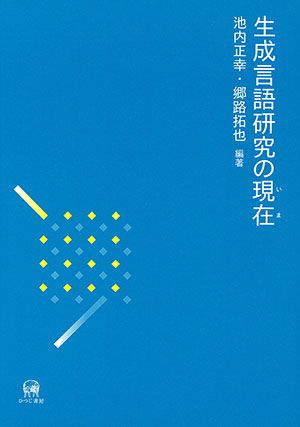
池内正幸・郷路拓也編著 『生成言語研究の現在』を刊行しました。
本書は、津田塾大学言語文化研究所のプロジェクト「英語の共時的及び通事的研究の会」発足25周年記念研究大会(2011年8月開催)での成果を基にした論文集である。まず、シンポジウム「生成文法の企ての現在を問う―LGB 刊行30周年にあたって」における論考を収め、次に、音韻論、形態論などの各領域の研究論文、そして、事例研究・理論的研究の典型例としての招待講演を所収する。
池内正幸・郷路拓也編著『生成言語研究の現在』詳細。
ツイート
2013.4.4
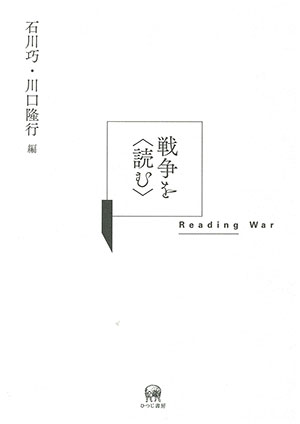
石川巧・川口隆行編 『戦争を〈読む〉』を刊行しました。
戦争をモチーフとした文学テクストを選りすぐり、現代の時代を生きる私たちに投げかける問題に迫る。戦争について何かが分かったつもりになって〈大きな物語〉のなかに安住するのではなく、戦争を多様な局面から捉え直し、私たちが戦争に対して漠然と抱くイメージを細分化していく。文学としての魅力を持った作品の収録と、それぞれを〈問題編成〉の観点からテクストがいまこの時代を生きている私たちにどのような問題を投げかけているかという観点から考察を加え、また研究への案内となるような資料の紹介を行う。
石川巧・川口隆行編 『戦争を〈読む〉』詳細。
ツイート
2013.4.3
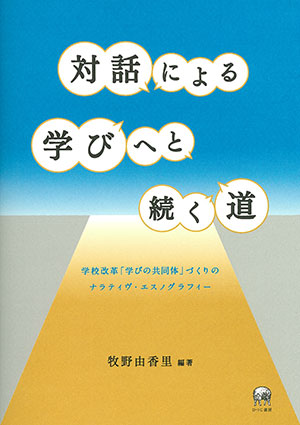
牧野由香里編著 『対話による学びへと続く道—学校改革「学びの共同体」づくりのナラティヴ・エスノグラフィー』を刊行しました。
「学びの共同体」とは、21世紀の学校づくりに挑戦する人々が創り出す文化である。教師も子どもも学び合い育ち合う学校に地域や大学を巻き込む複合的なネットワークである。本書はその成長と変容の軌跡をたどり、「学びの共同体」づくりの実体に迫る。物語は登場人物の語りや映像から抽出した写真によって構成される。事実に基づき学校現場のドラマを緻密に再現することにより、「学びの共同体」を読み解こうとする試みである。
牧野由香里編著 『対話による学びへと続く道』詳細。
ツイート
2013.4.2

中村三春著 未発選書 18『〈変異する〉日本現代小説』を刊行しました。
先行するジャンル・定型・物語を踏まえ、それらを組み替えて小説は新たな生命を獲得し続ける。テクスト生成にまつわる小説の〈変異〉と、読解の営為における〈変異〉とを連動させた、精緻な現代小説論。中上健次・笙野頼子・金井美恵子らの作品を中心として、谷崎潤一郎・三島由紀夫・安岡章太郎から松浦理英子・多和田葉子に至る多数の現代作家を追究する。現代小説の最新レヴューも収録。
中村三春著 『〈変異する〉日本現代小説』(未発選書 18)詳細。
ツイート
2013.4.1
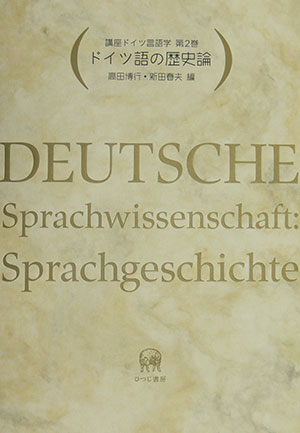
高田博行・新田春夫編 『講座ドイツ言語学 第2巻—ドイツ語の歴史論』を刊行しました。
初めにドイツ語の歴史に関して概略的説明を行う。そのあと、第1部では完了形、受動構文、使役表現、機能動詞構造、語順、造語といった文法カテゴリーに関して体系的な通時的記述を行う。第2部では、15世紀から19世紀に至るドイツ語の歴史を、印刷工房、宗教改革、文法家、日常語、大衆新聞という切り口から社会とコミュニケーションと関連づけて、過去におけるドイツ語話者の息づかいが聞こえてくるように描く。執筆者は、井出万秀、黒田享、清水誠、高田博行、新田春夫、藤井明彦、細川裕史の7名。
高田博行・新田春夫編『講座ドイツ言語学 第2巻』詳細。
ツイート
2013.3.29

山内博之編 橋本直幸・金庭久美子・田尻由美子・山内博之著 『実践日本語教育スタンダード』を刊行しました。
旧日本語能力試験出題基準に収録の実質語(約8000語)と機能語(約270語)をもとに、学習・教育・評価に生きる日本語教育スタンダードの雛型として「語彙・構文表」を作成。言語活動と言語素材を100の話題で分類し、さらに、ABCという三段階のレベル設定を行った。言語活動を「場所」「話題」で分類したロールカードも付す。
山内博之編 橋本直幸・金庭久美子・田尻由美子・山内博之著 『実践日本語教育スタンダード』詳細。
ツイート
2013.3.26

岩田祐子・重光由加・村田泰美著 『概説 社会言語学』を刊行しました。
社会言語学とは何を研究する学問なのか、社会言語学を学ぶことで言語や言語の背景にある社会・文化について何がわかるのかについて、学部生にもわかるように書かれた入門書。入門書とはいえ、英語や日本語の談話データを分析しながら、社会言語学の様々な分野におけるこれまでの代表的な研究成果だけでなく、最新の研究成果も網羅している。社会言語学を学ぶ学生だけでなく、英語教育や日本語教育、異文化コミュニケーションを学ぶ学生にとっても役立つ内容である。
岩田祐子・重光由加・村田泰美著 『概説 社会言語学 』詳細。
ツイート
2013.3.22

木下りか著 ひつじ研究叢書(言語編) 第107巻『認識的モダリティと推論』を刊行しました。
研究の蓄積が豊富な認識的モダリティ形式について、推論という新たな切り口から体系的意味記述を行った待望の書。本書の分析を貫くのは、非現実世界の認識に推論が介在するという視点である。これにより、証拠、蓋然性等の従来の記述概念は相互に関連付けられ、意味記述が精緻化される。さらに、人間の認識や思考を支える演繹・帰納等の推論の型、類似性・隣接性等の関係性が、認識的モダリティ形式の意味に塗り込まれているさまが詳述される。
木下りか著 『認識的モダリティと推論』(ひつじ研究叢書(言語編)第107巻)詳細。
ツイート
2013.3.18
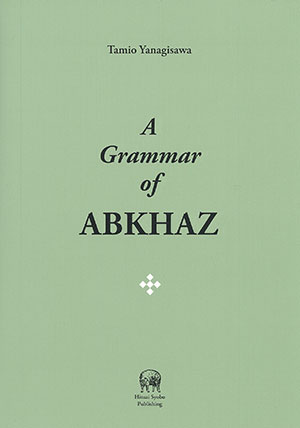
柳沢民雄著 『A Grammar of Abkhaz 』を刊行しました。
本書はアブハジア人より収集した資料に基づいて、音韻論、形態論、統語論に亘って記述した北西コーカサス諸語に属するアブハズ語の記述文法である。アブハズ語は複統合語であるので、特に動詞の形態論についてはアクセントの移動を含め網羅的に記述することに努めた。さらに北部方言であるブジィプ方言の概略と民話テキストも本書に加えた。
柳沢民雄著 『A Grammar of Abkhaz 』詳細。
ツイート
2013.3.13

山橋幸子著 ひつじ研究叢書(言語編) 第106巻『品詞論再考—名詞と動詞の区別への疑問』を刊行しました。
名詞と動詞は言語普遍的必須の区別として一般に受け入れられている。本書はこの区別の起源とされる古代ギリシャの哲学者の原理に遡って品詞論を再考。従来とは異なる見地から日本語における単語の規定をし、語類体系を提示する。提案の形式上の区分は意味上の区分と相関しており、転成名詞や形容動詞等の品詞の問題が解決されるが、統語論的考察に基づく語の分類や単語の規定に疑義を呈することになる。これからの品詞の研究のみならず、存在論の研究にも何らかのヒントとなる。
山橋幸子著 『品詞論再考』(ひつじ研究叢書(言語編)第106巻)詳細。
ツイート
2013.3.11
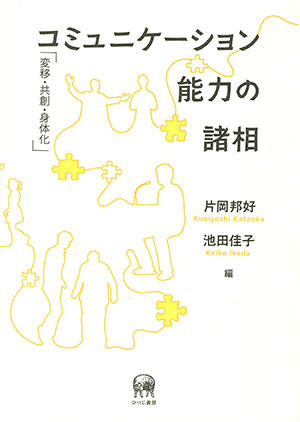
片岡邦好・池田佳子編 『コミュニケーション能力の諸相—変移・共創・身体化』を刊行しました。
コミュニケーション能力に関わるさまざまな分野(フィールドワーク、言語的社会化、教示・指導場面、医療・福祉現場、法廷・司法、政治討論、ニューメディアなど)からの知見をもとに、そこから浮かび上がる特徴を「変移」、「共創」、「身体化」という観点から検討する。
片岡邦好・池田佳子編 『コミュニケーション能力の諸相』詳細。
ツイート
2013.3.8
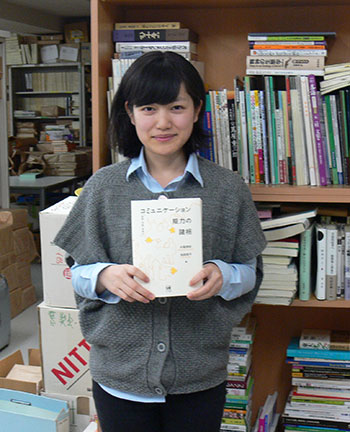
片岡邦好・池田佳子編 『コミュニケーション能力の諸相―変移・共創・身体化』を刊行しました。
What's new
2013.3.11

米山優子著 『ヨーロッパの地域言語〈スコッツ語〉の辞書編纂―『古スコッツ語辞典』の歴史と思想』を刊行しました。
スコッツ語は古英語と共通の素地をもち、中世のスコットランド王国では国家語として幅広く用いられた。現在は「地域・少数言語のための欧州憲章」で保護の対象となっている。12世紀から1700年までの文献に現れたスコッツ語を収録する『古スコッツ語辞典』(1931-2002)は、スコッツ語辞書史における一つの到達点と言える。本書は、辞書編纂者の思想と完成までの経緯をつぶさに検証し、その意義を明らかにした。
米山優子著 『ヨーロッパの地域言語〈スコッツ語〉の辞書編纂』詳細。
ツイート
2013.3.7

秋元実治・前田満編 ひつじ研究叢書(言語編) 第104巻『文法化と構文化』を刊行しました。
文法化の研究に比べて、構文化の研究は緒についたばかりである。構文文法の誕生以来、国内外で構文研究は盛んになっている。しかし、多くの研究は、構文の通時的発達にはほとんど関心を払ってこなかった。本書は、最新の理論に基づき、コーパスなどを駆使し、通時的、共時的観点から英語を分析した画期的な論文集である。執筆者:秋元実治、前田満、大室剛志、中村不二夫、大堀寿夫、岡崎正男、川端朋広、石崎保明、米倉よう子、久米祐介
秋元実治・前田満編 『文法化と構文化』(ひつじ研究叢書(言語編)第104巻)詳細。
ツイート
2013.3.6
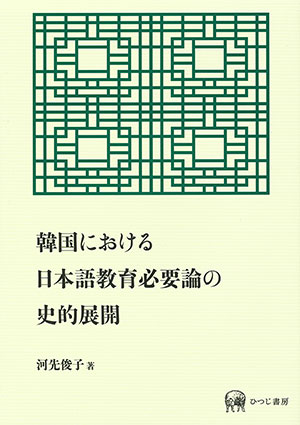
『韓国における日本語教育必要論の史的展開』を刊行しました。
本書は、韓国における日本語教育の歴史を、韓国の人々の日本語教育に対する認識の変遷を通して記述したものである。書かれた史料とオーラル・ヒストリーを分析し、韓国が近代化を進める中で、日本語教育をめぐる言説が、「民族の主体性」に対する認識と日韓関係に対する認識とを織り込んで形成され、変容する様相を示した。そして、なぜ植民地解放後の韓国で日本語教育が再開され発展したのか考察した。
河先俊子著 『韓国における日本語教育必要論の史的展開』詳細。
ツイート
2013.3.5
NHK放送研修センターが開催する「全国巡回朗読セミナー」で、『ことばの宇宙への旅立ち』の1章、「ことばの宇宙への誘い」(大津由紀雄)の一部が朗読教材として使用されることになりました。
「全国巡回朗読セミナー」は全国の朗読愛好者の方々が朗読の基本を学ぶことができる、元NHKアナウンサーによるセミナーとのことです。
大津由紀雄編 『ことばの宇宙への旅立ち』詳細。
2013.3.1

佐藤髙司著 ひつじ研究叢書(言語編) 第105巻『新方言の動態30年の研究―群馬県方言の社会言語学的研究』を刊行しました。
1980年代、共通語化に逆らう言語変化として若年層に方言が生じる現象が「新方言」として注目された。当時、若年層に発生・拡大した新方言は30年後、どうなったのか。本書は、30年間にわたる群馬県での3回の経年調査をもとに、現代の若年層における方言使用の動態を社会言語学的視点から解明した。30年間におよぶ新方言の動態観察に加え、新方言の理論整理や研究史、若年層における伝統方言「ベー」の使用実態の変容、方言使用と属性など、群馬の新方言研究の集大成である。
佐藤髙司著 『新方言の動態30年の研究』(ひつじ研究叢書(言語編)第105巻)詳細。
ツイート
2013.2.28

大嶋秀樹著 Hituzi Linguistics in English No.18『fMRI Study of Japanese Phrasal Segmentation:Neuropsychological Approach to Sentence Comprehension』を刊行しました。
fMRIによる神経心理学的アプローチからの日本語の句分節・群化処理 (phrasal segmentation) の研究。人間が文を理解する際の、phraseごとのまとまりにまとめ、区切る能力の根拠となる脳の神経基盤を、fMRIにより明らかにした。句分節・群化処理の関連脳領域を、脳科学の手法により実証的に特定し、実証的言語研究と理論的言語研究のインターフェース部分の研究の今後の新展開に寄与する内容。fMRIによる言語研究のナビゲーターとして研究方法の事例をも示す。
大嶋秀樹著 『fMRI Study of Japanese Phrasal Segmentation』(Hituzi Linguistics in English No.18)詳細。
ツイート
2013.2.13

岡智之著 ひつじ研究叢書(言語編) 第103巻『場所の言語学』を刊行しました。
主体や主語、個物(モノ)を中心にして考える従来の言語学に対し、場所や述語(コト)を重視した言語学の構築を主張した書。第1部理論編では、場所の哲学を基礎として、主語論、日本語の論理をめぐる論争に対する見解を述べる。また、認知言語学を場所論の観点から位置づけ、発展させる方途を模索する。第2部は事例研究として、場所論に基づく「ハ」と「ガ」の規定、格助詞「ニ」「ヲ」「デ」のスキーマとネットワークの提示などを行う。
岡智之著 『場所の言語学』(ひつじ研究叢書(言語編)第103巻)詳細。
ツイート
2013.2.4

高山善行・青木博史・福田嘉一郎編『日本語文法史研究 1』がお目見えします。
日本語文法の歴史的研究は日本語研究のなかで重要な位置を占めており、その成果は世界的に注目されている。本書は文法史研究の最新の成果を国内・国外に発信する論文集である。文法史の分野で初となる継続刊行の論文集であり、本書は創刊号となる(隔年刊行の予定)。今回は、語構成、構文、モダリティ等の論考10本を収める。巻末付録として、「テーマ解説」「文法史の名著」「文法史関係文献目録」が付されている。執筆者:小柳智一、近藤要司、勝又隆、竹内史郎、西田隆政、福田嘉一郎、黒木邦彦、岩田美穂、山本佐和子、青木博史、小田勝、高山善行
高山善行・青木博史・福田嘉一郎編『日本語文法史研究 1』詳細。
ツイート
2013.1.28
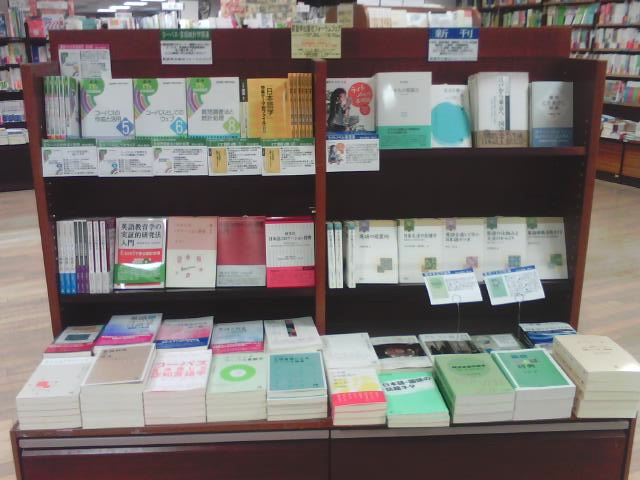
2月28日まで、紀伊國屋書店新宿南店にて言語学フェア開催!
年賀状で行ったお年玉クイズの受付を締め切りました。 クイズと正解はこちら。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。本日より、新年の営業を開始いたしました。
(年賀状お年玉クイズにご応募いただいたみなさま、ありがとうございます。お年玉クイズは1月18日締め切りです。ご応募なさる方はご注意ください。)
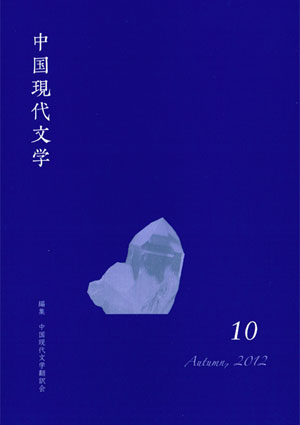
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 10』を刊行しました。
現代中国の文学作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第10号。翟永明「十四首の素歌—母へ」(組詩。母から娘へ受け継がれる時間の深遠に刻まれた歴 史)、范小青「天気予報」(短編小説。天気予報の検索履歴をめぐって繰り広げられる人間模様)、葉弥「明月寺」(短編小説。花を求めて山里へ、古い寺を守 る老夫婦との出会い)、残雪「紅葉」(短編小説。入院した辜先生の前に現れた、かつての教え子の正体は?)、紅柯「哈納斯(ハナス)湖」(中編小説。国境 アルタイ山の奥にある神秘の湖をめぐる幻想)、沈石渓「ゴーラルの飛翔」(児童文学。命をつなぐ奇跡の跳躍、谷間に架けた虹色の橋)などを掲載。
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 10』』詳細。
ツイート
2012.12.14
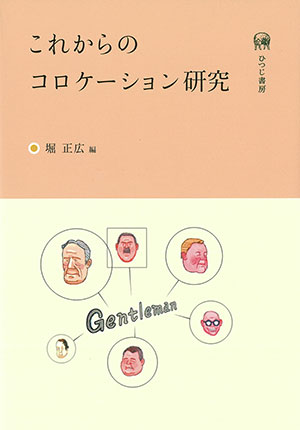
堀正広編『これからのコロケーション研究』を刊行しました。
英語教育・日本語教育・英語史・辞書学・文体等の各分野におけるコロケーション研究の第1人者が、これまでのコロケーション研究を概観・整理し、これからのコロケーション研究の可能性を様々な面から提示します。平成21年に行われた日本英語学会公開シンポジウム「これからのコロケーション研究」(堀正広、小屋多恵子、赤野一郎、田畑智司、渡辺秀樹)の発表者に加え、日本語については田野村忠温、コーパス利用の落とし穴に関しては大名力の各氏が執筆。
堀正広編『これからのコロケーション研究』詳細。
ツイート
2012.12.13

澤田治美編『ひつじ意味論講座 第6巻 意味とコンテクスト』を刊行しました。
『ひつじ意味論講座』(全7巻)の第6巻「意味とコンテクスト」。言語学のほか、様々な分野で活躍する第一線の研究者による、あらたな「意味」研究の書。
第6巻 意味とコンテクスト
1.直示とコンテクスト(渡辺伸治)
2.言語行為と発話のコンテクスト(久保進)
3.コンテクストと前提(加藤重広)
4.意味と含み(清塚邦彦)
5.関連性理論とコンテクスト(東森勲)
6.論理的意味論におけるコンテクスト(野本和幸)
7.モダリティとコンテクスト(澤田治美)
8.メタファー理解プロセスと意味(中本敬子)
9.とりたてとコンテクスト(野田尚史)
10.指示表現と結束性(庵功雄)
11.感動詞とコンテクスト(冨樫純一)
澤田治美編『ひつじ意味論講座 第6巻』詳細。
ツイート
2012.12.10

デボラ・カメロン著、林宅男監訳『話し言葉の談話分析』(言語学翻訳叢書 15)を刊行しました。
本書では、談話(特に話し言葉の)分析の理論と実践が、実際のデータと著者の深く鋭い洞察を通して巧みに解説されています。第1部はディスコースの定義と談話分析の目的及び分析のためのデータ収集と文字化の方法、第2部は談話分析のアプローチについての様々な理論(「ことばの民族誌」、「語用論」、「会話分析」、「相互行為の社会言語学」、「批判的談話分析」)の検討、第3部は談話分析のパワーやアイデンティティ等についての社会問題の研究への応用例と実際の談話分析プロジェクトの取り組み方を解説。
デボラ・カメロン著 林宅男監訳『話し言葉の談話分析』詳細。
ツイート
2012.12.4

大津由紀雄先生より、ひつじグッズをいただきました。
ありがとうございます!
大津先生には、TCPなどさまざまな面でお世話になっています。
大津由紀雄編『The Proceedings of the Twelfth Tokyo Conference on Psycholinguistics (TCP2012)』詳細
田尻英三・大津由紀雄編『言語政策を問う!』詳細
大津由紀雄研究室編『国際会議の開きかた』詳細
大津由紀雄編『ことばの宇宙への旅立ち 10代からの言語学』詳細
大津由紀雄著『ことばに魅せられて』詳細
大津由紀雄著『探検!ことばの世界(新版)』詳細
2012.12.3
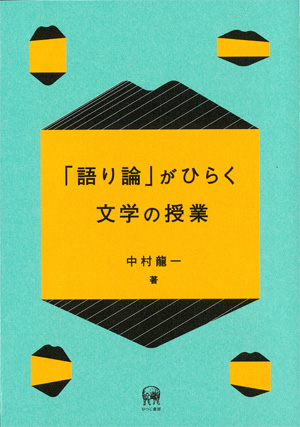
中村龍一 著『「語り論」がひらく文学の授業』を刊行しました。
国語科教育における文学作品の受容論は、読解論、視点論、読者論から、読書行為論、語り論へとひらかれてきた。「語り論」は、これまでの受容論を抱え込み新たな〈読み〉の世界を切りひらいた。物語と語り手の相克からの〈読み〉の世界である。この「語り論」を国語科教育の基礎的な実践理論とするため、著者のこれまでの考察と提案、実践報告をまとめた。一人で読む以上に、教室でみんなで文学作品を読むのは面白い。そのような授業を目指して。
中村龍一 著『「語り論」がひらく文学の授業』詳細。
ツイート
2012.11.29


近刊書籍のご案内です。
澤田治美 編『ひつじ意味論講座 第6巻 意味とコンテクスト』、デボラ・カメロン(Deborah Cameron) 著、林宅男 監訳『話し言葉の談話分析』(言語学翻訳叢書 15、原著名:Working with Spoken Discourse)の2冊を刊行します。
どちらも、12月上旬の刊行予定です。どうぞお楽しみに。
ツイート
澤田治美 編『ひつじ意味論講座 第6巻』詳細。
デボラ・カメロン著 林宅男監訳『話し言葉の談話分析』詳細。
2012.11.22

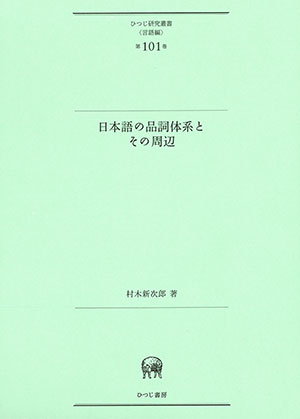
ひつじ研究叢書(言語編)より、新刊2冊のご案内です。
宗宮喜代子 著『文化の観点から見た文法の日英対照―時制・相・構文・格助詞を中心に』(第98巻)と、村木新次郎 著『日本語の品詞体系とその周辺』(第101巻)を刊行します。
ひつじ研究叢書(言語編)は、第101巻より装丁を一新します。今回の新刊2冊では、新旧の装丁が並びました。新しい装丁は、デザイン雑誌『アイデア』なども手がける白井敬尚氏にお願いしました。新しくなった言語編を、ぜひご覧下さい。
ツイート
ひつじ研究叢書(言語編) 第98巻『文化の観点から見た文法の日英対照』
文化の特徴は語彙のみでなく文法にも表れる。本書ではアングロ文化の直線思考と日本文化のウチ・ソト指向を説明原理として、時制と相など主要な文法範疇が英語と日本語で内容的に大きく異なること、その一方では各々の文法の中でこれらが空間前置詞、文字種など一見無関連な諸項目と原理を共有し、文化の特徴を反映した内容を示すことを論じる。記述は言語事実に即して客観的かつ体系的に行い、文法への理解を深めることを目指す。
宗宮喜代子 著『文化の観点から見た文法の日英対照』詳細。
ひつじ研究叢書(言語編) 第101巻『日本語の品詞体系とその周辺』
伝統的な学校文法や標準化しつつある日本語教育文法を是としない立場から、日本語のあるべき単語認定と品詞体系について提言した書。従来の文法が形式中心で、syntagmaticな側面に傾斜していたことを指摘し、意味・機能を重視し、paradigmaticな側面をとりこむ必要性を説く。形容詞をひろくとらえること、日本語の品詞として、後置詞、従属接続詞をみとめるべきであることなどを主張する。日本語の感動詞や節の類型にも言いおよぶ。
村木新次郎 著『日本語の品詞体系とその周辺』詳細。
2012.11.20

彭国躍 著『古代中国語のポライトネス―歴史社会語用論研究』(神奈川大学言語学研究叢書 3)を刊行しました。
古代中国語の敬語問題に関する初の専門書。歴史社会語用論の視点から古代中国語敬語表現の運用実態、言語規範、副詞体系および訓釈の歴史を明らかにし、言語の普遍的な対人機能―ポライトネスの起源と変遷を探究する上での古代中国語のケースを提供。鄭玄をはじめ、2千年にわたる36名の訓詁学者たちの敬語訓釈例を通し、中国のポライトネス研究史、意識史を示しつつ、包括的なポライトネス理論の通時的検証を行ないます。
彭国躍 著『古代中国語のポライトネス』詳細。
ツイート
2012.11.12
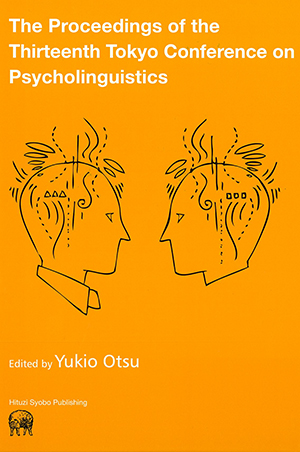
大津由紀雄 編『The Proceedings of the Thirteenth Tokyo Conference on Psycholinguistics(TCP2012)』を刊行しました。
慶應義塾大学でおこなわれている東京言語心理学会議(Tokyo Conference on Psycho-linguistics)の第13回大会の研究発表/講演集(英語)です。
大津由紀雄 編『The Proceedings of the Thirteenth Tokyo Conference on Psycholinguistics(TCP2012)』詳細。

富山から清明堂書店の方が、ご出張の際に弊社までお立ち寄りくださいました。
2012.11.6
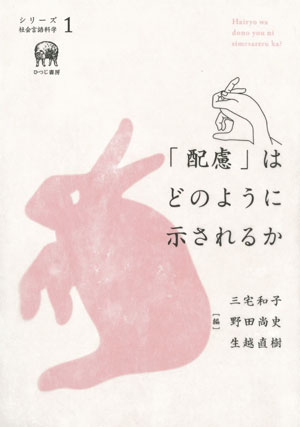
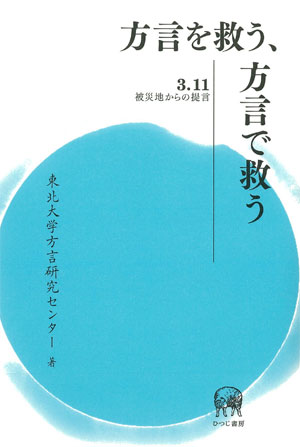
三宅和子・野田尚史・生越直樹編『「配慮」はどのように示されるか』、東北大学方言研究センター著『方言を救う、方言で救う—3.11被災地からの提言』の2冊を刊行しました。
シリーズ社会言語科学 1『「配慮」はどのように示されるか』
本書は、社会言語科学会設立10周年を記念して2009年3月に東京外国語大学で開催された2つのシンポジウム「配慮言語行動研究の新地平」と「アジア圏の社会言語科学」をもとに編まれました。社会言語科学が究明すべき現代的課題として取り上げられた2つのシンポジウムをもとに、登壇者がそれぞれの立場から新たに書き起こした「配慮」をめぐる多彩な視点をもつ論文集です。
執筆者:井出祥子・植野貴志子、井上史雄、生越直樹、姜錫祐、ザトラウスキー ポリー、高山善行、大坊郁夫、西尾純二、野田尚史、日高水穂、彭国躍、三宅和子
三宅和子・野田尚史・生越直樹編『「配慮」はどのように示されるか』詳細。
『方言を救う、方言で救う—3.11被災地からの提言』
東日本大震災は、方言にどのような影響を与えるのでしょうか。また、方言は、地域の復興にいかなる役割を果たし得るのでしょうか。そして、この震災を機に、今後方言をどうしていくべきでしょうか。本書はこのような問いのもと、危機的な方言の把握と記録・継承に向けた提言、支援者のための方言パンフレットの作成、被災者と支援者・研究者をつなぐ「方言ネット」の構築など、さまざまな課題に取り組んできた東北大学方言研究センターの活動をまとめた1冊です。
東北大学方言研究センター著『方言を救う、方言で救う』詳細。
2012.11.1
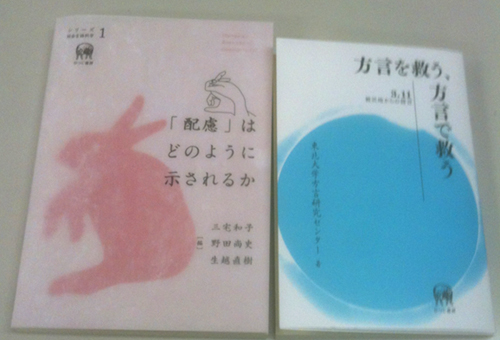
『方言を救う、方言で救う 3.11被災地からの提言』、『配慮はどのように示されるか』刊行しました。方言研究会、日本語学会にてお目見えします。よろしくお願いします。

新刊・近刊のご案内の冊子『未発ジュニア版』を発送しております。
『未発ジュニア版』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いします。
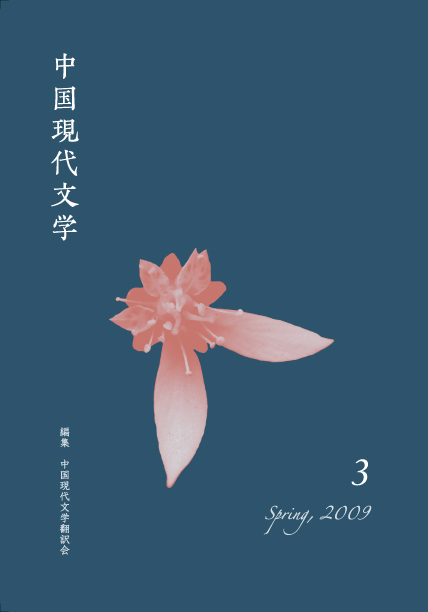
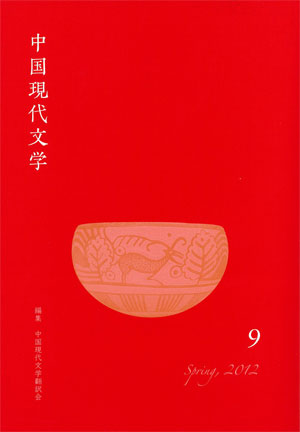
収録作品に関する情報は以下のリンクをご覧下さい。
中語現代文学翻訳会編『中国現代文学 3』詳細。
中語現代文学翻訳会編『中国現代文学 9』詳細。
What's new
2012.10.10

西田谷洋・浜田秀 編『認知物語論の臨界領域』を刊行しました。
昨年2011年に開催したワークショップ「認知物語論の臨界領域」での議論をふまえ、認知物語論の最新の成果を示す論文集です。認知物語論は、認知科学や認知言語学の成果を取り込み、物語論の再構築をめざしてきましたが、未だ理論的には完成されていません。本書は、言語行為と語りの接続、スキーマとデフォルト解釈、可能世界解読時の推論、コンストラクションと解釈、非物語的認知と寓話的解釈を、理論的な問題領域の先端と捉え、理論的・解釈的検討の実践を行いました。
西田谷洋・浜田秀 編『認知物語論の臨界領域』詳細。
2012.9.7

澤田治美 編『ひつじ意味論講座 第2巻』を刊行しました。『ひつじ意味論講座』(全7巻)の第4回配本です。言語学のほか、様々な分野で活躍する第一線の研究者による、あらたな「意味」研究の書。
第2巻 構文と意味
1.認知のダイナミズムと構文現象(山梨正明)
2.構文的意味とは何か(大堀壽夫・遠藤智子)
3.二重目的語構文と与格交替(加賀信広)
4.使役構文をめぐって(高見健一)
5.結果構文の意味論(小野尚之)
6.条件構文をめぐって(藤井聖子)
7.比較構文の語用論(澤田治)
8.場所句倒置構文をめぐって(奥野忠徳)
9.壁塗り交替(岸本秀樹)
10.中間構文の意味論的本質(吉村公宏)
11.数量詞遊離構文とアスペクト制約(三原健一)
12.コーパス分析に基づく構文研究(李在鎬)
澤田治美 編『ひつじ意味論講座 第2巻』詳細。
2012.9.7
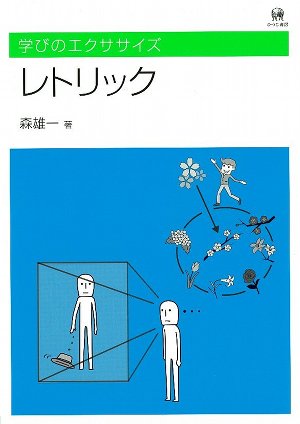
森雄一 著『学びのエクササイズ レトリック』を刊行しました。
本書は、大学1・2年生向けの教科書として、レトリックを平易に解説したものです。言葉の彩、説得の技術、物事の認識のために欠かせないもの…といったレトリックの見せるいろいろな顔を14の章をかけて照らしています。単に、レトリックに関する知識を提示するだけではなく、言葉遊びやネーミングといったレトリック周辺のテーマも扱い、読者の日本語表現力の向上にも役に立つように実践面でも工夫を凝らした構成となっています。
森雄一 著『学びのエクササイズ レトリック』詳細。
What's new
2012.9.5

西田谷洋・浜田秀 編『認知物語論の臨界領域』を近日刊行します。
昨年2011年に開催したワークショップ「認知物語論の臨界領域」での議論をふまえ、認知物語論の最新の成果を示す論文集です。認知物語論は、認知科学や認知言語学の成果を取り込み、物語論の再構築をめざしてきましたが、未だ理論的には完成されていません。本書は、言語行為と語りの接続、スキーマとデフォルト解釈、可能世界解読時の推論、コンストラクションと解釈、非物語的認知と寓話的解釈を、理論的な問題領域の先端と捉え、理論的・解釈的検討の実践を行いました。
西田谷洋・浜田秀 編『認知物語論の臨界領域』詳細。
2012.9.4

大名力 著『言語研究のための正規表現によるコーパス検索』を刊行しました。
一見、文系の研究者には無関係と思われる正規表現も、うまく利用すれば「worthの後に最大3語挟んで-ingで終わる語(ただし、thing, something, anything, everything, nothingは除く)が続く」のような条件を指定しコーパスからデータを抽出することもでき、言語研究・言語教育にも大いに役立ちます。本書では、このような言語研究に役立つ正規表現の使い方を基礎から上級まで段階的に解説しており、また、英語の例を基に基礎を学んだ後は、日本語や韓国語の検索方法に進むこともでき、自分の目的に合わせ正規表現を学ぶことができます。
大名力 著『言語研究のための正規表現によるコーパス検索』詳細。
2012.8.23

宮本正夫・小野尚之・Kingkarn Thepkanjana・上原聡編『Typological Studies on Languages in Thailand and Japan』を刊行しました。Hituzi Linguistics in English No.19です。
本書は、タイ国チュラロンコン大学言語学部と東北大学国際文化研究科附属言語脳認知総合研究センターとの共同研究活動として2010年にバンコクで行われたシンポジウムでの発表をまとめたものです。Prosody、Sound Symbolism、Reduplication、Transitivity、Resultative、Subjectivity、Pronominal Forms、Rapport Management、Blog Comments、Synesthetic Expressions、Writing Systemなど多岐にわたる分野について、認知言語学的な、あるいはニュートラルな立場から論じる1冊となっています。
宮本正夫・小野尚之・Kingkarn Thepkanjana・上原聡 編『Typological Studies on Languages in Thailand and Japan』詳細。
2012.8.20

中井陽子著『インターアクション能力を育てる日本語の会話教育』を刊行しました。シリーズ言語学と言語教育第25巻です。
人と人が会話をして友好な関係を作っていくには、「インターアクション能力」が必要である。「インターアクション能力」には、語彙・文法等の言語能力だけでなく、会話に参加していく社会言語能力や、実質的な行動を行っていく社会文化行動といった能力が含まれる。こうした能力育成を目的とした日本語の会話教育を開発するための「研究と実践の連携」のあり方を提案するとともに、教育法案を具体的に提示した。特に、教師と学習者が会話データ分析をした成果を指導学習項目化し、それを教育実践に生かすプロセスを詳述した。
中井陽子 著『インターアクション能力を育てる日本語の会話教育』詳細。
2012.8.2
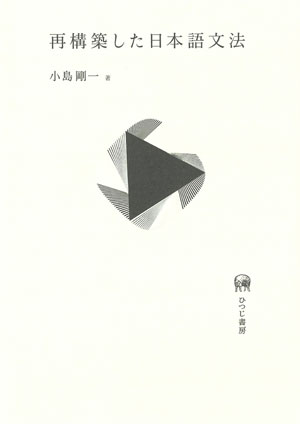
小島剛一著『再構築した日本語文法』を刊行しました。
日本語は、明快で論理的な表現もでき、曖昧模糊とした表現もできる素晴らしいコミュニケーション(およびコミュニケーション拒否)の手段です。すべての日本語話者にこの手段が有効に駆使できるように、他言語に由来する「人称」「数」「代名詞」「時制」「主語」などの無用な概念の呪縛を捨て去り、日本語に具わっている独自の豊かな構造に着目して再構築した新しい日本語文法を提唱します。
小島剛一 著『再構築した日本語文法』詳細。
2012.7.31
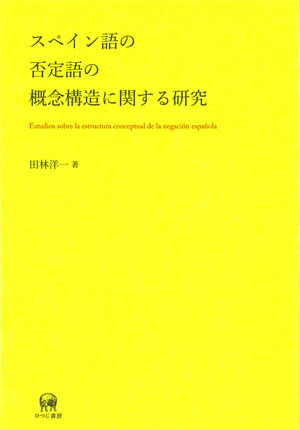
田林洋一著『スペイン語の否定語の概念構造に関する研究』を刊行しました。
本書は、スペイン語の否定現象、特にENを伴う前置詞句を主題化させると否定文になる「EN否定」と呼ばれる現象の概念構造を考察した研究です。EN否定のみならず、スペイン語の否定語に関する概念構造を網羅し、それに対して一定の説明原理を構築することを目的としています。スペイン語や否定現象に関心のある大学生、大学院生、研究者を主な対象としているが、認知言語学的な考察は、広く言語学に興味のある読者にも有益。
田林洋一 著『スペイン語の否定語の概念構造に関する研究』詳細。
2012.7.27

杉藤美代子著『日本語のアクセント、英語のアクセント―どこがどう違うのか』を刊行しました。
日本語は高さアクセント、英語は強さアクセントと言われてきたが、本当にそうなのか、両者はいったいどこがどうちがうのか、筆者は、これらを調べるために研究を始めた。そして数十年、次々と生じる疑問点について、発想の及ぶ限りの実験等を続けてきた。その過程で、日本語(特に関西アクセント)と英語のアクセントには思いがけない類似点があることを見出した。また、英語話者と日本語話者では文中のアクセントの使い方がまったく違うこと等も見えてきた。この書は、アクセントに関する入門書であり、多くの疑問点への回答書でもあります。ぜひご一読下さい。
杉藤美代子 著『日本語のアクセント、英語のアクセント』詳細。
2012.7.17
概要
おかしな文法用語がある。「爽やか」のように「形容詞」でも「動詞」でもないものをなぜ「形容動詞」と呼ぶのだろう。後接辞の「た」が「過去」を表わすという、事実に即していない説が流布している。「どいた、どいた」と言った瞬間にはまだ誰もどいていない。「さあ、買った、買った」と何度繰り返しても誰も何も買ってくれないこともある。ここに「過去」に似たものは何も無いのだ。「腹が減った」あるいは「お腹が空いた」と言う人は、「過去」のことを述べているのではない。「現在」空腹であることを表現している。探し物がやっと見つかった時に言う「あ、ここにあった」は、どう考えても「現在」の状況を述べている。それでは、日本語では何が「時」を示すのだろう。フランス人に日本語を教えて40年になる小島剛一が新しい日本語文法を書き上げた。「動詞の時制」だの「代名詞」だのは、日本語の体系には存在しないのである。
日時 2012年8月3日(金)19時〜21時 予定
場所 アジア学生文化会館
(〒113-8642 東京都文京区本駒込2-12-13 都営地下鉄三田線 千石駅(A1出口)より徒歩3分)
参加費 1,000円
詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。
小島剛一 著『再構築した日本語文法』詳細。
2012.7.9
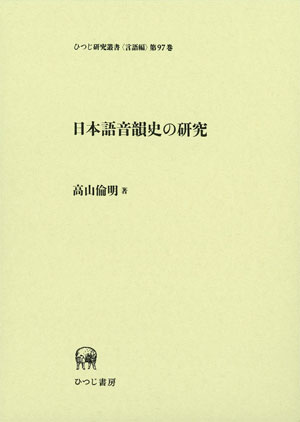
新刊書籍、高山倫明著『日本語音韻史の研究』(ひつじ研究叢書(言語編) 第97巻)のお知らせです。
日本語音韻史の研究で、定評のある著者のこれまでの研究の成果を集めた1冊。清音濁音、四つ仮名、促音、アクセント、プロソディなど、これまでも日本語音韻史の中心的で伝統的に議論されてきたテーマである題材を扱いながら、従来の学説、通説に縛られず、日本語の音韻史を革新することを提案する卓越した研究書です。
高山倫明 著『日本語音韻史の研究』詳細。
2012.6.29
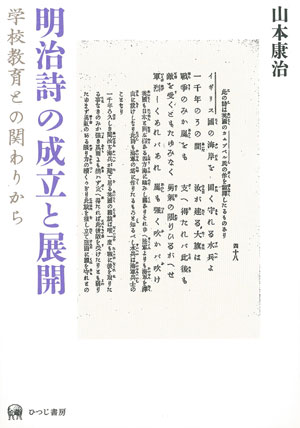
週刊読書人(2012年6月29日)に山本康治著『明治詩の成立と展開―学校教育との関わりから』の書評が掲載されました。
評者は府川源一郎先生(横浜国立大学教授)。新体詩と学校教育との関わりを追究する本書は、「新体詩は忠君愛国を旨とする学校令の影響を受けて学校教育に持ち込まれた」というような、教育と文学の共犯的な関係についての問題を鋭く提起している、とのご評価をいただきました。
山本康治 著『明治詩の成立と展開』詳細。
2012.6.25
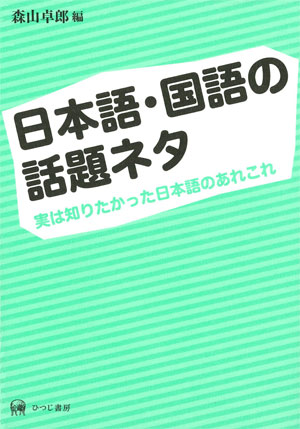
森山卓郎編『日本語・国語の話題ネタ―実は知りたかった日本語のあれこれ』を刊行しました。
「蔵人」はなぜ「くろうど」と読む?「ピアノをひく」と「風邪をひく」は関係がある? ちょっとした小話が国語(日本語)の学びを楽しくします。文字表記、語彙、文法、方言、国語の教育など様々なトピック群に分け、「授業で使える小ネタ」、「実はちょっぴり聞きたかった疑問点」、「どうでもいいけどやっぱり知りたい言葉の豆知識」などを楽しく読める1冊です。国語に関わる全ての先生、日本語の先生へ。また、大学生の参考図書などにもおすすめです。
森山卓郎 編『日本語・国語の話題ネタ』詳細。
2012.6.15


山梨正明他編『認知言語学論考No.10』、澤田治美編『ひつじ意味論講座 第4巻 モダリティⅡ:事例研究』の2冊を刊行しました。
『認知言語学論考No.10』
認知言語学の最先端の論文を継続的に掲載するシリーズ第10巻。国内外の第一線の研究者の論文を掲載し、多岐にわたる認知言語学や関連する言語学の最新研究成果を掲載します。今巻より装丁を変更し、上製本となりました。
執筆者:古牧久典、内田諭、尾谷昌則、久保田ひろい、吉川正人、遠藤智子、有光奈美
山梨正明 他編『認知言語学論考No.10』詳細。
『ひつじ意味論講座第4巻 モダリティⅡ:事例研究』
『ひつじ意味論講座』(全7巻)の第3回配本です。言語学のほか、様々な分野で活躍する第一線の研究者による、あらたな「意味」研究の書。
執筆者:柏本吉章、長友俊一郎、吉良文孝、澤田治美、黒滝真理子、宮崎和人、土岐留美江、野田春美、半藤英明、杉村泰、井上優、守屋三千代
澤田治美 編『ひつじ意味論講座第4巻』詳細。
2012.6.15
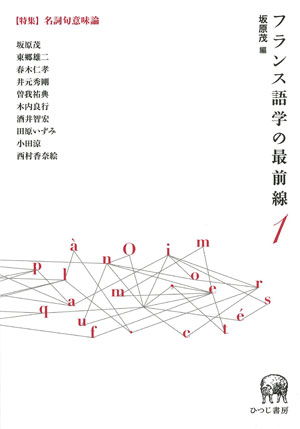
『フランス語学の最前線1 【特集】名詞句意味論』を刊行しました。
フランス語学の最先端の研究を取り上げるシリーズ「フランス語学の最前線」の第1巻です。本シリーズでは特集テーマ論文を主に、特集外論文も収め、さまざまな関心に応えられる論文集を目指します。収録論文は、フランス語学を基盤としながらも、広く一般言語学的視野を射程に収めたものです。
第1巻では名詞句研究を中心に、冠詞、存在文、指示形容詞、否定、時間表現、使役構文などさまざまな研究を収録してます。
執筆者:坂原茂、東郷雄二、春木仁孝、曽我祐典、井元秀剛、木内良行、田原いずみ、酒井智宏、小田涼、西村香奈絵
坂原茂 編『フランス語学の最前線1』詳細。
2012.6.12
日本語ジェンダー学会第13回年次大会が開催されます。
(武蔵野大学有明キャンパス 2012年6月16日〔土〕10時30分〜17時)
大会の詳細は公式サイトをご覧下さい。
日本語ジェンダー学会
2012.6.11

神奈川大学言語学研究叢書2『モダリティと言語教育』を刊行しました。
言語教育においてモダリティを適切に教えることは必ずしも容易ではありません。本書は、日本語・中国語・韓国語・ロシア語・英語のそれぞれの各言語におけるモダリティ研究の最先端を紹介し、どのように言語教育に生かすことができるのか、言語教育に必要なモダリティ研究とは何かについて論じた1冊です。
執筆者:砂川有里子、アンドレイ・ベケシュ、黒沢晶子、彭国躍、文彰鶴、佐藤由美・久保野雅史、堤正典、小林潔、富谷玲子、武内道子
富谷玲子・堤正典 編『モダリティと言語教育』詳細。
2012.6.1
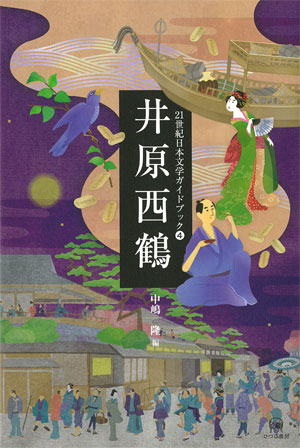
21世紀日本文学ガイドブック4『井原西鶴』を刊行しました!21世紀日本文学ガイドブックシリーズの第2回配本です。
本書では、西鶴の魅力を、最新研究成果をふまえながら、わかりやすく解説します。江戸時代初期の出版文化を視野に置き、西鶴の俳諧と浮世草子について、メディア史・東アジア文化史・テキスト構造など多様な観点から言及。参考文献も豊富に掲載し、学生には格好の参考書になります。井上和人、染谷智幸、森耕一、森田雅也など、気鋭の研究者が執筆。
中嶋隆 編 21世紀日本文学ガイドブック4『井原西鶴』詳細。
2012.5.16

新刊・近刊のご案内の冊子『未発ジュニア版』を発送しております。
『未発ジュニア版』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いします。

中西久実子著『現代日本語のとりたて助詞と習得』(シリーズ言語学と言語教育28巻)、学会では今週末の方言研究会・日本語学会でお目見えします。
とりたて助詞の特徴を語用論的に規定し、その使用実態と習得の実態を明らかにした研究書。とりたて助詞というのは、前提推意を外部否定型で否定して表出命題の顕在化を表すものであり、何が前提推意になっているかによって肯定的用法か否定的用法になる。本書の前半ではこの規定に基づいて「も」「だけ」などとりたて助詞の特徴を明らかにし、後半では、コーパスによる調査で日本語学習者の習得の実態を示している。
中西久実子 著『現代日本語のとりたて助詞と習得』詳細
2012.5.8

大場美和子著『接触場面における三者会話の研究』刊行しました。シリーズ言語学と言語教育27巻です。
本書は、接触場面と内的場面の三者自由会話を対象に、話題開始の発話とそれに応答する発話に着目し、発話者、発話の方向、発話の種類、参加者の情報量という観点から分類を行い、二者会話とは異なる三者会話の実態を探ったものです。留学生が2人の日本人学生と日本語で話すのは困難なようですが、データからは参加者の役割調整の負担の軽減も観察され、多様な会話への参加の実態を教育現場で活用する可能性を示唆しています。
大場美和子 著『接触場面における三者会話の研究』詳細
2012.4.26
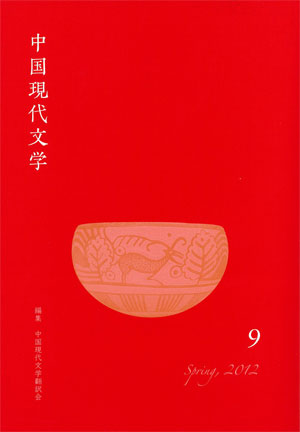
現代中国の文学作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第9号。鮑十「ヒマワリの咲く音」(元国語教師が人生の終わりに聞いたヒマワリの咲く音)、莫言「普通話(プートンホア)」(山村で標準語を推進していた女性教師の身に何が?)、鄭小驢「鬼節(グイジエ)」(あの年の中元節、母は決心した…)、残雪「鹿二(ルーアル)の心配」(私たちは虚空に跳躍し、生まれ変わることができるのか?)、史鉄生「たとえばロックと“書く”こと」「地壇を想う」(随筆集『記憶と印象』を締めくくる2編。本誌創刊号からの連載完結)などを掲載。
中国現代文学翻訳会 編『中国現代文学 9』詳細
2012.4.26

アマゾンでは「この本は現在お取り扱いできません。」と表示されていますが、弊社には問題なく在庫しており、注文分に対しては出荷をしています。アマゾンのサーバーの何らかのバグと思われますので、最寄りの書店でご注文下さい。お客様からの発注数とアマゾンの在庫計画が合わないと、「入荷未定」表示になります。注文に対しては次々と出荷していますので、在庫状態の表示はこくこくと変わっていきますので、アマゾンで購入されたい方は、アマゾンをチェックして下さい。もよりの書店からも注文できます。

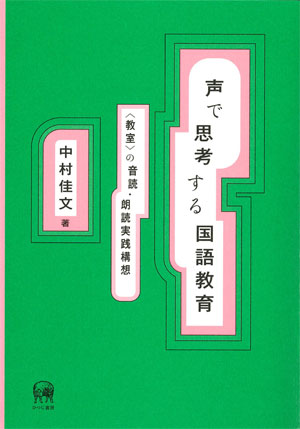
『ベーシックコーパス言語学』、『声で思考する国語教育 〈教室〉の音読・朗読実践構想』の2冊を刊行しました!
『ベーシックコーパス言語学』石川慎一郎 著
コーパス言語学(corpus linguistics)は、1990年代以降、急速な進展を見せ、現在 、言語や言語教育に関わる幅広い研究分野に大きな影響を及ぼしています。本書は、英語コーパスと日本語コーパスの両者に目配りしつつ、初学者を対象に、豊富な実例を通して、コーパスの諸相やコーパスを生かした言語研究の方法論について平易に解き明かしています。
『ベーシックコーパス言語学』石川慎一郎 著
『声で思考する国語教育 〈教室〉の音読・朗読実践構想』中村佳文 著
本書は、自らの音声表現のあり方に疑問を抱き検証を続けてきた著者が、教育現場での実践を踏まえてその理論と効用をまとめものである。音声表現とは常に〈解釈〉との関連を考慮しつつ、「理解」と「表現」という目的をもって行なうべきであるとし、その具体的な方法論を提唱している。文学作品冒頭文・韻文(和歌・漢詩・近現代詩)・『平家物語』・『走れメロス』などを教材にした「声で思考する〈国語教育〉」の実践を理論化した一書である。
『声で思考する国語教育 〈教室〉の音読・朗読実践構想』中村佳文 著
2012.4.2

新入社員1名を迎え、入社式を行いました。播磨坂のイタリアンレストラン・Tanta Robaにて。
スタッフ日誌 新入社員のご挨拶はこちら
2012.3.29
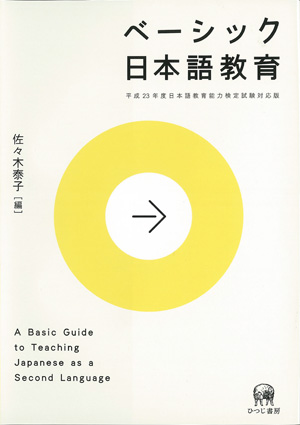
2007年に刊行し、現在も好評をいただいている本書ですが、その後の教育業界の進展、日本語能力試験改定、日本語教育能力検定試験の一部改訂などの流れを受けて、今回の版では主に日本語能力試験のレベル別の表が掲載されている10章を中心に情報のアップデートを行いました。引き続き、内容の全面改定を行ってまいる予定です。
佐々木泰子編『ベーシック日本語教育』詳細
2012.3.21

高度経済成長期の祝祭的な高揚感は、戦後日本の問題を〈忘却〉させ、〈記憶〉の再構成を促した。「やさしさ」が価値となり、モラトリアム感覚が蔓延した。本書では、この時代を近代の分節点と規定し、知性・大衆・愛欲・事件・教化という五つの概念を用いつつ、柴田翔、庄司薫、大江健三郎、川上宗薫、松本清張、吉川英治、三島由紀夫などの文学を読み解くとともに、万博、同棲ブーム、吉永小百合の表象といったトピックに迫った。
石川巧 著『高度経済成長期の文学』詳細
2012.3.7
進化言語学は言語能力の起源・進化を通じて人間の本性の根本的理解を目指す、学際色豊かな研究領域である。この新しい人間科学の最前線の姿を伝えるべく編集された本書は、言語学、認知生物学、生物人類学、脳機能イメージング、遺伝子進化学、ロボット工学、コンピュータ・シミュレーション等々、多彩な関連分野の第一線に立つ研究者たちによる全13章からなる我が国初の専門論文集である。巻末には白熱した討論会の模様も収録した。2012年3月『第9回言語進化の国際会議』(EVOLANG IX)京都大会開催記念出版。
★詳細ページでご注文書をダウンロードいただけます。
藤田耕司・岡ノ谷一夫編『進化言語学の構築—新しい人間科学を目指して』詳細
2012.3.7

続々と新刊を刊行しています。第二弾の3冊です。
和泉司著『日本統治期台湾と帝国の〈文壇〉 〈文学懸賞〉がつくる〈日本語文学〉』詳細
本田弘之著『文革から「改革開放」期における中国朝鮮族の日本語教育の研究』詳細
山本康治著『明治詩の成立と展開 学校教育との関わりから』詳細
2012.3.5

続々と新刊を刊行しています。第一弾の4冊をご紹介します。
平野尊識著『Tagalog Grammar A Typological Perspective』詳細
塚本秀樹著『形態論と統語論の相互作用–日本語と朝鮮語の対照言語学的研究』詳細
金庚芬著『日本語と韓国語の「ほめ」に関する対照研究』詳細
堀川智也著『日本語の「主題」』詳細
2012.2.20

大学での学習に必要なコミュニケーション能力とライティング能力を身につけるための実践的表現活動をタスク化したテキスト。各課のタスクは仲間同士の対話(ピア活動)を通じて行われる。前半では学習計画書・志望動機書を書き、口頭発表を行う。後半では、本を紹介し合い批判的に分析するグループワーク(ブック・トーク)からレポート執筆までの流れを通じて、批判的に読み、書く能力を育成する。大学入学後の初年次教育や入試・編入の小論文指導に適した活動型教科書。正確な文や表現を書くためのエクササイズも豊富。
★『ピアで学ぶ大学生の日本語表現』はもりだくさんで全部を教えるのがちょっとむずかしい…という声、日本語の表現について、もうすこしベーシックなところから教えていきたいという声などにお答えして、つまずきやすいところにひと工夫を加えたテキストとなっています。
★非母語話者向けの語彙リストや指導用ヒント(模擬授業の映像)なども準備中です。
大島弥生・大場理恵子・岩田夏穂・池田玲子著『ピアで学ぶ大学生・留学生の日本語コミュニケーション—プレゼンテーションとライティング』詳細
2012.2.15
ひつじ書房は、書籍編集と営業・商品管理について、人手が不足しています。スタッフを募集します。小さな会社ですので、細かい仕事の区分けはなく、その時その時で、必要な仕事は行ってもらいます。本が好きで、好奇心のある方を募集します。未経験者可です。新卒可。編集・本作りを一から教えます。詳細は次のリンク先をご覧下さい。
求人・採用について
2012.2.1

大学での学習に必要なコミュニケーション能力とライティング能力を身につけるための実践的表現活動をタスク化したテキスト。各課のタスクは仲間同士の対話(ピア活動)を通じて行われる。前半では学習計画書・志望動機書を書き、口頭発表を行う。後半では、本を紹介し合い批判的に分析するグループワーク(ブック・トーク)からレポート執筆までの流れを通じて、批判的に読み、書く能力を育成する。大学入学後の初年次教育や入試・編入の小論文指導に適した活動型教科書。正確な文や表現を書くためのエクササイズも豊富。
★『ピアで学ぶ大学生の日本語表現』はもりだくさんで全部を教えるのがちょっとむずかしい…という声、日本語の表現について、もうすこしベーシックなところから教えていきたいという声などにお答えして、つまずきやすいところにひと工夫を加えたテキストとなっています。
★非母語話者向けの語彙リストや指導用ヒント(模擬授業の映像)なども準備中です。
大島弥生・大場理恵子・岩田夏穂・池田玲子著『ピアで学ぶ大学生・留学生の日本語コミュニケーション—プレゼンテーションとライティング』詳細
2012.1.19
ひつじ書房は、書籍編集と営業・商品管理について、人手が不足しています。スタッフを募集します。小さな会社ですので、細かい仕事の区分けはなく、その時その時で、必要な仕事は行ってもらいます。本が好きで、好奇心のある方を募集します。未経験者可です。新卒可。詳細は次のリンク先をご覧下さい。
茗荷バレーで働く編集長兼社長からの手紙—ルネッサンス・パブリッシャー宣言、再び。
2012.1.11

大津由紀雄先生より、ひつじグッズのつめあわせをいただきました。
ありがとうございます!
大津先生には、TCPなどさまざまな面でお世話になっています。
大津由紀雄編『The Proceedings of the Twelfth Tokyo Conference on Psycholinguistics (TCP2011)』詳細
田尻英三・大津由紀雄編『言語政策を問う!』詳細
大津由紀雄研究室編『国際会議の開きかた』詳細
大津由紀雄編『ことばの宇宙への旅立ち 10代からの言語学』詳細
大津由紀雄著『ことばに魅せられて』詳細
大津由紀雄著『探検!ことばの世界(新版)』詳細
2012.1.5
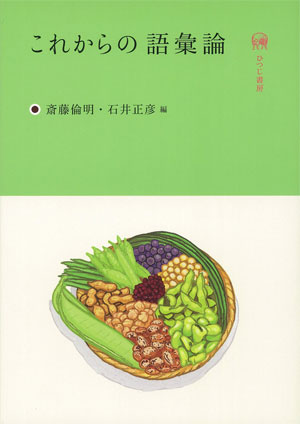
2011年末、ながらくお待たせしておりました『これからの語彙論』が刊行いたしました。
編者らによる語彙論の基礎とこれまでの成果の概説をふまえ、フェミニズム、認知言語学、日本語教
育、民俗学、情報学などの立場からの語彙研究を紹介していく新しい概説書。語彙研究の今後の可能性を展望する。執筆者:小野正弘、影浦峡、笹原宏之、佐竹久仁子、佐竹秀雄、定延利之、鈴木智美、高崎みどり、田野村忠温、町博光、屋名池誠、由本陽子。
斎藤倫明・石井正彦編『これからの語彙論』詳細
2011.12.28

これからの言語研究において習得すべき分析方法を、最新の研究成果と共に紹介する。文法、コロケーション、コミュニケーション、言語習得、音声等の研究における、コーパスの可能性、心理言語学的実験方法、音声収録・分析の手法などを示す。執筆者:藤村逸子、滝沢直宏、大曾美恵子、大島義和、木下徹、山下淳子、杉浦正利、加籐高志、成田克史、大名力、笠井直美。
藤村逸子・滝沢直宏 編『言語研究の技法 データの収集と分析』詳細
2011.11.25

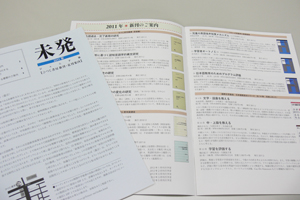
書籍目録『未発』ジュニア版です。今回のジュニア版は、全点目録ではなく、今年出た新刊と来年に刊行する近刊の紹介がメインコンテンツです。以下のページからPDFをご覧いただけますので、どうぞご覧下さい。
未発2011年ジュニア版PDFのページ
2011.11.16

『平家物語の多角的研究 屋代本を拠点として』を刊行しました!
本書は、平成20年度〜22年度科学研究費補助金による共同研究「平家物語の初期形態に関する多角的研究−屋代本を拠点として−」の、3年間にわたる研究成果(調査・報告・講演・シンポジウム)をまとめたもです。研究範囲は、文学研究から言語研究、歴史研究に及び、平家物語研究の新しい時代を切り開く1冊です。
執筆者:佐倉由泰・佐々木孝浩・吉田永弘・千明守・伊藤悦子・松尾葦江・大谷貞徳・原田敦史・多ヶ谷有子・内田康・山本岳史・野口実・佐伯真一・高橋典幸・坂井孝一
千明守 編『平家物語の多角的研究 屋代本を拠点として』詳細
2011.11.9
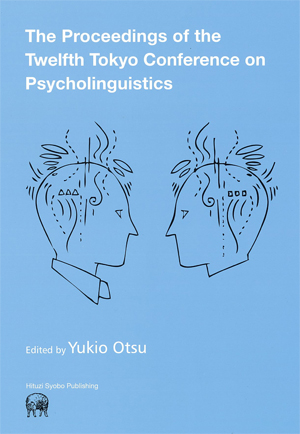
『The Proceedings of the Twelfth Tokyo Conference on Psycholinguistics (TCP2011)』を刊行しました!
慶應義塾大学でおこなわれている東京言語心理学会議(Tokyo Conference on Psycho-linguistics)の第12回大会の研究発表/講演集(英語)。
大津由紀雄 編『The Proceedings of the Twelfth Tokyo Conference on Psycholinguistics (TCP2011)』詳細
2011.11.1
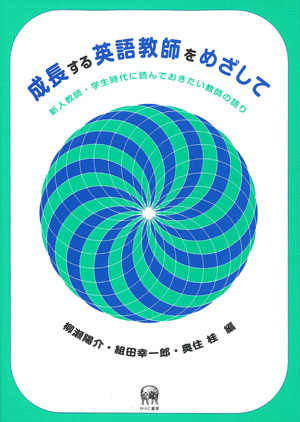
旺文社の小学校英語期活動のサポートページ「学校英語ハピラボ」で、『成長する英語教師をめざして 新人教師・学生時代に読んでおきたい教師の語り』を紹介していただきました。「役立つ!書籍Web一覧」の「外国語学習」のコーナーです。
柳瀬陽介・組田幸一郎・奥住桂 編 『成長する英語教師をめざして 新人教師・学生時代に読んでおきたい教師の語り』詳細。
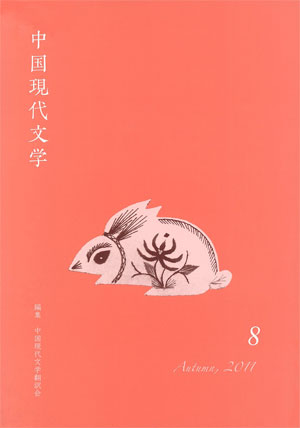
続々と新刊を刊行しております。中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 8』を刊行しました。かわいいピンクのうさぎが目印です。
現代中国の文学作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第8号。蘇童「西瓜舟」(毎年夏にやってくる西瓜売りの舟で事件は起こった…)、遅子建「北極村童話」(少女は最北の村で不思議な老女に出会う…。作者の原点となる作品)、徐則臣「養蜂場旅館」(旅先の宿の女将から意外な事を告げられた男は…)、劉慶邦「いちめんの白い花」(村を訪れた女性画家と村人たちとの心暖まる触れ合い)、史鉄生「荘子(ジュアンズ)」(1976年の夏、19の少年は集団武闘の中で死んだ…)などを掲載。
中国現代文学翻訳会 編 『中国現代文学 8』詳細。
2011.10.25


釘貫亨・宮地朝子編『ことばに向かう日本の学知』、森篤嗣・庵功雄編『日本語教育文法のための多様なアプローチ』の2冊を刊行しました。
『ことばに向かう日本の学知』は、2010年9月に開催された名古屋大学グローバルCOEプログラム第9回国際研究集会「ことばに向かう日本の学知」を元にした論文集です。第一線の研究者による、音韻学史、文法学史、方言学史、また伝統的学史から科学史にいたるまで、学史をテーマとし広く日本語に向かう学知を包括的に論じた初の試みとなります。
執筆者:カレル・フィアラ、金銀珠、宮地朝子、小柳智一、松澤和宏、狩俣繁久、李漢燮、ズデンカ・シュヴァルツォヴァー、釘貫亨、山東功、安田尚道、肥爪周二、岡島昭浩、齋藤文俊、今野真二
『日本語教育文法のための多様なアプローチ』は、これから日本語教育文法研究を志す研究者や院生に向け、コーパス調査、アンケート調査、授業実験、統計分析などを用いた具体的な方法としてのケーススタディ・解説を収録。「日本語教育文法」への参入を促す1冊です。
執筆者:庵功雄、岩田一成、太田陽子、小西円、建石始、中俣尚紀、橋本直幸、藤城浩子、松田真希子、森篤嗣
釘貫亨・宮地朝子編『ことばに向かう日本の学知』詳細。
森篤嗣・庵功雄編『日本語教育文法のための多様なアプローチ』詳細。
2011.10.20
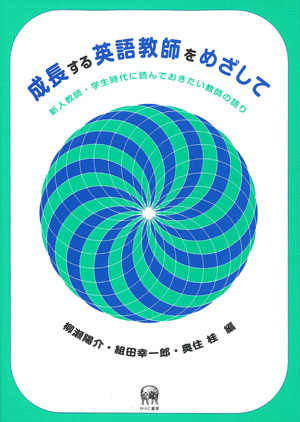
「読売新聞」(2011年10月20日)教育面で、『成長する英語教師をめざして』の紹介が掲載されました。
柳瀬陽介・組田幸一郎・奥住桂 編 『成長する英語教師をめざして 新人教師・学生時代に読んでおきたい教師の語り』詳細。
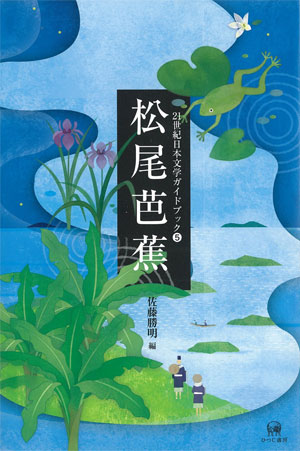
21世紀日本文学ガイドブック5『松尾芭蕉』を刊行しました!21世紀日本文学ガイドブックシリーズの第1回配本です。
本書は、松尾芭蕉の人とその文学を知るための入門書です。韻文史に芭蕉が登場した意義をはじめ、その生涯、摂取した先行文学、蕉門の人々、関連する俳書、主要研究書などを紹介します。さらに筆跡の問題、紀行文や俳論の特色、当代俳壇での位置や後世への影響など芭蕉に関する興味深いトピックを集めました。
執筆者:佐藤勝明・伊藤善隆・中森康之・金田房子・越後敬子・大城悦子・黒川桃子・小財陽平・山形彩美・小林孔・金子俊之・永田英理・竹下義人・玉城司
佐藤勝明 編 21世紀日本文学ガイドブック5『松尾芭蕉』詳細。
2011.9.29


昨年2010年に開催したひつじ書房20周年記念シンポジウム「可能性としての文学教育」、「書くことの倫理」の書籍化! 当日の登壇者の他、新たに執筆者を加え文系や理系の学問の枠を越えて、現代の社会を生きる我々にとって重要な問題に取り組みます。カバーの背景は画像では分かりにくいですがきれいな銀色です。
助川幸逸郎・相沢毅彦編『可能性としてのリテラシー教育』詳細 *この十数年で、情報の伝えられ方は想定できなかったほどの変化を遂げた。この新しい状況に対応した読解力、表現力とはどのようなものかを考え、21世紀の国語教育がいかにあるべきかを提唱する。現場の教員や国語教育の研究者のみならず、音楽学者や物理学者、フランス文学研究者などの意見も結集させ、こうした時代だからこそ、文学教育にできることを問いかける書。2010年9月に行なわれた、ひつじ書房創立20周年記念シンポジウムをもとに、新たな執筆者を迎えて編集。
助川幸逸郎・堀啓子編『21世紀における語ることの倫理』詳細 *雑誌、放送などの既存メディアには、編集者やプロデューサーといった、情報の価値を判断する〈管理人〉がいた。現在では、インターネットを通じて、誰のチェックを受けていない情報が、不特定多数の対象にむけて発信されている。こうした〈管理人不在〉の環境の中で、価値ある情報を見分け、情報がやりとりされる〈場〉を維持していくために、われわれがなしうることを考える。気鋭の文藝批評家や国際金融専門家などが参加して行なわれた、ひつじ書房創立20周年記念シンポジウムを母胎とする一書。

「教育新聞」(2011.9.22)に編者である佐野正俊先生へのインタビューが掲載されました。
「自分の頭で考える」ことが改めて求められる現代にあって、村上春樹作品を教室の中で有効に生かすこと、その一助として。

定評ある書評紙図書新聞(2011.10.1 3021号)で書評。広島工業大学、荒木直樹先生よる書評です。
浜口稔著『言語機械の普遍幻想―西洋言語思想史における「言葉と事物」問題をめぐって』詳細。
浜口稔先生は言語学を今井邦彦先生、文学を高山宏先生に学ぶという都立大学英文学科のスパーハイブリッドと呼ぶべき研究者です。
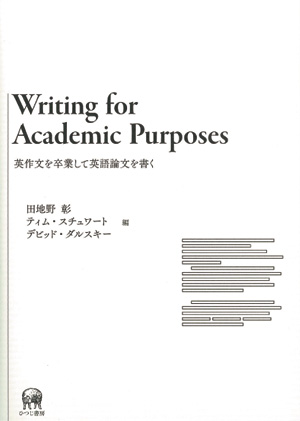
田地野彰、ティム・スチュワート、デビッド・ダルスキー編『Writing for Academic Purposes 英作文を卒業して英語論文を書く』が、大学英語教育学会賞実践賞を受賞しました。大学英語教育学会賞は1977年に創設された賞で、大学を中心とする英語教育で業績をあげた個人または団体に授与されます。
田地野彰、ティム・スチュワート、デビッド・ダルスキー編『Writing for Academic Purposes 英作文を卒業して英語論文を書く』詳細。
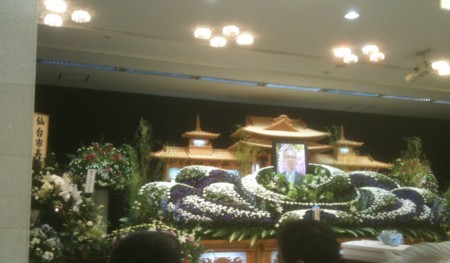
『市民の日本語』の著者、加藤哲夫さんが、26日午前零時半にお亡くなりになりました。31日が62歳のお誕生日のはずでした。享年61歳です。ご冥福をお祈りします。
『市民の日本語』
「茗荷バレーで働く編集長兼社長からの手紙」
2011.8.22

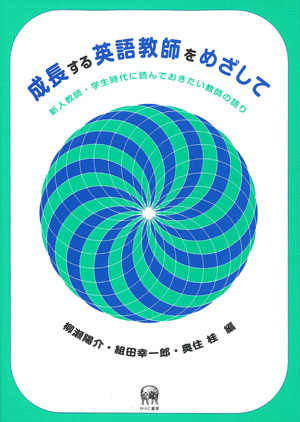
中島平三 著『ファンダメンタル英語学 改訂版』詳細 *英語学の入門テキストとして好評の『ファンダメンタル英語学』、1995年初版を大幅改訂しました。「英語学研究のエッセンスをなるべく時流に流されない形でしかもコンパクトに提供」という方針を継承しつつ、その後の研究で明らかにされた新たな分析法や説明法を積極的に取り入れました。
柳瀬陽介・組田幸一郎・奥住桂 編『成長する英語教師をめざして 新人教師・学生時代に読んでおきたい教師の語り』詳細
*英語教師を目指す(主に)若者へ、日本で英語を教育することの「意味」を示した書。英語教師の実態を、実践者・経験者ならではの具体的なエピソードや教員としての充実感を盛り込みながら描いています。
2011.8.8

『社会参加をめざす日本語教育 社会に関わる、つながる、働きかける』を刊行しました!
日本語教育の現状における様々な問題点を乗り越えるために日本語教室で行った実践を「社会参加」をキーワードとして分析、考察したものです。カタカナ、ブログ、ポッドキャストプロジェクトの3つの実践から構成されており、様々な視点から実践を分析しその可能性と問題点を考えます。学際的な協働思考の試みを一冊の本にすることで、「社会参加」を目指す日本語教育の新たなビジョンを読者に提供!
佐藤慎司・熊谷由理 編『社会参加をめざす日本語教育 社会に関わる、つながる、働きかける』詳細
2011.8.4
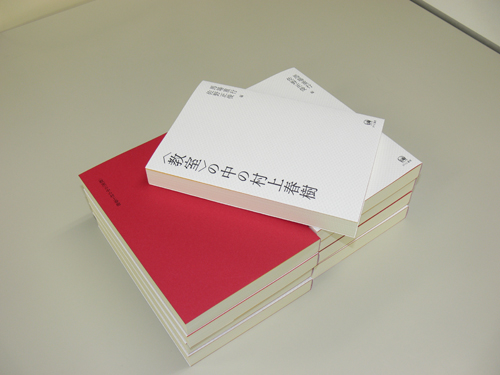
『〈教室〉の中の村上春樹』刊行しました! 作家村上春樹の小説が中高の国語の教科書に掲載されているということは、当然といえば当然のことかもしれませんが、あまり知られていないのではないかと思います。その一方で、春樹文学は面白いがわけが分からないという声は教師からも生徒からも上がっています。本書は、文学研究者・現場の教師が総力を挙げ村上春樹の翻訳を含む小説の教材価値を発掘し、さらには新たな春樹文学を読むことの可能性をも浮き彫りにします。内田樹氏による書き下ろし論考も収録。
馬場重行・佐野正俊 編『〈教室〉の中の村上春樹』詳細
書店様用注文書(PDF)
2011.8.3
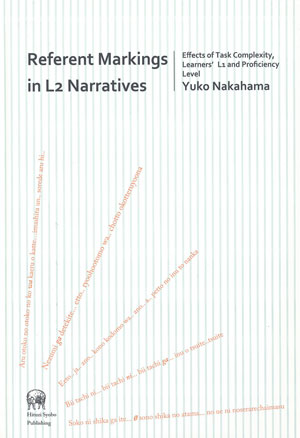
『Referent Markings in L2 Narratives: Effects of Task Complexity, Learners’L1 and Proficiency Level』刊行しました!
日本語学習者が如何に形式と意味のマッピングをしながら、結束性のあるナラティブを産出するのかを、指示対象の言及という観点から考察。近年、第二言語習得研究で注目されている“タスク”に着目し、タスクの種類とナラティブ談話構成との関係について、学習者の母語・言語習熟度という視点から解明を試みた点が意義深い。教育学的示唆にも富んでおり、研究者はもとより、語学教育者にとっても有用性が高く、教育現場にも還元できる研究書。
中浜優子(Yuko Nakahama)著『Referent Markings in L2 Narratives: Effects of Task Complexity, Learners’L1 and Proficiency Level』詳細
2011.8.1

『〈教室〉の中の村上春樹』もうすぐ刊行です! 村上春樹の教科書掲載作品(翻訳含)について、新たな教材価値を発掘しようと試みた本邦初の論集。
馬場重行・佐野正俊 編『〈教室〉の中の村上春樹』詳細
書店様用注文書(PDF)
2011.7.25
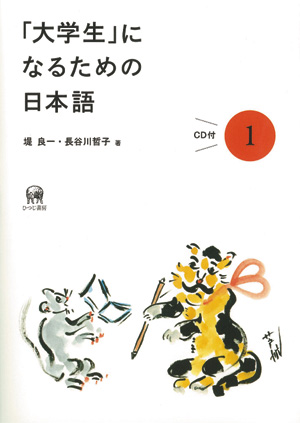
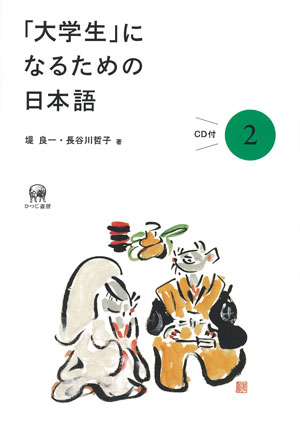
先日の大阪でのイベントに続く『「大学生」になるための日本語』イベント第3弾を開催します。
* * *
一昨年10月にひつじ書房で初めての、日本の大学への進学を希望する日本語学習者向けテキスト『「大学生」になるための日本語1』を刊行しました。そして、昨年11月にそのかたわれの『「大学生」になるための日本語2』を刊行しました。「文法とタスクの融合」を目指しているところを始めとして、読解・聴解のひとつひとつにおいて、大変画期的なテキストです。
完結して半年が経とうとしていますが、みなさまにもっと『「大学生」になるための日本語』というテキストのことを知っていただくため、好評だった東京、大阪での開催に引き続き、名古屋でもイベントを開催いたします。
* * *
今回はワークショップ形式となります。著者の堤先生と長谷川先生におこしいただき、本テキストを用いた授業展開について考えたいと思います。
お手にとってくださった方も、そうでない方も、本テキストをくわしく知ることのできる絶好の機会ですので、ぜひおこしください!
★イベント名
「留学生の日本語力を高めるために 『「大学生」になるための日本語』を使用して」
大学進学希望の学習者を対象にした『「大学生」になるための日本語』1・2巻は、茂木健一郎や福岡伸一を始めとした豪華な生教材によって各学問分野にふれながら、N2程度の文法が学べる総合テキストです。また、文型練習の例文には「場面(タスク)」がつき、文法とタスクの融合も目指しています。本イベントでは、『「大学生」になるための日本語」』がどのようなコンセプトで作られ、どのような構成になっているかを概説します。後半では参加者の方々とワークショップ形式で、本テキストを用いた授業展開について考えてみたいと思います。
〈講師〉
堤良一(つつみ りょういち) 岡山大学准教授
長谷川哲子(はせがわ のりこ) 関西学院大学准教授
〈日時・場所〉
2011年7月30日(土) 14時半〜16時(受付開始14時)
於 ウインクあいち[WINC AICHI]
定員:60名
参加費:1000円(当日会場でお支払いください)
★お申し込み・詳細についてのお問い合わせは凡人社大阪営業所まで
http://www.bonjinsha.com/event/
詳しくは板東のスタッフ日誌をご覧ください。
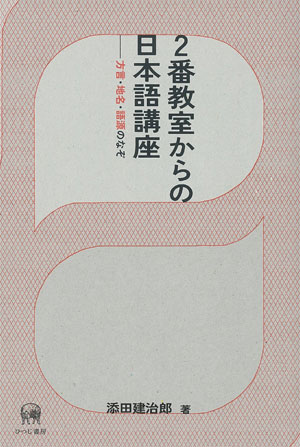
『2番教室からの日本語講座 方言・地名・語源のなぞ』を刊行しました! 著者の添田建治郎先生が、山口大学で長年ご担当されてきた日本語学の授業をもとにした「日本語講座」です。
添田建治郎 著『2番教室からの日本語講座 方言・地名・語源のなぞ』詳細
2011.7.13
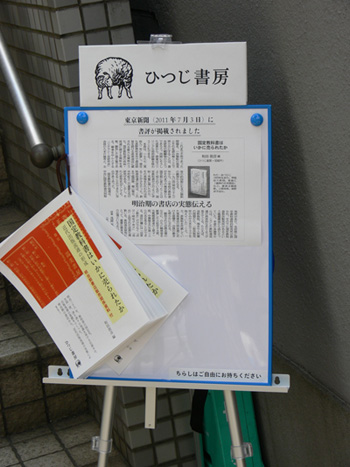
和田敦彦 編『国定教科書はいかに売られたか』詳細
2011.7.3
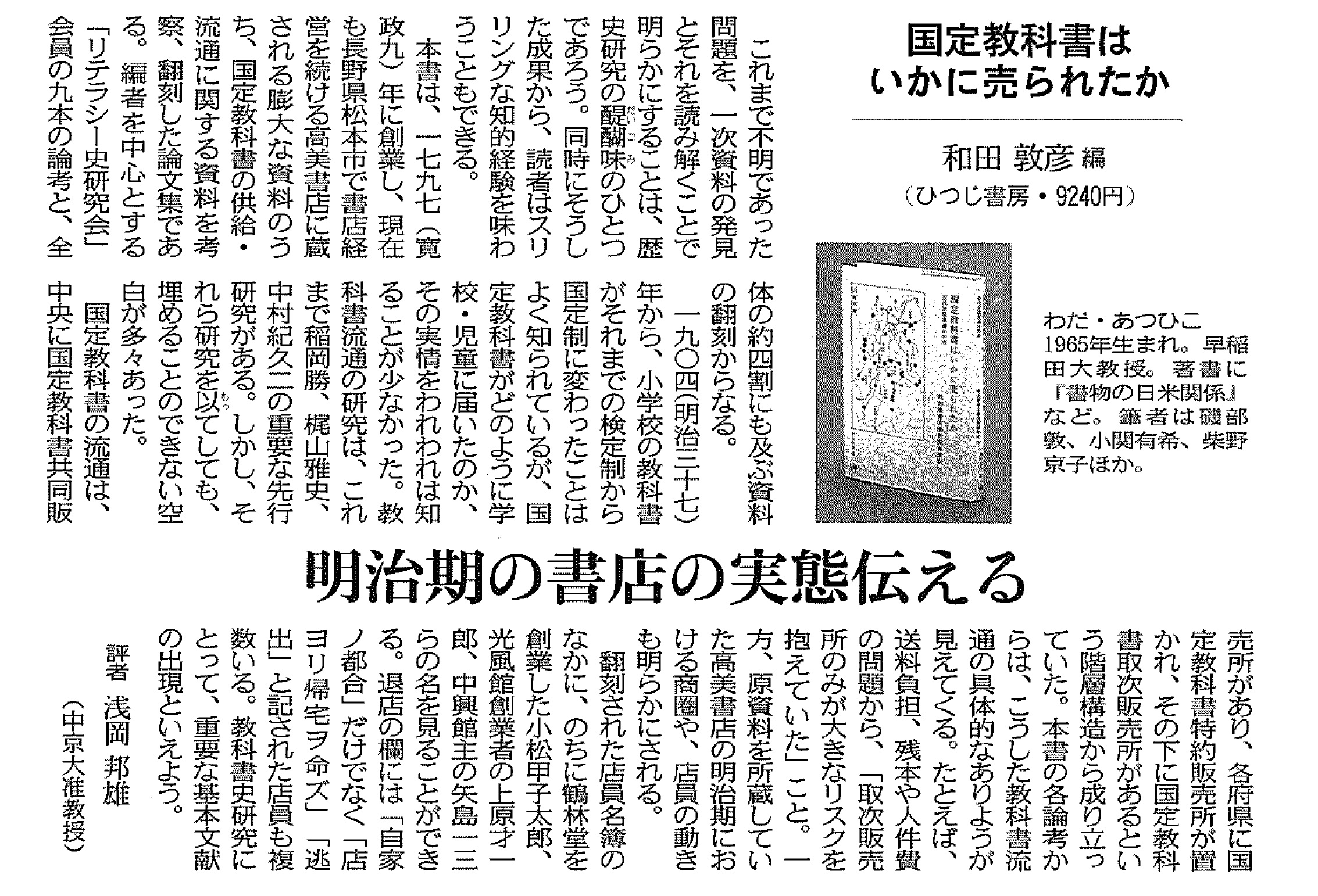
和田敦彦 編『国定教科書はいかに売られたか』詳細
2011.6.28

今春つくった『未発』24号のPDFを公開しました。
弊社刊行物の最新情報が掲載されています。
どうぞご覧下さい。
PDFはこちら
から
2011.6.17

『ひつじ意味論講座 第5巻』を刊行しました! 第5巻は、昨年末に刊行した第1巻に続くシリーズの2冊目となります。本シリーズは、ひつじ書房創立20周年を記念した企画のひとつです。今週末に開催される日本言語学会でも販売いたしますので、お越しの際はぜひご覧ください。
澤田治美 編『ひつじ意味論講座 第5巻 主観性と主体性』詳細
シリーズの詳細はこちら
2011.6.16
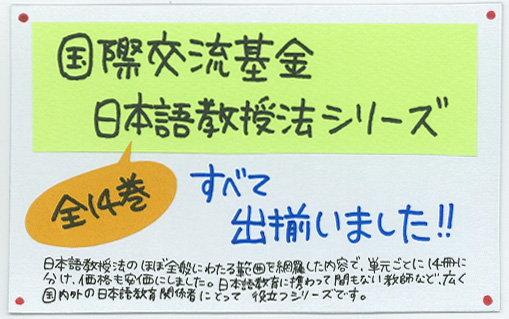
作りました。ご希望の書店様にはお送りいたしますので、ぜひご連絡ください。ひつじ書房営業部三井まで。
2011.6.6
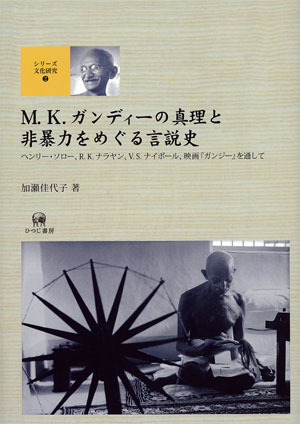
『M. K. ガンディーの真理と非暴力をめぐる言説史』(加瀬佳代子著)が、日本比較文学会第16回学会賞を受賞しました。非暴力ということには支配的な側面があったとことなどを説いた、ガンディーの非暴力を捉え直す研究書です。日本学術振興会研究成果公開促進費をいただいての刊行でした。学振にも多謝。
加瀬佳代子著『M. K. ガンディーの真理と非暴力をめぐる言説史』詳細
2011.6.2
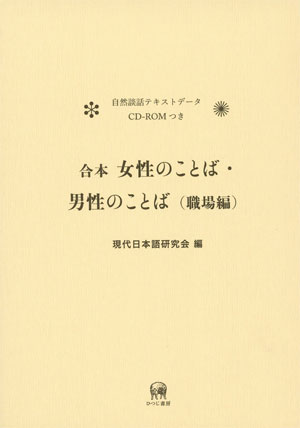
お待たせしました。長らく品切が続いており、お問い合わせの多かった『女性のことば・職場編』『男性のことば・職場編』を合本版として復刊しました。
付属CD-ROMに生の談話テキストデータを収録しています。実際の話し言葉に近いコーパスとして談話研究に必須の1冊です。
現代日本語研究会編『合本 女性のことば・男性のことば(職場編)』詳細
2011.6.1
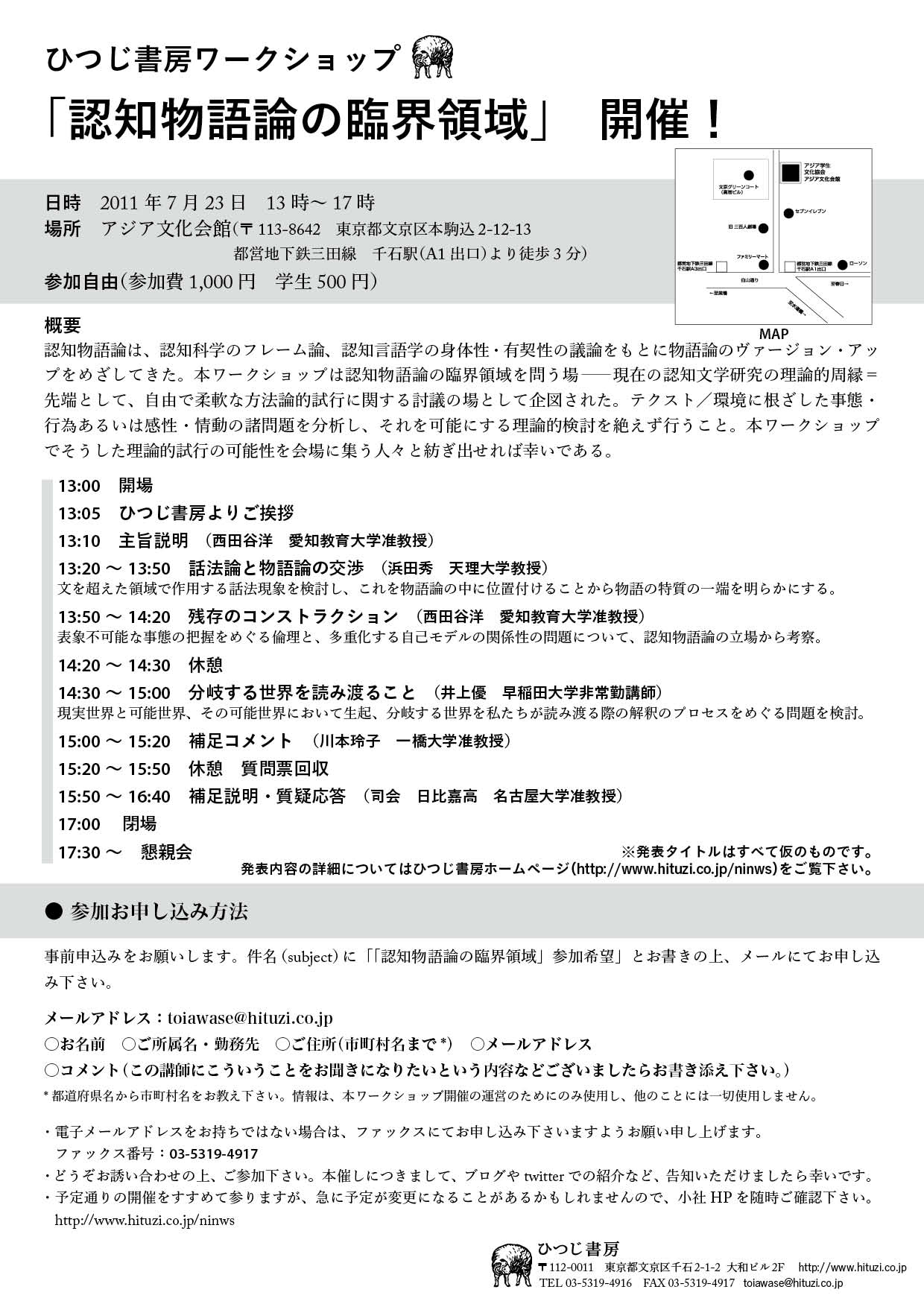
2011年7月23日(土)13時〜17時 アジア文化会館(都営地下鉄三田線 千石駅より徒歩3分)にて、認知物語論ワークショップを開催いたします。
登壇者は、西田谷洋(愛知教育大学准教授)、浜田秀(天理大学教授)、井上優(早稲田大学非常勤講師)、川本玲子(一橋大学准教授)、日比嘉高(名古屋大学准教授)の各氏です。
どなたでもご参加いただけますが、以下の詳細ページから事前申込みをお願いいたします。認知の観点から多角的に小説を読むことについて迫る本ワークショップ、ぜひお誘い合わせの上ご参加下さい! お申し込みをお待ちしております。
詳細はこちらから
ひつじ書房ワークショップ「認知物語論の臨界領域」
2011.5.26
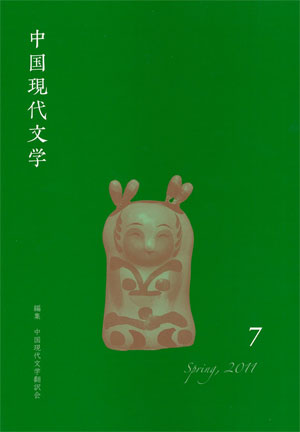
『中国現代文学 7』刊行しました。
『中国現代文学』は2008年4月創刊、年2回発行です。
現代中国の文学作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第7号。掲載作品:劉慶邦「月は遥かに」(中秋節に出稼ぎ先から村に帰ってきた夫は…)、残雪「埋葬」(男は慣れ親しんだものを次々に埋めていき…)、畢飛宇「虹」(高層マンションに暮らす老夫婦は不思議な少年に出会い…)、蘇童「キンモクセイ連鎖集団(チェーングループ)」(嘘つきリウは都会でキンモクセイを売り始めたが…)、史鉄生「Mの物語」「B先生」(“反動”と呼ばれて孤立した少女は…/少年にとって理想だった先生…)。このほか、昨年2010年末に急逝した史鉄生に関する解説・資料などを掲載する。
中国現代文学翻訳会編『中国現代文学 7』詳細
2011.5.23


国際交流基金日本語教授法シリーズ第3巻『文字・語彙を教える』、同じく第12巻『学習を評価する』の2冊を刊行しました。シリーズ完結です。
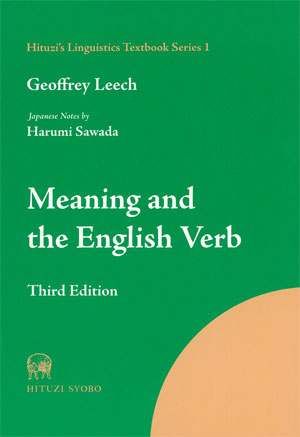
Geoffrey Leech著、澤田治美注釈『『Meaning and the English Verb [Third edition]』を刊行しました。前作の第2版(1994年にリプリント版を刊行)に続き、澤田治美教授の日本語注釈付き。注釈にも改訂を加えました。
英語の動詞や助動詞の微妙な意味の違いを教えてくれる意味論の名著のテキスト版です。英語の真髄を学ぶのに最適。注釈は研究課題を含んでおり、レポートのテーマを見つけるのにも便利な1冊です。
Geoffrey Leech著 澤田治美注釈『Meaning and the English Verb [3rd edition]』詳細
2011.5.18

今週より書籍目録『未発』24号を発送しております。
『未発』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いします。

浜口稔著『言語機械の普遍幻想—西洋言語思想史における「言葉と事物」問題をめぐって』を刊行しました。
言葉と事物の対応は、西洋人にとって宿年の難題であり続けてきました。かつて言葉の理論とは即事物の理論(自然学・博物学)でしたが、近現代の言語学は事物世界から離反した自律的立場を志向し、その難題を回避しました。言葉の理論は一方で事物を制御する言語機械として展開し、近現代の言語学も機械論的な特徴を尖鋭化させてきました。この経緯は言語研究の学としての成立にも触れてくることです。本書は、こうした言葉と事物の相関を、西洋言語思想史に底流する観念の歴史として浮き彫りにします。
浜口稔著『言語機械の普遍幻想』詳細

札野寛子著『日本語教育のためのプログラム評価』を刊行しました。シリーズ言語学と言語教育の第24巻です。
社会的使命を担う日本語教育活動では、プログラム評価はその責任の一端であるとの思いで取り組んだ実践的な研究。プログラム評価の歴史的発展経緯や理論的な背景、過去の外国語教育での評価事例を踏まえ、日本語教育プログラムを想定した評価像を描き出します。また、評価を専門としない者でも実践できる「12ステップ」など具体的な方策を紹介。このステップに則って行なった日本語教育プログラムの評価事例を検証し、今後の評価の在り方を論ずる1冊です。
札野寛子著『日本語教育のためのプログラム評価』詳細
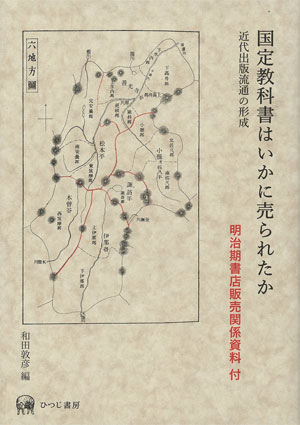
和田敦彦編『国定教科書はいかに売られたか—近代出版流通の形成』(明治期書店販売関係資料付)を刊行しました。
日本の近代において、教科書というメディアが果たした役割は大きいものです。特に国定教科書は、全国に及ぶ販売、流通網を形成し、近代の出版、教育、文化と、多方面に幅広い影響を与えていきました。本書は、明治期に整備されていくこの国定教科書の販売、流通の実態を、当時の書店の取引や契約の豊富な一次資料をはじめて利用することで、詳細にあとづけていきます。あわせて、多くのこれら一次資料を翻刻し、収録しており、今後の教育史やメディア史、あるいは文化史を研究するうえでの貴重な基礎資料ともなります。
和田敦彦編『国定教科書はいかに売られたか—近代出版流通の形成』詳細

今年もオープン・オフィス「研究書出版」のための相談会、を開催します。これまでのやり方を少しかえています。詳細は追って、お知らせします。次のページをご覧下さい。
オープン・オフィス「研究書出版」のための相談会のページ
2011.5.6

国際交流基金日本語教授法シリーズ第10巻『中・上級を教える』を刊行しました。
中級レベル、上級レベルとはどのようなレベルなのか。この教材では、多様化する学習者のニーズを考慮して中級・上級レベルではどのような能力を育成すれば良いのかを考える。その上で、複数の技能を組み合わせて現実的な運用に結びつける方法を検討する。さらに国内外のさまざまな教授環境のもとで、どのようなリソース(人・もの・場所)が実際に活用できるのかという点を重視し、具体的な教室活動の作り方や授業全体の流れを実際例とともに考える。
国際交流基金著『中・上級を教える』詳細

浜口稔著『言語機械の普遍幻想—西洋言語思想史における「言葉と事物」問題をめぐって』をもうすぐ刊行します。
即事物の理論(自然学・博物学)だった言葉の理論が、近現代に機械論的な特徴を尖鋭化させるまで。西洋人にとって宿年の難題であり続けた「言葉と事物」対応の歴史をたどります。
浜口稔著『言語機械の普遍幻想』詳細
2011.4.27
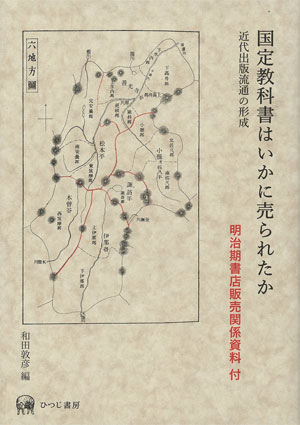
和田敦彦編『国定教科書はいかに売られたか—近代出版流通の形成』をもうすぐ刊行します。
明治期の書店の契約書や資料を翻刻、分析し、当時の出版流通の実態にせまります。
和田敦彦編『国定教科書はいかに売られたか』詳細
2011.4.25

国際交流基金 日本語教授法シリーズ 第10巻『中・上級を教える』もうすぐ刊行します。
本巻が出ると、本シリーズはいよいよ残り2冊、5月に完結予定です。
『中・上級を教える』詳細

『「大学生」になるための日本語』イベント第2弾を先週土曜日の大阪にて開催、盛況のうちに終了しました。ご参加いただいた皆さま、凡人社大阪営業所の皆さま、ありがとうございました。
『「大学生」になるための日本語1』
2011.4.4

エレン・ウィナー著 津田塾大学言語文化研究所読解研究グループ訳『ことばの裏に隠れているもの—子どもがメタファー・アイロニーに目覚めるとき』を刊行しました。言語学翻訳叢書12巻です。
本書は、アメリカの心理学者でボストンカレッジ教授、Ellen WinnerによるThe Point of Words: Children’s Understanding of Metaphor and Irony(1988)の全訳。子どものメタファー・アイロニーの習得過程、それらの習得がなぜ遅いかの解明への試みです。認知言語学などのメタファー研究、発達心理学の「心の理論」、語用論などのメタファー、アイロニー研究をユニークな視点で結びつけており、初等教育における日本語・英語の指導、障害児の文字通りでない言語理解が注目される今こそ、研究者、学生、自閉症・アスペルガー症候群の子どもの教育者、子を持つ親に読んでほしい一冊です。
エレン・ウィナー著 津田塾大学言語文化研究所読解研究グループ訳『ことばの裏に隠れているもの』詳細。
先日の凡人社麹町店での店頭イベントに続く『「大学生」になるための日本語』イベント第2弾を開催します。
* * *
一昨年10月にひつじ書房で初めての、日本の大学への進学を希望する日本語学習者向けテキスト『「大学生」になるための日本語1』を刊行しました。そして、昨年11月にそのかたわれの『「大学生」になるための日本語2』を刊行しました。「文法とタスクの融合」を目指しているところを始めとして、読解・聴解のひとつひとつにおいて、大変画期的なテキストです。
完結して5ヶ月が経とうとしていますが、みなさまにもっと『「大学生」になるための日本語』というテキストのことを知っていただくため、好評だった東京での開催に引き続き、大阪でもイベントを開催いたします。
* * *
今回も著者の堤先生と長谷川先生におこしいただき、「大学生」になるということ、またそのための日本語とは?ということから、本テキストのこだわり、「教える先生方に工夫していただいてこそ」の本テキストの教え方のヒントを伝授します。
お手にとってくださった方も、そうでない方も、本テキストをくわしく知ることのできる絶好の機会ですので、ぜひおこしください!
★イベント名
「留学生の日本語力を高めるために 『「大学生」になるための日本語』を使用して」
大学進学希望の学習者を対象にした『「大学生」になるための日本語』1・2巻は、茂木健一郎や福岡伸一を始めとした豪華な生教材によって各学問分野にふれながら、N2程度の文法が学べる総合テキストです。また、文型練習の例文には「場面(タスク)」がつき、文法とタスクの融合も目指しています。当日は、自然な会話を収録したCD等、様々な工夫のつまった本書の概要、授業展開ポイントを具体例とともにお話しします。
〈講師〉
堤良一(つつみ りょういち) 岡山大学准教授
長谷川哲子(はせがわ のりこ) 関西学院大学准教授
〈日時・場所〉
2011年4月9日(土) 14時半〜16時(受付開始14時)
於 愛日会館
定員:60名
参加費:1000円(当日会場でお支払いください)
★お申し込み・詳細についてのお問い合わせは凡人社大阪営業所まで
http://www.bonjinsha.com/event/
詳しくは板東のスタッフ日誌をご覧ください。

辻幸夫 監修 中本敬子・李在鎬 編『認知言語学研究の方法—内省・コーパス・実験』を刊行しました。
認知言語学の代表的研究法として、作例と内省による研究、コーパス研究、心理実験・調査を紹介した入門書。各研究方法の特色や、実際の研究の進め方を具体的に解説している。また,最先端の研究を例に、実際の研究がどのように行われたかを紹介している。卒論、修論で初めて認知言語学研究を行う学生の他、研究法の幅を広げたいと考える研究者のニーズにも応える内容である。執筆者:黒田航、松本曜、加藤鉱三、玉岡賀津雄、大谷直輝、楠見孝
辻幸夫 監修 中本敬子・李在鎬 編『認知言語学研究の方法—内省・コーパス・実験』詳細。

青木直子・中田賀之 編『『学習者オートノミー—日本語教育と外国語教育の未来のために』』を刊行しました。
時代の変化に対応した新しい形の言語学習を可能にするものとして、外国語教育や日本語教育の関係者の間で、学習者オートノミーへの関心が高まっている。本書は、学習者オートノミーの研究と実践のエッセンスを紹介することを目的として編まれた論文集で、アンリ・オレック、デビッド・リトル、フィル・ベンソンら学習者オートノミー研究の第一人者が執筆者に名を連ねている。学習者オートノミーに関して日本語で読める初めての本格的な書。
青木直子・中田賀之 編『学習者オートノミー—日本語教育と外国語教育の未来のために』詳細。

武内道子・佐藤裕美編『発話と文のモダリティ 対照研究の視点から』(神奈川大学言語学研究叢書 1)を刊行しました。
本書は、12名の著者によるそれぞれ研究対象とする言語(日本語、英語、ロシア語、韓国語、スペイン語)におけるモダリティ、モーダルについての認知語用論、統語論、意味論の視点からの論考を収録しています。神奈川大学共同研究奨励助成プロジェクト「モダリティ・プロジェクト」による論集です。
主観性シンポジウム 2011/3/26〜3/27開催予定( 於 関西大学)であった「主観性シンポジウム」は、中止とのこと。ことば工学研究会は開催します、のでご注意下さい。

『日本語の対人関係把握と配慮言語行動』の著者、三宅和子先生と刊行のお祝いをしました。
2011.3.14
3月18日に開催予定の第32回研究会は、東日本大震災とそれに伴う諸事情(被災状況、今後の交通事情、計画停電、余震の可能性)などを考慮し、運営委員で検討した結果、中止を決定しました。
なお、今後の開催予定や方法などについては、後日、あらためてメディアとことば研究会ホームページで発表します。
メディアとことば研究会ホームページ
先日の麹町店イベントの録画映像をYouTubeにアップいたしました。 容量の関係から6分割しています。 当日のパワーポイントはこちら
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
What's new
2011.3.12
ひつじ書房は無事です。12日朝、社員全員無事に帰宅したことを確認しました。震源地に近い東北地域のみな様の安全をお祈りします。
状況に注意を払いつつ、できるだけ、冷静に平常心で仕事をしていきたいと考えています。


ひつじ研究叢書(言語編)第87巻『中古語過去・完了表現の研究』、同じく第91巻『コーパス分析に基づく認知言語学的構文研究』の2冊を刊行しました。
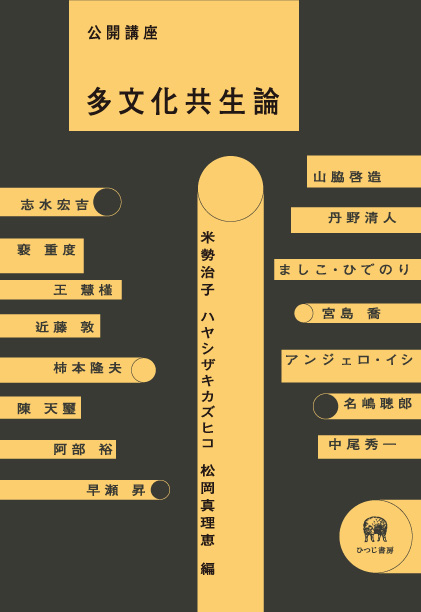
米勢治子・ハヤシザキカズヒコ・松岡真理恵編『公開講座 多文化共生論』を刊行しました。
外国人集住地の静岡県浜松市にある、浜松学院大学で開催された公開講演会の記録に基づく書。現代社会の新たなテーマ「多文化共生」について、日本語教育・法律・社会学・言語学・心理学など多様な分野の第一線で活躍する講師たちの研究や実践を収録。多様な側面を持つ多文化共生の基礎を外観できる1冊です。
米勢治子・ハヤシザキカズヒコ・松岡真理恵編『公開講座 多文化共生論』詳細。

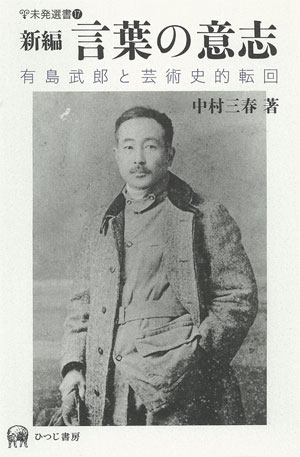
中島平三著『ファンダメンタル英語学演習』、中村三春著『新編 言葉の意志ー有島武郎と芸術史的転回』の2冊を刊行しました。
『ファンダメンタル英語学演習』はおもに英語の構文交替と動詞の意味の関係を題材にして、英語やことばを研究する際の問題発見とその解決の方法を学ぶ、英語学のテキストです。採用見本も受け付けております。
『新編 言葉の意志』は有島武郎の代表作を網羅してその文学と思想の軌跡を辿ります。未発選書の第17巻です。
中村三春著『新編 言葉の意志ー有島武郎と芸術史的転回』詳細。
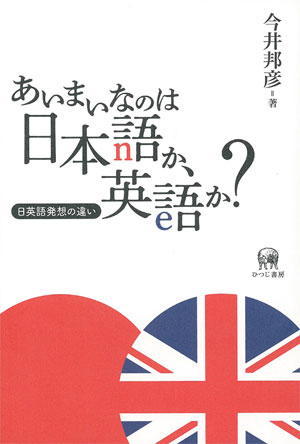

『あいまいなのは日本語か、英語か? 日英語発想の違い』、『認知言語学論考No.9』の2冊を刊行しました。
『あいまいなのは日本語か、英語か?』は、「英語圏の人の言うことは論理的で明白だが、日本人の発話は曖昧で不明瞭なことが多い」という迷信に反論します。著者の経験談も豊富な1冊です。
『認知言語学論考』は認知言語学の最先端の論文を継続的に掲載するシリーズです。刊行が少し遅れましたが、今回が第9巻になります。
今井邦彦著『あいまいなのは日本語か、英語か? 日英語発想の違い』詳細。
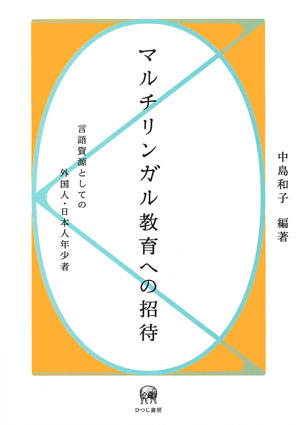

新刊の刊行が続いています。『マルチリンガル教育への招待 言語資源としての外国人・日本人年少者』、シリーズ言語学と言語教育22『児童の英語音声知覚メカニズム L2学習過程において』の2冊を刊行しました。
中島和子編著『マルチリンガル教育への招待 言語資源としての外国人・日本人年少者』詳細。
西尾由里著『児童の英語音声知覚メカニズム L2学習過程において』詳細。
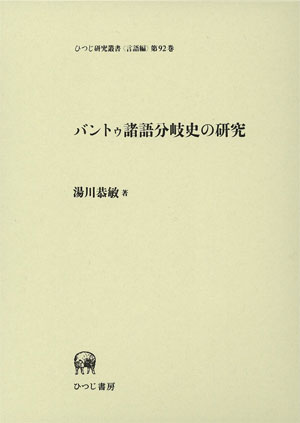
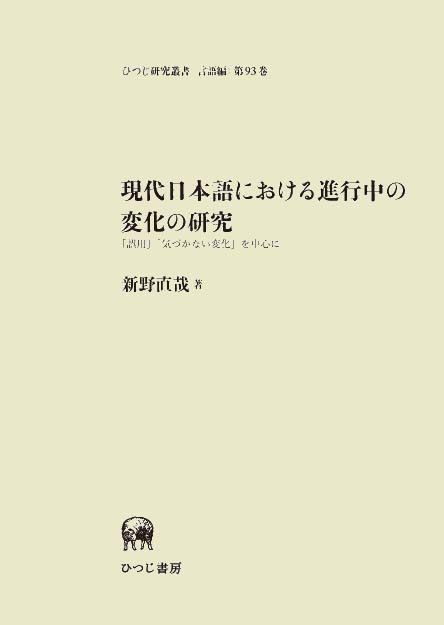
ひつじ研究叢書(言語編)第92巻『バントゥ諸語分岐史の研究』、同じく第93巻『現代日本語における進行中の変化の研究 「誤用」「気づかない変化」を中心に』の2冊を刊行しました。
新野直哉著『現代日本語における進行中の変化の研究 「誤用」「気づかない変化」を中心に』詳細。
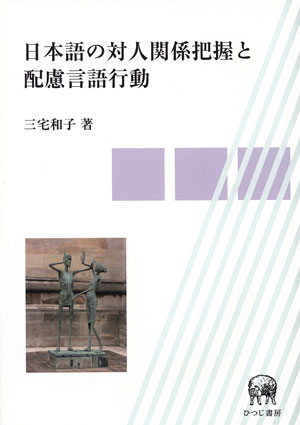
三宅和子先生の『日本語の対人関係把握と配慮言語行動』を、いよいよ刊行いたしました。談話、ケータイメールの分析を通して、日本語の対人関係把握の仕方とその背景にある価値観、特に日本人の「配慮」意識との関連を考察します。
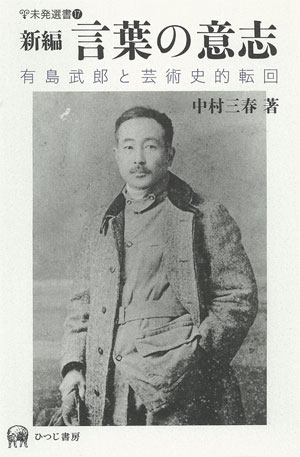
中村三春先生の『新編 言葉の意志 有島武郎と芸術史的転回』を、もうすぐ刊行いたします。未発選書17巻です。1994年に有精堂から出版された書籍に大幅な加筆を加えた「新編」です。
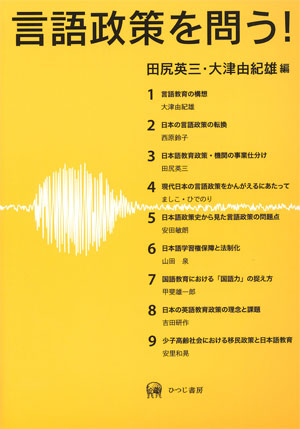
『言語政策を問う!』(田尻英三・大津由紀雄編)の書評が、本日発売の『週刊朝日』(2/18号)に掲載されました。書評されたのは、杉山春さんというフリーライターの方です(著書『移民環流?南米から帰ってくる日系人たち?』新潮社 2008ほか)。本書は、日本の将来に関わる重要な言語政策上の問題が噴出している今、各分野のトップクラスの研究者が、研究領域を超えて、日本の進むべき道を熱く提言します。
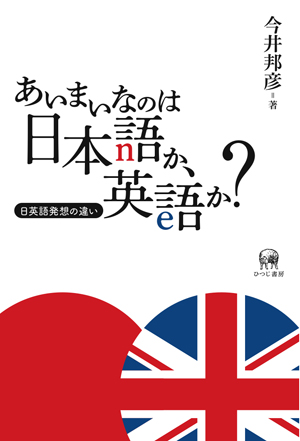
今井邦彦先生の『あいまいなのは日本語か、英語か? 日英語発想の違い』が、もうすぐ刊行いたします。本書では、英語の発話が、日本語の発話にくらべて「あいまいさ」を残す傾向がある、という新説を、今井先生の豊富な実例から説得的に展開します。細間のスタッフ日誌にも詳細を書いていますので、あわせてご覧ください。
http://www.hituzi.co.jp/staff/staff-nisshi.html
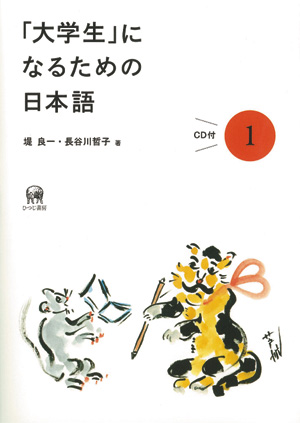
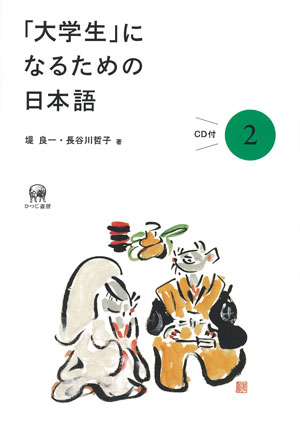
★イベント名
「留学生の日本語力を高めるために 『「大学生」になるための日本語』を使用して」
大学進学希望の学習者を対象にした『「大学生」になるための日本語』1・2巻は、茂木健一郎や福岡伸一を始めとした豪華な生教材によって各学問分野にふれながら、N2程度の文法が学べる総合テキストです。また、文型練習の例文には「場面(タスク)」がつき、文法とタスクの融合も目指しています。当日は、自然な会話を収録したCD等、様々な工夫のつまった本書の概要、授業展開ポイントを具体例とともにお話しします。
〈講師〉
堤良一(つつみ りょういち) 岡山大学准教授
長谷川哲子(はせがわ のりこ) 大阪産業大学准教授
〈日時・場所〉
2011年2月12日(土) 14時〜15時半
凡人社麹町店にて開催・予約不要
http://www.bonjinsha.com/kojimachi/
(「イベント情報」をご覧ください)

『ひつじ意味論講座 第1巻』が、昨年末に刊行しました。本講座は、ひつじ書房創立20周年を記念した企画のひとつです。続刊の刊行に向けて、編者の澤田先生と今年初のミーティングをしました。全7巻完結をめざして、がんばりたいと思います。大型書店など、店頭でもぜひご覧ください。編者の澤田治美先生と。
澤田治美 編『ひつじ意味論講座 第1巻 語・文と文法カテゴリーの意味』詳細。
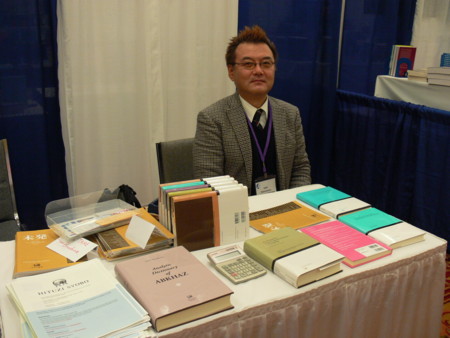
アメリカ言語学会(ピッツバーグ)Linguistic Society of Americaに出展しました。参加しましたことは、間違っていなかったと思います。ひつじ書房は、言語学の研究書を、アメリカでも販売していきたいと思います。日本国内で読まれるに留まらず、世界的に読まれ、言及され、研究を進める研究書を刊行したいと考えています。今後の5年間を海外での流通に、本格的に取り組みたいと考えています。
電子学術出版のセッションがあったりと、なかなか盛りだくさんな学会でした。以下の報告並びにブログでの報告をご覧下さい。
アメリカ言語学会(LSA annual meeting)に参加して


アメリカ言語学会(ピッツバーグ)Linguistic Society of Americaに出展します。アメリカ、ピッツバーグで6日から9日まで開催されます。ひつじ書房は6日から8日まで出店します。以下が、配布するカタログです。どうぞご覧下さい。
LSA_hituzi_catalog

昨年はお世話になりました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
出版というメディアについて、創業以来考えてきました。編集という機能、社会的な機能についてずっと考えてきました。私の現在の結論は、編集という社会的機能とそれを支える社会的な機能である出版というものは、社会的に必要なものである、ということです。しかし、社会的ということは、社会的に認知されなければ、存在できないということでもあります。
存在するべきというだけではだめで、存在させなければなりません。そのためには、出版にかんけいする私たちが、社会的な存在として発信していく必要があります。
動いたり、会ったり、お話を聞いたり、お話しをしたり、発言したり、書いたり、実際に丁寧な仕事をしたり、あたりまえのことをキチンとしていくということ、これまでよりいっそう丁寧にやっていくということです。新しい考えに出会い、話しをお聞きし、それをさらに世の中に伝えていく、学術書の分野で、発信媒介者であるということは、これからも大事なことです。定説になった考えを広めることについては、得意ではありませんが、新しい考えと出会って、送り出していくことにドキドキしています。
存在するべきというだけではだめで、存在させなければなりません。そのためには、出版に携わる私たちが、社会的な存在として発信していく必要もあります。
言語学の学術成果を世に送り出すために、本年もつとめて参ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
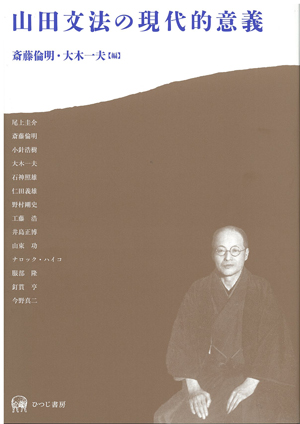
今年最後にできた本です。
本書は、2008年11月に、山田孝雄没後50周年・『日本文法論』刊行100周年を記念して東北大学で開催されたシンポジウム「山田文法の現代的意義」を基にした論文集である。当日のパネリスト4名(仁田義雄・斎藤倫明・山東功・尾上圭介)の他に、山田文法を含む近代文法学に造詣の深い10名の研究者に新たに声を掛け、あらためて山田文法の有する現代的意義について様々な観点から究明した。

シンポジウム「連用・連体を考える」無事終了しました。
12月19日(日)に、ひつじ書房の20周年記念シンポジウム「連用・連体を考える」を学習院大学にて催行いたしました。100名以上の方にご参加いただき、活発な議論が行われました。盛況のうちに終了することができましたのも、皆さまのおかげです。大変ありがとうございました。写真は、パネルディスカッションの様子です。
2010.11.17

『ひつじ意味論講座第1巻 語・文と文法カテゴリーの意味』刊行しました。
ひつじ書房の20周年記念企画『ひつじ意味論講座』の第1巻が、いよいよ刊行いたします。本講座は、言語学を中心としつつも、それに限定することなく、様々な分野で活躍している第一線の研究者の論考を7巻に編集することによって、幅広い観点から意味の問題にアプローチし、これまでの意味研究を振り返るとともに、これからの意味研究のあり方を模索するものです。
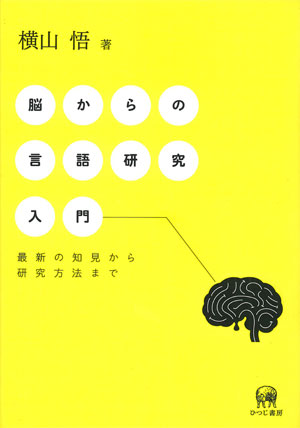
『脳からの言語研究入門 最新の知見から研究方法まで』刊行しました。
近年、脳機能計測技術の発達により、人間の言葉・言語を使っているときの脳活動を画像化しようという研究が増えてきています。本書は、脳からの言語研究に興味を持つ学生及び研究者を対象に、脳機能計測を用いた言語研究の最新の知見概説と、実際に人文系の学生・研究者が脳からの言語研究を行う際に、具体的に何から始めればいいのか、何を準備してどうすればデータ解析結果が得られるのか、の説明までを網羅した入門書です。
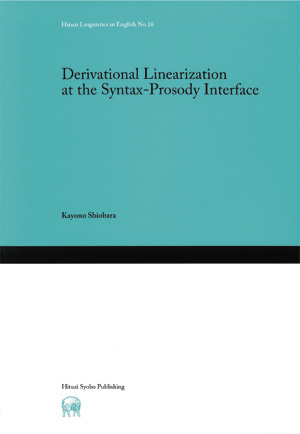
塩原佳世乃先生が、ご著書『Derivational Linearization at the Syntax-Prosody Interface』(2010年3月 ひつじ書房)で、財団法人語学教育研究所より市河三喜賞を受賞されました。市河三喜賞は、英語学研究の優れた論文を公刊した若手研究者に対して贈られるものです。
『Derivational Linearization at the Syntax-Prosody Interface』詳細。
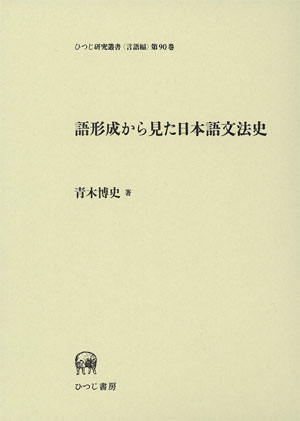
『語形成から見た日本語文法史』刊行します。
ひつじ研究叢書(言語編)第90巻です。
本書は、日本語における派生・複合などの語形成に関する諸現象について、歴史的観点から分析を行ったものである。主として中世室町期に考察の基盤を置き、文法変化をダイナミックに捉えることを目的としている。文献資料の精査によって得られた用例に基づいた実証的な記述に、語彙論から統語論・構文論へと拡がる形で理論的観点から説明を加えている。方言事象も視野に収めた、日本語文法史研究の新しい試みである。
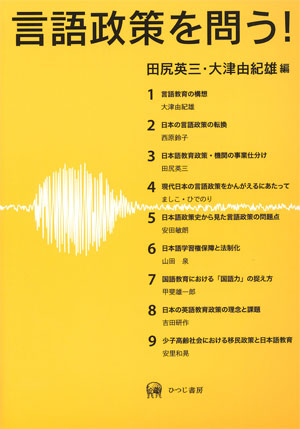
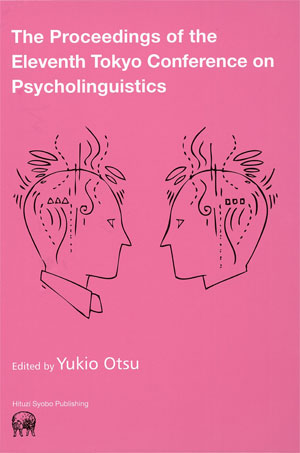
『言語政策を問う!』『The Proceedings of the Eleventh Tokyo Conference on Psycholinguistics (TCP2010)』の2冊を刊行しました。

『養蚕語彙の文化言語学的研究』刊行しました。
ひつじ研究叢書(言語編)第75巻です。
日本語方言における養蚕語彙の記述的研究。養蚕語彙を、具体的な養蚕の生活や文化との関係に注目して論じている。消滅へと向かっている養蚕語彙の現状をふまえ、危機言語の記録・保存の性格をももつ。第1部目的と方法・第2部養蚕語彙の概観・第3部養蚕語彙の造語法と語彙体系・第4部養蚕語彙の比喩表現の四部構成。養蚕語彙にたちあらわれた人びとの認識のありようと、専門的な生業世界の方言形成への関与にせまる。
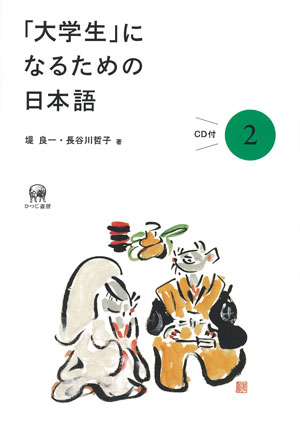
『「大学生」になるための日本語2』刊行しました。
2巻で完結になります。
1に続くこの巻では、統計学、数学、文学、心理学、倫理学、医学等に関連する文章を教材として扱っている。1より少し高度な内容に触れることにより、より高い文法能力やタスク遂行能力を養えるようになっている。日本語能力試験N2程度の文法で、しかも非常に抽象的な話題を扱うことによって、1巻と同様に、学習者の人間的成長を促すような教材である。なお、1巻2巻とも、日本留学試験(作文)や、大学の入試問題に出題されるような問題も掲載してあり、これらの試験対策にもなっている。
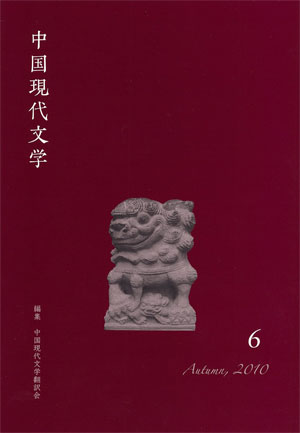
『中国現代文学 6』刊行しました。
『中国現代文学』は2008年4月創刊、年2回発行です。
現代中国の実力派作家の作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第6号。
張小波「検察大官」(監獄を舞台とした寓意に満ちた物語)、徐則臣「アヒルが空を飛ぶなんて」(アヒルを追って暮らす少年少女に突然訪れた試練)、鮑十「子洲の物語」(「初恋の来た道」の原作者が描く少年と祖父の心暖まる交流)、全勇先「昭和十八年」(そのとき満州の一角で起こったある事件)、史鉄生「海棠の老木」「孫姨(スンイー)と梅娘(メイニャン)」(記憶の中の祖母/幻の作家・梅娘との奇しき出会い)、などを掲載する。
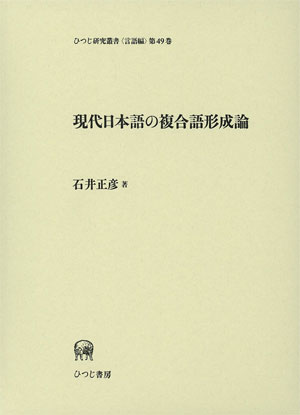
ひつじ研究叢書(言語編)第49巻『現代日本語の複合語形成論』重版が出来ました。
お問い合わせいただいておりましたみなさま、お待たせいたしました。
石井正彦著『現代日本語の複合語形成論』詳細。
2010.10.25
ひつじ書房では、編集・本作り・本の販売・マーケティングのスタッフとなるべきスタッフ(社員)を募集しています。理系文系学部は問いません。既卒、2011年大学院卒でもかまいません。ことばと学術の世界に興味がある方で、やる気があって、コミュニケーション力(人の気持ちが分かること)がある方を募集しています。
応募は12月15日までとしています。卒業論文などたいへんな時期と思いますが、ご応募下さいましたら、幸いです。採用試験の日時については、卒論の提出日とのかねあいでご相談に応じます。
詳細は以下をご覧下さい。
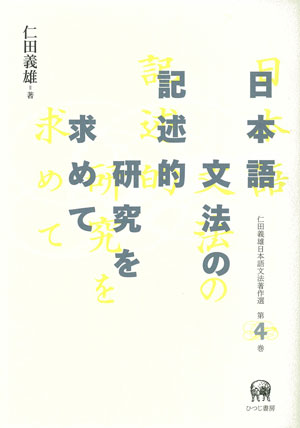
『日本語文法の記述的研究を求めて』刊行しました。
仁田義雄日本語文法著作選の第4巻です。この度の刊行で、本シリーズが完結しました。
1980年代から日本語文法研究をリードして来られた仁田義雄先生の、文法研究を集めた軌跡ともいえるシリーズ。第4巻は文構造と構成要素の分類について。

『学びのための英語指導理論 4技能の指導方法とカリキュラム設計の提案』刊行しました。
表紙のかえるが目印です。
本書ではこれまで理論的に組み立てられてこなかった英語の「指導法」を詳述する。効果的な授業を展開するためには本質的にカリキュラム設計とシラバス・デザインの指針が必要である。 初級・中級・上級段階での4技能の指導方法を系統立てて説明しつつ、小・中・高・ 大学までの一貫した教育設計の提案を行う。教育現場での実践に役立ち、更には英語教育の政策立案・制度設計のための基礎となる。これから 教壇に立つ人をはじめ、英語教育関係者必携の書。

今週より書籍目録『未発』23号を発送しております。
『未発』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いします。
期限を決めた方がよいとのことですので、期限を決めます。8月1日から募集しておりました2011年3月新卒の社員募集のための書類提出の期限は、10月15日(必着)とします。ご応募されます方は、期限内に届きますように応募されますようお願いします。
求人・採用について
2010.10.8
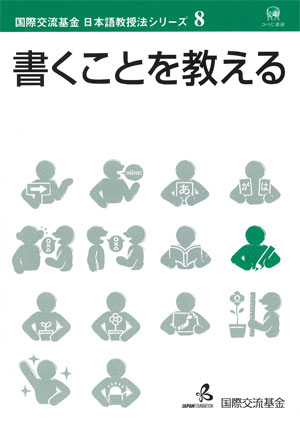
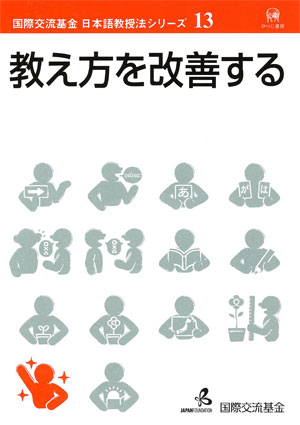
国際交流基金日本語教授法シリーズ第8巻『書くことを教える』、同じく第13巻『教え方を改善する』を刊行しました。
国際交流基金日本語教授法シリーズは全14巻です。今回刊行いたしました2冊を含め、11冊が既に刊行されています。
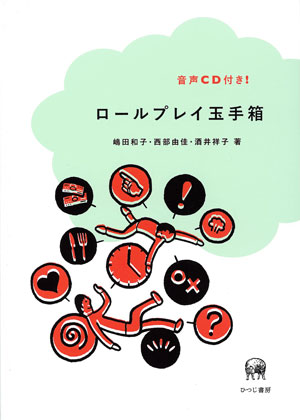
『ロールプレイ玉手箱』刊行しました。
今週末の学会でお披露目になります。
学習者はどんな場面で、どんな状況で日本語を使ってコミュニケーションをしているのだろう?本書は「接触場面を学習者とともに洗い出し、ロールプレイを作ること」から始まりました。タスクを★の数でレベル別に分け、スパイラルにあげていくコツを提示。授業展開例や実践した現場教師の声も豊富に取り入れています。『目指せ、日本語教師力アップ!?OPIでいきいき授業』(ひつじ書房)を実践するための必読書。
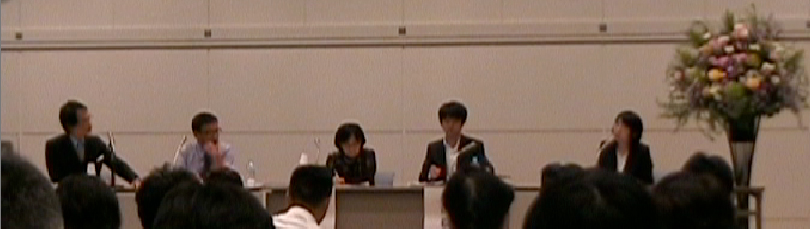
昨日23日に行いました「可能性としての文学教育」盛況の内に幕を閉じました。会場にお越しくださいました皆様、まことにありがとうございました。議論は盛り上がり、もう一日あった方がよいのではないかというほどでした。次回は26日(日)の「書くことの倫理」です。教育から実際に書く方へとテーマは緩やかに続いています。皆様のご来場、お待ちしております!
いよいよ、明日よりひつじ書房創立20周年記念シンポジウム開催です。
明日の23日は「可能性としての文学教育」、26日は「書くことの倫理」です。
席数はまだ余裕がございますので、事前にご予約されていない方でもどうぞご遠慮なく当日直接会場の日仏会館までお越しください。
お待ちしています!

『文化と会話スタイル 多文化社会・オーストラリアに見る異文化間コミュニケーション』刊行しました。
言語学翻訳叢書11巻です。
オーストラリアは多文化主義を政策として採用しながらも英語を国の土台ととらえ、移民の英語教育を保証している。本書は移民たちが英語母語話者を交えて問題解決をはかるとき、母語の文化的価値観や談話構造、ターン・ティキング、主張の仕方といった会話のスタイルがどのように英語母語話者や他の文化出身者との意思疎通を阻んだり、誤解を与えたのかを実際の会話データから分析した。英語教育、日本語教育、多文化教育でのコミュニケ—ションの在り方を考えるための必読書。訳書原題『How Different Are We? Spoken Discourse in Intercultural Communication』
「東京新聞」9月11日夕刊の文化面「土曜訪問」で、『私学的、あまりに私学的な』の内容についてのインタビューが掲載されました。
こちらから
見出しは「批評の場 再構築へ」、「揺らぐ時代に“不良”指南」。ぜひご覧下さい。
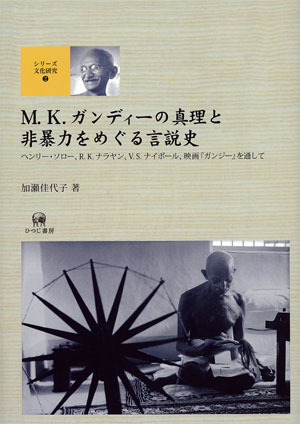
『M. K. ガンディーの真理と非暴力をめぐる言説史 ヘンリー・ソロー、R. K. ナラヤン、V. S. ナイポール、映画『ガンジー』を通して』刊行しました。
シリーズ文化研究第2巻になります。
本書は「M. K. ガンディーの非暴力」から「現代の非暴力」に至るまでの変化の過程を追跡し、非暴力をめぐる言説分析を通して、非暴力という思想について批判的に考察したものである。ガンディーの非暴力には支配的側面があったこと、非暴力は社会に広がるにつれて形を変えたが、その支配性の影響は現代に及んでいることを明らかにしている。
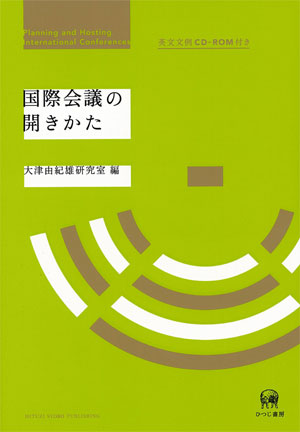
『国際会議の開きかた』刊行しました。
ピスタチオ色の表紙が目印です。英語文書の作成に便利な文例見本CD-ROM付きです。
国際会議を開く機会が増えました。国内会議とそう変わるわけではないからと高をくくっていると、とんでもない目にあいます。この本は国際会議を10年間にわたって主催してきた大津由紀雄研究室が蓄積したノウハウを一挙公開するものです。国際会議開催の段取りから、開催に必要なさまざまな英語文書の例まで、有益な情報が満載です。これから国際会議を開こうとしている学会などの組織、国際会議開催に興味のある方々のお役に立つ本です。
期限を決めた方がよいとのことですので、期限を決めます。8月1日から募集しておりました2011年3月新卒の社員募集のための書類提出の期限は、9月15日(必着)とします。ご応募されます方は、期限内に届きますように応募されますようお願いします。
求人・採用について 2010.8.30

ひつじ書房創立20周年記念の新しいロゴの「表札」を三美印刷さんが作って下さいました。プレゼントです。表札と言っていますが、入り口ではなくて窓に貼っているものです。茗荷谷からひつじの事務所に来られる時に、ビルの2階の窓に掲げてありますので、どうぞご覧下さい。

なお、お気付きでしょうか。これに合わせて、HPトップのロゴとマークもあたらしいものにしました。9月から新しいロゴでのサイトとなります。2日、早いですが。
以前のロゴ★。
「ひつじ書房創立20周年記念シンポジウムのご紹介」のリンクから詳細をご覧下さい。
房主松本功からの言語研究者への9月に行う文学系のシンポジウムへの参加の呼びかけ。「ひつじ書房の20周年を記念したシンポジウムの説明」(茗荷バレーで働く編集長兼社長からの手紙—ルネッサンス・パブリッシャー宣言、再び)のリンクから詳細をご覧下さい。
バナーを作りました。ブログでのご紹介などにお使い頂けますとさいわいです。以下のバナーをご自由にお使い下さい。
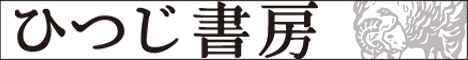

『日本語教育からの音声研究』著者の土岐哲先生に、お越しいただきました。ありがとうございます。青森料理で、刊行お祝いをしました。長年にわたるご研究の集大成といえる一冊です。音声学のみならず、日本語学など広い分野の関係者に、ご一読をおすすめします。

先週発売の「週刊現代」8月14日号「リレー読書日記」にて、斎藤美奈子さんによる書評が掲載されました。本書のスローガン「人生に出る」を受けて、文芸評論は一部文学マニアのための本ではないということが語られています。ぜひ「週刊現代」ご覧下さい。
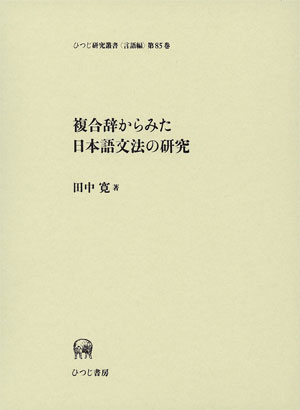
田中寛著『複合辞からみた日本語文法の研究』刊行しました。
ひつじ研究叢書(言語編)第85巻、学会などでも多くお問い合わせいただいていた本です。よろしくお願いします。
日本語の論理的な表現形式としての複合辞は、中上級日本語教育の指導要目としても重要な位置を占める。本書は副詞節を中心とした接続成分と否定表現を軸にした文末成分の意味機能について考察を加えたもので、同時にヴォイス、モダリティ、とりたて助詞といった文法カテゴリーをも内包しながら、日本語文法を複合辞という視点から再構築しようという試みである。類義表現も多く収録し、巻末には詳細な複合辞文献目録を付す。

『日本語教育からの音声研究』刊行しました。
シリーズ言語学と言語教育の第20巻です。
本書は、幾多の日本語学習者との接触により触発され、自発性の高い自然な日本語音声とはどんなものかに焦点を当てることで生まれた研究である。音声教育の史的概観、一般音声学的視点の重要性、縮約現象の諸相、リズムの規則性、アクセントの下げとイントネーションの下げ、海外(南洋群島、台湾)に残存する日本語の音声等の他、現代社会に於ける音声教育観等、音声教育を考える上での主要な項目を内容として展開する。

『私学的、あまりに私学的な—陽気で利発な若者へおくる小説・批評・思想ガイド』刊行しました。
これから文学や思想の勉強をしたいとお考えの方から、大学やカルチャーセンターで教えていらっしゃる方まで、幅広くお楽しみいただけます。
文芸批評家であると同時に教育者でもある著者の、授業の「ネタ」が詰まった一冊です。巻末には国内外の小説、批評ブックリスト付。
市川真人/前田塁氏にコメントをいただいた帯も、思わず手に取りたくなるものです。ぜひ、書店でじっくりご覧ください。早いところでは、今週末から店頭に並びます。
詳細ページから、目次とまえがきをご覧頂けます。
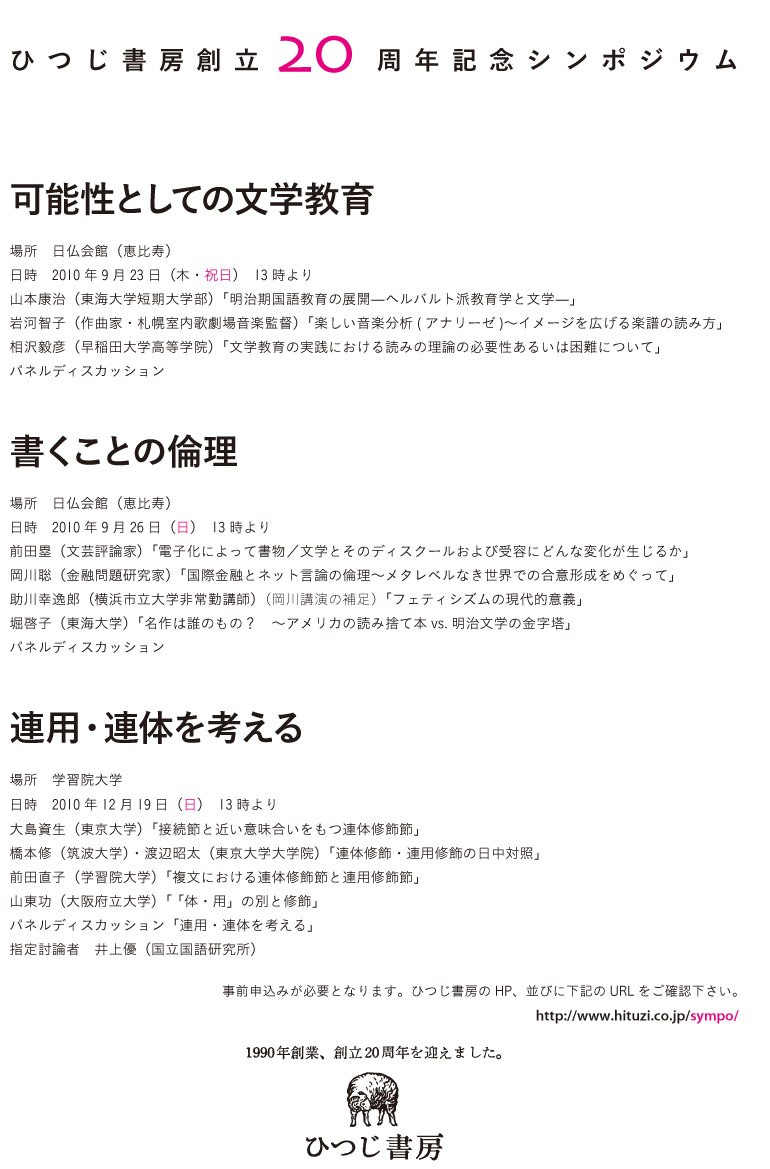
ひつじ書房創立20周年記念シンポジウムの案内ページと申込みページを作りましたので、ご覧下さい。
場所 日仏会館(恵比寿)
日時 2010年9月23日(木・祝日) 開場12時半 開演13時
山本康治(東海大学短期大学部)「明治期国語教育の展開—ヘルバルト派教育学と文学—」
岩河智子(作曲家・札幌室内歌劇場音楽監督)「楽しい音楽分析(アナリーゼ)〜イメージを広げる楽譜の読み方」
助川幸逸郎(横浜市立大学非常勤講師)(岩河講演の補足)
相沢毅彦(早稲田大学高等学院)「文学教育の実践における読みの理論の必要性あるいは困難について」
場所 日仏会館(恵比寿)
日時 2010年9月26日(日) 開場12時半 開演13時
前田塁(文芸評論家)「電子化によって書物/文学とそのディスクールおよび受容にどんな変化が生じるか」
岡川聡(金融問題研究家)「国際金融とネット言論の倫理〜メタレベルなき世界での合意形成をめぐって」
助川幸逸郎(横浜市立大学非常勤講師)(岡川講演の補足)「フェティシズムの現代的意義」
堀啓子(東海大学)「名作は誰のもの? 〜アメリカの読み捨て本vs.明治文学の金字塔」
場所 学習院大学
日時 2010年12月19日(日) 開場12時半 開演13時
大島資生(東京大学)「接続節と近い意味合いをもつ連体修飾節」
橋本修(筑波大学)・渡辺昭太(東京大学大学院)「連体修飾・連用修飾の日中対照」
前田直子(学習院大学)「複文における連体修飾節と連用修飾節」
山東功(大阪府立大学)「 「体・用」の別と修飾」
パネルディスカッション「連用・連体を考える」
指定討論者 井上優(国立国語研究所)
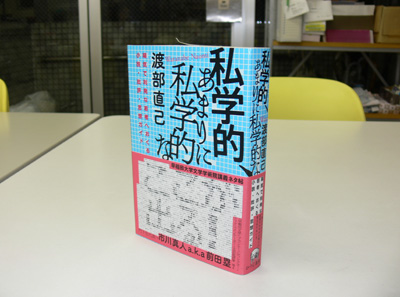
今月の下旬頃から店頭に並び始めます。
ひつじ書房からは珍しい、文芸批評家の著者による著書を刊行します。文芸批評から思想、果てはレポートの書き方まで、著者が大学で教えていることのエッセンスが詰まっており、単なるハウツー本ではなく、読み進めながら総合的に人文的な思考の力を養うことができる本とでも言ったらよいでしょうか。小説や批評の書き方、読み方はもちろん硬派な文学研究にも参考になると共に、スポーツコラムやNHKの「禁語録」などは、読んだ後でガラッとテレビの見方が変わってしまう面白さ。写真からも分かる通りボリューム満点で、内容の詰まったお得な一冊です。
帯は「早稲田文学」のプランナー/ディレクターでもあり文芸批評家でもある市川真人/前田塁氏に素敵な文章を書いて頂きました。文字がこんなに詰まった帯はいまだかつて無いのではないでしょうか。この一見不穏な細かな文字でびっしりと何が書かれているのか、そして浮かび上がった謎のことば、何が出るというのでしょうか……、答えはぜひ完成版の実際の帯をご覧下さい。
装幀や本文の組版も非常に凝っています。中の様子もご覧頂きたいので,
本の紹介ページからサンプルページをご覧頂けるようにしました。以下からぜひページをぱらっとめくってみてください。この素敵なデザインは奥定泰之氏によるものです。

『ガイドブック文章・談話』を刊行しました。
文章・談話について、短時間にその概要を知りたい人から本格的に学びたい人まで、必携のガイドブック。上代から近代までの「文章史・言語生活史」のほか、「比喩」や「接続」などの重要項目を文章・談話の中でとらえるためのヒントを示した。また、さまざまな基礎的な用語を体系的に詳しく説明し、今まできちんととりあげられることが少なかった両分野の研究史については、国内だけでなく海外におけるもっとも新しい研究までを網羅的にとりあげている。さらにコーパス検索など情報処理に関する章も設けてある。
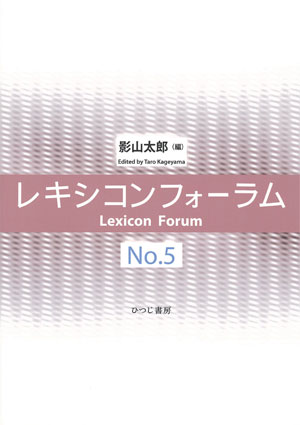


『レキシコンフォーラム No.5』『現代日本語のアスペクト論—形態論的なカテゴリーと構文論的なカテゴリーの理論』『日本語形態の諸問題 鈴木泰教授東京大学退職記念論文集』の3冊を刊行しました。
『現代日本語のアスペクト論—形態論的なカテゴリーと構文論的なカテゴリーの理論』詳細。
『日本語形態の諸問題 鈴木泰教授東京大学退職記念論文集』詳細。
19日は言語学会が筑波大学で開催されましたが、その日、ひつじ書房は創立20周年を迎えました。20年前に有限会社として登記した日です。20年間のご愛顧を感謝申し上げますとともに、今後とも学術書の出版に誠心誠意尽くして参ります。どうぞご支援下さい。

言語学会にて、『可能性としての文化情報リテラシー』の編者の定延先生と担当者海老澤の記念撮影。定延先生、お世話になりました。ありがとうございます。ちなみに、19日、ひつじ書房創立20周年を迎えました。申し上げたいことがたくさんありますが、項を改めまして。


『法コンテキストの言語理論』、『可能性としての文化情報リテラシー』を6月19・20日の日本言語学会に持っていきます。海老澤が初めて担当した本になります。ぜひご覧ください。

『認知と社会の語用論 統合的アプローチを求めて』を刊行しました。
薄緑色の、きれいな表紙です。
本書は、Jef Verschueren1998 Understanding Pragmaticsの全訳。氏はベルギー人、アントワープ大学教授、国際語用論学会事務局長で、ヨーロッパにおける語用論研究の中心人物。従来の語用論入門書とは異なり、本書は「語用論的視点が全ての言語現象(音から会話まで)に必ず関わっているもので、その新しい語用論的視点とはどういうものかを統合的に説明しようとしたもの」である。語用論の教科書としてだけでなく、哲学・心理学など関連領域読者にも役立つものである。
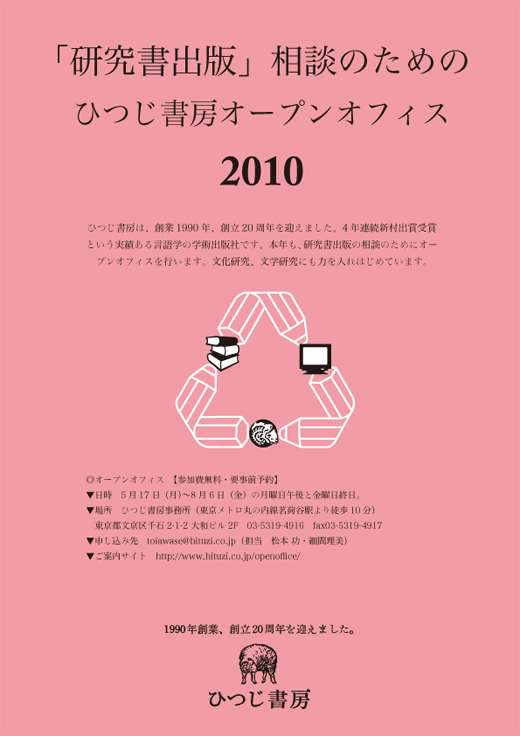
今年も、オープンオフィスをはじめました。研究書の出し方などなどについて、ご相談申し上げます。オープンオフィス、開催中です。
研究書を出版することについてどうぞご遠慮なくご相談下さい。ひつじ書房は、創業以来、学術書の刊行に携わって参りました。出版助成金の申請などについても、長年の蓄積があります。これまでの経験を踏まえまして、ご相談に乗ることができます。ジャンルは、中心は言語学・日本語学に限らず、日本文学などの文学研究、さらには文化研究などのジャンルも受け付けています。

『方言の発見 知られざる地域差を知る』を刊行しました。
日本の方言にはまだまだ知られていない地域差がたくさんある。本書は、方言の地理的変異について、これまで十分取り組まれてこなかった分野を開拓し、方言に関心のある人たち、特に、これから方言研究に取り組もうとする若い人たちを、知られざる日本語方言の世界へと案内し、新たな研究へと誘う。イントネーションや感動詞、オノマトペ、あるいは、言語行動や談話展開などを対象に、今後の方言研究の萌芽となるような発見やアイデアを豊富に盛り込む。

『仁田義雄日本語文法著作選第3巻 語彙論的統語論の観点から』を刊行しました。
1980年代から日本語文法研究をリードしてきた仁田義雄の文法研究を集めた軌跡ともいえる著作選全4巻の第3巻。語彙と文法の関係についてまとめた1冊。
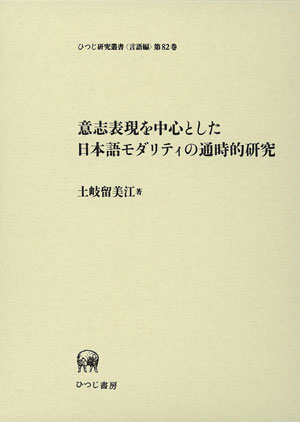
『ひつじ研究叢書(言語編)第82巻 意志表現を中心とした日本語モダリティの通時的研究』を刊行しました。
古代語のモダリティ研究は、いわゆる推量系のモダリティを中心に研究が進められてきた。推量と意志とは多くの推量系のモダリティ形式において表裏の関係にあるにも関わらず、かえってそれ故に、意志系のモダリティに光があてられることはほとんどなかったといえよう。本書は意志系のモダリティ形式について、現代語にいたるまでの通時的な変遷の過程を明らかにすることを中心に、その成立の体系的考察をめざした書である。

20周年のコピー&ロゴ、作りました。
いろいろ迷いもし、悩みもしたのですが、やっと20周年のコピー&ロゴができました。ロゴ部分は澤辺由記子さんに作ってもらい、ひつじのマークにも手を入れてもらいました。この部分は凸版にして、コピーは、オールライト工房に活字で組んでもらって一緒に刷っています。これはその清刷です。
2010.5.20

『国際交流基金 日本語教授法シリーズ 第11巻 日本事情・日本文化を教える』を刊行しました。
日本語教育において、日本事情や日本文化を扱うことは必要だと思っていても、時間がない、機会がない、情報がないという現場も多いだろう。しかし、「何を教えるか」より「どう教えるか」「どう取り上げるか」を大切にすることで、時間や環境が充分整わなくても、日本事情や日本文化を取り上げることはできる。この教材では、そのために、言語と文化を結びつける効果的なリソースを検討し、学習者と共に発見し考えながら、楽しんで教えることができる方法を提案する。
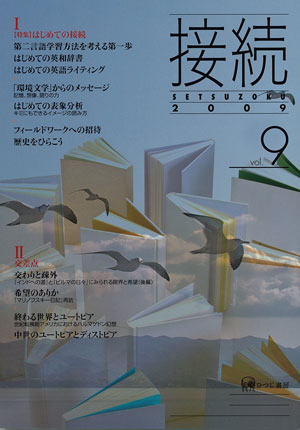
『接続2009 特集:はじめての接続』を刊行しました。
今回の特集は「はじめての接続」。開かれた知の「場」という本シリーズの理念に立ち返り、各執筆者の専門分野の内容を、大学へ入ったばかりの学生にも分かりやすくその魅力を紹介します。
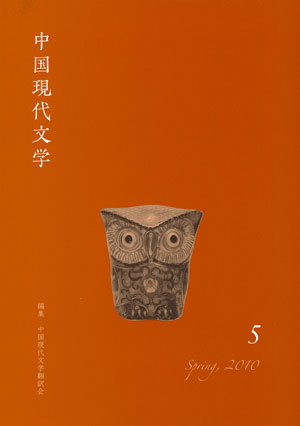
『中国現代文学 5』を刊行しました。
現代中国の実力派作家の作品を翻訳・紹介する『中国現代文学』の第5号です。
北の大地の物語を紡ぐ遅子建の中編小説「世界中のすべての夜」/上海と上海人を活写する陳丹燕の短編小説「X ON THE BUND」/北京の胡同に流れる記憶を辿る史鉄生の随筆集『記憶と 印象』より「珊珊(シャンシャン)」「小恒(シャオホン)」などを掲載します。
※『中国現代文学』は2008年4月創刊、年2回発行。

今週より書籍目録『未発』22号を発送しております。
『未発』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawase(アットマーク)hituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願いします。

『言語政策として「日本語の普及」はどうあったか—国際文化交流の周縁—』を刊行しました。
海外における日本語普及事業の戦後史。国際文化交流の中で、いかにして日本語は、海外で普及されてきたのか。言語政策の政策研究分野でほぼ初となる基礎的な参考書。

少し盛りだくさんな目録誌『未発』22号、できました。今度の『未発』は、綺麗なピンクです。シャーベットのようです。おいしそうですね。来週は社員、総出で、助っ人もお呼びして、発送します。
ちなみに『未発』という名前には、今まで誰からも発せられたことがない、ということと、それとひつじが発する、という意味をかけています。いささか、尊大とも言える名前なのです。お手にとってご覧下さいませ。


『英語研究の次世代に向けて 秋元実治教授定年退職記念論文集』と『海外短期英語研修と第2言語習得』の2冊を刊行しました。
『英語研究の次世代に向けて 秋元実治教授定年退職記念論文集』詳細。We have just revised our homepage in English today. Please visit our new homepage in English.
We release the new logo in western characters! As the event of 20th anniversary, we are happy to release the new logo.


『ガイドブック日本語文法史』、刊行しました。編者のお一人、高山善行先生にお越し頂きました。おかげさまでやっと刊行することができました。ありがとうございます。古典文学研究者の方にもぜひとも読んでもらいたいと思います。
『ガイドブック日本語文法史』詳細。

2009年の春に、ひつじ書房より刊行した堀田隆一先生のご著書『The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English』が日本中世英語英文学会松浪奨励賞の佳作を受賞されました。これまで詳細に明らかにされていなかった英語のs語尾についての非常に緻密で興味深いご研究です。
『The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English』詳細。
事業仕分けが、行われることになっている。23、26、27、28日の4日間、実施されるとのこと。今回、仕分けの対象になっていることがらとして、ひつじ書房の関心事は、研究費と学生の奨学金と日本語教育についてである。産経新聞によって報道された、個々の機関内で実際に対象になるだろうと言われているものがある。その中でここでは3つに注目していたい。
・国際交流基金(外務省)→日本語能力試験
・日本学術振興会(文科省)→科学研究費補助金
・理化学研究所(文科省)→先端的融合研究の推進
無駄遣いは、やめなければいけないが、必要不可欠なものを安易に削減しないでもらいたい。日本語能力試験については、現在、新しい仕組みに変更中であり、また、日本国内外の日本語学習者への公的な試験になっている。試験料をきちんと組み込む必要はあるが、基金が研究者や経験ある事務官の制度的なサポートのもとで行われるべきである。将来的に民営化あるいは第三セクター的に運営することは検討されていいが、現時点で試験だから、採算が採れるだろうというのは安易だと考える。

『ガイドブック日本語文法史』(高山善行・青木博史編)もうじき、刊行します。日本語文法研究の成果を古典の世界に活用するテキスト。日本語文法史の基本テーマをわかりやすく解説した教科書。「ヴォイス」「アスペクト・テンス」「モダリティ」「係り結び」「とりたて」「待遇表現」「談話・テクスト」「文法史と方言」など、15章で構成されている。
『ガイドブック日本語文法史』詳細。

『Writing for Academic Purposes 英作文を卒業して英語論文を書く』 (田地野彰・ティム スチュワート・デビッド ダルスキー編)刊行しました。新しいタイプの英文アカデミックライティングの教科書です。多くの類書がパラグラフライティングの本に留まっていますが、本書は本の読み方なども解説し、アカデミックスキルの初歩の紹介の本にもなっています。
大学等で英文で論文を書くという授業をされている方で、採用するかどうかを検討してくださいます場合には、採用見本をご請求下さい。講座名、受講予定人数などをお教え下さいましたら、見本をお送りします。
『Writing for Academic Purposes 英作文を卒業して英語論文を書く』詳細。
4月になりました。新しい年度になりました。その4月1日、ひつじ書房では新しく社員になるEを迎えての、入社式を行いました。入社式といいましても、講堂があるわけではありません。社員で食事会を行いました。近くの播磨坂のイタリアン、タンタローバにて。
昨年の12月からアルバイトに来てもらっていたので、彼女の場合は4月から、無事に社員となりました。ひつじ書房では3ヶ月程度、実際に働いてもらってから決めるのです。
こちらもご覧下さい。
『文法を教える』(国際交流基金)、『Derivational Linearization at the Syntax-Prosody Interface』(塩原佳世乃 著)刊行しました。たいへん、お待たせをいたしました。『接尾辞「げ」と助動詞「そうだ」の通時的研究』(漆谷広樹 著)も刊行しました。3冊、一気に刊行しました。
『Derivational Linearization at the Syntax-Prosody Interface』(塩原佳世乃 著)詳細。
ひつじ書房では、オンライン洋古書店abebooksと取引開始し、ひつじ書房の欧文学術書籍の販売を行います。つきましては、取引書類に書かれている英語の文章を読むことができ、受注・発送業務をこなす頃のできる程度の英語力があり、書籍販売に興味のある方を募集します。洋書店などでの経験を優遇します。未経験者でも応募は可能です。
詳細。
『清国人日本留学生の言語文化接触 ー相互誤解の日中教育文化交流』(酒井順一郎 著) A5判上製 定価4,700円+税。明治期、列強諸国に学ぶことに力を注ぐ日本。その最中、思いも寄らず清国から多数の留学生が来日してしまう。初の海外体験と近代教育を受ける清国人留学生、初の留学生教育を経験する嘉納治五郎と日本教育界、それぞれの戸惑い、苦悩、喜び、発見は一体何であったか。
『清国人日本留学生の言語文化接触 ー相互誤解の日中教育文化交流』』詳細。

『Writing for Academic Purposes 英作文を卒業して英語論文を書く』 (田地野彰・ティム スチュワート・デビッド ダルスキー編)4月第1週に刊行します。現在、大詰めです。新しいタイプの英文アカデミックライティングの教科書です。多くの類書がパラグラフライティングの本に留まっていますが、本書は本の読み方なども解説し、アカデミックスキルの初歩の紹介の本にもなっています。
『Writing for Academic Purposes 英作文を卒業して英語論文を書く』詳細。

高橋美樹著『沖縄ポピュラー音楽史ー知名定男の史的研究・楽曲分析を通して』を刊行しました。シリーズ文化研究の第1巻です。文化研究というジャンルで、新しい研究を世に送り出していきます。第1巻は音楽学、それもポピュラー音楽の歴史、それも沖縄でのポピュラー音楽です。装丁にも時間をかけています。カルスタと呼ばれたジャンルは、いまや低調ですが、文化研究というジャンルの重要性は失われてはいないでしょう。刊行開始です。第2巻はガンジーの抵抗を巡る議論です。ご期待下さい。
『沖縄ポピュラー音楽史ー知名定男の史的研究・楽曲分析を通して』(高橋美樹著)詳細

アブハズ語の辞書『Analytic Dictionary of Abkhaz』(柳沢民雄著)、『中世王朝物語の引用と話型』(中島泰貴著)、『ことばの宇宙への旅立ち3 ー10代からの言語学』(大津由紀雄編)、『格助詞「ガ」の通時的研究』(山田昌裕著)、『日本語指示詞の歴史的研究』(岡?友子著)、『日本語連体修飾節構造の研究』(大島資生著)、『現代日本語における外来語の量的推移に関する研究』(橋本和佳著)
『Analytic Dictionary of Abkhaz』(柳沢民雄著)詳細

アブハズ語の辞書、『Analytic Dictionary of Abkhaz』(柳沢民雄著)刊行しました。「本書は、アブハジア人のインフォーマントより収集した一次資料に基づいて編纂したアブハズ語・英語・ロシア語辞典である。」


ひつじ書房はおかげさまで20周年を迎えました。
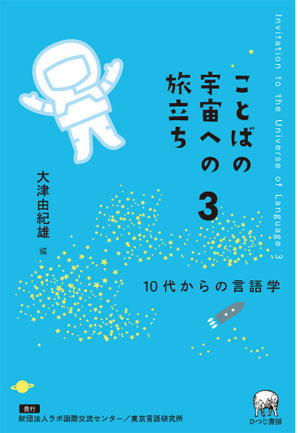
『ことばの宇宙への旅立ち』の第3弾。目次:今井むつみ(どうして子どもはことばの意味を学習できるのか)、長嶋善郎(「後ろ姿」は日本語的なことば)、野矢茂樹(ことばと哲学)、滝浦真人(夫婦ゲンカの敬語と上手な友だちの作り方、の言語学)、岡ノ谷一夫(動物の鳴き声と言語の起源)、尾上圭介(「文法」て"芸"ですか)。装丁は大崎善治さん。

『日本語がいっぱい』(李徳泳・小木直美・當眞正裕・米澤陽子著 Cui Yue Yan絵)刊行しました。ひつじ書房にとって、英語話者向けの日本語教科書です。このタイプのものははじめての刊行です。日本に来た留学生向けの『「大学生」になるための日本語1』につづいて英語話者むけの日本語教科書の刊行です。装丁は上田真未さん。

『日本語がいっぱい』(李徳泳・小木直美・當眞正裕・米澤陽子著 Cui Yue Yan絵)もう直ぐ刊行されます。ひつじ書房にとって、英語話者向けの日本語教科書です。このタイプのものははじめての刊行です。日本に来た留学生向けの『「大学生」になるための日本語1』につづいて英語話者むけの日本語教科書の刊行です。
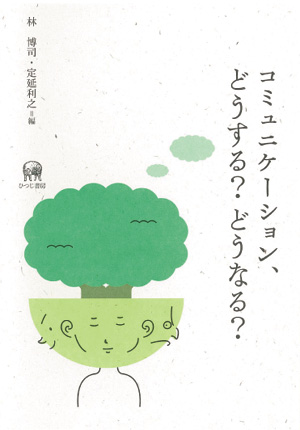
林博司・定延利之編『コミュニケーション、どうする?どうなる?』やっと、といいますか、でました。編者の先生、執筆者の先生方、まことに申し訳ありません。ひとえに編集長の怠慢です。内容はとてもユニークです。コオロギを1匹だけで飼うと凶暴になる、発音の断面図、などなど。おって、もう少し丁寧に紹介します。

東京さぬき倶楽部にて、新春の合宿・新年会を行いました。今年の予定を話し合いました。今年は20周年を迎える年です。合宿の内容については、房主が近日の内に報告します。報告

丑年が明けて、寅年となりました。ひつじ書房にとっては20周年を迎える年となります。これを節目として大きく飛躍したいと思っています。研究者の方々のご期待に応えられるよう頑張っていきたいと思います。至らない点も多々あることと思いますが、丁寧にきちんとした研究書を刊行していきたいと思っています。叱咤、激励をお願いします。

実質的な仕事納めの日、3冊を刊行しました。『自然な日本語を教えるために ー認知言語学をふまえて』(池上嘉彦・守屋三千代 編著)、未発選書 16『「女ことば」は女が使うのかしら?』(任利)、ひつじ研究叢書(言語編) 第81巻『疑問文と「ダ」ー統語・音・意味と談話の関係を見据えて』(森川正博)刊行しました。
『疑問文と「ダ」』 『「女ことば」は女が使うのかしら?』
中国現代文学翻訳会編 A5判並製 定価2,000円+消費税 ISBN978-4-89476-487-3
再びの残雪(「陰謀の網」(近藤直子訳)記憶の果てから不思議な若者とともに血と硝煙のにおいが立ち昇る……)ほか、中国の現代の文学をつたえる作品のアンソロジー。
みなさまのおかげで第2期に突入できそうです。したがって、5巻が来年の4月に刊行予定です。でもまだ、webcatによると全国の大学図書館で33館しか入っていません。大学の数は708(平成16年度大学図書館実態調査結果報告によるhttp://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/05070501.htm)あるので、この数の比率で言うと4.6パーセントということになります。
詳細
『中国現代文学 4』
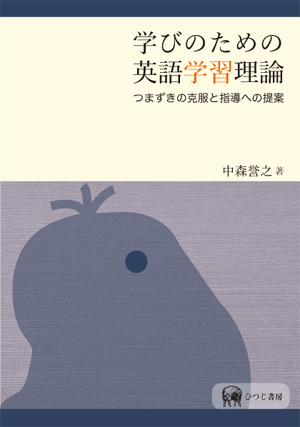
中森誉之 著 A5並製 定価2,400円+税
内容紹介 「英語学習者の代表的なつまずきの原因と克服の方法を、言語習得と言語処理の理論を援用しながら系統立てて考察し、実践と理論の調和から、より効果的かつ効率的な英語指導が展開できることを示す。英語教師必携の書であるとともに、英語の学習過程におけるつまずきの原因と解決策が示されており英語を学ぶ人のためにも書かれている。「経験と勘である」と思われ、先輩の指導方法が連綿と受け継がれる英語教育に理論的根拠を与え、「経験と勘」の世界から英語学習を解き放つ。」
詳細
『学びのための英語学習理論ーつまずきの克服と指導への提案』

本書では、いわゆる「女性語」「男性語」といった二項対立的な視点を相対化させ、≪女性性・男性性≫という言語理論を導入し、日本語に観察される女性と男性の言葉遣いの特徴を記述し、その原因を解明する。
今年も、


鈴木泰恵・高木信・助川幸逸郎・黒木朋興 編『〈国語教育〉とテクスト論』、大津由紀雄 編 The Proceedings of the Tenth Tokyo Conference on Psycholinguistics (TCP2009)、刊行しました。両方とも担当は森脇です。
『〈国語教育〉とテクスト論』は、「テクスト論を中心とする、70〜80年代に受容された欧米文学理論はもはや過去のものにすぎないのか? そして文学教育は、「実用性」を欠いた無用の長物なのか? このような問題意識の下(…)」企画されました。気鋭の文芸批評家、前田塁氏も執筆しています。どうぞご覧下さい。『〈国語教育〉とテクスト論』は、日本文学協会にて20冊完売しました。
詳細
鈴木泰恵・高木信・助川幸逸郎・黒木朋興 編『〈国語教育〉とテクスト論』

今まで、言語学の研究者の方以外には目録をお送りしていませんでしたが、この冬、はじめて、目録誌「未発」を日本文学の研究者の方々に発送します。20周年企画として『21世紀日本文学ガイド第1期』(三田村雅子・中島隆・金子明雄監修)を来年から刊行します。この企画のチラシを同封しています。これから、日本文学研究のジャンルに参入して参ります。どうぞよろしくお願いします。

東北大学言語認知総合科学COE論文集刊行委員会編『言語・脳・認知の科学と外国語習得』、刊行しました。担当は、竹下です。新人ですが、4冊目。

やっとのことで、『コミュニケーション、どうする? どうなる?』もうすぐ刊行します。言語学会には、ちょっと難しそうですが、そんなに遠くなく刊行します。本当にお待たせしました。
詳細(作成中)
『コミュニケーション、どうする? どうなる?』


『結果構文のタイポロジー』(小野尚之編)、『コロケーションの通時的研究 ー英語・日本語研究の新たな試み』(堀正広・小迫勝・浮網茂信・西村秀夫・前川喜久雄著)。2冊同時刊行となりました。担当は細間です。英語学会に間に合わせるべく一生懸命すすめておりました。そのかいあって、無事に学会に登場します。この土日に大阪大学で開かれます英語学会に出店しますので、どうぞお手にとってご覧下さい。
『コロケーションの通時的研究 ー英語・日本語研究の新たな試み』

ひつじ書房から『古代日本語母音論--上代特殊仮名遣の再解釈 (ひつじ研究叢書 (言語編 第4巻))』を出されていらっしゃいます松本克己先生が、瑞宝中綬章叙勲されました。おめでとうございます。古代日本語の母音は5つなのか8つなのか、言語学の論争を呼び起こした松本克己先生の主著『古代日本語母音論』を1995年に刊行しています。(論争自体はもっと前ですが、長い間書籍になっていませんでしたものを書籍にしたのです。上代特殊仮名遣を参照。)ひつじ書房の初期の頃、無名というべきひつじ書房から、刊行して下さったことはたいへん、ありがたいことです。
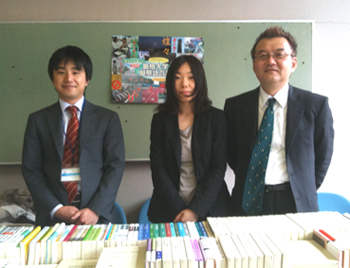
日本語学会が、島根にて無事に開催されました。日本語学会は春はインフルエンザにて急遽開催が中止され、この秋も小中学校ではあちこちでインフルエンザによる休校もある中、開催が心配されていましたが、無事に開催されました。講演は村木新次郎先生と大坪併治先生でした。大坪先生はかぞえで100歳、お元気でした。ご尊顔を拝するだけでありがたい気持ちになりました。私の個人的な印象からしますと内容ではなく、風貌の印象ですが、小ゑんと小さんの親子会という感じでした。落語ですね。小さんは先代の方です。日曜日の研究発表は、若手が出てきたな、という印象です。こっちは二つ目かな?
日本語学会の前日に開かれる近代語研究会に間に合わせるべく、『日本近代語研究5』も無事に間に合いました。大部な立派な書籍です。『日本近代語研究5』、川上蓁先生も書いて下さっています。川上先生は、桂文楽かな、先代の。
詳細
『日本近代語研究5』
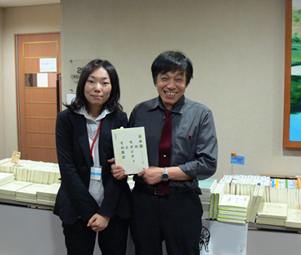
仁田義雄日本語文法著作選 第2巻『日本語のモダリティとその周辺』刊行しました。学習院女子大学で開催されました第10回、日本語文法学会に間に合わようと作っていましたが、間に合いました。本書の担当は新人の竹下です。無事にできまして、仁田先生と学会で記念撮影をいたしました。第2巻は、モダリティですので、全4巻の中でも1つの頂点的な巻だと思います。どうぞお求め下さい。第3巻の原稿もいただきましたので、着々と進んでいます。春には3巻目も刊行することができますので、ご期待下さい。

今年も秋の未発ができました。今年の色は紫です。21号です。先週から今週にかけて、言語系の方への発送をしました。言語系以外の方へは、少し後に発送します。
もうすぐ、『月刊言語』が休刊されてしまうということです。そうなると読者の方に刊行のお知らせをするメディアがなくなってしまいます。(ネット版『季刊言語』でも、創刊しますかね?出資して下さる方はいらっしゃいますか?仕事をする時期だけでよいですが、編集者1名と広告担当1名、プログラマー1名あと原稿料の分を出資してもらうことができれば創刊します。)目録は数少ない、貴重なメディアだと思っています。社員とお願いしたスタッフで、発送いたしました。近日のうちにお手元に届くことと思いますので、どうぞご覧下さい。
『未発』をご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、どうぞひつじ書房までご連絡下さい。連絡先は、toiawaseアットマークhituzi.co.jp.co.jpで担当は三井です。どうぞよろしくお願いします。
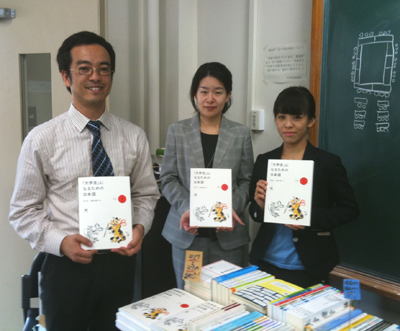
堤良一先生、長谷川哲子先生著『「大学生」になるための日本語1』刊行しました。日本語教育学会にお目見えしました。文法とタスクの融合を目指し、豊富で分かりやすいイラスト、著者が書き下ろさない実際に世の中に書かれた本文を使い、日常的な話し方をする俳優さんに吹き込んでもらった自然な会話の音声CD2枚。新しい試みが随所で行われています。
日本語教育学会の初日のシンポジウムは、国際交流基金による新しい日本語能力試験の解説でしたが、課題遂行型のコミュニケーション能力を測るものになるとのことですが、文法(言語知識)とタスクを融合させることを目標として作成した本書は、現時点でもっとも新しい日本語能力試験に対応している教科書と言えるのではないでしょうか。聴解も、新しい日本語能力試験のモデルに標準を合わせ、ある部分追い越しているとさえもいえる内容になっていると思います。
「新しい「日本語能力試験」に対応?」もう少し詳しく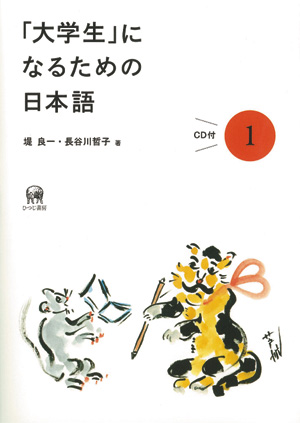
『「大学生」になるための日本語1』刊行しました。2006年の春に開始し、企画から4年目の秋、ようやく刊行にいたりました。文法とタスクの融合を目指し、豊富で分かりやすいイラスト、著者が書き下ろさない実際に世の中に書かれた本文を使い、きちんとした俳優さんに吹き込んでもらった自然な会話の音声CD2枚。新しい試みが随所で行われています。著者は、堤良一先生、長谷川哲子先生です。板東が担当しました。デザイナーは大崎さんです。

綾部保志、榎本剛士先生と『言語人類学から見た英語教育』の刊行のお祝いをいたしました。特に今回、大修館書店から刊行されている『英語教育』で、柳瀬先生に本書を紹介していただきましたので、そのことをきっかけに祝宴をあげました。柳瀬先生の書評がきっかけでしたので、『リフレクティブな英語教育をめざして』の担当の竹下と松本がお祝い申し上げました。
『リフレクティブな英語教育をめざして』は、10月11日(日)・12日(月)に神戸で開かれます「ナラティブが英語教育を変える?--ナラティブの可能性」(関西英語教育学会:KELES 第17回セミナー)にてお目見えします。竹下が担いで会場に参ります。『言語人類学から見た英語教育』ともども、ぜひ、ご覧下さい。
『リフレクティブな英語教育をめざして—教師の語りが拓く授業研究』
関西英語教育学会:KELES 第17回セミナー
ナラティブが英語教育を変える?--ナラティブの可能性
10月になりました。現在、今年申請することを決めた方々の書類の作成をお手伝いしています。ひつじ書房での本年の学術振興会申請のための新規の出版提案書の受付は10月7日までとさせていただきます。恐れ入りますが、このギリギリの時期は加えましてひつじかいに入っている方、ひつじメール通信の読者に限らせていただきます。
まことに勝手ではございますが、この先、申請をされようと考えている方は、ひつじかいに入っていただきますことをお願いします。

市民活動をリードしてきた加藤哲夫さん(『市民の日本語』著者)、還暦突入のお祝いに仙台に行ってきました。写真は、ハンズオン!埼玉の吉田理映子さんのプレゼント。何と『市民の日本語』のかぶりものです。

『市民の日本語』につきましては、詳細をご覧下さい。
還暦突入のお祝いの会についてはこちらをご覧下さい。
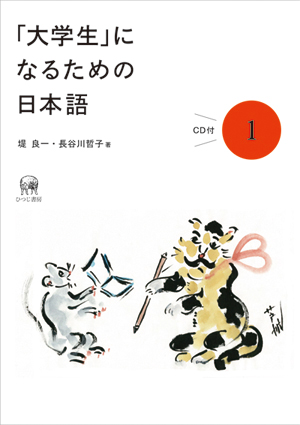
たいへん、お待たせしました。「大学生」になるための日本語1、もう少しで刊行します。
詳細につきましては、『「大学生」になるための日本語1』をご覧下さい。
執筆要項(和文横組み用)の最新版は1.504です。
詳細につきましては、執筆要項のページへようこそをご覧下さい。
ひつじ書房では現在、文学関係のシリーズ書籍を企画中です。本シリーズ製作にあたり、書籍のデザイナーを募集いたします。カバー等の外観だけでなく、本文の設計についても造形が深く、意欲的に一緒に本作りに取り組んでくれる方を募集いたします。
詳細につきましては、担当:森脇(toiawase@hituzi.co.jp、アットマークを半角に変更して下さい)までメールにてお問い合わせ下さい。どうぞよろしくお願いします。

日本橋「住庄ホテル」で、13回目の合宿をしました
2009.8.21
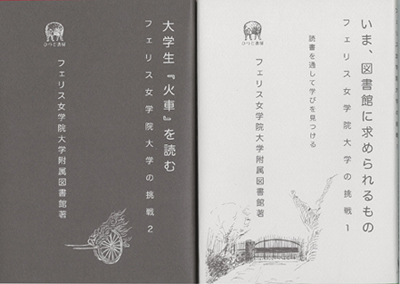
読書が危機だとよく言われる。日本の高校生も大学生も半数以上本を読まないし、読む本も圧倒的に少なくなっている。大学図書館の需要は下がる一方で、しかも大学図書館では人べらし、本べらしが深刻で、もはや知の蓄積と運用の態勢を維持できないところまで追い詰められている。いまデキルことは何なのか。図書館が頭をしぼって考えた読書推進運動は学生・教員を巻き込み、台風の目玉のように全学を席捲したフェリス図書館の七年間。
詳細
『いま、図書館に求められるもの フェリス女学院大学の挑戦1』
『大学生『火車』を読む フェリス女学院大学の挑戦2』
2009.8.19
月刊『言語』12月より休刊とのこと。広告代理店よりの連絡がありました。長い間、言語学を支えてきた雑誌の休刊につきまして、たいへん残念です。
たとえば、大日本印刷が丸善やジュンク堂を経営的に吸収したように、言語という雑誌に対して、出資して雑誌を継続させるというようなことを検討するという可能性もあったのではないか。そういう場合に、ひつじ書房が編集部ごとに引き取るということもできる。海外の出版ではM&Aということがあるが、そういう方法もあるのではないか。このようなことはネットで述べることではなく、大日本印刷なりに提案すべきことだ。私の力不足を悔やむ。
大修館書店が経営的に悪化したとは聞いていないだけに、学術出版に対する1つの判断として受け取らざるを得まい。それゆえ、ひとしお残念である。
2009.8.10
2009年の春夏のオープンオフィス、無事に終了しました。本年も多くの方にお越し頂きましたことをうれしく、そして感謝申し上げます。
企画提案そのもののご相談は一年中、承っています。どうぞ声をお掛け下さい。本年の科学研究費公開促進費に申請してみようとお考えの方は、内容について、ひつじ書房で出版をすることができるかを判断した上で進めたいと考えていますので、検討する時間が必要ですので、なるべく9月の半ばまでにご相談下さいますようお願いします。
2009.8.3
 朝日新聞の新聞求人広告と言っても5行の広告で小さなものです。同じ日にもっと大きな出版社の求人もでていました。会社の規模ではとうてい勝てませんが、書籍編集特に学術書に対する情熱ではどこの社にも負けをとらないと自負しています。ひつじ書房では、ひつじ書房の出版の仕事に活力をもたらしてくれる若いスタッフを求めています。
朝日新聞の新聞求人広告と言っても5行の広告で小さなものです。同じ日にもっと大きな出版社の求人もでていました。会社の規模ではとうてい勝てませんが、書籍編集特に学術書に対する情熱ではどこの社にも負けをとらないと自負しています。ひつじ書房では、ひつじ書房の出版の仕事に活力をもたらしてくれる若いスタッフを求めています。
未経験者・来春新大卒の方も可です。
詳細 求人について
2009.7.29

この春から、ひつじ書房の書籍のデザインをしてくれているブックデザイナー上田真未さん。『グローバル化社会の日本語教育と日本文化』は上田さんの装丁です。ひつじの本でできあがった本は、これで9冊目になります。『マイノリティの名前はどのように扱われているのか』、『改訂版 日本語要説』、『裁判とことばのチカラ』、『プロフィシェンシーと日本語教育』、『多文化社会オーストラリアの言語教育政策』、『さらに進んだスピーチ・プレゼンのための日本語発音練習帳』、『大学の授業をデザインする 日本語表現能力を育む授業のアイデア』、『文化間移動をする子どもたちの学び』を装丁してもらっています。センスが良く、色遣いもステキです。これからもひつじ書房の書籍の装丁で上田さんにお願いすることが多いと思います。ご期待下さい。
2009.7.29
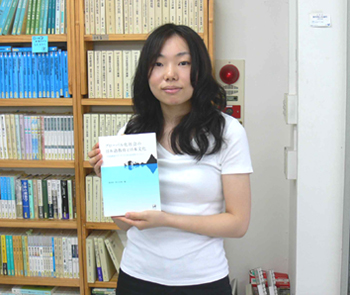
『グローバル化社会の日本語教育と日本文化』刊行しました。2008年11月に行われた、香港大学日本研究学科主催の国際シンポジウムで発表された論考から、アジア・オセアニアでの多文化共生社会と日本語教育・日本研究に深く関連するものをまとめた書籍です。グローバル化が進み、多文化共生が身近なテーマとなった昨今、どの方にとっても興味深く読める一冊です。担当は、この春、入社の新人の竹下乙羽が担当しました。竹下の記念すべき1冊目です。
2009.7.26
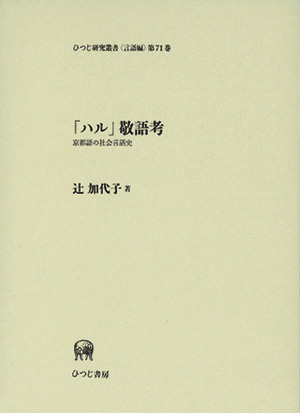
京都の不思議なハル敬語についての考察をした『「ハル」敬語考−京都語の社会言語史』が、毎日新聞書評欄にて紹介されました。
2009.7.24

『マイノリティの名前はどのように扱われているのか』の著者リリアンさん7月23日付け朝日新聞夕刊6面のテークオフ欄で紹介されました。本書の内容とともにリリアンさんの活動・研究について紹介されています。
2009.7.22

『「大学生」になるための日本語1』もう少しで刊行します。聴解部分の音声の収録、編集を池尻大橋のスタジオで行いました。吹き込みは、俳優さんにお願いしました。青年団の足立誠さん、東京タンバリンのミギタ明日香さんたちにお願いして、無事収録が終わりました。これまでの日本語の教材より、より自然な日本語の会話となったと思います。ご期待下さい。
2009.7.16

『グローバル化社会の日本語教育と日本文化』まもなく刊行します。2008年11月に行われた、香港大学日本研究学科主催の国際シンポジウムで発表された論考から、アジア・オセアニアでの多文化共生社会と日本語教育・日本研究に深く関連するものをまとめた書籍です。グローバル化が進み、外国文化に触れることが身近なテーマとなった昨今、どの方にとっても興味深く読める一冊です。
2009.7.9
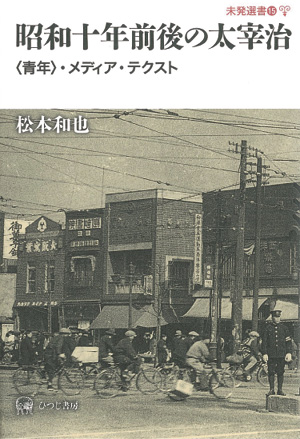
松本和也著『昭和十年前後の太宰治』が、2009年7月8日付けの聖教新聞の書評に取り上げられました。青年が注目される太宰神話を内破することに成功している、と取り上げて下さっています。
2009.7.8
「執筆要項」でgoogleで検索していただくと、ひつじ書房のHPが一番にくるほどに、ひつじ書房の執筆要項は検索して、ご覧いただいているモノと思いますが、10年くらいで、つぎはぎつぎはぎできた執筆要項です。不統一が多々ありました。そのような点などをある程度整理して、整合性を高めました1.501版をアップします。これもまだ、途中ですので、ご意見コメントをお待ちしております。
詳細
『執筆要項1.5』
2009.6.29

工藤真由美・森幸一・山東功・李吉鎔・中東靖恵著『ブラジル日系・沖縄系移民社会における言語接触』刊行しました。A5判上製 定価8,000円+税、ISBN 978-4-89476-423-1。「本書は2002から2006年度に実施された、大阪大学・21世紀COE「インターフェイスの人文学」を中心とする研究成果の一部であり、ブラジル日系・沖縄系移民社会における「日本語」の諸相について、言語接触の観点を重視した「複数の日本語」という視角から、考察を試みたものである。特に、沖縄系移民社会については、これまでほとんど調査研究がなされていなかった。「ブラジル日系社会における談話」「ブラジル沖縄系移民社会における談話」の一部についてDVD-ROM付きで紹介している。」担当は細間です。装丁は中山銀士さんです。
2009.6.28

『マイノリティの名前はどのように扱われているのか』6月28日付け朝日新聞の書評欄で紹介されました。
2009.6.24
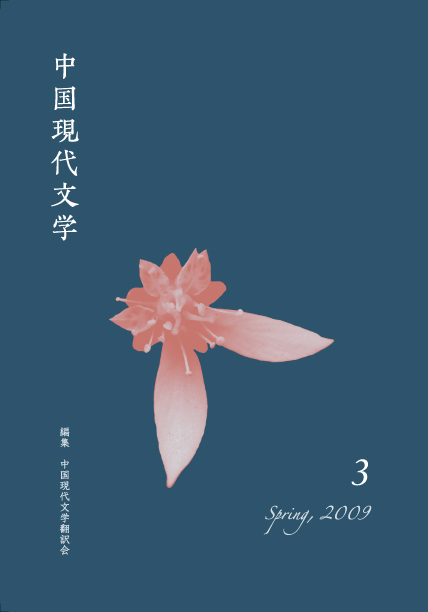
『中国現代文学』、やっと3巻までこぎつけました。今回は、中国のマンガを1編収録しています。中国のマンガの紹介も珍しいことだと思います。必見の1冊となっています。担当、本文組、板東です。
詳細
『中国現代文学3』
2009.6.17
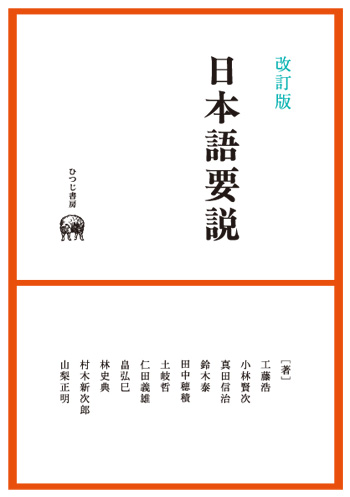
好評を博した1993年の初版以降の研究動向を踏まえ、内容、装丁共に改訂。日本語のしくみを広いフィールドから知ることができる日本語の入門書。日本語について主要なことを的確に学ぶための1冊。
詳細
『改訂版 日本語要説』
2009.6.11

味岡美豊子著『社会人・学生のための情報検索入門』刊行しました。著者の味岡さんは、自分で検索事務所を立ち上げたプロの検索者(サーチャー)です。
「インターネットが普及し、だれでも「ググる」ということが当たり前になった。だれでも情報を自由に検索できるという思いこみが生まれている。情報検索というとただことばを検索窓に入れて、リターンキーを押すだけだと思っている人が多い。情報検索というビジネスで生きている著者は、そうではないという。本当の意味での情報検索のやり方、方法、考え方への招待。」担当は、不肖松本です。刊行の遅延は、松本の責任です。おまたせしましてすみませんでした。
2009.6.10
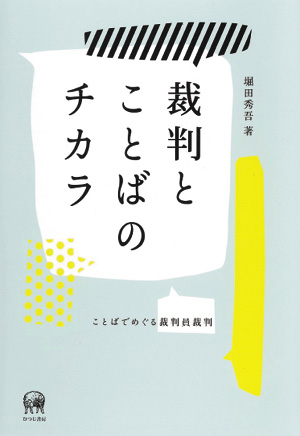
『裁判とことばのチカラーことばでめぐる裁判員裁判』刊行いたしました。著者の堀田秀吾(明治大学法学部准教授)先生は、言語学者マッコーレーの弟子でありつつ、ロースクールでも学んでいる若手の法言語学者。本書は裁判で使われている用語についての解説ではなく、裁判の過程でことばがどんな機能を働かせるかの研究、概説の書です。担当は、細間です。
2009.6.3
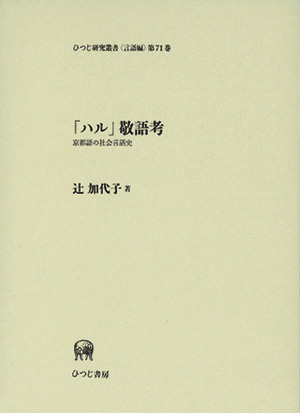
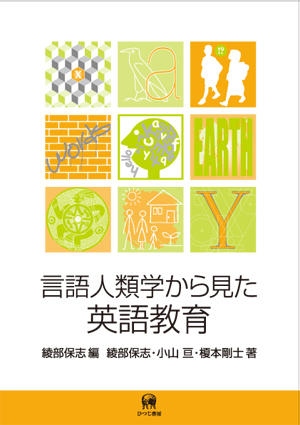
辻加代子著『「ハル」敬語考ー京都語の社会言語史』、綾部保志編『言語人類学から見た英語教育』刊行しました。『「ハル」敬語考ー京都語の社会言語史』は、「江戸時代後期から現代に至る京都語言語資料に基づき、近畿中央部とりわけ京都市で隆盛を極める「ハル」敬語の包括的記述を試みたモノグラフ。」『言語人類学から見た英語教育』は、「英語教育のみならず言語教育に関わる者にとって、文法とは一体何であり、コミュニケーション(言語使用)が行われることで、私たちの社会・文化がどのように構築されているのか、と問い直してみる」内容。
詳細
『「ハル」敬語考ー京都語の社会言語史』
『言語人類学から見た英語教育』
2009.5.29
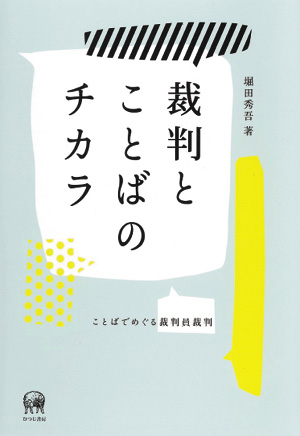
『裁判とことばのチカラーことばでめぐる裁判員裁判』まもなく刊行します。「これまで市民には全く馴染みのなかった「裁判」の世界を、「ことば」を手掛かりに、コーパス言語学や語用論などの言語学の理論だけでなく言語心理学や社会心理学などの理論を用いながら、さまざまな角度から分析」著者の堀田秀吾(明治大学法学部准教授)先生は、言語学者マッコーレーの弟子でありつつ、ロースクールでも学んでいる若手の法言語学者。
2009.5.28

『日本語教育学研究への展望ー柏崎雅世教授退職記念論集』刊行しました。「2009年3月にご退職を迎えた東京外国語大学教授柏崎雅世氏と、東京外国語大学留学生日本語教育センターにゆかりのある研究者や大学院の教え子たちが寄稿し、27本の論文によって編まれた論文集。幅広く日本語教育に関わる論文が集められている。」担当は細間です。
詳細
『日本語教育学研究への展望
ー柏崎雅世教授退職記念論集』
2009.5.26
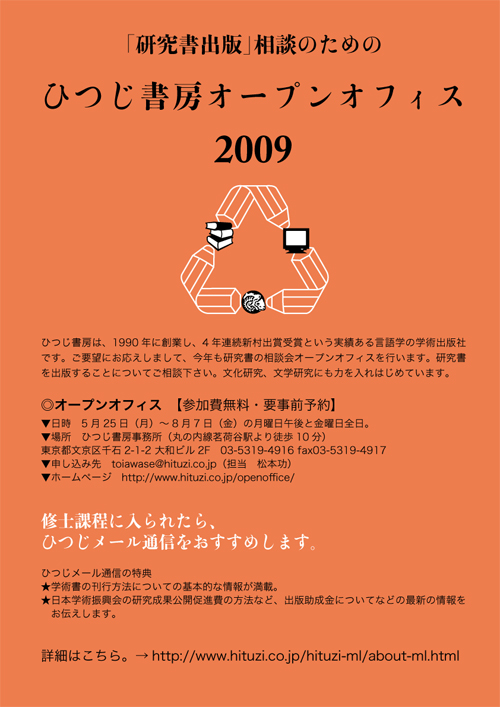
本年も、研究書出版相談会、オープンオフィス、開催します。言語学、日本語学、英語学などから文学研究、文化研究まで、人文科学の研究書の刊行についての相談会を開催します。
2009.5.21

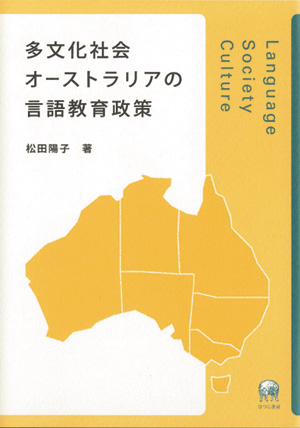
鎌田修・堤良一・山内博之編『プロフィシェンシーと日本語教育』、松田陽子著『多文化社会オーストラリアの言語教育政策』刊行しました。日本語教育学会に間に合いまして、ほっとしています。担当はそれぞれ森脇と松本です。ステキな装丁は上田真未さんです。
詳細
『プロフィシェンシーと日本語教育』
『多文化社会オーストラリアの言語教育政策』
2009.5.15

山本富美子著『第二言語の音韻習得と音声言語理解に関与する言語的・社会的要因』刊行しました。「日本語の音声言語理解について中国北方方言話者と上海語話者,非中国語系話者を比較調査した。その結果,母語に破裂音の有声・無声の対立を持たない北方方言話者は,日本語の音声言語で生起頻度の高い破裂音の習得が困難なため,音声言語の意味理解が劣ることを明らかにした。」担当は細間です。
詳細
『第二言語の音韻習得と音声言語理解に関与する言語的・社会的要因』
2009.5.14
ひつじ書房では、日本語学習者向けの日本語の教材『「大学生」になる日本語 1』の編集を行っています。この中の会話の部分の音声を吹き込んで下さる方を募集しています。
若者男女二人が中心で、一部に年上の男性が登場するという内容です。
声優か俳優の方、ご連絡下さい。声で年上の方の声を表現することができるのであれば、男女二人のグループかたが助かります。3人でも、いいと思います。
このような募集ははじめてのことで、失礼の点がありましたら、申し訳ありません。謝礼などもご相談しながら進めていきたいと考えています。連絡先は編集部宛、次の通りです。
hensyuアットマークhituzi.co.jp
2009.5.11
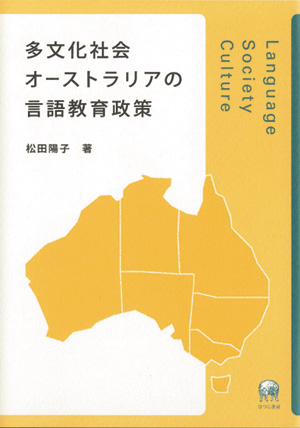
松田陽子著『多文化社会オーストラリアの言語教育政策』もうすぐ刊行します。多文化主義ということで評価されてきたオーストラリアの言語政策の実際を分析する。オーストラリアは、本当に多文化主義といえるのか。政治の変化の中で、変わるものと変わらないものは、何なのか。
2009.5.8
ひつじ書房では、今秋の刊行に向けて、スペイン語教科書を編集しています。本文のデザイナーさんは先日決まりまして、本文のイラストを描いてくれるイラストレーターさんを募集することにしました。詳細は、次のメールアドレス宛に、お問い合わせ下さい。担当は板東です。
seisakuアットマークhituzi.co.jp
2009.4.30
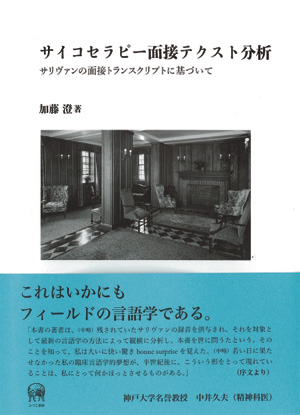

加藤澄著『サイコセラピー面接テクスト分析 ーサリヴァンの面接トランスクリプトに基づいて』を刊行しました。中井久夫先生に序文を書いていただきました。サイコセラピーと機能言語学の接点を作る言語研究です。サイコセラピストサリヴァンを言語学に紹介する研究でもあります。装丁はみすず書房的なのですが、カバーをとると…。細間が担当しました。
詳細
『サイコセラピー面接テクスト分析 ーサリヴァンの面接トランスクリプトに基づいて』
中川千恵子・中村則子・許舜貞著『さらに進んだスピーチ・プレゼンのための日本語発音練習帳』は、よりちゃんとした日本語アクセント、プロソディで話せるようになるための練習方法の本です。日本語上級学習者向けですが、教師にとって指導可能(teachable)、学習者にとって学習可能(learnable)な方法を提示します。装丁は上田真未さんです。
詳細
『さらに進んだスピーチ・プレゼンのための日本語発音練習帳』
2009.4.28

リリアン・テルミ・ハタノ著『マイノリティの名前はどのように扱われているのかー日本の公立学校におけるニューカマーの場合』を刊行しました。「日本の公立学校でブラジル人・ペルー人の子どもたちの名前はどう扱われ、日本での暮らしは彼・彼女たちの「命名」にどんな影響を与えているのか。」研究が、研究される人々、子どもたちからにも益があるように願い、これからの社会のありかたもたぐり寄せようとする研究。松本が担当しました。ステキな装丁は上田真未さんです。
2009.4.24

大島弥生・大場理恵子・岩田夏穂編『大学の授業をデザインする 日本語表現能力を育む授業のアイデア』を刊行しました。刊行までずいぶんとお待たせしてしまいました。日本語表現の授業をお持ちの先生方、これから大学で日本語表現の授業を担当する可能性のある先生方にとって、とても役に立つ本ができたと思います。細間が担当しました。きれいな装丁は上田真未さんです。
詳細
『大学の授業をデザインする 日本語表現能力を育む授業のアイデア』
2009.4.17

中村三春 編『ひつじアンソロジー小説編II 子ども・少年・少女』刊行しました。「子ども・少年・少女を描いた、現代の童話・児童文学・小説作品を選りすぐり、10作家14作品を収録。各編に珠玉の解説を付すことにより、ジャンルにこだわらず、時代ごと、作家別の文芸様式を味わい、変遷をたどる中で現在におけるその意義を問い直す。」森脇が担当しました。
2009.4.16

リリアン・テルミ・ハタノ著『マイノリティの名前はどのように扱われているのか ー日本の公立学校におけるニューカマーの場合』近日、刊行します。
詳細
『マイノリティの名前はどのように扱われているのか ー日本の公立学校におけるニューカマーの場合』
2009.4.15

齋藤ひろみ・佐藤郡衛 編『文化間移動をする子どもたちの学び—教育コミュニティの創造に向けて』刊行しました。「いわゆるニューカマーと呼ばれる子どもたちへの教育は、当初の学校適応・日本語指導を経て、新たな取り組みが始まっている。新しい実践や支援活動の経過と成果を分析し、文化間移動をする子どもたちの教育の課題を再設定するとともに、その解決に向けて教育実践の方向性と枠組みを探る。」松本が担当しました。カバーのデザインは上田真未さんです。
詳細
『文化間移動をする子どもたちの学び—教育コミュニティの創造に向けて』
2009.4.14
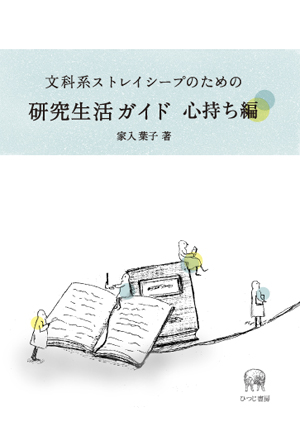
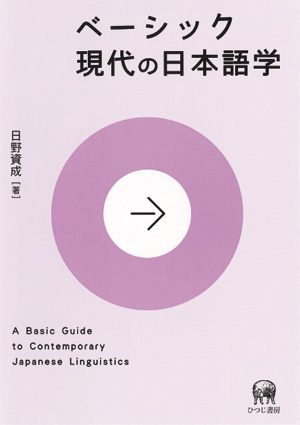
『ベーシック現代の日本語学』『文科系ストレイシープのための研究生活ガイド 心持ち編』刊行しました。『ベーシック現代の日本語学』は、日野資成先生による新しい日本語学の概説書です。『文科系ストレイシープのための研究生活ガイド 心持ち編』は、『文科系ストレイシープのための研究生活ガイド』の続編です。
詳細
『ベーシック現代の日本語学』
文科系ストレイシープのための研究生活ガイド 心持ち編
2009.4.13

『The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English』の著者の堀田隆一先生が、ひつじ書房の事務所にお越しになりました。名詞の複数を表すs語尾の本格的研究。Lexical Diffusionの理論や史的コーパスを用いた本書は、新しい英語史・言語史を提案するものです。
詳細
『The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English』
2009.4.9


『日本語の文法カテゴリをめぐって』『プロフィシエンシーから見た日本語教育文法』刊行しました。『日本語の文法カテゴリをめぐって』は仁田義雄先生の日本語文法著作選全4巻の第1巻になります。これから、春と秋と2年間で完結を目指していきます。ご期待下さい。担当は松本です。
『プロフィシエンシーから見た日本語教育文法』は、『OPIの考え方に基づいた日本語教授法』の続編とも言える書籍です。担当は板東です。
詳細
日本語の文法カテゴリをめぐって
プロフィシェンシーから見た日本語教育文法
2009.4.6
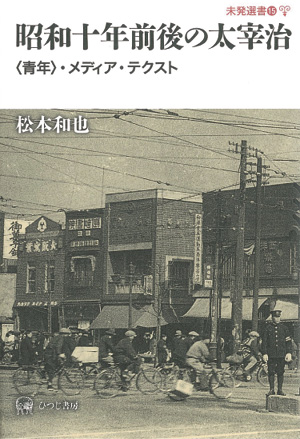

松本和也著『昭和十年前後の太宰治』と接続刊行会編『接続2008:言語と教育』が、刊行になりました。この二冊は、森脇が担当しました。
『昭和十年前後の太宰治』の表紙は、昭和10年代の神保町の交差点です。神保町の交差点というと、20世紀少年の舞台にもなっているという(ロボットが細菌を撒きながら動き出す出発点)場所です。
太宰生誕100周年を記念して…。
詳細
昭和十年前後の太宰治ー〈青年〉・メディア・テクスト
接続2008 特集:言語と教育
2009.4.2

4月1日、新しい新人を迎えて、竹下さんの入社式を行いました。近くの播磨坂のイタリアン、タンタローバにて。まかないたまごパスタ、たまごがふたつのって美味しかった。★たまごというのも、竹下さんの門出の日のメニューとして合っていたと思います。ひつじで、育ってくれますように。(このパスタは、たまごによって味が完成するようになっていました。)願いであるとともに期待しています。ひつじ書房の未来は、あなたにかかっていますから。
2009.3.30


東京外国語大学で開催されました社会言語科学会に参加しました。今回は、10周年記念シンポジウムも開催され、参加者も多く、盛況でした。
ひつじ書房では、社会言語科学会の設立の10周年をお祝いするお花をお送りしました。なかなか素敵でしょう?
2009.3.27


桜も開花し、年度末です。次々と刊行していきます。木山三佳著『日本語学習者の「から」にみる伝達能力の発達』と『メディアとことば4』を刊行しました。
『日本語学習者の「から」にみる〜』は「教室環境にある学習者を対象に、統語的規則を理解している状態から場面にふさわしい言語使用ができる状態になる段階に焦点をおき、場面に応じて「から」を使いわけられるようになるプロセスを分析した」内容。本書は、松本が担当しました。
『メディアとことば4』は、新しいメディア(YouTube)などを研究資料として活用しつつ、メディアの中の言説を分析します。麻生首相の自称詞や女は子どもを産む機械発言などを取り上げています。
奇跡的に去年と今年と1年の間隔で刊行することが出来ました。本日のメディアととことば研究会でお目見えです。本書の担当は板東です。
『日本語学習者の「から」にみる伝達能力の発達』の詳細
『メディアとことば4』の詳細
2009.3.24
 3月24日『朝日新聞』朝刊の、「日本と韓国の対人行動の違いについて」の記事のなかで、『対人行動の日韓対照研究』(尾崎喜光編)が紹介されています。尾崎喜光先生へのインタビューと、共著者である任栄哲先生の「身体接触から見た個人テリトリー意識」についても、掲載されています。
3月24日『朝日新聞』朝刊の、「日本と韓国の対人行動の違いについて」の記事のなかで、『対人行動の日韓対照研究』(尾崎喜光編)が紹介されています。尾崎喜光先生へのインタビューと、共著者である任栄哲先生の「身体接触から見た個人テリトリー意識」についても、掲載されています。
掲載記事は、『対人行動の日韓対照研究』からご覧いただけます。
2009.3.23
 岸本秀樹著『ベーシック生成文法』刊行になりました。生成文法についてのいま日本語で書かれているものとしては、一番わかりやすいものだと思います。生成文法の入口に入ってみたいと考えた場合に、最適な書籍です。春らしい色、ブックデザインはオオサキさんです。本書は、細間が担当しました。
岸本秀樹著『ベーシック生成文法』刊行になりました。生成文法についてのいま日本語で書かれているものとしては、一番わかりやすいものだと思います。生成文法の入口に入ってみたいと考えた場合に、最適な書籍です。春らしい色、ブックデザインはオオサキさんです。本書は、細間が担当しました。
詳細は、『ベーシック生成文法』をご覧下さい。
2009.3.18
 先頃刊行になりました『Hituzi Linguistics in English No.11
Chunking and Instruction
:The Place of Sounds, Lexis, and Grammar in English Language Teaching』の著者の中森誉之先生、来社されました。担当の森脇との記念撮影です。
先頃刊行になりました『Hituzi Linguistics in English No.11
Chunking and Instruction
:The Place of Sounds, Lexis, and Grammar in English Language Teaching』の著者の中森誉之先生、来社されました。担当の森脇との記念撮影です。
今回の来社ではお祝いの酒宴をいたします余裕もなく、この秋に刊行予定の『教える人のための英語学習理論』(仮題)の打ち合わせに来社されました。ユニークでよい本ができそうです。
2009.3.15
 TCP、東京言語心理学会議(Tokyo Conference on Psycholinguistics)の開催が、10周年を迎えました。大津先生から、森脇といっしょに閉会式に参加せよとのおことば。閉会式で私と森脇に花束の贈呈をいただきました。予期していないサプライズです。事務局をつとめてきた村田さんにも花束の贈呈。大津先生のお心遣い、うれしく、感動いたしました。
TCP、東京言語心理学会議(Tokyo Conference on Psycholinguistics)の開催が、10周年を迎えました。大津先生から、森脇といっしょに閉会式に参加せよとのおことば。閉会式で私と森脇に花束の贈呈をいただきました。予期していないサプライズです。事務局をつとめてきた村田さんにも花束の贈呈。大津先生のお心遣い、うれしく、感動いたしました。
東京言語心理学会議(Tokyo Conference on Psycholinguistics)
The Proceedings of the Ninth Tokyo Conference on Psycholinguistics (TCP2008)
2009.3.13
 『日本語の文法カテゴリをめぐって』3月末から4月初旬に刊行いたします。本書は「仁田義雄日本語文法著作選」の第1巻となります。全4巻となります。どうぞ、ご期待下さい。
『日本語の文法カテゴリをめぐって』3月末から4月初旬に刊行いたします。本書は「仁田義雄日本語文法著作選」の第1巻となります。全4巻となります。どうぞ、ご期待下さい。
詳細については、下のリンクをご覧ください。
詳細は以下をご覧下さい。(まだ、ほとんど詳細ではないのですが)『日本語の文法カテゴリをめぐって』
2009.3.12
 『文科系ストレイシープのための研究生活ガイド 心持ち編』(家入葉子著)間もなく刊行します。どうぞ、ご期待下さい。ネットの紹介などでも好評をいただいております『文科系ストレイシープのための研究生活ガイド』の続編です。
『文科系ストレイシープのための研究生活ガイド 心持ち編』(家入葉子著)間もなく刊行します。どうぞ、ご期待下さい。ネットの紹介などでも好評をいただいております『文科系ストレイシープのための研究生活ガイド』の続編です。
詳細については、下のリンクをご覧ください。
詳細は以下をご覧下さい。『文科系ストレイシープのための研究生活ガイド 心持ち編』
2009.3.9
日本学術振興会の刊行助成をいただいて刊行します書籍などが、先週一気に刊行しました。安間先生のご著書は、学振の助成ではありません。タイトルは次の通りです。
Hituzi Linguistics in English No.12
Detecting and Sharing Perspectives Using Causals in Japanese
宇野良子 著
Hituzi Linguistics in English No.13
Discourse Representation of Temporal Relations in the So-Called Head-Internal Relatives
石川邦芳 著
ひつじ研究叢書(言語編) 第68巻
現代日本語のとりたて詞の研究
沼田善子 著
ひつじ研究叢書(言語編) 第69巻
日本語における聞き手の話者移行適格場認知メカニズム
榎本美香 著
Parsing Strategies of Japanese Low-proficiency EFL Learners
安間一雄 著
著者の先生方には、刊行までこぎ着けるまでの過程でたくさんの山や谷を乗り越えて、たどりついたことと存じます。出版社として、お疲れ様ということばとおめでとういうことばをお送り申し上げたいと存じます。本当にお疲れ様でした。若い研究者の方にとってはこれからの研究のスタート地点になることと思います。頑張ってください。
榎本美香先生の著書は、板東が担当し、それ以外の4冊は森脇が担当しました。二人ともお疲れ様です。特に森脇は、怒濤の刊行、お疲れ様です。
2009.3.6
 『文化間移動をする子どもたちの学びー教育コミュニティの創造に向けて』(齋藤ひろみ・佐藤郡衛編)間もなく刊行します。ご期待下さい。
『文化間移動をする子どもたちの学びー教育コミュニティの創造に向けて』(齋藤ひろみ・佐藤郡衛編)間もなく刊行します。ご期待下さい。
詳細については、下のリンクをご覧ください。
目次をアップしましたので、ご覧ください。
詳細は以下をご覧下さい。『文化間移動をする子どもたちの学び』
2009.3.3
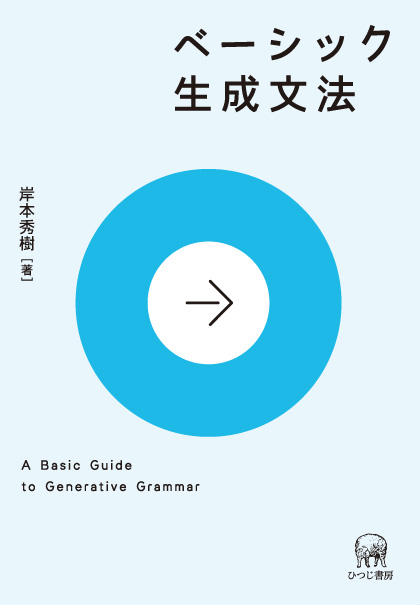 4月から使うべき教科書ですのに、刊行が3月になってしまいまして、申し訳ありません。『ベーシック生成文法』間もなく刊行します。岸本秀樹先生の書き下ろしで、ご自身が授業で試用してみてわかりやすさを追求した内容になっています。類書にない平易な内容です。生成文法が苦手な方も、ご期待下さい。
4月から使うべき教科書ですのに、刊行が3月になってしまいまして、申し訳ありません。『ベーシック生成文法』間もなく刊行します。岸本秀樹先生の書き下ろしで、ご自身が授業で試用してみてわかりやすさを追求した内容になっています。類書にない平易な内容です。生成文法が苦手な方も、ご期待下さい。
詳細については、下のリンクをご覧ください。細間が担当しました。
目次をアップしましたので、ご覧ください。
2009.2.26
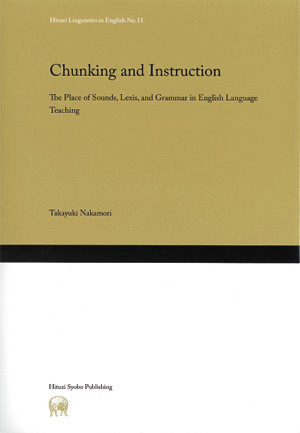 今日は、2月26日、2.26事件の日です。それはともかく、2008年度の年度末シーズンに突入しています。ということで、年度内(2月中)刊行のため、学術振興会研究成果公開促進費にて助成される書籍の刊行が続きます。そのうち、ここで報告しますのは3冊。『Features and Roles of Filled Pauses in Speech Communication』と
『The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English』と
『Chunking and Instruction』の3冊の英文学術書です。表紙の画像は中森先生の表紙を代表して掲示させていただきます。コーヒー牛乳のようで綺麗な色だと思います。フォーマットデザインおよび色の選択はグラフィックデザイナーの向井裕一さん。
今日は、2月26日、2.26事件の日です。それはともかく、2008年度の年度末シーズンに突入しています。ということで、年度内(2月中)刊行のため、学術振興会研究成果公開促進費にて助成される書籍の刊行が続きます。そのうち、ここで報告しますのは3冊。『Features and Roles of Filled Pauses in Speech Communication』と
『The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English』と
『Chunking and Instruction』の3冊の英文学術書です。表紙の画像は中森先生の表紙を代表して掲示させていただきます。コーヒー牛乳のようで綺麗な色だと思います。フォーマットデザインおよび色の選択はグラフィックデザイナーの向井裕一さん。
詳細については、下のリンクをご覧ください。3冊とも、なんと全て森脇の担当です。
The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English
Chunking and Instruction:The Place of Sounds, Lexis, and Grammar in English Language Teaching
2009.2.25

いろいろと出すところまでこぎつけるのが大変でした。できあがりまた書籍を見ると担当者としてひとしおです。大津由紀雄先生、日比谷潤子先生、酒井邦嘉先生、池上嘉彦先生の文章がとても面白いです。大津先生の若い頃の写真もあります。どうぞ手にとってご覧下さい。
2009.2.23
文部科学省の科学技術・学術審議会学術分科会が、「人文学及び社会科学の振興について(報告)」で、報告しているように、学術書籍は、対話と議論によって社会に貢献するものです。
1990年に2月21日にスタートしたということになります。時のたつのははやいものです。来年には、20周年を迎えることになります。新しい学術出版のあり方を提案するのもひつじ書房の使命だと考えています。学術出版の分野で丁寧できちんとした仕事をしてまいります。どうぞご支援下さい。
2009.2.18

田尻悟郎先生に帯のことばをいただきました。ご謙遜で恐れ入りますが、お忙しい中、帯を書いてくださいました。感謝申し上げます。
もうすぐ刊行です。ご期待下さい。
2009.2.17

風がやむとあたたかく、梅見日よりの快晴の中、小石川植物園へ、梅見にでかけました。
2009.2.13
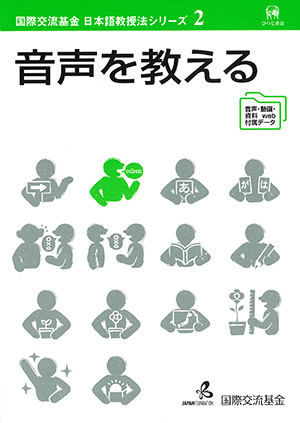

 大坊郁夫・永瀬治郎 編『講座社会言語科学 第3巻 関係とコミュニケーション』、鈴木泰著『ひつじ研究叢書(言語編)第67巻 古代日本語時間表現の形態論的研究』、『国際交流基金 日本語教授法シリーズ 第2巻 音声を教える』を刊行しました。
大坊郁夫・永瀬治郎 編『講座社会言語科学 第3巻 関係とコミュニケーション』、鈴木泰著『ひつじ研究叢書(言語編)第67巻 古代日本語時間表現の形態論的研究』、『国際交流基金 日本語教授法シリーズ 第2巻 音声を教える』を刊行しました。
おわびが多くなってしまいますが、講座は、この3巻でやっと完結しました。たいへんにお待たせいたしました。申し訳ございません。国際交流基金の『音声を教える』は、昨年半ばからずっとお問い合わせいただいておりました。お待たせしておりました。やっとできました。さ来週後半から予約をいただいております書店にはならぶと思います。
言語編の『古代日本語時間表現の形態論的研究』は、鈴木泰先生の代表作になるであろう大著です。どうぞご覧下さい。
『講座社会言語科学 第3巻 関係とコミュニケーション』の詳細
2009.2.6
 刊行が遅れまして、お待たせをいたしております『日本語教育政策ウォッチ2008』まもなく刊行です。
刊行が遅れまして、お待たせをいたしております『日本語教育政策ウォッチ2008』まもなく刊行です。
田尻英三編『日本語教育政策ウォッチ2008』まもなく刊行するべく進めております。2月20日製本でき、流通には翌週に回ります。書店様でご予約いただければ、 3月はじめにはお手元に届くことと存じます。
ひつじ書房は今年言語政策、多言語社会に関わる書籍を多く刊行していきます。その書籍群の先頭を飾ります。本書を含め、その書籍群について、ご期待下さい。
2009.2.4
ひつじ書房では現在、大学での授業用のスペイン語の教科書の企画を進めています。和文と欧文が混在している教科書ということですので、欧文フォントについても、スキルと知識と経験のある方で、この教科書をオペレーターとしても組んでくれるデザイナーを募集します。
1課分のワードデータをお渡ししますので、見本で1課分を作ってください。見本を拝見して、お願いするかどうかを決めます。
実際に仕事をしてもらうことになった場合には、1ページ1000円になります。使用するアプリケーションは、InDesignとします。
応募される方は、seisaku(アットマーク)hituzi.co.jpまで、お問い合わせ下さい。担当者 板東。
2009.2.3

お待たせいたしました。『講座社会言語科学第1巻 異文化とコミュニケーション』重版ができました。
講座社会言語科学シリーズは、まもなく、2月中旬すぎに第3巻『関係とコミュニケーション』(現在印刷中)ができますと、全6巻すべてが刊行されたことになります。2003年夏から順次刊行してきまして5年越のシリーズ完結となります。たいへん、お待たせ致しました。第3巻も刊行しましたらすぐにこの場でお知らせいたしますので、お待ち下さい。どうぞよろしくお願い致します。
『講座社会社会言語科学第1巻 異文化とコミュニケーション』の詳細
講座社会言語科学 全6巻 各3,360円
第1巻 異文化とコミュニケーション 【重版しました】
第2巻 メディア 【発売中】
第3巻 関係とコミュニケーション【近刊】
第4巻 教育・学習 【発売中】
第5巻 社会・行動システム 【発売中】
第6巻 方法 【発売中】
2009.1.29
 『ことばの宇宙への旅立ち2』2月刊行します。鋭意、編集中。編集の終盤です。大津由紀雄先生をはじめ、4名の著名な研究者が、読者をことばの研究の世界を道案内します。
『ことばの宇宙への旅立ち2』2月刊行します。鋭意、編集中。編集の終盤です。大津由紀雄先生をはじめ、4名の著名な研究者が、読者をことばの研究の世界を道案内します。
昨年刊行し好評をいただいております『ことばの宇宙への旅立ち』の続編です。表紙のイラストは、これから、宇宙に旅立つところ。みなさんをことばの宇宙へと誘います。お楽しみに!本書の内容の紹介ページは、近日公開します。お待ち下さい。
表紙カバーを含めたブックデザインは、大崎善治さんです。
2009.1.26
 年賀状代わりに毎年発行していますひつじ新聞2009年新年号のpdfをアップしました。お得意様、著者の方に年賀状として送っています。こちらご覧下さい。
年賀状代わりに毎年発行していますひつじ新聞2009年新年号のpdfをアップしました。お得意様、著者の方に年賀状として送っています。こちらご覧下さい。
2008年の刊行物のご案内と2008年の出来事など、1年の締めくくりとして紹介しています。
2009年の上半期に刊行予定の書籍は、何と50冊以上となっています。言語学、言語教育、多言語多文化、言語政策など、言語学関連分野の刊行物が目白押しです。
2009.1.20
 刊行が遅れまして、たいへん、お待たせをいたしております。ご迷惑をお掛けしております。申し訳ありません。おわび申し上げます。
刊行が遅れまして、たいへん、お待たせをいたしております。ご迷惑をお掛けしております。申し訳ありません。おわび申し上げます。
国際交流基金日本語教授法シリーズ第2巻『音声を教える』やっと2月半ばに刊行いたします。CD-ROM付きで、180ページを越えるものです。音声を教える際の基本的な書籍になると思います。本文が確定しまして、印刷の段階についに入りましたので、もう少しお待ち下さい。
表紙の色を訂正しました。こちらの色が正しい色です。
2009.1.15
 刊行が遅れまして、たいへん、お待たせをいたしております。ご迷惑をお掛けしております。申し訳ありません。
刊行が遅れまして、たいへん、お待たせをいたしております。ご迷惑をお掛けしております。申し訳ありません。
春原憲一郎編『移動労働者とその家族のための言語政策』まもなく刊行するべく進めております。1月末から2月初旬に刊行いたします。
ひつじ書房は今年言語政策、多言語社会に関わる書籍を多く刊行していきます。その書籍群の先頭を飾ります。本書を含め、その書籍群について、ご期待下さい。続いては、間を置かず田尻英三編『日本語教育政策ウオッチ2008』が、刊行になります。どうぞご覧下さいますよう。
2009.1.8
日本語教育学の大坪一夫先生がお亡くなりになりました。名古屋大学、筑波大学、東北大、麗澤大学で日本語教育に関わる弟子を育てられました。ひつじ書房の著者ではいらっしゃいませんでしたが、先生の古希の記念論集を刊行させていただきました。『大学における日本語教育の構築と展開 大坪一夫教授古稀記念論文集』です。ご冥福をお祈り申し上げます。
2009.1.4

2009年は準備の年。21世紀型学術出版のモデルを示すための準備の年にしたい。
抽象的ないい方になってしまうが、そうしたい。21世紀型学術出版のスタイルというからには、20世紀型学術出版のスタイルがあったということであり、それとは違ったスタイルがあるべきであるということを主張したいということでもある。(房主の日誌)
2009.1.1

2008年、お世話になりました。ことしもどうぞよろしくお願い申し上げます。
2008.12.16
定時株主総会開催を開催しました。二人ぼっちの定時株主総会開催でしたが、19期おかげさまで増収増益となりました。昨年に続きまして、単年度黒字です。読者の方、著者の方、書店さん、取次さん、そして株主の方ありがとうございます。こころより御礼申し上げます。
2008.12.14

『国会会議録を使った日本語研究』の編者の松田謙次郎先生が朝日新聞「ひと」に取り上げられました。紹介文の中には、ひつじ書房とは書いてありませんが、書名も紹介されています。
2008.12.12
金澤裕之先生の『留学生の日本語は未来の日本語』が、神奈川新聞にて書評に取り上げられました。
2008.12.8
日本語学の概説書として定番ともされる『日本語要説』の改訂がはじまりました。2009年3月上旬刊行予定で、進行します。
2008.12.5
金澤裕之先生の『留学生の日本語は未来の日本語』が、神奈川新聞にて書評に取り上げられたとのことです。詳細は追って報告します。
2008.12.2

11月30日の日本言語学会で、2008年の主要な学会は、終了しました。もう一つ、第二言語習得研究会に参りますが、その学会を残して終了です。9月のJACET、社会言語科学会、認知言語学会からスタートした秋の学会シーズンも一段落です。
今年の学会は、集客、売上げ的には課題もありましたが、ひとまずというところです。一息つこうかというところで、12月となりまして、年の瀬も近づいて参りました。年賀状代わりのひつじ新聞を作っているところです。あわただしいですね。メール通信を取ってくださっている方には、クリスマスセールを実施中です。どうぞこの機会をお見逃し無く。
2008.11.23

大石泰夫著『芸能の〈伝承現場〉論—若者たちの民俗的学びの共同体』が第二回の本田安次賞を受賞しました。日本民俗芸能学会にて行われました受賞式に参加してきました。おめでとうございます。
『芸能の〈伝承現場〉論—若者たちの民俗的学びの共同体』の詳細
2008.11.21
詳細につきましては、以下の書籍ページをご覧ください。
2008.11.13
 『TCP2008』『中国現代文学2』刊行しました。『TCP2008』は、今週末の英語学会に間に合わせての刊行です。
『TCP2008』『中国現代文学2』刊行しました。『TCP2008』は、今週末の英語学会に間に合わせての刊行です。
『中国現代文学2』は、板東が組みました。今回も綺麗な表紙です。委託せず、注文のみの出荷となりますので、書店でご注文下さいますようお願いします。ジュンク堂三宮店からは見計らい注文をいただきましたので、さ来週には、並びます。他の書店も、追って掲載します。
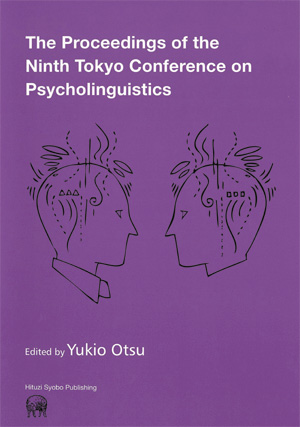
『The Proceedings of the Ninth Tokyo Conference on Psycholinguistics (TCP2008)』の詳細
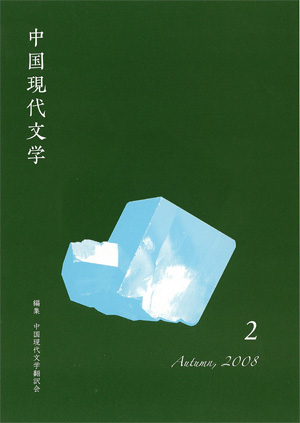
2008.11.11
 『対人行動の日韓対照研究—言語行動の基底にあるもの』の編者であります尾崎喜光先生がお近くに来られたとのことで、事務所に寄って下さいました。
『対人行動の日韓対照研究—言語行動の基底にあるもの』の編者であります尾崎喜光先生がお近くに来られたとのことで、事務所に寄って下さいました。
韓国人は他人に自分のうちの冷蔵庫の中を見てもらっても、日本人ほどには気にしない。携帯を借りて使うのも案外平気など、ちょっと面白い「対人行動」の調査が載っています。R25向きではないかと思っていますが、どうでしょうか。エルゴノミクス、人間工学、環境工学などなど、さまざまな領域の研究者にとって有意義な研究です。
2008.11.10
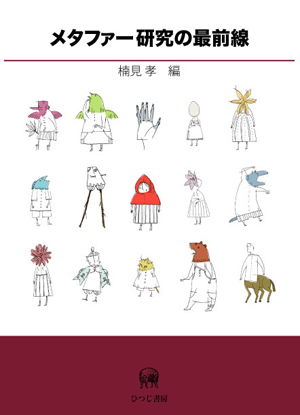 たいへんお待たせいたしました。『メタファー研究の最前線』重版ができました!。研究書で重版ができますことはたいへん希なことと思います。うれしく思います。
たいへんお待たせいたしました。『メタファー研究の最前線』重版ができました!。研究書で重版ができますことはたいへん希なことと思います。うれしく思います。
「かくも多様な興味と方法論によって比喩研究は進められており、その学際性が定着しつつあることが本書によってよくわかる。編者は最終章を次のように締めくくる。「メタファーの認知的研究は、それぞれの学問分野でのこれまでの成果と蓄積を生かし、その自立性を保ちながら、相互に影響し合うリゾナンス(共鳴)によって、いっそう発展すると考える。」評者もまったく同感である。本書はそうした多角的な比喩探求の最前線を概観できる有益かつ楽しい論文集である。」(慶應義塾大学 辻幸夫 大修館書店『言語 vol.37-2』より)
2008.11.4
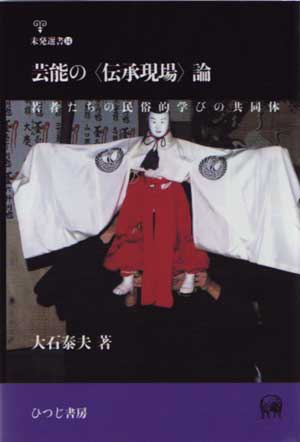 大石泰夫著『芸能の〈伝承現場〉論—若者たちの民俗的学びの共同体』が第二回の本田安次賞受賞しました。大石先生には長い期間にわたります研究に敬意を表しますとともにこころからお祝い申し上げますともに、編集しましたものとして審査に当たられた民俗芸能学会の関係各位に対しまして感謝を申し上げます。おめでとうございます。
大石泰夫著『芸能の〈伝承現場〉論—若者たちの民俗的学びの共同体』が第二回の本田安次賞受賞しました。大石先生には長い期間にわたります研究に敬意を表しますとともにこころからお祝い申し上げますともに、編集しましたものとして審査に当たられた民俗芸能学会の関係各位に対しまして感謝を申し上げます。おめでとうございます。
『芸能の〈伝承現場〉論—若者たちの民俗的学びの共同体』の詳細
2008.10.30
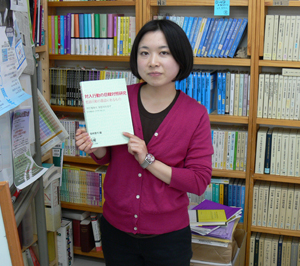 尾崎喜光編『対人行動の日韓対照研究—言語行動の基底にあるもの』刊行しました。読者の方、たいへん、長らくお待たせいたしました。日本語学会・方言研究会にぎりぎりで間に合わせました。
尾崎喜光編『対人行動の日韓対照研究—言語行動の基底にあるもの』刊行しました。読者の方、たいへん、長らくお待たせいたしました。日本語学会・方言研究会にぎりぎりで間に合わせました。
「2001年度から4年間、日韓の言語行動やその背景にあると考えられる対人意識の異同に関する国際共同研究を行なった。日本側は東京都・大阪府、韓国側はソウル・プサンに在住する20代・40代・60代の市民を無作為に抽出し2175人から回答を得た。一般市民を対象とした日韓対照研究ではいまだかつてない規模である。本書はその調査報告書である。分析対象としたデータはCD-ROMにより添付する。」とのこと。
最後、細間が担当しました。カバーも綺麗です。手にとってご覧下さい。
2008.10.27
 森山新著『認知言語学から見た日本語格助詞の意味構造と習得』刊行しました。読者の方、たいへん、長らくお待たせいたしました。
森山新著『認知言語学から見た日本語格助詞の意味構造と習得』刊行しました。読者の方、たいへん、長らくお待たせいたしました。
認知言語学の知見と日本語教育の実践の接点から生み出された本書は、言語学と言語教育学の可能性を示しています。寺村秀夫先生以来、日本語学は日本語教育によって作られてきたものですが、第2局面に入ったと言えるのではないでしょうか。本書は、そのようなエポック的な研究書と言えると思います。日本語教育と日本語学が今後、さらに連携し合って発展していくのかそうではないのかの試金石といえると思います。その意味で、責任重大です。
板東が担当しました。
2008.10.14
山形で開かれました日本語教育学会に間に合わせるべく2冊の本を刊行しました。4月にはでるはずでしたので、おくれにおくれての刊行です。この秋、9冊目の刊行です。お待ち下さっていた読者の方、書店の方、まことに申し訳ありません。こころよりおわび申し上げます。
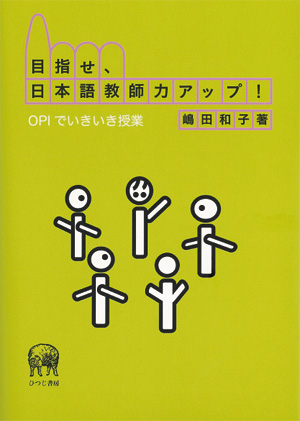 『目指せ、日本語教師力アップ!』は、非常に画期的な本です。日本語教育の世界では、アルクの『月刊日本語』をはじめとして、これから日本語教師になるという未経験者にとっての情報提供はとても多いのですが、経験をある程度積み重ねた人が、さらに頑張ろうと思って研修しようとした時に学べるモノがほとんどないという状況があります。それに対して本書は超ベテランの嶋田先生が、中堅になりかけている教師に具体的にアドバイスするという内容です。
『目指せ、日本語教師力アップ!』は、非常に画期的な本です。日本語教育の世界では、アルクの『月刊日本語』をはじめとして、これから日本語教師になるという未経験者にとっての情報提供はとても多いのですが、経験をある程度積み重ねた人が、さらに頑張ろうと思って研修しようとした時に学べるモノがほとんどないという状況があります。それに対して本書は超ベテランの嶋田先生が、中堅になりかけている教師に具体的にアドバイスするという内容です。
これは真に求められている内容でしょう。このようなベテランが新人ばかりではなく、中堅を指導できる体制を作るということも日本語教育にとっての重要な可能性ではないでしょうか。
『目指せ、日本語教師力アップ!』の詳細

さらにこちらも画期的な本ではないでしょうか。思えば、元留学生であった楊逸さんが芥川賞をとった時代にふさわしい新刊です。仮に日本語少し変、ということがあったとしても、それは日本語の可能性を広げることであるはず。そんな作家が芥川賞をとったというタイミングでの刊行。芥川賞といっしょに刊行できればよかった。おわび申し上げます。
『留学生の日本語は、未来の日本語』の詳細
これらの本をひっさげての山形入りでした。しかし、初日は本が売れず……。行ってみたら、複合施設でした。複合施設は、市民会館とデパートの融合で人が集まり、商業も活性化するための場所のはず。そこで、商売が禁止されているとは。
2008.10.08
 秋の『未発』ができあがりました。表紙のカラーは、なんともいえない素敵なグリーンです。涼しい季節になり、『未発』の色まで涼しげです。
秋の『未発』ができあがりました。表紙のカラーは、なんともいえない素敵なグリーンです。涼しい季節になり、『未発』の色まで涼しげです。
 できあがった『未発』をみなさんにお届けするために、ひつじ書房では発送という大仕事に取り組んでいます。たくさんの人手が必要なので、いつものひつじメンバーに加えて、たくさんの人が手伝ってくれています。みなさん表情が真剣です。自分に与えられた作業をこなしているのです。もうすぐお手元に、きれいな色の『未発』が届くと思いますので、楽しみにしてください。そして、新しく出た本やこれから刊行されるものをぜひチェックしてみてください。
できあがった『未発』をみなさんにお届けするために、ひつじ書房では発送という大仕事に取り組んでいます。たくさんの人手が必要なので、いつものひつじメンバーに加えて、たくさんの人が手伝ってくれています。みなさん表情が真剣です。自分に与えられた作業をこなしているのです。もうすぐお手元に、きれいな色の『未発』が届くと思いますので、楽しみにしてください。そして、新しく出た本やこれから刊行されるものをぜひチェックしてみてください。
2008.9.22
 認知言語学会には間に合いませんでしたが、児玉先生小山先生のご尽力もあり、大著『言葉と認知のメカニズムー山梨正明教授還暦記念論文集ー』をついに刊行しました。「京都大学において氏の指導を受けた教え子を中心とする43名が寄稿し、編集された記念論文集」。若手による認知言語学の可能性の追求といえましょう。担当は、森脇です。
認知言語学会には間に合いませんでしたが、児玉先生小山先生のご尽力もあり、大著『言葉と認知のメカニズムー山梨正明教授還暦記念論文集ー』をついに刊行しました。「京都大学において氏の指導を受けた教え子を中心とする43名が寄稿し、編集された記念論文集」。若手による認知言語学の可能性の追求といえましょう。担当は、森脇です。
『言葉と認知のメカニズムー山梨正明教授還暦記念論文集ー』詳細はこちら。
京都のリーガロイヤルホテルで開かれました還暦のお祝いのパーティに編集長と森脇が参加してきました。会は、歌舞音曲まで、入り乱れて楽しい集まりでした。今の時代、60歳というのは、折り返し点なのですね。これからも、ご活躍下さい。
2008.9.18
 お彼岸の時期、最後の残暑と秋に入り立ての時期に地面から、にょきと不思議に咲く花、ヒガンバナが咲きました。今、小石川植物園ではヒガンバナが咲いています。まだ、6部、咲きくらいでしょう。たぶん来週の前半が、満開となるのではないでしょうか。本当に不思議な花です。写真撮影は、板東です。
お彼岸の時期、最後の残暑と秋に入り立ての時期に地面から、にょきと不思議に咲く花、ヒガンバナが咲きました。今、小石川植物園ではヒガンバナが咲いています。まだ、6部、咲きくらいでしょう。たぶん来週の前半が、満開となるのではないでしょうか。本当に不思議な花です。写真撮影は、板東です。
 こちらは、『「議論」のデザイン』です。やっと刊行にいたりました。思いの外、時間がかかってしまいました。お待ち下さっていた方、長い間お待たせいたしました。関西大学総合情報学部の牧野由香里先生の「議論学」自体の創出を目指した挑戦的な力作です。
こちらは、『「議論」のデザイン』です。やっと刊行にいたりました。思いの外、時間がかかってしまいました。お待ち下さっていた方、長い間お待たせいたしました。関西大学総合情報学部の牧野由香里先生の「議論学」自体の創出を目指した挑戦的な力作です。
コミュニケーション研究と教育工学の接点に位置する議論のデザインをめぐる488ページにわたる大著です。議論自身を巡る様々な議論そのものが、この本から始まることになるのではないでしょうか。最後の締めは、板東が行いました。デザインは伊高純子さんです。
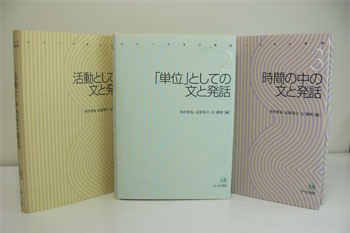 『文と発話 第2巻』刊行しました。これで、シリーズ文と発話、3巻完結です。談話研究の金字塔といえますし、この3巻によって、これからいっそう、この研究ジャンルの研究が盛んになることでしょう。担当は、森脇です。
『文と発話 第2巻』刊行しました。これで、シリーズ文と発話、3巻完結です。談話研究の金字塔といえますし、この3巻によって、これからいっそう、この研究ジャンルの研究が盛んになることでしょう。担当は、森脇です。
本当は社会学、自然言語処理、言語哲学などの研究者にも読んでもらいたいと思っています。紹介してくだされれば、興味を持ってもらえる内容だと思うのですが。全国紙で書評を載せてくれないでしょうか。さて、「ことばに魅せられて」のYouTubeのPVへのアクセスが1000アクセス越えました。これは快挙です。
2008.9.12
 7月、8月と刊行ができずにおりました。秋の学会を目指して、次々と刊行していきます。お待たせいたしました『講座社会言語科学4巻』、『認知言語学論考 No.7』、『レキシコンフォーラム No.4』、『イメージスキーマに基づく格パターン構文』ができてまいりました。『文と発話 第2巻』も、社会言語科学会には間に合いませんでしたが、来週、刊行します。
7月、8月と刊行ができずにおりました。秋の学会を目指して、次々と刊行していきます。お待たせいたしました『講座社会言語科学4巻』、『認知言語学論考 No.7』、『レキシコンフォーラム No.4』、『イメージスキーマに基づく格パターン構文』ができてまいりました。『文と発話 第2巻』も、社会言語科学会には間に合いませんでしたが、来週、刊行します。
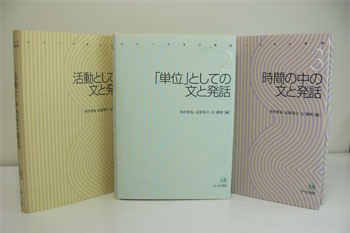 『文と発話』、やっとですが、3巻完結。
『文と発話』、やっとですが、3巻完結。
ふうふういいながら、本を作っています。9月末、10月頭にできます本もたくさんあります。
『言葉と認知のメカニズム』、『議論のデザイン』(牧野由香里)、『留学生の日本語は未来の日本語』(金澤裕之)、『目指せ、日本語教師力アップ!』(嶋田和子)、『対人行動の日韓の対照研究—言語行動の基底にあるもの』(尾崎喜光他)、認知言語学から見た日本語格助詞の意味構造と習得、『中国現代文学2』なんと沢山!
イメージ・スキーマに基づく格パターン構文 -日本語の構文モデルとして
2008.9.4
ひつじ書房で刊行しました『国会会議録を使った日本語研究』が、『日本語学』9月号の書評欄に登場です。詳細はこちら
国研の田中牧郎先生に紹介していただきました。
国会会議録を様々なアプローチによって研究し、研究資源として「使ってみせ」、また情報化時代の新しい研究態勢を示した研究書として、本書を高く評価していただきました。
2008.8.25
 ひつじ書房は、本郷、東大正門から5分の旅館「つたや」で2008年の夏合宿を行いました。2003年から、夏と冬に行っている合宿です。12回目の合宿。
ひつじ書房は、本郷、東大正門から5分の旅館「つたや」で2008年の夏合宿を行いました。2003年から、夏と冬に行っている合宿です。12回目の合宿。
秋からはじまる来年の春に刊行します本作りへの作戦会議です。
2008.8.21
 ひつじ書房で使用している電話機を、家庭用電話機からビジネスフォンに変えました。2001年に神保町から茗荷谷に移動して以来、電話機は家庭用の電話機を使ってきましたが、7年ぶりにビジネスフォンに変更しました。昨日までとは違う呼び出し音が飛び交っています。ルルルルル。
ひつじ書房で使用している電話機を、家庭用電話機からビジネスフォンに変えました。2001年に神保町から茗荷谷に移動して以来、電話機は家庭用の電話機を使ってきましたが、7年ぶりにビジネスフォンに変更しました。昨日までとは違う呼び出し音が飛び交っています。ルルルルル。
最新機種で、子機はみな、携帯タイプの持ち運びができるものです。書店さんから電話を受けながら、棚に言って在庫を確認したり、内容を確認して応答することができます。これまでは、家庭用電話機を2回線つかっていましたが、それぞれのラインにはとばせませんでしたので、手渡し(!)していました。
家庭用電話機ではできないことがいろいろとできそうです。導入したのはNEC AspireXです。6年リースですが、ひつじ書房のような10名未満の零細企業にとって使いやすいモノでしょうか。使いやすいとよいのですが。
2008.8.19
ひつじ書房で刊行しました『国会会議録を使った日本語研究』が、8月17日の読売新聞朝刊の書評に掲載されました。詳細はこちら
国会会議録データベースの「お宝性」と、それを正しく利用するための手引きとしての本書の有効性について、メディア社会学者である佐藤卓己氏にご紹介いただきました。
2008.8.6


大津先生より、とてもすてきな贈り物をいただきました。「揺れひつじ」に続きまして、「まるひつじ」です。暑さの中、雷、大雨もつづきますが、この夏を乗りきる「癒し系」となること間違いありません。
大津先生、ありがとうございました。
2008.7.25
 松田陽子先生(兵庫県立大学)の『多文化社会オーストラリアの言語教育政策』が豪日交流基金の出版助成を得られることになりました。正式な名称は、オーストラリア政府豪日交流基金サー・ニール・カリー奨学金です。たいへん、ありがたく栄誉のあることと思います。本日は、その受賞式に参加してきました。この書籍は今年度中に刊行することをめざしています。
松田陽子先生(兵庫県立大学)の『多文化社会オーストラリアの言語教育政策』が豪日交流基金の出版助成を得られることになりました。正式な名称は、オーストラリア政府豪日交流基金サー・ニール・カリー奨学金です。たいへん、ありがたく栄誉のあることと思います。本日は、その受賞式に参加してきました。この書籍は今年度中に刊行することをめざしています。
2008.7.16

ひつじ書房では、IPAフォント作成中を作成中です。既存のIPAフォントが、Timesに合う書体しかありませんでした。そのため、ひつじ書房で書籍を作る場合に使っていますcaslonに合わせることが困難でありました。そこでcaslonに合うIPAフォントを作ってもらっています。
この書体のかたちについて、ご意見をお寄せ下さいましたら幸いです。
2008.7.11

ひつじ書房でGIFアニメを作成中です。
ご意見をお寄せ下さい。
2008.6.28

ひつじ書房で刊行しました『国会会議録を使った日本語研究』の編者の松田先生がお越しになりました。「国会会議録」は、過去60年にわたる、出身・在外歴までほぼ判明している日本各地出身者による議論を文字化した資料で、世界に誇るべき言語資料(政治資料でもある)です。
PVも作りました。詳細でご覧下さい。
詳細はこちら。『国会会議録を使った日本語研究』
2008.6.20
ひつじ書房で刊行しました『ことばに魅せられて』(大津由紀雄著 え 早乙女民)のプロモーションビデオができました。YouTubeから、本日、公開します。リンクをお願いします。どうぞご覧下さい。Art Direction & Designは、畑中宇惟さんです。
2008.6.17

ワークショップ「社会に参加していく市民としての言語教育」開催のお知らせをアップロードいたしました。ワークショップは、7月2日開催です。
講師
佐藤慎司(さとうしんじ)
熊谷由理(くまがいゆり)
深井美由紀(ふかいみゆき)
概要:本ワークショップではクリティカルリテラシーという用語をキーにその理論的な背景を簡単に振り返った後、日本語教育における3つの実践例を紹介したい。1)教科書に提示される「カタカナ=外来語」という規範について批判的に考察し、調査することで日本語の文字使いの流動性に気付くことを目的とするカタカナプロジェクト、2)日本語の教科書を批判的に読み、実際の教科書の書き直し、調査研究を行う教科書書き換えプロジェクト、3)メディアを批判的にとらえ、ポッドキャストを作成し発信するポッドキャストプロジェクトである。本ワークショップは日本語/外国語教師のみならず、異文化間コミュニケーション、多文化教育に興味のある教師、研究者も対象にしており、言語教育でふだん忘れられがちな、社会に参加していく一市民としての教育という側面に焦点を当てる。
詳細はこちら。社会に参加していく市民としての言語教育
2008.6.5

第21回メディアとことば研究会のポスターを作成し、第21回メディアとことば研究会開催のお知らせの情報をアップロードいたしました。
発表者名:佐竹秀雄(武庫川女子大学言語文化研究所長)
タイトル:新聞における投書表現の分析−付録:ことば研究の方法と立
場−
発表内容:新聞における投書を調査対象として、その内容と表現スタイルとの間にどのような関係が見られるかについて、計量言語的な視点から分析した。投書を内容によって公的なものと私的なものとに分類し、両者が、品詞比率、語種比率、文の長さ、字種比率などの点でどのように異なるのかを調査した。その結果について発表する。また、この調査研究を踏まえて、ことばを研究するに際して、どういう点に留意し、何を目指すべきかについての私見を述べたい。
発表者名:三宅和子(東洋大学文学部日本文学文化学科教授)
タイトル:メディアへの視線をどう研究に位置づけるか-研究の射程と方法論をめぐって-
キーワード:
マスメディア、パーソナルメディア、CMC、方法論、ジャンル、モードの多層性
概要:
2007年度に国外研究で滞英し、ことばとメディアをめぐる国際学会・研究会に複数参加した。本発表は欧英の
言語系メディア研究・学会の動向を出発点に、メディアに注目した言語研究が切り拓いていく世界を考えたい。
現在、「メディア」で括られ語られ研究される対象は多岐にわたる。従来からあるマスメディア(新聞、雑誌、
テレビなど)の研究に、近年発展の著しい電子メディアを中心としたパーソナルメディア(PC、ケータイ、電話
など)の研究が増加しているというのが大雑把な図式だが、さらに文字・視覚メディアと音声メディア、道端の
看板やサイン、道路標識などに至るまで多種多様な研究が存在する。際限なく拡散していきそうな対象領域とテ
ーマを言語系メディア研究がつなぎとめる礎として、「メディアそのものへの視線」を意識することの重要性を
強調したい。すなわち、当該のコミュニケーションが行われる場としてのメディアとその特性への鋭く執拗な視
線である。メディアを介することにより、どのようなものが生み出され、どのようなものが失われているのかと
いう視点である。それなくしては、例えばCMC研究と称しても、単に新しい場
と材料を獲得して従来通りの言語研究を行っているに過ぎない。新しい場の特性を注視することにより、従来
の言語研究では見えにくかったコミュニケーションの側面を炙り出すことができるのではないだろうか。
どうぞふるってご参加下さい。
2008.5.26
 松田謙次郎先生たちの研究書、『国会会議録を使った日本語研究』、まもなく刊行します。表紙は、帝国議会の錦絵を使いました。憲政記念館よりお借りし、使用許可をとったものです。速記者も描かれていて、さらに発言するために手をあげる議員なども描かれている臨場感あるものです。
松田謙次郎先生たちの研究書、『国会会議録を使った日本語研究』、まもなく刊行します。表紙は、帝国議会の錦絵を使いました。憲政記念館よりお借りし、使用許可をとったものです。速記者も描かれていて、さらに発言するために手をあげる議員なども描かれている臨場感あるものです。
企画・内容編集担当は松本で、カバーデザインは新人の板東が担当しました。
2008.5.26
 2008年春の日本語学会に出展しました。首都大学のキャンパスで、あいにく雨降りでしたが、土砂降りではなくてよかった。
2008年春の日本語学会に出展しました。首都大学のキャンパスで、あいにく雨降りでしたが、土砂降りではなくてよかった。
『教材開発』『日本語スタンダード試案 語彙』『ことばに魅せられて』の3冊を金曜日に間に合わせて作りました。3冊一挙のデビューとなりました。
2008.5.21
 2008年春の日本語学会に出展しました。日本大学文理学部のキャンパスで、緑の綺麗な気持ちのよい会場でした。
2008年春の日本語学会に出展しました。日本大学文理学部のキャンパスで、緑の綺麗な気持ちのよい会場でした。
1日目は、会場が狭く、机が1つしかつかえませんでしたが、2日めは発表会場から少々遠くて客足は今ひとつであったのですが、机を3列並べて、本を展示することができました。新人二人を連れての学会出店でした。
シンポジウムは、私にとっては面白いものでした。方言のシンポにでましたが、方言とこころの研究について触れた佐藤先生の発表が啓発的であったと思います。2日目はあまり準教授クラスの発表が少なく、少し寂しいと感じました。中堅どころの発表があると充実するからです。一方、盛況であったとも聞いていますので、若手の研究会としてはよかったのかもしれません。春の第一弾を乗り切りました。今週末は日本語教育学会です。
2008.5.19
 『ことばに魅せられて 対話篇』間もなく刊行となります。先日は、イラスト・装幀をしてくれた早乙女民さんが、用紙の選定のために来社されました。
『ことばに魅せられて 対話篇』間もなく刊行となります。先日は、イラスト・装幀をしてくれた早乙女民さんが、用紙の選定のために来社されました。
早乙女民さんは『探検!ことばの世界』につづいて、大津由紀雄先生とのコラボレーションです。素敵なマンガふうのイラストも本書の楽しみの大きな部分です。
2008.5.10
 『国会会議録を使った日本語研究』間もなく刊行とのことで、憲政記念館に行ってきました。国会会議録は、帝国議会からはじまり今に続いて行われている国会での議論の談話テキストデータベースです。
『国会会議録を使った日本語研究』間もなく刊行とのことで、憲政記念館に行ってきました。国会会議録は、帝国議会からはじまり今に続いて行われている国会での議論の談話テキストデータベースです。
帝国議会時代の錦絵を表紙に使おうと考え、錦絵を所蔵している憲政記念館に行って使用の手続きをしました。

2008.4.29
研究成果公開促進費の今年の内定をいただいた書籍をお知らせします。採択された先生方はおめでとうございます。来年の2月までに書籍にするために頑張って参ります。
2008.4.28
 『日本語の文章理解過程における予測の型と機能』を刊行しました。担当は松本です。人は話を聞くとき、相手の話がどう進んでいくのかを予測しながら聞いています。予測文法というのはどういう機能なのかという点は、長年の課題であったといってよいでしょう。本書は、読解という点に焦点をあてて、その予測文法を大きく解き明かしていく待望の書籍です。
『日本語の文章理解過程における予測の型と機能』を刊行しました。担当は松本です。人は話を聞くとき、相手の話がどう進んでいくのかを予測しながら聞いています。予測文法というのはどういう機能なのかという点は、長年の課題であったといってよいでしょう。本書は、読解という点に焦点をあてて、その予測文法を大きく解き明かしていく待望の書籍です。
詳細は、次をご覧下さい。『日本語の文章理解過程における予測の型と機能』石黒圭 著
2008.4.25
 『ここからはじまる文章・談話』を刊行しました。担当は森脇です。携帯であるとかブログであるとか、現代社会の文章・談話は著しく変化を遂げつつある。一方、電子媒体によって現れたと思われている絵文字は、もともと江戸時代からあったものでもある。新しさと意外な伝統。文章・談話のいろいろと面白い局面を授業で取り扱い、日本語を研究する入り口となる本。そのまま読んでも面白い。ここからはじまるシリーズの最新刊。
『ここからはじまる文章・談話』を刊行しました。担当は森脇です。携帯であるとかブログであるとか、現代社会の文章・談話は著しく変化を遂げつつある。一方、電子媒体によって現れたと思われている絵文字は、もともと江戸時代からあったものでもある。新しさと意外な伝統。文章・談話のいろいろと面白い局面を授業で取り扱い、日本語を研究する入り口となる本。そのまま読んでも面白い。ここからはじまるシリーズの最新刊。
詳細は、次をご覧下さい。『ここからはじまる文章・談話』高崎みどり・立川和美 編
2008.4.18
 『コミュニケーション育成教育再考』は言語教育で中心的な考え方となっているコミュニカティブという考え方の提唱者でもあるウィドーソンの教え子たちである研究者たちが、編んだ研究論文集です。文法主体ではなくコミュニケーションできる言語教育と言ったとき、目指されるものは本当は何であったのか。コミュニカティブということ自体を振り返る必要性があるのではないのか。担当は松本です。
『コミュニケーション育成教育再考』は言語教育で中心的な考え方となっているコミュニカティブという考え方の提唱者でもあるウィドーソンの教え子たちである研究者たちが、編んだ研究論文集です。文法主体ではなくコミュニケーションできる言語教育と言ったとき、目指されるものは本当は何であったのか。コミュニカティブということ自体を振り返る必要性があるのではないのか。担当は松本です。
言語教育から、批判的談話分析(CDA)をも含む。
詳細は、次をご覧下さい。『コミュニケーション能力育成再考』村田久美子・原田哲男編著
 『学びのエクササイズ日本語文法』は、日本語文法の分かりやすく取っつきやすい教科書。日常的に面白く、かつ日本語の仕組みを考える時に重要なことがらを解き明かしていきます。担当は松本です。
『学びのエクササイズ日本語文法』は、日本語文法の分かりやすく取っつきやすい教科書。日常的に面白く、かつ日本語の仕組みを考える時に重要なことがらを解き明かしていきます。担当は松本です。
詳細は、次をご覧下さい。『学びのエクササイズ日本語文法』天野みどり 著
2008.4.10

『中国現代文学1』刊行しました。中国現代文学翻訳会が、翻訳した中国の現代文学のアンソロジーです。「18年続いた『季刊中国現代小説』の停刊から2年8ヵ月。新たなメンバーのもと、装いも新たに、同時代の中国文学を紹介する翻訳誌が創刊」されるものです。書店にて注文できますので、どうぞお求めください。
装幀は、ひつじ書房のスタッフでもある板東(写真中央)が、行いました。組版も彼女がおこなったものです。覚えていらっしゃいますでしょうか、ひつじ書房のトップページにてこの本の装幀者を募集しておりました。それに募集してくれたことが、スタッフになるきっかけでした。2人は、ひつじ書房のニューフェースです。

『中国現代文学1』中国現代文学翻訳会 編
2008.4.2

阿部潤先生の『問題を通して学ぶ 生成文法』刊行しました。生成文法は、文法研究において共通語のようになっているところもあります。その意味で、理論的に賛成するか否かを越えて、その術語や考え方や操作方法について理解しておくことが必要と言えるのではないでしょうか。この意味で、生成文法自体を極めたい方はもちろん、生成文法のテクニックを知りたい方にも有益な本となっています。実際に問題を解きながらツリーの書き方をマスターすることができます。
装幀は、本書がはじめての近藤祐子さん。線のタッチが、とても印象的で、綺麗な、新人の装幀デザイナーです。書店で注文が出来るようになりますのは、4月半ばからです。
『問題を通して学ぶ 生成文法』阿部潤著
2008.3.24

東京女子大学で開催されました社会言語科学会にひつじ書房は、出展しました。桜もちらほら咲き出している折ですが、まだ寒い中、西荻まで行ってきました。今回の新刊のいくつかをピックアップします。
『ことば・空間・身体』 篠原和子・片岡邦好 編
『メディアとことば 3』 岡本能里子・佐藤彰・竹野谷みゆき 編
『ニュータウン言葉の形成過程に関する社会言語学的研究』朝日祥之 著
『日本語会話における言語・非言語表現の動的構造に関する研究』坊農真弓著
2008.3.20
ひつじ書房は、昨年の6月より、私を入れまして5名の編集部体制で進めて参りましたが、3月20日をもちまして、3名が退社いたしますことになりました。これから、しばらくは、編集長の松本と森脇の2名で本を編集してまいります。退社しますものが担当しておりました書籍は、担当者からご連絡をしておりますが、松本が引き継ぎますので、今後は松本までご連絡下さい。また、これまで著書を出された方で、今後の連絡先が分からないという場合は、どうぞご遠慮なく、松本功までご連絡下さい。
2008.3.19
 お待たせいたしました。『メディアとことば3』刊行となりました。21日のメディアとことば研究会第20回には、お目見えします。
お待たせいたしました。『メディアとことば3』刊行となりました。21日のメディアとことば研究会第20回には、お目見えします。
2008.3.15
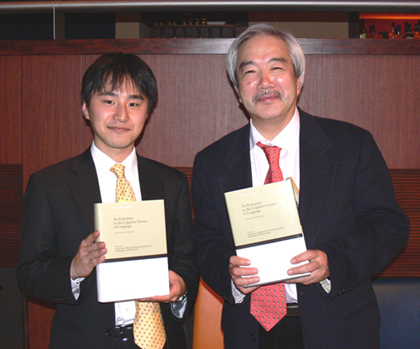 編者の佐野哲也・遠藤美香・磯部美和・大滝宏一・杉崎鉱司・鈴木猛先生の尽力によりまして『An Enterprise in the Cognitive Science of Language』が、刊行となりました。担当は森脇です。
編者の佐野哲也・遠藤美香・磯部美和・大滝宏一・杉崎鉱司・鈴木猛先生の尽力によりまして『An Enterprise in the Cognitive Science of Language』が、刊行となりました。担当は森脇です。
本書は、A Festschrift for Yukio Otsuとのことで、50名近い研究者からの論文が集結しています。Stephen Crain, Nina Hyams, Thomas Roeper, William Snyderら海外からの寄稿も含まれています。ぎりぎり14日にできてしまして、15日に無事お渡しすることができました。内容も優れたものですが、書籍としてもかなりしっかりしたものとなっております。

『An Enterprise in the Cognitive Science of Language』の詳細はこちら。
2008.3.13
 阿部潤先生著の『問題を通して学ぶ 生成文法』が、まもなく刊行となります。担当は松本功(編集長)です。
阿部潤先生著の『問題を通して学ぶ 生成文法』が、まもなく刊行となります。担当は松本功(編集長)です。
生成文法の考え方、方法について、問題を通して学びます。学問には考え方という面とやり方という側面の両方がありますが、やり方についてもプロセスをきちんと作って学んでいきことができます。自習したい方、生成文法の使い方を知りたい方にとてもよい入門書になっていると思います。
3月末刊行の予定です。
2008.3.10
 たいへん、長らくお待たせいたしました。『ことば・空間・身体』がまもなく刊行となります。たびたびの遅れにてまことに申し訳ありませんでした。
たいへん、長らくお待たせいたしました。『ことば・空間・身体』がまもなく刊行となります。たびたびの遅れにてまことに申し訳ありませんでした。
「日本英語学会第21回大会のワークショップをもとに、認知言語学、心理学、言語人類学的視点から空間概念の構築/移転/拡張を扱った論文集。空間・時間表現の言語分析にとどまらず、メタファー、ジェスチャー、談話なども射程に収め、身体を通しての空間的経験を基盤とする言語現象、言葉に伴う身体現象などを、さまざまなアプローチによって総合的に考察する。」とのことで、日本では少ない言語人類学的な研究論文を集めたものです。
社会言語科学会にお目見えの予定です。
2008.3.7
 お待たせいたしました。『メディアとことば3』まもなく刊行となります。メディアとことば研究会第20回には、お目見えする予定です。
お待たせいたしました。『メディアとことば3』まもなく刊行となります。メディアとことば研究会第20回には、お目見えする予定です。
言語研究とメディア研究の接点ともいえるメディア言語研究の臨界的研究誌です。言語研究の中でもピュアな伝統的言語学にとどまらず、言語人類学、応用言語学、語用論、クリティカルディスコースアナリシス、談話分析から、言語学を越えて政治学、社会学、メディア論、新聞研究、出版研究、文化人類学、民俗学、テキスト研究、加えてデザイナーや編集者、イラストレーターなどの実務家にまで広く関わるユニークな研究誌です。
3集の特集は「社会を構築することば」ということで、社会を作り上げていることばの諸相を研究します。社会構築主義とはあまり関係はありません。
2008.3.5
 『ニュータウン言葉の形成過程に関する社会言語学的研究』の著者の朝日祥之先生がお越しになりました。その後、ご一献いたしました。
『ニュータウン言葉の形成過程に関する社会言語学的研究』の著者の朝日祥之先生がお越しになりました。その後、ご一献いたしました。
概要は次の通り。「都市計画のもとに全国各地で建設が進んでいるニュータウンを取り上げ、移住者が持ち込んだ方言間の接触によって生まれるニュータウン言葉の形成過程を、社会言語学の見地から考察したもの」「神戸市にある西神ニュータウンをフィールドとし、2年半にわたる現地調査で収集したデータを用いながら、ニュータウン居住者による言語使用実態とニュータウンで使われている言葉の認知の在り方について、分析を行な」い、「ニュータウン言葉の形成過程を構築した。」
2008.3.3
シリーズ言語学と言語教育『第二言語としての日本語教室における「ピア内省」活動の研究』(金孝卿著)/『非母語話者日本語教師再教育における聴解指導に関する実証的研究』(横山紀子著)/『『異文化間コミュニケーションからみた韓国高等学校の日本語教育』(金賢信著)。ひつじ研究叢書(言語編)の『日本語会話における言語・非言語表現の動的構造に関する研究』(坊農真弓著)を刊行しました。
2007年度は、研究成果公開促進費による刊行は、9冊。それらをすべて刊行し終わりました。
2008.2.28
 あたたかく、日差しの柔らかな、春らしいよい気候となりました。シリーズ言語学と言語教育『日本語eラーニング教材設計モデルの基礎的研究』の著者の加藤由香里先生がおこしになりました。担当は森脇でした。
あたたかく、日差しの柔らかな、春らしいよい気候となりました。シリーズ言語学と言語教育『日本語eラーニング教材設計モデルの基礎的研究』の著者の加藤由香里先生がおこしになりました。担当は森脇でした。
ひつじ書房の事務所の近くのTipsy'sでささやかな刊行のお祝いをいたしました。本の刊行のお手伝いができまして、幸いでした。ありがとうございます。
本書の詳細は、次のページをご覧下さい。
『日本語eラーニング教材設計モデルの基礎的研究』へ。
2008.2.27
年度内(2月中)に刊行する科研費「研究成果公開促進費」による刊行がはじまりました。最初の半分は、ひつじ研究叢書(言語編)『韓日新聞社説における「主張のストラテジー」の対照研究』、『ドイツ語再帰構文の対照言語学的研究』、『狂言台本とその言語事象の研究』、『ニュータウン言葉の形成過程に関する社会言語学的研究』、シリーズ言語学と言語教育『日本語eラーニング教材設計モデルの基礎的研究』の5冊です。
これらが、刊行になりました。あと4冊は今週末に刊行になります。一番搾りの本で、学術振興会に提出しますので、お求めになれますのは、3月初旬からです。
2008.2.25
このたび、ひつじ書房のテキストサポートページのサイトを移転することとなりました。
これまでは「moodle」というeラーニング用のサービスを使用していましたが、機能が複雑で使いこなすことが難しかったため、web上でプロジェクト管理をするサービスへ移行します。これまでよりもシンプルにヒントを閲覧することができることになります。
移転先のサポートページは、2月25日より開設いたします。現在までのサポートページをご利用下さっている先生方にはすでにお知らせをしておりますが、もし、連絡が来ていないとのことがありましたら、ご連絡下さい。
大変ご不便をおかけいたしますが、なにとぞご容赦いただけますようお願い申し上げます。
2008.2.21
ひつじ書房は創業18年を迎えました。これも、みなさまがたの日頃のご愛顧のおかげと存じ、こころより御礼申し上げます。人間ならば、高校を卒業するという年齢になった、ということだと思います。これから大学生になるという次のステップへ進む時であります。言語学、言語教育学という分野にいっそう邁進していきたいと思います。
19年目に入ります。20年も遠くありません。困難の中でもへこたれないで、一歩一歩歩んで参りたいと思います。
もとより、不完全、未熟でありますことを日々実感しております。今後ともどうぞご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
房主 松本功
2008.2.1
ひつじ書房では、新刊の案内を「ひつじだより」というファックスレターにて、全国200軒の書店様にお送りしています。ご注文いただいて出荷の際の条件は「返品条件付き」と言われるものです。書店の方が「ひつじだより」をご覧下さり、置いてみようと積極的に取り扱っていただいているものにつきましては、返品が可能という条件で出荷しています。返品については期限は全くありません。
ただし、戻していただきます際には「ひつじだより」に明記してあります返品了解者の名前を書いていただくようお願いしています。この了解者名が書いてありましたら、返品の期限は全くありません。半年以内に返さないと返品を受け取らない、ということはございません。
半年後でも1年後でも10年後でも返品は受け取ることにしています。了解者名を書いていただくということは煩雑な手続きと思われるかも知れませんが、原則として注文については、このことをお願いしておりますので、ご理解いただければと存じます。
フリー入帖の方が、簡単であるのは理解しておりますが、学術書を出版しております立場からしますと、客注品の返品などは、無条件に何でも受け取るということはできません。このことは、学術書などは少ない部数でもありますので、1冊1冊を丁寧に販売することで経営をなりたたせている小社にとって、最低限のルールは必要と考えておりますので、なにとぞご理解のほどお願い申し上げます。
なお、「ひつじだより」につきまして、ご希望の書店様にはファックスでお送りいたしますので、どうぞご連絡下さい。ひつじだより見本
試しにおいてみようという場合は注文条件付きで出荷しますので、どうぞ私たちにご連絡下さいますようお願いします。
2008.1.27
 7月に刊行しました中村桃子先生の『「女ことば」はつくられる』が、本年度27回「山川菊栄記念婦人問題研究奨励金」(通称「山川菊栄賞」)を受賞し、田町「女性と仕事の未来館」にて授賞式が開かれました。
7月に刊行しました中村桃子先生の『「女ことば」はつくられる』が、本年度27回「山川菊栄記念婦人問題研究奨励金」(通称「山川菊栄賞」)を受賞し、田町「女性と仕事の未来館」にて授賞式が開かれました。
最初の社会主義婦人団体「赤瀾会」を結成し、日本における女性解放運動の思想的原点と呼ばれる山川菊栄の名を冠した賞を本書が受賞しました。
本書の詳細は、『「女ことば」はつくられる』へ。
2008.1.16
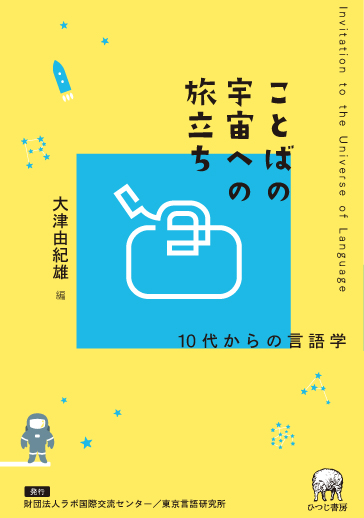
『ことばの宇宙への旅立ち』2月中旬に、刊行になります。大津由紀雄先生、上野善道先生、窪薗晴夫先生、西村義樹先生、今西典子先生、今井邦彦先生の6名の言語学者による言語学への誘いです。10代の若者に向けて、言語を考える楽しみを説きます。インタビューが元になっており、読みやすい入門書です。
本書の詳細は、『ことばの宇宙への旅立ち』へ。
2008.1.9
ひつじ新聞がとても好評です。噂のゆきちゃんをご覧になりたい、送ってほしいという方がいらっしゃいましたら、お送りしますので、ご連絡下さい。年賀カードの裏面は、年間スケジュールになっておりまして、ひつじ書房のオープンオフィスなどの予定も書かれています。
2008年の賀状
2008年のスタッフ
|
あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。
社員・スタッフ一同
|
 年末ぎりぎりで『日本語の主文現象』、『接続2007』の2冊ができました。ちょうど社員一同で、年賀状を必死に書いているところに、製本屋さんに届けてもらいました。
年末ぎりぎりで『日本語の主文現象』、『接続2007』の2冊ができました。ちょうど社員一同で、年賀状を必死に書いているところに、製本屋さんに届けてもらいました。
『日本語の主文現象』の編集は河口が担当しました。神田外語大学の長谷川信子先生の編で、生成文法の枠組みでは、今まで扱うことの困難であった日本語の主文について扱ったものです。言語研究にとって画期的な内容になっています。
本書の詳細は、『日本語の主文現象』へ。
もう1つの『接続2007』の特集テーマは、「【特集】:マルチチュードの可能性」です。「グローバル化される社会=〈帝国〉の内部で「マルチチュード」は果たして現代の社会を変革しうる勢力たりえるのか。「世界社会フォーラム」への参加やネグリ=ハートの文献から多角的に考察する」論文集です。森脇が担当しました。
 詳細は、『接続2007』をご覧下さい。
詳細は、『接続2007』をご覧下さい。
本年最後になってできた2冊です。生成文法を捉え直す本とグローバリゼーションを捉え直す本。こじつけ気味ですが、2007年の締めくくりとしてふさわしい本でしょう。今年はずいぶん、沢山の本を作りました。販売は年明けからとなります。いましばらくお待ち下さい。
本日は、年賀状書きで終わり、28日は大掃除と席替えです。それで今年も仕事納めです。本年は、たいへんお世話になりました。2008年がみなさまにとって良い年になりますように。
ふるってご参加下さい。新しい研究会の出発です。
講師 境田稔信 明治期の国語辞書に使われた約物・記号類(仮題)
日時 2008年1月12日(土)15時より
場所 大妻女子大学本館4F コミュニケーション文化学科411演習室
日本語句読法研究会のホームページをご覧下さい。
 ひつじ書房で勝手にまとめた言語学、言語学出版2007年、10大ニュースです。これは大学生協の忘年会でひつじ書房が名刺の交換といっしょに大学生協書籍部の方にお配りしたものです。書店様むけということになります。
ひつじ書房で勝手にまとめた言語学、言語学出版2007年、10大ニュースです。これは大学生協の忘年会でひつじ書房が名刺の交換といっしょに大学生協書籍部の方にお配りしたものです。書店様むけということになります。
河口が資料を集め、松本がまとめて、三井がペンで書いたもので、即席でつくったものですが、少し面白いかと思いますので、公開する次第です。手書きの味は、なかなかいいと思いませんか?
この中で述べていますように、書店様の言語学の棚作りのお手伝いをしたいと思っています。書店のみな様、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。10坪の書店から2000坪の書店まで、お受けします。
拡大表示
印刷用のpdfはこちらです。
おまけ、今年後半のポップ

『未発』16号、発送が完了しました。今年は、例年よりも2週間も遅れてしまい、学会がはじまってからになってしまいました。てんてこ舞いとはこのことか、という感じです。ぜひとも、ご注文下さい。
今週末は、言語学会に参ります。言語学会で一段落です。ぜひ、店頭にお越し下さい。
詳しくは…こちらをご覧下さい。
ひつじ書房の目録誌『未発』がようやくできました。今年は、引っ越しがあり、例年よりも2週間も遅れてしまいました。遅れてしまったのは、もう一つ今回大きな改訂をしたということも理由としてあります。
大きさがA5からB5に変わっています。それに加えてひつじで出しているジャーナル(研究誌)の紹介のページを作るなど、新しい工夫をこらしています。紹介のページでは、編集の先生方による紹介の文章も写真付きで載せています。
デザインは向井裕一さん、オペレーションは田中君が行いました。きれいで海外の学術出版社の目録のような立派な目録になりました。今週から社員全員で、発送作業を行います。ひつじかいに入って下さっている方には週明けには届くと思いますので、楽しみにお待ち下さい。

日本語句読法研究会、第1回研究会。来年、1月12日に開催します。場所は未定です。主旨は「句読法をはじめ、文字符号に付随する空白・空間をも含めた記号性のある符号全体を対象とする。書式の類や、他言語表記との接触により生ずる現象も扱う。」ということで、研究に重点を置きつつ、研究者と実務者の間をつなぐものを目指します。
日本語句読法研究会のホームページをご覧下さい。
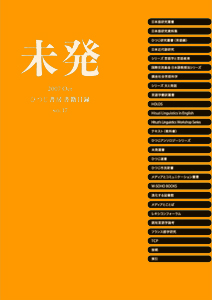
今秋の最新の目録『未発17号』、pdfデータをアップしました。どうぞご利用下さい。既刊、新刊、来年の3月までに刊行される書籍の内容を紹介しております。どうぞご覧下さい。
pdfデータですので、検索を行ったり、必要なところを印刷したりすることも可能です。ひつじ書房2007年の新刊のご紹介のページ(http://www.hituzi.co.jp/books/sinkan.html)のエクセルファイルとお併せてご利用下さいましたら、幸いです。
『未発17号』のページをご覧下さい。
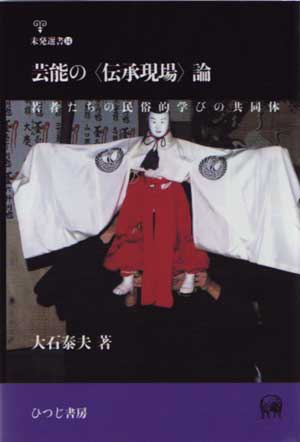
9月に刊行しました大石泰夫著『芸能の〈伝承現場〉論—若者たちの民俗的学びの共同体』が、11月18日付け日経新聞にて赤坂憲雄さんに書評していただきました。
「いくつかの民俗芸能が伝承されていく現場に、継続的に立ち会いながら、まさに変容の最前線からの報告を重ねていく著者には過剰な悲観といったものはない。」「著者はまさに、みずからたどり着いた変容の最前線から、不意に身をひるがえし、民俗芸能における〈古代〉への欲望をまっすぐに表明するのである。」
本書の詳細は、『芸能の〈伝承現場〉論—若者たちの民俗的学びの共同体』へ。

方言研究会、日本語学会の直前に間に合わせるタイミングで『日本語形容詞の文法』、『ガイドブック方言調査』を刊行しました。
『日本語形容詞の文法』は、あまり行われてこなかった形容詞についての果敢な研究です。日本語の形容詞に対する従来の見方を再検討させます。
『日本語形容詞の文法』の担当は、河口で、『ガイドブック方言調査』は田中が担当しました。方言研究会、週末の日本語学会で、たくさん売れてくれますように!

7月に刊行しました中村桃子先生の『「女ことば」はつくられる』が、本年度27回「山川菊栄記念婦人問題研究奨励金」(通称「山川菊栄賞」)を受賞しました。
最初の社会主義婦人団体「赤瀾会」を結成し、日本における女性解放運動の思想的原点と呼ばれる山川菊栄の名を冠した賞を本書が受賞しましたことは、たいへんうれしく、ありがたく思います。山川菊栄は今の津田塾大学の卒業生なのですね。この受賞により、いっそう本書が読まれるきっかけになることを祈っています。
2008年1月27日(日)に田町「女性と仕事の未来館」にて授賞式が開かれます。

『TCP2007』を刊行しました。担当は森脇です。この本はフォトレディ(先生に印刷用の原稿で提出していただく形式)です。
これまでは並製だったのですが、今号から上製で値段を9800円+税ということにしました。4000円台では採算をとるのが困難だったためです。少ない部数で採算をとるための価格の改定です。表紙の装画は、『メタファー研究の最前線』につづいて前屋歩未さんです。
今週末に名古屋で英語学会がありますので、できるだけ売りたいと思っています。

『芸能の〈伝承現場〉論』(大石泰夫)の書評が「望星」12月号に掲載されました。佐藤康智さんによる書評です。芸能伝承の「舞台裏のてんやわんや。てんやわんや」と紹介してくださっています。これは本書の中心について突いている優れた書評だと思います。
「時代時代による担い手たち(観客も含めた)の葛藤とドラマが当然の如くある。そしてその影響を少なからず受けて、民俗芸能は「変化するもの」なのだ。……そんな興味深い切り口で論じられる〈伝承現場〉を、下衆な読者である私なりに言い換えるならこうだ。舞台裏のてんやわんや。てんやわんやが伝統に影響を与えるだなんて、面白過ぎるではないか。」
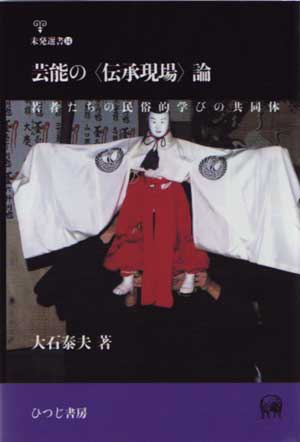
全文はこちら。「変化する民俗芸能を追う」
佐藤康智さんの書評にも書かれていますが、〈伝承現場〉ということは、民俗芸能の現場だけではなく、民俗芸能研究の現場でも問題になっていることです。そういう点では、教育の問題をも示唆してくれているというで、本書の意義について、きちんと把握してくださっていること感謝しています。
宮沢章夫氏の大学での演劇教育の話にも通じる話でしょう。教育とか伝承とか学びの共同体とかいった問題は、かなり現代的な課題ということ。

大津由紀雄先生から「揺れる羊」を贈っていただきました。まことにありがとうございます。ひつじ書房も今、揺れ動いています。それでも、動揺しているのかもしれませんが、何とか前進していると言えるでしょう。揺れながら、進んでいるのではないでしょうか。
 一同童心に帰って(?)、急に工作にいそしんで、組み立てました。せっかくなので1人1人一応乗って揺らしてみました。乗っていいのは50kgまでとのことなので、許容されているのは本当は2人だけなのですが。
一同童心に帰って(?)、急に工作にいそしんで、組み立てました。せっかくなので1人1人一応乗って揺らしてみました。乗っていいのは50kgまでとのことなので、許容されているのは本当は2人だけなのですが。
仕事に疲れたら、そっと乗って癒されましょう。科研の申請のお手伝いがやっと一段落したので、とてもよいタイミングで贈っていただきました。なかなか和む「羊」です。ありがとうございました。
 LANGUAGE IN PAPUA NEW GUINEA(岡村徹編著)ができました。ピジンクレオール語という際にピジンの議論のもとになったパプアニューギニアの言語の研究。これまで、欧米の研究者の外から研究しかありませんでしたが、現地の研究者が執筆者として参加しているのも今回の出版物の特徴の一つです。
LANGUAGE IN PAPUA NEW GUINEA(岡村徹編著)ができました。ピジンクレオール語という際にピジンの議論のもとになったパプアニューギニアの言語の研究。これまで、欧米の研究者の外から研究しかありませんでしたが、現地の研究者が執筆者として参加しているのも今回の出版物の特徴の一つです。
英文の研究書はなかなか売れにくいというジンクスがあります。みな様、大学図書館に1冊入れてくださるとうれしいです。
詳細はこちら ひつじ書房は、この時期、研究成果公開促進費の申請書類の作成のお手伝いをしています。申請書類を拝見して、分かりにくいところ、読みにくいところ、少しの工夫で研究内容がより分かりやすくなるところなどを指摘したりというアドバイスを行っています。
ひつじ書房は、この時期、研究成果公開促進費の申請書類の作成のお手伝いをしています。申請書類を拝見して、分かりにくいところ、読みにくいところ、少しの工夫で研究内容がより分かりやすくなるところなどを指摘したりというアドバイスを行っています。
編集者が、担当を決めて個々の書類を拝見して、丁寧にコメントをお付けしています。数回はやりとりして、その上で申請をすることになります。今年は機関による提出が多くなりましたので、昨年までは11月初旬がピークでしたが、今年は10月19日に第一陣の波がありました。編集担当者以外も、見積書の検算などに関わり、社員総出で取りかかっています。
今年春の採択率は、昨年からすると半減にちかいものでした。大きな問題です。文科系の学問は、書籍というかたちで公開されることに意味があるからです。(その理由は簡単でネットで読んで打ち出したものを繰り返し読むことはかなりたいへんです。なくなってしまいやすいです。その点では、書籍の方がよほど優れています。ディスプレイで読んだり、打ち出した紙を読むよりも、書籍の方が人間のワークメモリーの機能や理解作業のプロセスにより合致しているからです。)学振の学術書籍への助成の復興を祈っています。先日の谷口先生の受賞を例に挙げるまでもなく、役に立っているのですから。この助成金があって世に送り出せる研究成果も多いからです。
学振だけではなく、学会出張などもあり、この時期、日常的な業務が滞りがちになり、新規のこともなかなかできなくなります。一段落すれば、滞らなくなりますので、お待ち下さい。
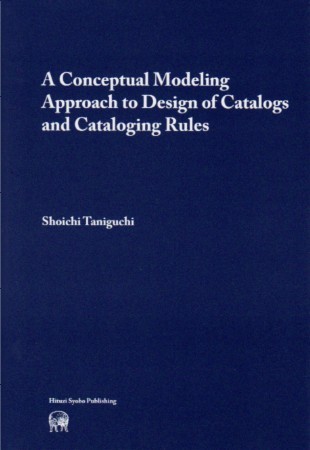 谷口祥一先生が、A Conceptual Modeling Approach to Design of Catalogs and Cataloging Rulesにて、第55回日本図書館情報学会におきまして2007年度学会賞を受賞されました。
谷口祥一先生が、A Conceptual Modeling Approach to Design of Catalogs and Cataloging Rulesにて、第55回日本図書館情報学会におきまして2007年度学会賞を受賞されました。
図書館情報学のジャンルの本は、ほとんど刊行しておりません。また、英語の学術書は、正直に申し上げまして、なかなか売れません。それでも、今回、刊行することができてたいへんうれしいです。おめでとうございます。お祝い申し上げます。
本書は、日本学術振興会の研究成果公開促進費の交付を受けて、刊行したものです。担当者は、森脇です。
詳細はこちら。
2007.10.11
 ひつじ書房では、2007年秋の目録『未発』発送作業を、正に今、社員総出でしています。(社長は、ホームページを更新しながら、電話番です。)パートのMさん、アルバイトのTさん、そして、T先生に紹介していただいて、急遽お願いした助っ人の方の力もかりて、封入作業を行っています。ひつじ書房にとって、学会参加と日本学術振興会の研究成果公開促進費の申請と並ぶ、秋のメインイベントの一つです。
ひつじ書房では、2007年秋の目録『未発』発送作業を、正に今、社員総出でしています。(社長は、ホームページを更新しながら、電話番です。)パートのMさん、アルバイトのTさん、そして、T先生に紹介していただいて、急遽お願いした助っ人の方の力もかりて、封入作業を行っています。ひつじ書房にとって、学会参加と日本学術振興会の研究成果公開促進費の申請と並ぶ、秋のメインイベントの一つです。
学術出版社にとって、読者の方に目録を直接お届けするのがいちばん重要な告知方法です。このような本が出ました、このような本がもうすぐ出ますということをお知らせします。もちろん、ホームページやメールマガジンも重要な手だてと考えていますが、なんと言ってもページに組まれて紙に印刷されたかたちというのは、一覧性という点でも○を付けられるという点でも優れていると思います。
 目録をご覧頂きまして、ぜひぜひ、ご注文下さいますようお願いします。本が売れることによって学術書の刊行を続けていくことができるからです。目録の送付を希望されます方は、toiawaseアットマークhituzi.co.jpまでご連絡下さい。個人宛発送の後、追っかけで、外商部様、書店様、図書館様へもお送りします。どうぞよろしくお願いします。
目録をご覧頂きまして、ぜひぜひ、ご注文下さいますようお願いします。本が売れることによって学術書の刊行を続けていくことができるからです。目録の送付を希望されます方は、toiawaseアットマークhituzi.co.jpまでご連絡下さい。個人宛発送の後、追っかけで、外商部様、書店様、図書館様へもお送りします。どうぞよろしくお願いします。
 写真を撮ってから、少し時間がたってしまいましたが、河口が、9月半ばの名古屋出張の際に丸善さんでプロモーション中の『ファンダメンタル音声学』店頭の様子をデジカメに撮ってきましたので、その様子をご覧下さい。売れ筋の本の多いコーナーの真ん中、とてもよいところに置いてくださっています。めだっているのではないでしょうか。
写真を撮ってから、少し時間がたってしまいましたが、河口が、9月半ばの名古屋出張の際に丸善さんでプロモーション中の『ファンダメンタル音声学』店頭の様子をデジカメに撮ってきましたので、その様子をご覧下さい。売れ筋の本の多いコーナーの真ん中、とてもよいところに置いてくださっています。めだっているのではないでしょうか。
丸善名古屋栄店さん、ありがとう!売れてくれますように!
詳細(『ファンダメンタル音声学』)。
●書店プロモーション用の『ファンダメンタル音声学』
●書店プロモーション用の『ファンダメンタル音声学』作成中
2007.10.5
 『連体即連用?』(奥津敬一郎)、『引用表現の習得研究』(杉浦まそみ子)、『外国人の定住と日本語教育(増補版)』ができました。ひつじ書房の目録誌『未発』もできてきました。週末の日本語教育学会に向けて、作ったということです。
『連体即連用?』(奥津敬一郎)、『引用表現の習得研究』(杉浦まそみ子)、『外国人の定住と日本語教育(増補版)』ができました。ひつじ書房の目録誌『未発』もできてきました。週末の日本語教育学会に向けて、作ったということです。
『連体即連用?』は河口が、『引用表現の習得研究』(杉浦まそみ子)田中が最後、担当しました。『外国人の定住と日本語教育(増補は『外国人の定住と日本語教育(増補版)』は吉峰担当です。
『未発』は、田中君が担当しました。あわただしい中、きちんとした目録を学会に持って行くことができることをうれしく思います。これで、刊行した本をどんどん売っていきましょう。明日は、日本語教育学会と日本民俗学会に参ります。両方とも京都で開催されます。
詳細(『連体即連用?』)。
詳細(『引用表現の習得研究』)。
詳細(『外国人の定住と日本語教育(増補版)』)。
 『中国人学生の綴った戦時中日本語日記』が刊行されました。週末の日本語教育学会に向けて、作りました新刊です。遠藤織枝、黄慶法先生の共編です。日記を書いていた方を「発見」することができまして、インタビューも掲載しています。安田敏朗先生も研究の部分の執筆者の1人です。吉峰が担当しました。
『中国人学生の綴った戦時中日本語日記』が刊行されました。週末の日本語教育学会に向けて、作りました新刊です。遠藤織枝、黄慶法先生の共編です。日記を書いていた方を「発見」することができまして、インタビューも掲載しています。安田敏朗先生も研究の部分の執筆者の1人です。吉峰が担当しました。
内容はタイトルの通り、ずばり戦時中に日本語を学んでいた中国人学生の日記です。編者の1人黄先生が、別のことを調査中、偶然、図書館で見つけたものです。日本語学習者の生の声、それも戦時中という時期のもので、めずらしいということに価値がありますとともに、この時代にどのように日本語が学ばれていたのか、ということがとても興味深いものだと思われます。言語学習者の研究、日本語教育史、日本近代史、植民地史などさまざまな分野にとって重要な書籍です。
 10月になりました!ひつじ書房にとっては新たな会計年度のはじまりです。さて、今週は、週末の日本語教育学会に向けて、新刊が一気に5冊刊行になります。本日は、まず第一段目『日本語の構造変化と文法化』(青木博史編)を刊行しました。
10月になりました!ひつじ書房にとっては新たな会計年度のはじまりです。さて、今週は、週末の日本語教育学会に向けて、新刊が一気に5冊刊行になります。本日は、まず第一段目『日本語の構造変化と文法化』(青木博史編)を刊行しました。
日本語の古代語研究の若手の研究者たちによる力作です。日本語古代語研究の新しい時代の到来です。
中国現代文学翻訳会では創刊号のデザイン・組版をしてくださるデザイナーを募集しています。中国、中国文化、中国語、中国映画、中国文学に関心があって、デザインをしてみようという方がいらっしゃいましたら、ご応募下さい。(ほとんどボランタリーな条件でのお願いです。)
募集の内容については次をご覧下さい。ひつじ書房の仕事としてではなく、仕事の発注は翻訳会が行います。創刊された雑誌は、ひつじ書房が流通します。ひつじ書房は、発売所ということになります。募集の内容
 認知言語学会でもとても評判が良かった『メタファー研究の最前線』の装画・装幀者である前屋歩未さんが、次の書籍の打ち合わせに来てくれました。次にお願いしているのは10月に刊行予定の『ことば・空間・身体』(篠原和子・片岡邦好編)★です。この本の装画のラフスケッチを持ってきてくれたのです。いくつかのパターンを持ってきてくれましたので、担当者の河口といっしょに相談をしました。次は色を付けて見せてくれるそうです。
認知言語学会でもとても評判が良かった『メタファー研究の最前線』の装画・装幀者である前屋歩未さんが、次の書籍の打ち合わせに来てくれました。次にお願いしているのは10月に刊行予定の『ことば・空間・身体』(篠原和子・片岡邦好編)★です。この本の装画のラフスケッチを持ってきてくれたのです。いくつかのパターンを持ってきてくれましたので、担当者の河口といっしょに相談をしました。次は色を付けて見せてくれるそうです。
来社してくれたこの機会に記念撮影をしました。素敵な装幀・装画に感謝します。ありがとう。背景が出荷用の在庫の本棚で申し訳ない。
仕事の内容の中心は、お客様へのカスタマーサービスです。顧客の方からあるいは書店からの注文の受注、書籍の注文の処理、発送、販売、書類作成などです。出版社、書店などの経験者を優遇します。パソコンについても最低限のことができることが望ましいと思います。最低限と言いますのは、メールのやりとりができること。エクセルで簡単な表を作ることができること。ファイルメーカーなどでデータベースを作れる方は優遇します。
一般事務の実務経験や出版社か書店で働いた経験をお持ちの方は優遇します。とはいいますものの、人と話したり、おいしい食べ物を食べるのが好きな方であれば、出版関係の経験が未経験でも全くかまいません。
試用期間があります。
求人の詳細はこちら。締め切り間近かです、ご応募されます方はお急ぎ下さい。
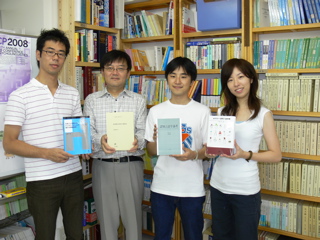 『メタファー研究の最前線』(楠見孝編)、『結果構文研究の新視点』(小野尚之編)、『認知言語学論考No.6』(山梨正明他編)の3冊ができました。認知言語学会に間に合わせることができました。
『メタファー研究の最前線』(楠見孝編)、『結果構文研究の新視点』(小野尚之編)、『認知言語学論考No.6』(山梨正明他編)の3冊ができました。認知言語学会に間に合わせることができました。
この3冊は、森脇が担当しました。『メタファー研究の最前線』の装画・装幀は前屋歩未さんです。素敵にできています。もちろん、内容については楠見孝先生をはじめとした著者の先生方のおかげですばらしいものになっています。『メタファー研究の最前線』の詳細はこちら。
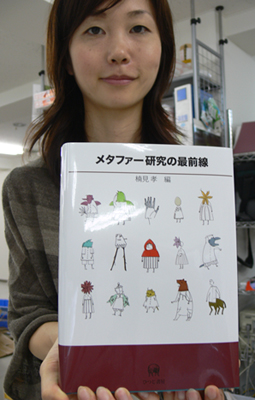 ひつじ書房にはひつじ研究叢書(言語編)にというコアなシリーズがあります。この中に入りにくい、新しい研究を押し出していくことを目指しています。本書は、言語研究者だけではなく、心理学者、認知科学研究者などの横断的な研究であり、さらには分野を超えて、たとえば、作家の方、文学研究者や広告を作るようなプランナーの方にも読んでいただきたい内容です。
ひつじ書房にはひつじ研究叢書(言語編)にというコアなシリーズがあります。この中に入りにくい、新しい研究を押し出していくことを目指しています。本書は、言語研究者だけではなく、心理学者、認知科学研究者などの横断的な研究であり、さらには分野を超えて、たとえば、作家の方、文学研究者や広告を作るようなプランナーの方にも読んでいただきたい内容です。
本書のような新しい領域の研究を精力的に出版していきたいと考えています。そのようなために、今回の刊行は、とても重要であり、そのための装幀・装画なのです。カッコイイだけではだめで、カッコイイことに加えて、さらに内容へのお誘いという要素も重要と考えています。装画の前屋さんはこちらの期待に応えてくれたのではないかと思います。(何を目指して装幀を新しくしたか)
どうぞ学会などで手にとってご覧下さい。
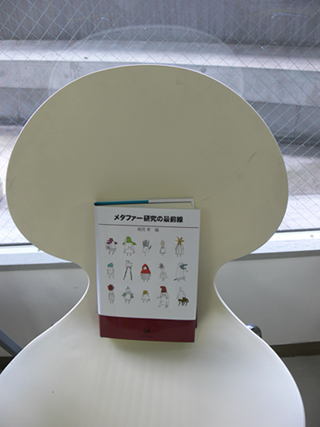
『メタファー研究の最前線』
『結果構文研究の新視点』
『認知言語学論考No.6』
先週、刊行しました『 日本人と外国人のビジネス・コミュニケーションに関する実証研究』も今回HPでお目見えです。社会言語科学会では、よく売れていたとのことです。こちらは、田中が担当しました。
『日本人と外国人のビジネス・コミュニケーションに関する実証研究』
執筆要項のマイナーチェンジを繰り返しておりますが、現時点での最新版ですので、これから執筆される方はご参照下さい。
執筆要項のページです。pdfで1MBです。
 本日、『芸能の〈伝承現場〉論』と『日本人と外国人のビジネス・コミュニケーションに関する実証研究』(近藤彩 著)の2冊ができました。ここでは、『芸能の〈伝承現場〉論』を紹介します。15日に静岡県民俗学会が伊豆の国市中央図書館で開催されます。その機会にあわせて刊行しました。
本日、『芸能の〈伝承現場〉論』と『日本人と外国人のビジネス・コミュニケーションに関する実証研究』(近藤彩 著)の2冊ができました。ここでは、『芸能の〈伝承現場〉論』を紹介します。15日に静岡県民俗学会が伊豆の国市中央図書館で開催されます。その機会にあわせて刊行しました。
著者の大石さんとは『課題としての民俗芸能研究』に結実した研究会の時からのお付き合いで、本にしましょうと申し上げてからもかなりの年月がたっています。それがようやく結実したということです。
本書の目玉は、西伊豆の宇久須の人形芝居(?)を巡る若者のエスノグラフィーです。状況論などの成果も十分に生かしつつ、民俗誌として面白いものです。民俗学・民俗芸能研究の研究者はもちろん、他の分野の研究者にとっても有意義な内容だと思います。
 東京では9月にお祭りがあるとことが多いようです。ひつじの事務所がある茗荷谷近辺では、あちこちの町内で、先週末と今週末に祭礼があります。御輿も出まして、土日、街は少しだけ賑やかになります。残念ながら、大人御輿は出ずに、子供御輿だけです。大人が祭りを執行するほどは、街は人々が根付いておりません。私も、4年前は、地元の子供御輿を手伝ったくらいです。
東京では9月にお祭りがあるとことが多いようです。ひつじの事務所がある茗荷谷近辺では、あちこちの町内で、先週末と今週末に祭礼があります。御輿も出まして、土日、街は少しだけ賑やかになります。残念ながら、大人御輿は出ずに、子供御輿だけです。大人が祭りを執行するほどは、街は人々が根付いておりません。私も、4年前は、地元の子供御輿を手伝ったくらいです。
 ひつじ書房の裏手に神社があります。正確に言うと簸川神社の直ぐ近くにひつじ書房の事務所があるということになります。こちらは8、9日がお祭りで出店がでておりました。私の子供が小学生低学年のときは、一緒に焼きそばとか買いに行ったのですが、縁遠くなってしまいました。それでも、秋を告げる風物の一つです。東京も秋になりました。
ひつじ書房の裏手に神社があります。正確に言うと簸川神社の直ぐ近くにひつじ書房の事務所があるということになります。こちらは8、9日がお祭りで出店がでておりました。私の子供が小学生低学年のときは、一緒に焼きそばとか買いに行ったのですが、縁遠くなってしまいました。それでも、秋を告げる風物の一つです。東京も秋になりました。
われわれの会社も、もう少し地元に根ざしてもいいのかも知れません。ひつじ書房が祭りに寄付をする日は来るのでしょうか。子供がいないと街に根付くことも、ハードルが高いようです。
5月から、開催して参りましたオープンオフィスが、27日で終了いたしました。ご参加下さいました研究者の方々に御礼申し上げます。
3年目となり、オープンオフィスの開催については知られるようになってきていると思います。博士論文をこれから書くというような若い研究者から、実績のある研究者の方まで幅広い方にご参加いただくことができました。
今期のオープンオフィスについて自己評価した上で、次の展望を考えたいと思います。
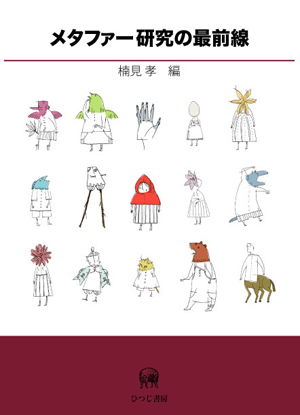 ひつじ研究叢書(言語編)以外の言語研究書の装幀を検討していましたが、このたびようやく決定しました。「純粋」な言語研究以外のもう少し臨界的な要素のある言語研究を、できるだけ広い人々に手にとってもらいたいという主旨で、箱入りの言語編とは違った装幀を希望していました。おかげさまで、この願いを実現してくれそうなすばらしいイラストと装幀を決めることができました。このかたちがひな形になります。最初の発案
ひつじ研究叢書(言語編)以外の言語研究書の装幀を検討していましたが、このたびようやく決定しました。「純粋」な言語研究以外のもう少し臨界的な要素のある言語研究を、できるだけ広い人々に手にとってもらいたいという主旨で、箱入りの言語編とは違った装幀を希望していました。おかげさまで、この願いを実現してくれそうなすばらしいイラストと装幀を決めることができました。このかたちがひな形になります。最初の発案
少なくない方にご応募いただきましたことをたいへんありがたく思います。2ヶ月をへて、やっと決まりましたことに一安心しています。
装幀とイラストの両方なので、装幀・装画ということになりますが、装幀・装画は、前屋歩未さんです。
この『メタファー研究の最前線』は、認知言語学会までに刊行になりますので、認知言語学会でご覧いただけます。内容ともどもすばらしいものです。ご期待下さい。
 先週の25日、にほんごの凡人社麹町店にて、日本語教授法シリーズ説明会が開かれました。第6巻『話すことを教える』の巻で、執筆された長坂水晶先生(国際交流基金日本語国際センター専任講師)が解説をされました。
先週の25日、にほんごの凡人社麹町店にて、日本語教授法シリーズ説明会が開かれました。第6巻『話すことを教える』の巻で、執筆された長坂水晶先生(国際交流基金日本語国際センター専任講師)が解説をされました。
当日は、大盛況で、60名を超える方が参加されました。参加された方はねっしんで、質問された方もおおぜいいらっしゃいました。
ご参加された方に御礼申し上げますとともに貴重なお話しをくださった長坂先生、場所を提供された凡人社さまに御礼申し上げます。
次回は、2007年9月22日(土)14:00~15:30で、日本語教授法シリーズ9『初級を教える』(阿部洋子先生)です。凡人社さんにてご確認の上ご参加下さい。凡人社さん
 音声学の教科書の決定版『ファンダメンタル音声学』(今井邦彦著)の書店プロモーション用の見本ができました。見本は、本にインデックスをつけまして、本の特徴を分かりやすくして、お客さんにお求めいただきやすくするものです。
音声学の教科書の決定版『ファンダメンタル音声学』(今井邦彦著)の書店プロモーション用の見本ができました。見本は、本にインデックスをつけまして、本の特徴を分かりやすくして、お客さんにお求めいただきやすくするものです。
これを店頭に見本として置いてくださる書店様を募集しましたところ、6軒の書店様からご応募をいただきました。ありがとうございます。ひつじ書房としてははじめての試みです。1冊1冊、手作りです。これから、発送しますので週末には書店に届けられると思います。
読者のみな様は、どうぞ書店にて手にとってご覧下さい。
書店様におかれましては、第一次募集は締め切っていますので、次回の募集をお待ち下さい。問い合わせは、三井まで。
ひつじ書房では、現在、外国人日本語学習者向けの日本語の教材を作っています。その中で、文型の説明の部分でイラストを載せることにしていますが、ついては文型の説明の部分のイラストを募集します。ことばを分かりやすい動作にするということはむつかしいことだと思います。頑張ってご応募下さい。 索引のページの間違い(申し訳ありません)など、現時点での訂正を行っています。電子版ですと検索などができますのが、便利です。どうぞご利用下さい。3.6Mありますので、時間があります時にダウンロードしてくださいましたら、幸いです。 『「女ことば」はつくられる』(中村桃子著)まもなく刊行です。表紙は、明治初期、女子師範の前身の卒業生の写真を元にしています。女性が、おとこ袴を履いているという写真を元にしています。 松本が担当しました。(そのせいで刊行が遅れました。申し訳ありません。)「女ことば」はあるのか、あどこにあるのか。これまで行われなかった言語研究の新しい分野です。 詳しくは…こちらをご覧下さい。書店での注文用のチラシがダウンロードできます。 『レキシコンフォーラムNo.3』ができました。印刷所でできて、届いたばかりのほやほやです。 河口が担当しました。執筆者の先生方にはご協力いただき、明日のレキシコンフォーラムに間に合うことができました。先生方、ありがとうございました。 作った本は出来た段階で、倉庫に入れるのですが、この3ヶ月は本当に忙しかった。ということで、三美印刷さんに納品を待ってもらっていた本を倉庫に受け入れました。 4月から作ってきた本を倉庫に受け入れるのでたいそうな量になります。倉庫を整理して、それから受け入れるということになり、社員と専務は、今日は一日倉庫です。受け入れの後に在庫の数を数えること(棚卸し)をします。というわけで、社長の私が留守番をしております。誰もない事務所の風景です。 トップページでの6月15日の移転パーティの報告をし忘れていることに気がつきました。東泉先生と高崎・立川先生にいただきましたお花です。ひつじがあしらってありますことおわかりになりますでしょうか。 たいへんお待たせしてしまいましたが、今井邦彦先生の『ファンダメンタル音声学』を刊行しました。本書は、英語の音声について学び、自分で発音することができるようにするための本です。 今井先生自ら吹き込んでいただいています。今井先生の発音はイギリス人も賞賛したとてもすばらしいもので、聞いているだけでも発音がうまくなるような気になります。(アメリカ英語に特徴的な部分は、アメリカ出身の方が吹き込んでいます。)でも、この本の特徴はとても理詰めであることです。 ネイティブの発音をただ聞いて真似をするだめでは、日本語の耳になってしまった耳で聞くのでは、発音を自覚的に変えることは不可能と言うことです。そのための秘訣(理論)と学ぶことになります。
詳しくは…こちらをご覧下さい。 『文と発話 時間の中の文と発話』(森脇担当)『ピア・ラーニング入門』『複合助詞がこれでわかる』(青山担当)の3冊ができました。3冊とも斬新な本です。『文と発話』は、文を問い直し、『ピア・ラーニング入門』は、学びの方法を問い直し、『複合助詞』はこれまであまり研究されてこなかったトピックの本です。 日本語学会、日本語教育学会に間に合わせました。たいへん、お待たせしました。
ひつじ書房が新しい事務所に引っ越ししてはじめてできあがりました本です。文法化研究の起源とも言われるメイエの文法化に関わる論究を集めて日本語訳したものです。松本明子先生の編訳です。近代英語協会の大会に間に合わせました。お待たせしました。
ひつじ書房は、2005年から行っておりますオープンオフィスを本年も行います。学術書の刊行について、様々な相談を受け付けいます。具体的に博士論文を刊行する方法であるとか、これから学術書を出したいであるとか、本をだすというのはどういうことなの、というような漠然とした質問まで、どんな質問・相談でもかまいません。どうぞご参加下さい。
ひつじ書房は、連休のはじめに引っ越しました。距離的には100メートル程度ですが、地名は小石川から千石への引っ越しです。コープとうきょう氷川下店の上です。駅からはだいぶ分かりやすくなりました。どうぞお越し下さい。
ベーシック日本語教育が、刊行されました。これを機会に、4月に刊行された書籍3冊の記念撮影を行いました。『ベーシック日本語教育』(佐々木泰子編著)は、だいぶお待たせしての刊行です。お待たせしました。日本語教育能力検定試験の新基準に準拠した1冊です。日本語教師を目指す方には簡便なよい教科書だと思います。
A Conceptual Modeling Approach to Design of Catalogs and Cataloging Rulesの著者である谷口祥一先生がお越しになりました。ひつじ書房にとってはまれな図書館学の研究書です。図書館などにおける情報(資料)組織化について、扱った研究書です。
 中村三春山形大学教授、『係争中の主体』と『修辞的モダニズム』(弊社刊)にて、宮澤賢治賞奨励賞しました。長年の宮沢賢治の文学に対する研究が認められたことと存じます。単純に褒めたたえるとか、従来の見方を踏襲したという研究ではありませんので、授与下さった各位に編集者としてもお礼を申し上げたいと思います。中村先生へは、こころからお祝いを申し上げます。おめでとうございました。
中村三春山形大学教授、『係争中の主体』と『修辞的モダニズム』(弊社刊)にて、宮澤賢治賞奨励賞しました。長年の宮沢賢治の文学に対する研究が認められたことと存じます。単純に褒めたたえるとか、従来の見方を踏襲したという研究ではありませんので、授与下さった各位に編集者としてもお礼を申し上げたいと思います。中村先生へは、こころからお祝いを申し上げます。おめでとうございました。
新聞の記事へのリンクを以下に載せます。
●岩手日報
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20070802_9
●毎日新聞
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/iwate/news/20070802ddlk03040193000c.html
2007.8.2
イラストレーター募集します。
2007.7.30
未発16号をアップしました。
未発第16号
2007.7.20
ひつじ書房 出版事務(カスタマーサービス)のアシスタントを募集します。ご応募される方は、以下の内容をご覧の上、ご応募下さい。
2007.7.5
『「女ことば」はつくられる』まもなく刊行!

2007.6.29
『レキシコンフォーラムNo.3』ができました

2007.6.28
棚卸しと受け入れ、社長は留守番です。(プラス移転パーティの報告)


 引っ越しパーティのレポートです。
引っ越しパーティのレポートです。
2007.5.25
『ファンダメンタル音声学』、刊行しました。

『文と発話』『ピア・ラーニング入門』『複合助詞』できました。

『複合助詞がこれでわかる』
『ピア・ラーニング入門』
2007.5.18
メイエ『いかにして言語は変わるか』できました。

2007.5.15
本年もオープンオフィスを行います。

2007.5.1
ひつじ書房、引っ越しました。

2007.4.24
ベーシック日本語教育が、刊行されました。

2007.4.17
谷口祥一先生が、お越しになりました。


ベーシック英語史(家入葉子著)が、刊行されます。ながらくお待たせしてしまいましてすみません。大部になりすぎず、簡便で分かりやすい内容です。松本が担当しました。
2007.4.4ひつじ書房は、4月29日に移転します。現在、入居しておりますビルが、立て直しになるということで、近くに事務所を探しておりましたところ、よい物件が見つかりましたので、今月末に移転することになりました。地名は千石ですが、最寄り駅は、現在と同じ茗荷谷駅で、事務所の場所も、ほぼ100メートル程度の移動になります。新しい住所は次の通りです。1階がコープとうきょう氷川下店で、そこの2階です。ご不便をお掛けすることがあると存じますが、よろしくお願い申し上げます。
112-0011
2007年の花見をしました。昨年につづいて、播磨坂での2度目のお花見を開催することが出来ました。季節の変わり目には季節の変わり目のイベントを無理矢理、忙しくてもするのが、江戸時代からの(長屋の)伝統であるとの信念によって、多少一段落したこの時期にお花見を開催できるのはうれしいことです。つづく

学びのエクササイズ ことばの科学(加藤重広著)が、刊行されました。ながらくお待たせしてしまいましてすみません。分かりやすく面白い内容にできていると思います。どうぞご覧下さい。松本が担当しました。
学びのエクササイズ ことばの科学
正確に言いますと、日高水穂先生が朝日新聞の夕刊に若手研究者として紹介されて、その中で書名にも触れてあったということです。なかなかよい記事だと思いますので、転載します。(転載許可を受けています。)

2006年の科研の本ができました。クレア・マリィさんが、事務所に寄って下さいました。クレア・マリィさんの『発話者の言語ストラテジーとしてのネゴシエーション行為の研究』の刊行は、言語研究にとって大きな事件であると言っていいでしょう。話者の立場から、言語を捉え直すという初めての試みと言っていいでしょう。ここでの話者の立場というのは、言語のコミュニティに参加していく人という意味です。
参加していくときに、私たちはいろいろな葛藤やおそれやどきどきを感じているわけです。そんな気持ちを持ちながら、私をどうその中に参加させていこうか、というストラテジーを持っています。通常言語(教育)研究は、どう教えるかという視点に立つことが多いと思います。それを逆転させる研究です。

2006年の科研の本ができました。『授与動詞の対照方言学的研究』(日高水穂著)、『日本語のアスペクト体系の研究』(副島健作著)、『現代日本語の複合語形成論』(石井正彦著)、『発話者の言語ストラテジーとしてのネゴシエーション行為の研究』(クレア・マリィ著)の4冊を紹介します。
この4冊は河口が担当した書籍です。彼女は房主といっしょに担当し、この4冊を作りました。はじめての本たちということです。誰でも最初に作る本がありますが、これらの4冊が河口にとっての最初の本です。(おめでとう!)
2007.3.1ひつじ書房の新しい広告用バナーを作りました。もし、お気に召しましたら、みな様のホームページのどこかに入れてくださいましたら、幸いです。こちらに直接リンクして下されば、新しくなるたびに自動的に新しい情報に変わります。
リンク先 http://www.hituzi.co.jp/img/hituzibanner2007_6.gif
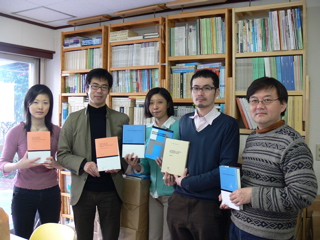
2006年度の科研本ができあがりました。著者の先生方にお送りしてご覧いただいているところです。今回、ご紹介しておりますのは、4冊です。全部で13冊ですが、追って紹介申し上げます。
Communicating Skills of Intention
Japanese women's listening behavior in face-to-face conversation

現在すすめております2006年度の科研本ができはじめました。まずは最初の2冊。これからぞくぞくとできてきます。まずは、この2冊。田中と森脇が担当しました。
A Conceptual Modeling Approach to Design of Catalogs and Cataloging Rules こちらは図書館学の英文の研究書です。表紙カバーの色は、Bleu de Chineのきれいな本です。

現在、編集をすすめております『ファンダメンタル音声学』の編集のために今井邦彦先生がお越しになりました。もうすぐ再校です。3月半ばには刊行となります。どうぞご期待下さい。吉峰が担当しています。

国際交流基金 日本語教授法シリーズの第6巻、『話すことを教える』ができました。読むこと、書くことについては、ある程度教え方について法則化されているといえますが、「話すこと」についてきちんと論じたものはそれほど多くないと言えるかもしれません。注目、待望の1冊です。
担当は吉峰です。ひつじでの第2作目となります。

大坪一夫先生の古希の記念の論文集でもあります。日本語教育の転換期である現在、留学生センターの問い直しなどが行われています。そのような時期に時宜を得た刊行だと思います。
担当は吉峰です。ひつじでの第1作目です。

今年1冊目は、二枝美津子先生の『主語と動詞の諸相』です。松本が担当しました。主語というものを再考するにはとても良い本だと思います。言語学以外の方が読んでも面白いのではないでしょうか。主語というものはあるのか、といったことが思想的な意味でも問い直されています。重要な文献の登場と思います。
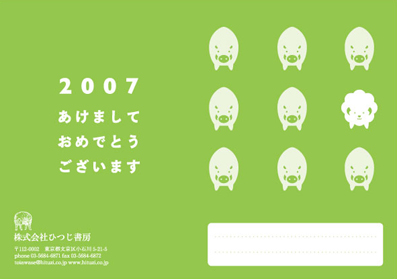
ひつじの本年の年賀カードです。デザインはオオサキヨシハルさん。昨年は、アカデミックプレゼンテーションの装幀・組版をやってもらいました。
さて、鏡開きも終わり、松の内があけました。今年は、科研の公開促進費を受けて刊行するものが13冊、それ以外の研究書も10冊、教科書まであわせると30冊以上の刊行の予定です。順次仕事を進めています。これから2月までが佳境です。

あけましておめでとうございます。言語学の出版の分野で日本でNo.1の出版社として本年も頑張って参ります。どうぞご支援下さい。
 『接続2006』、刊行しました。特集は、「ひらかれる身体」です。ギブソンの直接知覚論から皮下脂肪まで。
『接続2006』、刊行しました。特集は、「ひらかれる身体」です。ギブソンの直接知覚論から皮下脂肪まで。
Open Your Bodies 知覚する身体—J.J.ギブソンの直接知覚論における身体観とその根拠を巡る考察— 境 敦史 知覚の過去と未来ーギブソンの直接知覚論をめぐってー 村井則夫 - 音を使って覗いた身体—私たちの骨格筋の「かたち」と「はたらき」— 村岡慈歩 身体とコミュニケーションー今こどもたちに必要なことー 星山麻木 機械と人間 ─二一世紀の身体─など
担当は森脇です。書店にてご注文されますと年末には手に入ります。
 『新訂版 聞いておぼえる関西(大阪)弁入門』、刊行しました。
『新訂版 聞いておぼえる関西(大阪)弁入門』、刊行しました。
もともとはアルクから刊行され、長らく絶版状態になっていた『聞いておぼえる関西(大阪)弁入門』を新訂版として刊行しました。別売であったテープをCDとして付けています。日本語を学ぶ外国人の方を中心的な対象としていますが、関西に出張される方、関西に転居される方にもお役に立ちます。
担当は田中です。書店に並びますのは、24日ごろになります。事前にご予約されますと確実に手に入ります。
 12月9日、麹町の凡人社のお店で『アカデミックプレゼンテーション入門』のミニ講演会を、開催しました。
12月9日、麹町の凡人社のお店で『アカデミックプレゼンテーション入門』のミニ講演会を、開催しました。
著者の三浦香苗先生、深澤のぞみ先生、ヒルマン小林恭子先生の3名の先生にミニ講演会を行ってもらいました。日本語が全く分からない段階から、5ヶ月間で見事なプレゼンテーションができるようになったモハマドさんのビデオを見せてもらった際には、感嘆のため息がでました。このビデオは付属CDに収録されています。あいにくの小雨でしたが、参加者は活発な議論をしていました。
 『アカデミックプレゼンテーション入門』刊行しました。本書を担当したのは青山です。デザインは、大崎善治さん。
『アカデミックプレゼンテーション入門』刊行しました。本書を担当したのは青山です。デザインは、大崎善治さん。
著者は、三浦香苗先生、岡澤孝雄先生、深澤のぞみ先生、ヒルマン小林恭子先生です。もともとは留学生向けの内容でしたが、日本人学生も、本当に意味のある内容を発表できるように工夫されています。必要な日本語表現だけでなく、テーマの選び方からデータの処理・分析のプロセス、さらには実際に発表するためのスライド作成や話し方,態度などのノウハウまでを網羅。プレゼンテーションを学ぶ際にとても役に立つテキストです。
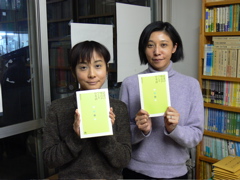 『話者の視点がつくる日本語』刊行しました。本書を担当したのは宮島です。第二言語習得研究会、語用論学会に持って行きますので、ぜひともご覧下さい。
『話者の視点がつくる日本語』刊行しました。本書を担当したのは宮島です。第二言語習得研究会、語用論学会に持って行きますので、ぜひともご覧下さい。
森田良行先生の日本語を成り立たせている視点についての研究書です。研究書といいましてもテクニカルな内容ではありませんので、予備知識が無くても日本語の視点についてなるほどと思わせてくれること請け負います。
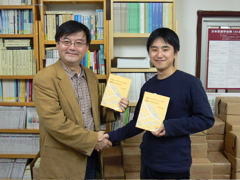 『公民パートナーシップの政策とマネジメント』を刊行しました。きれいなクリーム色の本です。本書を担当したのは森脇です。明日、東洋大学で開催される日本評価学会に展示用に持って行きますが、ぜひともご覧頂きたいものです。
『公民パートナーシップの政策とマネジメント』を刊行しました。きれいなクリーム色の本です。本書を担当したのは森脇です。明日、東洋大学で開催される日本評価学会に展示用に持って行きますが、ぜひともご覧頂きたいものです。
ひつじ書房は、言語研究以外のものも年に何冊か刊行しています。本書の内容は、行政と民(市民やNPOや学生や企業)のパートナーシップについての研究書・解説書です。政府だけでも、市場だけでも、市民だけでも解決しない問題をパートナーシップをもとに解決していく。課題は多いですが、21世紀の社会にとって重要な課題について迫ります。

『アカデミック・プレゼンテーション入門』は、日本語力が十分ではない日本語学習者から日本人学生までを対象とした「プレゼンテーション」の入門書です。
本書刊行を記念いたしまして、12月9日(土)凡人社麹町店にて刊行記念イベントを開催いたします。詳細は次の通りです。
◎『日本語学習者と日本人学生のためのアカデミック・プレゼンテーション入門』セミナー
▼講師 深澤のぞみ(富山大学留学生センター)先生ほか予定
▼日時 12月9日(土)14時〜15時30分(予定)
▼場所 凡人社麹町店(東京都千代田区平河町1-3-13 菱進平河町ビル1F)
▼参加費 無料
*事前申し込みは特に必要ありませんが、資料を準備する関係上、下記までご連絡いただけますとありがたく存じます。多くの方のご来場をお待ちいたしております。
→お申し込み・お問い合わせ:toiawaseアットマークhituzi.co.jp(担当:青山)
 『多民族社会の言語政治学−英語をモノにしたシンガポール人のゆらぐアイデンティティ』(奥村みさ・江田優子・郭俊海 著)を刊行しました!この土日に北海道で開催される言語学会に間に合わせて作りました。内容は、言語学会よりも言語政策学会向けではあります。学会には、吉峰と森脇が参ります。本書を担当したのは田中です。本当にご苦労様。
『多民族社会の言語政治学−英語をモノにしたシンガポール人のゆらぐアイデンティティ』(奥村みさ・江田優子・郭俊海 著)を刊行しました!この土日に北海道で開催される言語学会に間に合わせて作りました。内容は、言語学会よりも言語政策学会向けではあります。学会には、吉峰と森脇が参ります。本書を担当したのは田中です。本当にご苦労様。
英語が共通言語となっているシンガポールの栄光と苦悩についての研究書です。小学校での英語教育が叫ばれたりもしている現在、シンガポールのような英語で全ての授業を行うということはないにしろ、我々にとっても、重要なケーススタディの紹介と言えるでしょう。
『多民族社会の言語政治学−英語をモノにしたシンガポール人のゆらぐアイデンティティ』の詳細はこちら本日、科研費の申請が締め切りとなります。ひつじ書房に、関係しますのは「研究成果公開促進費」になります。提出された方は、論文を書き上げ、申請書を何度も書き直して作成されたことと思います。お疲れ様でした。4月に採択の連絡がきますことをこころから祈っています。
岡山大学での日本語学会に出店します。次の週の言語学会で、秋の主な学会が終了します。この時期は、学会が毎週あり、遠方であれば出張します。日本学術振興会の科研申請もありますので、10月末から11月の前半は、1年間を通してもとりわけ立て込む時期なのです。
全国から先生方が来られますので、多くの方とお話しができ、それはうれしく、楽しいのですが、バタバタしてしまていて気ぜわしい時期です。学会が終われば本格的な冬に突入します。ことしも最終局面です。
 TCP no.7が刊行されました!この土日の英語学会に間に合わせて作ったものです。きれいな表紙にできあがりました。担当は森脇です。
TCP no.7が刊行されました!この土日の英語学会に間に合わせて作ったものです。きれいな表紙にできあがりました。担当は森脇です。
残念ながら、いつも論文は力作揃いなのですが、TCPはあまり売れていません。学会で20冊は売れてほしいものです。生成文法派の言語心理学の研究者はぜひとも1冊かならず買って下さい。
 金水先生の20年来の研究をまとめた成果である『日本語存在表現の歴史』が新村賞を受賞しました!
金水先生の20年来の研究をまとめた成果である『日本語存在表現の歴史』が新村賞を受賞しました!
ひつじ書房にとっては、新村出賞4年連続受賞ということになります。これは驚くべき快挙です。
『日本語存在表現の歴史』が優れた研究であることと共に、これまでも多くの優れた研究者の方々によって支えられてきた証しだと思います。研究者の方そして読者の方のご支援のたまものです。厚く御礼申し上げます。
これからも優れた研究書の出版に向けて努力していきたいと社員一同考えています。
 未発15号の発送を社員総出で、行いました。秋に未発を出しますのは、はじめてのことです。今年の秋から来春にかけて多くの書籍を刊行しますので、秋にも目録を作って、発送することにいたしました。今年度はなんと1年間で50冊も刊行する予定です。どうぞごひいきに。
未発15号の発送を社員総出で、行いました。秋に未発を出しますのは、はじめてのことです。今年の秋から来春にかけて多くの書籍を刊行しますので、秋にも目録を作って、発送することにいたしました。今年度はなんと1年間で50冊も刊行する予定です。どうぞごひいきに。
ひつじのメールリストに入っている方には来週には届くと思います。届きましたら、どうぞご覧の上、ご注文くださいましたら、幸いです。未発をご覧になりたい方は、メールリストに登録させていただきますのでご連絡下さい。toiawaseアットマークhituzi.co.jpまで!
英語コーパス学会にて、本年刊行しました加野(木村)まきみ先生のLexical Borrowing and its Impact on Englishが英語コーパス学会賞奨励賞を受賞しました。加野(木村)まきみ先生に対してお祝い申し上げますとともに、刊行した小社としてとてもうれしく思います。おめでとうございます。
Lexical Borrowing and its Impact on Englishの詳細はこちら
 認知言語学論考No.5ができました。担当は宮島です。認知言語学会までに間に合いました。今週末の認知言語学会にお目見えです。貞光宮城、崎田智子、平井剛、酒井智宏、森山新、Yoshikata Shibuya、Yuki-Shige Tamura先生の論文が収録されています。
認知言語学論考No.5ができました。担当は宮島です。認知言語学会までに間に合いました。今週末の認知言語学会にお目見えです。貞光宮城、崎田智子、平井剛、酒井智宏、森山新、Yoshikata Shibuya、Yuki-Shige Tamura先生の論文が収録されています。
平成19年度科学研究費補助金(研究成果公開促進費)公募要領・計画調書等のページが開始されました。提出日は、11月13日〜16日ということです。
本年の申請をお考えの方は、早めにご相談下さい。お問い合わせは、toiawaseアットマークhituzi.co.jpまでお願いします。

堀素子、津田早苗、大塚容子、村田泰美、重光由加、大谷麻美、村田和代先生たちの執筆された『ポライトネスと英語教育』が本日、JACETの大会にて大学英語教育学会学術賞を受賞しました。授賞式の詳細はこちら
先生方の研究が評価されたことをお喜び申し上げます。おめでとうございました。ひつじ書房では英語教育研究の分野での受賞ははじめての快挙です。森脇が担当しました。JACETの学会会場にて取っていただいた写真です。
 中島平三先生の還暦をお祝いした論文集『言語科学の真髄を求めて』が刊行になりました。立派な本になりました。担当は青山です。彼女にとっては500ページを超える重厚な研究論文集ははじめて編集したものです。
中島平三先生の還暦をお祝いした論文集『言語科学の真髄を求めて』が刊行になりました。立派な本になりました。担当は青山です。彼女にとっては500ページを超える重厚な研究論文集ははじめて編集したものです。
英語、日本語、および他言語の統語的、意味的、語用論的諸現象が鋭く分析されているものです。どうぞご覧下さい。
 2004年の11月から仕事をしていました松原が、8月31日付けで退職しました。入れ替わりのタイミングで9月1日に、吉峰晃一朗さんが入社しました。吉峰さんは、日本語教育関係の編集のベテランです。編集の力も充実することと期待しています。
2004年の11月から仕事をしていました松原が、8月31日付けで退職しました。入れ替わりのタイミングで9月1日に、吉峰晃一朗さんが入社しました。吉峰さんは、日本語教育関係の編集のベテランです。編集の力も充実することと期待しています。
退職は悲しいことであり、入社はうれしいことです。松原さんが、激動の2年半を支えてくれたことには、感謝のことばもありません。実るとも分からない荒れ地を黙々と耕しつづけてくれた労苦に深く感謝します。松原さんの今後の活躍を祈るとともに、新しい力を受け入れることができたことを喜びたいと思います。
5月から行ってまいりましたオープンオフィスが、無事終了しました。多くの方のご参加をいただきましたことを厚く御礼申し上げます。
研究者の方々からのご質問・お問い合わせについて、オープンオフィスの期間以外であるからお断りする、ということはありません。期間を設けたオープンオフィスの主旨は、期間を設けることで、敷居を低くしたいということです。何かお問い合わせされたいことがありましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
 ながらくお待たせいたしました「講座社会言語科学6巻 方法」の巻を刊行しました。金曜日のメディアとことば研究会でお目見えです。田中が担当しました。今週末の社会言語科学会に間に合わせるべく、最後の追い込みで刊行となりました。
ながらくお待たせいたしました「講座社会言語科学6巻 方法」の巻を刊行しました。金曜日のメディアとことば研究会でお目見えです。田中が担当しました。今週末の社会言語科学会に間に合わせるべく、最後の追い込みで刊行となりました。
本書は、方法論の巻で、社会言語科学の研究方法をひととおり見渡せる内容になっています。この分野に関心のある方には、お得な1冊になっています。
講座社会言語科学6巻 方法の詳細松本功(ひつじ書房代表取締役社長・編集長)
題目:電子メディア時代における紙の出版の意義について
—知性のマネジメントという視点から—
場所:北星学園大学
日時:8月25日(金)15時〜18時
電子メディアがメディアとして大きな比重をしめるようになりつつある時代において、紙への印刷を主にする出版というものの意味が変容していることは疑いようのないことである。しかし、その変容の結果、紙の出版は不要なモノになるのだろうか、あるいは出版は電子出版となるのだろうか、あるいは出版という機能自体が喪失されるのだろうか。出版が、知的な営みに対して果たしてきた役割が、電子メディア時代において、紙という制限を超えて広がるのか、それとも紙とともに失われていくのか。これは、単に紙かネットかというメディア(手段)の問題を超えて、知識を社会的にどう持続していくかというメディア(媒介)の問題として問題提起したい。
詳細・申し込み方法など 今回で、7回目になる合宿をおこないました。合宿をはじめてから、3年半がたちました。激動の3年半でした。しかしまた、これからもひつじ書房は、大きく成長していきます。成長していくということは現状にとどまらないで進化していくということです。現在、問題もあるし、課題も多いと思います。現状にとどまらず、21世紀の学術出版を作り出すというビジョンに向かって進みます。容易なことではありません。
今回で、7回目になる合宿をおこないました。合宿をはじめてから、3年半がたちました。激動の3年半でした。しかしまた、これからもひつじ書房は、大きく成長していきます。成長していくということは現状にとどまらないで進化していくということです。現在、問題もあるし、課題も多いと思います。現状にとどまらず、21世紀の学術出版を作り出すというビジョンに向かって進みます。容易なことではありません。
東京駅の前のホテルでの1泊2日の合宿でした。昼に入って、まじめに、丁寧に話し合いました。次のステージのための有意義なステップだと信じています。
 横組み研修を行いました。書籍にとって、行とはどのような意味を持つのか、ということを考えたことがありますか?
横組み研修を行いました。書籍にとって、行とはどのような意味を持つのか、ということを考えたことがありますか?
書籍に行があるのは当たり前のことと思われるかも知れません。しかしながら、著者の方にこの行はこうしてほしいと言われた時に、「それは○○の理由で、そのようにしない方が書籍としてはいいのです。」という説明ができる必要があります。
よほどのことがない限り許されないこと、許容されること。許容されることであれば、受け入れればいいのです。また、本を作る際に、悩むべきなのか、悩まないでいいのか。悩んでも意味のないところは悩まない方が仕事をこなせます。背景になる知識があるのとないのとでは大きく違うのです。
組版の知識のある編集を行いたいということで、行いました。写真は、三美印刷さんにお借りした活字で組んだページです。


 『ピアで学ぶ大学生の日本語表現』ワークショップ、8月1日、開催しました。
『ピアで学ぶ大学生の日本語表現』ワークショップ、8月1日、開催しました。
アジア学生文化会館で行いましたワークショップ無事に終了いたしました。『ピアで学ぶ大学生の日本語表現』の主旨、プロセスを重視した表現法の教科書であることピアレスポンスについての概説の後、実際に参加者にピア活動を経験してもらいました。
ひつじ書房の社員も参加し、ピアを体験しました。大島先生、池田先生の授業運営も、とても活動的で啓発されるものでした。盛況かつ充実したワークショップであったと思います。4時間では、時間が足りないという感想の方もいらっしゃいました。
 本枯れの時期と言われる夏ですが、ひつじ書房では、西田谷洋さんの斬新な挑戦の書を刊行しました。認知科学・認知言語学を文学研究に使うという挑戦です。
本枯れの時期と言われる夏ですが、ひつじ書房では、西田谷洋さんの斬新な挑戦の書を刊行しました。認知科学・認知言語学を文学研究に使うという挑戦です。
文学がテキストによるものごとの認識であるとしたら、それが認知活動であることは疑えないものであり、素朴な作家論・作品論を超えるとしたら、この挑戦は通らなければならない道です。この挑戦を手にとってご覧下さい。本書は田中が担当しました。
『認知物語論とは何か?』の詳細はこちら
2006.7.27
現在、弊社では松原が中心となって準備を進めています。あと数日後ですので、追い込みの段階です。もうあとわずかですが、若干名の余裕があります。ピア活動にご興味のある方、体験してみたい方は、以下をご覧の上、お申し込み下さい。
|
講師 :大島弥生・池田玲子(東京海洋大学)ほか 日時 :8月1日(火)13時から17時 場所 :アジア学生文化協会(文京区白山) ●JR山手線 駒込駅(南口)または巣鴨駅より徒歩10分 参加費:1000円(当日受付でお支払い下さい) 『ピアで学ぶ大学生の日本語表現』は、日本語表現法という点とピア活動という点の2つの特徴がある。今回は、急に日本語表現の科目を担当することになった方や、ピア活動について馴染みがない方、本書を教室で使ってみようと検討されている方で、日本語表現法を教えること、ピア活動を使うことについて知識や経験のない方、少ない方など、日本語表現法やピア活動についての初心者の方向けにワークショップを行う。一部、実際に簡単なピア活動の経験をしていただく予定。多くの方の参加を期待したい。 以下の情報をメールかファックスでお知らせ下さい。 お申し込み用紙 |
 『読むことを教える』刊行しました。国際交流基金の日本語教授法シリーズの第1回目の本です。青山が、担当しました。
『読むことを教える』刊行しました。国際交流基金の日本語教授法シリーズの第1回目の本です。青山が、担当しました。
国際交流基金日本語国際センターの17年間の成果を世に問うものになっています。定価は700円+税です。青山のとなりが、本書のデザインをしてくれたアサヒエディグラフィーの吉岡さん。その横で目をつぶっているのが新人アルバイトの松上さんです。
書店さんに並ぶのは少し先です。また、書店さんでご注文いただければ、たいがい1週間くらいで届きます。
『読むことを教える』の詳細はこちら

2006.6.14
 湯川恭敏先生を祝っての論文集『言語研究の射程』を刊行しました。加藤重広・吉田浩美編です。私が、担当しました。
湯川恭敏先生を祝っての論文集『言語研究の射程』を刊行しました。加藤重広・吉田浩美編です。私が、担当しました。
今回は、多岐にわたる言語が研究されているため、フォトレディで作りました。多言語のものでも、本来は印刷所に組んでもらって編集して作りたいと思っています。週末の言語学会から販売します。ぜひ、みな様お求め下さい。定価は8800円+税。発行部数は250部です。
『言語研究の射程』の詳細はこちら
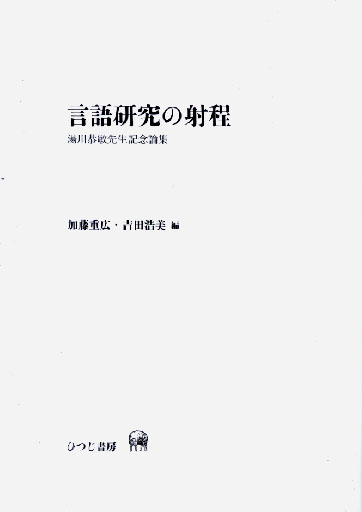
2006.6.12
 『アカデミック・ジャパニーズの挑戦』刊行のお祝いと加えて翌日の大学教育学会のラウンドテーブルの打ち合わせを行いました。
『アカデミック・ジャパニーズの挑戦』刊行のお祝いと加えて翌日の大学教育学会のラウンドテーブルの打ち合わせを行いました。
門倉、筒井、三宅の3人の編者に加えてラウンドテーブルのパネラーの加藤哲夫さん、高知大の吉倉先生も打ち合わせを兼ねてご一緒されました。『市民の日本語』を書かれた加藤さんのおかげで、『アカデミック・ジャパニーズ』は、大学人の主張にとどまらず、より市民に開かれるものになったと思います。もちろん、全ての論文が将来のアカデミックジャパニーズを考えるための必見の内容です。
『アカデミック・ジャパニーズの挑戦』の詳細はこちら
2006.6.9
研究書の刊行に向けて、本を作っていくときに、原稿の執筆の方法やルールなどについての要項が必要になります。この要項によって、本を作る作業の効率が大きく変わります。効率的にできれば、より内容に関わる余裕を持つことができます。言語学には特殊な用法もあり、例文を合わせたり、単純に本文と見出ししかない本と比べると「20倍」も大変です。できるだけよい執筆要項を提示することは編集にとって本当に重要なことなのです。執筆要項に加えて「赤字の入れ方」についてもアップしました。両方とも担当は、松原です。
執筆要項 6月に入っても刊行が続いています。『レキシコンフォーラムNO.2』(影山太郎編)刊行いたしました。担当は、松原です。
6月に入っても刊行が続いています。『レキシコンフォーラムNO.2』(影山太郎編)刊行いたしました。担当は、松原です。
『レキシコンフォーラム』は、語彙(単語)研究と、言語学各分野や言語の機械処理、心理学、脳科学、言語教育、辞書編纂など言語学以外の研究をも連携させるべく創刊されたレフリー付きのジャーナルです。今回の特集は「辞書と言語情報処理」。
『レキシコンフォーラムNO.2』の詳細はこちら
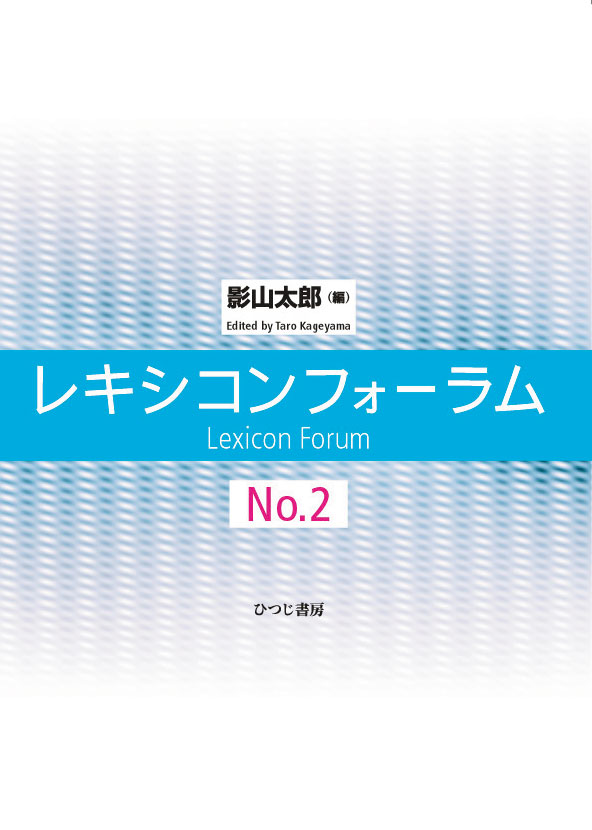
2006.6.8
ひつじ書房では、DVDによる日本語教材を編集する企画を検討しています。現在はまだ、企画段階ですが、実際にスタートしますとDVDの製作を行うことになります。DVDの製作・編集の経験のある方で、興味のある方は、ご連絡下さい。社員というよりも連携というかたちができればと思っています。
恐れ入りますが、打ち合わせもありますので、東京近郊の方とさせて下さい。こちらの連絡先は、toiawaseアットマークhituzi.co.jpです。担当は松本功です。
2006.6.6
 『アカデミック・ジャパニーズの挑戦』(門倉正美・筒井洋一・三宅和子編)刊行いたしました。担当は、田中です。
『アカデミック・ジャパニーズの挑戦』(門倉正美・筒井洋一・三宅和子編)刊行いたしました。担当は、田中です。
留学生のための日本語とは何かというところから、はじまったアカデミックジャパニーズという考えが、留学生という枠を超え、日本人学生という枠を超え、市民という考えにまで含んでいく。日本語の構造にとどまらず、日本人のコミュニケーション、これからのコミュニケーションへの道、ことばへの教育学を提案する。

『アカデミック・ジャパニーズの挑戦』の詳細はこちら
2006.6.2
 『日本語とジェンダー』(日本語ジェンダー学会編 佐々木瑞枝監修)刊行いたしました。担当は昨日に引き続き、宮島です。
『日本語とジェンダー』(日本語ジェンダー学会編 佐々木瑞枝監修)刊行いたしました。担当は昨日に引き続き、宮島です。
ジェンダー研究にとって、ことばの研究は重要ですが、これまで中村桃子さん以外にはあまりまとまったものはありませんでした。本書は、日本語とジェンダーについての画期的な基本書になると信じています。中村桃子さんも1章書いて下さっています。
日本語とジェンダー学会で販売されますので、そちらでご覧下さい。主要書店に並びますのは10日頃になります。ご予約ご注文いただけましたら、幸いです。
『日本語とジェンダー』の詳細はこちら
2006.6.1
 『草の根NPO運営術』(澤村明)刊行いたしました。担当は宮島です。
『草の根NPO運営術』(澤村明)刊行いたしました。担当は宮島です。
NPOは、市民生活の様々局面に対する市民の事業であるのが、あるべきすがたです。しかし、実際には悪いNPOと良いNPOが存在し、ひどい事件やばかばかしい事件も起きています。一方、良いNPOがきちんと運営できているかというと、難しいです。通常のビジネスよりもマネジメントが難しいといえるNPOをどのように運営したら、うまく行くのか。ヒント満載の本です。
ひつじ書房は新潟で開催されるNPO学会に参りますので、そちらでご覧下さい。
『草の根NPO運営術』の詳細はこちら
2006.5.26
 『問題な日本語』で有名な北原保雄先生の筑波大学退官を祝った『現代日本語文法 現象と理論のインタラクション』(矢澤真人・橋本修編)と文学研究の最先端『修辞的モダニズム−テクスト様式論の試み』(中村三春)を刊行しました。担当は松原です。
『問題な日本語』で有名な北原保雄先生の筑波大学退官を祝った『現代日本語文法 現象と理論のインタラクション』(矢澤真人・橋本修編)と文学研究の最先端『修辞的モダニズム−テクスト様式論の試み』(中村三春)を刊行しました。担当は松原です。
『現代日本語文法 現象と理論のインタラクション』は、現代日本語文法研究の分野で北原先生へのお祝いの書で、筑波大出身の若手・中堅の優れた論文が集結しています。
『修辞的モダニズム−テクスト様式論の試み』は、中村三春さんのひつじでの第2冊目の単著。1冊目は『フィクションの機構』で、日本近代文学研究の研究書としては画期的な文芸理論の書でした。その続編であり、理論によって実際の作品を扱いよりパワーアップした書です。
宮沢賢治、横光利一、スポーツ小説、百貨店小説を扱っています。ちなみに本文組版は、デザイナーの向井裕一さんで、とてもすばらしく仕上がっています。
『現代日本語文法 現象と理論のインタラクション』の詳細はこちら
『修辞的モダニズム−テクスト様式論の試み』の詳細はこちら
先週12日にお送りしました「ひつじ通信」が文字化けをしているとのご指摘を多くの方よりいただきました。文字が化けて読めないメールをお送りしてしまいましたことをお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。
Mac OS XのメールソフトEntrourageからお送りしておりますが、お送りするメールの文字コードをUNIコードでお送りしてしまいました。受信された方が、UNIコード対応のメールソフトでないと文が全て化けてしまいます。このようなメールをお送りしてしまいましたことをたいへん申し訳なく存じます。
ひつじ書房の代表者としてお詫び申し上げます。1月にも同様のことがあり、2度目であります。メールに対するひつじ書房全体の認識と体制を改善することが必要と痛感しています。メールで情報をお送りすることはとても重要なことと考えていますだけに根本的に体制を作り替えようと思います。

ひつじ書房の目録誌「未発」の14号ができました。今年は、56ページになり、昨年よりも12ページも多くなり、内容もさらに充実しています。
昨日から開催される日本語学会で配り始め、今月末にはお手元にお送りします。刊行情報はやはり紙で読んだ方がわかりやすいですし、探しやすいと思います。電子媒体は、ピンポイントで探すことができる点は便利ですが、トータルでは紙の方が優れています。
大学院に進学したり、言語研究に取り組みはじめた方で言語研究の最新の情報を知りたい方は、「未発」を送付しますので、送付先を教えて下さい。toiawaseアットマークhituzi.co.jpに、ご連絡先下さい。(お送り申し上げます方々のグループ名を「ひつじかい」とさせていただきました。)
あるいは案内と申し込み用紙をご覧になりたい方は次をご覧下さい。(pdfが開きます)ひつじかいのお知らせについて
ひつじ書房は、言語学・言語教育の学術書を編集・発行する出版社です。現在、企画・編集する書籍が増えています。秋から増員しているのですが、編集を外注せず、手を掛け丁寧に作っていますので、まだまだ人手不足の状態です。
人手不足を解消し、これからの本作りをスムーズに行うために、書籍編集者を募集(正社員)します。言語・日本語教育の分野に興味のある方で編集経験のある方を募集します。この分野が未経験の方でも、ご相談下さい。
編集者募集
これとは別に、書籍の表紙のデザインをしてくれる人を探しています。われと思う方は、どうぞご相談下さい。年間4冊くらいお願いすることになります。恐れ入りますが、打ち合わせもありますので、東京近郊の方とさせて下さい。こちらの連絡先は、toiawaseアットマークhituzi.co.jpです。
2006年オープンオフィスの概要が決まりました。昨年の研究書出版支援講座の中で、研究書を出版するということについてのご相談、ご質問を受け付けますオープンオフィスを行いました。とても好評でしたのでことしも行います。チラシを作りましたのでご覧下さい。オープンオフィスのチラシ。
大学も新学期が始まりました。後期の教科書採用のためのチラシを作りましたのでご覧下さい。ひつじ書房では、大学生向けの教科書も充実してきています。チラシはこちら。

東泉先生にお越し頂きました。本の刊行を祝ってささやかなお祝いの酒宴を開きました。東泉先生は、英文の著書を刊行する際にcopy-editingの専門家に文章を編集してもらったとのことです。ひつじとしては英語の研究書の刊行をよりきちんと行いたいを思っておりまして、東泉先生のご体験はとても参考になりました。
『From a Subordinate Clause to an Independent Clause』の詳細はこちら

『学びのエクササイズ認知言語学』、『対人関係構築のためのコミュニケーション入門』、『Corpus Studies on Japanese Kanji』の3点が同時にできました。担当は松本で、社長業といっしょに編集作業(+DTP 作業も)を進めたため、予定よりもかなり遅れてしまいました。
著者の方、お待ちいただいていた読者の方にはお詫び申し上げます。
『学びのエクササイズ認知言語学』の詳細はこちら
『対人関係構築のためのコミュニケーション入門』の詳細はこちら
『Corpus Studies on Japanese Kanji』の詳細はこちら
ひつじ書房では、学術振興会の研究成果公開促進費を受けて、研究書を刊行しています。昨年11月に学術振興会の研究成果公開促進費の申請をお手伝いしました。先頃、採択結果がでました。今年は40パーセントの採択率であったとのことですが、13件の内定をいただきました。多くの研究者の方の研究の出版をお手伝いできることはまことにうれしいことです。
本年も研究書出版の支援としてオープンオフィスを行う予定です。詳細が決まりましたら、公開いたしますのでご期待下さい。
 ひつじのメインの出版ラインとは違いますが、『離婚後の親子関係サポートブック』本日刊行しました。NPO WINKのシリーズで、本書で4冊目になります。本書は宮島が担当しました。
ひつじのメインの出版ラインとは違いますが、『離婚後の親子関係サポートブック』本日刊行しました。NPO WINKのシリーズで、本書で4冊目になります。本書は宮島が担当しました。
ひつじが出すので、ことばの分析の本ですかと聞かれることもありますが、そのままのストレートなものです。公共機関、NPOなどいろいろなサポート機関や図書館などにとっても必備の本です。

青柳宏先生の『日本語の助詞と機能範疇』ができました。担当は青山です。彼女の担当した研究書の2冊目です。ひつじ研究叢書(言語編)としては1冊目。「日本語を特徴づける「とりたて詞」を中心とした助詞や接辞がどのように仕組みで実現し、また解釈されるのかを、生成文法理論の立場から論じる」ものです。

『発話行為論的引用論の試み−引用されたダイクシスの考察』の著者の中園篤典先生が、ひつじ書房の事務所に来て下さいました。
『発話行為論的引用論の試み−引用されたダイクシスの考察』の詳細はこちら

ひつじ書房では、2006年入社式を行いました。今年は、河口靖子さんを新入社員として迎えました。折しも桜も満開で、入社式の後に記念撮影を行いました。
1年後、2年後、優れた出版人になってくれることと期待しています。若くて、新しいひつじ書房のスタッフをどうぞご指導くださいますようお願い申し上げます。スタッフ日誌にも河口が、近日登場しますので、ご期待下さい。

中田清一・秋元美晴先生たちの『ことばと文化をめぐって—外から見た日本語発見記』ができました。春らしいきれいな色に仕上がりました。内容は、2005年11月に恵泉女学園大学で行われたシンポジウム「日本のことばとこころ—外から視座」に基づいています。この本は、青山が担当した最初の本です。真ん中は、三美印刷さんの山岡さん。若いけれど有能で、ひつじ書房の担当をしてくれています。

永田高志先生のA Historical Study of Referent Honorifics in Japaneseができました。この本は和泉書院で出版されていた研究書の英語版です。「日本語の複雑な待遇表現を、社会言語学の視点から、海外の日本文学研究者や言語学者に紹介するために、和泉書院から出版した『第三者待遇表現史の研究』を英訳し、さらに日本語の敬語について概説を加筆したもの」です。担当は森脇です。
A Historical Study of Referent Honorificsの詳細はこちら

これから1月の間にかなりの本ができてきます。今年は去年よりも多くの本ができる予定になっています。たぶん、このままでは倉庫の空きスペースがなくなることが予想されましたので、倉庫を拡充しました。留守番の専務以外みんなで倉庫の本を移動しました。
ひつじの倉庫は、浅草のお寺の地下にあって、なかなか味のある独特な空間です。一度、倉庫見学、いかがですか?

『日本語とジェンダー』の監修者、佐々木瑞枝先生がひつじ書房にお寄り下さいました。
ジェンダーの問題は、社会的にも研究にとっても重要なテーマだと思います。しかしながら、このテーマに関わる研究は今までもありましたが、まとまったかたちでの論集というものは今まで存在しませんでした。新しい研究成果をこの春に出版します。

『発話行為的引用論の試み』ができました。引用についての新たな成果の発表です。いよいよ引用研究が進むことを祈ります。
この本で、ひつじ研究叢書(言語編)は41巻目となります。これを期に本文の文字組、表紙も箱も体裁を変えました。また、この本の担当の田中にとりましては、最初から編集しましたはじめての本です。さらに田中がひつじに来て1周年になりますので、その意味でも記念すべき本です。

『日本語存在表現の歴史』が製本所から届きました。金水敏先生のたいへんな労作であり、存在表現研究においては今後最も重要な書の1つになると思います。
ひつじ書房としては、この本は10年来の恋が実ったような感慨深い本です。待ち続けて、待ちぼうけて、待ち続けて、それでも最後は結ばれた人のよう。担当は松原梓で最後のところ、編集者としての本の仕上げを手伝いました。彼女の功績は大です。
となりは、今週、入社したばかりの河口靖子です。これからの成長を期待している新人です。

もうすぐ刊行する『ことばと文化をめぐって—外から見た日本語発見記』の出張校正に中田清一先生、秋元美晴先生がいらっしゃいました。恵泉女学園大学での講演会をもとに編んだ書籍です。
『ことばと文化をめぐって-外から見た日本語発見記』の詳細はこちら

『From a Subordinate Clause to an Independent Clause』を書かれた東泉裕子先生がいらっしゃいました。これから、学術振興会に直接お持ちになると言うことです。日英語の節の研究として画期的なものです。編集担当は宮島がいたしました。
From a Subordinate Clauseの詳細はこちら

英語の本が3冊届きました。とてもきれいに美しく仕上がりました。きれいな本は気持ちがよいです。
加野まきみ先生の『Lexical Borrowing and its Impact on English』、東泉裕子先生の『From a Subordinate Clause to an Independent Clause』、野村先生の『ModalP and Subjunctive Present』の3冊。野村先生の本は松本が担当し、他の2冊は宮島が担当しました。
From a Subordinate Clauseの詳細はこちら ModalPの詳細はこちら
『ポライトネスと英語教育』が製本所から届きました。先日、先生方が出張校正に来られたことを報告しましたが、かたちになって手元に届きました。担当は森脇です。「シリーズ言語学と言語教育」の表紙の青はきれいです。英語教育の世界で、ポライトネスの研究が盛んになり、広まることを祈っています。
 2006年春、ひつじ書房は、昨年にもまして、研究書を刊行して参ります。ホームページのこれからでる本のページを改訂しました。
2006年春、ひつじ書房は、昨年にもまして、研究書を刊行して参ります。ホームページのこれからでる本のページを改訂しました。
学術振興会の公開促進費の助成を受けて刊行する研究書も印刷の段階に入りました。来週から次々とできてきます。3月中に刊行する予定のものなども告知しています。どうぞご覧下さい
写真は小石川植物園の梅です。現在、半分くらい開花しています。
これは試験的な公開です。こちらのページは公開だけではなくインタラクティブなやりとりが可能な仕組みをめざしています。教科書を採用して下さった方へのTMなどのサポート資料・教案資料などを提供したり、お問い合わせにお答えしたりする予定です。まだ、学会開催情報のみの試験公開です。お気づきの点がありましたら、お教え下さい。

本日、『複合動詞・派生動詞の意味と統語 モジュール形態論から見た日英語の動詞形成』の著者の由本陽子先生が弊社を訪問して下さいました。本書は、新村出賞を受賞した研究書です。新村出賞受賞のささやかなお祝いをちかくのワインレストランでしました。おめでとうございます。
『複合動詞・派生動詞の意味と統語』の詳細はこちら
2月前半は、本作りの追い込みの季節です。本日、『ポライトネスと英語教育』の出張校正のために、重光由加先生と村田和代先生がひつじ書房にこられました。
明日までかかるかと思われた作業は終了しました。朝から、10時までかかりました。先生方お疲れ様でした。重光先生の娘さんも学校の後、夕方手伝いに。助かりました。
毎年、この時期は本作りのラッシュになるのですが、やはり、ことしも2月末、年度末に向けて本作りに邁進しています。ひつじ書房、創業以来の冊数を作っているといえるかもしれません。
研究書は、著者の研究の集大成です。短い期間でできるものではありません。研究をはじめた時からすれば、かなりの時間と労力を傾けてできあがっていくものです。刊行予告をだしてからだけでも、10年以上たっているのものもあります。読者の方にはお待たせしましたということになりますし、著者の方に対しては最後のプロセスをいっしょに仕上げているという感慨があります。
もう少しで、お届けすることができます。もう少しお待ち下さい。

寒い日が続いています。ひつじのメンバーは、冬生まれが多いのです。1月は松原で、2月は専務と松本。
春が待ち遠しいです。寒さにめげずにがんばります。梅が、そろそろ咲く頃でしょうか。植物園の梅が咲いたら、報告します。
ひつじ書房では、書籍編集者を募集しています。本を作るとともに、本を支える出版文化のルネッサンスを起こしていきませんか。
新しいことにチャレンジするやる気のあるあなたを求めています。新しい時代の編集者といっても難しく考える必要はありません。具体的なことに一歩一歩取り組んでいくことが、21世紀の新しい出版を創ります。まずは、ご応募下さい。

『アカデミックジャパニーズの挑戦』の編者の先生方が打ち合わせのためひつじ書房に来社されました。
アカデミックジャパニーズとはもともとは「大学で学ぶために必要な日本語力」のこと。本書では、アカデミックジャパニーズが、留学生への日本語教育の領域を越えて、「市民の日本語」へと展開していくための問題提起と教育実践を提案します。門倉正美先生、三宅和子先生、筒井洋一先生の熱い思いが込められた本が春の終わり頃にはできあがりそうです。

いただきましたのは昨年ですが、慶応義塾大学の大津由紀雄先生から、すてきなひつじのおきものをいただきました。すてきなひつじなので、今日、お披露目することにいたします。大津先生、ありがとうございました。
お正月あけですが、ひつじにとっては縁起物のような気がします。昨日、秋葉原で新しく購入したLUMIXのデジカメで撮った写真です。接写でもかなりきれいにとれます。
 2005年はたいへん、お世話になりました。2006年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。
2005年はたいへん、お世話になりました。2006年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。
2005年は、新村出賞3年連続の受賞、研究書出版支援講座の開催、株式会社化と多くの方に出資頂いての増資など、とても大きく飛躍した年でした。2006年はその上に立って、さらに発展する年といたしたいと思っています。
本年もどうぞよろしくご支援下さいますようお願い申し上げます。
房主より「あけましておめでとうございます」新村出賞3年連続について、紹介されています。朝日新聞を購読されている方は、12月24日の記事を、ぜひともご覧下さい。「ひと」の欄は2面です。
ひつじ書房にとって、とてもうれしいクリスマスプレゼントです。日本の言語学を代表する賞である新村出賞受賞を3年連続で行えたことがまずうれしいことですが、このように朝日新聞に取り上げてもらえたことも、うれしいことです。学術書の刊行についての記事はまれなことと思います。とても貴重な記事だと思います。今回の記事を励みに、いっそうこれからも学術書の刊行に全力をあげて取り組んでいきたいと思います。
この件についてのプレスリリースひつじ書房は、9月に有限会社から株式会社に組織変更を行いました。引き続き、12月6日付けで995万円の増資を行い、本日、法務局への登記が完了いたしました。(午前中に法務局に行きまして確認しました。)多くの著者の先生方、読者の方々、お取引先の方々が、今回、増資のお願いをお引き受けくださったおかげです。資本金が、2195万円になりました。あつく御礼申し上げます。
増資を受けまして、学術研究書の発行にいっそう精進してまいります。今後とも、どうぞご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
(株主になっていただい方へ 文面でのお礼をお送りいたしますのは、来週の頭になりますことをお知らせします。)
大津由紀雄先生が、朝日新聞の「親子で読もう科学の本:3 脳って?心って?」の中で、『探検!ことばの世界』を紹介して下さいました。先週の20日の朝日新聞に掲載されたものですが、朝日新聞のホームページにも掲載されましたので紹介します。
「心って何だろう、どこにあるんだろう。そんなことを考えて頭が痛くなったことはないでしょうか。専門家たちも頭を悩ましてきた、この問題にも、ようやくおぼろげながら手がかりが見えてきています。……」続きはこちら
27日、日本語文法学会が明海大学で開催され、ひつじ書房は土日とも出店いたしました。一日目のテーマが、アスペクトということであり、学会も盛況でした。(九州大学で開かれた英語学会よりも、成果がありました。)アスペクトの研究は、一段落と思われていました(?)が、今後もまた期待できそうですね。これで、学会出店・出張と学振の手続きに追われた11月の山をこえることができ、一段落しました。決算の手続きも済み、増資のお願いも先週発送を完了し、怒濤の11月をほぼのりきることができました。出張先で突然、研究室を訪問させていただいた先生方、学会でお目にかかったみな様に感謝です。
研究書の出版についての相談も再開しますので、どうぞお問い合わせください。
出版業界紙「新文化」(2005.11.5)に研究書出版支援講座についての記事を執筆しました。原稿執筆時の内容を掲載します。
先週、配信いたしましたメール通信に、文字化けがありましたことお詫びします。メールに使用した文字コードに不具合がありましたため、メールに文字化けが生じてしまいました。メール通信を読んで下さっている方に深くお詫び申し上げます。
担当者が、九州への出張から戻りましてから、もう一度、メールを送らせていただきます。申し訳ありませんが、来週までお待ち下さい。
 今年も、TCP2005ができました。大津由紀雄先生の編の生成文法派の言語心理学の論集です。毎年、英語学会の前に作るのですが、ことしも間に合いました。濃い赤の表紙です。(写真では光っていてよく見えないですね。学会でどうぞ手にとってご覧下さい。)
今年も、TCP2005ができました。大津由紀雄先生の編の生成文法派の言語心理学の論集です。毎年、英語学会の前に作るのですが、ことしも間に合いました。濃い赤の表紙です。(写真では光っていてよく見えないですね。学会でどうぞ手にとってご覧下さい。)
金曜日から、5名は学会出張にでます。日本語学会と英語学会が同時開催で、仙台と九州にわかれての出張です。松原は、仙台から東北の研究室回り、田中と森脇が九州から言語学会の開かれる広島へと向かいます。その合間をぬって、残ったスタッフが学振の書類を作成するのをアシストします。
記念撮影には、お祝いごとの意味もあります。森脇と青山が11月あたま、誕生日であり、松原は今日でひつじ2周年。とてもめでたいことでしょう。祝!
ひつじ書房は、研究者の方々の研究書の刊行を後押しています。その一つが出版助成の申請のお手伝いですが、その日本学術振興会の申請手続きの準備が大詰めを迎えています。
今まで、研究の内容について一度もことばを交わしたことのない研究者の方につきましては、申請のお手伝いをするかどうかを決めるためには時間がかかりますことを考えますと今年は、これからでは基本的にお受けできないと思います。時間が足りないことになります。簡単に言いますと次のようなプロセスが必要だからです。提案書送付→論文送付→プレゼンテーション→弊社で申請をするかどうかの決定→計画調書の送付→計画調書へのコメント→計画調書の完成、提出。このプロセスにたぶん最低3週間は必要です。あしからずご了解下さい。
今までに弊社のスタッフと研究内容についてことばを交わしたことがある研究者の方でもやはり2週間はかかりますので、来週一杯がデッドラインとなります。申請をお考えの方は、お急ぎ下さい。
 由本陽子先生の『複合動詞・派生動詞の意味と統語』が新村出(しんむらいずる)賞を受賞しました!ひつじ書房としては、3年連続の受賞となります。3年連続受賞というのは、驚愕すべき快挙です。この賞は、言語学の世界で大きな成果をあげた新村出を記念して作られた賞です。著者由本先生にお祝い申し上げるとともに、言語学の出版社としてうれしく、誇りに思います。
由本陽子先生の『複合動詞・派生動詞の意味と統語』が新村出(しんむらいずる)賞を受賞しました!ひつじ書房としては、3年連続の受賞となります。3年連続受賞というのは、驚愕すべき快挙です。この賞は、言語学の世界で大きな成果をあげた新村出を記念して作られた賞です。著者由本先生にお祝い申し上げるとともに、言語学の出版社としてうれしく、誇りに思います。
詳細はこちら。
昨年の受賞についての記事(『方言学的日本語史の方法』)・1昨年の受賞についての記事(『日本語修飾構造の語用論的研究』)
2005.10.19 『文と発話』ができました!この本は、画期的です。串田秀也・定延利之・伝康晴先生の編で、言語研究と社会学、情報処理の臨界領域の斬新な研究を集めています。たぶん、このシリーズによって新しい言語研究が切り開かれることになるでしょう。シリーズ第一巻目です。担当は森脇です。夜、札幌出張から帰ってきたところで、記念撮影しました。
『文と発話』ができました!この本は、画期的です。串田秀也・定延利之・伝康晴先生の編で、言語研究と社会学、情報処理の臨界領域の斬新な研究を集めています。たぶん、このシリーズによって新しい言語研究が切り開かれることになるでしょう。シリーズ第一巻目です。担当は森脇です。夜、札幌出張から帰ってきたところで、記念撮影しました。
詳細はこちら。表紙もきれいです。装幀は中山銀士さんです。
 英語の教科書です。ひつじ書房では、言語研究に関連するものは、刊行していますが、純然たる英語のtextbookは、はじめてです。
英語の教科書です。ひつじ書房では、言語研究に関連するものは、刊行していますが、純然たる英語のtextbookは、はじめてです。
アメリカ事情を英語で学ぶ。当たり前のテーマだと思われるかもしれませんが、内容はボランティアやNPO、公共図書館など、21世紀の市民生活に関わりの深いテーマに焦点をあて、英語で学ぶというものになっています。詳細はこちら。
ひつじ書房では、社会学、異文化コミュニケーション、パブリックコミュニケーション、談話分析、経営学、メディア研究、カルチュラルスタディズ、市民活動研究などの研究者による斬新なアメリカ事情のテキストを連続して刊行したいと思っています。ぜひ、みなさまのアイディアをお寄せいただければ幸いです。
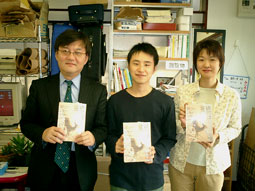 『接続2005』できました。特集は「環境というトポス」。文学研究から、歴史学、土木工学、音楽学まで、多彩な分野による共同研究。「環境」というと、まさに身近なモノであるし、そしてとらえどころがない。が、まず、できれば読んでいただきたい! 人文科学の共同戦線のほのかな可能性を感じることができるはず。詳細はこちら。
『接続2005』できました。特集は「環境というトポス」。文学研究から、歴史学、土木工学、音楽学まで、多彩な分野による共同研究。「環境」というと、まさに身近なモノであるし、そしてとらえどころがない。が、まず、できれば読んでいただきたい! 人文科学の共同戦線のほのかな可能性を感じることができるはず。詳細はこちら。
担当は森脇です。表紙もなかなか素敵。装幀はデザイナーの中山銀士さんです。
 『メディアとことば 2』できました。特集は「組み込まれるオーディエンス」。メディアにおけるディスコースは、テレビのニュース番組、児童雑誌の広告(コロコロコミックなど)、ネットのチャットであっても、オーディエンスを意識し組み込んでいる。組み込まれたオーディエンスに向けてのディスコースとは何か。詳細はこちら。
『メディアとことば 2』できました。特集は「組み込まれるオーディエンス」。メディアにおけるディスコースは、テレビのニュース番組、児童雑誌の広告(コロコロコミックなど)、ネットのチャットであっても、オーディエンスを意識し組み込んでいる。組み込まれたオーディエンスに向けてのディスコースとは何か。詳細はこちら。
担当は宮島です。宮島が引き継ぎまして完成させました。30日には龍谷大学で「メディアとことば研究会」が開催されます。詳細は「メディアとことば研究会」ホームページ。
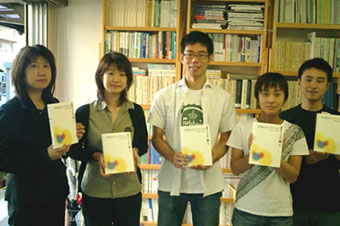 『講座社会言語科学第1巻 異文化とコミュニケーション』できました。第1巻は、社会言語学と異文化コミュニケーション研究の連携です。今後の異文化コミュニケーション研究の方向をしめす新しい内容になっています。この2つの研究をアクロバティックに連携させる試み。詳細はこちら。
『講座社会言語科学第1巻 異文化とコミュニケーション』できました。第1巻は、社会言語学と異文化コミュニケーション研究の連携です。今後の異文化コミュニケーション研究の方向をしめす新しい内容になっています。この2つの研究をアクロバティックに連携させる試み。詳細はこちら。
田中くんが、担当したはじめての本です。前任者から引き継ぐかたちでの担当となりましたが、最後の山場をきちんと切り抜けたと評価したいと思います。(担当1冊目の刊行を喜びたいと思います。祝! 房主)
ひつじ書房では、本づくりのスタッフを増員するために社員を募集します。小さな独立系の出版社ですので、編集の仕事は多岐にわたります。本作りの基礎から最後までの仕事をします。本を販売したり、プロモーションしたり、書店を回ったり、倉庫で在庫を数えたり、もろもろの仕事があります。本のプロセスにトータルに関わることができます。本というメディアにトータルに関わる中で、編集をしていきます。詳細は書籍編集社員募集から。
2005.9.16
9月7日(大安)にひつじ書房は社員総会(商法で言うところの社員は出資者のこと)で、株式会社になることを決議し、ひつじ書房は、16日、株式会社として登記申請を行いました。登記所で手続きを経て、登記されるには、10日ほどかかるとのことです。登記簿謄本には申請日である16日が株式会社になった日になるということです。感無量です。
これまでお世話になった方に感謝の意を表します。著者、読者、書店、印刷所、社員にありがとうと言いたいと思います。社長個人としては、専務である私の妻、私たち夫婦の両親、そして私の娘にもお礼をいいたいと思います。
日本学術振興会のホームページに平成18年度「研研究成果公開促進費」がアップされました(日付は9月1日)。平成18年度科学研究費補助金(研究成果公開促進費)公募要領・計画調書等のダウンロードページから、必要な書類を入手できます。詳細はこちら。ことしの締め切りは11月17日です。
ひつじ書房では、「研究成果公開促進費」の申請のお手伝いをいたしますが、これから、学会シーズンもはじまり、スタッフが出張するなど事務所を離れることも多くなりますので、できるだけ余裕を持ってご相談下さい。
 ひつじ書房創業15周年記念事業「研究書出版支援講座」を10日(土)に開催しました。仁田義雄先生、家入葉子先生にお話をしていただきました。参加者の方も大勢お越しいただきました。私も、研究書を学術出版社が出すと言うこと、助成金の申請の仕方について、お話申し上げました。少しでも参考になります部分があれば幸いです。ご参加下さいました方、お声をかけて下さった方にあつく御礼申し上げます。
ひつじ書房創業15周年記念事業「研究書出版支援講座」を10日(土)に開催しました。仁田義雄先生、家入葉子先生にお話をしていただきました。参加者の方も大勢お越しいただきました。私も、研究書を学術出版社が出すと言うこと、助成金の申請の仕方について、お話申し上げました。少しでも参考になります部分があれば幸いです。ご参加下さいました方、お声をかけて下さった方にあつく御礼申し上げます。
懇親会も、和やかに過ごすことができました。ご相談があってきてくださった先生方とも、お話しすることができたと思います。ほっとしました。出席して下さったある書店の方からは思いがけない提案をいただき、こうして「狼煙」をあげる意味はあるのだなとあらためて思いました。あらためて、報告申し上げます。取り急ぎのご報告です。
ひつじ書房創業15周年記念事業「研究書出版支援講座」が10日(土)に開催します。13時から17時まででプログラムは以下の通りです。ひつじ書房代表取締役社長・編集長松本功が、20年間の経験を総結集して、出版助成金の申請の仕方について伝授します。文字にはできない話しもでるかもしれません。17時半から、茗荷谷駅前のイタリアン、ラ・クローチェにて懇親会を開きます。懇親会は4000円(大学院生は2500円)です。どうぞふるってご参加下さい。
●プログラム
13時 ひつじ書房より開会の挨拶
13時10分〜35分 仁田義雄先生「研究書を出版すること」
13時35分〜14時 家入葉子先生「研究書の出版について−私がいま考えていること」
14時〜14時40分 松本功「研究者を支援する学術出版を目指して・出版助成金の申請について」
このあと、パネルディスカッションと質疑応答となります。
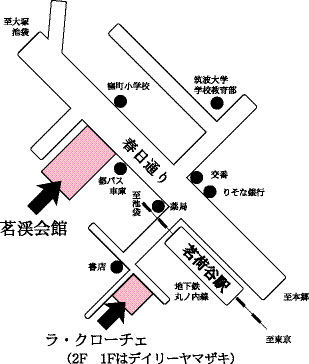
出版社が、研究者を支援するエポック的な講座になるでしょう。たぶん、学術出版社がこのような催しを行うのは、はじめてのことです。ご参加は講座、懇親会ともに受け付け中です。講座の方は無料です。当日、飛び込み参加も可です。toiawaseアットマークhituzi.co.jpまでお申し込み下さい。
 凡人社さんで店頭イベント、川口義一先生のミニ講演会を行いました。『成長する教師のための日本語教育ガイドブック』の刊行を記念して、9月3日に行いました。この本は、川口先生と横溝先生の共著ですが、今回は川口先生の講演でした。川口先生の講演とあって、凡人社さんの店の奥にしつらえられたミニ講演会場にたくさんのお客さんが来てくださいました。内容は本の内容を紹介するもので、1時間半という限られた時間の中で、全体像を掴むことのできるものであったと思います。実際の本の詳細はこちら。書店でも研修会でも本書はとても好評です。日本語教師を目指す方、すでになっている方にとっても役に立つ本だと思います。
凡人社さんで店頭イベント、川口義一先生のミニ講演会を行いました。『成長する教師のための日本語教育ガイドブック』の刊行を記念して、9月3日に行いました。この本は、川口先生と横溝先生の共著ですが、今回は川口先生の講演でした。川口先生の講演とあって、凡人社さんの店の奥にしつらえられたミニ講演会場にたくさんのお客さんが来てくださいました。内容は本の内容を紹介するもので、1時間半という限られた時間の中で、全体像を掴むことのできるものであったと思います。実際の本の詳細はこちら。書店でも研修会でも本書はとても好評です。日本語教師を目指す方、すでになっている方にとっても役に立つ本だと思います。
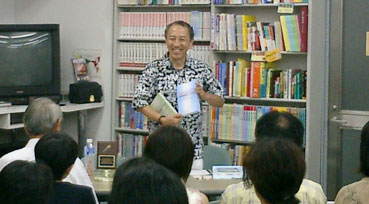
凡人社さんで店頭イベントは、ひつじ書房の著書の紹介が中心のものはずいぶん久しぶりです。この秋には山内先生の講演会もあります。ご期待下さい。
 ひつじ書房では、毎年8月末と正月明けに合宿を行っている。今年の春の成果の確認と反省、それと次の半年のスケジュールと仕事の割り振りなどの確認や検討を全員で行った。ことしは、ひつじ書房の倉庫から近いの「貞千代」という旅館。倉庫は浅草にあり、この旅館は、ROXの近くで中心街であるが、夜は静かであった。
ひつじ書房では、毎年8月末と正月明けに合宿を行っている。今年の春の成果の確認と反省、それと次の半年のスケジュールと仕事の割り振りなどの確認や検討を全員で行った。ことしは、ひつじ書房の倉庫から近いの「貞千代」という旅館。倉庫は浅草にあり、この旅館は、ROXの近くで中心街であるが、夜は静かであった。
会議の内容
2005.8.10
現在、オープンオフィスは多くの方にお越しいただいています。29日はまだ、余裕がありますので、お問い合わせ下さい。ひつじ書房では、9月10日に「研究書出版支援講座」を開催します。講座とそれに引き続き「懇親会」を行います。まだ、参加人数に余裕がありますので、どうぞご参加下さい。当日のご参加も可能ですが、できるだけ小社にご連絡くださいましたら、幸いです。連絡は、お電話がメールでお願いします。メールの場合には、toiawaseアットマークhituzi.co.jpです。どうぞよろしくお願い申し上げます。詳細は以下をご覧下さい。
詳細(html)・詳細(pdf)
2005.8.1
 『編集会議』9月号「本を売る技術」の座談会に松本功が出席しました。他の出版社の編集の方、2名といっしょの座談会。2社は、有名なそしてビジネス系に強い出版社。その中で、ひつじ書房は、専門書、学術書の出版社。話は合うのか、というのは心配でしたが、松本にとっても勉強になるよい座談会であったようです。テーマは、編集者自らが宣伝し、広報して本を売っていくと言うことで、意識して可能なかぎり広告塔になろうとしているという意味ではぴったりであるかも。
『編集会議』9月号「本を売る技術」の座談会に松本功が出席しました。他の出版社の編集の方、2名といっしょの座談会。2社は、有名なそしてビジネス系に強い出版社。その中で、ひつじ書房は、専門書、学術書の出版社。話は合うのか、というのは心配でしたが、松本にとっても勉強になるよい座談会であったようです。テーマは、編集者自らが宣伝し、広報して本を売っていくと言うことで、意識して可能なかぎり広告塔になろうとしているという意味ではぴったりであるかも。
詳細はこちら
2005.7.21
 『複合動詞・派生動詞の意味と統語』が刊行されました。著者は、大阪大学の由本陽子先生です。副題は、「モジュール形態論から見た日英語の動詞形式」で、語彙研究の最先端の内容です。複合動詞の研究という点では、英語教育にも参考になるものです。
『複合動詞・派生動詞の意味と統語』が刊行されました。著者は、大阪大学の由本陽子先生です。副題は、「モジュール形態論から見た日英語の動詞形式」で、語彙研究の最先端の内容です。複合動詞の研究という点では、英語教育にも参考になるものです。
この本は、割付から担当したという意味でひつじの新人森脇くんが作ったはじめての本です。(ご苦労様。)ひつじ研究叢書(言語編)として、第40巻にあたり、ひつじ書房として記念すべき本でもあります。
2005.7.20
ひつじ書房が、事務局をつとめているビジネス支援図書館推進協議会のHPがリニューアルしました。事務局を運営しておりますのは、ひつじ書房の代表の松本の提案したことがきっかけで、この活動が立ち上がったという縁があるからです。ビジネス支援図書館のできた経緯(房主の日誌)
2005.7.14
 12日、『広げる知の世界』が、中日新聞で取り上げられました。東京では中日新聞を手に入れることができないのですが、「自分の20歳の息子に読ませたいので注文したい」という母親の方のお電話でわかりました。ありがたいことです。京都新聞、西日本新聞などでも紹介されています。内容の詳細はこちら。内容は、いわゆる基礎ゼミ、スタディスキルの本です。
12日、『広げる知の世界』が、中日新聞で取り上げられました。東京では中日新聞を手に入れることができないのですが、「自分の20歳の息子に読ませたいので注文したい」という母親の方のお電話でわかりました。ありがたいことです。京都新聞、西日本新聞などでも紹介されています。内容の詳細はこちら。内容は、いわゆる基礎ゼミ、スタディスキルの本です。 3年間、ご苦労様。ひつじ書房を若くして中心で支えてくれた足立さんが、7月半ばに退職するということで、6月30日、浅草の倉庫の整理の後、浅草の雷門のそばの和食屋さんで送別会を行いました。
3年間、ご苦労様。ひつじ書房を若くして中心で支えてくれた足立さんが、7月半ばに退職するということで、6月30日、浅草の倉庫の整理の後、浅草の雷門のそばの和食屋さんで送別会を行いました。 『日本近代語研究4』、『OPIの考えに基づいた日本語教授法』が刊行されました。『日本近代語研究4』は日本近代語研究の第4巻目で飛田良文先生の古希記念のお祝いの巻となっています。『OPIの考えに基づいた日本語教授法』は、OPIの主要メンバーの一人、山内博之先生によるOPIについての本であると同時に『ACTFL-OPI入門』(アルク)より一歩進んだOPIの内容の紹介、実践方法を紹介しています。
『日本近代語研究4』、『OPIの考えに基づいた日本語教授法』が刊行されました。『日本近代語研究4』は日本近代語研究の第4巻目で飛田良文先生の古希記念のお祝いの巻となっています。『OPIの考えに基づいた日本語教授法』は、OPIの主要メンバーの一人、山内博之先生によるOPIについての本であると同時に『ACTFL-OPI入門』(アルク)より一歩進んだOPIの内容の紹介、実践方法を紹介しています。 3月に刊行しました『第二言語習得とアイデンティティ』がコミュニケーション学会奨励賞受賞しました。社会言語科学会や日本語教育学会に出店した際にもとても評判がよく、多くの研究者が手にとって見て、買って下さいます。(画像は窪田先生です。私の携帯電話のカメラでとりましたので、あまり鮮明でなくて申し訳ありません。)
3月に刊行しました『第二言語習得とアイデンティティ』がコミュニケーション学会奨励賞受賞しました。社会言語科学会や日本語教育学会に出店した際にもとても評判がよく、多くの研究者が手にとって見て、買って下さいます。(画像は窪田先生です。私の携帯電話のカメラでとりましたので、あまり鮮明でなくて申し訳ありません。) 甲南大学で開かれました日本語学会からの出張から戻ってきましたら、『広げる知の世界 大学でのまなびのレッスン』、できて届いていました。シナノさんに作ってもらいました。同志社大学の北尾謙治先生を中心として9名の先生方にご執筆いただきました。
甲南大学で開かれました日本語学会からの出張から戻ってきましたら、『広げる知の世界 大学でのまなびのレッスン』、できて届いていました。シナノさんに作ってもらいました。同志社大学の北尾謙治先生を中心として9名の先生方にご執筆いただきました。 『成長する教師のための日本語教育ガイドブック』(上下巻)できました。川口義一先生と横溝紳一郎先生による楽しい日本語教育のガイドブックです。松原梓が担当しました。大きな山でしたが、乗り切ることができましたことをうれしく思います。祝!発行。
『成長する教師のための日本語教育ガイドブック』(上下巻)できました。川口義一先生と横溝紳一郎先生による楽しい日本語教育のガイドブックです。松原梓が担当しました。大きな山でしたが、乗り切ることができましたことをうれしく思います。祝!発行。 『未発』13号、15周年のポスターできました。『未発』は、「みはつ」と呼びます。(今までに発せられたことのない発問という意味とその研究をひつじから発信するという2つの意味を掛けています。)
『未発』13号、15周年のポスターできました。『未発』は、「みはつ」と呼びます。(今までに発せられたことのない発問という意味とその研究をひつじから発信するという2つの意味を掛けています。) 学会前に、学会に間に合わせようと本を一生懸命作っています。講座社会言語科学第2巻「メディア」(橋元良明編)が、本日、田中製本から届きました。
学会前に、学会に間に合わせようと本を一生懸命作っています。講座社会言語科学第2巻「メディア」(橋元良明編)が、本日、田中製本から届きました。 まもなく「未発13号」できます。昨日、印刷所にデータを渡したところです。来週の土日の日本語教育学会までに、印刷ができあがります。
まもなく「未発13号」できます。昨日、印刷所にデータを渡したところです。来週の土日の日本語教育学会までに、印刷ができあがります。 関西大学の牧野由香里先生にきていただいて、社員が「議論のデザイン」ワークショップを行いました。午後1時から6時までの5時間。ご提案頂いたときのことば。「この試みを市民教育の基礎づくりとすることができれば、私にとって(そして恐らくひつじ書房さんにとっても)有益な時間となるだろうと考えました。」参加した社員にとっても有意義なものであったにちがいない。牧野さんは、「コミュニケーション能力」ということを副業ではなく、専門に研究している研究者。牧野由香里先生のHPはこちら
関西大学の牧野由香里先生にきていただいて、社員が「議論のデザイン」ワークショップを行いました。午後1時から6時までの5時間。ご提案頂いたときのことば。「この試みを市民教育の基礎づくりとすることができれば、私にとって(そして恐らくひつじ書房さんにとっても)有益な時間となるだろうと考えました。」参加した社員にとっても有意義なものであったにちがいない。牧野さんは、「コミュニケーション能力」ということを副業ではなく、専門に研究している研究者。牧野由香里先生のHPはこちら 高橋太郎先生が中心となって書かれた『日本語の文法』が、できました! 日本語の文法の全体について、学習者向けにわかりやすく書かれている本でとても優れたものです。今まで、私家版というかたちで出されていましたが、それをひつじ書房から出版したものです。日本語の文法を知ろうとしたときに最初にすすめられる内容です。
高橋太郎先生が中心となって書かれた『日本語の文法』が、できました! 日本語の文法の全体について、学習者向けにわかりやすく書かれている本でとても優れたものです。今まで、私家版というかたちで出されていましたが、それをひつじ書房から出版したものです。日本語の文法を知ろうとしたときに最初にすすめられる内容です。 『離婚家庭の面接交渉実態調査』(NPO法人WINK 新川てるえ 編)の編著者の新川てるえさんが、ひつじ書房を訪問されました。プロモーションの打ち合わせのあとで、担当者の宮島紘子と。NPO法人WINK
『離婚家庭の面接交渉実態調査』(NPO法人WINK 新川てるえ 編)の編著者の新川てるえさんが、ひつじ書房を訪問されました。プロモーションの打ち合わせのあとで、担当者の宮島紘子と。NPO法人WINK 4月も半ばを過ぎました。茗荷谷の桜ですが、ソメイヨシノは、ほぼ散ってしまいましたが、サトザクラは今が満開です。小石川植物園は、先週、満開でした。(桜の下でのひつじの面々)
4月も半ばを過ぎました。茗荷谷の桜ですが、ソメイヨシノは、ほぼ散ってしまいましたが、サトザクラは今が満開です。小石川植物園は、先週、満開でした。(桜の下でのひつじの面々) 『情報収集・問題解決のための図書館ナレッジガイドブック 類縁機関名簿2005』刊行しました。東京都立中央図書館が集めた情報源をまとめたものです。2003年版に続く、2005年版の刊行です。この2年間に変更された機関名で更新していること、機関数が40ほど増え、452機関が収録されていることなど、いっそう充実しています。何か調べたいと思ったとき、ご活用ください。情報源の定番です。
『情報収集・問題解決のための図書館ナレッジガイドブック 類縁機関名簿2005』刊行しました。東京都立中央図書館が集めた情報源をまとめたものです。2003年版に続く、2005年版の刊行です。この2年間に変更された機関名で更新していること、機関数が40ほど増え、452機関が収録されていることなど、いっそう充実しています。何か調べたいと思ったとき、ご活用ください。情報源の定番です。 4月に入りまして、暖かくなってまいりました。近所の桜も3分咲きです。だからというわけではないのですが、谷口一美先生が、事務所を訪問してくださいました。谷口先生は、認知言語学の若手のホープです。松原が、担当しました。本書は、2003年に提出された学位論文が元になっています。詳細はこちら。
4月に入りまして、暖かくなってまいりました。近所の桜も3分咲きです。だからというわけではないのですが、谷口一美先生が、事務所を訪問してくださいました。谷口先生は、認知言語学の若手のホープです。松原が、担当しました。本書は、2003年に提出された学位論文が元になっています。詳細はこちら。 1月に入りましたひつじ書房としては新人である宮島紘子が担当しました『副詞的表現をめぐって』と『離婚家族の面接交渉実態調査』が刊行できました。『副詞的表現をめぐって』は、神奈川大学の言語研究センターの研究者が中心になって作られたものです。詳細はこちら。『離婚家族の面接交渉実態調査』は、NPO法人Wink(新川てるえ代表)が、行った調査をまとめたものになっています。調査報告は、東京ウイメンズプラザの民間活動助成金対象事業となっています。
1月に入りましたひつじ書房としては新人である宮島紘子が担当しました『副詞的表現をめぐって』と『離婚家族の面接交渉実態調査』が刊行できました。『副詞的表現をめぐって』は、神奈川大学の言語研究センターの研究者が中心になって作られたものです。詳細はこちら。『離婚家族の面接交渉実態調査』は、NPO法人Wink(新川てるえ代表)が、行った調査をまとめたものになっています。調査報告は、東京ウイメンズプラザの民間活動助成金対象事業となっています。
 『弟二言語習得とアイデンティティ』と『講座社会言語科学 5巻 社会・行動システム』ができました。2冊とも足立が担当しました。『講座社会言語科学』は、社会言語科学会の5周年を記念して、企画したものです。社会言語科学会の扱っているフィールドは、従来の言語研究よりも広いジャンルですが、言語研究にとって重要なものです。その研究の最先端の部分の見取り図が得られます。『社会・行動システム』の詳細はこちら、
『弟二言語習得とアイデンティティ』と『講座社会言語科学 5巻 社会・行動システム』ができました。2冊とも足立が担当しました。『講座社会言語科学』は、社会言語科学会の5周年を記念して、企画したものです。社会言語科学会の扱っているフィールドは、従来の言語研究よりも広いジャンルですが、言語研究にとって重要なものです。その研究の最先端の部分の見取り図が得られます。『社会・行動システム』の詳細はこちら、
 『ピアで学ぶ大学生の日本語表現』著者の方にお越しいただきました。日本語表現法のテキストとしても、スタディスキルの本としても、ピア活動の実践の本としても、画期的な本です。その本を書いて頂いた先生方で日本にいらっしゃる方にお越しいただきました。
『ピアで学ぶ大学生の日本語表現』著者の方にお越しいただきました。日本語表現法のテキストとしても、スタディスキルの本としても、ピア活動の実践の本としても、画期的な本です。その本を書いて頂いた先生方で日本にいらっしゃる方にお越しいただきました。 遅れておりました『文科系ストレイシープのための研究生活ガイド』と『日仏対照現代日本語表現文型』をやっと刊行しました。『文科系ストレイシープ』は、研究生活をこれから進めようとしている大学院生のためのガイドブックです。こちらは谷川と松原の担当です。表紙もしゃれたものに仕上がっています。
遅れておりました『文科系ストレイシープのための研究生活ガイド』と『日仏対照現代日本語表現文型』をやっと刊行しました。『文科系ストレイシープ』は、研究生活をこれから進めようとしている大学院生のためのガイドブックです。こちらは谷川と松原の担当です。表紙もしゃれたものに仕上がっています。
 『日仏対照』は、最初は北村が担当し、最後は松本が作りました。日本語を学ぶフランス人の方、フランス語を学ぶ日本人の両方に役に立つ内容です。
『日仏対照』は、最初は北村が担当し、最後は松本が作りました。日本語を学ぶフランス人の方、フランス語を学ぶ日本人の両方に役に立つ内容です。
 『日本語述語の統語構造と語形成』の著者の外崎淑子先生が事務所を訪問してくださいました。足立が担当しました。無事、刊行することができまして、訪問してくださいました。本の内容はこちら
『日本語述語の統語構造と語形成』の著者の外崎淑子先生が事務所を訪問してくださいました。足立が担当しました。無事、刊行することができまして、訪問してくださいました。本の内容はこちら 『ピアで学ぶ大学生の日本語表現』が、とうとうできました。ピアというのは、仲間のことです。仲間で学ぶことを組み込んだ画期的でユニークな表現法のテキストになっていると思います。本としても、きれいでよい本になったと思います。ぜひとも、書店で手にとってご覧下さい。とは申し上げますが、どこの書店でも並んでいるというわけではないので、申し訳ないですが、表現法の本をきちんと置いているところにはある、というようにきちんと営業したいと思います。
『ピアで学ぶ大学生の日本語表現』が、とうとうできました。ピアというのは、仲間のことです。仲間で学ぶことを組み込んだ画期的でユニークな表現法のテキストになっていると思います。本としても、きれいでよい本になったと思います。ぜひとも、書店で手にとってご覧下さい。とは申し上げますが、どこの書店でも並んでいるというわけではないので、申し訳ないですが、表現法の本をきちんと置いているところにはある、というようにきちんと営業したいと思います。
 風邪で寝込んでいたので、記念撮影ができなかった松原が担当した本を紹介します。谷口先生の『事態概念の記号化に関する認知言語学的研究』です。谷口先生の『事態概念の記号化に関する認知言語学的研究』もできました。谷口先生は、認知言語学の若手のホープといえるでしょう。柳田優子先生のThe Syntax of FOCUS and WH-Questions in Japanese。日本の古代語において、WHの移動があることを指摘したもっとも早い研究です。
風邪で寝込んでいたので、記念撮影ができなかった松原が担当した本を紹介します。谷口先生の『事態概念の記号化に関する認知言語学的研究』です。谷口先生の『事態概念の記号化に関する認知言語学的研究』もできました。谷口先生は、認知言語学の若手のホープといえるでしょう。柳田優子先生のThe Syntax of FOCUS and WH-Questions in Japanese。日本の古代語において、WHの移動があることを指摘したもっとも早い研究です。
『言語表現ことはじめ』も刊行になりました。こちらは、大学での日本語表現の授業を切り開いた筒井洋一先生のどのように日本語表現科目を作ってきたかのルポ的ブックレット
 小野正樹先生の『日本語態度動詞文の情報構造』ができました。北村直子と大作光子が担当いたしました。大作にとっては、担当したはじめての本です。★
小野正樹先生の『日本語態度動詞文の情報構造』ができました。北村直子と大作光子が担当いたしました。大作にとっては、担当したはじめての本です。★ 宮崎和人先生の『現代日本語の疑問表現』ができました。足立綾子が担当いたしました。宮崎和人先生の書かれた博士論文を土台にしたものです。疑問表現研究での定番になる内容の研究書だと思います。
宮崎和人先生の『現代日本語の疑問表現』ができました。足立綾子が担当いたしました。宮崎和人先生の書かれた博士論文を土台にしたものです。疑問表現研究での定番になる内容の研究書だと思います。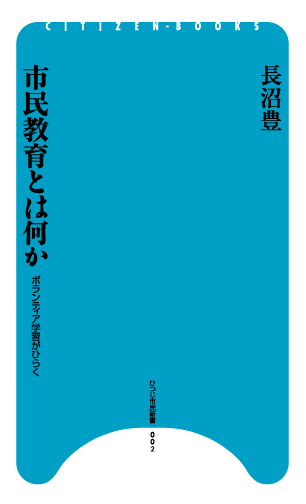 長沼豊先生の『市民教育とはなにか』が、明海大学の入試問題に使用されました。市民教育、ボランティアというものを考えることが、大学生になる学生さんに重要であるということの判断であると思われます。
長沼豊先生の『市民教育とはなにか』が、明海大学の入試問題に使用されました。市民教育、ボランティアというものを考えることが、大学生になる学生さんに重要であるということの判断であると思われます。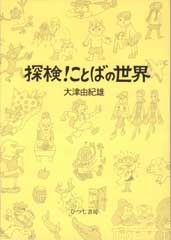 大津由紀雄先生の『探検!ことばの世界』を刊行しまた。元々はNHK出版から刊行されていたものですが、それがご縁がありまして、ひつじ書房から刊行となりました。本文の挿し絵にNHK版でイラストレーターとしてデビューし、その後、人気イラストレーターになった早乙女民さんのイラストを全面的にフィーチャーしました。大津先生のことばへの問いかけと合致した面白いイラストが満載です。もちろん、本文も分かりやすく面白い内容で、高校生でもだれでもことばのおもしろさを感じることができるでしょう。
探検!ことばの世界。詳細はこちら(目次)
大津由紀雄先生の『探検!ことばの世界』を刊行しまた。元々はNHK出版から刊行されていたものですが、それがご縁がありまして、ひつじ書房から刊行となりました。本文の挿し絵にNHK版でイラストレーターとしてデビューし、その後、人気イラストレーターになった早乙女民さんのイラストを全面的にフィーチャーしました。大津先生のことばへの問いかけと合致した面白いイラストが満載です。もちろん、本文も分かりやすく面白い内容で、高校生でもだれでもことばのおもしろさを感じることができるでしょう。
探検!ことばの世界。詳細はこちら(目次)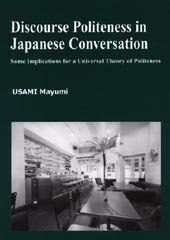 しばらく、お待たせいたしました日本語のポライトネス研究を前進させた本書を重版いたしました。宇佐美まゆみ著の名著です。
しばらく、お待たせいたしました日本語のポライトネス研究を前進させた本書を重版いたしました。宇佐美まゆみ著の名著です。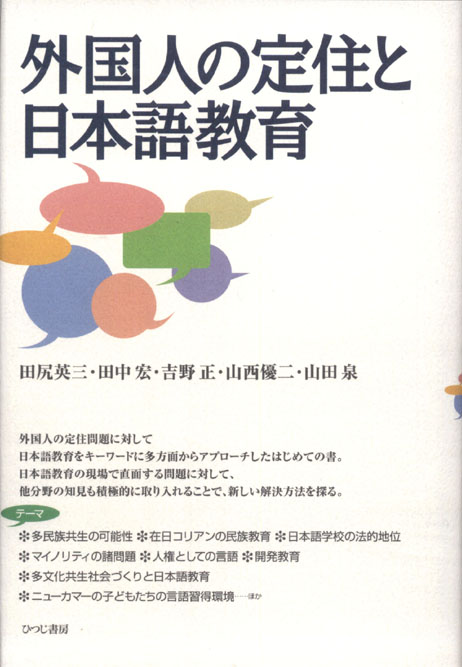 これまでの日本語教育ではあまり語られなかった外国人の定住問題についての基本的な文献。異文化との共生、多文化社会を考え、日本社会が外国人にとっても、日本人にとっても住み易い国、街になるためにどのようなことを考えたらよいのかを示唆してくれる本。
これまでの日本語教育ではあまり語られなかった外国人の定住問題についての基本的な文献。異文化との共生、多文化社会を考え、日本社会が外国人にとっても、日本人にとっても住み易い国、街になるためにどのようなことを考えたらよいのかを示唆してくれる本。
 2001年偶然の幸運から発見された小林勝氏のラジオドラマ台本。この台本をもとに、戦時中の話し言葉を研究。音声資料がほとんど残っていない時代の貴重な資料である。つまり、昭和初期の日本語を研究するためのもっとも基本的な文献が発掘され、また、その研究がスタートしたということである。さらに、ラジオの言語という点でも、本書はかつてないものと言うことができる。
2001年偶然の幸運から発見された小林勝氏のラジオドラマ台本。この台本をもとに、戦時中の話し言葉を研究。音声資料がほとんど残っていない時代の貴重な資料である。つまり、昭和初期の日本語を研究するためのもっとも基本的な文献が発掘され、また、その研究がスタートしたということである。さらに、ラジオの言語という点でも、本書はかつてないものと言うことができる。
 佐藤滋・堀江薫・中村渉編『対照言語学の新展開』が、刊行になりました。ご予約いただいた方にはたいへん、お待たせいたしました。著者30名、530ページの大著です。分量が多いので、本文は12級で組んでいます。対照言語学の研究における最新の内容です。本書は、マチネスタッフの谷川が担当しました。内容の詳細は、近日アップします。(出荷は、8月に入ってからになります。)
佐藤滋・堀江薫・中村渉編『対照言語学の新展開』が、刊行になりました。ご予約いただいた方にはたいへん、お待たせいたしました。著者30名、530ページの大著です。分量が多いので、本文は12級で組んでいます。対照言語学の研究における最新の内容です。本書は、マチネスタッフの谷川が担当しました。内容の詳細は、近日アップします。(出荷は、8月に入ってからになります。)
 インタビューはこちら。
インタビューはこちら。 ひつじサロン、昨年の10月から半年ぶりで開催しました。今回は京北学園学校図書館の川真田恭子さん。
ひつじサロン、昨年の10月から半年ぶりで開催しました。今回は京北学園学校図書館の川真田恭子さん。 『未発』11号できました。言語関係を専門としている方に発送しはじめました。今週末に届くと思いますので、ぜひご覧の上、お求め下さい。
『未発』11号できました。言語関係を専門としている方に発送しはじめました。今週末に届くと思いますので、ぜひご覧の上、お求め下さい。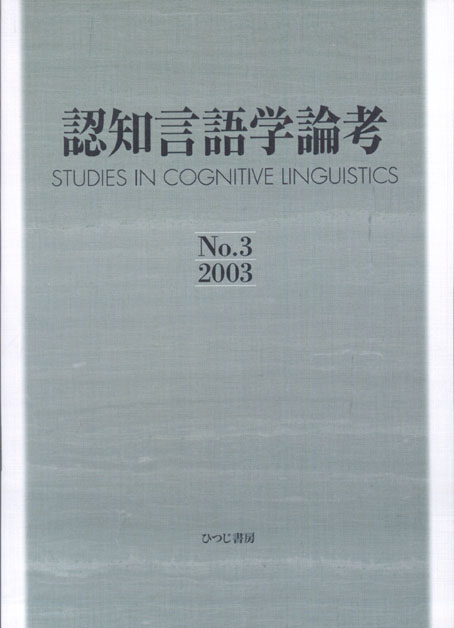


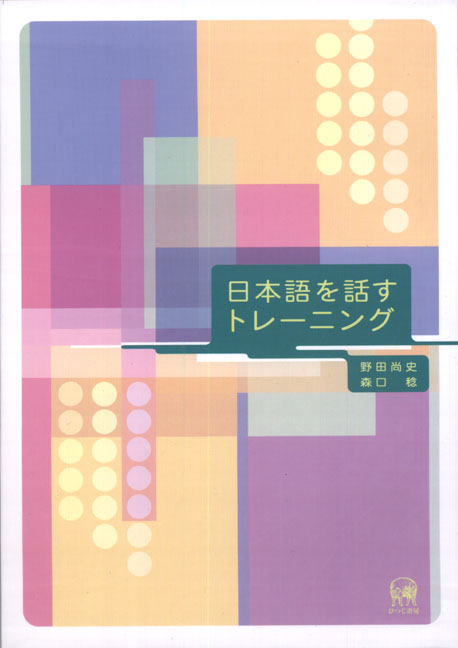 お待たせしました! 『日本語を話すトレーニング』ようやくできました。かならずしも良い例とはいえないかもしれない「話している実例」が付属CDについています。実際に話してみて、話している例を聞いて、自分たちで話し方を考えていく、内容です。
お待たせしました! 『日本語を話すトレーニング』ようやくできました。かならずしも良い例とはいえないかもしれない「話している実例」が付属CDについています。実際に話してみて、話している例を聞いて、自分たちで話し方を考えていく、内容です。









神戸学生青年センターの恒例、第7回古本市がまもなく開催。全国から古本を集めて、その市での古本の売り上げから、アジアからの留学生に奨学金を渡す六甲奨学基金。詳しくは、
古本市の案内をご覧下さい。古本の受付は3月1日から31日まで。この時期、引っ越しされる方はぜひご協力下さい。
2004.2.15
ひつじ書房房主が、「図書新聞」に書評特区4回目を編集、掲載しました。
『出版ルネッサンス』の書評を房主の日誌に書きました。
工業生産物と知的なコンテンツの産業としての違いが理解できていない『出版ルネッサンス』ご覧下さい。
-----
中略
-----
2003.8.17
 日誌の目次
日誌の目次
前田雅之さんによる『物語・オーラリティ・共同体』(兵藤裕己)への書評。かなりの長文で、非常に丁寧でかつ核心をついた書評になっています。優れた書評です。『物語・オーラリティ・共同体』は、文化研究ですがカルチュラルスタディーズとは立場が微妙に違っています。私は、カルスタは社会学的であり、『物語・オーラリティ・共同体』は文学的だと思います。この文学的な視点は悪くないと思っています。それは、対象に対する愛憎する気持ちと言っていいではないかと思います。対象を批評する時に、愛と憎しみの複雑な視点を持っています。10年に1冊の優れた文学研究書だと思いますので、どうぞお買い求め下さい。
『文学』の目次
online書店で注文する場合
2004.2.2
■■ひつじ書房★通信 2004.1.30■■発行しました。「なぜ、編集というスキルがプロフェッショナルに思われないか」他。
2004.1.26
ひつじ書房房主が、「エコノミスト」2月3日号にビジネス支援図書館について執筆しました。
インターネットが普及した現在でも、図書館には重要な情報が詰まっている。日本でも公共図書館がビジネス支援に取り組み始めた。続きは「エコノミスト」にて
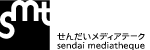 主催 仙台発<文化・市民活動情報>見本市「活動を育む情報拠点とは?」で基調講演をします。
主催 仙台発<文化・市民活動情報>見本市「活動を育む情報拠点とは?」で基調講演をします。
『年金』できました。割付は私がしましたが、校正はインターンの藤岡くんが行いました。写真は印刷所のシナノの小島さん。シナノさんとは実は、ゆかりがありまして…以下


ひつじ書房は、NPO関係の本を出していきたいと思っています。NPOと年金というのは?と思われるかもしれません。しかしながら、二つの点で、強く関わっています。ひとつは、著者の渡部記安先生は、ご自身でNPOの法人格で研究所を作っています。これは市民のために年金についての情報公開し、調査研究を行う機関です。情報発信型のNPOを支援することは、もともとの願いです。二つ目として、内容が市民にとって重要であるということです。日経新聞などでは401Kを日本の保険制度を批判するために、かなり持ち上げていますが、実際どうなのか、エンロンはどうだったのか、重要な内容でありながら、伝えられていないこと、それを伝えることも市民にとって重要であり、そのことを支援したいと思いました。米国の公的年金改革に関する著者の調査分析は、現時点では最も最新かつ詳細であり、わが国の2004年公的年金改革にも非常に有益な情報です。
4600円+税 A5 328頁
ISBN4-89476-208-0
2004.1.7
「ひつじ書房★通信」は、無料のメールマガジンです。月に1回ほどの配信です。内容は、ひつじ書房の活動全般についてお知らせするメール新聞です。基本的に代表取締役の松本か、社員が名刺を交換させていただいた方にお送りしています。今後、メールマガジン発行サイトから、登録ができるようにしようと思っています。
ひつじ書房★通信 2004.1
2004.1.1
あけましておめでとうございます。
2003.12.23
 社会学会の会員の方向けに、メールをお送りいたしました。まことに失礼なこととは存じております。今回は礼を失していても、お伝えしたいことがあったのです。弊社の刊行しております『接続』は、研究同人の方との共同で刊行しています。この「雑誌」には、旧来の「大学知」を越えるための様々な地道な試みが含まれています。内容の点ではすばらしいものです。ただ、問題は、臨界的であり脱境界的な考察であるために、プロの研究者から購買されていません。webcatでの検索では、5件の大学図書館にしか、所蔵されていませんでした。これはおかしい。従来の人文学のマイナーチェンジのようなものは、わかりやすい故か、そこそこ売れているのにも関わらず、これはおかしなことです。私は、『接続』は新しい人文的な研究、いわば臨床人文学とでも呼びうる領域への危険な—安全の保障されていない—旅であると思います。未だ受け入れたれていない行動です。その行動をつたえるための方法がメールしかありませんでした。このようなゲリラ的な告知方法をとりましたことを深くお詫びします。(房主)
社会学会の会員の方向けに、メールをお送りいたしました。まことに失礼なこととは存じております。今回は礼を失していても、お伝えしたいことがあったのです。弊社の刊行しております『接続』は、研究同人の方との共同で刊行しています。この「雑誌」には、旧来の「大学知」を越えるための様々な地道な試みが含まれています。内容の点ではすばらしいものです。ただ、問題は、臨界的であり脱境界的な考察であるために、プロの研究者から購買されていません。webcatでの検索では、5件の大学図書館にしか、所蔵されていませんでした。これはおかしい。従来の人文学のマイナーチェンジのようなものは、わかりやすい故か、そこそこ売れているのにも関わらず、これはおかしなことです。私は、『接続』は新しい人文的な研究、いわば臨床人文学とでも呼びうる領域への危険な—安全の保障されていない—旅であると思います。未だ受け入れたれていない行動です。その行動をつたえるための方法がメールしかありませんでした。このようなゲリラ的な告知方法をとりましたことを深くお詫びします。(房主)
 お待たせしました。『接続2003』刊行しました。今回の表紙は、海に近い都市です。さて、どこなのでしょうか。テーマは「越境する都市」に即したかっこよい装丁になっています。
お待たせしました。『接続2003』刊行しました。今回の表紙は、海に近い都市です。さて、どこなのでしょうか。テーマは「越境する都市」に即したかっこよい装丁になっています。

 (写真は新村出氏。京都市のページにリンクしています)
(写真は新村出氏。京都市のページにリンクしています)


司会 尾崎 正治 氏(株式会社デュオシステムズ執行役員開発本部 ナレッジチーム上級コンサルタント)・大野 邦夫 氏(JEITA サイバーリテラシー調査ワーキンググループ ドコモ・システムズ株式会社 テクニカルセンター 主席技師)・松本 功 氏(ひつじ書房 代表取締役)・樋浦 秀樹 氏(Free Standards Group OpenI18N Workgroup議長、理事)・安斎 利洋 氏(メディア・アーティスト)・矢野 直明 氏(サイバーリテラシー研究所代表)
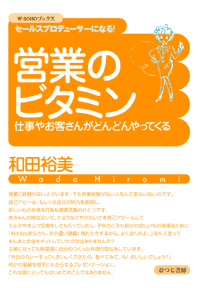

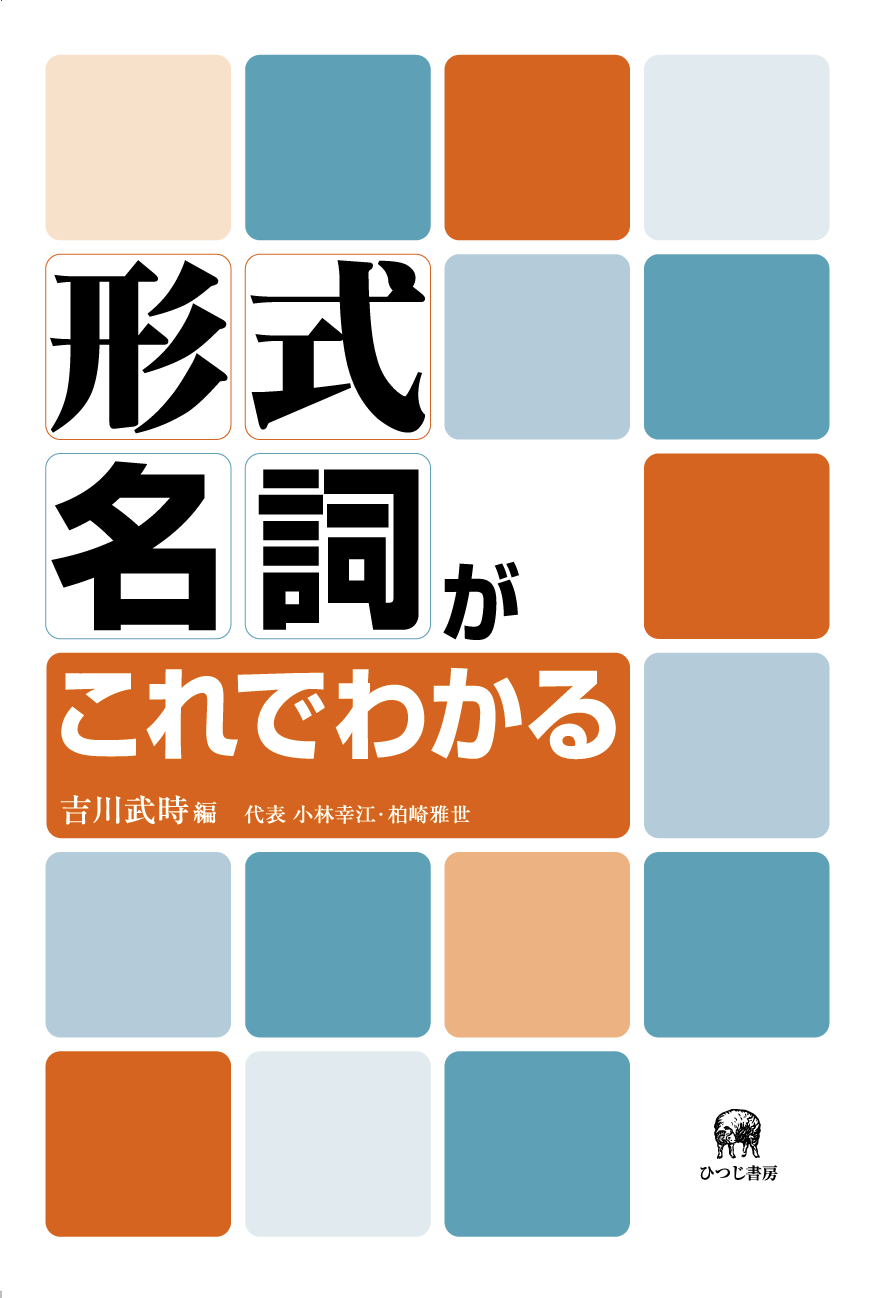




ハリーポッターのホグワーツではありません。立教大学の1号館と2号館の間の食堂です。魔法学校の生徒ではなく、社会言語科学会の懇親会の参加者です。特にポスター発表は大盛況でした。
2003.3.6
ここ
『日本語修飾構造の語用論的研究』もできました。加藤先生はもちろんのこと、郷野の追い込みと三美さんのご尽力でできました。松本は風邪でダウンしていますので、亡霊のようです。
online書店なら、BK1
2003.3.2
梅が満開
天気がよかったので、出かけましたところ、小石川植物園では梅が満開でした。
たまたま、最終日の博物館展を見ました。
★
(近くなのでもう少し早くわかればよかったのに)
2003.2.26
"Unaccusativity in Second Language Japanese and English"を刊行しました。足立の担当した2冊目の本です。
念入りに確認する専務と足立
2003.2.21
★
お待たせしました『ガイドブック方言研究』(小林隆、篠崎晃一編)を刊行しました。刊行の計画から、かなりの日数がたってしまいましたが、宮治さんの命日の前に刊行することができました。『ガイドブック方言研究』は、弊社社員、足立の一番最初の本です。ここ
ほぼ、同時に『日本語記述文法の理論』、『進化する図書館へ』を重版しました。
2003.2.14
女性起業家、新しいビジネスを作る女性の本を2冊刊行しました。こちらをご覧下さい。
2003.2.2
amazon.co.jpで『市民の日本語』が「市民」、「コミュニケーション」のカテゴリーで第1位になりました。こちらで検索してください。24時間以内に出荷のステイタスになっています。NPOでも第5位です。
2003.1.24
刊行が遅れていますテキストは、現在、鋭意編集中です。採用見本を請求の方にはコピーをお送りしますので、ご遠慮なくお申し付けください。toiawaseアットマークhituzi.co.jpまで。その際には、採用予定の授業名と予想人数をお教え下さい。あくまで、予定でかまいません。
2003.1.4
ひつじ年を迎えまして房主よりご挨拶申し上げます。
2002.12.27
今回、ご応募くださって、お電話をかけました方のためのものです。一般には応募していませんので、ご容赦ください。こちら
2002.12.9
『市民の日本語』を堀田力さんに書評してもらいました。キーになるポイントを的確に押さえたとてもよい紹介です。堀田さんありがとうございました。
2002.12.5
ひつじ書房のメールサーバーが不調のため、4日の朝から受信が上手くいかない状況が続いていました。現在、復旧中です。まだ、届かない場合があります。まことに恐れ入りますが、届きません場合には、再送していただけましたら、幸いです。ひつじ通信は、まことに申し訳ありませんが、週明けに再送いたしますので。ご注文いただけます場合には、それまでお待ち下さい。
2002.12.3
足立さんが編集長になって、書店様向け新聞を作りました。お得意の書店様に本日発送しました。さらに、これも足立が編集長に就任と言ってもいいでしょう、ひつじ通信という言語学関係の刊行物お知らせメールマガジンも発送しました。
2002.11.29
国文学資料館で、第8回 シンポジウム「コンピュータ国文学へのおさそい—出版とアカデミズム—」に参加します。
「学術研究上「有用」な情報の多くの部分が、すでにネットワーク上に格納される情報資源で事足りる(?)時代になってきました。インターネットによる論文の公開もさかんに行われる一方で、従来の学術出版社は、その経営基盤を脆弱にしつつあり、これまでこつこつと積み上げてきた学術出版の編集という営為が成り立ちがたくなるのではないかという懸念も現実的な問題となろうとしています。(後略) 」
2002.11.25
NHKのラジオか、テレビかわかりませんが、英会話の講座で『ファンダメンタル英語史』が紹介されました。おかげさまで、書店さんからの問い合わせが続いています。2002年最後のブームは、英語史?
(どのテキストで取り上げられたか、調査しております。ご存じの方は、ご一報下さい。→英会話goalで大津先生が紹介してくださっていました。)
営業経験といいましても出版社での営業経験である必要はありません。本を作るには、従来の編集者としてのセンスよりも、著者や読者といっしょに新しい本のイメージを持ち、従来の本のあり方を超えるものを作り出していきたいと考えているからです。それには「ものを売る」という感覚が、必須ではないかと思うからです。次をご覧ください。求人についての詳細
2002.10.15
先週のランキングで、教育書・語学書で、9位、人文書で10位になりました。仙台ジュンク堂での1位につづき、あちこちで売れ始めています。オンライン書店なら、お求めは、BK1で!
(お願い!先週のキャッシュを持っている方は、画像をお送りください!)
2002.10.7
「現場に学べ!売れる営業に変わるテクニック」というトピックの中に登場!口達者で勢いがあるからセールスもうまい、というのは間違いで、相手や顧客の気持ちを考える聞き上手なタイプが「できる営業」のタイプであると語っていらっしゃいます。なるほど。
2002.10.6
インターンを募集します。仕事をしてもらいながら、出版人としての基礎を教えます。21世紀の情報インフラを変えるために、基礎的で応用のきくスキルとマインドとセンスを伝えます。
2002.10.4
著者加藤さんの地元、仙台ジュンク堂で、なんと『海岸のカフカ』を抜いて、売り上げ第一位に。仙台以外では、ジュンク堂京都店をはじめ、あちこちで、売れ始めています。
2002.9.25
ここ数年、本を巡る議論が行われてきた。この本は、書籍を巡る議論の渦中に、『図書館の学校』に 回に渡って連載した文章をまとめたものである。
岩波書店などの人文書の専門取り次ぎ店である鈴木書店が倒産し、老舗の出版社である小沢書店や社会思想社が倒産し、発行される書籍の種類は7万2千点と増加しているのに書籍の売り上げは、6年連続で減少し、一冊あたりの実売部数も減っている。読書調査は、大学生や高校生が本を読まなくなっていることを示しており、学校の教師は本を読まない。新古書店が増える一方で、公共図書館は予算を大幅に減らされている。書籍の業界は曲がり角にきているということは確かである。『だれが「本」を殺すのか』(佐野眞一 プレジデント社)が、ちょっとしたベストセラーにもなった。(私もこの本の登場人物の一人である)多くの人にとって、本の世界が変わりつつあることは、そんなに重大なことではないかもしれないが、社会の節目であるということは間違いない。
『図書館の学校』の連載で、常に考えていたのは、大げさと受け止められるかもしれないが、本は、消えてしまうのかということだった。出版社を経営し、編集を営むものにとって、厳しい結論になるが、われわれ市民にとっては、本や出版というものが必要のないものであれば、消え去ってしまってもおかしくない。この機会に、存在の理由をもう一度、問い直してみたいと思った。






 新しい市民のコミュニケーションを考えるもっとも新しい新書を創刊します。刊行は、5月あたまになります。一冊目の『市民の日本語』が第一冊目です。
新しい市民のコミュニケーションを考えるもっとも新しい新書を創刊します。刊行は、5月あたまになります。一冊目の『市民の日本語』が第一冊目です。
長い日々がかかりましたが、ようやくできました。感慨深いところです。

兵藤裕己さんの『語り物序説』の根底改訂版、『物語・オーラリティ・共同体』まもなく刊行します。共同体からはみ出した職能民たちが、なぜ、国家に回収される物語を語っていったのか。共同体の成員たちは、なぜ、差別される民の声に感動さざるを得なかったのか。「投げ銭」の発想のオリジンはここにある。書店に並ぶのは、4月に入ってからになります。ご予約下さい。

『読むということ』重版しました。しかも、何と値下げしました。3600円から2800円へ。読むということは、どのような行為なのか?どのようにして作られたものなのか、その問いは今こそ、重要。
メディアについてのシンポジウムが、9日10日と安田講堂で開催される。水越さんたちの企画、運営するMellプロジェクト神田のではない、カナダのメディアリテラシーの中心人物、ダンカン氏の講演もある。

文化人類学の新しい書き手である福島さんの主著。イスラム最大国家であるインドネシアの研究の本。近代と宗教の狭間。イスラムの現在を知ると言う点でも本書の意味は大きい。
(福島さんは、大学院生時代に文化人類学の優れた研究に贈られる渋沢賞を(指導教官よりも先に!)受賞した新鋭。『身体の構築学』の編者。この本については大月隆寛による書評が『独立書評愚連隊』にある。川田順造、山口昌男以降の久方ぶりの理論的な文化人類学者。)
6400円

森田良行先生の著書が刊行になりました。私は、大学の授業で森田先生の授業をとって、それで文法への関心を持ちました。15年以上も前のことです。うれしく思います。
値段は400ページで3200円という破格のお求め安いお値段に抑えていますので、できるだけ、早めにお求め下さい。
浦安市で9月から10回に渡って、行ってきたセミナーが16日ひとまず終了しました。最終日には、NHKの取材が入りまして、個別相談会の様子が9時のニュースで全国放映されました。
お取り替えいたします。18ページに16ページと同じものが入ってしまいました。こちらのミスです。お詫びします。申し訳ありません。
お取り替えいたしますので、着払いでお送り下さい。直しましたものをお送りします。これから、直す手配を取りますので、直しましたものができますのは、2週間程度かかる見込みです。
なお、予約をされていたり、直接お送りしている方は、先にこちらから、直した本をお送りいたしますので、それまでお待ち下さい。
今年のNHKスペシャルは『変革の世紀』とのことで,日本科学未来館で開かれたワークショップに参加しました。ウェブでみる写真が,野間宏に似ている。喜ぶべきか。★

だいぶ遅くなってしまいましたが、TCP2001を刊行いたしました。
大津由紀雄編 菊判 3600円
ISBN4-89476-149-1 C3081 3600円
windows meが起動しなくなりました。現在、復旧中ですの、ご連絡が遅れることがあると思いますので、お許し下さい。メールはマックで受信できますので、メールをお送りいただくこと自体は大丈夫です。ただ、マックのメーラーが検索機能が弱いので・・・

言語学の知識を与えることにとどまらず、ことばを使うという人間の行為は、どういうものなのかを考える斬新なテキストブック。「ことばで道順を説明する」、「絵画をことばで表現してみる」、「温泉に浸かった猿の気持ちを表現する」ことばを使う楽しいエクササイズで、ことばの世界に入っていく。世界にも例をみない新しい内容は、「知性」の再構築のためのもの。青木三郎(筑波大学助教授)著。
PDFファイル<エクサイズ1>
PDFファイル<まえがき・目次>
PDFファイル<あとがき・奥付>
装丁・桜井ユカ(Art-will) 中央アジアの遺跡から見つかった不思議な壁画。そこには幻想の動物たちと草木が描かれていた・・・
ISBN4-89476-150-5 C1081 1400円
 法政大学大原社会問題研究所が、収集し、所蔵する戦前のポスターを図版とともに解説。ポスターは多色刷りであり、カラー印刷というメディア表現は、カラーテレビもない時代、脅威的な力を持っていた。戦前、反政府勢力も、政府も、言論を制覇するために、電信柱、壁という都市空間をせめぎあっていた。
法政大学大原社会問題研究所が、収集し、所蔵する戦前のポスターを図版とともに解説。ポスターは多色刷りであり、カラー印刷というメディア表現は、カラーテレビもない時代、脅威的な力を持っていた。戦前、反政府勢力も、政府も、言論を制覇するために、電信柱、壁という都市空間をせめぎあっていた。 すいませんでした!発行した書籍に、印刷の間違いがありました。すでにお求めの方は、お取り替えいたしますので、お送り下されば、直しました書籍をお送りいたします。送料は、こちらで負担しますので、着払いか、そうではない場合には、切手で送料を返金いたします。
すいませんでした!発行した書籍に、印刷の間違いがありました。すでにお求めの方は、お取り替えいたしますので、お送り下されば、直しました書籍をお送りいたします。送料は、こちらで負担しますので、着払いか、そうではない場合には、切手で送料を返金いたします。 ながらく途絶えていました「ひつじメール通信」を再起動します。どうぞよろしく。
ながらく途絶えていました「ひつじメール通信」を再起動します。どうぞよろしく。 今年も伊奈町に行って、花火を見た。はじめて奉納した。
今年も伊奈町に行って、花火を見た。はじめて奉納した。

(日経NET 2001.6.25)

大学での知の営みを構築する新しい方法とは・・・。明星大学人文学部の有志によって組織された新しい試み。ひつじ書房としては、2年ぶりに鈴木書店(取次店)で委託しました。都内大手人文書店でお求め、あるいはご注文下さい。それ以外の書店では、書店の方にお問い合わせ下さい。
簡単な目次アザレア訪問記をはじめます。さらに、文京区・茗荷谷のページにたべもの案内を開始。
ウチコミくんは、目の見えない人の、キーボード入力を支援し、マスターするためのソフトです。SCCJの高木さんが中心になって開発が進められ、このたびでき上がったことを記念して、パーティが開かれます。東京では6月1日。松本もパーティに参加します。国領さんの講演あり。
2001.5.15
私は、文京区の無明舎出版になりたいという高度な野望を持っています。
無明舎出版についてはこちら。「正しい」情報を上から降ろすのではなくて、地域の中からつくっていくような出版社になりたいと思っています。これは新しい挑戦です。
引っ越したひつじ書房の事務所(千代田区猿楽町)
2001.5.8
国語学会の前日、京都で「投げ銭」の話をします。一方的に話すのではなくて、お互いの益になるものでありたいと思っています。詳細はこちら・
SCCJについて
2001.5.3
事務所自体は移動しました。残してきた書類や本を、片づけている途中です。行ったり来たりしています。頭がくらくらしています。
新しい住所は
ハウジングアンドコミュニティ財団が、上記のテーマで助成事業を行う。詳しくはこちら。残念ながら、23区は対象外ということだが、「知恵のネットワーキング」というものの新しい姿がここにあると思う。「本」のようなものから、新しい形へ移動がはじまっていることを感じる。
2001.4.9
学問や研究というものもメディアである、という認識は当たり前のモノである。出版もメディアであるということも当たり前のものだと言い切ってもいいだろう。
『本とコンピュータ』という雑誌は、そういうメディアに対するもっとも自覚的な雑誌だと信じてきたが、そうでもないようだ。言い換えるとそうでもない人も書いているようだ。書いた西川祐子という人は、もっとも、ありきたりの視線しか持ち合わせていないらしい。
ひつじ書房で『文学者は作られた』を刊行したが、その紹介がでた。最後がひどい。学問の枠をこえてほしい、と来た。「しかし著者はどのような読者を想定してこの本を書いているのだろうか。文学研究もまた<文学>という制度の一部なのだから、これを破壊する決心をしたのなら、学術論文という制度の文体を超える必要があるのではないだろうか。」
2001年、ポストモダンも失敗であったということが、はっきりしている時代に、研究というメディアに自覚的でもない上に、1980年代中旬でもないのに、そんな脳天気さは犯罪的である。
続きへ
 2000年の8月にアゴラ劇場稽古場にて行った鼎談を公開しました。対話とは何か、複数のアイデンティティを祝福することとは、などなど、今もっとも興味深いことばについての鼎談です。こちらをご覧下さい。
2000年の8月にアゴラ劇場稽古場にて行った鼎談を公開しました。対話とは何か、複数のアイデンティティを祝福することとは、などなど、今もっとも興味深いことばについての鼎談です。こちらをご覧下さい。
2001.3.24
(長尾真 京都大学学長 朝日新聞2001.3.23夕刊より)


Mey先生に事務所に来ていただきました。ひつじ書房では、Mey先生の主著Pragmaticsをブラックウェルに先立ち、先駆けて翻訳権を取得しました。その時以来、何度かお会いしていますが、今回は、わざわざ事務所によっていただきました。Pragmaticsの2版がでたということです。
真ん中は、ご存じ澤田先生です。次の著書の打ち合わせも行いました。

コンピュータを単なる計算機ではなく、プログラムを処理できることを証明したコンピュータの父であり、シャノンは、ローマン・ヤコブソンの友人でもあり、彼は情報理論の創始者であると同時に、言語学・コミュニケーション研究にも大きな影響を与えた。写真は、『言語』2001・2別冊(大修館書店)より。
『コミュニケーションの数学的理論 : 情報理論の基礎』(明治図書)の再版を望む。
1995年から、DTPを利用して本を作ってきましたが、三美印刷で組版を行うことに転換するにともない、事務所のスペースが過剰になってしまいました。事務所スペースを適性化して、コストを削減するために移転することを決めました。本作りに変化はありません。変わらぬご支援をお願いします。
再販制がなくなれば、いろいろなサービスが生まれてくる。図書館の値段を倍にするとか、大学教授には10000円で、院生には3000円とか、学生には1000円とか、その人が給料をもらっている人か、そうではないかで変えたり、たくさん売ってくれている書店には値段を下げておろしたり。本当にPOST再販を運用するには、ITによる決めの細かいオークション=市会機能が必要だろう。しかし、市会のインフラができてから、というのは無理だ。先にシステムが、壊れないと・・・。
2001.2.17
出版界に二つめの魔物が現れた。一つめの魔物は、新古本を定価以下で売る魔物で、二つめは、最近になって水面下から現れた。本を無料で貸し、さらに「無料」で複製させる魔物だ。一つめは、委託制度と再販制度に根本的な刃を突きつけ、二つめの魔物は、著作権を扱う仕組みが出版界では機能していない、という事実を明らかにして…more(「新文化」2001.2.15号)
2001.2.9


書店さんにはあまり並んでいないと思いますので、まことに恐れ入りますが、なじみの書店でご注文下さい。2週間程度かかります。もし、お急ぎの場合は、着払いでお送りします。その場合、手数料が600円かかります。
意味分析の方法は、1996年に初版を作りました。どうにか、5年で、品切れになりました。今年の春は、どんどん重版をしようとおもっていますので、この本は、2月に重版をします。著者の森田先生には、新しく文法と表現の本を書いていただけるように、お願いしました。
邦訳で、「2001年宇宙の旅」ですが、英語だとSpace oddeseyと宇宙の旅となるわけですが、sheep oddeseyとひつじの旅に、ひっけています。30代以下の人が、ほとんどわからないようなので、こんな20世紀を代表するような映画の「古典」をほとんどの人が知らないということは、どういうことなのか?「古典」というものが、伝わらない仕組みがあるのでしょうか? こんなに分からなければ、引用にもパロディにもならないわけで、結果としてひとりよがりな年賀状ということになってしまったのでした。回答をお寄せ下さった一名の方に、プレゼントしました。
今年の年賀状です。何の引用かわかりますでしょうか。お分かりの方は、ひつじ掲示板へお書き込み下さい。先着順で3名様に、『文学者はつくられる』を差し上げます。しめきり、25日。
ここ(ねっとアゴラ 朝日新聞夕刊 1月12日)
ぼくらは何かをしようと思った時、そのことに関係する情報がないかどうか調べることからはじめる。たとえば旅行しようと思った時、今なら、インターネットで検索してみるだろう。→more
2000.11.21
『文学者はつくられる』まもなく刊行!文学者はいつごろ食えるようになったのか? 文学者が生きていけるようになる仕組みはどのようにできてきたのか? 有島武郎は、流行作家であった。今は忘れられてしまったベストセラー作家、江馬修。今読むとなんじゃやこりゃ、レベルでありながら、当時の哲学者・文学者がみな、涙を流して感銘したという・・・。意外な事実を発掘する貴重な研究。再販制や出版流通システムとの関係で、読んでも面白いと思う。さらに、メディアの経済史・社会史と読むこともできる。 読書自体の解明を目指した『読むということ』(和田敦彦 著)に続く、ひつじ書房の日本近代文学研究書。 |